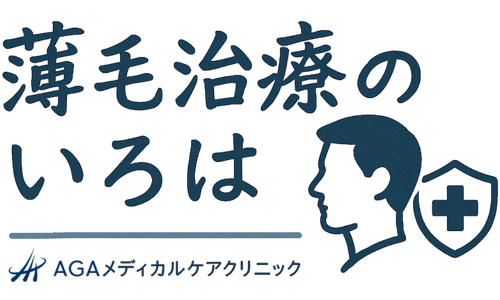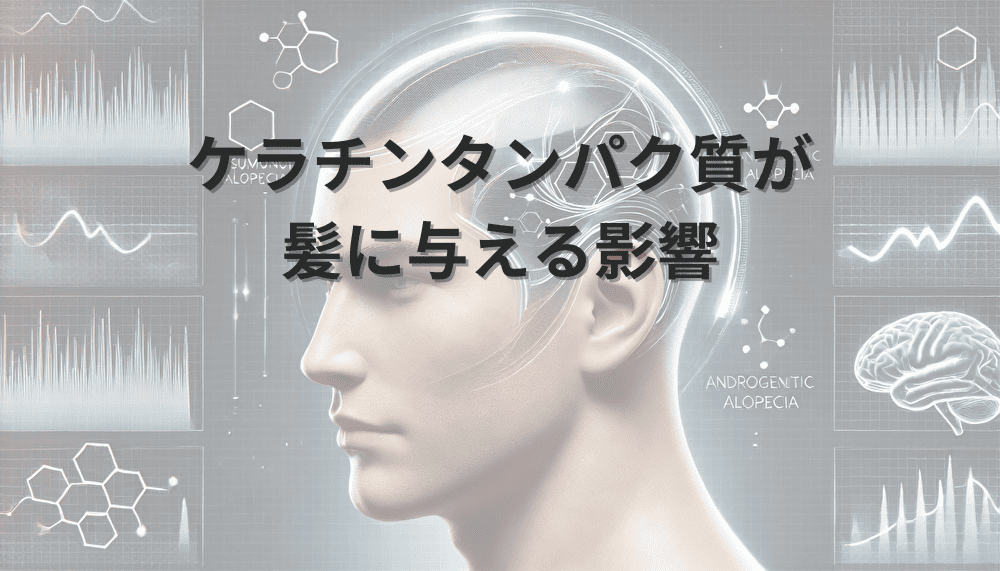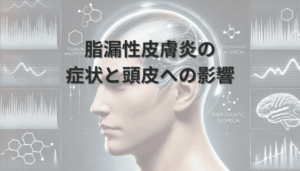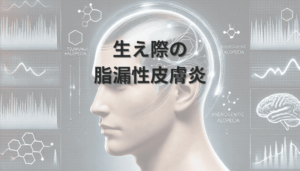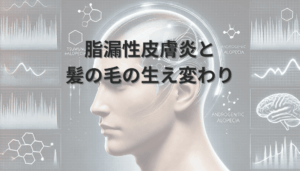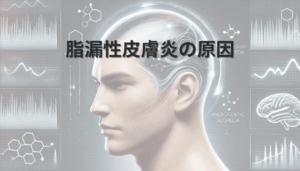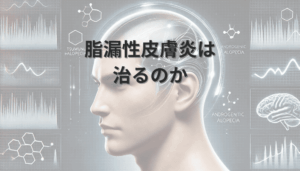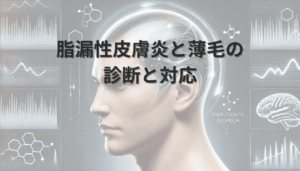髪のツヤや強さを保ちたいと考える方は少なくありません。健康的な髪を支えるうえで重要な成分の1つが「ケラチンタンパク質」です。
髪の大部分を構成するだけでなく、爪や皮膚とも深いかかわりを持ちます。
本記事では、ケラチンタンパク質とは何か、どのように髪に影響し、不足が起こるとどのような問題が出るのかを説明します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
ケラチンタンパク質とは
髪にかかわる要素として、まずはケラチンタンパク質そのものがどのようなものなのかを押さえておくことが大切です。
多くの方が「髪はたんぱく質でできている」と聞いたことがあるかもしれませんが、そのメインとなるのがケラチンタンパク質です。
ケラチンタンパク質の基本的な特徴
ケラチンタンパク質は人間の髪や爪、皮膚の角質部分などに豊富に含まれる構造たんぱく質です。
外部からの刺激に対して抵抗力を高めたり、水分の蒸散を抑えたりする働きがあり、生命活動を維持するうえで大切な役割を担います。
とくに髪は、主成分のうちおよそ8割以上がケラチン系のたんぱく質で構成されているため、ケラチンタンパク質の状態によって髪の健康状態が左右されやすい特徴があります。
ケラチンタンパク質に注目する理由
- 髪や爪が硬く強度を保つための主成分
- 皮膚の角質を形成し、乾燥や外部刺激から守る
- 体のさまざまな部位で共通して働くたんぱく質
髪表面のキューティクルや内部のコルテックスにもケラチンタンパク質が含まれますが、その配列の乱れや損傷が起こると、ツヤの低下や切れ毛などのトラブルが発生しやすくなります。
体内での合成と構造上の特徴
体内では、食事から摂取したアミノ酸が組み合わさり、さまざまなたんぱく質へと作り変えられます。
ケラチンタンパク質も例外ではなく、含硫アミノ酸の一種であるシステインをはじめとする複数のアミノ酸が結合して生成されます。
とくにシステインが多い点が特徴で、硫黄を含む構造が「ジスルフィド結合」をつくり、髪や爪などに強度をもたらしています。
ケラチンタンパク質を構成するアミノ酸
| アミノ酸名 | 特徴 | 髪への影響 |
|---|---|---|
| システイン | ジスルフィド結合を形成しやすい | 髪の強度や柔軟性を左右 |
| グリシン | 小さな分子量で柔軟性を高める | 髪のしなやかさに関与 |
| セリン | 保湿成分としての側面を持つ | 水分維持に影響 |
| チロシン | メラニン合成にかかわる | 髪色を左右する可能性あり |
このように、ケラチンタンパク質は複数のアミノ酸が結びつくことで構造を保っています。髪の強度や弾力、保湿性などにかかわるため、バランスよくアミノ酸を摂る工夫が重要です。
角質化との関係性
皮膚の最も外側の層は角質層と呼ばれ、ここにもケラチンタンパク質が豊富に存在します。
新陳代謝によって生まれた細胞が徐々に角質化し、やがて垢となって剥がれ落ちる仕組みは「ターンオーバー」として知られています。
このターンオーバーの過程で、ケラチンタンパク質が細胞内部に蓄積し、皮膚表面を強固にして外部刺激から身体を保護しています。
髪の毛も皮膚と同じ上皮組織の変化で成り立ち、タンパク質の角質化現象が関係しているため、爪や皮膚と同じ仲間といえる存在です。
髪・爪・皮膚に広く含まれる理由
ケラチンタンパク質は、「防御」や「保護」の機能をサポートする点が大きな特徴です。髪や爪が硬いのは、ケラチンタンパク質特有の結合構造が外力に強い性質を発揮しているためです。
また、皮膚表面の角質層は身体を異物や病原体から守る重要なバリアとして機能します。
髪や爪が傷んだり割れたりすると、「ケラチンが不足しているのではないか」とイメージされる方もいらっしゃいますが、実際にはシャンプーや洗剤などの外部刺激や栄養不良など多角的要因が絡み合ってダメージが進行します。
ケラチンタンパク質そのものへの理解を深めると、こうしたダメージ対策にもつながります。
髪の主成分とケラチンタンパク質の関係
髪を構成する主成分はケラチンタンパク質ですが、同時に水分や脂質も含まれます。このバランスが乱れると、ぱさつきや切れ毛などのトラブルが生じやすくなります。
髪の基本構造
髪は大きく分けて表面のキューティクル、中間のコルテックス、中心部のメデュラ(毛髄)の3層構造です。
なかでも髪の強度や太さ、弾力などを決めるコルテックスにはケラチンタンパク質が多く含まれ、シスチン結合の密度によって毛髪の物理的性質が左右されます。
髪の3層構造の概要
| 層の名称 | 主な構成 | 特徴 |
|---|---|---|
| キューティクル | ケラチン、脂質 | 髪の外側を覆ううろこ状の層。光沢と保護機能。 |
| コルテックス | ケラチン主体 | 髪の太さ・強度・弾力などを決定づける層。 |
| メデュラ | 空洞や少量のたんぱく質 | 髪の中心部で、熱伝導や毛髪の柔軟性に影響。 |
このうちコルテックス部分をいかに健康的に保つかが、ハリやコシを維持するポイントです。
ケラチンタンパク質の不足や損傷が進むと、このコルテックスが脆弱化し、枝毛や切れ毛などのトラブルが発生しやすくなります。
ケラチンタンパク質と水分・脂質のバランス
髪にはおよそ10〜15%程度の水分が含まれ、さらに脂質やメラニン色素、微量のミネラルなども存在します。
ケラチンタンパク質はこれらをつなぎ止める土台ともいえる役割を担います。
もしケラチンタンパク質に損傷や不足が起こると、水分保持が難しくなり、パサつきやうねりが目立つようになります。
髪を構成する成分の役割
| 成分 | 役割 |
|---|---|
| ケラチンタンパク質 | 強度、弾力、保護機能 |
| 水分 | 柔軟性、しなやかさ |
| 脂質 | ツヤ、外部刺激からの保護 |
| メラニン色素 | 毛髪の色調 |
こうした成分のバランスが崩れると、見た目の美しさだけでなく、髪自体の健康状態が低下します。
とくにドライヤーやカラー剤、パーマ液など外部刺激が強い場合は、ケラチンタンパク質の損傷を引き起こしやすいので注意が必要です。
補強されたケラチンタンパク質の働き
ケラチンタンパク質を外部から補う成分としては、加水分解ケラチンなどが有名です。これらは分子量を小さくした形で製品化されており、シャンプーやトリートメントなどに配合されています。
髪の表面や内部に付着することで、一時的にダメージ部分を補強し、ツヤや手触りを改善する効果が期待されます。
ただし根本的には、体内で作られるケラチンタンパク質の質と量を保つことが髪の状態を良好にする近道です。
髪の健康とケラチンタンパク質の関係性を理解する意義
髪は「タンパク質のかたまり」という言葉を耳にしたことがある方も多いでしょう。しかし、単なるタンパク質ではなく、ケラチンタンパク質の結合状態が髪の強度やつやを左右します。
表面のケラチン層が剥がれれば枝毛などができやすくなり、内部のコルテックスまでダメージが及ぶと修復に時間がかかります。
日々のケアや栄養バランスを見直す際、ケラチンタンパク質に着目することが大切です。
ケラチンタンパク質が髪に与える影響
ケラチンタンパク質は、髪の強度や弾力だけでなく、ツヤや保湿性にも深くかかわります。
髪のハリ・コシへの貢献度
髪のハリやコシが失われると、全体的にボリュームダウンして見えたり、セットがうまくいかなかったりします。
ハリコシを支える要素の1つが、コルテックス内のケラチンタンパク質の結合です。この結合がしっかりしていると、髪1本1本が折れ曲がりにくくなり、根元から立ち上がりやすくなります。
ケラチンタンパク質が充実している髪の特徴
- 根元からしっかり立ち上がる
- ブラッシングやドライヤーで痛みにくい
- 弾力があり、手ぐしが通しやすい
加齢やホルモンバランスの変化でケラチンタンパク質の合成が低下すると、細く柔らかい髪質に変わりやすくなり、薄毛やボリューム不足につながりやすいです。
ツヤ・光沢を左右する要因
ツヤのある髪は、表面のキューティクルが整然と並び、光を反射しやすい状態です。
キューティクルもケラチンタンパク質によって形成されているため、損傷すると光が乱反射して髪の輝きが失われます。
ツヤが低下すると、見た目がぱさついて見えやすいだけでなく、実際に髪内部の水分量が減少している場合も少なくありません。
保湿力・うるおいへの関係
ケラチンタンパク質は、含まれるアミノ酸の性質によって水分を抱え込みやすい面があります。セリンなどの親水性アミノ酸が水分を取り込む性質を持つため、髪内部のうるおい維持に寄与します。
しかし、ヘアカラーやパーマなどの化学処理、紫外線の影響によりケラチンタンパク質が破壊されると、水分が蒸散しやすい髪質へと変わっていきます。
ケラチンタンパク質に含まれる親水性アミノ酸
| アミノ酸名 | 特徴 |
|---|---|
| セリン | 水分の保持力が比較的高い |
| トレオニン | 保湿や繊維の維持に関与 |
| グルタミン酸 | イオン結合による水分・油分の安定化にかかわる |
このような保湿性は、外部からのトリートメントだけでは補いきれない面があるため、体の内側からの栄養補給が欠かせません。
ダメージ耐性との深いかかわり
ドライヤーやヘアアイロンなどの熱、ブラッシングや摩擦、カラー剤・パーマ液といった薬剤など、髪は日常生活の中で多くのダメージ要因にさらされています。
ケラチンタンパク質がしっかり結合している髪は、これらのダメージ要因に対して比較的耐性が高く、枝毛や切れ毛を起こしにくい傾向があります。
ただし、いったん損傷が進むと自力で完全に修復するのは難しく、ヘアケア製品や栄養摂取、適切な施術を組み合わせて対処することが大切です。
ケラチンタンパク質が不足すると起こる問題
ケラチンタンパク質が不足した髪は、見た目のダメージだけでなく、将来的な薄毛・抜け毛のリスクにも影響を与える可能性があります。
不足の原因と背景
ケラチンタンパク質の不足は、以下のような要因が重なり合って起こります。
ケラチンタンパク質が不足しやすい要因
- 偏った食生活によりアミノ酸を十分に摂れない
- 過度なダイエットでたんぱく質不足
- 化学処理や紫外線などによる過度のダメージ
- 加齢による合成能力の低下
- ホルモンバランスの乱れや病気などの影響
ケラチンタンパク質を作り出すためには原材料となるアミノ酸が必要ですが、摂取量が不足すると体全体のたんぱく質合成に影響が及びます。
すると、髪や爪など生命維持に直接関係しない部位は後回しにされ、結果的に髪の状態が悪化しやすくなります。
切れ毛・枝毛・パサつきなどのダメージ
ケラチンタンパク質が不足したり損傷したりすると、髪の内部構造を支える力が弱まり、切れ毛や枝毛が目立つようになります。
さらに、表面のキューティクルも剥がれやすくなり、水分保持力が低下してパサつきが顕著に表れます。
カラーリングの色落ちが早くなる、パーマの持ちが悪くなるなど、美容面でのトラブルも多発しやすくなります。
髪に生じる具体的なトラブル
| トラブル名 | 原因となる主な要素 | 見た目や触感の特徴 |
|---|---|---|
| 枝毛 | コルテックスの損傷・キューティクルのめくれ | 髪先が2つ以上に分かれる |
| 切れ毛 | 過度な摩擦や熱によるたんぱく質の破壊 | 途中で髪が断裂し、短く切れた毛が増える |
| パサつき | 水分・油分の不足、表面保護膜の破壊 | ゴワつきや広がり、ツヤの欠如が目立つ |
| うねり | 髪内部の構造変化や加齢、栄養不良 | 髪の表面に波打つようなクセが出る |
ケラチンタンパク質がしっかり働いていれば、こうしたトラブルは起こりにくくなりますが、いったん不足状態に陥ると、集中的なケアが欠かせない状況になる場合もあります。
抜け毛・薄毛リスクへの影響
髪のハリやコシが失われると、見た目のボリュームが減少し、実際に抜け毛が増えることで薄毛を実感するケースもあります。
とくに男性型脱毛症(AGA)などに悩む方は、ホルモンの影響に加えて髪を生成するための栄養バランスにも留意したいところです。
毛髪をつくる材料であるアミノ酸が不足していると、成長途中で十分な太さや強度を保てなくなり、細く短い毛が増えてしまいがちです。
頭皮環境への悪影響
頭皮も皮膚の一部であり、角質層や皮脂膜がうまく機能しないと、フケやかゆみ、炎症が起こりやすくなります。
ケラチンタンパク質が不足すると皮膚のバリア機能が低下しやすく、外部刺激を受けやすい頭皮環境へとつながります。
その結果、毛穴詰まりや頭皮トラブルが増え、髪の成長が阻害されやすくなる場合があります。
ケラチンタンパク質を補う食事・栄養のポイント
ケラチンタンパク質の生成をスムーズに行うには、食事から必要なアミノ酸をしっかり摂ることが大切です。
たんぱく質摂取の重要性
ケラチンタンパク質だけでなく、ホルモンや酵素、筋肉などもすべてたんぱく質からできています。
体全体の健康を保つには、毎日の食事の中でたんぱく質をきちんと摂取し、髪や皮膚にまで栄養が行き届くようにすることが欠かせません。
特に、肉や魚、卵、大豆製品などには必須アミノ酸が豊富に含まれています。
たんぱく質不足を避けるための食事
| 食材カテゴリー | 主な例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 肉類 | 鶏肉、牛肉、豚肉 | 良質なたんぱく質源。部位によって脂質量に違いがあるため選ぶ際に意識が必要。 |
| 魚介類 | 鮭、サバ、イワシ、エビなど | 不飽和脂肪酸やビタミンDなどを同時に摂取できる |
| 卵 | 鶏卵 | 必須アミノ酸がバランスよく含まれる優秀な食材 |
| 大豆製品 | 豆腐、納豆、豆乳 | 植物性たんぱく質を効率よく摂取できる |
こうした食材を偏りなく摂取すると、ケラチンタンパク質の合成に必要なアミノ酸を得やすくなります。
ケラチン合成を助ける栄養素
ケラチンタンパク質を作り出すうえでは、アミノ酸だけでなく各種ビタミンやミネラルの助けも必要です。
例えば、亜鉛はたんぱく質合成をサポートし、ビタミンB群はアミノ酸代謝に欠かせない存在です。
意識的に摂ると、髪の成長サイクルを整えやすくなります。
ケラチン合成をサポートする栄養素
- 亜鉛(牡蠣、牛肉、かぼちゃの種など)
- ビタミンB群(豚肉、レバー、豆類など)
- 鉄分(レバー、赤身肉、ほうれん草など)
- ビタミンC(柑橘類、キウイ、赤ピーマンなど)
不足しやすい栄養素があると、せっかく十分なたんぱく質を摂っていても、髪への影響が限定的になる可能性があります。
食事のバランスと時間配分
たんぱく質やビタミン・ミネラルの摂取は、朝・昼・晩の3食に分散させるほうが体内での合成がスムーズになることが多いです。
例えば、朝食を抜きがちで昼夜にまとめ食いをすると、血中のアミノ酸濃度が乱高下し、筋肉や髪などへの栄養供給が滞る恐れがあります。
あまりボリュームのある食事が取れない朝でも、卵や豆腐、ヨーグルトなどのたんぱく質源を少しでも取り入れると良いでしょう。
食事パターンを見直す
| 課題 | 改善の一例 |
|---|---|
| 朝食を抜いてしまう | 手軽に食べられる卵料理やプロテイン飲料を取り入れる |
| 夜にまとめ食いする | 昼にもしっかり主菜をプラスして総量を分散させる |
| 外食や偏食が多い | 外食時でも魚や肉の定食を選び、野菜を追加注文する |
小さな工夫を重ねて、ケラチンタンパク質の生成をサポートする栄養バランスを目指すことが大切です。
サプリメント利用の考え方
忙しい現代社会では、食事のみで十分な栄養素を摂取するのが難しい場合もあります。そうしたときに活用できるのがサプリメントです。
特にビタミンB群や亜鉛など、髪の生成過程を支える成分をピンポイントで補える利点があります。
ただし、サプリメントは栄養を補う手段であり、あくまでも食事を中心とした栄養バランスが根本である点を意識してましょう。
過剰摂取は副作用や健康トラブルの原因となる可能性があるため、医療機関や専門家に相談しながら利用を検討するのが望ましいです。
ケラチンタンパク質を補う外部ケアと注意点
ケラチンタンパク質を食事だけでなく、外部からも適切に補うと髪のコンディションを整えやすくなります。
ただし、製品の使い方や施術方法によっては逆効果になることもあるため、注意点を把握しておきましょう。
シャンプー・トリートメントでのケア
多くのヘアケア製品には、加水分解ケラチンやシルクたんぱく質、コラーゲンなどが配合され、毛髪補修効果をうたっています。
これらは髪表面に付着して切れ毛や枝毛を軽減したり、内部のアミノ酸バランスを整えたりする可能性があります。
外部ケア製品を選ぶ時に意識したいポイント
- 加水分解ケラチンなど補修成分の配合
- アミノ酸系や弱酸性の洗浄剤で刺激を抑える
- シリコンやオイル成分で表面をコーティングしすぎない
- 継続的に使用してコンディションの変化を見極める
ただし、ヘアケア製品はあくまでも補強的な役割ですので、髪の根本的な栄養不足を完全に解決できるわけではありません。
サロンでの集中補修
美容院では、トリートメントやヘアエステなどのメニューとして、ケラチンタンパク質を外部から補う施術を行うところがあります。
専用の機器や薬剤を用いて、髪の内部にケラチンやセラミドなどの成分を浸透させる方法です。施術直後は手触りやツヤが向上しやすいですが、持続期間は人によって異なります。
サロン施術のメリット
| 施術名 | 特徴 | メリット |
|---|---|---|
| ケラチントリートメント | 高濃度のケラチン・タンパク質を髪内部に補給 | 髪質改善やダメージ補修感を期待できる |
| 水素トリートメント | 活性酸素の除去を狙ったトリートメント成分を浸透させる | ツヤや手触りが一時的に向上する |
| 超音波トリートメント | 超音波アイロンなどで補修成分を浸透させやすくする | 効果が感じやすいが、施術費用が高めの傾向 |
一方で、これらの施術は定期的に続けなければ効果が薄れたり、施術に伴う費用や時間も考慮しなければならなかったりします。
髪質や予算、生活スタイルを考慮して無理のない範囲で取り入れると良いです。
ヘアアイロンやドライヤーの使い方
髪が濡れた状態はキューティクルが開きやすく、ダメージを受けやすいため、適切な熱管理や乾かし方が重要です。ドライヤーの温度が高すぎると髪内部のケラチンタンパク質が変性し、切れ毛や枝毛の一因になります。
ヘアアイロンを使用する際は、設定温度を必要以上に高くしすぎず、短い時間でスタイリングを済ませる工夫が必要です。
注意点と限界
外部ケア製品やサロン施術は、髪表面や内部を一時的に補修し、見た目の改善をサポートするものです。
しかし、根本的に新しく伸びてくる髪の健康を左右するのは、体内で合成されるケラチンタンパク質の量と質です。
つまり、内側からの栄養補給や適切な生活習慣なしには、真の意味でケラチンタンパク質を補い続けるのは難しいといえます。
薄毛・AGAとの関連と受診のメリット
ケラチンタンパク質の不足が進むと、髪のボリュームが落ちるだけでなく、薄毛やAGAを懸念する方にとって深刻な問題となりえます。
AGA(男性型脱毛症)とは
男性ホルモンの一種であるテストステロンがジヒドロテストステロン(DHT)に変換される過程で毛包が萎縮し、髪の成長サイクルが乱れる現象を指します。
生え変わりの周期が短くなり、太く長い髪へと育たなくなるため、生え際や頭頂部など部分的に薄毛が進行するパターンが一般的です。
もちろんAGAの主原因はホルモンバランスですが、髪の成長素材であるケラチンタンパク質が不足すると、さらに髪の質が低下するリスクがあります。
薄毛とケラチンタンパク質の関係
薄毛はAGA以外にも、生活習慣やストレス、栄養不良などの複数要因が絡み合って生じる場合があります。
もし髪を形成するための材料(アミノ酸)が欠乏していれば、毛根が健在でも十分な髪を合成できません。
ケラチンタンパク質の合成に必要な栄養バランスが乱れていることが、薄毛を加速させる一因となるケースもあります。
薄毛の進行を早める要因
- 極端なダイエットで栄養素が不足
- 忙しさによる食事の偏り
- 喫煙や過度な飲酒による血行不良
- ストレス過多によるホルモンバランスの乱れ
こうした要因はどれもケラチンタンパク質の供給不足につながりやすいため、薄毛対策としても意識的に改善する必要があります。
受診によるメリット
薄毛やAGAの兆候を感じた場合、専門の医療機関へ相談することには大きなメリットがあります。
単に外用薬を処方してもらうだけでなく、栄養バランスや生活習慣へのアドバイス、血液検査による原因の特定など、総合的な視点から治療プランを組み立てられるからです。
医療機関を受診するメリット
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 原因の特定・診断 | AGAなのか、ほかの脱毛症なのか、頭皮の状態や検査結果で判断できる |
| 適した治療薬や施術の提案 | 内服薬や外用薬、注入療法などさまざまな選択肢から適した方法を提案できる |
| 生活習慣改善のカウンセリング | 食事や睡眠、ストレス管理などのアドバイスを受けられる |
| 経過観察とフォローアップ | 定期的な受診で治療の効果を確認し、必要に応じて方針を柔軟に修正できる |
頭髪のお悩みはデリケートなテーマですが、専門家と連携するとケラチンタンパク質に関する知識や正しいヘアケア方法も得やすくなります。
クリニックに相談するタイミング
髪のボリュームダウンや抜け毛が以前より気になる方、家族や親戚にAGAの方が多いなど遺伝的要因がある場合は、早めにクリニックでの相談を検討すると良いでしょう。
薄毛や髪質の問題は、早期に対策を始めるほど結果を得やすい傾向があります。
食事とあわせて外部ケアを見直し、必要に応じて医療の力を活用すると、ケラチンタンパク質を軸にした髪の健康維持を実現しやすくなります。
クリニックで行うケラチン補給と相談
一般的なケアでは行き届かない髪のダメージや薄毛の悩みに対して、クリニックでの治療やケアを受ける選択肢があります。
内服薬・外用薬による治療だけでなく、施術としてケラチンタンパク質に注目する方法などを組み合わせるケースもあります。
医療機関でのケラチン補給施術
クリニックによっては、髪や頭皮に必要な成分を直接注入するメソセラピーなどの施術を用意している場合があります。
薬剤や成分の配合内容は施設によって異なり、ビタミン・ミネラルに加え、ケラチン由来成分を含むものを使用することも考えられます。
こうした施術は、一定期間の通院を前提に組み合わせて行う場合が多いです。
クリニックで行われる施術
| 施術 | 特徴 |
|---|---|
| 毛髪メソセラピー | 頭皮に直接栄養を注入 |
| プラズマ療法 | 血液を利用して成長因子を取り出し、頭皮へ戻す |
| 低出力レーザー療法 | 血行促進と細胞活性化を狙う |
いずれも外部ケアや内服薬と並行しながら行うと相乗効果が期待できます。カウンセリングや頭皮検査を通して、自分に合った施術を組み立てると良いでしょう。
サプリメント指導・生活習慣アドバイス
クリニックでは、食事やサプリメントの指導を行うケースがあります。
ケラチンタンパク質はアミノ酸がなければ合成できないため、どれだけ外部施術を受けても栄養面がおろそかになると十分な効果が得られません。
そこで医師や管理栄養士が、食事内容やサプリの選び方、さらには生活習慣全般についてアドバイスし、体内からの働きかけをサポートします。
薬物療法との併用
薄毛やAGA治療では、フィナステリドやデュタステリドなどを用いる内服薬や、ミノキシジル外用薬などの薬物療法を組み合わせる場合があります。
これらはホルモンや血流など、髪の成長サイクルに直接作用します。そのうえでケラチンタンパク質の材料を十分に確保し、髪が太く健康的に伸びる土台を整えれば、より満足度の高い結果につながる可能性があります。
治療薬との併用メリット
| 薬剤名 | 効果 | ケラチン補給との併用メリット |
|---|---|---|
| フィナステリド | DHTの産生を抑え、脱毛を抑制 | ホルモン面から抜け毛を抑えながら、髪質改善も狙える |
| デュタステリド | 5α還元酵素をさらに広範囲に抑制 | AGA進行を抑制しつつ栄養補給で髪の太さをサポート |
| ミノキシジル(外用) | 毛母細胞への血流を増やし、発毛を促進 | 栄養が行き届きやすい環境下でケラチン合成を後押し |
AGA治療薬は医師の診察のもとで使用するのが原則であり、副作用や個人の体質に合わせて処方されます。自己判断での使用は推奨されませんので、必ず専門医と相談してください。
早めの相談でより良い結果へ
髪の悩みは進行度合いや原因によって適した治療法が異なります。早期に相談することで、ケラチンタンパク質を補う栄養指導や外部ケア、必要に応じた薬物療法を組み合わせ、より良い結果に結びつきやすくなります。
クリニックでは定期的な診察や検査を行い、個人差の大きい髪の成長サイクルをトータルに把握しながらサポートします。
参考文献
BASIT, Abdul, et al. Health improvement of human hair and their reshaping using recombinant keratin K31. Biotechnology Reports, 2018, 20: e00288.
LAI, Hui Ying, et al. Evaluating the antioxidant effects of human hair protein extracts. Journal of Biomaterials science, Polymer edition, 2018, 29.7-9: 1081-1093.
CRUZ, Célia F., et al. Peptide—protein interactions within human hair keratins. International journal of biological macromolecules, 2017, 101: 805-814.
FERNANDES, Margarida M., et al. Keratin‐based peptide: biological evaluation and strengthening properties on relaxed hair. International journal of cosmetic science, 2012, 34.4: 338-346.
SHIMOMURA, Yutaka; ITO, Masaaki. Human hair keratin-associated proteins. In: Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings. Elsevier, 2005. p. 230-233.
MIRANDA‐VILELA, Ana Luisa; BOTELHO, Adelaide J.; MUEHLMANN, Luis A. An overview of chemical straightening of human hair: technical aspects, potential risks to hair fibre and health and legal issues. International journal of cosmetic science, 2014, 36.1: 2-11.
TINOCO, A., et al. Keratin‐based particles for protection and restoration of hair properties. International journal of cosmetic science, 2018, 40.4: 408-419.
FAN, Jiayi, et al. Performance and Mechanism of Hydrolyzed Keratin for Hair Photoaging Prevention. Molecules, 2025, 30.5: 1182.