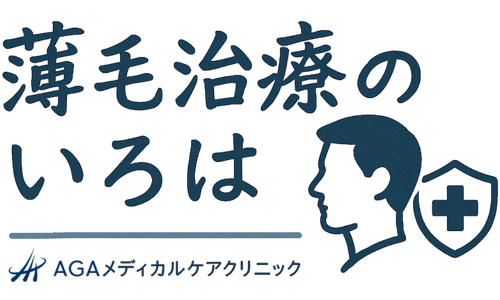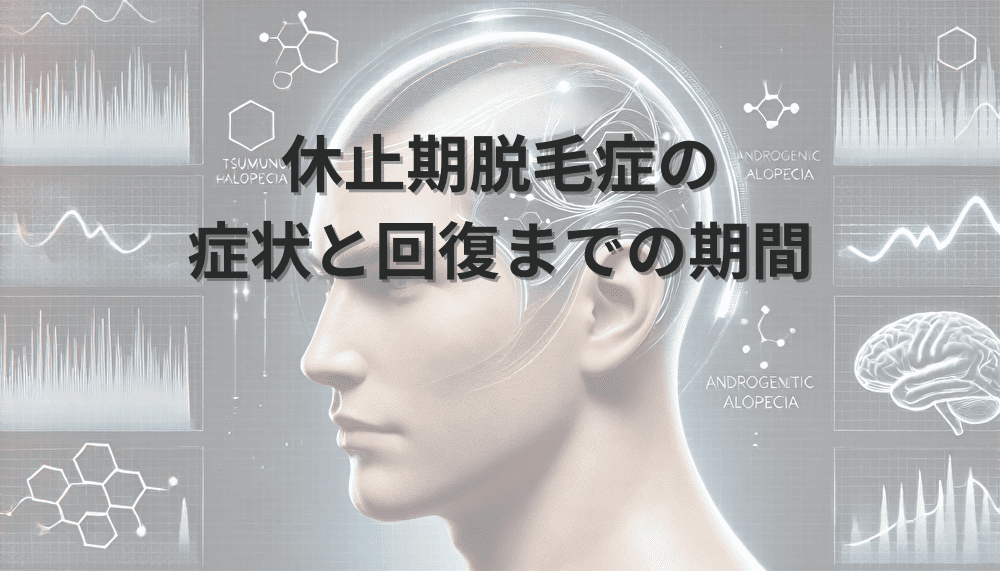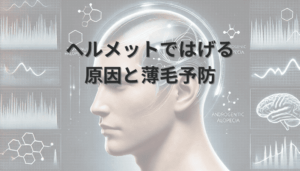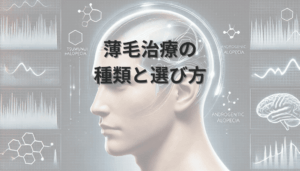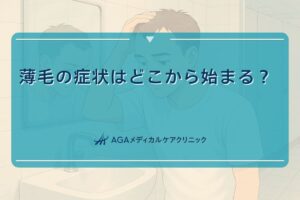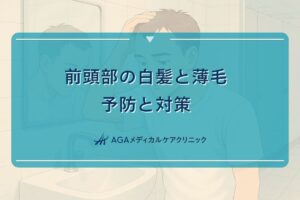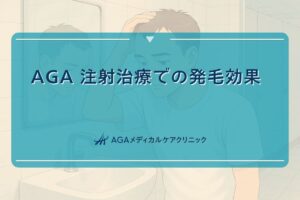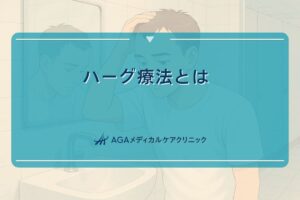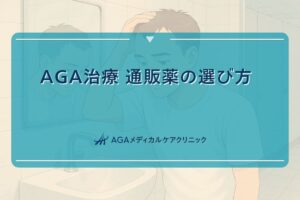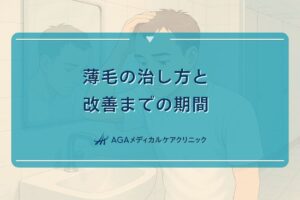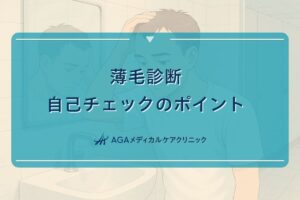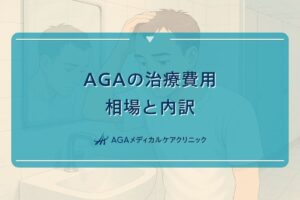生活の変化やストレスなどが重なり、一時的に抜け毛が増える「休止期脱毛症」は多くの方に見られるものです。
症状が続くと「いつ治るのか」「どんな対策を取ればいいのか」と不安になるかもしれません。
この記事では、休止期脱毛症とは何か、どのような症状が見られるのか、そして回復までの期間の目安や対処法についてまとめます。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
休止期脱毛症とは
日常的に見かける抜け毛とは少し違い、休止期脱毛症の場合は一定の時期に髪が急激に抜けやすくなります。
休止期脱毛症の定義
一般的に髪の毛は成長期・退行期・休止期を経て抜け落ちますが、休止期脱毛症では休止期に入る毛髪の割合が増えたり、休止期にとどまる毛髪が増えたりすることで、一時的な抜け毛が増加します。
通常の抜け毛量よりも多いと感じる状態が持続する場合、休止期脱毛症を疑うケースがあります。髪全体がまばらに抜けるのが特徴で、頭皮を触ると全体が薄くなっていると感じる方が多いです。
休止期脱毛症が疑われるきっかけ
休止期脱毛症が疑われるきっかけには、洗髪時に抜ける毛の量の増加やブラッシング時の抜け毛の目立ちなどがあります。
また、「髪のコシやハリが弱くなった」「頭頂部や生え際が薄くなったように感じる」などの訴えが増えると、日常生活でも不安が大きくなるかもしれません。
こうした変化を自覚した際には、髪の成長周期に異常が生じている可能性を考える必要があります。
休止期脱毛症の発症メカニズム
髪の成長周期は主に次の3つの段階で構成されています。
| サイクル | 特徴 |
|---|---|
| 成長期 | 毛髪が伸びる段階 |
| 退行期 | 毛髪の成長が止まり、抜ける準備を始める段階 |
| 休止期 | 毛髪が抜け、次に生えてくる毛髪の準備が整う段階 |
休止期脱毛症は、このサイクルのうち休止期に入る毛髪が増えてしまう状況です。
何らかの原因でストレスやホルモンバランスが乱れると、多くの毛髪が一度に休止期へ移行し、数か月後に抜け毛が一気に増える現象が起こります。
休止期脱毛症が起こりやすい背景
急激なダイエットや栄養不良、精神的ストレス、睡眠不足、出産後のホルモンバランスの乱れなど、さまざまな要因が重なると休止期脱毛症が起こりやすいと考えられています。
男性・女性を問わず起こりますが、特に女性は出産前後でホルモンバランスに大きな変化があるため、一時的な抜け毛が生じやすい傾向があります。
休止期脱毛症に関連する要因
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| ストレス | 自律神経の乱れやホルモンバランスの変化を引き起こす場合がある |
| 栄養不良 | 髪の成長に必要なタンパク質やビタミンなどが不足している |
| 睡眠不足 | 成長ホルモン分泌のバランスが崩れ、頭皮環境が悪化しやすい |
| ホルモン変動 | 出産前後や更年期など、女性特有の大きなホルモン変化が影響 |
| 遺伝的要素 | 家族に脱毛経験がある場合は、影響を受けやすい可能性がある |
このように多様な原因が重なると髪の毛のサイクルが乱れやすくなり、休止期脱毛症につながりやすいです。
髪の抜け毛が増えたときには、これらの要因を振り返ってみましょう。日常生活のなかでストレスを感じやすいか、食生活が偏っていないか、最近ダイエットを急に始めなかったかなど、生活習慣を見直すと原因を特定できるかもしれません。
- 髪質や頭皮環境の変化に早く気づく
- 原因となる生活習慣を把握する
- 自己判断で過度なヘアケアをしない
- 変化を実感したら医療機関に相談する
こうした点に意識を向けると、早めの対処がしやすくなります。
ほかの脱毛症との違い
一口に脱毛症といっても、原因や症状には複数のタイプがあります。一般的に知られている男性型脱毛症(AGA)や円形脱毛症、女性のびまん性脱毛症などと、休止期脱毛症はどのように異なるのでしょうか。
ここでは、それぞれの脱毛症との違いを整理します。
AGAとの違い
AGA(男性型脱毛症)は男性ホルモンの影響によって起こります。前頭部や頭頂部から毛が薄くなっていく特徴があり、進行しやすい点が注目されています。
休止期脱毛症は一時的に抜け毛が増えるもので、原因が解消すれば髪の成長サイクルが整いやすくなります。AGAの場合は進行性であるため、治療を怠ると薄毛が進行する可能性があります。
AGAと休止期脱毛症の特徴
| 項目 | AGA(男性型脱毛症) | 休止期脱毛症 |
|---|---|---|
| 原因 | 男性ホルモン(DHT)の影響が主 | ストレス、ホルモンバランスの乱れ、栄養不良など多岐 |
| 抜け毛の部位 | 前頭部や頭頂部が中心 | 全体的にまばら |
| 抜け毛の進行 | 徐々に進行する傾向 | 原因が解消すれば回復しやすい |
| 治療の必要性 | AGA治療薬やケアが必要 | 生活習慣の改善や一時的ケアで回復を目指すことが多い |
AGAの場合は、早めに適切な治療を受けると進行を抑えられます。一方、休止期脱毛症は原因の改善とともに髪の成長サイクルが整っていく可能性が高いです。
円形脱毛症との違い
円形脱毛症は自己免疫の異常が関与すると考えられており、円形または複数の円形が合体した形で脱毛するのが特徴です。
短期間で一気に抜け落ちる場合も多く、見た目の変化に大きな衝撃を受ける方が少なくありません。
休止期脱毛症の場合は、全体的に毛が抜けるため部分的な脱毛斑は生じにくいです。
女性のびまん性脱毛症との比較
女性のびまん性脱毛症は、加齢や女性ホルモンの低下によって髪全体が薄くなるものです。休止期脱毛症も髪全体が抜けやすくなるという点では似ていますが、びまん性脱毛症は進行性であり、長期的に少しずつ髪が薄くなっていく特徴があります。
一方、休止期脱毛症は生活習慣やホルモン変化などの原因が解消されれば、数か月後には抜け毛の量が落ち着いてくる傾向があります。
脱毛症の種類と特徴
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| AGA | 男性ホルモンに起因し進行しやすい |
| 円形脱毛症 | 自己免疫が関与し、円形に脱毛する |
| 女性のびまん性脱毛症 | 加齢やホルモン低下によってゆるやかに進行 |
| 休止期脱毛症 | 特定の要因で一時的に抜け毛が増え、原因が解消されれば回復しやすい |
このような違いを理解すると、自分の症状がどの脱毛症に近いか判断しやすくなります。
休止期脱毛症の症状
休止期脱毛症の症状は「一時的に大量の抜け毛が増えた」と感じる方が多いです。具体的には髪全体が薄くなっているように感じたり、抜けた髪を集めると量が多いことに驚いたりするケースがあります。
抜け毛の特徴
休止期脱毛症による抜け毛は、頭皮全体に及ぶのが特徴です。ブラッシング時に抜ける髪や、シャンプーの際に排水溝に溜まる髪が増えたと感じる方もいます。
一方、髪の太さや色、形状には大きな異常が見られないことが多いです。髪そのものが細くなっているわけではないが、抜ける本数が一時的に増えているというイメージです。
抜け毛の本数の目安
| 抜け毛の本数(1日あたり) | 状態 |
|---|---|
| 約50本~100本 | 生理的な抜け毛の範囲 |
| 約100本~300本 | 抜け毛が増えている可能性 |
| 300本以上 | 休止期脱毛症や他の脱毛症を疑う必要がある |
もちろん個人差があるため、一概に数値だけでは判断できませんが、この表を目安として捉えると把握しやすいかもしれません。
頭皮の状態
休止期脱毛症では、頭皮の炎症や赤み、かゆみなどが特に強く見られない場合が多いです。頭皮にトラブルがないのに抜け毛だけが増えている、という状況が典型的です。
頭皮をよく観察して、目立った炎症が見られないか、傷や湿疹が起きていないかを確認してみるといいでしょう。
心理的な影響
抜け毛が増えると、見た目の変化が気になって気分が落ち込みやすくなります。特に女性の場合は髪型をアレンジしたり、髪質にこだわったりする方が多いため、急激な抜け毛は大きな精神的負担となります。
こうしたストレスがさらに休止期脱毛症を悪化させる要因になるケースもあるため、意識して気持ちのケアを行うのが大切です。
- 頭皮トラブルの有無を観察する
- 抜け毛の本数をおおまかにチェックする
- 生活習慣を点検し、睡眠や栄養状態を把握する
- 必要に応じて医師に相談する
こうした対策をとりながら、自分の髪や頭皮の状態をモニタリングしてみてください。
休止期脱毛症の原因と誘因
休止期脱毛症は一時的な抜け毛が増える症状ですが、原因を特定するためには多角的な視点が必要です。
ストレスや栄養不足、ホルモンバランスの乱れなど、複数の誘因が複合的に作用するケースが珍しくありません。
ホルモンバランスと休止期脱毛症
人間の体内では、性ホルモンだけでなく副腎皮質ホルモンなどさまざまなホルモンが分泌され、それぞれが全身に影響を与えます。
ストレスが強いと副腎皮質ホルモンが増加してホルモンバランスが崩れ、毛髪の成長期を短縮する可能性があります。
女性の場合、出産前後で女性ホルモンのエストロゲン量が急激に変化すると、休止期脱毛症につながる場合があります。
ホルモンバランスの乱れが毛髪に及ぼす影響
| ホルモンの種類 | 主な作用 | 毛髪への影響 |
|---|---|---|
| エストロゲン | 女性の生殖機能や皮膚の新陳代謝を調整 | 髪を健康的に保つ作用があるが、急激な減少が脱毛に影響 |
| テストステロン | 筋肉量や体毛の増加に関係 | 過剰になると脱毛リスクが高まる可能性 |
| 副腎皮質ホルモン | ストレス時に分泌が増え、代謝や免疫を調整 | 過剰分泌でホルモンバランスが崩れ、抜け毛が増える場合がある |
ホルモンバランスの乱れは、一朝一夕で解消するものではありませんが、生活習慣の改善や医療機関での相談によってコントロールを図ることも可能です。
栄養不足やダイエット
急激なダイエットや偏った食生活で栄養不足が続くと、髪の成長に必要なタンパク質やビタミン、ミネラルが不足しやすくなります。
これによって髪の成長期が短くなり、休止期に移行しやすくなるため、一時的な抜け毛が増えるときがあります。
特に、炭水化物や脂質を極端に制限するダイエットは、体全体の代謝に影響を及ぼし、頭皮への血行を悪化させる場合があるため注意が必要です。
- タンパク質(肉、魚、卵、大豆製品)を意識して摂取する
- ビタミンB群や亜鉛など、髪の成長に役立つ栄養素に注目する
- 極端なカロリー制限は避け、バランスの良い食事を心掛ける
こうしたポイントを押さえると、栄養不足による休止期脱毛症のリスクを減らせます。
ストレスとの関連
強いストレスや急な環境変化が続くと、自律神経が乱れ、血行不良を起こしやすいです。その結果、頭皮への栄養供給が滞り、髪の成長期を維持しにくくなる可能性があります。
心理的な負担が髪に及ぶまでには数か月のタイムラグがあるため、「何か大きな出来事があった3か月後に抜け毛が増えた」などの事象が見られるかもしれません。
休止期脱毛症の回復において、ストレスを緩和する手段を見つけることが大切です。
ストレス発散の工夫
- 趣味や運動、散歩などで気分転換を図る
- 十分な睡眠時間を確保し、就寝前のスマホ使用を控える
- 好きな音楽や動画を視聴してリラックスする
- カウンセリングや友人との会話で気持ちを共有する
このようにストレスを抑える手段を講じると、休止期脱毛症の改善を後押しできます。
遺伝的要素
遺伝はAGAなどで大きな役割を果たすと考えられていますが、休止期脱毛症にも遺伝的な影響が全くないとは言いきれません。
家族に抜け毛や薄毛の傾向があると、髪の成長周期が乱れやすい体質を受け継ぐ可能性があります。
ただし、休止期脱毛症はあくまで一時的な現象のため、遺伝だけでなく生活習慣やストレスなどの環境要因が大きく関与する点を理解することが大切です。
休止期脱毛症の回復までの期間
休止期脱毛症は、一時的に大量の抜け毛が増えるものの、原因が解消されれば比較的早期に回復し始めるのが特徴です。ただし、その回復スピードには個人差があります。
個人差の理由
休止期脱毛症の回復期間は、早い人では数か月程度で抜け毛が減って回復傾向が見られます。一方、原因が長期的に続いていると、回復までに半年から1年ほどかかるケースもあります。
個人差が生じる理由としては、下記のような要因が考えられます。
- ホルモンバランスの状態
- 日常的なストレスの度合い
- 食生活や栄養摂取の状況
- 睡眠の質や生活リズム
- 頭皮環境やヘアケアの方法
髪は日々伸びてはいるものの、目に見える変化として感じられるまでには時間が必要です。焦らずに経過を観察しながら改善策を続けると良いです。
回復を遅らせる可能性のある生活習慣
| 生活習慣 | 回復に与える悪影響 |
|---|---|
| 深夜までのスマホやPC作業 | 睡眠不足によるホルモンバランスの乱れ |
| 極端な食事制限 | 栄養不足で髪の成長力が低下 |
| 喫煙・過度の飲酒 | 血行不良や栄養吸収の阻害 |
| 過度なヘアアレンジ | 頭皮や毛根への負担が大きく、切れ毛や抜け毛の増加 |
こうした生活習慣を見直すと、休止期脱毛症の回復を促しやすくなります。
回復の目安とプロセス
休止期脱毛症の回復は、まず抜け毛の量が落ち着くことが第一段階です。その後、新しく生えてくる髪のボリュームを感じるまでには、もう少し時間がかかるケースがあります。
髪が増え始めたと実感できるタイミングは以下のような流れをたどります。
- 抜け毛が減少し始める(1~3か月)
- 頭皮の手触りや見た目の薄さに変化が出る(3~6か月)
- 新たに生えてきた髪の長さが十分になる(6か月~1年)
あくまで目安であり、体調や生活習慣によって早まることもあれば遅れることもあります。
- 抜け毛の本数が以前より減った
- 髪のボリュームやハリが戻ってきた
- 分け目や生え際に短い毛が生えているのを確認できる
こうしたサインを見逃さずに気長に観察すると、回復の手ごたえを得やすくなります。
注意が必要なケース
休止期脱毛症だと思って対処を続けても、なかなか抜け毛が治まらない場合や、頭皮に異常を感じるケースがあります。
具体的には、次のような状況では医療機関の受診を検討したほうがいいかもしれません。
- 抜け毛の量が半年以上減らない
- 頭皮にかゆみや痛み、発疹がある
- 部分的に髪がごっそり抜け落ちている
- 生活習慣を改善しても効果がない
別の脱毛症が隠れている場合もあるため、専門家に相談すると原因を特定しやすくなります。
受診時に伝えると役立つ情報
- 抜け毛が増え始めた時期
- 日々のストレス状況や生活リズム
- 食生活の内容やサプリメントの使用状況
- 過去の脱毛症の有無や家族歴
これらの情報をスムーズに伝えると、医師や専門家の診断がより正確になりやすいです。
休止期脱毛症の対処法
原因を把握したうえで、正しい対処を行うことが休止期脱毛症からの回復を早める鍵になります。生活習慣の見直しから始まり、サプリメントやヘアケア製品の選び方など、多角的な取り組みが望ましいです。
生活習慣の見直し
休止期脱毛症の改善において、最初に検討したいのが生活習慣の再点検です。栄養バランスや睡眠時間、ストレス管理などを整えると、髪の成長サイクルが正常化しやすくなります。
- 規則正しい食事と十分なタンパク質の摂取
- 就寝時間を一定にして睡眠の質を高める
- 軽い運動や深呼吸などでストレスを軽減する
- 頭皮マッサージを日課にして血行促進を図る
生活習慣の改善前後で期待できる変化
| 項目 | 改善前 | 改善後 |
|---|---|---|
| 食事 | 偏食や不規則な食事 | バランスの良い食生活 |
| 睡眠 | 深夜まで作業やスマホを見続ける | 早めの就寝と睡眠時間の確保 |
| ストレス管理 | ストレスを溜め込んで発散できない | 日常的にストレスを解消する方法を習慣化 |
| ヘアケア | 洗浄力の強いシャンプーでゴシゴシ洗う | 頭皮環境を整えるシャンプーやマッサージ |
生活習慣を見直すと、髪だけでなく肌や体調全般にも良い影響を与えやすいです。
サプリメントや栄養管理
現代の食事環境では、仕事や家事が忙しくて十分な栄養をとりにくい方も多いかもしれません。そこで、不足しがちな栄養素を補う手段としてサプリメントの活用が考えられます。
ただし、サプリメントはあくまでも補助的なものであり、過剰摂取は避ける必要があります。医療機関で血液検査を行い、不足している栄養素を把握すると、より的確に選びやすくなります。
髪の健康に関わる代表的な栄養素
| 栄養素 | 働き | 食材例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪を構成するケラチンの材料 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 亜鉛 | タンパク質合成に必要なミネラル | 牡蠣、牛肉、ナッツ |
| ビタミンB群 | 代謝促進や皮膚・粘膜の健康維持 | レバー、緑黄色野菜 |
| ビタミンC | コラーゲン生成や抗酸化 | 柑橘類、いちご、キウイ |
| 鉄分 | 酸素を運搬し頭皮を健やかに保つ | レバー、赤身肉、ほうれん草 |
これらの栄養素を食事でまかなうのが理想的ですが、どうしても不足しがちな場合はサプリメントを検討するといいでしょう。
シャンプーや頭皮マッサージ
頭皮環境を整えることは、休止期脱毛症の改善にとって大切です。シャンプーの選び方や洗髪方法、頭皮マッサージなど、日々のヘアケアを見直すと血行が促進され、髪の成長を後押しする効果が期待できます。
- 洗髪前にブラッシングをしてホコリや汚れを落とす
- シャンプーは適量を使い、泡立ててから頭皮にしっかり行きわたらせる
- 指の腹を使って頭皮全体をマッサージするように洗う
- 洗い流しは十分に行い、シャンプーが残らないように注意する
頭皮マッサージのポイント
- お風呂で髪を濡らす前に、軽く頭皮をほぐす
- 耳の上から頭頂部、後頭部にかけて指を動かして血行を促す
- 力任せにこするのではなく、指の腹で小さく円を描くように行う
- ストレス緩和にもつながり、続けることで実感しやすい
頭皮ケアを丁寧に行うと、抜け毛だけでなく頭皮の脂質バランスやフケの抑制にも効果が期待できます。
医療機関での相談
「休止期脱毛症が治った」という声を聞くと、自然に回復していく印象を受けるかもしれません。
しかし、原因や状態によっては医療機関での相談が有効です。特に、他の脱毛症との鑑別が必要な場合や、長期間改善が見られない場合は早めに専門医に診てもらうと安心です。
医師の判断で血液検査やホルモン検査などを行い、必要に応じて栄養療法や内服薬、外用薬などの治療の組み合わせが考えられます。
休止期脱毛症とAGA治療の関係
休止期脱毛症は本来、一時的な脱毛状態であり、原因が取り除かれると回復する方が多いです。しかし、なかには「休止期脱毛症が治ったと思っても、結局薄毛が進行している気がする」というケースがあります。
実はAGA(男性型脱毛症)やびまん性脱毛症が潜在的に進行していた可能性もあり、休止期脱毛症のタイミングで顕在化することも珍しくありません。
休止期脱毛症が治った後にAGA治療を考える
男性に多いケースとして、若い頃は髪がフサフサだったが、ある時期に休止期脱毛症で抜け毛が増え、それをきっかけに髪の状態をより注意深く観察するようになったという話を耳にします。
そこでAGAの症状が潜在的にあった場合、休止期脱毛症の回復を待っている間にも、じわじわと生え際や頭頂部の髪が薄くなっていくことがあります。髪の量が戻らないと感じたときに、初めてAGA治療を検討するケースです。
- 休止期脱毛症とAGAが同時に起こっている
- 休止期脱毛症で抜け毛が増えた後も、AGAの進行によって生え際が後退し続ける
- 早めにAGAと診断されれば、治療によって進行を緩やかにできる
このような可能性を踏まえると、抜け毛が気になる場合は早めの診察が勧められます。
AGA治療を検討するタイミング
| 状況 | 対応 |
|---|---|
| 休止期脱毛症の抜け毛がおさまらない | 原因の見直しと専門医への相談 |
| 生え際や頭頂部の後退が気になる | AGAの可能性を視野に入れ検査を受ける |
| 家族に薄毛が多く自分も抜け毛が増えた | 早めの受診でAGAかどうか判断してもらう |
治療開始のタイミングが早いほど、望ましい発毛や維持が期待できます。
クリニックでの検査と診断
休止期脱毛症かAGAかを判断するには、クリニックでの検査が大きな助けになります。問診や視診だけでなく、血液検査や頭皮の状態を拡大して確認する場合もあります。
さらにホルモンバランスを調べると、休止期脱毛症を引き起こしている別の要因を見つけ出すことも可能です。
必要に応じてAGA治療薬の処方や栄養サポートを組み合わせて脱毛状態の改善を目指します。
発毛を目指す治療
休止期脱毛症であっても、髪の密度が大きく低下した場合や、AGAを併発している場合は積極的な発毛治療が必要になるケースがあります。
服薬、外用薬、注入療法などを組み合わせて、頭皮環境を整えながら毛母細胞の働きを活性化する治療が行われることがあります。
- 内服薬(AGA治療薬など)
- 外用薬(育毛剤、発毛剤)
- 生活習慣改善指導
- サプリメントなどの栄養サポート
このように複数の方法を組み合わせると、休止期脱毛症後の発毛をより効率的にサポートできる可能性があります。
まとめ
休止期脱毛症は原因さえ改善されれば自然に治る場合が多い一方、AGAやほかの脱毛症が隠れている可能性もあるため、髪の様子に気になる変化があれば専門家に相談すると安心です。
薄毛専門のクリニックでは、カウンセリングから治療、アフターケアまで一貫して行っているところも多くあります。
抜け毛が増えた、髪のボリュームが減ったと感じたら、いちど医療機関に足を運んでみましょう。
参考文献
HARRISON, S.; SINCLAIR, R. Telogen effluvium. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 389-395.
REBORA, Alfredo. Telogen effluvium: a comprehensive review. Clinical, cosmetic and investigational dermatology, 2019, 583-590.
GROVER, Chander; KHURANA, Ananta. Telogen effluvium. Indian journal of dermatology, venereology and leprology, 2013, 79: 591.
LIYANAGE, Deepa; SINCLAIR, Rodney. Telogen effluvium. Cosmetics, 2016, 3.2: 13.
MALKUD, Shashikant. Telogen effluvium: a review. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR, 2015, 9.9: WE01.
ASGHAR, Fahham, et al. Telogen effluvium: a review of the literature. Cureus, 2020, 12.5.
GILMORE, Stephen; SINCLAIR, Rodney. Chronic telogen effluvium is due to a reduction in the variance of anagen duration. Australasian journal of dermatology, 2010, 51.3: 163-167.
SINCLAIR, Rodney. Chronic telogen effluvium: a study of 5 patients over 7 years. Journal of the American Academy of Dermatology, 2005, 52.2: S12-S16.