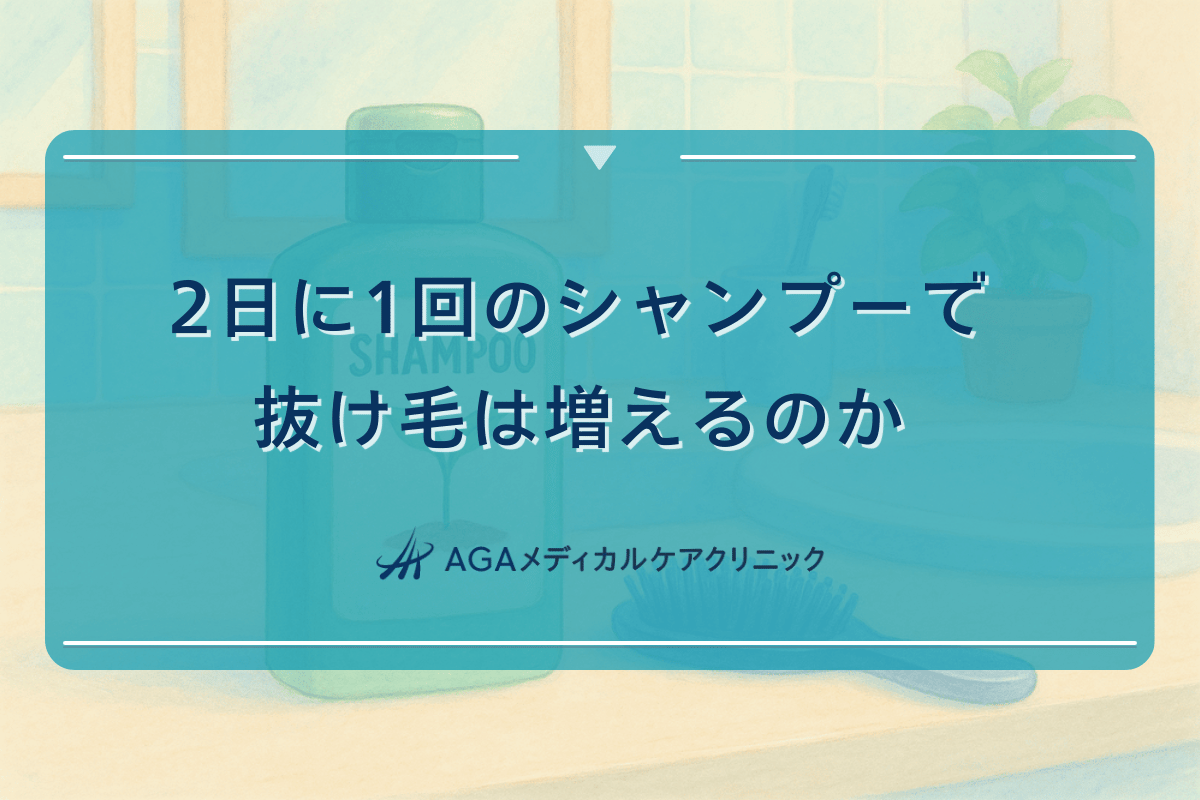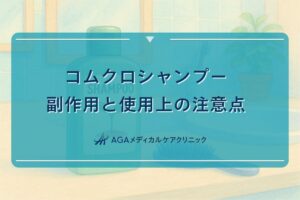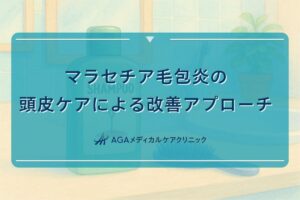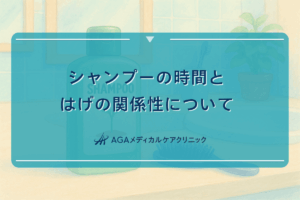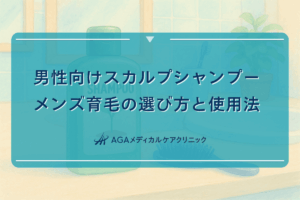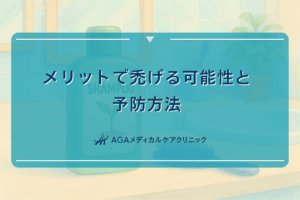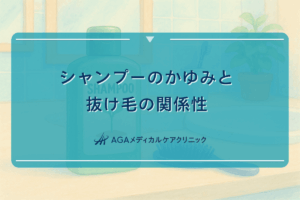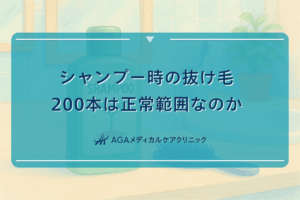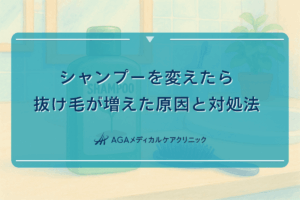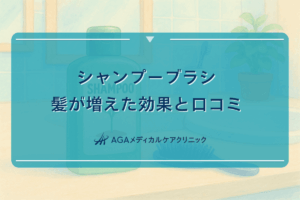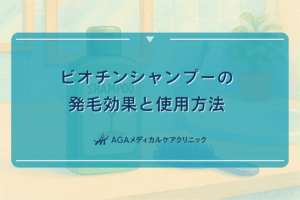シャンプーの頻度について「毎日洗うと頭皮に悪い」「2日に1回が良いらしい」といった情報を耳にしたことはありませんか。
しかし、その情報が本当にご自身の頭皮に合っているのか、不安に感じる方も多いでしょう。
特に抜け毛が気になり始めると、シャンプーの回数を減らしたことでかえって抜け毛が増えたように感じ、悩みが深まることもあります。
この記事では、シャンプーの頻度と抜け毛の本当の関係について専門的な観点から詳しく解説します。
ご自身の頭皮タイプを知り、正しいヘアケアを実践することで頭皮環境を健やかに保ち、抜け毛の不安を解消する一助となれば幸いです。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
シャンプーを2日に1回にすると抜け毛は増える?噂の真相
シャンプーの頻度を2日に1回に減らした途端、洗髪時の抜け毛が増えたように感じて驚く方は少なくありません。これは本当にシャンプーの回数を減らしたことが原因なのでしょうか。
その背景にある理由と、頭皮環境との関係を解き明かします。
抜け毛が増えたと感じる主な理由
シャンプーを2日に1回にすると、本来毎日洗い流されていたはずの寿命で自然に抜ける髪の毛が頭皮に留まります。その結果、2日分の抜け毛が一度に洗い流されるため、量が多く見えてしまうのです。
1日に抜ける髪の毛は健康な人でも50本から100本程度あります。2日間洗わなければ、その本数が単純に倍になるため、排水溝に溜まる髪の毛の量に驚いてしまうのです。
これは異常な抜け毛ではなく、見かけ上の問題であることがほとんどです。
シャンプー頻度変更後の抜け毛量の変化
| シャンプー頻度 | 1回の洗髪で流れる抜け毛(目安) | 解説 |
|---|---|---|
| 毎日 | 50~100本 | 1日分の自然脱毛が洗い流される。 |
| 2日に1回 | 100~200本 | 2日分の自然脱毛がまとめて洗い流される。 |
| 3日に1回 | 150~300本 | 3日分の自然脱毛がまとめて洗い流される。 |

頭皮環境とシャンプー頻度の関係
シャンプーの最も重要な役割は頭皮の余分な皮脂や汚れを洗い流し、清潔に保つことです。シャンプーの頻度が適切でないと頭皮環境が悪化し、かえって抜け毛を助長する可能性があります。
例えば、皮脂の分泌が多い方がシャンプーの回数を減らしすぎると毛穴に皮脂が詰まり、炎症やかゆみを引き起こすことがあります。
この状態が続くと健康な髪の成長が妨げられ、抜け毛につながる恐れがあります。
専門家が解説する適切なシャンプー頻度
結論から言うと「誰にとっても適したシャンプー頻度」というものは存在しません。適切な頻度は個人の頭皮タイプ、肌質、季節、生活習慣によって大きく異なります。
一般的には普通肌や乾燥肌の方は2日に1回でも問題ないことが多いですが、脂性肌の方や汗をかきやすい方は毎日のシャンプーが必要です。
自分の頭皮の状態を正しく把握し、それに合わせた頻度を見つけることが重要です。
なぜシャンプーの頻度で悩む人が多いのか
抜け毛を気にする多くの方が、シャンプーの頻度という基本的なケアで悩んでいます。その背景には情報過多の現代社会ならではの理由や、ご自身の身体に対する深い不安が隠されています。
ここでは、多くの方が抱える悩みの核心に迫ります。
「洗いすぎは良くない」という情報の氾濫
インターネットや雑誌で、「毎日のシャンプーは頭皮に必要な皮脂まで奪い、乾燥を招く」という情報が広く知られています。
この情報自体は間違いではありませんが、すべての人に当てはまるわけではありません。
この「洗いすぎは良くない」という言葉だけが一人歩きし、皮脂の多い方までシャンプーを控えてしまい、かえって頭皮トラブルを招くケースが見られます。
自分の頭皮タイプがわからない不安
多くの方は、ご自身の顔の肌タイプ(脂性肌、乾燥肌など)は把握していても、頭皮のタイプまで正確に理解しているわけではありません。
そのため自分に合ったシャンプー頻度がわからず、「2日に1回が良いらしい」といった一般的な情報に頼りがちになります。
自分の状態がわからないままケアを続けることは、大きな不安につながります。
頭皮の状態に関する自己認識のズレ
| 思い込み | 実際の状態 | 起こりうる問題 |
|---|---|---|
| 自分は乾燥肌だ | 実は皮脂が多い混合肌 | 洗浄力不足で毛穴が詰まる |
| 頭皮は丈夫だ | 季節の変わり目で敏感になっている | 刺激の強いシャンプーで炎症を起こす |
| フケは乾燥が原因だ | 皮脂をエサにする菌が原因の脂性フケ | 保湿ケアで悪化させる |
抜け毛に対する過剰な心配と自己判断の罠
一度抜け毛が気になり始めると、シャンプー時の抜け毛一本一本に過敏になりがちです。
そして「シャンプーの仕方が悪いのではないか」「回数が合っていないのではないか」と、原因をヘアケアに求め、自己判断で頻繁に方法を変えてしまいます。
この行動が、かえって頭皮環境を不安定にし、悩みを深刻化させる悪循環を生むことがあります。
ライフスタイルの変化と頭皮への影響
食生活の乱れ、睡眠不足、ストレスの増加など、現代人を取り巻くライフスタイルは頭皮環境に直接影響を与えます。
例えば、脂っこい食事が多いと皮脂の分泌が増え、以前は合っていたシャンプー頻度では対応できなくなることがあります。
自身の生活の変化を省みず、シャンプーの回数だけに原因を求めてしまうことも悩みが解決しない一因です。
正しいシャンプー頻度を見極める3つのポイント
自分に合ったシャンプー頻度を見つけることは、健やかな頭皮環境を保つための第一歩です。
ここでは、ご自身の状態を正しく把握し、適切な頻度を判断するための3つの重要なポイントを解説します。
自分の頭皮タイプ(脂性肌・乾燥肌・混合肌)を知る
まずは、ご自身の頭皮がどのタイプに当てはまるかを確認しましょう。夕方になると髪がベタつく、フケやかゆみがあるなど、日常のサインから推測できます。
正確な判断が難しい場合は、専門のクリニックで相談することも一つの方法です。
頭皮タイプのセルフチェックリスト
| 頭皮タイプ | 主な特徴 | 推奨されるケアの方向性 |
|---|---|---|
| 脂性肌 | 日中に髪がベタつく、頭皮が脂っぽい、フケが湿っている | 毎日のシャンプーで余分な皮脂をしっかり落とす |
| 乾燥肌 | 頭皮がつっぱる感じがする、フケがカサカサしている | 洗浄力のマイルドなシャンプーで2日に1回程度 |
| 混合肌 | 頭頂部はベタつくが、生え際は乾燥するなど部位で違う | 状態に合わせて洗い方を工夫する |
季節や環境の変化に合わせた調整
頭皮の状態は一年中同じではありません。夏場は汗や皮脂の分泌が増えるため、シャンプーの回数を増やす必要があるかもしれません。
逆に冬場は空気が乾燥し、頭皮も乾燥しやすくなるため、洗いすぎに注意が必要です。季節の変化に応じて柔軟に頻度を見直すことが大切です。
季節ごとのシャンプー頻度調整の目安
| 季節 | 頭皮への影響 | 頻度調整のポイント |
|---|---|---|
| 夏(梅雨~盛夏) | 汗、皮脂の分泌が増加。蒸れやすい。 | 脂性肌でなくても毎日洗うことを検討。 |
| 冬(晩秋~冬季) | 空気が乾燥し、頭皮の水分が奪われやすい。 | 乾燥肌の方は洗いすぎに注意し、保湿を心がける。 |
日中の活動量や汗の量を考慮する
デスクワーク中心の日と、スポーツで大量に汗をかいた日とでは頭皮の汚れ具合は全く異なります。運動後や屋外での作業後は、汗やホコリをその日のうちに洗い流すことが望ましいです。
ご自身のその日の活動内容に合わせて、シャンプーするかどうかを判断する習慣をつけましょう。
頭皮タイプ別に見る推奨シャンプー頻度

ご自身の頭皮タイプが把握できたら、次はそのタイプに合わせた具体的なシャンプー頻度とケア方法を実践していきましょう。
ここではタイプ別に推奨される頻度の目安と、注意すべき点について解説します。
脂性肌の方向けのシャンプー頻度と注意点
皮脂の分泌が多い脂性肌の方は、原則として毎日のシャンプーが必要です。
皮脂は時間とともに酸化し、頭皮の刺激物へと変化します。これを放置すると毛穴の詰まりや炎症、さらには脂漏性皮膚炎などを引き起こし、抜け毛の原因となり得ます。
洗浄力が適度にあるアミノ酸系や頭皮ケアを目的としたシャンプーを選び、余分な皮脂をしっかり洗い流しましょう。
乾燥肌・敏感肌の方向けのシャンプー頻度とケア方法
頭皮が乾燥しやすい、あるいは刺激に弱い方は、2日に1回のシャンプーを基本に考えて良いでしょう。毎日のシャンプーは必要な皮脂まで取り除き、バリア機能の低下を招く可能性があります。
洗浄力がマイルドで保湿成分が配合されたシャンプーを選び、洗髪時には爪を立てず、指の腹で優しくマッサージするように洗いましょう。
熱すぎるお湯は乾燥を助長するため、ぬるま湯を使用することも重要です。
頭皮タイプ別 推奨頻度とシャンプー選び
| 頭皮タイプ | 推奨頻度 | シャンプー選びのポイント |
|---|---|---|
| 脂性肌 | 毎日 | 適度な洗浄力があり、頭皮をすっきりさせるタイプ |
| 乾燥肌・敏感肌 | 2日に1回 | 洗浄力がマイルドなアミノ酸系、保湿成分配合タイプ |
| 普通肌・混合肌 | 毎日~2日に1回 | 基本はアミノ酸系で、頭皮の状態に合わせて調整 |
混合肌や普通肌の方向けのバランスの取れた頻度
特に大きなトラブルがない普通肌の方や部位によって状態が異なる混合肌の方は、毎日または2日に1回の頻度で、その日の頭皮の状態や活動量に応じて調整するのが良いでしょう。
基本的には洗浄力が穏やかなアミノ酸系のシャンプーを使い、ベタつきが気になる日はしっかり洗い、そうでない日は軽めに済ませるなど、洗い方に強弱をつけるのも一つの方法です。
自分の頭皮と対話するように、状態を観察する習慣が大切です。
抜け毛を減らすための正しいシャンプー方法

シャンプーの頻度だけでなく、その「やり方」も頭皮環境と抜け毛に大きく影響します。間違った洗い方は頭皮を傷つけたり、毛穴を詰まらせたりする原因になります。
ここで、抜け毛予防につながる正しいシャンプーの手順を確認しましょう。
洗髪前のブラッシングの重要性
シャンプー前に髪が乾いた状態でブラッシングを行うと髪の絡まりをほどき、表面のホコリや汚れを大まかに落とせます。
このひと手間により、シャンプー時の泡立ちが良くなり、少ない洗浄剤で効率的に洗うことができます。また、頭皮への適度な刺激が血行を促進する効果も期待できます。
- 髪の絡まりを解消
- ホコリやフケを浮かせる
- 頭皮の血行促進
- シャンプーの泡立ち向上
シャンプーの泡立て方と洗い方の基本
シャンプー剤を直接頭皮につけるのは避けましょう。まず手のひらでシャンプー剤を軽くなじませてから髪全体につけ、しっかりと泡立てます。
洗う際は爪を立てずに指の腹を使って、頭皮をマッサージするように動かします。髪の毛そのものをゴシゴシこするのではなく、頭皮の毛穴の汚れを揉み出すイメージで洗いましょう。
正しいシャンプー手順のポイント
| 手順 | ポイント | 目的 |
|---|---|---|
| 1. 予洗い | ぬるま湯で1~2分、頭皮と髪をしっかり濡らす | 汚れの7~8割を落とし、泡立ちを良くする |
| 2. 洗う | 指の腹で頭皮をマッサージするように洗う | 頭皮を傷つけず、毛穴の汚れを落とす |
| 3. すすぎ | シャワーで2~3分、洗い残しがないように徹底的に | かゆみやフケ、炎症の原因となるすすぎ残しを防ぐ |
すすぎ残しを防ぐための徹底したすすぎ
シャンプーやコンディショナーの成分が頭皮に残ると、毛穴を塞いだり、かゆみや炎症を引き起こしたりする原因になります。
特に生え際や耳の後ろ、首筋はすすぎ残しが多い部分です。洗う時間よりも長く、2~3分かけて丁寧に、ぬめり感が完全になくなるまですすぎましょう。
洗髪後の正しい乾かし方
濡れた髪はキューティクルが開いており、非常にデリケートな状態です。
タオルでゴシゴシこするのではなく、頭皮の水分を優しく拭き取り、髪はタオルで挟んで押さえるように水分を吸収させます。
その後、ドライヤーで髪から20cmほど離して、根本から乾かしていきましょう。自然乾燥は雑菌が繁殖しやすく、頭皮の臭いやかゆみの原因になるため避けるべきです。
シャンプーの回数以外に考えられる抜け毛の原因

シャンプーの頻度や方法を改善しても抜け毛が減らない場合、他に原因がある可能性を考える必要があります。
抜け毛は様々な要因が複雑に絡み合って起こるため、多角的な視点を持つことが重要です。
AGA(男性型脱毛症)の可能性
成人男性の抜け毛で最も多い原因がAGA(男性型脱毛症)です。これは男性ホルモンの影響でヘアサイクルが乱れ、髪が十分に成長する前に抜けてしまう進行性の脱毛症です。
生え際の後退や頭頂部の薄毛といった特徴的な症状が見られる場合、セルフケアだけでの改善は困難です。
AGAは早期に専門的な治療を開始することが、進行を食い止める上で非常に重要です。
- 生え際が後退してきた
- 頭頂部が薄くなったと感じる
- 髪の毛にハリやコシがなくなった
- 家族に薄毛の人がいる
生活習慣の乱れ(食事・睡眠・ストレス)
髪の毛は私たちが食べたものから作られます。栄養バランスの偏った食事、特に髪の主成分であるタンパク質や、その合成を助ける亜鉛、ビタミン類が不足すると健康な髪は育ちません。
また、睡眠不足や過度なストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、頭皮の血行不良を招いて抜け毛を増加させます。
髪の成長に関わる主な栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料となる | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助け、ヘアサイクルを正常に保つ | 牡蠣、レバー、牛肉 |
| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を促し、皮脂の分泌を調整する | 豚肉、うなぎ、マグロ、納豆 |
使用しているシャンプー剤との相性
シャンプー剤がご自身の頭皮タイプに合っていない場合も抜け毛の原因となり得ます。
例えば、乾燥肌の方が洗浄力の強すぎる高級アルコール系のシャンプーを使い続けると、頭皮の乾燥がさらに進み、バリア機能が低下してしまいます。
逆に脂性肌の方がマイルドすぎるシャンプーを使うと、皮脂を十分に落としきれず毛穴が詰まります。成分表示を確認し、自分の頭皮に合った製品を選ぶことが大切です。
抜け毛の悩みはいつ専門クリニックに相談すべきか
セルフケアは大切ですが、それだけでは解決できない問題もあります。特に抜け毛が進行性の場合、タイミングを逃さずに専門家の助けを求めることが、将来の髪を守るために重要です。
ここでは、クリニックへの相談を検討すべきサインを具体的に紹介します。
セルフケアで改善しない場合のサイン
シャンプーの頻度や種類を見直し、生活習慣の改善にも取り組んでみたけれど、2~3ヶ月経っても抜け毛が減らない、あるいは悪化しているように感じる場合は専門的な診断が必要です。
自己判断でのケアを長期間続けることは根本的な原因を見過ごし、症状を悪化させるリスクがあります。
明らかに抜け毛が増加したと感じる時
以前と比べて枕元の抜け毛やシャンプー時の抜け毛が明らかに増えたと感じる場合は注意が必要です。
「1日に100本程度は正常」とされても、ご自身の普段の量と比較して「倍以上になった」など、急激な変化は身体からの危険信号かもしれません。
特に髪全体のボリュームが減ってきたと感じる場合は早めに相談しましょう。
頭皮にかゆみや炎症などの異常がある場合
抜け毛に加えて、持続的なかゆみ、フケ、赤み、湿疹、痛みなど頭皮に何らかの異常を伴う場合は、単なるヘアサイクルの問題ではなく、皮膚疾患の可能性があります。
脂漏性皮膚炎や接触性皮膚炎などが隠れていることもあり、これらは専門医による適切な治療が必要です。
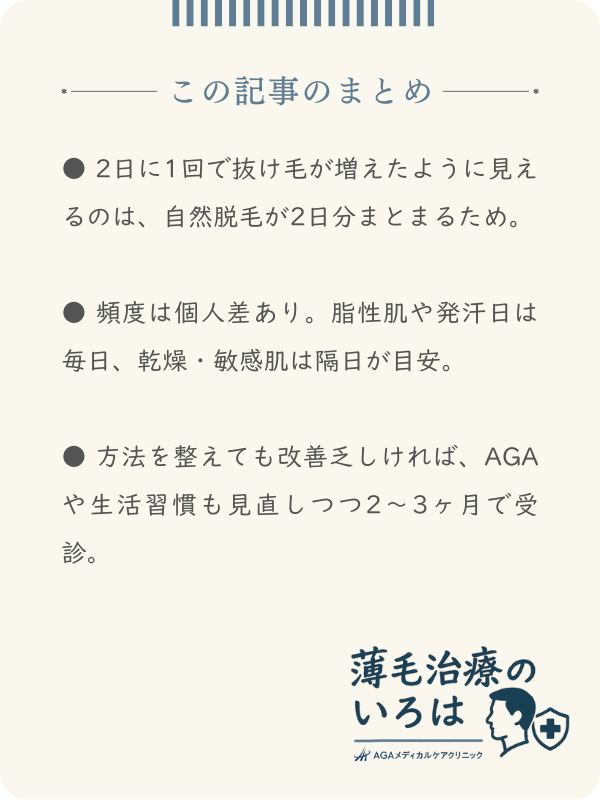
よくある質問
シャンプーや抜け毛に関して、多くの方から寄せられる質問にお答えします。日々のケアの参考にしてください。
- 朝シャンと夜シャンはどちらが良いですか?
-
どちらにも利点がありますが、頭皮環境を優先するなら夜のシャンプーをお勧めします。
日中に付着した皮脂、汗、ホコリなどの汚れをその日のうちにリセットすることで、睡眠中に頭皮を清潔な状態に保ち、髪の健やかな成長を促します。
朝シャンは寝癖直しや気分をすっきりさせる効果がありますが、時間がないとすすぎが不十分になりがちなので注意が必要です。
朝シャンと夜シャンの比較
夜シャンのメリット 朝シャンのメリット 頭皮ケア 1日の汚れをリセットし、頭皮を清潔に保てる 寝汗や皮脂を洗い流せる ヘアケア 成長ホルモンが分泌される夜間に頭皮環境を整える スタイリングがしやすくなる 注意点 しっかり乾かさないと雑菌が繁殖しやすい 急いで洗うとすすぎ残しや生乾きの原因に - 湯シャン(お湯だけで洗う)は効果がありますか?
-
湯シャンは、お湯だけで髪と頭皮を洗う方法です。乾燥が非常に強い方や、肌が極端に敏感な方にとっては、皮脂の取りすぎを防ぐという点で有効な場合があります。
しかし、整髪料を洗い流したり、脂性肌の方の余分な皮脂を落としたりする力はお湯だけでは不十分です。
多くの方にとっては洗浄力がマイルドなシャンプーを適切に使う方が、頭皮を健康に保ちやすいと言えます。
- シャンプーをしない日でも髪を濡らした方が良いですか?
-
シャンプーをしない日でも、ぬるま湯で髪と頭皮を洗い流す「予洗い」だけでも行うことをお勧めします。汗やホコリなど、お湯だけで落ちる汚れも多くあります。
このひと手間で頭皮を比較的清潔に保ち、次のシャンプー時の負担を軽減できます。
特に汗をかいた日などは、シャンプーを使わなくてもお湯で流すだけでもさっぱりします。
- 育毛シャンプーは毎日使った方が良いですか?
-
育毛シャンプーは頭皮環境を整える成分が含まれているものが多く、基本的には毎日使用することを想定して作られています。
ただし、製品によって推奨される使用頻度は異なりますので、必ずパッケージや説明書を確認してください。
ご自身の頭皮タイプに合っていることが大前提であり、もし使用中にかゆみや刺激を感じるようであれば、使用を中止し専門医に相談しましょう。
育毛シャンプーの使い方に戻る
参考文献
PUNYANI, Supriya, et al. The impact of shampoo wash frequency on scalp and hair conditions. Skin appendage disorders, 2021, 7.3: 183-193.
KIM, Sehyun, et al. Understanding the characteristics of the scalp for developing scalp care products. Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications, 2021, 11.3: 204-216.
WANG, Lei, et al. Effectiveness and tolerance of medicated shampoo containing selenium sulfide and salicylic acid in patients with seborrheic dermatitis. Journal of Dermatological Treatment, 2025, 36.1: 2506676.
POURADIER, F., et al. The worldwide diversity of scalp seborrhoea, as daily experienced by seven human ethnic groups. International Journal of Cosmetic Science, 2017, 39.6: 629-636.
KAMAMOTO, C. S. L., et al. Cutaneous fungal microbiome: Malassezia yeasts in seborrheic dermatitis scalp in a randomized, comparative and therapeutic trial. Dermato-endocrinology, 2017, 9.1: e1361573.
MONSELISE, Assaf, et al. What ages hair?. International journal of women’s dermatology, 2017, 3.1: S52-S57.