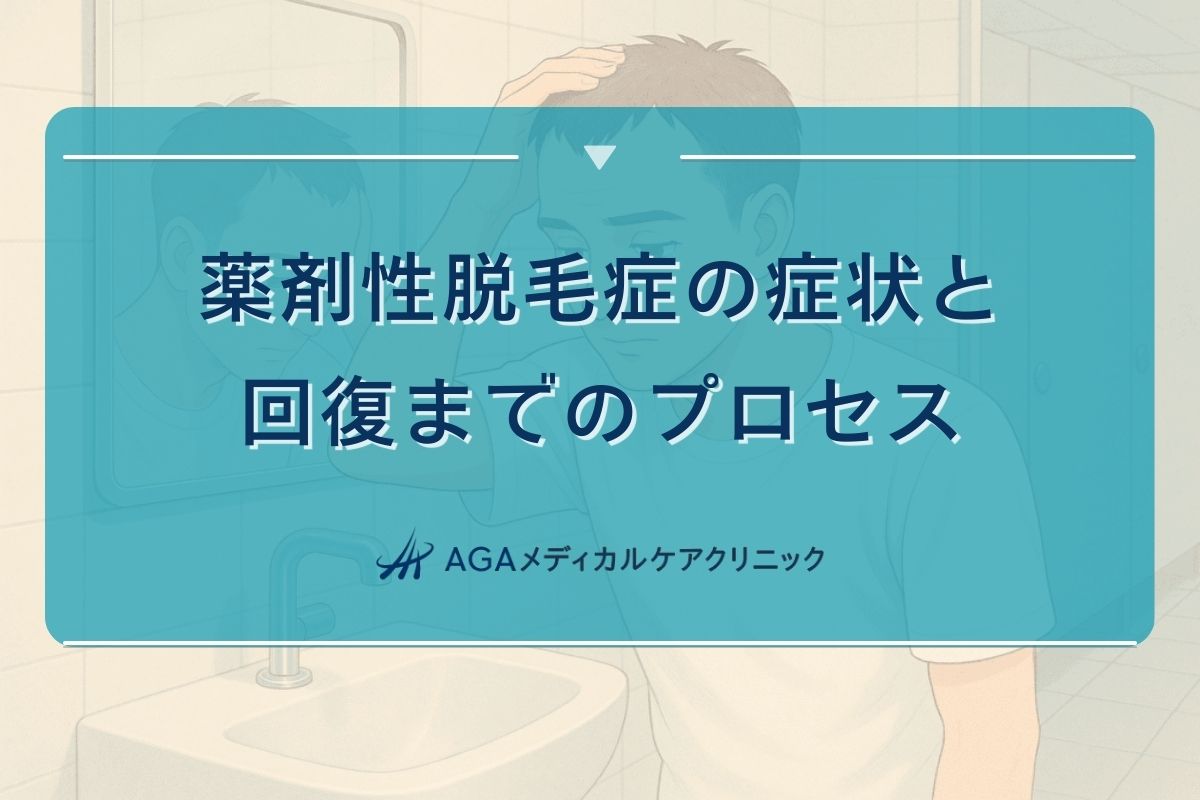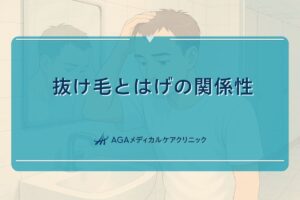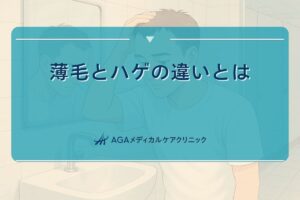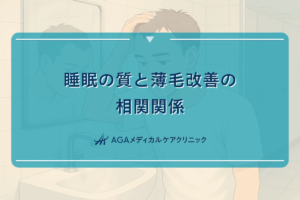特定の治療薬の使用が原因で髪が抜ける「薬剤性脱毛症」。ある日突然、あるいは徐々に髪が薄くなることに、大きな不安を感じる方は少なくありません。
この記事では薬剤性脱毛症がなぜ起こるのか、その症状や進行のパターン、そして回復に向けた正しい知識と治療法について、専門的な観点から詳しく解説します。
原因薬剤の中止や変更が回復の鍵ですが、自己判断は禁物です。回復までの期間や心のケアについても触れながら、お悩みの解決をサポートします。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
薬剤性脱毛症とは?原因となる薬剤と脱毛の仕組み
薬剤性脱毛症は内服薬や注射薬、点滴などの薬剤が原因で引き起こされる脱毛症です。病気の治療のために使用する薬剤が、髪の毛を作り出す毛母細胞の働きに影響を与えることで発生します。
原因となる薬剤は多岐にわたり、誰にでも起こりうる脱毛症の一つです。
薬剤性脱毛症の定義
薬剤の投与開始から数週間から数か月以内に脱毛が始まり、原因となる薬剤の使用を中止すると回復に向かうのが、薬剤性脱毛症の基本的な特徴です。
脱毛の程度は薬剤の種類や量、個人の体質によって大きく異なります。軽度なものから、頭髪全体が抜けてしまう重度なものまで様々です。
他の脱毛症と区別するためにも、使用中の薬剤を正確に把握することが重要になります。
脱毛を引き起こす主な薬剤の種類
様々な薬剤が脱毛の原因となる可能性があります。特に抗がん剤は有名ですが、それ以外にも日常生活で処方されることがある薬剤も含まれます。
どのような薬剤が影響を与える可能性があるかを知っておくことは大切です。
脱毛を引き起こす可能性がある薬剤の例
| 薬剤の系統 | 具体的な薬剤の例 | 脱毛の主な種類 |
|---|---|---|
| 抗がん剤 | 細胞障害性抗がん剤全般 | 成長期脱毛 |
| 抗うつ薬 | SSRI、三環系抗うつ薬など | 休止期脱毛 |
| 高血圧治療薬 | β遮断薬、ACE阻害薬など | 休止期脱毛 |
| 脂質異常症治療薬 | フィブラート系薬剤など | 休止期脱毛 |
髪の毛のサイクルと薬剤の影響
髪の毛には「ヘアサイクル」と呼ばれる周期があり、薬剤がこのサイクルの特定の段階に作用することで脱毛が起こります。
ヘアサイクルは髪が成長する「成長期」、成長が止まる「退行期」、そして髪が抜ける準備に入る「休止期」に分かれます。
この正常な循環が薬剤によって乱されるのです。
- 成長期(Anagen)
- 退行期(Catagen)
- 休止期(Telogen)
薬剤性脱毛症の主な症状と進行パターン
薬剤性脱毛症の症状の現れ方は、原因となる薬剤がヘアサイクルのどの段階に影響を与えるかによって、大きく二つのパターンに分類されます。
それぞれの特徴を理解することで、ご自身の状態を把握しやすくなります。
突然始まる「休止期脱毛」
多くの薬剤性脱毛症がこのパターンです。薬剤の影響で、本来は成長期にあるべき髪の毛が prematurely(時期尚早に)休止期に入ってしまいます。薬剤の使用開始から2~4か月後に、シャンプーやブラッシングの際に抜け毛が急に増えることで気づくことが多いです。びまん性(全体的)に髪が薄くなるのが特徴です。
徐々に進行する「成長期脱毛」
抗がん剤による脱毛が代表的な例です。この場合、活発に細胞分裂している成長期の毛母細胞が直接ダメージを受け、髪の毛の形成自体が阻害されます。
その結果、薬剤の投与から数日から数週間という比較的短い期間で、急激かつ広範囲に脱毛が起こります。髪が途中で切れたり、もろくなったりするのも特徴の一つです。
休止期脱毛と成長期脱毛の違い
| 比較項目 | 休止期脱毛 | 成長期脱毛 |
|---|---|---|
| 脱毛開始時期 | 薬剤使用開始後2~4か月 | 薬剤使用開始後1~3週間 |
| 進行の速さ | 比較的緩やか | 急速で重度 |
| 主な原因薬剤 | 抗うつ薬、高血圧治療薬など | 抗がん剤など |
頭皮以外の体毛への影響
薬剤性脱毛症は、頭髪だけに影響が限定されるわけではありません。特に成長期脱毛を引き起こす薬剤の場合、眉毛、まつ毛、鼻毛、脇毛、陰毛といった全身の体毛に影響が及ぶことがあります。
体毛の脱毛は外見の変化だけでなく、汗が目に入る、鼻水が出やすいなど日常生活における機能的な問題につながることもあります。
薬剤性脱毛症の診断方法
薬剤性脱毛症の診断は患者さんからの情報が何よりも重要です。
医師は脱毛の症状と薬剤の使用歴を照らし合わせることで、原因を特定していきます。正確な診断のために、いくつかの検査を行うこともあります。
医師による問診の重要性
診断において最も重要なのが問診です。
脱毛がいつから始まったか、どのようなペースで進行しているか、そして現在使用しているすべての薬剤(処方薬、市販薬、サプリメントを含む)について、できるだけ詳しく医師に伝える必要があります。
診断時に医師に伝えるべき情報
| 情報項目 | 伝えるべき内容の具体例 |
|---|---|
| 脱毛の状況 | いつから、どの部位が、どのくらい抜けているか |
| 使用中の薬剤 | 薬の名前、使用開始時期、1日の量(お薬手帳を持参) |
| 既往歴 | 現在治療中の病気、過去にかかった病気 |
視診とダーモスコピー検査
医師が頭皮や毛髪の状態を直接目で見て確認します。脱毛の範囲やパターン、頭皮に炎症がないかなどを観察します。
さらに、ダーモスコピーという特殊な拡大鏡を用いることで、毛穴の状態や毛髪の太さ、切れ毛の有無などを詳細に調べ、脱毛の種類を判断する手がかりとします。
血液検査でわかること
薬剤性脱毛症を直接診断する血液検査項目はありません。しかし、甲状腺機能の異常や鉄欠乏性貧血など、他の原因による脱毛症の可能性を排除するために血液検査を行うことがあります。
全身状態を把握し、より正確な診断につなげるために重要な検査です。
回復に向けた基本的な考え方と治療方針
薬剤性脱毛症の治療の基本は、原因となっている薬剤への対処です。ただし、その判断は必ず主治医と相談の上で行う必要があります。
自己判断で薬をやめることは治療中の病気を悪化させる危険があるため、絶対に避けてください。
原因薬剤の中止・変更が第一選択
薬剤性脱毛症であると診断された場合、可能であれば原因薬剤の使用を中止するか、脱毛の副作用が少ない別の薬剤に変更することを検討します。
これにより、多くの場合では脱毛の進行が止まり、数か月後には新しい髪が生え始めます。
薬剤の変更は、処方した主治医との連携が不可欠です。
自己判断での断薬は危険
脱毛の悩みは深刻ですが、治療中の病気にとってその薬剤が必要な場合がほとんどです。
自己判断で服用を中止すると原疾患が悪化し、より深刻な事態を招く恐れがあります。必ず、薬剤を処方している主治医に相談し、指示を仰いでください。
治療方針の選択肢
| 方針 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 原因薬剤の中止 | 薬剤の服用を完全にやめる | 主治医の許可が必須 |
| 原因薬剤の変更 | 同等の効果で副作用の少ない薬に変える | 変更可能な薬剤があるか主治医と相談 |
| 治療の継続と発毛治療の併用 | 原因薬剤を継続しつつ、発毛を促す | 抗がん剤治療中など |
脱毛だけではない心の負担と向き合う
薬剤性脱毛症は、単に髪が抜けるという身体的な変化だけにとどまりません。外見が大きく変わることによる精神的な影響は、ご本人が感じている以上に大きいものです。
当院では、その心の負担にも寄り添うことを大切にしています。
外見の変化がもたらす心理的影響
髪は人の印象を大きく左右する部分です。そのため、脱毛によって自信を失ったり、人と会うのが億劫になったりすることがあります。
特に、治療が長引く場合には、社会的な孤立感や抑うつ気分につながることも少なくありません。これは決して特別なことではなく、多くの方が経験する自然な感情です。
治療中の不安やストレスとの付き合い方
「いつになったら髪は生えてくるのだろうか」「元の状態に戻れるのだろうか」といった不安は、大きなストレスとなります。ストレスは血行を悪化させ、髪の健やかな成長を妨げる要因にもなりえます。
ご自身に合った方法で意識的にリラックスする時間を作ることが、心と髪の健康のために重要です。
- 趣味や好きなことに没頭する時間を作る
- 軽いウォーキングなどの運動を取り入れる
- 信頼できる人に話を聞いてもらう
家族や周囲の理解とサポートの重要性
患者さんご本人が悩みを抱え込まないためには、ご家族や親しい友人など身近な人々の理解とサポートが大きな力になります。
外見の変化について過度に言及せず、これまでと変わらない態度で接することが、ご本人の安心につながります。
治療への協力や精神的な支えは、回復への道のりを共に歩む上で欠かせません。
回復までにかかる期間と具体的な経過
原因薬剤を中止または変更した後、髪が回復するまでの期間には個人差があります。一般的な目安を知っておくことで、焦らずに回復を待つことができます。
また、回復過程で見られる変化についても解説します。
薬剤中止後の回復の目安
原因となる薬剤の服用を中止してから、通常1~3か月で抜け毛が減少し始めます。そして、3~6か月ほど経つと、新しい髪の毛(産毛)が生えてくるのを実感できることが多いです。
しっかりとした髪が生えそろうまでには、1年から1年半程度の期間を要することもあります。
回復をサポートする栄養素
| 栄養素 | 髪への働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料になる | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 亜鉛 | ケラチンの合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉 |
| ビタミンB群 | 頭皮の環境を整え、代謝を促す | 豚肉、うなぎ、マグロ |
髪質や色が変わることも
新しく生えてくる髪が、以前とは異なる髪質(くせ毛になるなど)や色になることがあります。これは、薬剤の影響を受けた毛母細胞が回復する過程で起こる一時的な変化であることが多いです。
ヘアサイクルが正常化するにつれて、徐々に元の髪質に戻っていくことが期待できます。
回復をサポートする生活習慣
髪の回復を早めるためには栄養バランスの取れた食事に加え、健やかな生活習慣を心がけることが大切です。
十分な睡眠は髪の成長を促す成長ホルモンの分泌に重要ですし、適度な運動は全身の血行を促進し、頭皮に栄養を届ける助けとなります。
生活習慣の改善ポイント
| 項目 | 具体的な行動 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 睡眠 | 1日6~8時間の質の良い睡眠をとる | 成長ホルモンの分泌促進 |
| 運動 | ウォーキングなどの有酸素運動を習慣にする | 血行促進、ストレス軽減 |
| ストレス管理 | リラックスできる時間を持つ | 自律神経のバランスを整える |
クリニックで受けられる専門的な治療とケア
薬剤性脱毛症の基本的な対処は原因薬剤への対応ですが、より早い回復を望む場合や、なかなか回復しない場合には薄毛治療専門クリニックでの治療が有効な選択肢となります。
専門医の管理のもとで、発毛を促進する治療を行います。
専門医による正確な診断
まずは、脱毛の原因が本当に薬剤によるものなのか、あるいは他の脱毛症(AGAや円形脱毛症など)が関与していないかを専門医が正確に診断します。
この鑑別診断が、適切な治療方針を立てるための第一歩です。
ミノキシジル外用薬などの治療
発毛効果が認められているミノキシジルの外用薬は、薬剤性脱毛症の回復を後押しする治療として用いられることがあります。
ミノキシジルには血管を拡張して頭皮の血流を改善し、毛母細胞を活性化させる働きがあります。医師の診断のもと、適切な濃度のものを処方します。
クリニックでの治療メニュー例
| 治療法 | 概要 | このような方へ |
|---|---|---|
| ミノキシジル外用薬 | 頭皮に直接塗布し、発毛を促す | 回復を早めたい方 |
| LED治療 | 特定の波長の光を頭皮に照射し細胞を活性化 | 痛みなく治療したい方 |
| メソセラピー | 成長因子などを頭皮に直接注入する | より積極的な治療を望む方 |
頭皮環境を整えるケア
新しい髪が健やかに育つためには、その土台である頭皮の環境を良好に保つことが重要です。クリニックでは、専門的な頭皮ケアのアドバイスも行っています。
ご自宅での正しいシャンプー方法や、頭皮の血行を促すマッサージ指導などを通して、発毛しやすい環境作りをサポートします。
- アミノ酸系の低刺激シャンプーを選ぶ
- 指の腹で優しく頭皮をマッサージする
- 頭皮用の保湿ローションで乾燥を防ぐ
頭皮トラブルに戻る
薬剤性脱毛症に関するよくある質問
- 原因の薬をやめれば必ず髪は元に戻りますか?
-
ほとんどの場合、原因薬剤を中止または変更することで髪は回復に向かいます。ただし、回復の程度やスピードには個人差があります。
ごく稀に、毛包が深くダメージを受けて回復が困難なケースもありますが、多くの場合は時間をかけて元に戻ることが期待できます。
ご不安な点は専門医にご相談ください。
- サプリメントや育毛剤は効果がありますか?
-
髪の成長にはタンパク質や亜鉛、ビタミンなどの栄養素が必要なため、栄養補助としてサプリメントを摂取することは有効な場合があります。
ただし、それだけで脱毛が治るわけではありません。市販の育毛剤については成分によっては頭皮に刺激を与える可能性もあるため、使用前に医師に相談することをお勧めします。
- 脱毛中にカラーやパーマをしても大丈夫ですか?
-
脱毛が起きている時期の頭皮は非常にデリケートな状態です。カラー剤やパーマ液に含まれる化学物質が刺激となり、頭皮の状態を悪化させたり、回復を遅らせたりする可能性があります。
回復して髪が生えそろい、頭皮の状態が落ち着くまでは控えるのが賢明です。
- 治療費はどのくらいかかりますか?
-
薬剤性脱毛症の診断自体は、保険診療の範囲内で行われることが一般的です。しかし、発毛を積極的に促すための治療(ミノキシジル外用薬の処方など)は、自由診療となる場合が多いです。
具体的な費用は治療内容によって異なりますので、カウンセリングの際に詳しくご説明します。
以上
参考文献
NAKAYAMA, Hideo; CHEN, Ko-Ron. Herb lotions to regrow hair in patients with intractable alopecia areata. Clinical and Medical Investigations, 2017, 2.3: 1-7.
TOMITA, Takashi, et al. Dose-dependent valproate-induced alopecia in patients with mental disorders. Indian Journal of Pharmacology, 2015, 47.6: 690-692.
YAMANE, Saki, et al. Development of alopecia areata-like reactions in a patient treated with dupilumab. Allergology International, 2022, 71.3: 420-422.
EBATA, Toshiya. Drug-induced itch management. Curr Probl Dermatol, 2016, 50: 155-163.
PEREZ, Sofia M.; NGUYEN, Betty; TOSTI, Antonella. Drug-induced scarring and permanent alopecia. JAAD Reviews, 2024, 1: 42-60.
ITO, Taisuke, et al. Roxithromycin antagonizes catagen induction in murine and human hair follicles: implication of topical roxithromycin as hair restoration reagent. Archives of dermatological research, 2009, 301.5: 347-355.