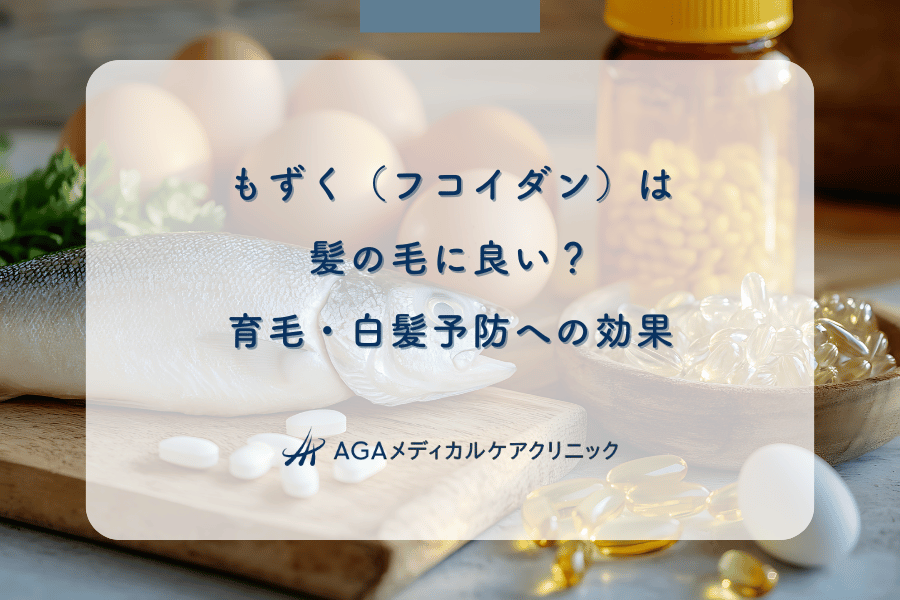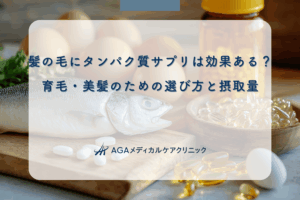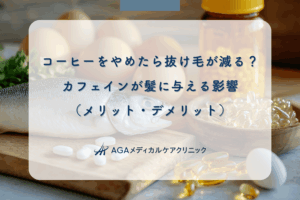「もずくを食べると髪の毛に良い」という話を聞いたことはありませんか?ネバネバとした食感が特徴的なもずくには「フコイダン」をはじめとする多様な栄養素が含まれています。
この記事では、「もずく 髪の毛」というキーワードで検索している方に向けて、もずくが髪の健康、特に育毛や白髪予防に対してどのような影響を与える可能性があるのかを詳しく解説します。
もずくの栄養価から、注目のフコイダンの働き、効果的な摂取方法、そして注意点まで、あなたの疑問に丁寧にお答えします。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
もずくと髪の毛の関係性とは?
昔から海藻類は髪の健康に良いと伝わってきました。その中でも、特にもずくが注目されることがあります。なぜ、もずくと髪の毛が関連付けて語られるのでしょうか。
ここでは、その背景と、髪の健康維持に必要な基本的な考え方を探ります。
もずくが注目される理由
もずくが髪の毛との関連で注目される最大の理由は、その特有の「ネバネバ成分」にあります。このネバネバの正体は「フコイダン」という水溶性食物繊維の一種です。
フコイダンには様々な健康への働きが期待されており、その一環として頭皮環境や髪の成長にも良い影響を与えるのではないか、と考えられています。
また、もずくはフコイダン以外にも、髪の健康をサポートするミネラル分を含んでいる点も理由の一つです。
髪の健康と栄養素
髪の毛は「ケラチン」というタンパク質を主成分としています。
健康な髪の毛を育むためには、タンパク質はもちろんのこと、その合成を助けるビタミンやミネラル、そして頭皮環境を健やかに保つ栄養素が重要です。
食生活が乱れ、これらの栄養素が不足すると、髪の成長が妨げられたり、髪質が悪化したりする可能性があります。
もずくは、そうした髪に必要な栄養素の一部を補給できる食品の一つとして認識されています。
もずくに含まれる主な栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 髪との関連 |
|---|---|---|
| フコイダン | 水溶性食物繊維、ネバネバ成分 | 頭皮環境の保湿、毛母細胞への働きかけの可能性 |
| ミネラル類 | ヨウ素、カルシウム、マグネシウムなど | ヨウ素は代謝を促進、他ミネラルも髪の健康維持を助ける |
| ビタミン類 | ビタミンK、葉酸など(量は多くない) | 他の食品と合わせ、頭皮の健康維持をサポート |
「もずくを食べると髪がフサフサになる」は本当か
「もずくを食べれば髪がフサフサになる」あるいは「白髪がなくなる」といった極端な表現は、残念ながら現実的ではありません。
もずくに含まれる栄養素が髪の健康維持に寄与する可能性はありますが、もずくだけを食べていれば薄毛や白髪の問題がすべて解決するわけではありません。
特にAGA(男性型脱毛症)のように、特定の原因が関与している場合、食事改善だけで顕著な育毛効果を得るのは困難です。
もずくは、あくまで健康的な髪を育むための「サポート役」の一つと捉えるのが適切です。
注目成分フコイダンとは何か
もずくの健康効果を語る上で欠かせない成分が「フコイダン」です。このネバネバした物質は、もずくやコンブ、ワカメといった褐藻類(かっそうるい)に特有のものです。
フコイダンが具体的にどのような成分なのか、その特徴を見ていきましょう。
フコイダンの基本的な特徴
フコイダンは、硫酸基(りゅうさんき)という構造を持つ多糖類(たとうるい)の一種で、水溶性食物繊維に分類されます。化学的には「硫酸化フコース」を主成分とする高分子の物質です。
もともとは、海藻が潮流や紫外線、乾燥などから自らの体を守るために備えているバリア機能や保湿機能の一部を担っていると考えられています。
このネばる力が、人間の健康にも様々な形で役立つのではないかと研究が進められています。
もずくに含まれるフコイダンの量
フコイダンは多くの褐藻類に含まれますが、特にもずく、中でも沖縄もずく(オキナワモズク)はフコイダンの含有量が豊富であることで知られています。
他の海藻類と比較しても、乾燥重量あたりのフコイダン含有率が高い傾向にあります。これが、もずくがフコイダン摂取源として特に注目される理由です。
ただし、製品によって含有量は異なるため、加工品を選ぶ際は成分表示を確認することも一つの方法です。
フコイダンのネバネバパワー
フコイダンの最大の特徴である「ネバネバ(粘性)」は、水分を保持する能力に由来します。この保水力は、私たちの体内でも有益な働きをすると期待されています。
例えば、腸内環境を整える食物繊維としての役割や、粘膜を保護する働きなどです。
髪の毛との関連で言えば、この保湿する力が頭皮の乾燥を防ぎ、健やかな頭皮環境を維持するのに役立つ可能性が指摘されています。
フコイダンに期待される主な働き
| 期待される働き | 概要 |
|---|---|
| 保湿作用 | 高い保水力で潤いを保つ |
| 食物繊維としての働き | 腸内環境の維持をサポートする |
| 毛母細胞への働きかけ | 髪の成長を促す因子への影響(研究段階) |
フコイダンが育毛に与える影響
もずくの核心成分であるフコイダンが、具体的に育毛に対してどのような影響を与える可能性があるのでしょうか。
まだ研究段階の部分も多いですが、現在注目されているフコイダンの働きについて解説します。これらは、もずくが「髪に良い」と言われる根拠の一部となっています。
頭皮環境へのアプローチ
健康な髪は、健康な頭皮から育ちます。フコイダンが持つ高い保湿能力は、乾燥しがちな頭皮に潤いを与えるのに役立つ可能性があります。
頭皮が乾燥すると、フケやかゆみの原因となり、毛穴の環境が悪化してしまいます。
フコイダンが頭皮の水分バランスを保つことを助け、柔軟で健康な状態を維持できれば、それは髪の毛が育ちやすい土壌を作ることにつながります。
毛母細胞への働きかけ
髪の毛は、毛根の奥にある「毛母細胞」が分裂・増殖することによって作られます。この毛母細胞の活動は、「毛乳頭」から送られる様々な成長因子(グロースファクター)によって調整されています。
近年の研究では、フコイダンがこの毛乳頭に働きかけ、髪の成長を促す特定の成長因子(例えばFGF-7など)の産生をサポートする可能性が示唆されています。
毛母細胞が活発に働くことは、太く健康な髪の成長に直結する重要なポイントです。
血流促進の可能性
髪の毛の成長に必要な栄養素や酸素は、血液によって毛乳頭まで運ばれます。したがって、頭皮の血流が良好であることは、育毛において非常に重要です。
フコイダンのネバネバ成分には、血液の流れをスムーズに保つことを助ける働きがあるのではないか、という点も研究されています。
頭皮の隅々まで栄養が行き渡るようになれば、毛母細胞の活動もより活発になることが期待できます。
頭皮環境に影響を与える主な要因
| 要因 | 髪への影響 | フコイダンの関与(可能性) |
|---|---|---|
| 乾燥 | フケ、かゆみ、バリア機能低下 | 保湿作用による乾燥の緩和 |
| 血行不良 | 栄養不足、毛母細胞の活動低下 | 血流サポートによる栄養運搬の補助 |
| 酸化ストレス | 細胞の老化、炎症 | 抗酸化作用による頭皮の保護(後述) |
育毛研究の現状
フコイダンの育毛に関する研究は、まだ進行中の段階です。
細胞レベルや動物実験での良好な結果が報告され始めていますが、これがそのまま人間の薄毛改善にどの程度直結するかについては、さらなる検証が必要です。
フコイダンを含む育毛剤なども開発されていますが、食品としてのもずくを摂取することと、育毛剤として直接塗布することでは、その働き方も異なります。
「もずくを食べれば必ず髪が生える」というわけではなく、あくまで髪の健康をサポートする一つの要素として捉えるべきでしょう。
もずく(フコイダン)は白髪予防にも役立つか
薄毛と並んで多くの男性を悩ませるのが白髪です。もずくやフコイダンは、この白髪の予防に対しても何らかの良い影響をもたらすのでしょうか。
白髪が発生する理由と、フコイダンがそこに関与する可能性について考察します。
白髪が発生する理由
髪の毛の色は、毛根にある「メラノサイト」という色素細胞が作り出す「メラニン色素」によって決まります。
何らかの理由でこのメラノサイトの働きが低下したり、メラノサイト自体が減少したりすると、メラニン色素が作られなくなり、髪の毛は色素のない状態(つまり白髪)のまま生えてきます。
このメラノサイトの機能低下には、加齢、遺伝、ストレス、栄養不足、酸化ストレスなどが関わっていると考えられています。
メラノサイトとチロシナーゼ
メラノサイトがメラニン色素を作る際、「チロシナーゼ」という酵素が重要な役割を果たします。このチロシナーゼの働きが鈍ると、メラニンの生産量も減ってしまいます。
フコイダンに関する研究の中には、フコイダンがメラノサイトの活動や、このチロシナーゼの働きに何らかの影響を与える可能性を探るものもありますが、まだ明確な結論には至っていません。
白髪の主な原因
| 主な原因 | 概要 |
|---|---|
| 加齢 | 年齢と共にメラノサイトの機能が自然に低下する |
| 遺伝的要因 | 白髪になりやすい体質は遺伝的影響を受ける |
| 酸化ストレス | 活性酸素がメラノサイトを傷つけ、機能を低下させる |
| 栄養不足 | メラニン生成に必要な栄養(チロシン、銅など)の不足 |
フコイダンとメラニン生成
フコイダンが直接的にメラニン色素の生成を劇的に増やすという強力な証拠は、現時点では限定的です。
しかし、フコイダンが頭皮環境を健やかに保つことや、血流をサポートする可能性(前述)は、間接的にメラノサイトが働きやすい環境づくりに寄与すると考えることはできます。
栄養がしっかり届く健康な頭皮は、色素細胞の活動にとっても良い条件であることは間違いありません。
抗酸化作用の観点から
白髪の原因として近年特に注目されているのが「酸化ストレス」です。体内で過剰に発生した活性酸素が、メラノサイトを攻撃し、その機能を奪ってしまうという考え方です。
フコイダンを含む多くのポリフェノール類には、この活性酸素の働きを抑える「抗酸化作用」があるとされています。
フコイダンが持つ抗酸化作用によって、頭皮や毛根の細胞が酸化ストレスから守られれば、それはメラノサイトの機能維持、ひいては白髪予防につながる可能性があると言えるでしょう。
もずく以外に含まれる髪に良い栄養素
もずくはフコイダンが豊富ですが、健康な髪の毛を維持するためには、他の栄養素もバランス良く摂取することが重要です。
もずくにも含まれていますが、特に意識して摂取したい、髪の健康に関連する栄養素について解説します。
ミネラル類(ヨウ素、亜鉛など)
髪の毛の健康維持にはミネラル類が深く関わっています。もずくのような海藻類には、これらのミネラルが比較的多く含まれています。
髪の成長に必要な主なミネラル
- ヨウ素
- 亜鉛
- 銅
ヨウ素(ヨード)は、甲状腺ホルモンの主成分であり、全身の代謝活動を活発にします。これには髪の毛の成長を促す働きも含まれます。
ただし、ヨウ素は摂取バランスが重要なミネラルであり、過剰摂取には注意が必要です(詳しくは後述します)。
亜鉛は、髪の主成分であるケラチンというタンパク質を合成する際に必要不可欠なミネラルです。
亜鉛が不足すると、髪の毛の成長が妨げられたり、抜け毛が増えたりする原因にもなります。亜鉛はもずくよりも牡蠣やレバー、赤身肉などに多く含まれます。
銅は、メラニン色素を生成するチロシナーゼという酵素の働きを助けるミネラルです。白髪予防の観点からも重要な栄養素です。
ビタミン群
ビタミン類も、頭皮環境を整え、髪の成長をサポートするために必要です。特にビタミンB群は、タンパク質の代謝や細胞分裂に関わり、育毛に重要です。
ビタミンCやビタミンEは、高い抗酸化作用を持ち、酸化ストレスから頭皮や毛根を守るのに役立ちます。
もずくだけで全てのビタミンを補うことは難しいため、野菜や果物、肉、魚など、多様な食品から摂取することを心がけましょう。
食物繊維の役割
フコイダンも水溶性食物繊維の一種ですが、食物繊維全体として腸内環境を整えることは、全身の健康、ひいては髪の健康にもつながります。腸内環境が良好であれば、栄養素の吸収効率が高まります。
食事から摂取したタンパク質やビタミン、ミネラルが効率よく体内に取り込まれ、頭皮や髪の毛に届けられることは、育毛の基礎となります。
効果的なもずくの摂取方法と注意点
もずくが髪の健康維持に役立つ可能性があるとして、どのように日々の食生活に取り入れるのが良いのでしょうか。効果的な食べ方と、知っておくべき注意点をまとめました。
1日の推奨摂取量
もずくの摂取量に明確な「1日何グラムまで」という決まりはありませんが、一般的に市販されている「もずく酢」の小パック(約50g〜70g)を1日に1〜2パック程度が目安とされます。
大切なのは毎日大量に食べることではなく、適量を継続して食べることです。何事も「過ぎたるは猶及ばざるが如し」です。
もずく酢だけじゃない 食べ方の工夫
もずくと聞くと「もずく酢」を連想する方が多いですが、市販のもずく酢は糖分や塩分が多く含まれている場合があります。
健康のために食べていても、糖分や塩分の摂り過ぎになっては本末転倒です。味付けされていない「生もずく」や「塩蔵もずく(塩抜きが必要)」を購入し、自分で味付けを工夫するのも良い方法です。
例えば、味噌汁やスープの具材にする、納豆やオクラと和える、卵焼きに入れるなど、様々な料理に活用できます。
加熱してもフコイダンが失われることはありませんが、ビタミン類などは熱に弱いものもあるため、調理法は偏らないようにすると良いでしょう。
食べ過ぎによる影響(ヨウ素過剰摂取など)
もずくを食べる上で最も注意したいのが「ヨウ素(ヨード)」の過剰摂取です。
前述の通り、ヨウ素は髪の健康にも関わる重要なミネラルですが、日本人は海藻類や魚介類を食べる習慣から、ヨウ素が不足することは稀で、むしろ過剰摂取に注意が必要です。
ヨウ素を長期間にわたって過剰に摂取し続けると、甲状腺の機能が低下する「甲状腺機能低下症」などを引き起こす可能性があります。
甲状腺ホルモンは髪の成長にも関わるため、機能が低下すれば逆に抜け毛が増えることにもなりかねません。
もずくの摂取目安とヨウ素
| 項目 | 目安・数値 | 備考 |
|---|---|---|
| ヨウ素の耐容上限量(成人) | 1日 3,000μg (3mg) | 日本人の食事摂取基準2020年版より |
| もずく(生)100g中のヨウ素 | 約140μg | 食品成分データベースより(目安) |
| もずく酢1パック(約60g) | 約84μg | 単純計算上の目安 |
表の通り、もずく酢を1〜2パック食べる程度で直ちにヨウ素が過剰になることは考えにくいですが、昆布(特にだし昆布)など他の海藻類を日常的に多く摂取している場合は、合計量に注意が必要です。
もずく製品の選び方
もずく製品を選ぶ際は、できるだけ添加物が少なく、糖分や塩分が控えめなものを選びましょう。
フコイダンの含有量を表示している製品もあるため、成分にこだわりたい場合はそうした表示を参考にするのも良いでしょう。
産地(沖縄産など)も品質の一つの目安になります。
もずく(フコイダン)は補助的な役割と理解する
ここまで、もずくとフコイダンが髪の毛に与える影響について多角的に見てきました。最後に、育毛や白髪予防における、もずくの「立ち位置」を明確にしておくことが重要です。
期待しすぎず、上手に取り入れるための心構えです。
食事だけで薄毛は改善するか
結論から言えば、栄養バランスの取れた食事が髪の健康の土台であることは間違いありませんが、食事「だけ」で進行する薄毛、特にAGA(男性型脱毛症)を改善させることは極めて困難です。
もずくを毎日食べたからといって、AGAの原因である男性ホルモンの影響を打ち消すことはできません。食事はあくまで「守り」や「土台作り」の側面が強いと認識しましょう。
AGA(男性型脱毛症)の場合
AGAは、男性ホルモン(DHT)と遺伝的要因が関与して進行する脱毛症です。
この場合、フコイダンやミネラルを摂取するだけでは進行を止めることは難しく、専門のクリニックなどで医学的根拠に基づいた対策(例えば、内服薬や外用薬の使用)を検討する必要があります。
もし薄毛の進行が早い、生え際や頭頂部が特に気になるという場合は、食事改善と並行して、一度専門家に相談することをお勧めします。
生活習慣全体の見直し
髪の毛の健康は、食事だけでなく、日々の生活習慣全体が反映されます。もずくを食生活に取り入れると同時に、他の生活習慣も見直すことが、より効果的な頭皮ケアにつながります。
見直したい生活習慣
- 十分な睡眠
- 適度な運動
- ストレス管理
良質な睡眠は、髪の成長を促す成長ホルモンの分泌に不可欠です。適度な運動は全身の血流を良くし、頭皮への栄養補給を助けます。
過度なストレスは血管を収縮させ、血行不良やホルモンバランスの乱れを招き、髪に悪影響を与えます。これらを見直さずにもずくだけに頼っても、期待する効果は得にくいでしょう。
専門家への相談
もずくは健康食品であり、医薬品ではありません。髪や頭皮に関する悩みは多岐にわたり、その原因も人それぞれです。
もずくを試してみるのは良いことですが、深刻な悩みや急激な変化を感じる場合は、自己判断で食品に頼り続けるのではなく、皮膚科医や毛髪専門のクリニックなど、専門家の診断を仰ぐことが大切です。
食品別検証に戻る
Q&A
もずくと髪の毛に関して、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- どのくらいの期間食べ続ければ効果が出ますか?
-
食品による体質改善や健康維持は、医薬品とは異なり即効性を期待するものではありません。
髪の毛には「ヘアサイクル(毛周期)」があり、新しい髪が生えて成長するまでには数ヶ月から数年の時間がかかります。
もし、もずくの栄養素が髪の健康に良い影響を与えるとしても、それを実感できるまでには最低でも3ヶ月から6ヶ月、あるいはそれ以上の継続的な摂取と、バランスの取れた生活習慣が必要です。
- もずくが苦手な場合はサプリメントでも良いですか?
-
もずくのネバネバや酸味が苦手な方もいるでしょう。その場合、フコイダンや海藻ミネラルを抽出したサプリメントを利用するのも一つの選択肢です。
サプリメントは手軽に成分を摂取できる利点がありますが、製品によって品質や含有量、吸収率などが異なります。
信頼できるメーカーの製品を選び、過剰摂取にならないよう目安量を守ることが重要です。ただし、基本は食事から多様な栄養素を摂ることが望ましいです。
- もずくを直接髪に塗ることに意味はありますか?
-
もずく(フコイダン)の保湿性や育毛への働きかけに着目し、フコイダンを配合したシャンプーや育毛剤、トリートメントなどが市販されています。
これらは化粧品や医薬部外品として、皮膚への塗布に適した形に成分を調整・配合しています。しかし、食用の「もずく酢」や「生もずく」をそのまま髪や頭皮に塗ることは推奨できません。
糖分や塩分、その他の成分が頭皮に残り、かえって毛穴の詰まりや炎症、かゆみなどを引き起こす可能性があります。
塗布する場合は、専用に開発されたヘアケア製品を使用してください。
- 子供や女性が食べても髪に良い影響がありますか?
-
もずくは自然の食品であり、健康な髪の維持に必要なミネラルや食物繊維を含んでいるため、性別や年齢を問わず、バランスの取れた食事の一環として有益です。
特に女性は、髪の健康維持に重要なミネラル(亜鉛や鉄分など)が不足しがちなため、海藻類でミネラルを補うことは良いことです。
ただし、いずれの場合もヨウ素の過剰摂取には注意し、適量を心がけることが大切です。
Reference
WANG, Zhiyan, et al. Fucoidan treats chemotherapy-induced alopecia and helps cyclophosphamide treat tumors. International Journal of Biological Macromolecules, 2025, 287: 138321.
WANG, Zhiyan, et al. Fucoidan treatment reverses hair loss and inhibits inflammatory responses in a mouse model of androgenetic alopecia. International Journal of Biological Macromolecules, 2025, 146382.
HUANG, Chih-Yu, et al. Hair growth-promoting effects of Sargassum glaucescens oligosaccharides extracts. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 2022, 134: 104307.
HAO, Yuanping, et al. Bio-multifunctional alginate/chitosan/fucoidan sponges with enhanced angiogenesis and hair follicle regeneration for promoting full-thickness wound healing. Materials & Design, 2020, 193: 108863.
SHIN, Kyungha, et al. Effectiveness of the combinational treatment of Laminaria japonica and Cistanche tubulosa extracts in hair growth. Laboratory Animal Research, 2015, 31.1: 24-32.
SEOK, Joon, et al. Efficacy of Cistanche tubulosa and Laminaria japonica extracts (MK-R7) supplement in preventing patterned hair loss and promoting scalp health. Clinical nutrition research, 2015, 4.2: 124.
NARAYANASWAMY, Radhakrishnan, et al. Fucoidan: Versatile cosmetic ingredient. An overview. Journal of Applied Cosmetology, 2013, 31.3-4: 131.
SHIN, Hyoseung, et al. Enhancement of human hair growth using Ecklonia cava polyphenols. Annals of Dermatology, 2016, 28.1: 15.
ARIANI, Lilies Wahyu, et al. Potential of Macroalgae for Anti Alopecia: A Systematic Review. Indonesian Journal of Pharmacy, 2025.