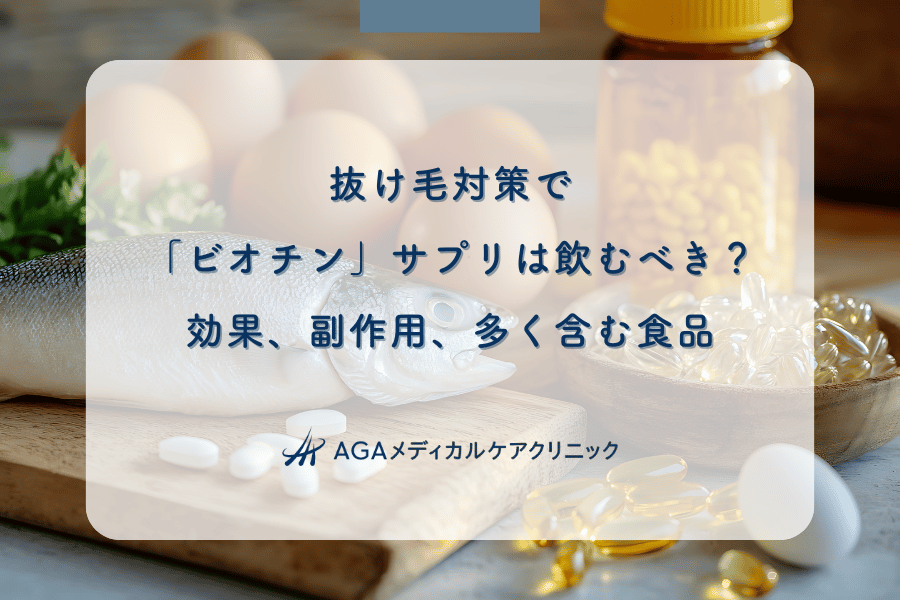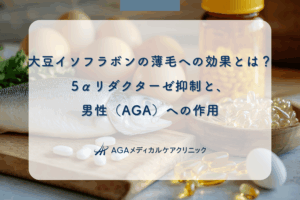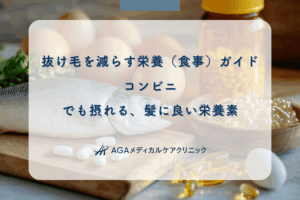抜け毛や薄毛が気になり始め、「ビオチン 抜け毛」と検索してこの記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。
近年、ビオチンは「髪や肌に良いビタミン」として注目を集め、多くのサプリメントも販売されています。
しかし、「本当に抜け毛に効果があるのか?」「サプリを飲むべきか悩む」「副作用はないのか?」といった疑問や不安を感じているかもしれません。
この記事では、男性の抜け毛対策という観点から、ビオチンの基本的な情報から、抜け毛との関係性、効果の科学的根拠、副作用のリスク、食品からの摂取方法、そしてサプリメントの必要性まで、わかりやすく丁寧にご説明します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
ビオチンとは そもそもどんな栄養素?
抜け毛対策を考える上で、まずはビオチンがどのような栄養素なのか、その基本を理解しておくことが重要です。名前は聞いたことがあっても、具体的な働きを知らない方も少なくないでしょう。
ビオチンの正体と、私たちの体で果たす役割について見ていきましょう。
水溶性ビタミンの一種 (ビタミンB7)
ビオチンは、ビタミンB群に分類される水溶性のビタミンです。「ビタミンB7」や、発見当初皮膚炎を改善する働きから「ビタミンH」(ドイツ語のHaut=皮膚に由来)と呼ばれることもあります。
水溶性ビタミンに共通する特徴として、水に溶けやすい性質を持っています。このため、体内に大量に蓄積することが難しく、余剰分は比較的速やかに尿として排出されます。
この性質は、安全性を考える上で一つのポイントとなります。
ビタミンB群の仲間として、他のB群ビタミン(B1, B2, B6, B12, ナイアシン, パントテン酸, 葉酸)と協力し合いながら、体の機能を正常に保つために働いています。
体内で果たす重要な役割
ビオチンは、私たちの体がエネルギーを生み出すための重要な代謝活動に関わっています。
具体的には、糖質(ブドウ糖)、脂質(脂肪酸)、タンパク質(アミノ酸)の3大栄養素の代謝を助ける「補酵素」として機能します。補酵素とは、酵素の働きをサポートする物質のことです。
ビオチンは特に「カルボキシラーゼ」と呼ばれるタイプの酵素にとって必要であり、これらの酵素が正常に働かなければ、エネルギー代謝やアミノ酸の利用がスムーズに行われなくなります。
このエネルギー生成への関与は、全身の細胞が活発に活動するための基盤であり、もちろん頭皮や髪の毛の細胞も例外ではありません。
「皮膚のビタミン」と呼ばれる理由
ビオチンが「皮膚のビタミン」とも呼ばれるのは、皮膚や粘膜の健康維持に深く関わっているためです。
ビオチンは、皮膚の炎症を抑える物質の生成に関与したり、皮膚の細胞が正常に新陳代謝を行うのを助けたりします。また、コラーゲンの生成にも間接的に関わっているとされています。
実際に、ビオチンが極端に不足すると、皮膚炎や粘膜の異常といった症状が現れることが知られています。
この「皮膚を健康に保つ」働きが、頭皮環境を健やかに維持すること、ひいては健康な髪の育成にもつながるのではないか、と考えられているのです。
ビオチンと抜け毛の関係 本当に効果は期待できるのか
ビオチンが皮膚や粘膜の健康に関わることはわかりました。では、本題である「抜け毛」に対しては、どの程度期待できるのでしょうか。
「ビオチンが抜け毛に効く」という話を耳にしたことがあるかもしれませんが、その根拠や実際のところを冷静に見ていく必要があります。
ビオチンが髪の健康に関わる仕組み
ビオチンが直接的に発毛を促すわけではありませんが、髪の健康を「サポート」する形で関わっています。髪の毛の約90%は「ケラチン」というタンパク質でできています。
ビオチンは、このケラチンの合成に必要なアミノ酸の代謝を助ける補酵素として働きます。
つまり、髪の主成分であるケラチンをスムーズに作るための、いわば「縁の下の力持ち」のような役割を担っているのです。
また、前述の通り、頭皮の健康を維持する働きも重要です。健やかな頭皮環境は、健康な髪が育つための土壌となります。
頭皮が荒れていたり、炎症を起こしていたりすると、髪の成長にも悪影響が出かねません。ビオチンは、この土壌を整える役割の一部を担っていると言えます。
「抜け毛に効く」と言われる根拠
なぜ「ビオチンが抜け毛に効く」と言われるようになったのでしょうか。その最大の理由は、「ビオチン欠乏症」の症状の一つに「脱毛」があるためです。
ビオチンが極度に不足すると、皮膚炎などと共に、頭髪や眉毛、まつ毛などの脱毛が起こることが報告されています。
この事実から、「ビオチンが不足すると毛が抜ける」ならば、「ビオチンを補えば抜け毛が改善・予防できるのではないか」という考えが広まりました。
実際に、ビオチン欠乏が原因で脱毛していた患者にビオチンを投与した結果、脱毛が改善したという報告は存在します。
また、一部の小規模な研究で、ビオチンを含むサプリメントを摂取したグループで、髪の質や量に改善が見られたとする報告も、この説を後押ししています。
科学的根拠は十分か 抜け毛治療への有効性
では、ビオチン欠乏症ではない、健康な人が抜け毛対策としてビオチンを摂取することに、どれほどの科学的根拠があるのでしょうか。
結論から言うと、現時点では「健康な人の抜け毛予防や発毛に対して、ビオチン摂取が直接的な効果を持つ」という強力な科学的根拠は確立されていません。
特に、男性の抜け毛の大きな原因であるAGA(男性型脱毛症)は、男性ホルモンの影響によって引き起こされるものです。ビオチンは、このAGAの根本的な原因に直接働きかけるものではありません。
したがって、ビオチンサプリを飲むだけでAGAの進行が止まったり、著しく発毛したりすることを期待するのは難しいと言えます。
ビオチンはあくまで「髪の健康維持に必要な栄養素の一つ」であり、AGA治療薬(フィナステリドやミノキシジルなど)とは全く異なる位置づけであることを理解しておく必要があります。
ビオチン不足が引き起こす症状 抜け毛以外のサイン
ビオチンが不足すると脱毛が起こる可能性がある、と述べました。では、どのような人がビオチン不足に陥りやすいのでしょうか。
また、抜け毛以外にどのようなサインが現れるのかを知っておくことは、ご自身の状態を把握する上で役立ちます。
欠乏症は稀なケース
まず知っておいていただきたいのは、日本において通常の食生活を送っている健康な人がビオチン欠乏症になることは、非常に稀であるということです。
ビオチンは多くの食品に含まれていますし、さらに私たちの腸内にいる「腸内細菌」によっても合成されるため、必要量を確保しやすい栄養素なのです。
そのため、極端に心配する必要はありませんが、特定の条件下では不足するリスクが高まることも事実です。
不足しやすい人の特徴
以下のような特定の要因があると、ビオチンが不足しやすくなる可能性があります。
- 生卵白の長期・大量摂取
- 抗生物質の長期服用
- 特定の遺伝性疾患
- 重度のアルコール依存症
- 透析患者
特に有名なのが「生卵白」です。生卵白に含まれる「アビジン」というタンパク質は、ビオチンと強力に結合し、体内への吸収を妨げます。
毎日10個以上の生卵白を長期間摂取し続けると、ビオチン欠乏症になる可能性があるとされています。
ただし、アビジンは加熱によって働きを失うため、加熱した卵(ゆで卵、目玉焼き、卵焼きなど)であれば問題ありません。
また、抗生物質を長期間服用すると、ビオチンを合成する腸内細菌が減少し、不足につながる場合があります。
抜け毛以外の主な欠乏症状
ビオチンが不足すると、エネルギー代謝や皮膚・粘膜の維持に支障をきたし始めます。抜け毛(脱毛)もその一つですが、それ以外にも以下のような多様な症状が現れる可能性があります。
これらの症状が複数当てはまる場合は、食生活の偏りなどを疑う必要があるかもしれません。
欠乏による皮膚・毛髪への影響
ビオチンの別名が「皮膚のビタミン」であることからもわかるように、欠乏症状はまず皮膚や毛髪に現れやすいです。
具体的には、顔(特に目、鼻、口の周り)や四肢に、うろこ状(鱗屑性)あるいは脂漏性の皮膚炎が起こることがあります。皮膚が赤くなったり、カサカサしたりするイメージです。
毛髪に関しては、脱毛だけでなく、髪が細くなったり、色が抜けたり(色素脱失)、脆くなったりするといった変化が見られることもあります。
その他の全身症状
皮膚や毛髪以外にも、全身に様々な影響が出ることがあります。例えば、舌が赤く腫れたり痛んだりする「舌炎」、唇の両端が切れる「口角炎」、目の充血や炎症を起こす「結膜炎」といった粘膜系の症状です。
さらに、全身の倦怠感、食欲不振、吐き気、筋肉痛といった消化器系や全身の症状、ひどくなると、うつ症状や知覚過敏などの神経症状が現れることも報告されています。
ビオチンを多く含む食品 日常の食事で摂取する方法
ビオチン欠乏症は稀であり、多くの食品から摂取可能であることがわかりました。では、具体的にどのような食品にビオチンは多く含まれているのでしょうか。
サプリメントに頼る前に、まずは日々の食事内容を見直すことが基本です。
ビオチンが豊富な食材
ビオチンは、動物性食品・植物性食品を問わず、幅広い食材に含まれています。
特に含有量が多いとされるのは、レバー類、卵黄、一部のナッツ類や種実類、大豆製品、魚介類、キノコ類などです。
これらの食材をバランス良く食事に取り入れることで、ビオチンを効率的に摂取できます。
食品からの摂取目安量
厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、18歳以上の成人におけるビオチンの「目安量」は、男女ともに1日あたり50μg(マイクログラム)と設定されています。
目安量とは、特定の集団において、ほとんどの人が不足状態とならない摂取量のことです。
多くの日本人は、通常の平均的な食事でこの目安量を満たしていると考えられています。特定の食品に偏らず、多様な食材を食べることが大切です。
ビオチンを多く含む主な食品
日常的に摂取しやすい食品の中で、ビオチン含有量が比較的多いものを紹介します。含有量は食品の個体差や調理法によって変動するため、あくまで目安としてご覧ください。
| 食品名 | 一般的な目安量 | ビオチン含有量 (μg) |
|---|---|---|
| 鶏レバー | 100g | 約 200~230 |
| 豚レバー | 100g | 約 130 |
| 卵黄 (加熱) | 1個 (約20g) | 約 12~15 |
| アーモンド (煎り) | 30g (約25粒) | 約 18~20 |
| 納豆 | 1パック (50g) | 約 9~10 |
| 煎りピーナッツ | 30g | 約 10~11 |
| マイワシ (生) | 1尾 (100g) | 約 10 |
調理時のポイントと注意点
ビオチンは比較的熱に安定しているビタミンですが、水溶性であるため、調理法によっては損失することもあります。茹でたり煮たりすると、煮汁にビオチンが溶け出す可能性があります。
そのため、煮汁ごと食べられるスープや煮物にするか、蒸し料理や炒め物といった、水への流出が少ない調理法を選ぶと効率的です。
また、生卵白に含まれるアビジンはビオチンの吸収を妨げるため、卵は加熱して食べることを強く推奨します。卵黄にはビオチンが豊富に含まれているため、加熱して卵全体を食べるのが最も賢明な方法です。
ビオチンサプリの選び方と注意点 飲む前に知っておきたいこと
食事から摂取するのが基本ですが、ライフスタイルによってはサプリメントの活用を考える方もいるでしょう。
特に「抜け毛対策」としてビオチンに関心を持った場合、サプリメントが選択肢に上がるのは自然なことです。しかし、やみくもに摂取するのではなく、選び方と注意点を理解しておく必要があります。
サプリ摂取が推奨されるケース
前述の通り、通常の食生活でビオチンが不足することは稀です。
しかし、ビオチンが不足しやすい特徴(生卵白の長期・大量摂取、抗生物質の長期服用など)に当てはまる場合や、極端な偏食、あるいは吸収不良を伴う疾患などで、食事からの摂取が著しく困難な場合には、サプリメントによる補充が有効な場合があります。
また、医師によってビオチン欠乏、あるいはその疑いがあると診断された場合は、治療の一環として高用量のビオチンが処方されることもあります。
自己判断での「抜け毛対策」目的での摂取は、その必要性を慎重に考えるべきです。
サプリメントの種類と特徴
ビオチンサプリメントは、いくつかのタイプに分けられます。それぞれの特徴を知り、自分の目的に合っているかを見極めることが重要です。
サプリメントのタイプ別比較
市販されているビオチン関連サプリは、主に以下の3つのタイプに分類できます。
| サプリメント種類 | 特徴 | どのような人向けか |
|---|---|---|
| ビオチン単体サプリ | ビオチンのみを高濃度で含む。海外製品に多い (例: 5,000μg, 10,000μg)。 | ビオチン不足が明らか、または高用量を必要とする特定の目的がある人。 |
| ビタミンB群 (Bコンプレックス) | ビオチンを含む8種類のビタミンB群がバランス良く配合されている。 | ビタミンB群全体の不足を補いたい人。栄養バランスを整えたい人。 |
| マルチビタミン・ミネラル | ビオチンを含む様々なビタミンやミネラルが総合的に配合されている。 | 基礎的な栄養素を幅広く補給したい人。食生活が不規則な人。 |
含有量 (μg) のチェックポイント
サプリメントを選ぶ際に最も注意したいのが「含有量」です。前述の通り、日本の食事摂取基準の目安量は50μg/日です。
国内のビタミンB群やマルチビタミンに含まれるビオチンは、この目安量前後(例: 30μg〜100μg程度)に設定されていることが多いです。
一方で、海外製のビオチン単体サプリメントでは、5,000μgや10,000μg (10mg) といった、目安量をはるかに超える高含有量の製品が主流となっています。
抜け毛対策をうたう情報の中には、こうした高用量摂取を推奨するものも見受けられますが、その必要性や安全性については後述の通り、慎重に考える必要があります。
まずは製品ラベルをよく確認し、どれだけの量が含まれているかを把握しましょう。
国内製品と海外製品の違い
含有量以外にも、国内製品と海外製品では違いがあります。
一般的に、国内製品は日本の法律や基準(栄養機能食品の基準など)に基づいて製造・販売されており、含有量も比較的穏やかです。品質管理が徹底されている製品が多いという安心感もあります。
対して海外製品(特に個人輸入などで入手するもの)は、高含有量であることが多い反面、その国の基準で製造されているため、品質基準や添加物が日本のものと異なる場合があります。
どちらが良い悪いというわけではありませんが、信頼できるメーカーや販売ルートから購入することが、安全性の確保につながります。
ビオチンの副作用と安全性 過剰摂取のリスクは?
サプリメントを利用する上で、効果と同等以上に気になるのが「安全性」と「副作用」です。
特に海外製の高含有量サプリを検討する場合は、過剰摂取のリスクについて正しく理解しておくことが絶対に必要です。
水溶性ビタミンの安全性
ビオチンは水溶性ビタミンであるため、過剰に摂取したとしても、体内に蓄積されにくく、多くは尿として排出されます。
この性質から、ビオチンは一般的に安全性の高い栄養素と考えられています。
脂溶性ビタミン(A, D, E, K)のように、過剰摂取による明確な健康被害(中毒症状)の報告は、通常の食品やサプリメントの摂取範囲では極めて少ないです。
日本の食事摂取基準でも、ビオチンの「耐容上限量」(これ以上摂取すると健康被害のリスクが高まる量)は、十分なデータがないため設定されていません。
過剰摂取による潜在的な問題
「耐容上限量が設定されていない=いくら摂っても安全」というわけではありません。
1日に数千〜1万μg(数mg)といった高用量を、長期間にわたって摂取し続けた場合の安全性については、まだ十分に解明されていない部分もあります。
健康な人が必要量以上にビオチンを摂取しても、その分がすべて髪の健康に使われるわけではなく、大半は排出されてしまいます。
現時点で抜け毛に対する明確な効果が確立されていない以上、不必要に高用量のサプリメントを摂取し続けることは、コストの面からも、未知のリスクを避けるという意味でも、賢明とは言えないかもしれません。
血液検査への影響 (重要)
ビオチンの過剰摂取に関して、現在最も重要視されている注意点があります。
それは、ビオチンを高用量(特に1日5,000μgを超えるような量)摂取していると、一部の血液検査の結果に「影響を与える」可能性があることです。
これは、検査の測定法(ビオチンを利用した技術)にビオチンが干渉してしまうために起こります。
例えば、甲状腺機能の検査(TSH, FT3, FT4など)や、心筋梗塞のマーカー(トロポニン)などの検査結果が、実際とは異なる数値(異常に高い、または低い)として出てしまう可能性があります。
これにより、誤った診断や不必要な治療につながるリスクが指摘されています。
健康診断や病院での検査を受ける際は、高用量のビオチンサプリを摂取していることを必ず医師に申告するようにしてください。
場合によっては、検査の数日前から摂取を中止するよう指示されることもあります。
過剰摂取に関する注意点まとめ
ビオチンの安全性と過剰摂取に関するポイントを整理します。
| 項目 | 内容 | 対策・留意点 |
|---|---|---|
| 基本的な安全性 | 水溶性で排出されやすく、毒性は低いとされる。耐容上限量は設定なし。 | 通常の食事や目安量程度のサプリ摂取では問題視されない。 |
| 高用量摂取のリスク | 長期的な安全性は不明な点もある。抜け毛への明確な効果も確立されていない。 | 医師の指示がない限り、自己判断での極端な高用量摂取は避けるのが賢明。 |
| 血液検査への干渉 | 高用量摂取(特に5,000μg/日以上)は、特定の血液検査の結果を狂わせる可能性あり。 | 検査時は必ず医師にサプリ摂取の事実を申告する。 |
抜け毛対策におけるビオチンの立ち位置 他の対策との併用
ここまでビオチンの詳細を見てきましたが、抜け毛に悩む男性にとって、ビオチンをどのように位置づければよいのでしょうか。
ビオチン単体で解決を期待するのではなく、総合的な対策の中の一部として考えることが重要です。
ビオチンは「守り」の栄養素
抜け毛対策には「攻め」と「守り」があるとすれば、ビオチンは明らかに「守り」の栄養素です。
AGA治療薬であるフィナステリド(抜け毛の原因ホルモンの生成を抑える)やミノキシジル(毛根に働きかけ発毛を促す)が「攻め」の対策だとすると、ビオチンは、髪の材料となるケラチンの合成を助け、頭皮環境を健やかに保つという「守り」、あるいは「土台作り」の役割を担います。
ビオチンが不足すれば髪の健康が損なわれる可能性はありますが、ビオチンを過剰に摂ったからといって、AGAの進行を止めたり、積極的に発毛を促したりする「攻め」の効果は期待できません。
この違いを明確に認識することが、適切な抜け毛対策の第一歩です。
他の栄養素とのバランス
髪の健康を維持するためには、ビオチンだけでは不十分です。髪はケラチンというタンパク質でできていますから、その主原料であるタンパク質(アミノ酸)の摂取が何よりもまず重要です。
さらに、タンパク質の合成や細胞分裂をサポートする「亜鉛」も、髪の成長に深く関わるミネラルとして知られています。
また、ビオチン以外のビタミンB群(特にB2やB6)も皮脂のバランスを整えたり、タンパク質の代謝を助けたりする働きがあります。血行を促進し、頭皮に栄養を届けるためにはビタミンEなども役立ちます。
ビオチンもこれらチームの一員であり、特定の栄養素だけを大量に摂るのではなく、バランスの取れた食事を心がけることが、髪の「守り」を固める上で最も効果的です。
髪の健康に関わる主な栄養素
ビオチン以外にも、髪の健康維持に貢献する代表的な栄養素とその働きを紹介します。
| 栄養素 | 主な役割 | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 (アミノ酸) | 髪の主成分 (ケラチン) の材料。 | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |
| 亜鉛 | ケラチンの合成を助ける。細胞分裂をサポート。 | 牡蠣、レバー、赤身肉、チーズ、ナッツ類 |
| ビタミンB群 (B2, B6等) | タンパク質の代謝を助ける。皮脂の分泌を調整。 | 豚肉、レバー、マグロ、カツオ、バナナ |
| ビタミンE | 抗酸化作用。血行を促進し、頭皮への栄養供給を助ける。 | アーモンド、植物油、アボカド、うなぎ |
総合的な抜け毛対策の重要性
男性の抜け毛、特にAGAは進行性です。栄養バランスに気をつけることは非常に重要ですが、それだけで進行を食い止めるのは困難な場合が多いです。
もしAGAが疑われるのであれば、まずは専門のクリニックで診断を受けることが最優先です。その上で、医師の指導のもとで適切な治療(内服薬や外用薬など)を開始することが「攻め」の対策となります。
ビオチンを含む栄養摂取や生活習慣の改善は、これらの治療の効果を最大限に引き出すための「土台固め」として機能します。
栄養、睡眠、運動、ストレス管理、適切なヘアケア、そして専門的な治療、これらを多角的に組み合わせることが、抜け毛対策において最も重要な考え方です。
抜け毛対策の多角的アプローチ
抜け毛対策を成功させるためには、一つの方法に頼るのではなく、様々な角度からのアプローチが必要です。ビオチン(栄養)はその一部に過ぎません。
| アプローチ | 具体的な取り組み例 | ビオチンの関連性 |
|---|---|---|
| 栄養 (食事) | タンパク質中心のバランス良い食事。 | 髪の健康維持に必要な栄養素の一つとして摂取。 |
| 生活習慣 | 十分な睡眠、適度な運動、ストレス発散。 | 全身の健康状態を良好に保ち、栄養吸収や血行をサポート。 |
| ヘアケア | 頭皮を清潔に保つ正しい洗髪。ゴシゴシ洗いすぎない。 | ビオチンがサポートする「健やかな頭皮環境」の維持。 |
| 専門的治療 (AGAの場合) | 専門医の診断。フィナステリド内服、ミノキシジル外用など。 | 直接的な関連はなし。治療の土台としての健康維持。 |
サプリメントに戻る
よくある質問
最後に、ビオチンと抜け毛に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。
- ビオチンサプリを飲めば髪は増えますか?
-
健康な人がビオチンサプリを飲むだけで髪が「増える」という直接的な発毛効果は、現在のところ科学的に確立されていません。
ビオチンは髪の健康維持に必要な栄養素ですが、AGA(男性型脱毛症)などの治療薬とは異なります。
ただし、ビオチン欠乏状態にある場合は、補充することで脱毛が改善する可能性はあります。
- ビオチンサプリはどれくらいの期間飲めば効果が出ますか?
-
もしビオチン欠乏による症状改善が目的の場合、効果を実感するまでの期間は個人差がありますが、数週間から数ヶ月かかる場合もあります。
抜け毛対策として摂取する場合、前述の通り明確な発毛効果は期待しにくいため、「いつまで飲めば」という明確な目安はありません。
肌や髪のコンディション維持を目的として、継続的に摂取する人もいます。
- ビオチンは育毛剤と一緒に使っても大丈夫ですか?
-
はい、ビオチンサプリメント(内側からの栄養サポート)と市販の育毛剤(外側からの頭皮環境整備や毛根への働きかけ)を併用すること自体に、特に問題はありません。
両者は役割が異なります。ただし、AGA治療薬(内服薬)などをすでに服用している場合は、サプリメントの追加について、念のため医師にご相談ください。
- 生卵を食べると本当にビオチン不足になりますか?
-
生卵白に含まれる「アビジン」というタンパク質が、ビオチンの吸収を妨げます。毎日10個以上の生卵白を長期間食べ続けると、ビオチン欠乏症になる可能性があります。
しかし、通常の食事で1日1〜2個程度の生卵(例えば、卵かけご飯やすき焼きなど)を食べる程度であれば、過度に心配する必要はありません。
卵黄にはビオチンが豊富に含まれていますし、アビジンは加熱すれば失活するため、卵は加熱して食べることをおすすめします。
- ビオチンサプリを飲むのをやめると、また抜け毛が増えますか?
-
もし万が一、ビオチン欠乏が原因で抜け毛が起きていた場合、サプリをやめて再び欠乏状態になれば、症状が再発する可能性はあります。
しかし、AGA(男性型脱毛症)など他の原因による抜け毛の場合、ビオチンサプリの摂取を中止したことが、抜け毛の増減に直接大きく影響する可能性は低いと考えられます。
ご自身の抜け毛の根本原因を把握することが何よりも重要です。
Reference
NARDA, M., et al. Efficacy and safety of a food supplement containing L-cystine, Serenoa repens extract and biotin for hair loss in healthy males and females. A prospective, randomized, double-blinded, controlled clinical trial. J Cosmo Trichol, 2017, 3.127: 2.
PATEL, Deepa P.; SWINK, Shane M.; CASTELO-SOCCIO, Leslie. A review of the use of biotin for hair loss. Skin appendage disorders, 2017, 3.3: 166-169.
TRÜEB, Ralph M. Serum biotin levels in women complaining of hair loss. International journal of trichology, 2016, 8.2: 73-77.
DRAKE, Lara, et al. Evaluation of the safety and effectiveness of nutritional supplements for treating hair loss: a systematic review. JAMA dermatology, 2023, 159.1: 79-86.
YELICH, Allyson, et al. Biotin for Hair Loss: Teasing Out the Evidence. The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, 2024, 17.8: 56.
FAMENINI, Shannon; GOH, Carolyn. Evidence for supplemental treatments in androgenetic alopecia. J Drugs Dermatol, 2014, 13.7: 809-812.
SAMADI, Aniseh, et al. Efficacy of intramuscular injections of biotin and dexpanthenol in the treatment of diffuse hair loss: a randomized, double‐blind controlled study comparing two brands. Dermatologic therapy, 2022, 35.9: e15695.
LIPNER, Shari R. Rethinking biotin therapy for hair, nail, and skin disorders. Journal of the American Academy of Dermatology, 2018, 78.6: 1236-1238.
GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.
ŞEN, Ozan; TÜRKÇAPAR, Ahmet Gökhan. Hair loss after sleeve gastrectomy and effect of biotin supplements. Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques, 2021, 31.3: 296-300.