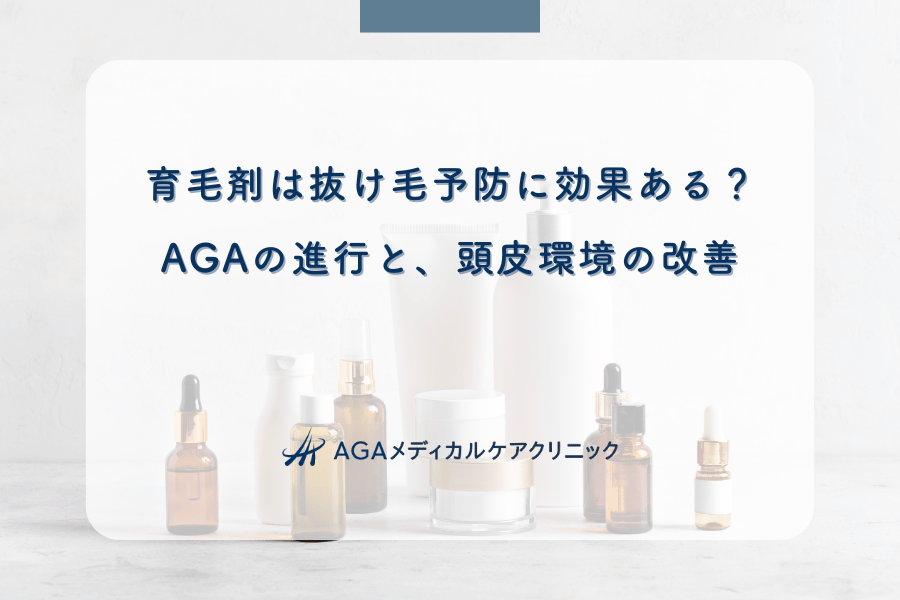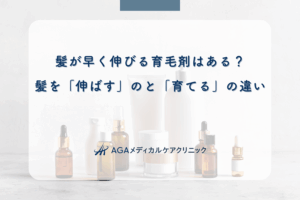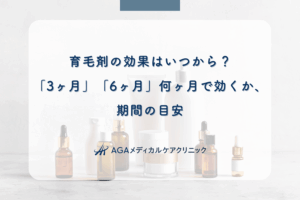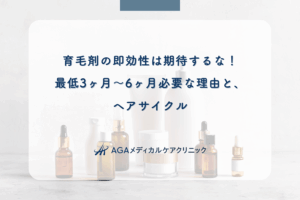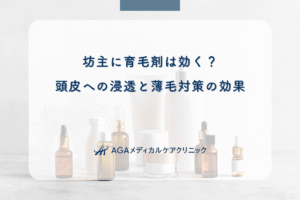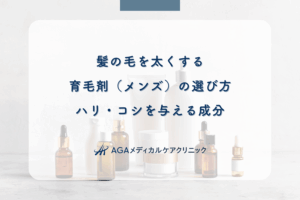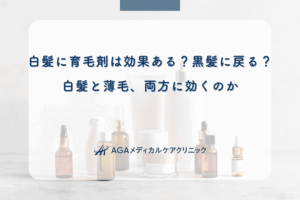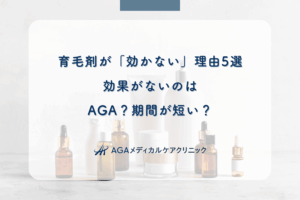「最近、枕元の抜け毛が増えた気がする」「シャンプーの時の排水溝が気になる」…。ふとした瞬間に感じる抜け毛の不安は、男性にとって深刻な悩みです。
その対策として真っ先に「育毛剤」を思い浮かべる方は多いでしょう。
しかし、「育毛剤は本当に抜け毛予防に効果があるのか?」「自分の抜け毛の原因がAGAだったらどうしよう」と、疑問や不安を抱えているのも事実です。
この記事では、育毛剤が抜け毛予防に対してどのような役割を果たすのか、AGAとの関係性、そして育毛剤の効果を高めるために重要な頭皮環境の改善について、詳しく解説します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
まず知っておきたい 育毛剤の本当の役割
抜け毛対策を考えたとき、「育毛剤」と「発毛剤」という言葉を耳にします。これらは似ているようで、その目的と役割は根本的に異なります。
抜け毛予防のために育毛剤を正しく活用するには、まず育毛剤が何を目指すものなのかを正確に理解することが大切です。
育毛剤と発毛剤の根本的な違い
育毛剤と発毛剤は、法律(医薬品医療機器等法)上の分類が異なり、それによって期待できる効果も変わります。育毛剤の多くは「医薬部外品」に分類されます。
これは、厚生労働省が許可した効果・効能に有効な成分が一定の濃度で配合されているものを指します。
主な目的は「今ある髪の毛を健康に保つこと」や「抜け毛を防ぐこと」、そして「頭皮環境を整えること」です。
一方、発毛剤は「医薬品」に分類されます。これは病気の「治療」を目的としており、具体的には「新しい髪の毛を生やす(発毛)」効果が認められた成分(ミノキシジルなど)を含みます。
発毛剤は、医師の処方が必要なものや、薬剤師の説明が必要な第一類医薬品として販売されています。
つまり、育毛剤は「守り」や「予防」、発毛剤は「攻め」や「治療」と考えると分かりやすいでしょう。
自分の目的が、抜け毛の「予防」なのか、すでに薄くなった部分の「発毛」なのかを明確にすることが第一歩です。
育毛剤と発毛剤の比較
| 項目 | 育毛剤(医薬部外品) | 発毛剤(医薬品) |
|---|---|---|
| 主な目的 | 抜け毛予防、育毛、頭皮環境の改善 | 発毛、脱毛の進行停止(治療) |
| 主な成分例 | センブリエキス、グリチルリチン酸2Kなど | ミノキシジル、フィナステリド(内服)など |
| 入手方法 | ドラッグストア、通販などで自由に購入可能 | 医師の処方、または薬剤師の対面販売 |
育毛剤が目指す「抜け毛予防」とは
育毛剤が目指す「抜け毛予防」とは、主に頭皮環境を良好に保つことによって、健康な髪が育つ土台を維持し、ヘアサイクル(毛周期)の乱れを防ぐことを指します。
髪の毛は「成長期」「退行期」「休止期」というサイクルを繰り返しています。
抜け毛が増える原因の一つに、この「成長期」が短くなり、髪が太く長く育つ前に抜けてしまう「ヘアサイクルの乱れ」があります。
育毛剤は、頭皮の血行を促進して毛根に栄養を届けたり、頭皮の炎症や乾燥を防いだりすることで、このヘアサイクルが正常に働くようサポートします。
結果として、今生えている髪がすぐに抜けてしまうのを防ぎ、ハリやコシのある健康な状態を維持することを目指します。これが育毛剤による「抜け毛予防」の基本的な考え方です。
頭皮環境を整えることがなぜ重要か
健康な髪は、健康な頭皮という「土壌」から育ちます。畑の土壌が悪ければ作物が育たないのと同じで、頭皮環境が悪化すれば、髪の毛も正常に成長できません。
例えば、頭皮が乾燥すると、外部からの刺激に弱くなり、かゆみやフケが発生しやすくなります。逆に皮脂が過剰に分泌されると、毛穴が詰まり、炎症(脂漏性皮膚炎など)を引き起こす原因となります。
また、頭皮の血行が悪くなると、髪の成長に必要な栄養素が毛根まで十分に行き渡りません。
これらの頭皮トラブルは、すべて抜け毛のリスクを高める要因です。
育毛剤は、保湿成分、抗炎症成分、血行促進成分などを含んでおり、これらのトラブルを総合的にケアし、頭皮環境を「髪が育ちやすい状態」に整える上で重要な役割を果たします。
なぜ抜け毛は増えるのか?主な原因を探る
抜け毛予防を考える上で、育毛剤を使うかどうか以前に、「なぜ自分の抜け毛が増えているのか」という原因を理解することが重要です。原因が分からなければ、適切な対策も立てられません。
抜け毛の主な原因は、大きく分けて「AGA(男性型脱毛症)」「頭皮環境の悪化」「生活習慣の乱れ」の3つが考えられます。
AGA(男性型脱毛症)の進行
成人男性の抜け毛・薄毛の悩みで最も多い原因がAGA(Androgenetic Alopecia)です。これは思春期以降に始まり、徐々に進行する脱毛症です。
AGAの主な特徴は、生え際(M字部分)が後退したり、頭頂部(O字部分)が薄くなったりすることです。
AGAは、男性ホルモン(テストステロン)が特定の酵素(5αリダクターゼ)と結びつくことで生成される「DHT(ジヒドロテストステロン)」が深く関係しています。
このDHTが毛根の受容体と結合すると、髪の成長期を短くするよう指令を出してしまいます。その結果、髪が太く成長する前に抜け落ち、徐々に薄毛が目立つようになります。
AGAは遺伝的な要因も影響すると言われており、進行性のため、放置すると薄毛は進んでいきます。
頭皮環境の悪化(乾燥・皮脂過剰・血行不良)
AGAではなくても、頭皮環境の悪化によって抜け毛が増えるケースも非常に多いです。前述の通り、頭皮は髪の土壌です。
乾燥した頭皮はバリア機能が低下し、少しの刺激でかゆみや炎症が起こり、フケ(乾性フケ)の原因にもなります。かゆくて頭皮を掻きむしれば、物理的なダメージで髪が抜けることもあります。
逆に、皮脂が過剰な頭皮(脂性肌)では、皮脂が酸化して頭皮に刺激を与えたり、毛穴を詰まらせたりします。これが炎症やニオイの原因(脂漏性皮膚炎)となり、やはり抜け毛につながります。
また、肩こりや首こり、運動不足などで頭部の血行が悪くなると、毛根にある毛母細胞の活動が低下し、髪の成長が妨げられます。これも抜け毛や髪のやせ細りを引き起こします。
抜け毛の主な原因と特徴
| 原因 | 主な特徴 | 育毛剤の役割 |
|---|---|---|
| AGA(男性型脱毛症) | 生え際や頭頂部から薄くなる。進行性。 | 頭皮環境を整えるサポート。進行抑制は医薬品の領域。 |
| 頭皮環境の悪化 | フケ、かゆみ、赤み、ベタつき。全体的に抜けることも。 | 保湿、抗炎症、皮脂コントロール。主要な役割。 |
| 生活習慣の乱れ | 髪にハリ・コシがなくなる。ストレス性の円形脱毛症も。 | 血行促進などでサポート。根本改善は生活の見直しが必要。 |
生活習慣の乱れが髪に与える影響
日々の生活習慣も、髪の健康に直結しています。髪の毛は「ケラチン」というタンパク質からできています。
偏った食生活でタンパク質や、その合成を助けるビタミン、ミネラル(特に亜鉛)が不足すると、健康な髪は作られません。
また、髪の成長は睡眠中に活発になります。特に成長ホルモンが分泌される夜間の睡眠は重要です。睡眠不足が続くと、髪の成長が妨げられるだけでなく、自律神経が乱れて頭皮の血行不良も招きます。
喫煙は血管を収縮させ、頭皮への血流を悪化させます。過度な飲酒も、アルコールの分解に体内のビタミンやアミノ酸を消費するため、髪の栄養不足につながる可能性があります。
ストレスと抜け毛の関係性
精神的なストレスも抜け毛の大きな要因です。強いストレスを感じると、交感神経が優位になり、血管が収縮します。これにより頭皮の血流が悪化し、毛根に栄養が届きにくくなります。
また、ストレスはホルモンバランスの乱れを引き起こし、皮脂の分泌を過剰にすることもあります。ストレスが原因で睡眠の質が低下することも、髪の成長にはマイナスです。
特定の箇所が円形に抜ける「円形脱毛症」は、自己免疫疾患の一つと考えられていますが、ストレスが引き金になるケースもあると言われています。
育毛剤が抜け毛予防に「効果あり」と言われる理由
育毛剤は、前述したような抜け毛の原因、特に「頭皮環境の悪化」に対してアプローチするために開発されています。
医薬部外品として認められた「有効成分」が、頭皮を健やかな状態に導き、抜け毛を予防します。具体的にどのような働きで効果を発揮するのかを見ていきましょう。
有効成分が頭皮にどう働くか
育毛剤には様々な有効成分が配合されていますが、その働きは主に「抗炎症」「保湿」「血行促進」「皮脂分泌の調整」「毛母細胞の活性化」などに分類できます。
多くの育毛剤は、これらの成分を複数組み合わせることで、多角的に頭皮環境にアプローチします。
育毛剤の主な有効成分と期待される働き
| 働きの分類 | 主な有効成分例 | 期待される働き |
|---|---|---|
| 抗炎症・殺菌 | グリチルリチン酸2K、ピロクトンオラミン | フケ、かゆみ、頭皮の炎症を抑える。 |
| 血行促進 | センブリエキス、トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE誘導体) | 頭皮の血流を良くし、毛根へ栄養を届ける。 |
| 保湿 | セラミド、ヒアルロン酸、コラーゲン | 頭皮の乾燥を防ぎ、バリア機能をサポートする。 |
頭皮の炎症を抑え、フケ・かゆみを防ぐ
抜け毛のサインとして現れやすいのが「フケ」と「かゆみ」です。これらは頭皮で炎症が起きている、あるいは雑菌が繁殖しているサインです。
育毛剤に配合される「グリチルリチン酸ジカリウム」や「アラントイン」などの抗炎症成分は、頭皮の炎症を鎮め、赤みやかゆみを和らげます。
また、「ピロクトンオラミン」や「イソプロピルメチルフェノール」などの殺菌成分は、フケの原因となる菌(マラセチア菌など)の過剰な繁殖を抑え、頭皮を清潔に保ちます。
これにより、かゆみで頭皮を掻き壊して抜け毛を悪化させる、といった負の連鎖を防ぎます。
保湿成分による頭皮の乾燥対策
頭皮も顔の肌と同じように乾燥します。特に洗浄力の強いシャンプーを使っていたり、空気の乾燥する季節だったりすると、頭皮の水分が奪われ、バリア機能が低下します。
育毛剤には「セラミド」「ヒアルロン酸」「コラーゲン」などの高保湿成分や、植物由来の保湿エキスが配合されていることが多くあります。
これらの成分が頭皮の角質層に潤いを与え、水分の蒸発を防ぎます。頭皮が潤うことでバリア機能が正常に働き、外部刺激によるかゆみや炎症が起こりにくい、しなやかな頭皮状態を維持できます。
血行促進による毛根への栄養補給
髪の毛は、毛根にある毛母細胞が細胞分裂を繰り返すことで成長します。そのエネルギー源となるのが、血液によって運ばれてくる栄養素です。
育毛剤に含まれる「センブリエキス」や「ビタミンE誘導体(トコフェロール酢酸エステル)」などは、頭皮の毛細血管に働きかけ、血流を促進する効果が期待されます。
頭皮の血行が良くなることで、毛母細胞に必要な栄養と酸素が十分に行き渡り、細胞分裂が活発になります。これにより、髪が太く、長く成長するのを助け、抜けにくい丈夫な髪を育むことにつながります。
育毛剤はAGAの進行を止められるか
抜け毛の原因として最も多いAGAに対して、育毛剤(医薬部外品)はどのような立ち位置にあるのでしょうか。「AGAかもしれない」と不安に思う方にとって、ここは最も知りたい点かもしれません。
AGAによる抜け毛の特異性
まず再確認したいのは、AGAによる抜け毛は、頭皮環境の悪化や生活習慣の乱れによる抜け毛とは根本的な原因が異なるという点です。
AGAは、男性ホルモン由来のDHTが毛根の受容体に作用し、ヘアサイクルを強制的に短縮させることで起こります。
いくら頭皮環境を清潔にし、生活習慣を整えても、このDHTの働きを抑えない限り、AGAの進行を根本的に止めることは難しいとされています。
AGAは進行性であるため、対策を講じなければ、抜け毛は続き、薄毛の範囲は広がっていきます。
育毛剤のAGAに対する立ち位置
結論から言うと、一般的に「育毛剤」として販売されている医薬部外品の多くは、AGAの直接的な原因であるDHTの生成を阻害したり、その働きをブロックしたりする効果を主目的とはしていません。
育毛剤の役割は、あくまで「頭皮環境の改善」です。AGAが進行している人の頭皮が、必ずしも健康とは限りません。
AGAの進行と並行して、皮脂が過剰であったり、乾燥して炎症を起こしていたりするケースも多くあります。
育毛剤を使用することで、このようなAGA以外の抜け毛要因(頭皮環境の悪化)をケアし、現状の髪を少しでも健康に保つ、あるいは抜け毛の速度を「頭皮環境の悪化分」だけ緩和させる、というサポート的な役割が期待されます。
「予防」と「治療」の境界線
ここで重要なのが「予防」と「治療」の境界線です。育毛剤は、頭皮環境を整えることで、将来的な抜け毛を「予防」したり、今ある髪の健康を「育んだり」するものです。
一方、AGAの進行を止めたり、すでに薄くなった部分から発毛させたりすることは「治療」の領域に入ります。
AGAの「治療」には、先述した発毛剤(ミノキシジル外用薬)や、医師の処方が必要な内服薬(フィナステリドやデュタステリドなど、DHTの生成を抑える薬)が用いられます。
育毛剤で抜け毛予防を試みることは大切ですが、もし抜け毛が止まらず、生え際の後退や頭頂部の薄毛が明らかに進行している場合は、育毛剤(医薬部外品)でのケアには限界がある可能性を認識しなくてはなりません。
AGAが疑われる場合の最初の行動
「自分はAGAかもしれない」と感じた場合、育毛剤を試すのと並行して、あるいはその前に、一度専門のクリニック(皮膚科やAGA専門クリニック)で相談することをお勧めします。
専門医であれば、マイクロスコープで頭皮の状態を診断したり、問診を通じて抜け毛の原因がAGAによるものか、それ以外の要因(円形脱毛症や脂漏性皮膚炎など)かを判断したりできます。
AGAであった場合は、進行度合いに応じた治療(内服薬、外用薬など)の提案を受けられます。
もしAGAでなく、頭皮環境の悪化が主な原因であれば、適切な頭皮ケアの方法や、場合によっては育毛剤の使用についてアドバイスをもらえます。
自己判断で悩み続けるよりも、専門家の診断を受けることが、抜け毛予防への一番の近道となる場合も多いのです。
抜け毛予防のための育毛剤選びのポイント
育毛剤が頭皮環境の改善に役立つとして、いざ購入しようと思っても、市場には無数の商品があり、どれを選べばよいか迷ってしまいます。
ここでは、抜け毛予防という観点から、自分に合った育毛剤を選ぶためのポイントを解説します。
自分の頭皮タイプ(乾燥肌・脂性肌)を知る
育毛剤選びでまず重要なのは、自分の頭皮タイプを把握することです。頭皮タイプによって、必要なケアや相性の良い成分が異なります。
簡単な見分け方として、シャンプーをしてから数時間後、あるいは翌朝の頭皮の状態を確認してみましょう。
頭皮がカサカサしてフケ(乾性フケ)が出やすいなら「乾燥肌」。逆に、すぐにベタつき、髪が束になるようなら「脂性肌」の可能性が高いです。
乾燥肌の人は、セラミドやヒアルロン酸などの高保湿成分を重視して選びましょう。
アルコール(エタノール)の配合量が多いものは、清涼感はありますが乾燥を助長することもあるため、配合量をチェックするか、アルコールフリーのものを選ぶと良いでしょう。
脂性肌の人は、過剰な皮脂を抑える成分(ビタミンC誘導体など)や、殺菌成分(ピロクトンオラミンなど)が配合されたものが適している場合があります。
ただし、皮脂を取りすぎると逆に乾燥を招くため、保湿も怠らないバランスが大切です。
頭皮タイプ別のおすすめ成分傾向
| 頭皮タイプ | 主な悩み | 注目したい成分例 |
|---|---|---|
| 乾燥肌 | カサつき、乾性フケ、かゆみ | セラミド、ヒアルロン酸、コラーゲン(高保湿成分) |
| 脂性肌 | ベタつき、湿性フケ、毛穴詰まり、ニオイ | ピロクトンオラミン(殺菌)、ビタミンC誘導体(皮脂調整) |
| 敏感肌 | 赤み、ヒリヒリ感、刺激に弱い | アルコールフリー、無添加(香料・着色料など) |
配合されている有効成分に注目する
自分の頭皮タイプと悩みに合わせて、配合されている「有効成分」をチェックしましょう。医薬部外品の場合、パッケージや説明書に有効成分の記載が義務付けられています。
例えば、「抜け毛予防」と「フケ・かゆみ防止」を同時にケアしたいなら、血行促進成分(センブリエキスなど)と抗炎症成分(グリチルリチン酸2Kなど)の両方が入っているものが効率的です。
また、商品によっては、メーカー独自の保湿成分や、特定の植物エキスを配合していることを特徴としている場合もあります。
成分表を見て、自分の悩みにアプローチできる成分が含まれているかを確認しましょう。
使い続けられる価格と使用感
育毛剤は、薬とは異なり、即効性を期待するものではありません。頭皮環境が改善され、ヘアサイクルが整うまでには時間がかかります。
一般的に、効果を判断するためには最低でも3ヶ月から6ヶ月の継続使用が必要とされます。
そのため、いくら高価で良い成分が入っていても、経済的に継続できなければ意味がありません。自分が無理なく続けられる価格帯の商品を選ぶことが非常に重要です。
また、使用感(テクスチャ)も継続の鍵です。液だれしやすいサラサラタイプ、頭皮に留まりやすいとろみのあるタイプ、スプレータイプ、ノズルタイプなど様々です。
ベタつきが気になる、ニオイが苦手、といった理由で使うのが億劫になっては本末転倒です。テスターや返金保証制度などを利用して、自分が毎日快適に使えるものを見つけましょう。
無添加・低刺激処方の重要性
特に頭皮がデリケートな人(敏感肌)や、乾燥がひどい人は、低刺激処方であるかどうかもチェックポイントです。
育毛剤には、清涼感を出すためのエタノール(アルコール)、品質保持のための防腐剤(パラベン)、香り付けの香料、着色料などが含まれていることがあります。
これらの成分が必ずしも悪いわけではありませんが、人によっては刺激となり、かゆみや赤みを引き起こす原因になることもあります。
「アルコールフリー」「パラベンフリー」「無香料」「無着色」といった表記があるものは、比較的低刺激な処方と考えられます。
自分の肌質に合うか不安な場合は、パッチテスト(腕の内側などで試す)を行ってから使用すると安心です。
育毛剤の効果を引き出す正しい使い方
せっかく選んだ育毛剤も、使い方が間違っていては期待する効果を得られません。育毛剤は頭皮に直接作用させるものです。
その効果を最大限に引き出すためには、正しいタイミングと手順で使用することが大切です。
使うタイミングは「洗髪後」が基本
育毛剤を使用するベストなタイミングは、夜の洗髪後です。1日の活動で付着した皮脂、汗、ホコリ、整髪料などをシャンプーでしっかり落とし、頭皮が清潔な状態で使用します。
毛穴が汚れで詰まっていると、育毛剤の成分が毛根まで浸透しにくくなります。また、頭皮が濡れたままだと、成分が薄まったり、水分と一緒に蒸発してしまったりします。
シャンプー後は、まずタオルで髪の水分をしっかり拭き取り、ドライヤーである程度(8割程度)乾かしてから育毛剤を塗布するのが最も効率的です。
朝も使いたい場合は、朝シャン(朝シャンプー)をするのが理想ですが、時間がない場合は、軽く蒸しタオルで頭皮を温めて毛穴を開かせてから使うのも一つの方法です。
ただし、基本は1日1回、夜の清潔な頭皮への使用を推奨する商品が多いです。
頭皮マッサージを組み合わせる方法
育毛剤を塗布した後は、頭皮マッサージを組み合わせることで、成分の浸透を助け、同時に頭皮の血行を促進できます。ただし、やり方を間違えると逆効果になるため注意が必要です。
マッサージの基本は「爪を立てず、指の腹を使うこと」です。そして「頭皮を擦るのではなく、頭皮そのものを動かすイメージ」で行います。
両手の指の腹で頭部全体を掴むようにし、ゆっくりと円を描くように揉みほぐします。特に血行が滞りやすい頭頂部や、側頭部、後頭部(首の付け根)を意識的にほぐすと良いでしょう。
育毛剤を塗布した箇所を中心に、1〜3分程度、心地よいと感じる強さで行います。強く叩いたり、ゴシゴシ擦ったりするのは、頭皮を傷つけ、抜け毛の原因になるため絶対にやめましょう。
育毛剤の正しい使い方
| 手順 | ポイント | 注意点 |
|---|---|---|
| 1. 洗髪 | シャンプーで頭皮の汚れをしっかり落とす。 | 洗浄力の強すぎるシャンプーは避ける。すすぎ残しに注意。 |
| 2. タオルドライ | ゴシゴシ擦らず、タオルで頭皮を押さえるように水分を吸い取る。 | 髪ではなく「頭皮」の水分を拭き取る意識で。 |
| 3. ドライヤー | 温風で髪の根元(頭皮)から乾かす。8割程度乾いた状態にする。 | ドライヤーを近づけすぎない。完全に乾かしすぎない。 |
| 4. 育毛剤塗布 | 気になる部分だけでなく、頭皮全体に行き渡るよう塗布する。 | 液だれに注意。使用量を守る(多すぎても効果は変わらない)。 |
| 5. マッサージ | 指の腹で頭皮全体を優しく揉みほぐし、浸透を促す。 | 爪を立てない。強く擦らない。 |
塗布する量と回数の目安
育毛剤は、たくさん使えば早く効果が出るというものではありません。各商品に記載されている「1回の使用目安量」と「1日の使用回数」(通常1〜2回)を守ることが大切です。
量が少なすぎると成分が頭皮全体に行き渡りませんし、逆に多すぎても浸透しきれず、ベタつきの原因になったり、コストパフォーマンスが悪くなったりするだけです。
使用説明書をよく読み、指定された量を守って使いましょう。
塗布する際は、髪の毛ではなく、頭皮に直接つけることを意識します。髪をかき分け、ボトルのノズルを頭皮に近づけて塗布するか、スプレータイプなら頭皮に直接噴射します。
その後、すぐにマッサージでなじませます。
すぐに効果は出ない 継続使用の大切さ
最も強調したいのが「継続」の重要性です。育毛剤を使い始めて1週間や1ヶ月で「抜け毛が減らない」「髪が増えない」と判断するのは早すぎます。
育毛剤の目的は、頭皮環境を整え、乱れたヘアサイクルを正常化することです。ヘアサイクルは数ヶ月から数年単位の長いものです。
育毛剤の効果で頭皮環境が改善し、その結果として新しく生えてくる髪が健康になり、抜け毛が減ったと実感できるまでには、最低でも3ヶ月、一般的には6ヶ月程度の時間が必要です。
抜け毛予防は短距離走ではなく、マラソンです。すぐに結果が出なくても諦めず、まずは6ヶ月間、毎日のケアとして習慣化することを目指しましょう。
育毛剤と併行したい 頭皮環境の改善習慣
育毛剤は頭皮環境を改善する強力なサポーターですが、育毛剤だけに頼るのではなく、日々の生活習慣全体で頭皮環境を良くしていく意識が、抜け毛予防の効果を最大化します。
育毛剤の「外からのケア」と、生活習慣による「内からのケア」を両立させましょう。
正しいシャンプーの方法と選び方
毎日行うシャンプーは、頭皮環境に最も大きな影響を与えます。間違った方法は、良かれと思っていても頭皮を傷つけています。
まずシャンプー剤の選び方です。
皮脂が多いと感じる人でも、洗浄力が強すぎる高級アルコール系(ラウレス硫酸〜など)のシャンプーを毎日使うと、必要な皮脂まで奪いすぎ、かえって頭皮の乾燥や皮脂の過剰分泌を招くことがあります。
頭皮への刺激がマイルドな「アミノ酸系」や「ベタイン系」の洗浄成分を主としたシャンプーを選ぶのがお勧めです。
洗い方も重要です。お湯の温度は38〜40度程度のぬるま湯が適温です。シャンプー剤は手のひらで泡立ててから髪につけ、指の腹を使って頭皮をマッサージするように優しく洗います。
最も重要なのは「すすぎ」です。シャンプー剤やコンディショナーが頭皮に残ると、毛穴詰まりや炎症の原因になるため、洗い時間の2倍以上の時間をかけて丁寧にすすぎましょう。
避けるべきNGシャンプー習慣
- 熱すぎるお湯(42度以上)での洗髪
- 爪を立ててゴシゴシと頭皮を擦る
- シャンプー剤を直接頭皮につけて泡立てる
- すすぎが不十分で、ヌルつきが残っている
- 洗髪後、濡れたまま自然乾燥させる(雑菌が繁殖する原因)
髪の成長を支える食生活
髪は、私たちが食べたものから作られます。バランスの取れた食事は、健康な髪を育む基本です。
特に重要なのは、髪の主成分である「タンパク質」、タンパク質の合成を助け、毛母細胞の分裂を促す「亜鉛」、そして頭皮環境を整え、血行を促進する「ビタミン類」です。
これらを偏りなく摂取することが大切です。
一方で、脂っこい食事や糖質の多い食事に偏ると、皮脂の分泌が過剰になり、頭皮環境の悪化につながる可能性があります。
外食やインスタント食品が多い人は、意識してタンパク質や野菜、海藻類を取り入れるように心がけましょう。
髪の成長をサポートする主な栄養素
- タンパク質(肉、魚、卵、大豆製品)
- 亜鉛(牡蠣、レバー、牛肉、ナッツ類)
- ビタミンB群(豚肉、レバー、マグロ、納豆)
- ビタミンA・C・E(緑黄色野菜、果物、ナッツ類)
質の良い睡眠と運動の習慣
髪の成長は、睡眠中に分泌される「成長ホルモン」によって促進されます。特に、入眠から最初の3時間(ノンレム睡眠の深い段階)に多く分泌されると言われています。
睡眠時間が不足したり、夜更かしが続いて睡眠の質が低下したりすると、髪の成長が妨げられます。
毎日決まった時間に寝起きし、十分な睡眠時間(6〜8時間目安)を確保するよう努めましょう。寝る前のスマートフォン操作は、ブルーライトが睡眠の質を下げるため控えるのが賢明です。
また、適度な運動は、全身の血行を促進し、当然ながら頭皮の血流改善にもつながります。
デスクワークが多い人は、首や肩のコリが頭皮の血行不良を招きやすいため、ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動や、ストレッチを習慣にすると良いでしょう。
運動はストレス解消にも役立ち、一石二鳥です。
頭皮環境を整える生活習慣のポイント
| 習慣 | 改善のポイント | 頭皮への良い影響 |
|---|---|---|
| 食事 | タンパク質、亜鉛、ビタミンをバランス良く摂取する。 | 髪の材料を補給し、頭皮環境を整える。 |
| 睡眠 | 質の良い睡眠を6時間以上確保する。 | 成長ホルモンの分泌を促し、髪の成長を助ける。 |
| 運動 | ウォーキングなどの有酸素運動やストレッチを習慣化する。 | 全身の血行を促進し、頭皮への栄養補給を助ける。 |
ストレスマネジメントの工夫
現代社会でストレスをゼロにすることは困難ですが、溜め込まない工夫は可能です。ストレスは自律神経を乱し、頭皮の血行不良や皮脂の過剰分泌を引き起こします。
自分が何にストレスを感じているかを認識し、それを避ける工夫をするとともに、自分なりの解消法を見つけることが大切です。
趣味に没頭する時間を作る、ゆっくり入浴してリラックスする、友人と話す、自然の中を散歩するなど、何でも構いません。運動や良質な睡眠も、ストレス耐性を高める上で役立ちます。
Q&A
最後に、育毛剤や抜け毛予防に関してよく寄せられる質問にお答えします。
- 育毛剤を使い始めるタイミングは?
-
抜け毛予防としての育毛剤は、特に「何歳から」という決まりはありません。
「最近、髪にハリやコシがなくなってきた」「頭皮の乾燥やベタつきが気になる」「抜け毛が少し増えた気がする」など、何らかの変化を感じ始めた時が使い始める良いタイミングです。
抜け毛が明らかに進行してから慌てて対策するよりも、頭皮環境が悪化する前の「予防」として早期にケアを始める方が、健康な頭皮を維持しやすいと言えます。
- 効果はどれくらいで実感できますか?
-
本文でも触れましたが、育毛剤(医薬部外品)は即効性を期待するものではありません。
頭皮環境を整え、ヘアサイクルをサポートするものであり、その効果が「抜け毛が減った」「髪がしっかりしてきた」という実感につながるまでには時間がかかります。
個人差はありますが、まずは最低でも3ヶ月、できれば6ヶ月間は毎日継続して使用し、頭皮の状態や抜け毛の変化を観察してください。
- 副作用が心配です。
-
育毛剤は「医薬部外品」であり、「医薬品」である発毛剤(ミノキシジルなど)と比較すると、作用は穏やかで、副作用のリスクは低いとされています。
ただし、化粧品などと同様に、体質や肌質によっては、配合されている成分(特にアルコールや植物エキスなど)が肌に合わず、赤み、かゆみ、かぶれなどのアレルギー反応や炎症を引き起こす可能性はゼロではありません。
使用して頭皮に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、水かぬるま湯で洗い流してください。症状が改善しない場合は、皮膚科専門医に相談しましょう。
敏感肌の人は、使用前にパッチテストを行うことをお勧めします。
- 育毛剤をやめるとまた抜けますか?
-
育毛剤の使用を中止すると、育毛剤によって保たれていた良好な頭皮環境(保湿、血行促進、抗炎症など)が、元の状態に戻っていく可能性があります。
もし、その人の抜け毛の原因が頭皮環境の悪化によるものであった場合、ケアをやめることで、再び抜け毛が増える可能性はあります。
また、抜け毛の原因がAGAであった場合、育毛剤の使用中もAGA自体は進行している可能性があります。
育毛剤はあくまで頭皮環境を整えるサポートであり、AGAの進行を止めるものではないため、使用を中止したからといって急激に抜けるわけではありませんが、AGA自体の進行による抜け毛は続くことになります。
育毛剤の期間に戻る
Reference
DRAKE, Lara, et al. Evaluation of the safety and effectiveness of nutritional supplements for treating hair loss: a systematic review. JAMA dermatology, 2023, 159.1: 79-86.
CHOI, Dong‐Gi; SHIN, Woo‐Chul. Botanical Extract–Infused Shampoo and Hair Tonic for Hair Loss in Androgenetic Alopecia: A TREND‐Compliant, Prospective Single‐Arm Preexperimental Study. Journal of Cosmetic Dermatology, 2025, 24.6: e70273.
AL-WORAFI, Yaser Mohammed. Evidence-Based Complementary, Alternative and Integrated Medicine and Efficacy and Safety: Hair Care. In: Handbook of Complementary, Alternative, and Integrative Medicine. CRC Press. p. 920-938.
ISWANDI, Ridho; SUHUD, Usep. Sustainable Herbal Hair Tonic for Middle-Aged Health and Wellness. Economic, Management, Business and Accountancy International Journal, 2025, 2.1: 35-44.
ZHOU, Yaguang, et al. Effectiveness and safety of botulinum toxin type A in the treatment of androgenetic alopecia. BioMed Research International, 2020, 2020.1: 1501893.
KAISER, Michael, et al. Treatment of androgenetic alopecia: current guidance and unmet needs. Clinical, cosmetic and investigational dermatology, 2023, 1387-1406.
AHMED, Azhar, et al. Herbal Remedies for Hair Loss: A Review of Efficacy and Safety. Skin Appendage Disorders, 2025.
SRIVASTAVA, Ankita; SRIVASTAVA, Ankur Kumar; PANT, A. B. Strategic Developments for Pre-clinical Safety/Efficacy Studies of Hair Care Products. In: Hair Care Products: Efficacy, Safety and Global Regulation. Singapore: Springer Nature Singapore, 2024. p. 223-273.
ALLAM, Anood T., et al. Pathophysiology, conventional treatments, and evidence-based herbal remedies of hair loss with a systematic review of controlled clinical trials. Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of Pharmacology, 2025, 1-44.
THOR, Dominik, et al. A novel hair restoration technology counteracts androgenic hair loss and promotes hair growth in a blinded clinical trial. Journal of Clinical Medicine, 2023, 12.2: 470.