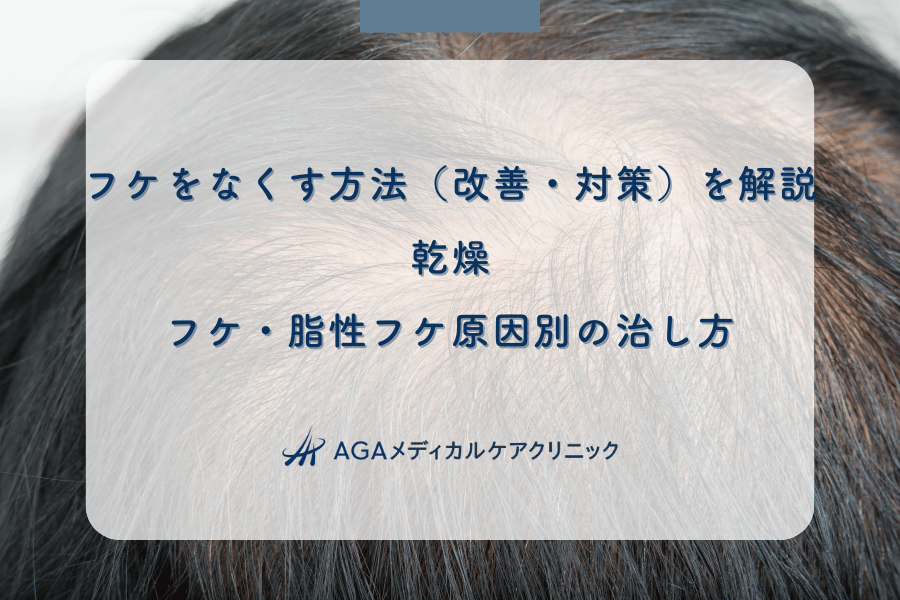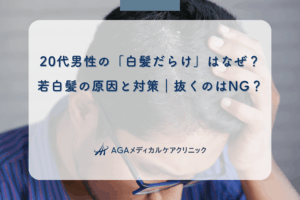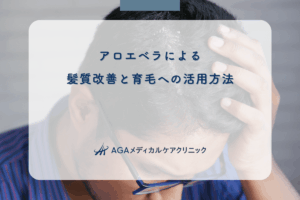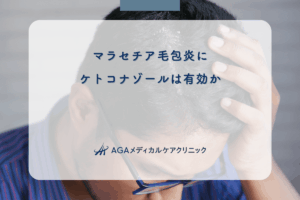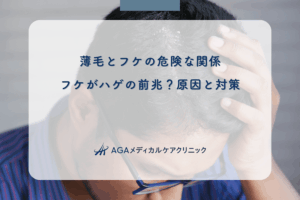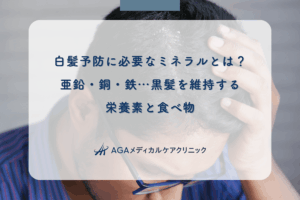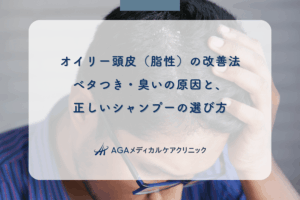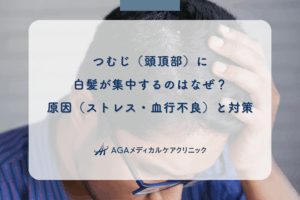肩に落ちる白い粉、頭皮のかゆみやベタつき。フケの悩みは、見た目の印象だけでなく、不快感も伴う深刻な問題です。
フケをなくすには、まず自分のフケが「乾燥フケ」なのか「脂性フケ」なのか原因を知ることが重要です。
この記事では、フケが発生する頭皮の仕組みから、タイプ別の原因、そして具体的な改善・対策方法までを詳しく解説します。
毎日のシャンプー習慣や生活習慣を見直し、フケの悩みから解放されるための第一歩を踏み出しましょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
フケとは何か? その正体と種類
フケをなくす方法を考える前に、まずフケが何であるかを正しく理解する必要があります。フケは単なる汚れではなく、頭皮の健康状態を示すサインです。
その正体を知ることで、適切な対策が見えてきます。
フケが発生する頭皮の仕組み
私たちの皮膚は、一定の周期で新しい細胞に生まれ変わっています。これを「ターンオーバー」と呼びます。
頭皮も同様で、表皮の一番奥にある基底層で新しい細胞が作られ、徐々に表面に押し上げられていきます。最終的に、最も外側の角質層に達した細胞は、垢(あか)となって自然に剥がれ落ちます。
健康な頭皮では、このターンオーバーは約28日〜40日周期で行われ、剥がれ落ちる角質細胞は非常に小さく目に見えません。
しかし、何らかの原因でこのターンオーバーの周期が乱れると、角質細胞が未熟なまま、あるいは大きな塊となって剥がれ落ちるようになります。これが、私たちが「フケ」として認識するものの正体です。
大きく分けて2種類 乾燥フケと脂性フケ
フケは、その性質によって大きく二つのタイプに分類されます。それぞれの特徴を理解することが、フケ改善の第一歩です。
乾燥フケの特徴
カサカサとした細かい粉状のフケです。頭皮全体が乾燥しており、洗髪後につっぱり感やかゆみを感じることが多くあります。特に空気が乾燥する冬場に悪化しやすい傾向があります。
肩や背中にパラパラと落ちやすいのが特徴です。
脂性フケの特徴
湿り気があり、ベタベタとした大きめのフケです。頭皮の皮脂分泌が過剰な状態で見られます。フケが皮脂と混ざり合って毛穴を塞いだり、頭皮にこびりついたりすることがあります。
脂っぽい独特のニオイを伴うことも少なくありません。
フケのタイプ別 見分け方
| フケのタイプ | 特徴 | 主な原因 |
|---|---|---|
| 乾燥フケ | ・カサカサ、粉っぽい ・白く細かい ・肩に落ちやすい | 頭皮の乾燥、皮脂の不足、洗浄力の強すぎるシャンプー |
| 脂性フケ | ・ベタベタ、湿っぽい ・黄色味を帯びた大きめの塊 ・頭皮に張り付く | 皮脂の過剰分泌、マラセチア菌の増殖、シャンプーのすすぎ残し |
フケと勘違いしやすい頭皮トラブル
フケのように見えても、実際には異なる頭皮の疾患である可能性もあります。
例えば、「脂漏性皮膚炎(しろうせいひふえん)」は、フケと症状が似ていますが、より強いかゆみや赤み、炎症を伴うことが多い疾患です。
また、「尋常性乾癬(じんじょうせいかんせん)」なども、頭皮にフケのような鱗屑(りんせつ)を生じることがあります。
セルフケアで改善しない、あるいは症状がひどい場合は、自己判断せずに皮膚科専門医に相談することが重要です。
さらに、フケと見間違いやすい症状の一つとしてヘアキャストがあります。ヘアキャストは、髪の毛の根元から数センチほどの部分に鞘(さや)のように巻き付いている、白く半透明な付着物です。
ヘアキャストは病気ではありませんが、頭皮環境やヘアケアの方法に何らかの偏りがあるのを示しています。
ヘアキャストについて詳しく見る
ヘアキャストとは?フケ・しらみとの違い、原因(シャンプー残し)と取り方
フケを放置するリスク
フケは不潔な印象を与えるだけでなく、放置すると頭皮環境をさらに悪化させる可能性があります。脂性フケの場合、過剰な皮脂とフケが毛穴を塞ぎ、雑菌が繁殖しやすい環境を作ります。
これにより、かゆみや炎症が強くなるだけでなく、抜け毛や薄毛の原因にもつながる可能性があります。
乾燥フケも、頭皮のバリア機能が低下しているサインであり、外部からの刺激を受けやすくなり、かゆみや炎症を引き起こしやすくなります。
【タイプ別】フケの主な原因を探る
フケを効果的に改善・対策するためには、なぜフケが発生しているのか、その根本的な原因を知る必要があります。
乾燥フケと脂性フケ、それぞれを引き起こす主な要因について詳しく見ていきましょう。
乾燥フケを引き起こす要因
乾燥フケは、その名の通り頭皮の「乾燥」が最大の原因です。頭皮の水分と皮脂が不足し、バリア機能が低下することで、ターンオーバーが早まり、未熟な角質が剥がれ落ちやすくなります。
洗浄力の強すぎるシャンプーの使用
毎日使うシャンプーの洗浄力が強すぎると、頭皮を守るために必要な皮脂まで洗い流してしまいます。
特に石油系界面活性剤(ラウリル硫酸Na、ラウレス硫酸Naなど)を主成分とするシャンプーは洗浄力が強力なため、乾燥肌や敏感肌の人は注意が必要です。
皮脂が奪われると、頭皮は水分を保持できなくなり、乾燥が進みます。
誤った洗髪習慣
一日に何度もシャンプーをしたり、熱すぎるお湯で洗髪したりする習慣も頭皮の乾燥を招きます。また、ゴシゴシと強く洗いすぎると頭皮が傷つき、バリア機能が低下します。
洗髪後はドライヤーでしっかり乾かすことが大切ですが、温風を当てすぎると頭皮の水分が奪われるため、適切な距離と時間を守る必要があります。
空気の乾燥と紫外線
冬場の暖房による空気の乾燥や、夏場の強い紫外線も頭皮を乾燥させる要因です。紫外線は頭皮にダメージを与え、水分を奪い、ターンオーバーの乱れを引き起こします。
日頃から帽子や日傘で頭皮を守る意識も重要です。
脂性フケを引き起こす要因
脂性フケは、頭皮の「皮脂の過剰分泌」が主な原因です。皮脂が多くなると、それをエサにする常在菌が増殖しやすくなり、頭皮環境が悪化します。
皮脂分泌の多い体質
皮脂の分泌量は、遺伝的な体質や性ホルモンの影響を強く受けます。
特に男性ホルモン(テストステロン)は皮脂腺の働きを活発にするため、男性は女性に比べて脂性フケになりやすい傾向があります。
シャンプーのすすぎ残し
シャンプーやコンディショナーの成分が頭皮に残っていると、それが毛穴に詰まったり、雑菌のエサになったりして皮脂の過剰分泌や炎症を引き起こす原因となります。
特に髪の生え際や襟足などは、すすぎ残しが多発する場所なので、意識して丁寧に洗い流す必要があります。
脂っこい食事の偏り
揚げ物やジャンクフード、スイーツなど、脂質や糖質の多い食事ばかり摂っていると、体内の皮脂分泌が活発になります。その結果、頭皮の皮脂も過剰になり、脂性フケの原因となります。
脂性頭皮の改善方法を詳しく見る
オイリー頭皮(脂性)の改善法|ベタつき・臭いの原因と、正しいシャンプーの選び方
共通する原因 マラセチア菌とは
乾燥フケ・脂性フケの両方に関連する原因として、「マラセチア菌(マラセチア・フルフル)」という常在菌(カビの一種)の存在が挙げられます。
マラセチア菌は、誰の頭皮にも存在し、皮脂をエサにして生きています。
通常は問題を起こしませんが、皮脂が過剰になったり、汗などで頭皮が蒸れたりすると、マラセチア菌が異常増殖します。
この菌は皮脂を分解する際に「遊離脂肪酸」という刺激物質を生成し、これが頭皮を刺激してターンオーバーを乱し、フケやかゆみを引き起こします。
脂性フケの場合はもちろん、乾燥フケの場合でも、バリア機能が低下した頭皮にマラセチア菌が増殖すると、症状が悪化することがあります。
生活習慣の乱れとフケの関係
フケの原因は頭皮だけにあるとは限りません。日々の生活習慣が頭皮環境に大きく影響します。
フケにつながる生活習慣の例
| 生活習慣の側面 | フケへの影響(例) | 改善のポイント |
|---|---|---|
| 食生活 | 脂質・糖質の過剰摂取は皮脂を増やす。ビタミンB群の不足は皮膚の新陳代謝を低下させる。 | バランスの良い食事を心がけ、特にビタミンB2、B6を意識して摂取する。 |
| 睡眠 | 睡眠不足は成長ホルモンの分泌を妨げ、頭皮のターンオーバーを乱す。 | 質の高い睡眠を十分な時間確保する。寝る前のスマートフォン操作を控える。 |
| ストレス | 過度なストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、皮脂の分泌を不安定にする。 | 趣味の時間を持つ、適度な運動をするなど、自分なりのストレス解消法を見つける。 |
フケをなくすための基本的な対策と考え方
フケの原因が多岐にわたるように、その対策も一つではありません。しかし、すべてのフケ対策に共通する基本的な考え方があります。正しいアプローチで、頭皮環境の改善を目指しましょう。
まずは自分のフケタイプを知る
前述の通り、フケには「乾燥フケ」と「脂性フケ」があります。カサカサした粉状なら乾燥フケ、ベタベタした塊なら脂性フケの可能性が高いです。
自分のフケがどちらのタイプなのかを見極めることが、フケをなくすためのスタートラインです。なぜなら、タイプによって選ぶべきシャンプーやケア方法が全く異なるからです。
間違ったケアは、かえって症状を悪化させる可能性もあるため注意しましょう。
頭皮環境の改善が鍵
フケ対策の根本は、フケを「取り除く」ことよりも、フケが「発生しにくい」頭皮環境を作ることです。健康な頭皮は、適度な皮脂と水分が保たれ、バリア機能が正常に働いています。
このバランスが崩れるとフケが発生します。したがって、シャンプー方法や生活習慣の見直しを通じて、頭皮のターンオーバーを正常化し、皮脂と水分のバランスを整えることが最も重要です。
毎日のシャンプー習慣の見直し
フケ対策において、毎日のシャンプーは最も重要なケアの一つです。しかし、ただ洗えば良いというものではありません。「洗いすぎ」は乾燥フケの原因となり、「洗い残し」は脂性フケの原因となります。
自分の頭皮タイプに合ったシャンプーを選び、正しい方法で洗髪することが求められます。
頭皮ケアの基本ステップ
- ブラッシング(洗髪前)
- 予洗い(ぬるま湯)
- シャンプー(指の腹で)
- すすぎ(丁寧に)
- 乾燥(ドライヤー)
特に「予洗い」と「すすぎ」は重要です。予洗いをしっかり行うことで、シャンプーの泡立ちが良くなり、少ない洗浄剤で効率よく汚れを落とせます。
すすぎは、シャンプー剤が頭皮に残らないよう、普段の倍の時間をかける意識で丁寧に行いましょう。
フケ対策は継続が重要
頭皮環境の改善やターンオーバーの正常化には時間がかかります。フケ対策用のシャンプーを使い始めたり、生活習慣を改善したりしても、すぐに結果が出るとは限りません。
効果が実感できるまでには、少なくとも1ヶ月以上はかかると考えましょう。症状が改善しても、すぐに元のシャンプーや生活に戻すと再発する可能性もあります。
健康な頭皮を維持するためには、日々の地道なケアを継続することが大切です。
【乾燥フケ】なくす方法と具体的な改善アプローチ
乾燥フケの対策は、「保湿」と「低刺激」がキーワードです。頭皮のバリア機能を取り戻し、うるおいを保つための具体的な方法を見ていきましょう。
保湿重視のシャンプー選び
乾燥フケの人は、頭皮に必要な皮脂まで奪わないよう、洗浄力がマイルドなシャンプーを選ぶ必要があります。アミノ酸系やベタイン系の洗浄成分を主成分としたシャンプーが適しています。
これらの成分は、適度な洗浄力を持ちつつ、頭皮のうるおいを保ちながら洗い上げます。
また、ヒアルロン酸、セラミド、コラーゲン、グリセリンなどの保湿成分が配合されているかどうかもチェックポイントです。成分表示を見て、洗浄成分と保湿成分を確認する習慣をつけましょう。
乾燥フケ対策シャンプーの選び方
| チェックポイント | 推奨される成分・特徴 | 避けたい成分・特徴 |
|---|---|---|
| 洗浄成分 | アミノ酸系(例 ココイルグルタミン酸Na) ベタイン系(例 コカミドプロピルベタイン) | 高級アルコール系(例 ラウリル硫酸Na、ラウレス硫酸Na) 石けん系(洗浄力が強い場合) |
| 保湿成分 | ヒアルロン酸、セラミド、グリセリン、コラーゲン、植物オイル(ホホバ油など) | 特になし(保湿成分は積極的に選びたい) |
| その他 | 無添加(香料、着色料、防腐剤フリー)、弱酸性、低刺激性 | 強い清涼感(メントールなど)、刺激の強い添加物 |
正しいシャンプーの手順と洗い方
乾燥フケの場合、洗い方が特に重要です。以下の手順を守り、頭皮への負担を最小限に抑えましょう。
- ブラッシング: 乾いた髪をブラッシングし、髪の絡まりをほどき、頭皮の汚れを浮かせます。
- 予洗い: 38度程度のぬるま湯で、頭皮と髪を1〜2分かけてしっかり濡らします。これだけで汚れの7割は落ちると言われています。
- 泡立て: シャンプーを手のひらに取り、少量のお湯を加えてよく泡立てます。原液を直接頭皮につけるのは避けましょう。
- 洗う: 泡を頭皮全体に行き渡らせ、指の腹を使ってマッサージするように優しく洗います。爪を立ててゴシゴシ擦るのは厳禁です。
- すすぎ: シャンプー剤が残らないよう、ぬるま湯で丁寧にすすぎます。特に生え際や襟足は念入りに。
- 保湿: 必要に応じて、頭皮用の保湿ローションなどを使用します。コンディショナーやトリートメントは、毛先中心につけ、頭皮には極力つかないように注意し、しっかりすすぎます。
洗浄力が強すぎるシャンプーを避ける
前述の通り、洗浄力が強力なシャンプーは乾燥フケの最大の敵とも言えます。現在使用しているシャンプーで洗髪後に頭皮のつっぱりやかゆみを感じる場合は、洗浄力が強すぎる可能性があります。
泡立ちが非常に良い、洗い上がりが「キュッキュッ」とするタイプのシャンプーは、皮脂を取りすぎる傾向があるため、見直しを検討しましょう。
頭皮の保湿ケアを取り入れる
シャンプーで「守り」のケアをしたら、次は「補う」ケアが大切です。洗髪後、タオルドライした後の清潔な頭皮に、頭皮専用の保湿ローションやエッセンスを使うことをおすすめします。
顔のスキンケアで化粧水や乳液を使うのと同じ感覚です。
保湿成分(セラミド、ヒアルロン酸など)が配合されたものや、抗炎症成分(グリチルリチン酸2Kなど)が配合されたものを選ぶと、乾燥とかゆみの両方にアプローチできます。
育毛剤の中にも、頭皮の保湿や環境改善を目的とした製品が多くありますので、フケ対策と合わせて検討するのも良いでしょう。
【脂性フケ】なくす方法と効果的な皮脂対策
脂性フケの対策は、「適切な皮脂コントロール」と「原因菌の抑制」が鍵となります。過剰な皮脂を放置せず、清潔な頭皮環境を維持する方法を解説します。
皮脂を適切に除去するシャンプー選び
脂性フケの人は、頭皮の余分な皮脂や汚れをしっかりと洗い流す必要があります。
ただし、乾燥フケ同様、皮脂を取りすぎるとかえって皮脂分泌が活発になる(過乾燥によるリバウンド)可能性もあるため、洗浄力と保湿のバランスが取れたシャンプーを選ぶことが重要です。
アミノ酸系の中でも比較的洗浄力がしっかりしたものや、スカルプケア(頭皮ケア)を謳った薬用シャンプーが適しています。皮脂の除去を助けるクレイ(泥)成分や炭が配合されたものも選択肢になります。
抗真菌成分配合のシャンプーの活用
脂性フケの原因となるマラセチア菌の増殖を抑える「抗真菌(抗カビ)成分」が配合された薬用シャンプーの使用は、脂性フケの改善に非常に効果的です。
主な抗真菌成分
| 成分名 | 主な働き | 特徴 |
|---|---|---|
| ミコナゾール硝酸塩 | マラセチア菌の増殖を抑える | フケ・かゆみを防ぐ薬用シャンプーに広く配合されている。 |
| ピロクトンオラミン | マラセチア菌の増殖を抑え、皮脂の酸化を防ぐ | 殺菌作用と抗酸化作用を併せ持つ。 |
| サリチル酸 | 硬くなった角質を柔らかくし、剥がれやすくする | ピーリング作用。他の抗真菌成分と併用されることも多い。 |
これらの成分が配合されたシャンプーを使用する際は、泡立てた後すぐに洗い流さず、泡が頭皮全体に行き渡った状態で数分間放置する「泡パック」を行うと、成分が浸透しやすくなり効果が高まる場合があります(製品の使用方法を確認してください)。
すすぎ残しを防ぐ丁寧な洗い方
脂性フケの人は、皮脂だけでなくシャンプー剤のすすぎ残しにも細心の注意を払う必要があります。シャンプー剤が頭皮に残ると、皮脂やフケと混ざり合い、マラセチア菌のエサとなり、症状を悪化させます。
洗う時よりも「すすぎ」に時間をかけることを意識してください。
シャワーヘッドを頭皮に近づけ、指の腹で頭皮を軽く動かしながら、髪の内部や生え際、襟足、耳の後ろなど、すすぎ残しやすい部分まで徹底的に洗い流しましょう。
「もう十分かな」と思ってから、さらに30秒すすぐくらいの意識が大切です。コンディショナーやトリートメントも同様に、頭皮に残らないようしっかりすすぎます。
頭皮のべたつきを悪化させる習慣
日中の頭皮のべたつきが気になるからといって、洗浄力の強すぎるシャンプーを使ったり、一日に何度も洗髪したりするのは逆効果です。
皮脂の取りすぎは、頭皮が「皮脂が足りない」と勘違いし、さらに皮脂を分泌しようとする悪循環を招きます。
また、洗髪後に髪を乾かさない「自然乾燥」は、頭皮が湿った状態が長く続き、雑菌が繁殖しやすい環境を作るため、脂性フケを悪化させる最たる原因の一つです。
洗髪後は速やかにドライヤーで頭皮から乾かす習慣を徹底しましょう。
フケの種類別の対策について詳しく見る
シャンプーしてもフケが出るのはなぜ?「乾燥フケ」「脂性フケ」原因別の対策
フケ予防のために見直したい生活習慣
フケをなくすためには、シャンプーなどの外側からのケアだけでなく、体の中から頭皮環境を整える「インナーケア」も非常に重要です。
日々の生活習慣を見直し、フケの出にくい健康な頭皮を目指しましょう。
食生活の改善と栄養バランス
私たちが食べたものは、血液を通じて頭皮にも運ばれ、髪や頭皮の健康状態に直結します。特に脂性フケの人は、脂質や糖質の多い食事を控えることが予防につながります。
頭皮環境の改善に役立つ栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| ビタミンB2 | 皮脂の分泌をコントロールし、皮膚の健康を保つ。 | レバー、うなぎ、卵、納豆、乳製品 |
| ビタミンB6 | 皮膚の新陳代謝(ターンオーバー)を正常化する。 | マグロ、カツオ、鶏肉、バナナ、ナッツ類 |
| ビタミンA・C・E | 抗酸化作用で頭皮の老化を防ぎ、血行を促進する。 | 緑黄色野菜、果物、アーモンド、植物油 |
| 亜鉛 | 皮膚や髪の毛の主成分であるケラチンの合成を助ける。 | 牡蠣、牛肉、レバー、チーズ |
これらの栄養素をバランス良く摂取することを心がけ、特定の食品に偏らないように注意しましょう。外食やコンビニ食が多い人は、意識的に野菜や海藻類、タンパク質を取り入れる工夫が必要です。
質の高い睡眠の確保
睡眠中は、成長ホルモンが分泌され、日中に受けたダメージを修復し、細胞の新陳代謝を促す大切な時間です。
睡眠不足が続くと、この成長ホルモンの分泌が減少し、頭皮のターンオーバーが乱れる直接的な原因となります。
特に、入眠から最初の3時間は「ゴールデンタイム」と呼ばれ、成長ホルモンが多く分泌されます。日付が変わる前に就寝することを目標にし、毎日6〜7時間程度の十分な睡眠時間を確保するよう努めましょう。
寝る直前のスマートフォンやパソコンの使用は、ブルーライトが脳を覚醒させ、睡眠の質を低下させるため控えるのが賢明です。
ストレス管理とリフレッシュ法
現代社会においてストレスをゼロにすることは困難ですが、過度なストレスは自律神経のバランスを崩します。
自律神経が乱れると、交感神経が優位になり、血管が収縮して頭皮の血行が悪くなったり、ホルモンバランスが乱れて皮脂が過剰に分泌されたりします。
自分なりのストレス解消法を見つけることが、フケの予防・改善につながります。
ゆっくり湯船に浸かる、好きな音楽を聴く、趣味に没頭する時間を作る、瞑想するなど、心身ともにリラックスできる時間を持つようにしましょう。
適度な運動のすすめ
適度な運動は、全身の血行を促進し、頭皮にも十分な栄養と酸素を届ける助けとなります。また、運動による心地よい疲労感は睡眠の質を高め、ストレス解消にも役立ちます。
ウォーキングやジョギング、ストレッチなど、無理のない範囲で継続できる運動を日常生活に取り入れましょう。
ただし、運動で汗をかいた後は、そのまま放置すると頭皮が蒸れて雑菌が繁殖しやすくなるため、早めにシャワーを浴びて清潔に保つことが重要です。
フケ対策でよくある間違いと注意点
フケを早くなくしたい一心で、間違ったケアをしてしまうと、かえって症状を悪化させることがあります。フケ対策で陥りやすい間違いや注意点を理解し、正しいケアを実践しましょう。
洗いすぎによる頭皮環境の悪化
フケやかゆみ、べたつきが気になると、一日に何度もシャンプーをしたくなるかもしれません。しかし、前述の通り、シャンプーのしすぎは頭皮に必要な皮脂まで奪い去り、乾燥フケを助長します。
また、皮脂の取りすぎが皮脂の過剰分泌を招き、脂性フケを悪化させることもあります。
シャンプーは原則として1日1回、夜に行うのが基本です。汗を大量にかいた日などを除き、過度な洗髪は控えましょう。
爪を立てて洗うことのリスク
かゆみがあると、つい爪を立ててゴシゴシと強く洗ってしまいがちです。その瞬間はスッキリするかもしれませんが、これは頭皮を傷つける非常に危険な行為です。
頭皮に細かい傷がつくと、そこから雑菌が侵入して炎症を起こしたり、頭皮のバリア機能が低下してさらに乾燥が進んだりします。
シャンプーは必ず「指の腹」を使い、頭皮をマッサージするように優しく洗いましょう。
フケを無理に剥がす行為
頭皮にこびりついた大きめのフケや、かさぶたのようになったフケが気になり、指や爪、くしなどで無理に剥がそうとするのは絶対にやめましょう。
無理に剥がすと、まだ剥がれる準備ができていない健康な皮膚まで一緒に剥がしてしまい、頭皮を傷つけ、炎症や出血を引き起こす可能性があります。
フケは、正しいシャンプーやケアを続けることで自然に剥がれ落ちるのを待つのが正解です。
自然乾燥はNG ドライヤーの正しい使い方
「ドライヤーの熱は頭皮に悪い」と考え、洗髪後にタオルドライだけで済ませ、自然乾燥させる人がいますが、これはフケ対策としては間違いです。
髪が濡れた状態が続くと、頭皮の温度と湿度が高まり、マラセチア菌をはじめとする雑菌が繁殖する絶好の環境を作ってしまいます。
これは脂性フケを悪化させるだけでなく、イヤなニオイの原因にもなります。
頭皮を守る正しいドライヤー術
- タオルドライ(吸水性の高いタオルで優しく水分を取る)
- ドライヤー(頭皮から20cm以上離す)
- 根元から乾かす(毛先は後で)
- 仕上げ(8割程度乾いたら冷風に切り替える)
洗髪後はできるだけ速やかに、ドライヤーでまず頭皮と髪の根元を乾かすことを徹底してください。
ただし、一箇所に熱風を当て続けると頭皮が乾燥するため、ドライヤーを小刻みに振りながら全体的に乾かすのがコツです。
よくある質問
フケをなくす方法や改善・対策に関して、多くの方が抱く疑問についてお答えします。
- フケはどのくらいで改善しますか?
-
フケの改善にかかる期間は、フケのタイプ、症状の程度、そして対策の適切さによって個人差が大きいです。
一般的に、頭皮のターンオーバーの周期(約1ヶ月)が一つの目安となります。
自分のフケタイプに合ったシャンプーを選び、正しい洗髪方法と生活習慣の改善を継続すれば、早い人では2週間程度でかゆみやフケの減少を実感し始め、1ヶ月から2ヶ月程度で頭皮環境が安定してくることが多いです。
ただし、脂漏性皮膚炎などが関わっている場合は、より時間がかかるか、専門的な治療が必要です。
- 育毛剤はフケに影響しますか?
-
育毛剤の目的は主に発毛促進や抜け毛予防ですが、多くの製品には頭皮環境を整える成分(保湿成分、抗炎症成分、血行促進成分など)が含まれています。
したがって、乾燥によるフケやかゆみ、血行不良による頭皮環境の悪化がフケの原因である場合、育毛剤の使用がフケの改善に良い影響を与える可能性はあります。
ただし、アルコール(エタノール)の配合量が多い育毛剤は、乾燥フケや敏感肌の人には刺激となり、症状を悪化させることもあります。
フケがひどい時は、まずフケ対策を優先し、症状が落ち着いてから育毛剤の使用を検討するのが賢明です。
- フケ対策シャンプーはずっと使い続けるべきですか?
-
フケの原因菌(マラセチア菌)を抑える抗真菌成分配合のシャンプーなどは、症状が改善した後も、予防として週に1〜2回程度の使用を継続することが推奨される場合があります。
毎日使用していたのを急にやめると、菌が再び増殖してフケが再発する可能性があるためです。
一方、アミノ酸系シャンプーなどで乾燥フケが改善した場合は、頭皮の状態が安定していれば、同じ系統の別のシャンプーに変えても問題ないことが多いです。
自分の頭皮の状態を観察しながら、使用頻度を調整することが大切です。
- フケが改善しない場合はどうすればよいですか?
-
セルフケアでフケ対策シャンプーを使ったり、生活習慣を見直したりしても、2週間以上フケやかゆみが改善しない、あるいは悪化する場合は、自己判断でのケアを中止し、速やかに皮膚科専門医を受診してください。
フケだと思っていたものが、脂漏性皮膚炎や乾癬、アトピー性皮膚炎など、別の皮膚疾患の可能性もあります。
専門医の診断を受け、適切な指導や治療を受けることが、フケをなくすための最も確実な方法です。
Reference
SCHWARTZ, James R., et al. A comprehensive pathophysiology of dandruff and seborrheic dermatitis–towards a more precise definition of scalp health. Acta dermato-venereologica, 2013, 93.2: 131-137.
GUPTA, Aditya K., et al. Understanding the Scalp: Dandruff and Seborrheic Dermatitis. Journal of Cutaneous Medicine and Surgery, 12034754251368845.
BORDA, Luis J.; WIKRAMANAYAKE, Tongyu C. Seborrheic dermatitis and dandruff: a comprehensive review. Journal of clinical and investigative dermatology, 2015, 3.2: 10.13188/2373-1044.1000019.
NALDI, Luigi; DIPHOORN, Janouk. Seborrhoeic dermatitis of the scalp. BMJ clinical evidence, 2015, 2015: 1713.
BARAK-SHINAR, Deganit; GREEN, Lawrence J. Scalp seborrheic dermatitis and dandruff therapy using a herbal and zinc pyrithione-based therapy of shampoo and scalp lotion. The Journal of clinical and aesthetic dermatology, 2018, 11.1: 26.
GUPTA, Aditya K., et al. Seborrheic dermatitis. Dermatologic clinics, 2003, 21.3: 401-412.
DALL’OGLIO, Federica, et al. An overview of the diagnosis and management of seborrheic dermatitis. Clinical, cosmetic and investigational dermatology, 2022, 1537-1548.
SCHWARTZ, James R.; DEANGELIS, Yvonne M.; DAWSON, T. L. Dandruff and seborrheic dermatitis: a head scratcher. Practical modern hair science, 2012, 1: 389-413.
PETER, R. U.; RICHARZ‐BARTHAUER, U. Successful treatment and prophylaxis of scalp seborrhoeic dermatitis and dandruff with 2% ketoconazole shampoo: results of a multicentre, double‐blind, placebo‐controlled trial. British Journal of Dermatology, 1995, 132.3: 441-445.
SCHWARTZ, James R.; DAWSON JR, Thomas L. Dandruff and seborrheic dermatitis. In: Textbook of cosmetic dermatology. CRC Press, 2017. p. 260-270.