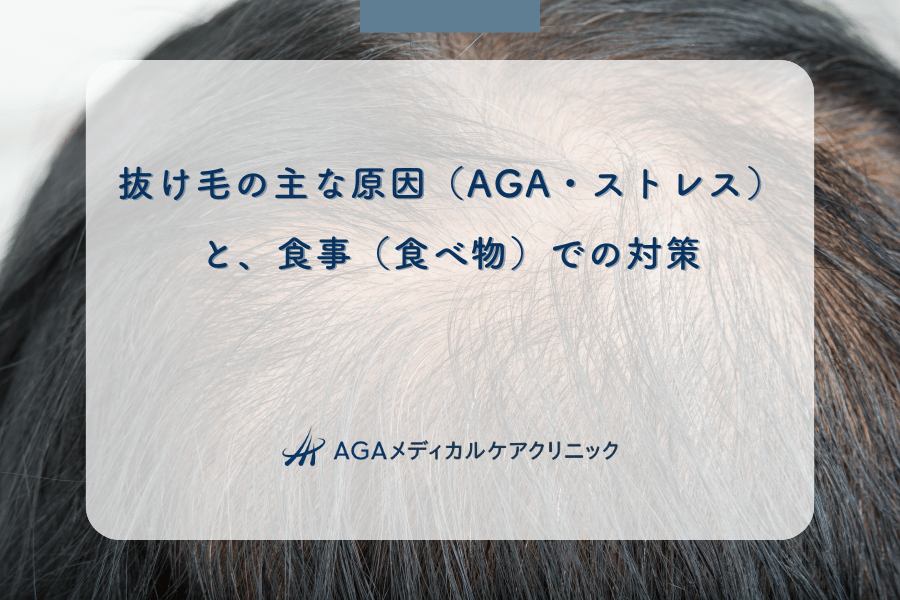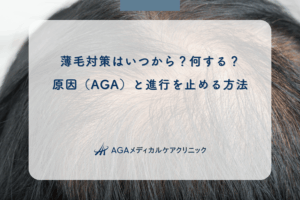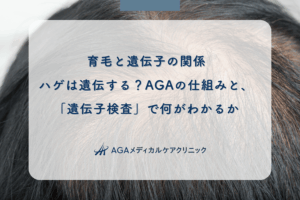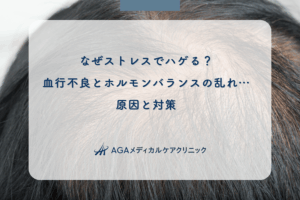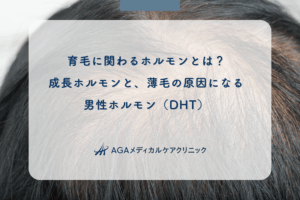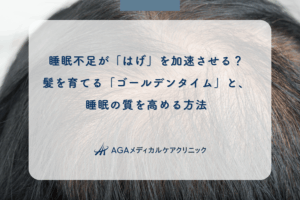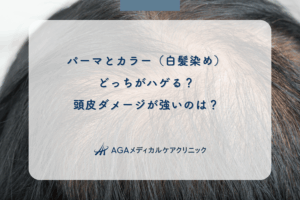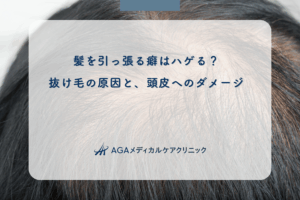抜け毛が気になり始めたけれど、何が原因で、どう対策すれば良いか分からない。そんな悩みを抱えていませんか。
抜け毛には、男性型脱毛症(AGA)や日々のストレスなど、複数の要因が複雑に関係しています。そして、その対策として今すぐ見直せるのが「食事」です。
私たちの体、そして髪の毛は、日々の食べ物から作られています。
この記事では、抜け毛を引き起こす主な原因であるAGAとストレスの仕組みを解説するとともに、髪の健康を支えるためにどのような食事(食べ物)を心がけるべきか、具体的な対策を詳しくご紹介します。
ご自身の生活習慣と照らし合わせながら、できることから始めてみましょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
抜け毛が起こる基本的な仕組み
抜け毛について考える前に、まずは髪の毛がどのように生え、成長し、そして抜け落ちるのか、その基本的な周期を理解することが重要です。この周期が乱れることが、抜け毛の増加に直結します。
正常なヘアサイクルとは
髪の毛1本1本には「ヘアサイクル(毛周期)」と呼ばれる寿命があります。これは、髪が成長する「成長期」、成長が止まる「退行期」、そして髪が抜け落ちる「休止期」の3つの期間を繰り返すことです。
健康な状態であれば、ほとんどの髪(約85〜90%)が成長期にあり、この期間は2年~6年ほど続きます。
その後、約2~3週間ほどの退行期を経て、約3~4ヶ月の休止期に入り、やがて新しい髪に押し出されるようにして自然に抜け落ちます。
ヘアサイクルの各段階
| 段階 | 期間の目安 | 髪の状態 |
|---|---|---|
| 成長期 | 2年~6年 | 毛母細胞が活発に分裂し、髪が太く長く成長する。 |
| 退行期 | 約2~3週間 | 毛母細胞の分裂が止まり、毛球が小さくなる。 |
| 休止期 | 約3~4ヶ月 | 髪の成長が完全に止まり、毛根が浅くなる。やがて抜け落ちる。 |
ヘアサイクルが乱れるとどうなるか
AGAやストレス、栄養不足などの影響を受けると、このヘアサイクルが乱れます。特に「成長期」が短くなることが大きな問題です。
通常なら数年間成長するはずの髪が、数ヶ月から1年程度で成長を終え、退行期・休止期へと移行してしまいます。
その結果、髪は十分に太く長く成長できず、細く短い「うぶ毛」のような状態で抜け落ちるようになります。これが「抜け毛が増えた」と感じる主な理由であり、薄毛の進行につながります。
抜け毛と薄毛の違い
抜け毛はヘアサイクルの一部であり、誰にでも毎日起こる自然な現象です。一般的に1日に50本から100本程度の抜け毛は正常範囲内とされます。
しかし、薄毛は、このヘアサイクルが乱れ、抜ける髪の量が増えたり、新しく生えてくる髪が細く弱くなったりすることで、全体の毛髪量が減少して地肌が見えやすくなる状態を指します。
つまり、抜け毛は「現象」であり、薄毛は「状態」を示すと言えます。抜け毛の質(細い、短い)や量(明らかに増えた)に変化が見られた場合、薄毛が進行し始めているサインかもしれません。
抜け毛の主な原因 AGA(男性型脱毛症)
男性の抜け毛・薄毛の悩みで最も多い原因が、AGA(Androgenetic Alopecia)、すなわち「男性型脱毛症」です。これは進行性の脱毛症であり、早めの理解と対策が求められます。
AGAとは何か
AGAは、思春期以降の男性に見られる進行性の脱毛症です。
特定のホルモンの影響によりヘアサイクルが乱れ、主に頭頂部(つむじ周り)や前頭部(生え際)から髪が細く短くなり、徐々に薄毛が進行していく特徴があります。
遺伝的な要因も関与すると考えられており、日本人男性の約3人に1人がAGAを発症するというデータもあります。
AGAは病気というより一種の体質的な現象ですが、放置すると薄毛はゆっくりと確実に進行していきます。
AGAを引き起こす男性ホルモン
AGAの主な原因物質は、「DHT(ジヒドロテストステロン)」と呼ばれる強力な男性ホルモンです。
体内の男性ホルモン「テストステロン」が、「5αリダクターゼ」という還元酵素と結びつくことでDHTが生成されます。
このDHTが、毛根にある「アンドロゲンレセプター(男性ホルモン受容体)」に結合すると、髪の成長を抑制する信号が出され、髪の成長期が極端に短くなってしまいます。
結果として、髪が太く成長する前に抜け落ちてしまい、薄毛が目立つようになります。5αリダクターゼの活性度やアンドロゲンレセプターの感受性は遺伝的要素が強いと言われます。
AGAの進行パターン
AGAによる薄毛の進行パターンには個人差がありますが、一般的にいくつかの典型的な型が存在します。
これは「ハミルトン・ノーウッド分類」として知られており、自分がどのパターンに当てはまるかを知る目安になります。
生え際から後退していくタイプ、頭頂部から薄くなるタイプ、その両方が同時に進行するタイプなどがあります。
主なAGA進行パターン
| パターン | 特徴 | 主な進行部位 |
|---|---|---|
| M字型 | 前頭部の生え際(特にこめかみの上あたり)が後退していく。 | 前頭部・生え際 |
| O字型 | 頭頂部(つむじ周辺)から円形に薄くなっていく。 | 頭頂部 |
| U字型 (M+O型) | 生え際の後退と頭頂部の薄毛が同時に進行する。 | 前頭部・頭頂部 |
自分でできるAGAチェック
AGAは専門のクリニックで診断を受けるのが最も確実ですが、いくつかの兆候からセルフチェックも可能です。
例えば、「以前より生え際が後退した気がする」「つむじ周りの地肌が目立つようになった」「髪の毛にハリやコシがなくなり、細くなった」「抜け毛が細く短いものが多い」「家族(特に父方・母方の祖父)に薄毛の人がいる」といった点に複数当てはまる場合、AGAの可能性を考えてもよいでしょう。
気になる点があれば、一人で悩まず専門家に相談することをおすすめします。
抜け毛のもう一つの大きな原因 ストレス
AGAと並んで、抜け毛の大きな原因として挙げられるのが「ストレス」です。現代社会においてストレスを完全になくすことは困難ですが、過度なストレスは髪の健康に深刻な影響を及ぼします。
ストレスが髪に与える影響
精神的なプレッシャーや過労、睡眠不足などの肉体的なストレスは、自律神経やホルモンバランスを乱し、頭皮環境を悪化させる原因となります。
ストレスを感じると体は緊張状態になり、さまざまな防御反応を示します。
これが一時的なものであれば問題ありませんが、慢性的に続くと、髪の毛の成長に使うべきエネルギーや栄養が、生命維持に重要な他の器官へ優先的に回されるようになり、髪の健康が後回しにされてしまいます。
自律神経の乱れと血行不良
強いストレスがかかると、交感神経が優位な状態が続きます。交感神経は体を活動的・緊張状態にする働きがあり、血管を収縮させる作用があります。
頭皮の毛細血管が収縮すると、血行不良に陥ります。髪の毛を育てる毛母細胞は、血液から酸素や栄養素を受け取って活動しています。
そのため、頭皮の血行が悪くなると、毛母細胞に十分な栄養が届かなくなり、髪の成長が妨げられ、抜け毛や細毛の原因となります。
ホルモンバランスの乱れ
ストレスはホルモンバランスにも影響を与えます。過度なストレスは、副腎皮質から「コルチゾール」というストレスホルモンの分泌を促します。
コルチゾールの分泌が増えると、体はストレスに対抗しようとしますが、この状態が続くと、男性ホルモンの分泌バランスにも影響が及ぶことがあります。
ホルモンバランスが崩れると、皮脂の分泌が過剰になったり、ヘアサイクルが乱れたりして、抜け毛につながる可能性があります。
ストレスによる無意識の行動
ストレスを感じると、無意識のうちに頭を掻きむしったり、髪の毛を抜いたりする「抜毛症(トリコチロマニア)」を引き起こすこともあります。
また、ストレスから暴飲暴食に走ったり、睡眠不足になったりするなど、生活習慣の乱れにもつながりがちです。
これらの行動や習慣の乱れが、間接的に頭皮環境を悪化させ、抜け毛を助長するケースも少なくありません。
食事と抜け毛の深い関係
髪の毛は、私たちが毎日口にする食べ物から作られています。AGAやストレス対策と並行して、食生活を見直すことは、抜け毛対策の基本であり、非常に重要な取り組みです。
髪の毛は何からできているか
髪の毛の主成分は、「ケラチン」と呼ばれるタンパク質です。全体の約90%以上を占めています。このケラチンは、18種類のアミノ酸が結合してできています。
つまり、良質なタンパク質(アミノ酸)を食事から摂取しなければ、健康な髪の毛を作るための「材料」が不足してしまうことになります。
髪は「死んだ細胞」と言われることもありますが、それは頭皮から外に出ている部分のことであり、頭皮の下にある毛根部では活発に細胞分裂が行われ、髪が作られています。
栄養不足が引き起こす髪の問題
過度なダイエットや偏った食事により栄養が不足すると、体は生命維持に必要な臓器(脳や心臓など)へ優先的に栄養を送ります。
髪の毛は生命維持の観点からは優先度が低いため、栄養不足の影響が現れやすい部分です。
髪を作るためのタンパク質はもちろん、そのタンパク質の合成を助けるミネラルや、頭皮環境を整えるビタミンが不足すると、毛母細胞の働きが鈍くなります。
その結果、髪が細くなる、ツヤがなくなる、成長が遅くなる、そして抜け毛が増えるといった問題が引き起こされます。
偏った食生活のリスク
外食やコンビニ食、インスタント食品に頼りがちな食生活は、栄養バランスが偏りやすい典型例です。特に、脂質や糖質の過剰摂取は、頭皮環境に悪影響を与えます。
脂質を摂りすぎると、皮脂の分泌が過剰になり、毛穴が詰まりやすくなったり、脂漏性皮膚炎などの頭皮トラブルを引き起こしたりする原因になります。
過剰な糖質は、体内でタンパク質と結びついて「糖化」を引き起こし、頭皮の弾力性を奪い、老化を早める可能性も指摘されています。バランスの取れた食事が、いかに髪の健康にとって大切かがわかります。
髪の健康を支える重要な栄養素
健康な髪を育てるためには、特定の栄養素だけを摂取するのではなく、さまざまな栄養素をバランス良く摂ることが重要です。中でも特に意識したい、髪の成長に深く関わる栄養素を紹介します。
タンパク質 髪の主成分
前述の通り、髪の主成分はケラチンというタンパク質です。そのため、タンパク質が不足すると、髪の材料不足に直結します。
肉、魚、卵、大豆製品、乳製品などから良質なタンパク質をしっかり摂取することを心がけましょう。
タンパク質は一度に多く摂取しても体内に蓄積されにくいため、毎食コンスタントに取り入れることが理想です。
タンパク質を多く含む食品例
| 分類 | 主な食品 | 特徴 |
|---|---|---|
| 動物性タンパク質 | 肉(鶏ささみ、豚ヒレ)、魚(アジ、サケ)、卵 | 必須アミノ酸がバランス良く含まれる。脂質の摂りすぎに注意。 |
| 植物性タンパク質 | 大豆製品(豆腐、納豆)、豆類 | 脂質が少なくヘルシー。イソフラボンも同時に摂取できる。 |
亜鉛 ミネラルの重要性
亜鉛は、髪の主成分であるケラチンを合成する際に必要不可欠なミネラルです。
食事から摂取したタンパク質(アミノ酸)を、髪の毛(ケラチン)へと再構築する「工場」の稼働に必要な栄養素とイメージすると分かりやすいでしょう。
また、亜鉛はAGAの原因物質であるDHTを生成する5αリダクターゼの働きを抑制する可能性も研究されています。
亜鉛は体内で作ることができず、汗や尿と共に排出されやすいため、意識して摂取する必要があります。
亜鉛を多く含む食品例
| 食品名 | 100gあたりの亜鉛含有量(目安) | 調理のポイント |
|---|---|---|
| 牡蠣(生) | 約14.0mg | 生食または加熱して。レモン(ビタミンC)と相性が良い。 |
| 豚レバー | 約6.9mg | ニラなどビタミンAが豊富な野菜と炒めると良い。 |
| 牛肉(赤身) | 約4.0mg~6.0mg | 部位による。脂身の少ない部位を選ぶ。 |
ビタミン群 頭皮環境を整える
ビタミン群は、髪の成長を直接的に促すわけではありませんが、頭皮環境を健やかに保ち、タンパク質や亜鉛の働きをサポートする重要な役割を持っています。
特にビタミンB群(B2, B6)、ビタミンC、ビタミンEが重要です。ビタミンB2やB6は、皮脂の分泌をコントロールし、頭皮の新陳代謝を促します。
ビタミンCはコラーゲンの生成を助けて頭皮の弾力を保つほか、亜鉛の吸収を助けます。ビタミンEは強い抗酸化作用を持ち、血行を促進する働きがあります。
髪の健康に関わる主なビタミン
| ビタミン | 主な働き | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| ビタミンB2 | 皮脂の分泌調整、細胞の再生 | レバー、うなぎ、納豆、卵 |
| ビタミンB6 | タンパク質の代謝(ケラチン合成)を助ける | マグロ、カツオ、バナナ、鶏肉 |
| ビタミンE | 血行促進、抗酸化作用 | ナッツ類、アボカド、植物油 |
イソフラボン ホルモンバランスへの影響
大豆製品に含まれる「大豆イソフラボン」は、女性ホルモン(エストロゲン)と似た化学構造と働きを持つことで知られています。エストロゲンは髪の成長期を維持し、髪のハリやコシを保つ働きがあります。
イソフラボンを摂取することで、AGAの原因となる男性ホルモンの影響を相対的に和らげ、ヘアサイクルの維持に役立つ可能性が期待されています。
また、イソフラボンには5αリダクターゼの働きを阻害するという研究報告もあり、納豆や豆腐などを日常的に食事に取り入れることは、抜け毛対策として有効と考えられます。
抜け毛対策におすすめの食べ物と食生活
必要な栄養素がわかったところで、次にそれらをどのように日々の食事に取り入れるか、具体的な食べ物や食生活のポイントを見ていきましょう。
積極的に摂りたい食べ物
髪に良い栄養素をバランス良く含む、積極的に取り入れたい食品群です。これらを組み合わせて、日々の献立を考えてみましょう。
- 大豆製品(納豆、豆腐、豆乳)
- 青魚(サバ、イワシ、アジ)
- 緑黄色野菜(ほうれん草、ブロッコリー、人参)
- レバー類(豚、鶏)
- 貝類(牡蠣、あさり)
- ナッツ類(アーモンド、くるみ)
- 海藻類(わかめ、ひじき)
避けた方が良い食べ物・飲み物
一方で、過剰に摂取すると頭皮環境を悪化させたり、栄養素の吸収を妨げたりする可能性があるため、摂取量に注意したい食べ物や飲み物もあります。
高脂質な食べ物(揚げ物、ジャンクフード、スナック菓子)は、皮脂の過剰分泌を招き、毛穴の詰まりや炎症の原因になります。
また、糖分の多いお菓子や清涼飲料水は、血糖値を急上昇させ、皮脂分泌を促すほか、ビタミンB群を大量に消費してしまいます。
アルコールの過剰摂取は、肝臓でアミノ酸の代謝を妨げたり、亜鉛の排出を促したりします。カフェインも適量なら問題ありませんが、摂りすぎは亜鉛の吸収を阻害する可能性が指摘されています。
これらを完全に断つ必要はありませんが、「摂りすぎない」意識が大切です。
バランスの良い食事のポイント
最も重要なのは「バランス」です。「髪に良いから」と特定の食品ばかり食べるのは逆効果です。理想的なのは、日本の伝統的な「一汁三菜」の食事スタイルです。
主食(ご飯)、主菜(魚や肉、大豆製品などタンパク質源)、副菜(野菜や海藻などビタミン・ミネラル源)、そして汁物(水分と塩分補給)を揃えることで、必要な栄養素を過不足なく摂取しやすくなります。
難しい場合は、まず「タンパク質+野菜」を毎食揃えることから意識してみましょう。
食事のタイミングと食べ方
食事のタイミングも髪の健康に関わります。特に夜遅い時間の食事、いわゆる「夜食」は避けるべきです。就寝中に胃腸が消化活動を行うと、睡眠の質が低下します。
髪の成長に重要な成長ホルモンは、深い睡眠中に最も多く分泌されます。睡眠の質が悪いと成長ホルモンの分泌が妨げられ、髪の成長にも悪影響が出ます。
また、夜はエネルギー消費が少ないため、食べたものが脂肪として蓄積されやすく、皮脂の増加にもつながります。夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。
食事以外でできる抜け毛対策
抜け毛の原因はAGAや食事だけではありません。食事改善とあわせて取り組むことで、より効果的な対策が期待できる生活習慣の見直しポイントを紹介します。
質の良い睡眠を確保する
髪の毛は寝ている間に成長します。特に、入眠後最初に訪れる深いノンレム睡眠時に「成長ホルモン」が最も多く分泌されます。この成長ホルモンが毛母細胞の分裂を促し、髪の成長を助けます。
睡眠時間が不足したり、眠りが浅かったりすると、成長ホルモンの分泌が減少し、髪の成長が妨げられます。
毎日6〜7時間程度の睡眠時間を確保し、就寝前はスマートフォンやPCの画面を避けてリラックスする時間を作るなど、睡眠の質を高める工夫をしましょう。
適度な運動で血行を促進
運動不足は全身の血行不良を招きます。頭皮も例外ではありません。
ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動を週に2〜3回程度取り入れると、全身の血流が良くなり、頭皮の毛細血管にも酸素と栄養が届きやすくなります。
また、適度な運動はストレス解消にも非常に効果的です。ストレスによる血管収縮を防ぐ意味でも、運動習慣は抜け毛対策に有効です。
正しいヘアケア方法
間違ったヘアケアは、頭皮環境を悪化させ、抜け毛を増やす原因になります。
洗浄力の強すぎるシャンプーで皮脂を取りすぎたり、逆に洗い残しがあったりすると、頭皮が乾燥したり、雑菌が繁殖したりします。
自分の肌質(乾燥肌、脂性肌など)に合ったシャンプーを選び、正しく洗うことが重要です。
正しいシャンプーのポイント
- 洗う前にブラッシングでホコリを落とす。
- まずはお湯だけでしっかり予洗いする。
- シャンプーは手のひらで泡立ててから髪につける。
- 指の腹で頭皮をマッサージするように優しく洗う。
- すすぎ残しがないよう、時間をかけてしっかり洗い流す。
また、洗髪後は濡れたまま放置せず、すぐにドライヤーで乾かしましょう。濡れた状態は雑菌が繁殖しやすいためです。
ストレスマネジメント
ストレスは自律神経を乱し、血行不良を引き起こす大きな原因です。現代社会でストレスをゼロにすることは難しいですが、自分なりの解消法を見つけて溜め込まないことが大切です。
趣味に没頭する時間を作る、ゆっくり入浴する、友人と話す、自然の中を散歩するなど、自分がリラックスできる方法を日常生活に取り入れましょう。
深刻な悩みを抱えている場合は、専門のカウンセラーに相談することも一つの手段です。
薄毛の基礎知識に戻る
よくある質問
最後に、抜け毛の原因や食事対策に関して、多くの方が疑問に思う点についてお答えします。
- 食事を変えたらすぐに髪は生えますか?
-
いいえ、すぐには効果は現れません。髪の毛にはヘアサイクルがあり、今生えている髪は数ヶ月から数年前に作られ始めたものです。
食事改善の効果は、これから新しく生えてくる髪や、現在成長期にある髪の健康状態をサポートするものです。
頭皮環境や体質が改善され、その変化が髪に現れるまでには、最低でも3ヶ月から6ヶ月程度の期間が必要です。焦らず、まずは健康的な食生活を「続ける」ことを目標にしてください。
- サプリメントで栄養を補うのはどうですか?
-
栄養は基本的に食事からバランス良く摂取するのが理想です。しかし、忙しい現代人にとって、毎日完璧な食事を用意するのは難しい場合もあります。
そのような時に、不足しがちな栄養素(特に亜鉛やビタミンなど)をサプリメントで補うことは有効な選択肢の一つです。ただし、サプリメントはあくまで「補助」です。
食事を疎かにしてサプリメントに頼るのは本末転倒です。また、特定の栄養素の過剰摂取はかえって体調を崩す原因にもなるため、摂取量を守って利用することが重要です。
不安な場合は医師や薬剤師に相談しましょう。
- 育毛剤と食事改善はどちらが重要ですか?
-
どちらか一方ではなく、両方とも重要です。例えるなら、食事改善は「土壌を豊かにする」こと、育毛剤の使用は「土壌に肥料を与える」ことに似ています。
AGAなどが原因でヘアサイクルが乱れている場合、育毛剤などで外から働きかけることは有効な対策です。
しかし、土壌である体(頭皮)が栄養不足では、いくら肥料を与えても健康な作物が育ちにくいように、髪の材料となる栄養が不足していては育毛剤の効果も十分に発揮されません。
体の内側からのケア(食事・生活習慣)と、外側からのケア(育毛剤・ヘアケア)を両立させることが、抜け毛対策には最も効果的です。
- 抜け毛が減らない場合、どうすればよいですか?
-
食事や睡眠、運動などの生活習慣を見直しても抜け毛の減少が見られない、あるいは薄毛が進行していると感じる場合は、AGA(男性型脱毛症)が強く関わっている可能性があります。
AGAは進行性のため、セルフケアだけでは進行を止めることが困難なケースが多くあります。
抜け毛の原因を正確に特定するためにも、皮膚科やAGA専門のクリニックなど、髪の毛の専門家に相談することを強く推奨します。
専門家の診断のもと、ご自身の状態に合った適切な対策を講じることが、悩み解決への一番の近道となります。
Reference
GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.
RAJENDRASINGH, J. R. Role of non-androgenic factors in hair loss and hair regrowth. J Cosmo Trichol, 2017, 3.2: 118.
WANG, Ruilong, et al. Micronutrients and Androgenetic Alopecia: A Systematic Review. Molecular Nutrition & Food Research, 2024, 68.22: 2400652.
GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.
RAJPUT, Rajendrasingh. A scientific hypothesis on the role of nutritional supplements for effective management of hair loss and promoting hair regrowth. J Nutrition Health Food Sci, 2018, 6.3: 1-11.
RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.
PHAM, Christine T., et al. The role of diet as an adjuvant treatment in scarring and nonscarring alopecia. Skin appendage disorders, 2020, 6.2: 88-96.
NATARELLI, Nicole; GAHOONIA, Nimrit; SIVAMANI, Raja K. Integrative and mechanistic approach to the hair growth cycle and hair loss. Journal of clinical medicine, 2023, 12.3: 893.
GOMES, Nuno; SILVA, Nuno; TEIXEIRA, Beatriz. Assessing the relationship between dietary factors and hair health: A systematic review. Nutrition and Health, 2025, 02601060251367206.
PENG, Lin, et al. Unhealthy diet and lifestyle factors linked to female androgenetic alopecia: a community-based study from Jidong study, China. BMC Public Health, 2025, 25.1: 606.