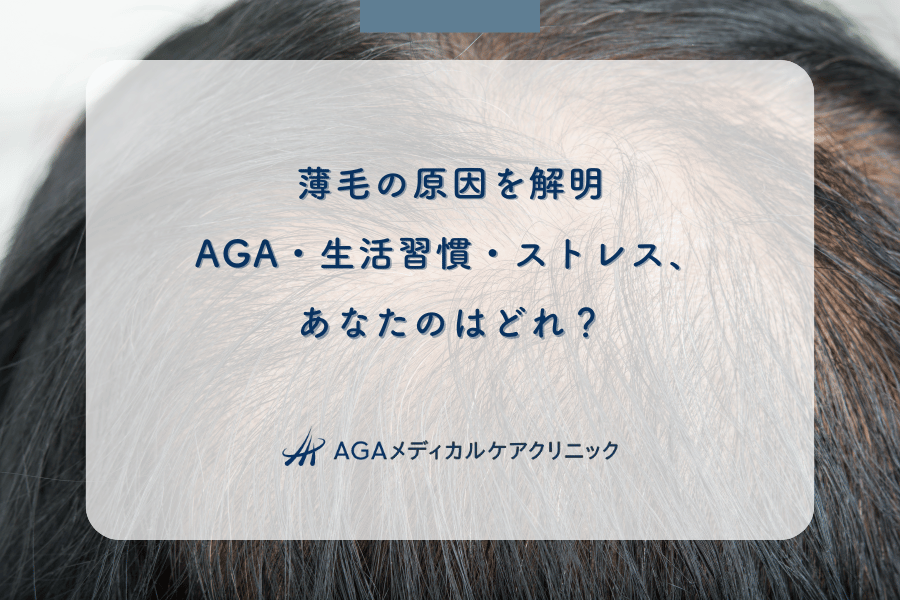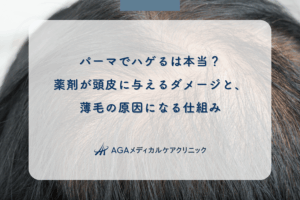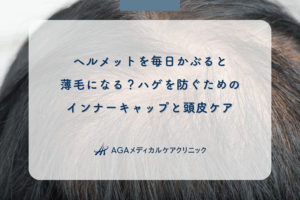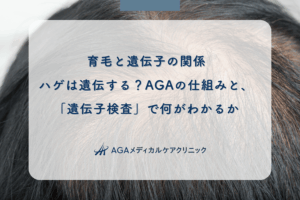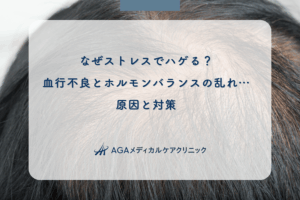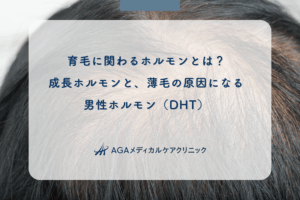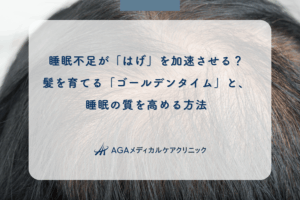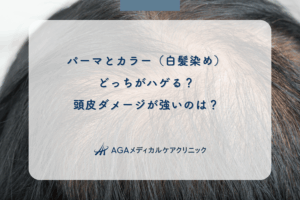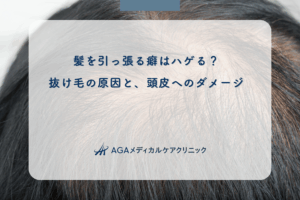「最近、抜け毛が増えた気がする」「髪のボリュームが減ってきた」と感じていませんか。薄毛の悩みは非常にデリケートでありながら、多くの男性が抱える問題です。
しかし、その原因は一つではありません。
男性型脱毛症(AGA)のような遺伝的要因から、日々の食事や睡眠といった生活習慣、さらには精神的なストレスまで、様々な要因が複雑に絡み合っています。
この記事では、薄毛を引き起こす主な原因を深く掘り下げ、あなたがどのタイプに当てはまる可能性があるのかを解明する手助けをします。
原因を知ることが、適切な対策への第一歩です。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
薄毛の悩み、まずは原因を知ることから
薄毛や抜け毛の悩みは、多くの人にとって深刻な問題です。鏡を見るたびに気になる、他人の目が気になるなど、精神的な負担を感じることも少なくありません。
しかし、ただ悩んでいるだけでは状況は改善しません。まずは、なぜ薄毛が進行するのか、その根本的な原因を理解することが大切です。
そもそも「薄毛」とはどのような状態か
一般的に「薄毛」とは、髪の毛が細くなったり、抜け毛が増えたりすることによって、頭皮が透けて見える状態を指します。
医学的には、毛髪の密度が低下したり、一本一本の毛髪が軟毛化(細く短くなる)したりする状態を意味します。
単に抜け毛が多いだけでなく、新しく生えてくる髪が十分に育たないことも薄毛の進行に関係します。
なぜ薄毛の原因を知ることが重要なのか
薄毛の原因は人によって様々です。遺伝的な要因が強い場合もあれば、生活習慣の乱れが主な原因である場合もあります。原因が異なれば、当然、取るべき対策も異なります。
例えば、AGA(男性型脱毛症)が原因であるにもかかわらず、食生活の改善だけを行っても、十分な効果は期待しにくいでしょう。
自分の薄毛の原因を正しく把握することで、遠回りをせず、自分に合った効果的な対策を見つけることができます。これが、原因を知る最大の理由です。
この記事で解明する主な薄毛の原因
薄毛の原因は多岐にわたりますが、特に男性の薄毛において関連が深いとされる主な原因は存在します。
この記事では、それらの主要な原因を「AGA(男性型脱毛症)」「生活習慣の乱れ」「ストレス」という3つの大きな柱に分けて詳しく解説します。
さらに、これらと密接に関連する「頭皮環境の悪化」や「加齢による変化」についても掘り下げます。あなたの悩みの背景に何が隠れているのか、一緒に探っていきましょう。
あなたの薄毛はAGA(男性型脱毛症)かもしれない
男性の薄毛の原因として最も多く、そして最もよく知られているのが「AGA(Androgenetic Alopecia)」、すなわち男性型脱毛症です。
もしあなたが成人男性で、特定のパターンで薄毛が進行していると感じるなら、AGAを疑う必要があります。
AGAとは何か? その特徴と進行パターン
AGAは、思春期以降の男性に見られる進行性の脱毛症です。遺伝的要因と男性ホルモンの影響が主な原因と考えられています。特徴的なのは、薄毛の進行パターンです。
多くの場尚、額の生え際が後退していく「M字型」や、頭頂部が薄くなる「O字型」、あるいはその両方が同時に進行する「U字型」など、特定の部位から薄毛が進行する傾向があります。
AGAの主なサイン
AGAが疑われる場合、以下のようなサインに注意しましょう。これらはAGAの初期段階から見られることがある特徴です。
- 抜け毛に細く短い毛が増えた
- 髪のハリやコシがなくなった
- 生え際が以前より後退した
- 頭頂部の地肌が目立つようになった
AGAを引き起こす男性ホルモン(DHT)
AGAの直接的な引き金となるのは、「ジヒドロテストステロン(DHT)」と呼ばれる強力な男性ホルモンです。
体内の男性ホルモン「テストステロン」が、「5αリダクターゼ」という酵素と結びつくことでDHTが生成されます。
このDHTが、毛根にある受容体(アンドロゲンレセプター)と結合すると、毛髪の成長期を短縮させる脱毛シグナルが発生します。
その結果、髪が太く長く成長する前に抜け落ちてしまい、徐々に薄毛が進行します。
AGAは遺伝すると聞くけれど本当か
AGAの発症には遺伝的要因が強く関与していることが分かっています。具体的には、「5αリダクターゼの活性度」と「アンドロゲンレセプターの感受性」という2つの遺伝的素因が影響します。
5αリダクターゼが活性しやすい体質(DHTが作られやすい)や、アンドロゲンレセプターがDHTに反応しやすい体質(脱毛シグナルを受け取りやすい)は、親から子へと遺伝する可能性があります。
特に母方の家系から受け継がれやすいとも言われますが、父方からも影響を受けるため、一概には言えません。
AGAのセルフチェック方法
自分がAGAかどうかを簡易的にチェックする方法があります。まずは自分の薄毛の進行パターンを確認しましょう。前述の「M字型」や「O字型」に当てはまるかを見ます。
次に、家族歴を確認します。父方、母方ともに、祖父や父、叔父などに薄毛の人がいるかどうか。これらに当てはまる場合、AGAである可能性は高まります。
また、抜け毛の状態も重要です。太く長い毛だけでなく、細く短い毛が多く抜けている場合もAGAのサインと考えられます。
ただし、これらはあくまで目安であり、正確な診断は専門の医療機関で行う必要があります。
AGAの原因について詳しく見る
髪が薄くなる理由は?男性の薄毛(AGA)の原因と、今すぐできる予防法
生活習慣の乱れが髪を弱らせる
AGAのような遺伝的要因だけでなく、日々の生活習慣も髪の健康に大きな影響を与えます。不規則な生活や栄養バランスの偏りは、頭皮環境を悪化させ、髪の成長を妨げる原因となります。
AGAの素因があったとしても、生活習慣が良ければ進行を遅らせる可能性があり、逆に素因がなくても生活習慣の乱れだけで薄毛が目立つこともあります。
食生活と髪の健康
私たちの体は、食べたものから作られています。髪の毛も例外ではありません。髪の主成分は「ケラチン」というタンパク質です。
健康な髪を育てるためには、バランスの取れた食事が不可欠です。
髪に必要な栄養素
特に髪の成長に重要とされる栄養素があります。これらを意識的に摂取することが大切です。
- タンパク質(ケラチンの材料)
- 亜鉛(ケラチンの合成を助ける)
- ビタミン類(頭皮環境を整え、血行を促進する)
避けるべき食習慣
逆に、以下のような食習慣は頭皮環境を悪化させ、薄毛の原因となる可能性があります。高脂肪・高カロリーな食事は、皮脂の過剰分泌を招き、毛穴を詰まらせる原因になります。
また、過度な飲酒は、髪の生成に必要なアミノ酸やビタミンを消費してしまいます。塩分や糖分の過剰摂取も血行不良を招くため注意が必要です。
睡眠不足が頭皮環境に与える影響
睡眠は、日中に受けた体のダメージを修復し、成長ホルモンを分泌する重要な時間です。髪の毛も、この睡眠中に成長します。睡眠不足が続くと、成長ホルモンの分泌が減少し、髪の成長が妨げられます。
また、自律神経のバランスが乱れ、頭皮の血行不良を引き起こすこともあります。血行が悪くなると、髪の成長に必要な栄養素が毛根まで届きにくくなり、結果として薄毛の原因となります。
最低でも6時間、できれば7〜8時間の質の良い睡眠を確保するよう心がけましょう。
ホルモンについて詳しく見る
育毛に関わるホルモンとは?成長ホルモンと、薄毛の原因になる男性ホルモン(DHT)
運動不足と血行不良の関係
デスクワーク中心の生活などで運動不足になると、全身の血流が悪くなりがちです。特に、心臓から遠い頭頂部は血行不良の影響を受けやすい部位です。
頭皮の血流が滞ると、毛母細胞の活動が低下し、健康な髪が育ちにくくなります。
適度な運動、例えばウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は、全身の血行を促進し、ストレス解消にも役立つため、薄毛対策としても有効です。
日々の生活の中に、意識的に運動を取り入れることが重要です。
ストレス社会が招く薄毛のリスク
現代社会は「ストレス社会」とも呼ばれ、仕事や人間関係、将来への不安など、多くの人が何らかのストレスを抱えています。この精神的な負担が、実は髪の健康にも深刻な影響を及ぼすことがあります。
AGAや生活習慣とは別に、ストレスが薄毛の直接的な原因、あるいは悪化させる要因となるのです。
ストレスが薄毛を引き起こす流れ
人が強いストレスを感じると、体は緊張状態(交感神経が優位な状態)になります。この状態が続くと、自律神経のバランスが崩れます。
自律神経は、血管の収縮や拡張、ホルモン分泌などをコントロールする重要な役割を担っています。バランスが崩れると、血管が収縮し、特に末端である頭皮への血流が著しく低下します。
これにより、毛根に十分な栄養や酸素が供給されなくなり、髪の成長が阻害され、抜け毛や薄毛を引き起こします。
精神的ストレスと身体的ストレス
ストレスには、職場のプレッシャーや家庭内の悩みといった「精神的ストレス」の他に、過労、睡眠不足、不規則な生活、病気などによる「身体的ストレス」もあります。
どちらのストレスも、自律神経やホルモンバランスの乱れを引き起こし、薄毛の原因となり得ます。自分が今どのようなストレスを感じているのかを認識し、それに対処することが大切です。
特に、自覚しにくい身体的ストレスにも目を向ける必要があります。
ストレスによる頭皮への具体的な影響
ストレスは、単に血行を悪くするだけではありません。頭皮環境に対しても様々な悪影響を及ぼします。
ストレスによる血行不良
前述の通り、ストレスによる交感神経の緊張は、頭皮の毛細血管を収縮させます。毛細血管は髪の毛に栄養を送る唯一のルートです。
このルートが細くなれば、毛母細胞は栄養失調状態に陥り、健康な髪を作れなくなります。これが「ストレス性脱毛症」や、AGAの進行を早める一因となります。
ストレスによる皮脂の過剰分泌
ストレスはホルモンバランスにも影響を与え、男性ホルモンの分泌を活発にさせることがあります。
男性ホルモンは皮脂腺の働きを活発にする作用があるため、ストレスによって頭皮の皮脂が過剰に分泌されることがあります。
過剰な皮脂は、毛穴を詰まらせたり、雑菌の繁殖を招いたりして、頭皮環境を悪化させ、抜け毛の原因となります。
頭皮環境の悪化も薄毛の引き金に
AGA、生活習慣、ストレスといった大きな原因に加え、直接的に髪の土壌である「頭皮環境」の悪化も、薄毛や抜け毛の重大な原因となります。
畑が荒れれば作物が育たないように、頭皮の状態が悪ければ健康な髪は育ちません。これまでの原因とも密接に関連していますが、ここでは特に頭皮ケアの側面に焦点を当てます。
間違ったヘアケアが頭皮を傷つける
良かれと思って行っている毎日のヘアケアが、実は頭皮にダメージを与えているケースは少なくありません。
例えば、洗浄力の強すぎるシャンプーの使用は、頭皮に必要な皮脂まで奪い去り、乾燥やバリア機能の低下を招きます。逆に、すすぎ残しは毛穴詰まりの原因になります。
また、頭皮を清潔にしようと爪を立ててゴシゴシ洗う行為は、頭皮を傷つけ炎症を引き起こす原因となります。
自分の頭皮タイプに合ったシャンプーを選び、指の腹で優しくマッサージするように洗うことが重要です。
皮脂の過剰分泌と毛穴の詰まり
ストレスや食生活の乱れ、ホルモンバランスの影響で皮脂が過剰に分泌されると、古い角質やホコリと混ざり合い、「角栓」となって毛穴を塞いでしまいます。
毛穴が詰まると、髪の正常な成長が妨げられるだけでなく、皮脂を栄養源とする雑菌(マラセチア菌など)が繁殖しやすくなります。
これにより「脂漏性皮膚炎」などを発症し、炎症やかゆみ、抜け毛を伴うこともあります。適切な洗髪で頭皮を清潔に保つことが予防につながります。
頭皮の乾燥とかゆみ、フケ問題
皮脂の過剰分泌とは逆に、頭皮の乾燥も大きな問題です。洗浄力の強すぎるシャンプーや、空気の乾燥、加齢などによって頭皮が乾燥すると、角質層のバリア機能が低下します。
すると、外部からのわずかな刺激にも敏感に反応し、かゆみや炎症を引き起こしやすくなります。また、頭皮のターンオーバーが乱れ、「乾性フケ」が発生することもあります。
かゆみで頭皮を掻きむしると、さらに頭皮環境が悪化するという悪循環に陥ります。
頭皮タイプ別ケアのポイント
自分の頭皮がどのタイプなのかを理解し、それに合ったケアを選ぶことが大切です。
| 頭皮タイプ | 特徴 | ケアのポイント |
|---|---|---|
| 脂性肌(オイリー) | 洗髪後、半日程度でベタつく。フケが湿っぽい。 | 洗浄力はありつつも、保湿成分も配合されたシャンプーを選ぶ。すすぎを徹底する。 |
| 乾燥肌(ドライ) | 洗髪後につっぱり感がある。フケがカサカサしている。 | アミノ酸系など洗浄力がマイルドなシャンプーを選び、保湿ローションなどで潤いを補給する。 |
| 混合肌 | Tゾーンはベタつくが、他は乾燥するなど部位による差がある。 | 基本は乾燥肌ケアに準じ、ベタつきが気になる部分のすすぎを丁寧に行う。 |
年齢と共に変化する髪と頭皮
薄毛の原因として、これまで述べてきた要因に加えて「加齢」も無視できません。年齢を重ねることは自然なことですが、それに伴い体には様々な変化が現れます。
髪と頭皮も例外ではなく、加齢による変化が薄毛の進行に影響を与えることがあります。
加齢による毛周期(ヘアサイクル)の変化
髪の毛には「毛周期(ヘアサイクル)」と呼ばれる、成長、退行、休止という一連のサイクルがあります。一本一本の髪がこのサイクルを繰り返しています。
健康な状態では、髪の多くが「成長期」(通常2〜6年)にありますが、加齢と共にこの成長期が短くなる傾向があります。
成長期が短くなると、髪が十分に太く長く成長する前に「退行期」「休止期」へと移行してしまいます。その結果、細く短い毛が増え、全体のボリュームが減少し、薄毛と感じるようになります。
ヘアサイクルについて詳しく見る
髪が生える仕組みとは?ヘアサイクル(毛周期)と、発毛を促す方法
加齢と血流低下の関係
年齢を重ねると、全身の血管が徐々に硬くなり、血流が悪化しやすくなります。これは「動脈硬化」などとも関連しますが、そこまで深刻な状態でなくとも、毛細血管の機能は低下しがちです。
特に頭皮は毛細血管が張り巡らされている場所であり、加齢による血流低下の影響を受けやすい部位です。
血流が低下すれば、毛根にある毛母細胞に送られる栄養や酸素が減少し、細胞の活動が鈍くなります。これが、加齢による薄毛や白髪の一因となります。
50代、60代で特に注意すべき点
50代、60代になると、多くの方がAGAの進行に加えて、加齢によるこれらの変化を実感し始めます。
この年代では、男性ホルモンの影響だけでなく、全体的な髪のボリュームダウンや、髪質の変化(ハリ・コシの低下)が顕著になることが多いです。
対策としては、AGAへのアプローチと同時に、頭皮の血行を促進するマッサージや、バランスの良い食事、適度な運動を継続し、全身の健康を維持することが、髪の健康を保つためにもより一層重要になります。
薄毛の原因別に見る対策アプローチ
これまで見てきたように、薄毛の原因は一つではありません。AGA、生活習慣、ストレス、頭皮環境、加齢など、様々な要因が絡み合っています。
したがって、効果的な対策を行うためには、自分の主な原因を推測し、それに合ったアプローチを選ぶことが重要です。ここでは、主な原因別に取りうる対策を紹介します。
AGAが疑われる場合の対策
生え際の後退や頭頂部の薄毛など、AGA特有のパターンが見られる場合は、セルフケアだけでの改善は難しいことが多いです。AGAは進行性のため、早めの対策が鍵となります。
主な対策には、医療機関での相談や、育毛剤の使用があります。
AGA対策の選択肢
AGAが疑われる場合、どのような選択肢があるのかをまとめます。
| 対策 | 主な内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 専門機関への相談 | 医師による診断と、必要に応じた内服薬や外用薬の処方。 | 原因(DHT)に直接アプローチする方法。医学的根拠に基づいた対策が可能。 |
| 育毛剤(医薬部外品) | 頭皮環境を整え、血行を促進し、毛髪の成長をサポートする成分を含む。 | 主に「抜け毛予防」や「育毛促進」。ドラッグストアなどで購入可能。 |
| 発毛剤(第1類医薬品) | 毛母細胞に直接働きかけ、「発毛」を促す成分(ミノキシジルなど)を含む。 | 「新しい髪を生やす」ことを目的とする。薬剤師のいる店舗や医療機関で扱う。 |
生活習慣の改善でできること
薄毛の原因が生活習慣の乱れにある場合、またはAGAであってもその進行を早めないためには、日々の生活を見直すことが基本であり、非常に重要です。
特に「食事」「睡眠」「運動」の3つの柱を整えましょう。
食生活の見直しポイント
健康な髪を育てるための食事のポイントです。
| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料。 | 肉類、魚介類、卵、大豆製品、乳製品 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助け、毛髪の成長を促す。 | 牡蠣、レバー、牛肉(赤身)、チーズ |
| ビタミンB群 | 頭皮の代謝を助け、皮脂バランスを整える。 | 豚肉、レバー、うなぎ、マグロ、納豆 |
質の良い睡眠のために
髪の成長を促す成長ホルモンは、深い睡眠時に多く分泌されます。質の良い睡眠を確保するために、以下の点を意識しましょう。
| 行動 | 理由 |
|---|---|
| 就寝1〜2時間前に入浴する | 一時的に体温を上げ、その後下がることで自然な眠気を誘う。 |
| 就寝前のスマホ・PC操作を控える | ブルーライトが脳を覚醒させ、睡眠ホルモン(メラトニン)の分泌を妨げる。 |
| カフェイン・アルコールの摂取を控える | カフェインは覚醒作用があり、アルコールは眠りを浅くする。 |
ストレスと上手に付き合う方法
ストレスをゼロにすることは困難ですが、溜め込まずに上手に発散する方法を見つけることが大切です。まずは自分が何にストレスを感じているかを認識しましょう。
その上で、自分に合ったリラックス方法を実践します。例えば、趣味に没頭する時間を作る、軽い運動で汗を流す、ゆっくりと入浴する、信頼できる人と話すなどが挙げられます。
また、深呼吸や瞑想なども、自律神経のバランスを整えるのに役立ちます。
頭皮環境を整えるヘアケア
健康な髪は、健康な頭皮から生まれます。日々のシャンプー方法を見直すだけでも、頭皮環境は大きく改善できます。
正しいシャンプーの手順
頭皮を傷つけず、汚れをしっかり落とすための手順です。
| 手順 | ポイント |
|---|---|
| ブラッシング | 洗髪前に髪のもつれを解き、ホコリや汚れを浮かす。 |
| 予洗い(湯洗い) | シャンプー前にぬるま湯(38度程度)で頭皮と髪をしっかり濡らし、汚れの7割を落とす。 |
| シャンプー | 手のひらで泡立ててから、指の腹で頭皮をマッサージするように優しく洗う。(爪を立てない) |
| すすぎ | シャンプー剤が残らないよう、時間をかけて(洗いの2倍程度)しっかりすすぐ。 |
| 乾燥 | タオルドライ後、ドライヤーで頭皮を中心にしっかり乾かす。(雑菌の繁殖を防ぐ) |
Q&A
ここでは、薄毛の原因に関して多くの方が抱く疑問についてお答えします。
- 薄毛は治りますか?
-
薄毛の原因によります。AGA(男性型脱毛症)は進行性のため、何もしなければ薄毛は進んでいきますが、適切な対策(医療機関での相談や育毛剤・発毛剤の使用など)を早期に始めることで、進行を遅らせたり、毛髪の状態を改善したりすることは可能です。
生活習慣の乱れやストレスが主な原因である場合は、それらの要因を取り除くことで改善が期待できます。
ただし、「完治」というよりは「症状をコントロールし、改善する」という考え方が適切です。自己判断せず、気になる場合は専門家に相談することをお勧めします。
- 育毛剤と発毛剤の違いは何ですか?
-
目的と分類が異なります。「育毛剤」は、主に「医薬部外品」に分類され、今ある髪の毛を健康に育て、抜け毛を防ぐこと(育毛・脱毛予防)を目的としています。
頭皮環境を整えたり、血行を促進したりする成分が含まれています。
一方、「発毛剤」は、「第1類医薬品」に分類され、毛母細胞に働きかけて新しい髪の毛を生やすこと(発毛)を目的としています。
日本国内ではミノキシジルを配合した製品がこれにあたります。自分の目的が「予防」なのか「発毛」なのかによって選ぶものが変わります。
- 若くても薄毛になるのはなぜですか?
-
薄毛は中高年の悩みというイメージがあるかもしれませんが、AGA(男性型脱毛症)は早い人では思春期過ぎ、20代前半から発症することがあります。
これは遺伝的素因が強いためです。
また、若い世代でも、過度なダイエットによる栄養不足、就職や人間関係による強いストレス、不規則な生活による睡眠不足などが原因で、一時的に抜け毛が増えたり、薄毛が進行したりすることがあります。
若さが原因を一つに特定するものではなく、様々な要因を考慮する必要があります。
- 海藻類を食べると髪が増えるというのは本当ですか?
-
「ワカメや昆布などの海藻類が髪をフサフサにする」とよく言われますが、これは俗説の域を出ません。
海藻類にはミネラルや食物繊維が豊富に含まれており、これらは髪の健康維持に役立つ栄養素です。
しかし、海藻類だけを大量に食べたからといって、髪が新しく生えたり、薄毛が劇的に改善したりするという医学的根拠はありません。
髪の主成分はタンパク質です。海藻類も取り入れつつ、タンパク質やビタミン、亜鉛など、バランスの取れた食事を心がけることが最も重要です。
- 帽子をかぶると薄毛になりやすいですか?
-
帽子をかぶること自体が、直接的に薄毛の原因になるわけではありません。むしろ、帽子は紫外線から頭皮を守るというメリットがあります。ただし、注意点もあります。
長時間帽子をかぶり続けることで頭皮が蒸れると、雑菌が繁殖しやすい環境になります。また、サイズの合わないきつい帽子は、頭皮の血行を妨げる可能性があります。
帽子をかぶる際は、通気性の良いものを選び、室内では脱ぐ、汗をかいたら清潔に保つなど、頭皮を清潔で快適な状態に保つよう心がければ、問題ありません。
薄毛の基礎知識の記事
Reference
CASH. The psychosocial consequences of androgenetic alopecia: a review of the research literature. British Journal of Dermatology, 1999, 141.3: 398-405.
SAWANT, Neena, et al. Androgenetic alopecia: quality-of-life and associated lifestyle patterns. International journal of trichology, 2010, 2.2: 81-85.
CASH, Thomas F. The psychological effects of androgenetic alopecia in men. Journal of the American Academy of Dermatology, 1992, 26.6: 926-931.
AUKERMAN, Erica L.; JAFFERANY, Mohammad. The psychological consequences of androgenetic alopecia: A systematic review. Journal of Cosmetic Dermatology, 2023, 22.1: 89-95.
FRITH, Hannah; JANKOWSKI, Glen S. Psychosocial impact of androgenetic alopecia on men: A systematic review and meta-analysis. Psychology, Health & Medicine, 2024, 29.4: 822-842.
DANYAL, MUHAMMAD, et al. Impact of androgenetic alopecia on the psychological health of young men. Pakistan Journal of Medical and Health Sciences, 2018, 12.1: 406-410.
PAVASKAR, MAYURESH SHAMSUNDER, et al. Lifestyle Risk Factors in Male Androgenetic Alopecia: A Cross-sectional Study. Journal of Clinical & Diagnostic Research, 2025, 19.6.
STOUGH, Dow, et al. Psychological effect, pathophysiology, and management of androgenetic alopecia in men. In: Mayo Clinic Proceedings. Elsevier, 2005. p. 1316-1322.
MOHAMMED, Sherif. Psychological and Emotional Impacts of Androgenetic Alopecia on Adolescent and Young Adult Males: A Systematic Review. Available at SSRN 5557045, 2025.
CHENG, Yi, et al. Psychological stress impact neurotrophic factor levels in patients with androgenetic alopecia and correlated with disease progression. World journal of psychiatry, 2024, 14.10: 1437.