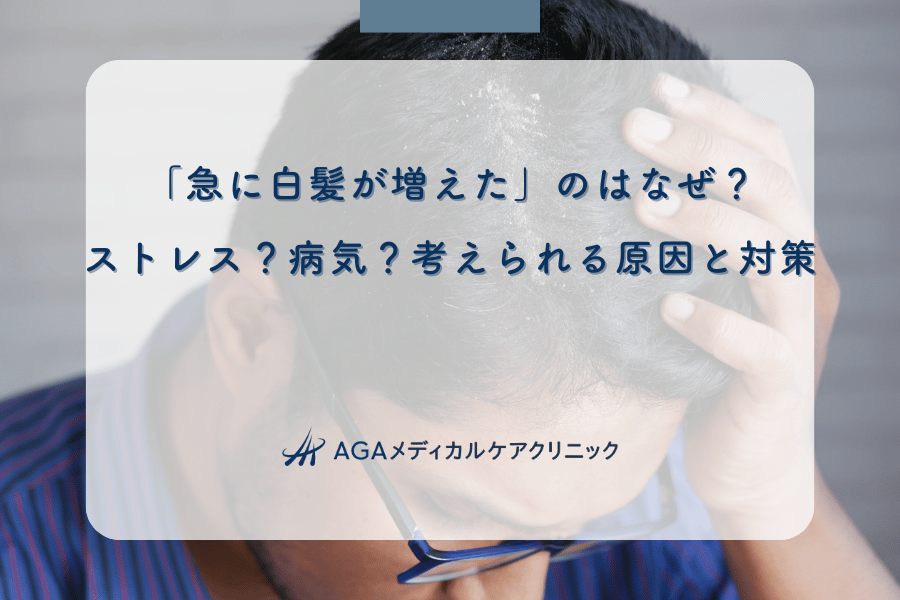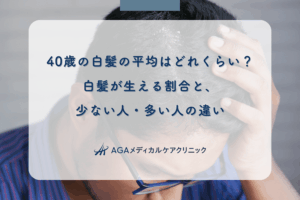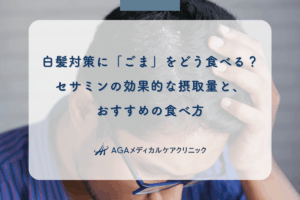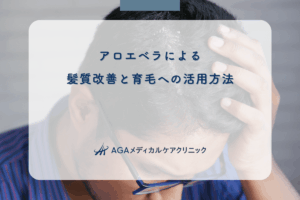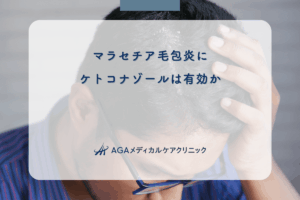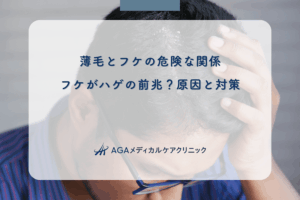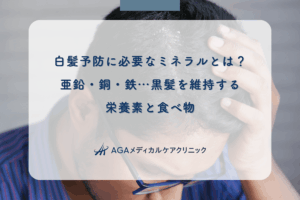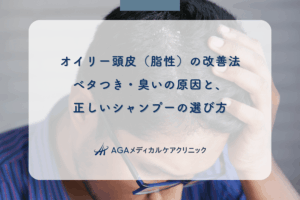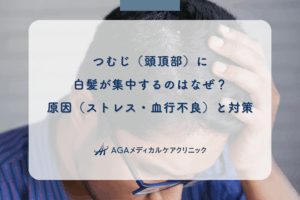鏡を見て「急に白髪が増えた」と感じ、驚きや不安を抱えていませんか。特に男性にとって、髪の変化は大きな悩みの一つです。
その原因はストレスだけなのか、あるいは何か注意すべき病気のサインではないかと心配になる方も多いでしょう。この記事では、急に白髪が増える背景にある様々な要因を丁寧に解説します。
白髪が発生する基本的な仕組みから、ストレスや生活習慣、栄養状態、そして考えられる病気の可能性まで、幅広く掘り下げます。
さらに、今日から始められる具体的な対策や、白髪と上手に付き合っていくためのヘアケア方法も紹介します。あなたの疑問や不安に寄り添い、適切な情報を提供します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
そもそも白髪はなぜ生えるのか
「急に増えた」と感じる前に、まずは白髪がどのようにして生えるのか、その基本的な仕組みを知ることが大切です。
髪の色が失われる背景を理解することで、不安が和らぐかもしれません。
髪の色が決まる仕組み
私たちの髪の毛は、毛根部にある「毛球」という場所で作られます。生まれたての髪の毛は、実はすべて白髪と同じく無色透明です。
この無色の髪の毛に色を与えているのが、「メラニン色素」と呼ばれる色素です。
メラニン色素には黒〜褐色系の「ユーメラニン」と、黄〜赤色系の「フェオメラニン」の2種類があり、この2つの色素の量やバランスによって、人それぞれの髪の色(黒髪、金髪、赤毛など)が決まります。
メラノサイトの役割とは
メラニン色素は、「メラノサイト(色素細胞)」という特定の細胞によって生成されます。
メラノサイトは毛球部に存在し、髪の毛が成長するのに合わせて、活発にメラニン色素を作り出し、髪の毛の内部(毛皮質)へと送り込みます。
この働きによって、髪の毛は根元から毛先まで色がついた状態で伸びていくのです。
メラニン色素が作られなくなると白髪になる
白髪は、何らかの理由でこのメラノサイトの働きが低下したり、メラノサイト自体が消失したりすることで発生します。
メラニン色素が生成されなくなると、新しく生えてくる髪の毛に色をつけることができません。その結果、色素の入っていない無色のままの髪の毛、すなわち「白髪」として生えてくるのです。
年齢による変化は自然なこと
一般的に、年齢を重ねると白髪が増えるのは、このメラノサイトの働きが徐々に衰えたり、色素幹細胞(メラノサイトの元となる細胞)が枯渇したりするためと考えられています。
これは自然な老化現象の一つであり、多くの人が経験することです。個人差はありますが、30代後半から白髪が出始め、年齢とともに増えていくのが平均的な傾向です。
ただし、何らかの理由でメラノサイトが機能を低すると、10代・20代であっても白髪が増えます。
若年性の白髪について詳しく見る
10代の白髪は治る?考えられる原因(ストレス・栄養不足)と対策、染める以外の対処法
20代男性の「白髪だらけ」はなぜ?若白髪の原因と対策|抜くのはNG?
「急に白髪が増えた」と感じる主な原因
年齢による自然な変化とは別に、「急に」白髪が増えたと感じる場合、いくつかの特定の要因が影響している可能性があります。
メラノサイトの活動が短期間で低下する背景を探ります。
メラノサイトの機能低下または消失
急激な白髪の増加は、毛根部のメラノサイトが何らかの強いダメージを受け、その機能が急停止したり、細胞自体が消失したりしたことを示唆しています。
これは一時的な場合もあれば、永続的な場合もあります。
特定のエリアに集中して白髪が増えた場合、その部分のメラノサイトに局所的な問題が起きた可能性も考えられます。
遺伝的要因の影響
白髪の生え始める時期や増え方には、遺伝的な要因が強く関与していることが知られています。両親や祖父母に若白髪の人が多い場合、自身も比較的早い段階から白髪が出やすい傾向があります。
「急に増えた」と感じる背景にも、もともと持っている遺伝的な素因が関係している可能性は否定できません。
栄養不足による影響
髪の毛やメラノサイトも、私たちが摂取する栄養素によって作られ、その活動を維持しています。
極端なダイエットや偏った食生活によって、メラニン色素の生成に必要な栄養素が不足すると、メラノサイトは正常に働くことができません。
特に、髪の毛の主成分であるタンパク質や、メラニンの原料となるチロシン、ミネラル(亜鉛や銅)、ビタミン類が不足すると、白髪の増加につながる可能性があります。
睡眠不足や不規則な生活
私たちの体は、睡眠中に成長ホルモンを分泌し、細胞の修復や再生を行います。頭皮や毛根部の細胞も例外ではありません。
睡眠不足が続いたり、夜更かしなどで生活リズムが乱れたりすると、自律神経のバランスが崩れやすくなります。
これにより、頭皮の血行が悪化し、毛根部に十分な栄養が届きにくくなることで、メラノサイトの活動が低下し、白髪が増える一因となることがあります。
ストレスは本当に白髪を増やすのか
「苦労すると白髪が増える」と昔から言われるように、ストレスと白髪の関係を気にする人は多いです。近年の研究では、その関係性が科学的にも少しずつ明らかになってきています。
ストレスと自律神経の関係
人間が強いストレスを感じると、交感神経が優位な状態(緊張・興奮状態)が続きます。
交感神経は血管を収縮させる働きがあるため、全身の血流、特に末端である頭皮の毛細血管の血流が悪化しやすくなります。
この状態が慢性化すると、毛根部への栄養供給が滞り、髪の成長や色素生成に悪影響を及ぼすと考えられます。
簡単なストレスセルフチェック
ご自身の最近の状態を振り返ってみましょう。当てはまるものが多いほど、ストレスが蓄積している可能性があります。
| 項目 | チェック(はい・いいえ) | 主な状態 |
|---|---|---|
| 睡眠 | 寝つきが悪い、または途中で目が覚める | 心身がリラックスできていない可能性 |
| 食欲 | 食欲がない、または食べ過ぎてしまう | 自律神経の乱れが消化器系に影響 |
| 気分 | イライラしやすい、または気分が落ち込む | 精神的な疲労の蓄積 |
| 身体 | 肩こり、頭痛、めまいなどが続く | 過度な緊張による身体的サイン |
| 集中力 | 仕事や趣味に集中できない | 脳の疲労やキャパシティオーバー |
血行不良が頭皮に与える影響
頭皮の血行不良は、メラノサイトにとって深刻な問題です。メラノサイトがメラニン色素を作るためには、血液から送られてくる十分な栄養素(アミノ酸、ミネラル、ビタミンなど)と酸素が必要です。
血流が滞ると、これらの供給が不足し、色素の生産ラインがストップしてしまうのです。その結果、新しく生える髪が白髪になる可能性があります。
ストレスによる色素幹細胞へのダメージ
最近の研究では、強いストレスが交感神経を過剰に興奮させ、その結果放出される神経伝達物質(ノルアドレナリン)が、毛包にある「色素幹細胞」を枯渇させてしまう可能性が指摘されています。
色素幹細胞はメラノサイトの供給源であるため、これが枯渇すると、将来的にメラノサイトを補充できなくなり、永続的な白髪につながる恐れがあるのです。
「急に増えた」という実感は、この現象が短期間で起きた結果かもしれません。
ストレス解消法の重要性
このように、ストレスは複数の経路で白髪の増加に関与している可能性があります。
もちろん、ストレスをゼロにすることは現代社会では難しいですが、自分に合った方法でストレスを上手に管理し、溜め込まないようにすることが重要です。
趣味の時間を持つ、適度な運動をする、リラックスできる時間を作るなど、意識的に心身を休ませる工夫をしましょう。
ストレスと白髪について詳しく見る
40代の「急な白髪」はストレスが原因?白髪を増やさないための生活習慣
白髪と関連が疑われる病気の可能性
「急に白髪が増えた」場合、多くは生活習慣やストレス、遺伝的要因によるものですが、ごく稀に特定の病気が背景にあることもあります。
過度な心配は不要ですが、知識として知っておくことも大切です。
自己免疫疾患の可能性
自己免疫疾患とは、本来体を守るはずの免疫システムが、自分自身の正常な細胞や組織を攻撃してしまう病気です。
一部の自己免疫疾患(例えば尋常性白斑など)では、免疫細胞がメラノサイトを攻撃対象としてしまい、その結果、皮膚の色が白く抜けたり、その部分に生える毛が白髪になったりすることがあります。
円形脱毛症でも、回復期に生えてくる髪が一時的に白髪になるケースが見られます。
甲状腺機能の異常
甲状腺は、体の新陳代謝を活発にするホルモンを分泌する器官です。
甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)や甲状腺機能低下症(橋本病など)といった甲状腺の病気では、新陳代謝のバランスが大きく崩れます。
この影響が毛髪にも及び、白髪の増加、脱毛、髪質の変化などを引き起こすことがあると報告されています。
栄養吸収障害を伴う疾患
例えば、胃腸の慢性的な疾患(悪性貧血や一部の消化器系疾患など)により、食事から特定の栄養素、特にビタミンB12などを正常に吸収できなくなる場合があります。
ビタミンB12はメラノサイトの正常な機能維持や、血液を作る上で重要な役割を果たします。このビタミンが極端に不足すると、白髪が増加する一因となり得ます。
白髪と関連が指摘されることのある主な状態
急激な白髪の増加とともに、以下のような他の症状が見られる場合は注意が必要です。
| 関連が指摘される状態 | 主な症状(白髪以外) | 考えられる影響 |
|---|---|---|
| 甲状腺機能の異常 | 極端な体重増減、動悸、倦怠感、むくみ | 新陳代謝の異常が毛母細胞やメラノサイトに影響 |
| 尋常性白斑 | 皮膚の一部が白く色が抜ける | メラノサイト自体が免疫系により攻撃される |
| 悪性貧血(ビタミンB12欠乏) | めまい、息切れ、手足のしびれ、倦怠感 | メラノサイトの機能低下、赤血球生成の障害 |
急激な変化は医療機関への相談も視野に
白髪の急増や脱毛だけでなく、上記のような明らかな体調不良(極端な倦怠感、体重の変化、皮膚の異常など)を伴う場合は、自己判断せずに内科や皮膚科などの医療機関を受診し、専門家に相談することを推奨します。
多くの場合、白髪は病気と直結しませんが、万が一の可能性を排除しておくことで、安心して対策に取り組むことができます。
生活習慣で見直すべきポイント
病的な原因が考えにくい場合、白髪の増加を食い止め、健康な髪を育むためには、日々の生活習慣を見直すことが非常に重要です。
特に頭皮の血行や自律神経のバランスに注目しましょう。
質の高い睡眠を確保する
睡眠は、日中に受けたダメージを修復し、細胞を再生させるためのゴールデンタイムです。
特に、午後10時から午前2時の間は成長ホルモンの分泌が活発になると言われています。メラノサイトを含む毛根部の細胞も、この時間に活発に働きます。
単に長く寝るだけでなく、深く質の高い睡眠をとることが大切です。
睡眠の質を高める工夫
- 就寝1〜2時間前に入浴し、体温を一度上げてから下げる
- 就寝前のスマートフォンやPCの使用を控える(ブルーライトを避ける)
- 寝室の温度や湿度、音、光などの環境を整える
定期的な運動で血行を促進
デスクワークが多いなど、体を動かす習慣が少ないと、全身の血行が悪くなりがちです。特に頭皮は心臓から遠い位置にあるため、血流が滞りやすい部位です。
ウォーキングやジョギング、ストレッチなどの有酸素運動を日常生活に取り入れることで、全身の血流が改善し、頭皮にも栄養素が行き渡りやすくなります。
運動はストレス解消にも役立ち、一石二鳥の効果が期待できます。
禁煙と適度な飲酒
喫煙は、白髪のリスクを高める要因の一つとして知られています。タバコに含まれるニコチンには強力な血管収縮作用があり、頭皮の毛細血管の血流を著しく悪化させます。
また、喫煙によって体内に大量の活性酸素が発生し、メラノサイトを含む細胞を酸化させ、老化を早める原因となります。白髪対策を考えるなら、禁煙は優先度の高い項目です。
また、過度な飲酒も体内でアルコールを分解する際にビタミンやミネラルを大量に消費するため、髪に必要な栄養素が不足しがちになります。飲酒は適量を心がけましょう。
頭皮マッサージの方法
頭皮の血行を直接的に促進する方法として、頭皮マッサージも有効です。硬くなった頭皮をほぐすことで、毛根部への血流をサポートします。
シャンプーのついでや、入浴後のリラックスした時間に行うのがおすすめです。
自宅でできる簡単頭皮マッサージ
指の腹を使い、爪を立てずに優しく行います。頭皮全体を動かすようなイメージで、気持ち良いと感じる強さで行ってください。
| ステップ | 方法 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 側頭部 | 両手の指の腹で、耳の上あたりを掴むように押さえ、円を描くようにほぐす。 | ゆっくりと圧をかけ、頭皮を動かす。 |
| 2. 前頭部〜頭頂部 | 生え際から頭頂部に向かって、指の腹でジグザグに動かしながら引き上げる。 | 血流を頭頂部に送るイメージで。 |
| 3. 後頭部 | 両手で後頭部を包み込むようにし、親指以外の4本指で襟足から頭頂部へほぐす。 | 首筋のコリもほぐすと効果的。 |
| 4. 仕上げ | 頭頂部にある「百会(ひゃくえ)」というツボを、中指の腹で心地よく押す。 | リラックスして深呼吸しながら行う。 |
食生活で意識したい栄養素
健康な髪とメラノサイトの働きを維持するためには、バランスの取れた食事が欠かせません。特に白髪との関連で注目される栄養素を意識的に摂取しましょう。
メラニン生成に必要な栄養素
メラニン色素を直接作り出すために必要な材料です。これらが不足すると、メラノサイトが働きたくても色素を作れません。
チロシン
メラニン色素の主原料となるアミノ酸(タンパク質の一種)です。チロシンは体内で合成されますが、原料となるフェニルアラニンとともに、食事からの摂取も重要です。
チーズや大豆製品、ナッツ類、魚介類、肉類などに多く含まれます。
銅
チロシンからメラニン色素を合成する際に働く酵素「チロシナーゼ」の活性に必要不可欠なミネラルです。銅が不足すると、チロシンがいくらあってもメラニン色素を効率よく作れません。
レバー、ナッツ類、甲殻類、大豆製品などに含まれます。
メラノサイトの働きを助ける栄養素
メラノサイトが正常に機能し、活発に活動するためにサポートする栄養素です。
亜鉛
亜鉛は、髪の毛の主成分であるケラチンタンパク質の合成に深く関わるミネラルです。また、新しい細胞が作られる際にも必要で、メラノサイトの維持にも関与します。
不足すると髪の成長自体が妨げられる可能性もあります。牡蠣、レバー、赤身肉、チーズ、ナッツ類に豊富です。
ビタミンB群(特にB12, B6)
ビタミンB群は、エネルギー代謝やタンパク質の合成を助ける重要な役割を担います。
特にビタミンB12は、メラノサイトの正常な機能や赤血球の生成に関与し、不足すると白髪や貧血の原因となることが知られています。
ビタミンB6はタンパク質の代謝を助け、健康な頭皮環境の維持に役立ちます。B12は貝類(しじみ、あさり)、レバー、魚類に、B6はマグロ、カツオ、バナナ、鶏肉などに多く含まれます。
白髪対策で注目したい栄養素と主な食材
これらの栄養素をバランスよく摂取することが、健康な髪を育む土台となります。
| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食材 |
|---|---|---|
| チロシン(アミノ酸) | メラニン色素の原料となる | チーズ、大豆製品、ナッツ、鶏肉、魚類 |
| 銅(ミネラル) | メラニン生成酵素の働きに必要 | レバー、牡蠣、ナッツ、大豆製品、甲殻類 |
| 亜鉛(ミネラル) | タンパク質合成、細胞分裂を助ける | 牡蠣、レバー、赤身肉、チーズ、ナッツ |
| ビタミンB12 | メラノサイトの機能維持、造血作用 | しじみ、あさり、レバー、さんま、さば |
| ビタミンB6 | タンパク質の代謝を助ける | マグロ、カツオ、レバー、鶏肉、バナナ |
抗酸化作用のある栄養素
体内で発生する「活性酸素」は、細胞を酸化させて老化を促進し、メラノサイトの働きを低下させる一因となります。
抗酸化作用のある栄養素を摂取し、活性酸素から細胞を守ることも重要です。
抗酸化作用を持つ主な栄養素
- ビタミンC(ピーマン、ブロッコリー、キウイフルーツなど)
- ビタミンE(ナッツ類、植物油、アボカドなど)
- ポリフェノール(緑黄色野菜、大豆製品、緑茶など)
バランスの取れた食事の重要性
特定の栄養素だけを偏って摂取しても、体はうまく機能しません。タンパク質、脂質、炭水化物の三大栄養素を基本に、ビタミン、ミネラルをまんべんなく摂取することが何よりも大切です。
主食、主菜、副菜を揃えたバランスの良い食事を一日三食とることを心がけましょう。
白髪との上手な付き合い方と対策
すでに増えてしまった白髪や、これからの予防のために、日常生活でできる具体的な対策と心構えを紹介します。頭皮環境を整えることが、育毛剤メディアの観点からも特に重要です。
白髪を抜くのはNG
目立つ白髪を見つけると、つい抜いてしまいたくなるかもしれませんが、これは避けるべきです。白髪を無理に抜くと、毛根やその周辺の頭皮にダメージを与え、炎症を引き起こす可能性があります。
さらに、同じ毛穴から次に生えてくる髪も白髪である可能性が高く、抜き続けることで毛穴自体がダメージを受け、将来的にその毛穴から髪が生えてこなくなる(脱毛につながる)リスクさえあります。
気になる場合は、根元近くでハサミでカットするようにしましょう。
白髪染めや白髪ぼかしの活用
増えてきた白髪が気になる場合、最も手軽な対策は「染める」ことです。
白髪染め(ヘアカラー)でしっかり染める方法のほか、最近では白髪を完全に隠すのではなく、白髪と黒髪をなじませて目立たなくする「白髪ぼかし」も人気です。
美容室で相談するほか、自宅で使えるトリートメントタイプや泡タイプのものもあります。
ただし、ヘアカラー剤は頭皮に刺激を与える可能性もあるため、使用方法を守り、肌が弱い人はパッチテストを行うなど注意が必要です。
白髪の主な対処法比較
ご自身のライフスタイルや白髪の量に合わせて、適切な方法を選びましょう。
| 対処法 | メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|---|
| 白髪染め(アルカリカラー) | 一度でしっかり染まる。色の選択肢が多い。 | 頭皮や髪へのダメージ。根元が伸びると目立つ。 |
| 白髪ぼかし | 自然な仕上がり。根元が伸びても目立ちにくい。 | 完全に染まらない。白髪の量が多いと不向きな場合も。 |
| ヘアマニキュア・カラートリートメント | 頭皮や髪へのダメージが少ない。 | 色持ちが短い(数日〜数週間)。汗や雨で色落ちしやすい。 |
| カットする | ダメージゼロ。手軽。 | 本数が多いと対応不可。短い白髪が立つことがある。 |
頭皮環境を整えるヘアケア
白髪対策だけでなく、薄毛や抜け毛の予防、そして健康な髪を育むためには、頭皮環境を清潔で健康な状態に保つことが非常に重要です。
毛穴の詰まりや血行不良は、髪の成長を妨げる大きな要因となります。
正しいシャンプーの方法
毎日のシャンプーは、頭皮の汚れを落とすだけでなく、頭皮環境を整える基本です。洗いすぎや洗い残しは、乾燥やかゆみ、フケの原因となります。
| ステップ | 手順 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 予洗い | シャンプー前にお湯で髪と頭皮をしっかり濡らす。 | これだけで汚れの7割は落ちると言われる。 |
| 2. 泡立て | シャンプーを手のひらでよく泡立ててから髪につける。 | 原液を直接頭皮につけない。 |
| 3. 洗う | 指の腹を使って、頭皮をマッサージするように優しく洗う。 | 爪を立てて頭皮を傷つけないように注意。 |
| 4. すすぎ | シャンプー剤が残らないよう、時間をかけて丁寧にすすぐ。 | 特に生え際や耳の後ろは残りやすい。 |
頭皮用美容液や育毛剤の活用
シャンプー後の清潔な頭皮に、頭皮用の保湿美容液や、血行促進・毛根活性化を目的とした育毛剤を使用することも、積極的な頭皮ケアとして有効です。
特に白髪が気になる方は、メラノサイトの活性化をサポートする成分や、抗酸化成分、血行促進成分が含まれた製品を選ぶのも一つの方法です。
育毛剤は、頭皮環境を整え、健康な髪が育つ土台作りをサポートするものです。白髪と同時に、髪のハリやコシ、ボリューム感が気になってきた男性には、日々のケアに取り入れることをおすすめします。
対策と目立たせない方法について詳しく見る
30代男性の「白髪だらけ」の悩み。原因と対策、目立たせない方法(白髪染め・髪型)
よくある質問
最後に、「急に白髪が増えた」と感じる方から多く寄せられる質問にお答えします。
- 一度白髪になった髪は黒髪に戻りますか?
-
原因によります。加齢や遺伝的要因、あるいは色素幹細胞が枯渇してしまったことによる白髪の場合、残念ながら黒髪に戻る可能性は低いと考えられています。
しかし、極度の栄養不足や強いストレス、特定の病気などが原因で一時的にメラノサイトの機能が低下していた場合は、その原因が解消されることで、再びメラニン色素が作られるようになり、黒髪が再生するケースも稀にあります。
- 白髪は予防できますか?
-
遺伝や加齢による白髪を完全に止めることは難しいですが、発生を遅らせたり、増加のスピードを緩やかにしたりするためにできることはあります。
本記事で紹介したような、バランスの取れた食事(特にミネラルやビタミン)、質の高い睡眠、適度な運動、ストレス管理、禁煙、そして良好な頭皮環境を保つヘアケアといった生活習慣の改善は、白髪の予防にもつながると期待できます。
- 特定の場所だけ白髪が増えるのはなぜですか?
-
特定の場所(例えば、分け目や生え際など)に白髪が集中する理由は、完全には解明されていません。
考えられる要因としては、その部分が特に紫外線を浴びやすい、あるいは無意識に触る癖などで物理的な刺激を受けやすい、といった局所的なストレスが挙げられます。
また、その部分の血行が特に悪い可能性や、遺伝的な要因でそのエリアのメラノサイトが早く衰えやすいといったことも考えられます。
- 若白髪と加齢による白髪は違いますか?
-
メラノサイトの機能が低下または消失し、メラニン色素が作られなくなるという点では、若白髪(10代や20代で生える白髪)も加齢による白髪も同じです。
若白髪の主な原因は遺伝的要因が強いと考えられていますが、生活習慣の乱れやストレスが影響している場合もあります。
- 食事を変えたらすぐに白髪は減りますか?
-
食事内容の改善は、今生えている白髪を黒くするものではなく、これから新しく生えてくる髪の毛の健康をサポートするためのものです。
髪の毛には生え変わりのサイクル(毛周期)があり、効果を実感するには時間がかかります。
即効性を期待するのではなく、まずは3ヶ月から半年程度、健康な髪と頭皮を育むための土台作りとして、バランスの良い食生活を気長に続けることが重要です。
白髪の原因の記事
Reference
THOMPSON, Katherine G., et al. Evaluation of physiological, psychological, and lifestyle factors associated with premature hair graying. International journal of trichology, 2019, 11.4: 153-158.
O’SULLIVAN, James DB, et al. The biology of human hair greying. Biological Reviews, 2021, 96.1: 107-128.
SEIBERG, M. Age‐induced hair greying–the multiple effects of oxidative stress. International journal of cosmetic science, 2013, 35.6: 532-538.
TRÜEB, Ralph M. Oxidative stress in ageing of hair. International journal of trichology, 2009, 1.1: 6-14.
KAUR, Kiranjeet; KAUR, Rajveer; BALA, Indu. Therapeutics of premature hair graying: A long journey ahead. Journal of Cosmetic Dermatology, 2019, 18.5: 1206-1214.
ARCK, Petra Clara, et al. Towards a “free radical theory of graying”: melanocyte apoptosis in the aging human hair follicle is an indicator of oxidative stress induced tissue damage. The FASEB Journal, 2006, 20.9: 1567-1569.
PANDHI, Deepika; KHANNA, Deepshikha. Premature graying of hair. Indian journal of dermatology, venereology and leprology, 2013, 79: 641.
YADAV, Mahipat S.; KUSHWAHA, Neeti; MAURYA, Neelesh K. The Influence of Diet, Lifestyle, and Environmental Factors on Premature Hair Greying: An Evidence-Based Approach. Archives of Clinical and Experimental Pathology, 2025, 4.1.
MIGLIS, Mitchell G.; LARSEN, Nicholas; MUPPIDI, Srikanth. The shock of it: sympathetic activation promotes hair greying, and other updates on recent autonomic research. Clinical Autonomic Research, 2020, 30.6: 503-505.
KUMAR, Anagha Bangalore; SHAMIM, Huma; NAGARAJU, Umashankar. Premature graying of hair: review with updates. International journal of trichology, 2018, 10.5: 198-203.