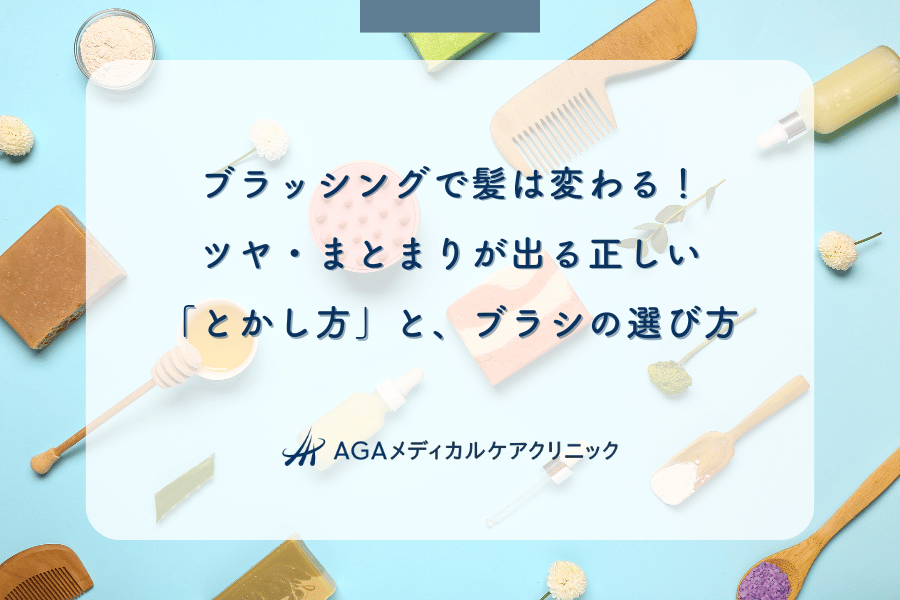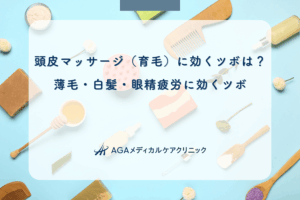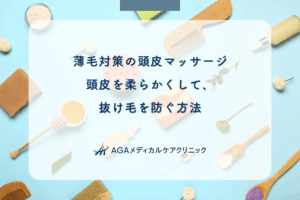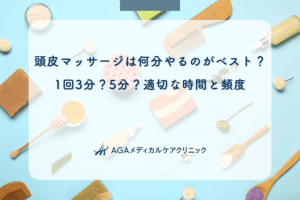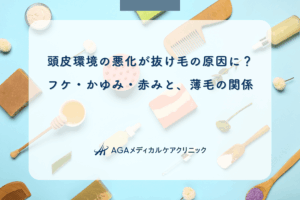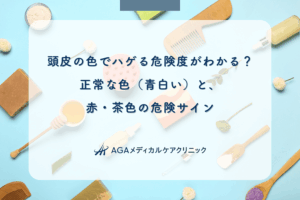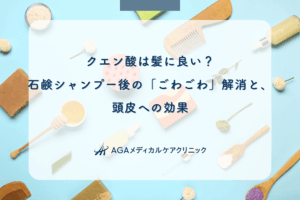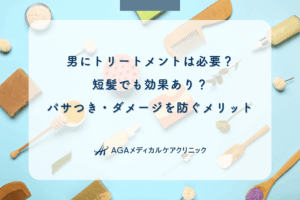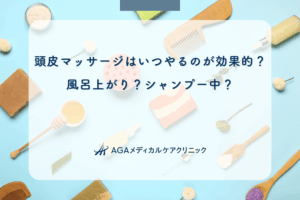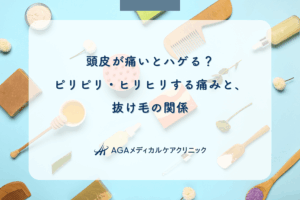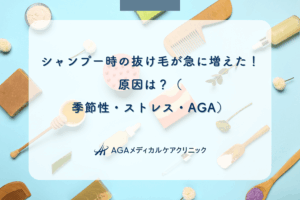毎日のヘアケアとして、シャンプーや育毛剤にこだわる男性は多いかもしれません。しかし、「ブラッシング」についてはどうでしょうか。「ただ髪をとかすだけ」と軽視していませんか?
実は、その認識が髪のコンディションを左右している可能性があります。正しいブラッシングは、単に髪の絡まりを解くだけでなく、髪に自然なツヤを与え、まとまりやすくする力を持っています。
さらに、頭皮環境を整えることにもつながり、健康な髪を育むための重要な土台作りになります。
この記事では、ブラッシングで髪が変わる理由と、髪の美しさを引き出す正しい「とかし方」、そしてあなたの髪質や目的に合ったブラシの選び方を詳しく解説します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
毎日のブラッシング、見直すだけで髪は変わる
日々の習慣であるブラッシング。もしあなたが「朝の寝癖を直すため」や「スタイリングのため」だけにブラシを手に取っているとしたら、その潜在能力の半分も活かせていないかもしれません。
ブラッシングは、意識を少し変えるだけで、髪と頭皮のコンディションを大きく改善する可能性を秘めたケアです。
育毛剤やトリートメントの効果を高めるためにも、まずは基本となるブラッシングを見直してみましょう。
ブラッシングは単なる「とかす」作業ではない
多くの方がブラッシングを「髪の絡まりを解く」行為、つまり「とかす」作業と捉えています。もちろんそれも重要な役割の一つですが、本質はそれだけにとどまりません。
正しいブラッシングは、髪の表面に付着したほこりや汚れを取り除き、キューティクルを整える役割を果たします。
さらに、頭皮に適度な刺激を与えることで、マッサージのような効果も期待できます。これは、髪を美しく見せるだけでなく、健康な髪を育てるための頭皮環境にも良い影響を与えます。
なぜ今、男性にもブラッシングが重要なのか
近年、男性の美意識の高まりとともに、ヘアケアへの関心も高まっています。
しかし、スタイリング剤の使用や、薄毛への懸念から頭皮を過剰に洗浄する一方で、ブラッシングの重要性が見過ごされがちです。
男性の髪は短めの方が多いですが、短いからこそ頭皮の状態が髪にダイレクトに影響します。
正しいブラッシングで頭皮の血行を促し、毛穴の汚れを浮き上がらせることは、育毛剤の浸透を助けることにもつながり、男性のヘアケアにおいて非常に合理的です。
髪と頭皮に与えるブラッシングの力
ブラッシングが髪と頭皮に与える影響は多岐にわたります。
まず髪に対しては、皮脂腺から分泌された皮脂を髪全体に行き渡らせることで、天然のトリートメントのように働き、髪を乾燥から守り自然なツヤを生み出します。
頭皮に対しては、ブラシの先端が適度な刺激となり、血行を促進します。血行が良くなることで、髪の成長に必要な栄養素が毛根に届きやすくなり、健康で丈夫な髪が育つ土壌を整えることにつながります。
まさに、ブラッシングは髪と頭皮両方にとって有益なケアなのです。
ブラッシングがもたらす髪への嬉しい変化
正しいブラッシングを習慣にすると、髪にはどのような具体的な変化が現れるのでしょうか。
ここでは、ブラッシングがもたらす「ツヤ」「まとまり」「頭皮環境の改善」といった嬉しい変化について、その理由とともに詳しく見ていきましょう。
これらの効果を知ることで、「ブラッシングで髪は変わる」という言葉の意味を実感できるはずです。
髪表面の汚れとほこりを除去
私たちは日常生活の中で、目に見えないほこりや花粉、排気ガスなどの汚れにさらされています。これらの汚れは髪の表面に付着し、手触りを悪くしたり、ツヤを失わせたりする原因となります。
毎日のシャンプーで洗い流すことはもちろん大切ですが、シャンプー前のブラッシングは、これらの付着した汚れを物理的に取り除くのに非常に有効です。
髪が乾いた状態であらかじめ汚れを落としておくことで、シャンプー時の泡立ちが良くなり、洗浄効果を高めることにも貢献します。
キューティクルを整えて自然なツヤを引き出す
髪のツヤは、髪の最も外側にある「キューティクル」の状態に大きく左右されます。キューティクルがウロコのようにきれいに整列していると、光が均一に反射して髪は美しく輝きます。
しかし、摩擦や乾燥などでキューティクルが乱れたり剥がれたりすると、光が乱反射し、髪はパサついて見えてしまいます。ブラッシングには、このキューティクルの流れを整える働きがあります。
根元から毛先に向かって優しくとかすことで、キューティクルの向きが整い、髪本来が持つ自然なツヤを引き出すことができます。
頭皮の血行を促し、健康な髪を育む土壌へ
健康な髪は、健康な頭皮から育ちます。頭皮には毛細血管が張り巡らされており、髪の成長に必要な酸素や栄養素を運んでいます。
しかし、ストレスや疲労、生活習慣の乱れなどで頭皮の血行が悪くなると、栄養が十分に行き渡らず、髪が細くなったり、抜け毛が増えたりする原因にもなりかねません。
ブラッシングによる頭皮への適度なマッサージ刺激は、この血行を促すのに役立ちます。
心地よいと感じる強さで頭皮全体を刺激することで、頭皮が柔軟になり、血流が改善し、健康な髪を育むためのしっかりとした土壌を整えます。
意外と知らない?髪を傷めるNGブラッシング
良かれと思って行っているブラッシングが、実は髪や頭皮を傷める原因になっているケースは少なくありません。
「ブラッシングで髪は変わる」という言葉には、良い方向にも悪い方向にも変わる可能性がある、という意味が含まれています。
ここでは、髪のツヤやまとまりを奪い、時には薄毛の原因にもなり得る、やってはいけないNGブラッシングについて解説します。
濡れた髪への強いブラッシング
髪が濡れている時は、キューティクルが開いており、非常にデリケートな状態です。この状態でブラシで強くとかすと、キューティクルが剥がれたり傷ついたりしやすくなります。
特にシャンプー後、タオルドライしただけの髪に、目の細かいブラシを通すのは避けましょう。
濡れた髪をとかす場合は、必ず目の粗いコームや、濡れ髪専用のブラシを使い、毛先から優しくほぐすようにします。
無理に絡まりをほどこうとする力任せのブラッシング
髪に絡まりを見つけた時、根元から一気に力ずくでとかそうとしていませんか?これは、髪を無理やり引きちぎったり、毛根に負担をかけたりする行為です。
髪が切れるだけでなく、キューティクルを傷つけ、枝毛や切れ毛の直接的な原因となります。
絡まりは、まず毛先から手ぐしやブラシで優しくほぐし、徐々に中間、根元へととかす範囲を広げていくのが鉄則です。
NGブラッシングによる主な悪影響
| NG行動 | 髪への影響 | 頭皮への影響 |
|---|---|---|
| 濡れ髪へのブラッシング | キューティクルの損傷・剥離 | (直接的影響は少ない) |
| 力任せのブラッシング | 枝毛・切れ毛・断毛 | 毛根への負担・牽引性脱毛 |
| 頭皮への過度な刺激 | キューティクルの損傷 | 炎症・フケ・かゆみ |
| 不潔なブラシの使用 | ニオイ・ベタつき | 毛穴詰まり・炎症 |
頭皮への過度な刺激と洗いすぎ
頭皮の血行促進は大切ですが、やりすぎは禁物です。ブラシの先端を頭皮に強く押し付けたり、ゴシゴシとこすったりするようなブラッシングは、頭皮を傷つけ、炎症を引き起こす原因になります。
特にナイロン製などの硬いブラシで力を入れすぎると、頭皮が赤くなったり、フケやかゆみが出たりすることも。
また、皮脂を気にするあまり、洗浄力の強すぎるシャンプーや過度なブラッシングで頭皮を洗いすぎると、必要な皮脂まで奪ってしまい、かえって乾燥や皮脂の過剰分泌を招くことがあります。
清潔でないブラシの継続使用
ブラシは毎日使うものですから、髪の毛はもちろん、頭皮の皮脂、ほこり、スタイリング剤などが付着していきます。これを放置すると、ブラシは雑菌の温床となりかねません。
不潔なブラシを使い続けることは、せっかく洗った髪や頭皮に、再び汚れや雑菌を塗り広げているようなものです。これが頭皮の毛穴詰まりやニオイ、炎症の原因となることもあります。
ブラッシングの効果を最大限に得るためにも、ブラシは常に清潔に保つ必要があります。
ブラッシング効果を高める!知っておきたい準備とタイミング
ブラッシングは、いつ、どのような状態で行うかによって、その効果が大きく変わってきます。最高の効果を引き出すためには、適切なタイミングと、髪の状態に合わせたちょっとした準備が重要です。
ここでは、ブラッシングを行うべきベストなタイミングと、その効果を高めるための準備について解説します。
ブラッシングはいつ行うのがベストか
ブラッシングのタイミングとして特におすすめしたいのが、「シャンプー前」と「就寝前」です。
朝のスタイリング時はもちろんですが、この2つのタイミングを意識することで、髪と頭皮の健康維持に大きく貢献します。それぞれのタイミングで行うブラッシングには、異なる目的と効果があります。
ブラッシングの主なタイミングと目的
| タイミング | 主な目的 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 朝(スタイリング前) | 寝癖を直し、髪を整える | まとまりのあるスタイル作り |
| 夜(シャンプー前) | 髪と頭皮の汚れを落とす | シャンプーの泡立ち・洗浄効果向上 |
| 夜(就寝前) | 髪の絡まりを取り、頭皮をほぐす | 就寝中の摩擦軽減、リラックス効果 |
髪が乾いた状態で行うのが基本
前述の通り、髪が濡れている時は非常にデリケートです。したがって、しっかりとしたブラッシングは、髪が完全に乾いている状態で行うのが大原則です。
シャンプー前にブラッシングする際も、当然ながら髪が乾いている状態で行います。
もし、お風呂上がりに髪をとかしたい場合は、ドライヤーで髪をほぼ乾かした後、最後の仕上げとして軽くブラッシングするか、目の粗いコームで優しくとかす程度にとどめましょう。
絡まりやすい髪の事前準備
髪が長い方や、乾燥して絡まりやすい方は、いきなりブラシを通すのではなく、簡単な準備をするとスムーズです。まずは手ぐしで、髪のもつれを大まかにほぐしておきましょう。
特に絡まりがひどい部分は、洗い流さないトリートメントやヘアオイルを少量なじませてから、指先で優しくほどくと、ブラッシング時の髪への負担を減らすことができます。
このひと手間が、切れ毛や枝毛の予防につながります。
ツヤ・まとまりを実現する正しい「とかし方」
「ブラッシングで髪は変わる」を実感するためには、正しい「とかし方」の実践が必要です。力を入れるポイント、ブラシを動かす順番、そして頭皮へのアプローチ。
これらを守ることで、髪への負担を最小限に抑えつつ、ツヤとまとまりを引き出し、頭皮環境を整えることができます。ここでは、具体的な手順を追って解説します。
ステップ1 毛先の絡まりを優しくほぐす
ブラッシングの基本は「毛先から」です。多くの方がやりがちな、根元から毛先へ一気にとかす方法は、途中でブラシが引っかかり、絡まった部分に無理な力がかかってしまいます。
まずは、髪の毛先部分を片手で軽く束ねるように持ち、もう片方の手でブラシを持って、毛先の絡まりだけを優しくほぐします。ここで焦らず、丁寧に引っかかりを取り除くことが重要です。
ステップ2 髪の中間から毛先へ
毛先の絡まりが取れたら、ブラシを入れる位置を少しずつ上にずらしていきます。今度は、髪の中間あたりから毛先に向かってブラシを通します。
この時も、まだ根元からはとかしません。中間から毛先までの流れがスムーズになるまで、数回に分けて優しくとかしましょう。
もし途中で引っかかりを感じたら、無理に引っ張らず、一度ブラシを抜き、再度毛先からほぐし直します。
ステップ3 根元から毛先まで全体をとかす
毛先から中間までの流れがスムーズになったら、いよいよ根元からとかします。頭皮にブラシの先端を軽く当て、そこから毛先まで、髪全体の流れを整えるようにゆっくりとブラシを動かします。
この段階では、もう強い絡まりは無いはずですので、力を入れず、髪の表面をなでるようにとかすことで、キューティクルが整い、ツヤが出てきます。
生え際から襟足、耳の上から後頭部へと、頭部全体をまんべんなくとかしましょう。
ステップ4 心地よい頭皮マッサージブラッシング
最後に、頭皮のマッサージを行います。クッション性のあるブラシ(クッションブラシやパドルブラシ)を使うのがおすすめです。
ブラシの先端を頭皮に垂直に近い角度で当て、心地よいと感じる程度の圧で、ゆっくりと動かします。
頭頂部に向かって、下から上へ引き上げるようにブラッシングすると、血行促進やリフトアップ効果も期待できます。
頭皮マッサージブラッシングのポイント
- 力を入れすぎず、「痛気持ちいい」程度で止める
- 頭皮全体をまんべんなく刺激する
- 一箇所を集中してこすり続けない
あなたに合うのはどれ?目的別ブラシの選び方
正しいブラッシング方法を実践しても、使用するブラシが髪質や目的に合っていなければ、その効果は半減してしまいます。それどころか、逆に髪や頭皮を傷めてしまうこともあります。
ブラシには様々な種類があり、それぞれ素材や形状、得意分野が異なります。ここでは、あなたの髪を理想の状態に導くための、ブラシの選び方を解説します。
ブラシの素材(猪毛・豚毛・ナイロン・木製)の特徴
ブラシのピン(歯)の部分に使われる素材は、使い心地や髪に与える影響を大きく左右します。代表的な素材の特徴を知り、自分の髪質や目的に合わせて選びましょう。
主なブラシ素材の特徴と相性
| 素材 | 主な特徴 | おすすめの髪質・目的 |
|---|---|---|
| 猪毛(天然毛) | 硬めでコシがある。油分・水分を含みやすい。 | 髪が多い、硬い、太い人。ツヤ出し。 |
| 豚毛(天然毛) | 猪毛より柔らかめ。適度な油分・水分。 | 髪が細い、柔らかい、量が普通の人。 |
| ナイロン | 耐久性が高い。洗いやすい。静電気が起きやすいものも。 | スタイリング、濡れ髪、頭皮マッサージ用。 |
| 木製(ウッドピン) | 頭皮への刺激が柔らかい。静電気が起きにくい。 | 頭皮マッサージ、敏感肌の人。 |
髪質や頭皮の状態で選ぶ
自分の髪質や頭皮の状態を考慮して選ぶことも大切です。例えば、髪が細く柔らかい方が猪毛のような硬いブラシを使うと、刺激が強すぎたり、髪が負けてしまったりすることがあります。
その場合は、より柔らかい豚毛や、ピンの先端が丸いナイロンブラシ、ウッドピンブラシなどが適しています。
逆に、髪が太く量が多い方は、豚毛では物足りず、しっかりと髪をキャッチできる猪毛や、コシのあるナイロンブラシが扱いやすいでしょう。
頭皮が敏感な方は、先端が丸く加工されたものや、クッション性の高いものを選ぶと安心です。
使用シーン(シャンプー前・スタイリング・頭皮マッサージ)で選ぶ
ブラッシングをどのタイミングで行うかによっても、適したブラシは異なります。全てのシーンを1本のブラシでまかなうのは難しいため、目的に合わせて使い分けるのが理想です。
シーン別のおすすめブラシタイプ
| 使用シーン | おすすめのブラシタイプ | 主な役割 |
|---|---|---|
| シャンプー前 | クッションブラシ、パドルブラシ(ナイロンや木製) | 汚れ落とし、頭皮マッサージ |
| スタイリング(ブロー) | デンマンブラシ、ロールブラシ(ナイロン) | 髪の流れを整える、クセ付け |
| ツヤ出し(乾いた髪) | 天然毛ブラシ(猪毛、豚毛) | キューティクルを整える、ツヤ出し |
| 頭皮マッサージ | パドルブラシ、ウッドピンブラシ | 血行促進、リラックス |
ブラシを清潔に保つ!簡単なお手入れ方法
最高のブラッシング効果を得るためには、ブラシそのものを清潔に保つことが非常に重要です。汚れたブラシを使い続けることは、頭皮トラブルの原因となり、ブラッシングのメリットを帳消しにしてしまいます。
しかし、お手入れと聞くと面倒に感じるかもしれません。ここでは、素材に合わせた簡単なお手入れ方法と、その頻度について解説します。
なぜブラシの手入れが必要なのか
ブラシには、目に見える髪の毛以外にも、多くの汚れが付着しています。頭皮から出る皮脂、フケ、汗、そして空気中のほこりや、使用したスタイリング剤などです。
これらが混ざり合い、ブラシの根元に蓄積すると、雑菌が繁殖しやすい環境が生まれます。
この汚れを放置したままブラッシングを続けると、雑菌や酸化した皮脂を髪や頭皮に再び広げてしまい、かゆみ、ニオイ、ベタつき、さらには炎症や抜け毛の原因となる可能性もあります。
素材別に見るブラシの洗い方と頻度
ブラシのお手入れ方法は、素材によって異なります。特に天然毛や木製のブラシは水洗いに注意が必要です。プラスチックやナイロン製のブラシは比較的お手入れが簡単です。
ブラシの素材別お手入れ頻度
| 素材 | お手入れ頻度 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| プラスチック・ナイロン | 月に1〜2回 | 水洗い可能。しっかり乾燥させる。 |
| 天然毛(猪毛・豚毛) | 月に1回程度(水洗いは半年に1回など) | 水洗いは極力避ける。専用クリーナー推奨。 |
| 木製(ウッドピン) | 月に1回程度 | 水洗いを避け、綿棒や布で拭き取る。 |
基本的なお手入れとしては、まずブラシに絡まった髪の毛を、手や専用のクリーナー、コームなどを使ってこまめに取り除きます。これが最も重要です。
水洗いができるナイロン製などのブラシは、シャンプーを溶かしたぬるま湯で振り洗いし、よくすすいだ後、タオルで水気を拭き取り、ピン(歯)の部分を下にして陰干しします。
天然毛や木製のブラシは水濡れに弱いため、基本的には乾いた布や綿棒で汚れを拭き取ります。どうしても汚れがひどい場合のみ、手早く水洗いし、すぐに乾かします。
ブラシを洗う際の注意点
- 熱湯は使用しない(変形の原因)
- 天然毛や木製は長時間水につけない
- 洗った後は風通しの良い場所で完全に乾かす
ブラシの交換時期の目安
丁寧にお手入れをしていても、ブラシには寿命があります。ピン(歯)が折れたり、曲がったり、抜けたりしてきたら、交換のサインです。
特にナイロンブラシの先端についている丸い部分(頭皮を保護する役割)が取れてしまうと、頭皮を傷つける原因になるため、すぐに使用を中止しましょう。
クッションブラシのゴム部分が劣化して硬くなったり、ひび割れたりした場合も、クッション性が失われ、頭皮への刺激が強くなるため、交換が必要です。
一般的に、毎日使用する場合、1年〜2年程度が交換の目安とされています。
Q&A
ここでは、ブラッシングに関して多くの方が抱く疑問についてお答えします。
- ブラッシングは1日に何回くらい行うのが良いですか?
-
一概に「何回が良い」とは言えませんが、一般的には、朝のスタイリング時、夜のシャンプー前、そして就寝前の計2〜3回程度を目安にすると良いでしょう。
ただし、これはあくまで目安です。大切なのは回数よりも、一回一回のブラッシングを丁寧に行うことです。
皮脂が多いと感じる方は、日中に軽く頭皮の皮脂を髪になじませるようにとかすのも良いですが、やりすぎは頭皮を刺激しすぎる可能性があるので注意しましょう。
- 静電気を防ぐブラッシング方法はありますか?
-
冬場など乾燥する季節は、静電気が起こりやすくなります。静電気は髪のキューティクルを傷める原因にもなります。
まず、プラスチックや金属製のブラシよりも、天然毛(猪毛・豚毛)や木製のブラシを選ぶと、静電気は格段に起きにくくなります。
また、ブラッシングの前に、ブラシ自体を少し湿らせたり(水洗い不可のブラシは除く)、髪にヘアミストやオイルを少量なじませてからとかしたりするのも効果的です。
- ブラシに髪の毛がたくさんつくのですが、大丈夫でしょうか?
-
人は1日に50本から100本程度の髪が自然に抜けています(自然脱毛)。
ブラッシング時には、このすでに抜け落ちるサイクルに入っていた髪の毛がブラシに絡まるため、ある程度の抜け毛がつくのは正常なことです。
特にシャンプー前のブラッシングでは、その日1日の自然脱毛分がまとめて取れるため、多く感じるかもしれません。
ただし、明らかに以前より量が増えた、短い毛や細い毛が目立つ、ブラッシング時に痛みを感じる(無理に引っ張っている)場合は、ブラッシング方法が間違っているか、他の脱毛要因が隠れている可能性も考えられます。
- 育毛剤の前にブラッシングは効果的ですか?
-
はい、非常に効果的と考えられます。育毛剤は、頭皮に浸透して毛根に作用することを目指すものです。
育毛剤を使用する前にブラッシングを行うことには、2つの大きなメリットがあります。一つは、頭皮や毛穴の汚れ、古い角質を浮き上がらせ、育毛剤が浸透しやすい清潔な状態を作ること。
もう一つは、頭皮のマッサージ効果により血行を促進し、育毛剤の成分が毛根に届きやすくなる土壌を整えることです。
ただし、育毛剤を塗布した直後にブラッシングすると、薬剤が髪の毛についてしまうため、塗布前のブラッシングがおすすめです。
Reference
BIRCH, M. P.; MESSENGER, J. F.; MESSENGER, A. G. Hair density, hair diameter and the prevalence of female pattern hair loss. British Journal of Dermatology, 2001, 144.2: 297-304.
RUSHTON, D. H., et al. Causes of hair loss and the developments in hair rejuvenation. International journal of cosmetic science, 2002, 24.1: 17-23.
PHILLIPS, T. Grant; SLOMIANY, W. Paul; ALLISON, Robert. Hair loss: common causes and treatment. American family physician, 2017, 96.6: 371-378.
SINCLAIR, Rodney, et al. Hair loss in women: medical and cosmetic approaches to increase scalp hair fullness. British Journal of Dermatology, 2011, 165.s3: 12-18.
ALESSANDRINI, A., et al. Common causes of hair loss–clinical manifestations, trichoscopy and therapy. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2021, 35.3: 629-640.
OLSEN, Elise A., et al. Central hair loss in African American women: incidence and potential risk factors. Journal of the American Academy of Dermatology, 2011, 64.2: 245-252.
HUTCHINSON, P. E. Hair density, hair diameter and the prevalence of female pattern hair loss. British journal of dermatology, 2002, 146.5: 922-923.
USTUNER, E. Tuncay. Baldness may be caused by the weight of the scalp: gravity as a proposed mechanism for hair loss. Medical hypotheses, 2008, 71.4: 505-514.
PRICE, Vera H. Treatment of hair loss. New England Journal of Medicine, 1999, 341.13: 964-973.
VAN ZUUREN, Esther J.; FEDOROWICZ, Zbys; SCHOONES, Jan. Interventions for female pattern hair loss. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2016, 5.