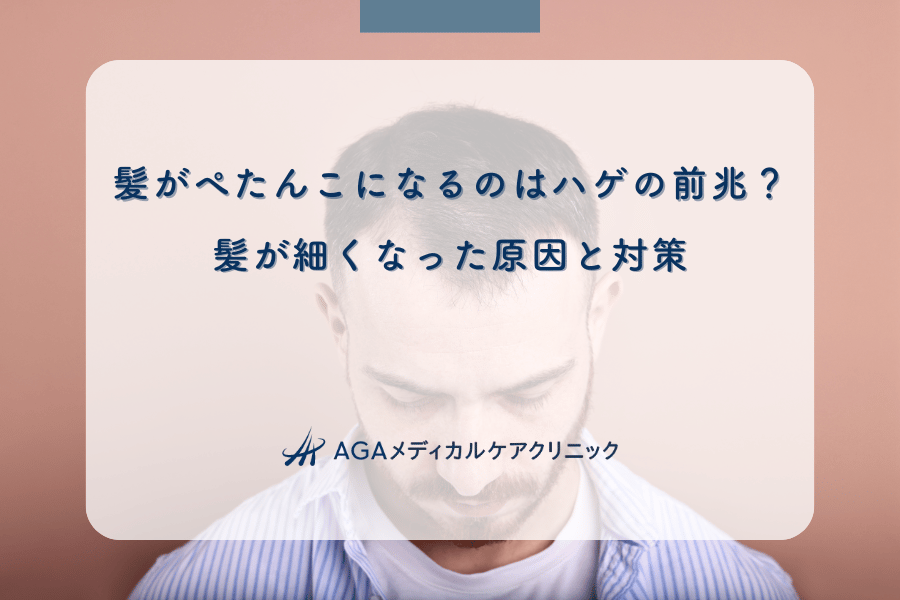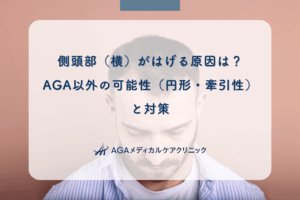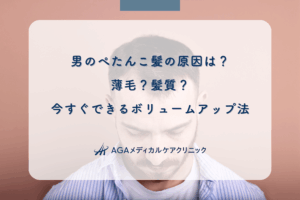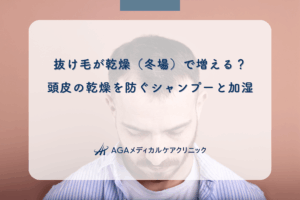朝、鏡を見てスタイリングが決まらない。髪に元気がなく、ぺたんとしてボリュームが出ない。そんな経験はありませんか。
特に男性にとって、髪のボリュームダウンは「もしかしてハゲ(薄毛)の前兆なのでは?」という大きな不安につながる問題です。
髪がぺたんこになる原因は一つではありませんが、中には薄毛のサインが隠れている可能性も否定できません。しかし、早期に原因を知り、正しい対策を講じることで、髪の健康を取り戻す手助けになります。
この記事では、髪がぺたんこになる原因と、それが薄毛とどう関係するのか、そして今すぐ始められる具体的な対策について詳しく解説します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
「髪がぺたんこ」は危険信号?薄毛との関係性
髪のボリュームが失われ、ぺたんこに見える状態は、多くの方が気になるサインです。これが一時的なものなのか、それとも進行する薄毛の始まりなのか、見極めることが大切です。
髪の状態と薄毛の関係性について見ていきましょう。
髪のボリュームダウンを感じる瞬間
日々の生活の中で、ふとした瞬間に髪のボリュームダウンを感じることがあります。
例えば、「以前よりスタイリング剤の量が必要になった」「ドライヤーで乾かしてもすぐに髪が寝てしまう」「帽子を脱いだ後の髪の潰れ方がひどい」といった感覚です。
これらの変化は、髪の毛自体の太さや本数、あるいは頭皮の状態に変化が起きている可能性を示しています。
「ぺたんこ髪」と「髪が細くなる」現象
髪がぺたんこに見える最大の要因の一つが、髪の毛一本一本が細くなる「菲薄化(ひはくか)」です。髪の毛が細くなると、同じ本数でも全体の体積が減少し、髪同士の間に隙間ができにくくなります。
その結果、髪全体が頭皮に張り付くように見え、ボリュームダウンにつながります。髪が細くなる現象は、薄毛、特にAGA(男性型脱毛症)の初期段階で見られる特徴的な変化です。
すべてがハゲ(AGA)につながるわけではない
髪がぺたんこになるからといって、すべての方がAGAを発症するわけではありません。
頭皮環境の悪化、例えば皮脂の過剰分泌で髪が束になったり、間違ったヘアケアで髪にハリやコシがなくなったりしても、髪はぺたんこに見えます。
また、栄養不足やストレス、睡眠不足といった生活習慣の乱れも、一時的に髪の元気を奪う原因となります。まずはご自身の状態がどれに当てはまるか冷静に把握することが重要です。
チェックしたい初期の薄毛サイン
ぺたんこ髪以外にも、薄毛の初期サインとして注意したい点がいくつかあります。これらが当てはまる場合は、早めの対策を検討する必要があります。
初期薄毛サインのセルフチェック
| チェック項目 | 具体的な状態 | 関連する可能性 |
|---|---|---|
| 抜け毛の質 | シャンプーや起床時に、細く短い毛が目立つ。 | ヘアサイクルの短縮(AGAなど) |
| 頭皮の状態 | 頭皮が硬い、または脂っぽい、フケやかゆみがある。 | 頭皮環境の悪化、血行不良 |
| 髪の生え際・つむじ | 以前より生え際が後退した、またはつむじ周りの地肌が透けて見える。 | AGAの進行パターン |
なぜ髪はぺたんこになるのか?考えられる主な原因
髪がぺたんこになる背景には、複数の要因が複雑に絡み合っています。
髪の毛自体の問題だけでなく、その土台である頭皮の状態や、体全体の健康状態も影響します。主な原因を整理してみましょう。
髪の毛自体の「菲薄化(ひはくか)」
前述の通り、髪の毛が細くなることはボリュームダウンの直接的な原因です。髪の毛は一定の周期(ヘアサイクル)で成長し、抜け落ちることを繰り返しています。
しかし、何らかの原因でこのサイクルが乱れ、髪が十分に太く、長く成長する前に抜け落ちるようになると、細い髪の割合が増えてしまいます。これが菲薄化の正体であり、AGAの主な症状です。
頭皮環境の悪化(皮脂や汚れ)
頭皮は髪が育つ土壌です。この土壌が健康でないと、良い髪は育ちません。皮脂が過剰に分泌されると、毛穴が詰まりやすくなります。
また、皮脂が髪の根元に付着することで、髪が束になり重くなるため、根元から立ち上がりにくくなり、ぺたんとした印象を与えます。
逆に頭皮が乾燥しすぎても、バリア機能が低下し、フケやかゆみが発生しやすくなり、健康な髪の成長を妨げる要因となります。
髪のハリ・コシの低下
髪の毛は主にタンパク質でできていますが、加齢やダメージによって内部の構造がもろくなると、弾力が失われ「ハリ」や「コシ」がなくなります。
ハリ・コシが失われた髪は、外部の力(湿気や重力)に弱く、すぐに形が崩れてぺたんこになりがちです。
髪のハリ・コシを低下させる主な要因
| 要因 | 内容 | 髪への影響 |
|---|---|---|
| 加齢 | 年齢と共に髪内部のタンパク質や脂質が変化・減少する。 | 髪のうねり、弾力低下。 |
| ヘアダメージ | カラー、パーマ、紫外線の影響でキューティクルが損傷する。 | 内部成分が流出し、髪が弱くなる。 |
| 生活習慣 | 栄養不足や睡眠不足による髪への栄養供給低下。 | 健康な髪を維持する力が弱まる。 |
生活習慣による影響
髪の健康は、体全体の健康と密接に関連しています。偏った食生活による栄養不足、慢性的な睡眠不足、過度なストレスは、自律神経やホルモンバランスを乱し、頭皮の血行を悪化させます。
血行が悪くなると、髪の成長に必要な栄養素が毛根まで届きにくくなり、結果として髪が細くなったり、ハリ・コシが失われたりする原因となります。
髪が細くなる「菲薄化」の正体
髪がぺたんこになる最も深刻な原因である「菲薄化」。これは単なる髪質の変化ではなく、多くの場合、ヘアサイクルの異常が関係しています。
特に男性の場合、AGA(男性型脱毛症)の関与を考える必要があります。
ヘアサイクルの乱れとは
健康な髪の毛には「成長期(髪が太く長く成長する期間)」「退行期(成長が止まる期間)」「休止期(髪が抜け落ちる準備をする期間)」というヘアサイクルがあります。
通常、成長期は2年から6年ほど続きますが、何らかの原因でこの成長期が極端に短くなることがあります。これがヘアサイクルの乱れです。
成長期が短縮するAGA(男性型脱毛症)
AGAは、男性ホルモン(テストステロン)が特定の酵素(5αリダクターゼ)と結びついて生成されるDHT(ジヒドロテストステロン)が主な原因とされています。
このDHTが毛根の受容体に作用すると、髪の成長期を短縮させる信号が出されます。
その結果、髪は十分に成長する前に退行期・休止期へと移行してしまい、細く短い「うぶ毛」のような髪の毛が増えていきます。
AGAによる髪質の変化
AGAが進行すると、単に髪が細くなるだけでなく、髪の色が薄くなったり、ハリやコシが失われたりといった質的な変化も伴います。
特に頭頂部(つむじ)や前頭部(生え際)から薄毛が進行しやすいのが特徴です。ぺたんこ髪がこれらの部位で特に目立つ場合、AGAの可能性をより強く考える必要があります。
AGAと正常なヘアサイクルの比較
| 項目 | 正常なヘアサイクル | AGAのヘアサイクル |
|---|---|---|
| 成長期の期間 | 2年~6年 | 数ヶ月~1年程度 |
| 髪の状態 | 太く、長く、コシがある。 | 細く、短く、うぶ毛のよう。 |
| 毛根への影響 | 髪が深く根付いている。 | DHTの影響で成長が阻害される。 |
栄養不足と血行不良の影響
AGAとは直接関係なくても、頭皮の血行不良や栄養不足は菲薄化を助長します。髪の毛は毛細血管から栄養を受け取って成長します。
偏った食事で髪の材料となるタンパク質やビタミン、ミネラルが不足したり、ストレスや運動不足で血行が悪化したりすると、毛根は栄養失調状態に陥り、健康な髪を作れなくなります。
これが菲薄化を進める一因となります。
頭皮環境と髪のボリューム
髪が根元からしっかりと立ち上がるためには、土台である頭皮が健康であることが重要です。頭皮環境が悪化すると、髪は本来の力を発揮できず、ぺたんこになってしまいます。
頭皮トラブルとボリュームの関係を見ていきましょう。
過剰な皮脂分泌と毛穴の詰まり
頭皮の皮脂は、本来は頭皮を乾燥や外部刺激から守るバリアの役割を果たしています。しかし、ホルモンバランスの乱れや脂っこい食事、不規則な生活などによって皮脂が過剰に分泌されると、問題が生じます。
余分な皮脂が古い角質やホコリと混ざり合うと、毛穴を塞いでしまいます。毛穴が詰まると、髪の成長が妨げられるだけでなく、皮脂の重みで髪が根元から倒れやすくなり、ボリュームダウンの原因となります。
乾燥頭皮が引き起こす問題
皮脂が多すぎるのとは逆に、頭皮が乾燥しすぎるのも問題です。洗浄力の強すぎるシャンプーの使用や、エアコンによる空気の乾燥などで頭皮の水分が奪われると、バリア機能が低下します。
乾燥した頭皮は、外部からのわずかな刺激にも敏感になり、かゆみやフケを引き起こしやすくなります。かゆみで頭皮を掻きむしると、頭皮や毛根が傷つき、健康な髪の成長に悪影響を与えます。
頭皮タイプ別の主な問題点
| 頭皮タイプ | 主な特徴 | 髪のボリュームへの影響 |
|---|---|---|
| 脂性頭皮 | 日中、頭皮や髪のベタつきが気になる。 | 皮脂の重みで髪が束になり、ぺたんこになる。毛穴が詰まりやすい。 |
| 乾燥頭皮 | フケ(特に乾いたパラパラしたもの)やかゆみが気になる。 | バリア機能低下により、健康な髪が育ちにくい環境になる。 |
頭皮の血行不良と髪の栄養
頭皮が硬いと感じることはありませんか。デスクワークでの長時間の同じ姿勢、目の疲れ、ストレスなどは、頭部の筋肉を緊張させ、頭皮の血行不良を引き起こします。
頭皮の毛細血管は非常に細く、血行が悪化するとその影響を真っ先に受けます。
髪の成長に必要な酸素や栄養素は血液によって運ばれるため、血行不良は毛根の栄養不足に直結し、髪が細くなったり、ハリ・コシが失われたりする原因となります。
間違ったヘアケアによるダメージ
良かれと思って行っているヘアケアが、逆に頭皮や髪にダメージを与えているケースもあります。
例えば、頭皮のベタつきを気にするあまり、一日に何度もシャンプーをしたり、爪を立ててゴシゴシ洗ったりすると、必要な皮脂まで取り除いてしまい、頭皮の乾燥や皮脂の過剰分泌を招きます。
また、熱すぎるお湯でのすすぎや、ドライヤーを近距離で当てすぎることも、頭皮や髪を傷つけ、ボリュームダウンの原因となります。
今すぐ始めたい 日常でできるボリュームアップ対策
髪がぺたんこになる原因が分かったら、次に行うべきは対策です。専門的な治療の前に、まずは日常生活で見直せることから始めましょう。
日々の小さな積み重ねが、髪の未来を変える第一歩です。
正しいシャンプーの選び方と洗い方
毎日のシャンプーは、頭皮環境を整える基本です。ご自身の頭皮タイプに合ったシャンプー剤を選び、正しい方法で洗うことが重要です。
脂性肌の方は皮脂を適切に除去するスカルプケアタイプ、乾燥肌の方は保湿成分が配合されたアミノ酸系シャンプーなどが選択肢になります。
正しいシャンプーの手順
- 洗髪前にブラッシングで髪のもつれを解き、ホコリを浮かす。
- ぬるま湯(38度程度)で頭皮と髪をしっかりと予洗いする。
- シャンプー剤は手のひらでよく泡立ててから、髪ではなく頭皮につける。
- 指の腹を使って、頭皮全体をマッサージするように優しく洗う。
- すすぎ残しはかゆみやフケの原因になるため、時間をかけて丁寧に洗い流す。
髪の乾かし方(ドライヤーテクニック)
髪を濡れたまま放置すると、雑菌が繁殖しやすくなり、頭皮環境に悪影響を与えます。また、髪は濡れている状態が最もダメージを受けやすいため、シャンプー後は速やかに乾かすことが大切です。
ドライヤーで乾かす際は、まずタオルドライで余分な水分をしっかり拭き取ります。その後、ドライヤーの温風を髪の根元に当て、指で髪をかき分けながら乾かしていきます。
根元が乾いたら、中間から毛先へと乾かします。最後に冷風を当てると、キューティクルが引き締まり、スタイルが長持ちしやすくなります。
頭皮マッサージの基本的な方法
頭皮マッサージは、硬くなった頭皮をほぐし、血行を促進するのに役立ちます。シャンプー中や、育毛剤をつけるタイミングで行うのが習慣化しやすくて良いでしょう。
リラックスした状態で、指の腹を使い、頭皮全体を優しく動かすようにマッサージします。
頭皮マッサージの注意点
- 爪を立てて頭皮を傷つけないように注意する。
- 強くこすりすぎず、心地よい圧で行う。
- 毎日短時間でも継続することが大切。
スタイリング剤の上手な活用法
すぐにボリュームアップを実感したい場合、スタイリング剤の力を借りるのも一つの方法です。
ただし、油分やシリコンが多い重いタイプのワックスやジェルは、髪の重みで逆にぺたんこになりやすいので注意が必要です。
ボリュームを出したい場合は、スプレータイプやパウダータイプ、軽い仕上がりのマットワックスなどを選び、髪の根元を中心に少量ずつ使用するのがコツです。
その日の終わりには、シャンプーでしっかりと洗い流し、頭皮に残さないようにしましょう。
根本から見直す生活習慣の改善
髪の健康は、体の内側からのケアが非常に重要です。いくら外側から良いケアをしても、体が健康でなければ元気な髪は育ちません。
髪がぺたんこになるのを防ぎ、強く太い髪を育てるための生活習慣を見直しましょう。
髪の成長に必要な栄養素
髪の毛の約9割は「ケラチン」というタンパク質でできています。したがって、良質なタンパク質の摂取は必須です。
また、タンパク質を髪の毛に合成する際には、ビタミンやミネラル(特に亜鉛)の助けが必要です。バランスの取れた食事を心がけ、特定の食品に偏らないようにしましょう。
髪の成長に寄与する主な栄養素と食材例
| 栄養素 | 主な役割 | 多く含む食材例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分であるケラチンの材料となる。 | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助け、ヘアサイクルを正常に保つ。 | 牡蠣、レバー、牛肉(赤身)、ナッツ類 |
| ビタミンB群 | 頭皮の代謝を促し、皮脂の分泌をコントロールする。 | 豚肉、レバー、マグロ、カツオ、納豆 |
質の高い睡眠の確保
髪の成長を促す「成長ホルモン」は、主に睡眠中に分泌されます。特に、入眠から最初の3時間(「ゴールデンタイム」とも呼ばれる)に深く眠ることが重要です。
睡眠時間が不足したり、睡眠の質が低下したりすると、成長ホルモンの分泌が減少し、髪の成長や頭皮の修復が十分に行われなくなります。
寝る前のスマートフォン操作を控える、リラックスできる環境を整えるなど、質の高い睡眠を確保する工夫をしましょう。
ストレス管理とリフレッシュ法
過度なストレスは、自律神経のバランスを崩し、血管を収縮させます。これにより頭皮の血行が悪化し、毛根に栄養が届きにくくなります。
また、ストレスはホルモンバランスの乱れにもつながり、皮脂の過剰分泌やAGAを悪化させる要因にもなり得ます。
日常生活でストレスをゼロにすることは困難ですが、趣味の時間を持つ、適度な運動をする、ゆっくり入浴するなど、自分なりのリフレッシュ法を見つけ、ストレスを溜め込まないようにすることが大切です。
喫煙や過度な飲酒のリスク
喫煙は、ニコチンの作用で全身の血管を収縮させ、血行を著しく悪化させます。特に頭皮の毛細血管は影響を受けやすく、髪の成長に必要な酸素や栄養素が届きにくくなります。
また、タバコは体内のビタミンCを大量に消費するため、髪の健康維持にも悪影響です。過度な飲酒も、アルコールの分解に肝臓で多くの栄養素が使われるため、髪に回る栄養が不足しがちになります。
髪の健康を考えるなら、禁煙や節酒を検討することが賢明です。
育毛剤の活用と専門家への相談
セルフケアを続けていても、なかなか髪のぺたんこ感が改善しない。あるいは、抜け毛の増加や地肌の透け感が明らかになってきた場合。それはAGAが進行しているサインかもしれません。
その場合は、セルフケアに加えて、より積極的な対策や専門家の助けを借りることを検討しましょう。
育毛剤の役割と期待できること
育毛剤(または発毛剤)は、薄毛対策の有力な選択肢の一つです。市場には多くの製品がありますが、その目的によって成分が異なります。
「育毛剤」は、主に現在ある髪の毛を健康に保ち、抜け毛を予防すること(頭皮環境の改善、血行促進など)を目的としています。
一方、「発毛剤」は、新しい髪の毛を生やし、育てること(毛根に直接作用するなど)を目的としており、医薬品に分類されるものが多いです(例:ミノキシジル配合のものなど)。
ご自身の目的が「予防」なのか「発毛」なのかを明確にして選ぶことが重要です。
育毛剤・発毛剤の主な成分と期待される役割
| 分類 | 主な有効成分例 | 期待される役割 |
|---|---|---|
| 発毛剤(医薬品) | ミノキシジル | 毛母細胞の活性化、血行促進による発毛促進。 |
| 育毛剤(医薬部外品) | センブリエキス、グリチルリチン酸ジカリウム | 血行促進、抗炎症作用による頭皮環境改善。 |
| 育毛剤(医薬部外品) | t-フラバノン、アデノシン | 毛母細胞への働きかけによる育毛促進、抜け毛予防。 |
育毛剤の選び方のポイント
育毛剤を選ぶ際は、まずご自身の頭皮の状態や悩みに合った成分が配合されているかを確認しましょう。
例えば、頭皮の乾燥が気になるなら保湿成分、脂っぽさが気になるなら皮脂コントロール成分が含まれているものが良いでしょう。また、育毛剤は短期間で結果が出るものではありません。
最低でも6ヶ月程度は継続して使用する必要があるため、価格や使用感(香り、べたつきなど)が、ご自身にとって続けやすいものであることも大切な選択基準です。
対策しても改善しない場合の選択肢
生活習慣を改善し、育毛剤も使用しているにもかかわらず、髪のぺたんこ感や薄毛が進行するように感じる場合、セルフケアの限界を超えている可能性があります。
特にAGAは進行性の脱毛症であり、放置すると症状は徐々に悪化していきます。AGAの原因(DHT)に直接アプローチする対策は、セルフケアだけでは困難です。
専門クリニックでの相談内容
薄毛の進行に強い不安を感じる場合は、薄毛治療を専門とするクリニックに相談することを推奨します。
専門クリニックでは、まず医師による問診や視診、マイクロスコープでの頭皮診断などを行い、薄毛の根本原因を特定します。
その結果、AGAと診断された場合には、内服薬(フィナステリドやデュタステリドなど)や外用薬(ミノキシジル)を用いた治療など、医学的根拠に基づいた対策を提案してくれます。
原因を正確に知ることが、適切な対策への最短距離となります。
Q&A
最後に、髪がぺたんこになることや薄毛に関して、多くの方が抱く疑問についてお答えします。
- 髪がぺたんこになるのは遺伝しますか?
-
髪質(髪の太さやクセ)が遺伝の影響を受けることはあります。そのため、もともと髪が細く、ぺたんこになりやすい体質を受け継いでいる可能性はあります。
また、薄毛(特にAGA)の発症しやすさも遺伝的要因が強く関わっていることが知られています。AGAの原因となる男性ホルモンの感受性の高さは、家族から受け継がれることが多いです。
ただし、遺伝がすべてではなく、生活習慣やヘアケアによって状態は変化します。
- 食事を変えれば髪は太くなりますか?
-
食事は髪の健康に非常に重要ですが、食事の改善だけで、もともと細い髪が劇的に太くなることを期待するのは難しいかもしれません。
しかし、栄養不足が原因で髪が細くなっていたり、ハリ・コシを失っていたりする場合には、バランスの取れた食事を心がけることで、髪が本来持つポテンシャル(太さや強さ)を取り戻す手助けになります。
特に髪の主成分であるタンパク質や、その合成を助ける亜鉛、ビタミン類を意識して摂取することは、健康な髪を育てる上で大切です。
- 育毛剤はいつから使い始めるべきですか?
-
育毛剤の使用を開始するタイミングに「早すぎる」ということはありません。特に育毛剤(医薬部外品)の多くは、頭皮環境を整え、抜け毛を予防することを目的としています。
「最近、髪にハリ・コシがなくなってきた」「抜け毛が少し気になる」と感じ始めた段階で、予防的に使い始めるのは良い選択です。
AGAの進行を抑える発毛剤(医薬品)に関しては、薄毛の進行が明らかになった時点で、専門家の診断のもとで使用を検討するのが一般的です。
- 髪を短くすると薄毛は目立たなくなりますか?
-
髪の毛を短く切っても、髪の毛自体の本数が増えたり、太くなったりするわけではありません。しかし、スタイリングの工夫次第で薄毛を目立たなくさせることは可能です。
髪が長いと、重力でぺたんこになりやすく、地肌が透けて見える部分とのコントラストがはっきりしてしまい、かえって薄毛が目立つことがあります。
一方、サイドを短く刈り上げ、トップにボリュームを持たせるようなショートヘアは、視覚的に薄毛をカバーしやすい髪型の一つです。
ご自身の髪質や頭の形に合ったスタイルを美容師に相談してみるのも良いでしょう。
Reference
OLSEN, Elise A., et al. Evaluation and treatment of male and female pattern hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2005, 52.2: 301-311.
BIRCH, M. P.; MESSENGER, J. F.; MESSENGER, A. G. Hair density, hair diameter and the prevalence of female pattern hair loss. British Journal of Dermatology, 2001, 144.2: 297-304.
ALESSANDRINI, A., et al. Common causes of hair loss–clinical manifestations, trichoscopy and therapy. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2021, 35.3: 629-640.
GAN, Desmond CC; SINCLAIR, Rodney D. Prevalence of male and female pattern hair loss in Maryborough. In: Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings. Elsevier, 2005. p. 184-189.
BANKA, Nusrat; BUNAGAN, MJ Kristine; SHAPIRO, Jerry. Pattern hair loss in men: diagnosis and medical treatment. Dermatologic clinics, 2013, 31.1: 129-140.
MANABE, Motomu, et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of male‐pattern and female‐pattern hair loss, 2017 version. The Journal of Dermatology, 2018, 45.9: 1031-1043.
RUSHTON, D. H., et al. Causes of hair loss and the developments in hair rejuvenation. International journal of cosmetic science, 2002, 24.1: 17-23.
HERSKOVITZ, Ingrid; TOSTI, Antonella. Female pattern hair loss. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013, 11.4: e9860.
YORK, Katherine, et al. A review of the treatment of male pattern hair loss. Expert opinion on pharmacotherapy, 2020, 21.5: 603-612.
SINCLAIR, Rodney, et al. Hair loss in women: medical and cosmetic approaches to increase scalp hair fullness. British Journal of Dermatology, 2011, 165.s3: 12-18.