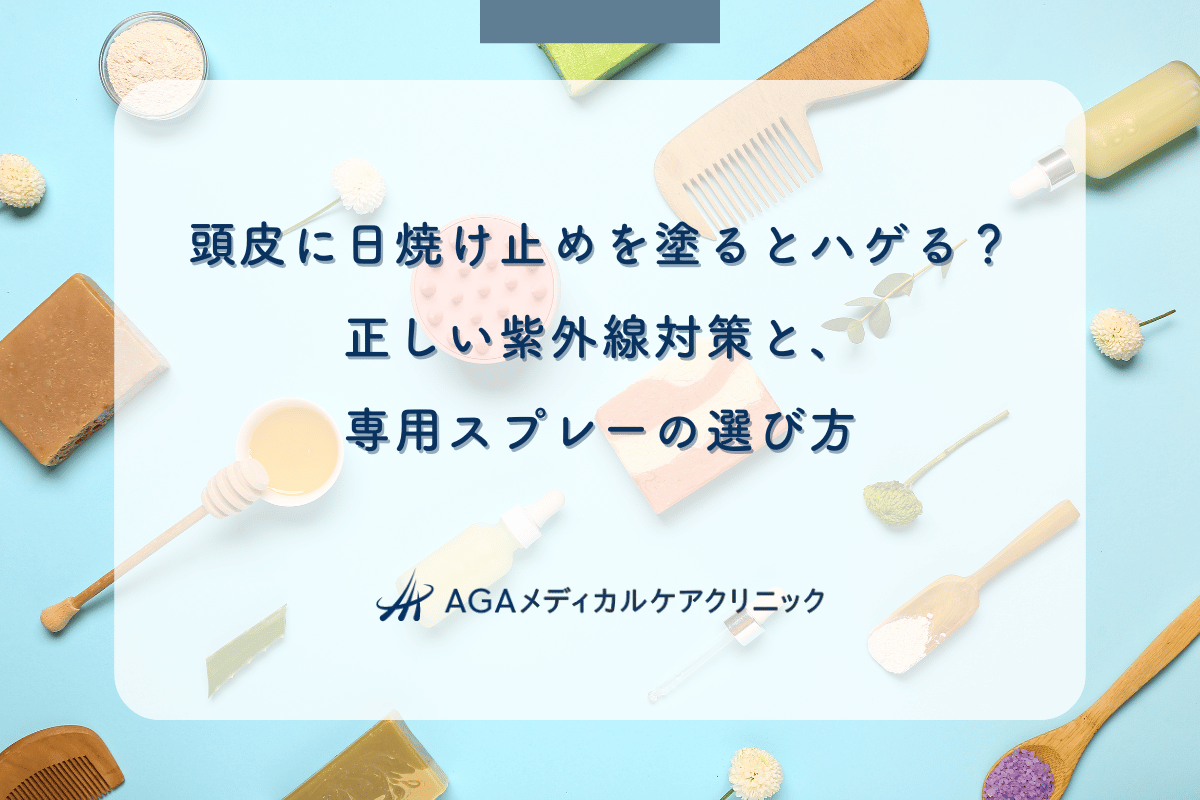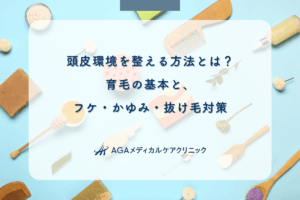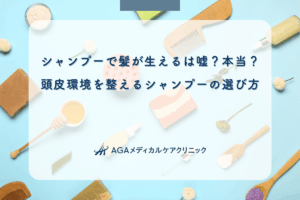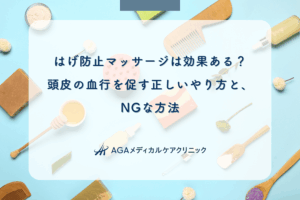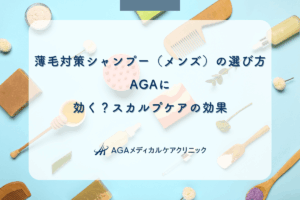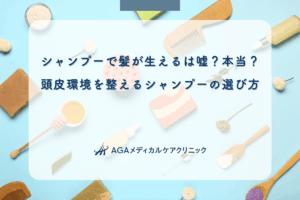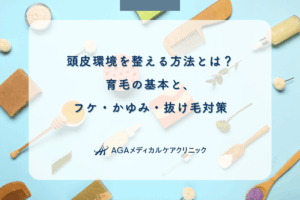「頭皮に日焼け止めを塗ると、毛穴が詰まってハゲるのでは?」そんな不安から、頭皮の紫外線対策をためらっていませんか。
しかし、実は対策をしないことの方が、頭皮環境にとって大きなリスクを招きます。紫外線は頭皮の乾燥や炎症を引き起こし、健康な髪の育成を妨げる一因となるのです。
この記事では、頭皮用日焼け止めと薄毛の関係についての真相を解明し、頭皮を守るための正しい紫外線対策、そしてあなたに合った専用スプレーの選び方まで、詳しく解説していきます。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
「頭皮に日焼け止めを塗るとハゲる」説の真相
夏の強い日差しやレジャーシーンで気になる頭皮の日焼け。
しかし、「日焼け止めは毛穴に悪そうで、薄毛の原因になるかもしれない」という不安を持つ方は少なくありません。まずは、この噂の真相を探ります。
日焼け止めと薄毛の直接的な関係性
結論から言うと、頭皮用日焼け止めを正しく使用することが、直接的な薄毛(ハゲ)の原因になるという医学的根拠は現在のところ明確ではありません。
むしろ、紫外線によるダメージを放置することの方が、頭皮環境を悪化させ、抜け毛や薄毛のリスクを高める可能性があります。
問題は「日焼け止めを塗ること」自体ではなく、「どのように使い、どのように落とすか」にあります。
なぜ「ハゲる」と噂されるのか?
この噂が広まる背景には、いくつかの誤解や懸念が考えられます。
懸念点1:毛穴詰まり
日焼け止めの成分や皮脂、汗、ほこりなどが混ざり合い、毛穴を塞いでしまうのではないか、という懸念です。
毛穴が詰まると、皮脂が正常に排出されず、炎症(毛嚢炎)を引き起こしたり、髪の成長サイクルに悪影響を与えたりする可能性があります。
特に、顔や体用の重いテクスチャーのクリームやミルクタイプを頭皮に塗った場合、このリスクは高まるでしょう。
懸念点2:成分による刺激
日焼け止めに含まれる特定の成分(例えば紫外線吸収剤など)が、肌質に合わない場合、頭皮にかゆみ、赤み、かぶれといった炎症を引き起こすことがあります。
頭皮が炎症を起こすと、健康な髪が育ちにくい環境になり、結果として抜け毛が増えることも考えられます。
毛穴詰まりの懸念と日焼け止めの成分
毛穴詰まりを防ぐためには、製品選びと洗浄が重要です。頭皮用として設計された製品、特にスプレータイプは、比較的粒子が細かく、ベタつきにくいように作られています。
また、日焼け止めには大きく分けて「紫外線吸収剤」を使用したものと「紫外線散乱剤」を使用したものがあります。
紫外線吸収剤は化学的に紫外線を熱などのエネルギーに変換するもので、肌への刺激を感じる人もいます。
一方、紫外線散乱剤(ノンケミカル)は物理的に紫外線を跳ね返すもので、比較的肌への負担が少ないとされますが、白浮きしやすい傾向があります。自分の肌質に合ったものを選ぶことが大切です。
結論:正しい使用と洗浄が鍵
頭皮に日焼け止めを塗ることが直接ハゲる原因になるわけではありません。問題は、落とし残しにあります。 日焼け止めを使用した日は、その日のうちにシャンプーで丁寧に洗い流すことが絶対条件です。
特にスタイリング剤なども併用している場合は、二度洗いやクレンジングシャンプーの使用も検討し、毛穴を清潔な状態に保つよう心がけましょう。
正しく選び、正しく使い、正しく落とす。この3点を守れば、日焼け止めは薄毛のリスクではなく、むしろ頭皮を守る強力な味方となります。
むしろ危険!紫外線が頭皮と髪に与える深刻なダメージ
日焼け止めによる薄毛のリスクを恐れるあまり、無防備な頭皮を紫外線にさらし続けることは、非常によくない選択です。
紫外線は、私たちが思う以上に頭皮と髪に深刻なダメージを与えます。
紫外線が引き起こす「光老化」の恐怖
肌が紫外線を浴び続けることでシミやシワが増える現象を「光老化」と呼びますが、これは頭皮でも同様に起こります。
頭皮は顔の皮膚とつながっており、体の最も高い位置にあるため、紫外線の影響を最も受けやすい部分の一つです。
頭皮が光老化を起こすと、皮膚が硬くなり、血行が悪化し、毛母細胞の働きが鈍る可能性があります。これは、健康な髪を育てる土壌が荒れてしまうことを意味します。
頭皮への具体的な悪影響(炎症・乾燥)
強い紫外線を浴びた直後、頭皮は軽いやけど(日焼け)状態になります。
赤みやヒリヒリとした痛みを伴う炎症が起こると、頭皮のバリア機能が低下します。 バリア機能が低下した頭皮は、水分が蒸発しやすくなり、極度に乾燥します。
乾燥した頭皮は、フケやかゆみの原因になるだけでなく、外部からの刺激に非常に敏感になります。
健康な髪は潤った柔軟な頭皮から生えてくるため、乾燥と炎症は育毛の大敵です。
髪(毛幹)へのダメージ
紫外線は、すでに生えている髪(毛幹)にもダメージを与えます。髪の表面を覆うキューティクルは、紫外線によって剥がれやすく、もろくなります。
キューティクルが損傷すると、髪の内部の水分やタンパク質が流出し、パサつき、枝毛、切れ毛の原因となります。
また、紫外線は髪のメラニン色素も分解するため、髪の色が褪せたり、赤茶けたりすることもあります。
紫外線は薄毛を悪化させる一因か
紫外線が直接的にAGA(男性型脱毛症)の引き金になるわけではありません。
しかし、上記のように頭皮環境(炎症、乾燥、血行不良)を悪化させることは、AGAの進行を助長する、あるいは他の要因による薄毛を悪化させる一因となり得ます。
特に薄毛が気になり始めている方にとって、頭皮環境を健やかに保つことは非常に重要であり、紫外線対策はその基本中の基本と言えます。
紫外線の種類と頭皮への影響
| 紫外線の種類 | 特徴 | 頭皮・髪への主なダメージ |
|---|---|---|
| UVA (紫外線A波) | 波長が長く、雲や窓ガラスを透過しやすい。 | 頭皮の奥(真皮)まで到達し、光老化(弾力低下、硬化)を引き起こす。 |
| UVB (紫外線B波) | 波長が短く、エネルギーが強い。 | 頭皮の表面(表皮)に炎症(日焼け、赤み)を引き起こす。髪のキューティクルを損傷させる。 |
頭皮の紫外線対策 なぜ専用品が推奨されるのか
紫外線の恐ろしさがわかったところで、次に対策です。「手持ちの顔用や体用日焼け止めを頭皮に使っても良いのでは?」と考えるかもしれませんが、それはあまり推奨できません。
頭皮には頭皮用の製品を選ぶべき理由があります。
顔や体用日焼け止めの頭皮使用リスク
顔や体用の日焼け止め、特にクリームやミルク、ジェルタイプは、油分が多く、テクスチャーが重いものが主流です。
これらを髪の毛がある頭皮に塗布しようとすると、髪がベタベタにかたまり、不快な使用感になるだけでなく、毛穴を強力に塞いでしまう可能性が高くなります。
また、均一に塗ることが難しく、塗りムラだらけになりがちです。
そして何より、落としにくい製品が多く、シャンプーだけでは洗い残しが発生しやすく、前述したような毛穴詰まりや炎症のリスクをかえって高めてしまいます。
頭皮用日焼け止めの主な特徴
頭皮用日焼け止めの多くは、スプレータイプを採用しています。これは、髪の毛をかき分けて頭皮に直接、かつ広範囲に塗布しやすくするためです。
成分的にも、頭皮の皮脂分泌量を考慮し、ベタつきを抑えたサラサラとした使用感のものや、清涼感を伴うメントールなどを配合した製品が多く見られます。
また、髪の毛についても考慮し、髪がごわついたり、白くなったりしにくいように工夫されています。
専用品が頭皮環境を守る設計
頭皮は顔や体とは異なる特殊な環境です。毛穴が多く、皮脂腺も活発です。
そのため、頭皮用製品は「毛穴を詰まらせにくいこと」「皮脂と混ざっても不快感が少ないこと」「シャンプーで落としやすいこと」を考慮して設計されています。
さらに、製品によっては、頭皮の乾燥を防ぐ保湿成分や、炎症を抑える成分、育毛環境をサポートする成分が配合されているものもあり、紫外線を防ぎながら同時に頭皮ケアができる点も専用品のメリットです。
顔・体用と頭皮用の日焼け止めの比較
| 項目 | 顔・体用(クリーム・ミルク等) | 頭皮用(スプレー等) |
|---|---|---|
| テクスチャー | 重め・しっとり・油分多め | 軽め・サラサラ・速乾性 |
| 塗布のしやすさ | 髪が邪魔で塗りにくい(ムラ・ベタつき) | 髪をかき分けて広範囲に塗布しやすい |
| 毛穴詰まりリスク | 高い(特に落とし残しの場合) | 比較的低い(製品設計による) |
| 洗浄 | シャンプーだけでは落ちにくい場合がある | シャンプーで落としやすい設計が多い |
後悔しない!頭皮用日焼け止めスプレーの選び方
頭皮用日焼け止めの必要性が理解できたところで、次は具体的な選び方です。多くの製品がスプレータイプですが、どれを選べば良いか迷うかもしれません。
以下の4つのポイントでチェックしましょう。
チェックポイント1:SPFとPA値の適切な選び方
日焼け止めの効果は「SPF」と「PA」という2つの指標で示されます。
SPFとは
SPF (Sun Protection Factor) は、主にUVB(短時間で肌を赤くする紫外線)を防ぐ効果の指標です。
数字が大きいほど防止効果が高く、SPF50+が最大値です。SPF1あたり約20分間の日焼け防止効果があるとされますが、これはあくまで目安です。
PAとは
PA (Protection Grade of UVA) は、UVA(肌の奥深くに届き、光老化を引き起こす紫外線)を防ぐ効果の指標です。「+」の数で示され、「PA++++」が最も高い効果を示します。
頭皮は紫外線を浴びやすいため、高い数値を選びたくなりますが、数値が高いほど肌への負担も増える傾向があります。シーンに合わせて使い分けるのが賢明です。
シーン別SPF/PA値の目安
| 利用シーン | SPF目安 | PA目安 |
|---|---|---|
| 日常生活(通勤、買い物など) | SPF20~30 | PA++~+++ |
| 屋外での軽いスポーツ、レジャー | SPF30~50 | PA+++~++++ |
| 炎天下でのレジャー、マリンスポーツ | SPF50+ | PA++++ |
薄毛が気になる方は、頭皮が露出している部分が多いため、やや高めの数値(SPF30/PA+++以上)を基準に考えると良いでしょう。
チェックポイント2:頭皮へのやさしさを考慮した成分
デリケートな頭皮に直接スプレーするため、配合成分のチェックは重要です。特に肌が敏感な方や、薄毛治療中の方は注意しましょう。
紫外線防御剤の種類
前述の通り、「紫外線吸収剤」フリー(ノンケミカル)の製品は、紫外線散乱剤(酸化チタン、酸化亜鉛など)を使用しており、肌への刺激がマイルドな傾向があります。
ただし、スプレータイプでは技術的に難しく、吸収剤と散乱剤を併用しているものも多いです。吸収剤が必ずしも悪いわけではありませんが、過去にかぶれた経験がある方は避けた方が無難です。
その他の添加物
アルコール(エタノール)は清涼感や速乾性を高めますが、敏感肌や乾燥肌の方には刺激になることがあります。
また、香料や着色料、パラベン(防腐剤)なども、人によっては合わない場合があります。
チェックしたい成分
- 紫外線吸収剤(メトキシケイヒ酸エチルヘキシル等)
- アルコール(エタノール)
- パラベン
- 合成香料・合成着色料
可能な限り、これらの成分がフリー(無添加)であったり、配合量が少ないものを選んだり、保湿成分(ヒアルロン酸、コラーゲン、セラミドなど)や抗炎症成分(グリチルリチン酸2Kなど)が配合されている製品を選ぶと、頭皮への負担を軽減できます。
チェックポイント3:使用感(ベタつき・香り)
毎日快適に使い続けるためには、使用感も大切です。頭皮用スプレーは「サラサラ」「速乾」を謳う製品が多いですが、中にはオイリーに感じるものもあります。
口コミなどを参考に、自分の皮脂量や好みに合ったテクスチャーを選びましょう。 また、香りも重要な要素です。
無香料タイプが最も無難ですが、汗のニオイをカバーするシトラス系やミント系の香り付き製品もあります。強い香りは周囲への配慮も必要になるため、テスターなどで確認できると安心です。
チェックポイント4:洗浄のしやすさ
最も重要なポイントの一つが「落としやすさ」です。製品パッケージに「いつものシャンプーで落ちる」「石けんでオフ」といった記載があるものを選びましょう。
「専用クレンジングが必要」と書かれたウォータープルーフタイプは、日常生活では洗浄の負担が大きくなるため、海やプールなど、絶対に焼きたくない特別なシーンに限定するのがおすすめです。
落とし残しこそが、毛穴詰まりや頭皮トラブルの最大の原因であることを忘れないでください。
効果半減?頭皮用日焼け止めの正しい使い方と注意点
せっかく選んだ頭皮用日焼け止めも、使い方が間違っていては十分な効果を発揮できません。それどころか、トラブルの原因になることもあります。
正しい使い方をマスターしましょう。
使用前の準備(パッチテストと攪拌)
新しい製品を初めて使う前には、必ずパッチテストを行いましょう。二の腕の内側などに少量スプレーし、24時間程度様子を見て、赤みやかゆみが出ないか確認します。
また、スプレータイプの多くは、成分が分離・沈殿しているため、使用直前にカチカチと音が鳴るまでしっかり振る(攪拌する)必要があります。
これを怠ると、防御成分が均一に出ず、効果にムラができてしまいます。
正しいスプレーの距離と塗布量
頭皮にスプレーする際は、髪の毛ではなく、頭皮に直接届けることを意識します。製品にもよりますが、一般的に頭皮から10cm~15cmほど離してスプレーします。
近すぎると一箇所に集中して液だれし、遠すぎると髪にばかり付着して頭皮に届きません。シューッと円を描くように動かしながらスプレーするか、数カ所に分けてスプレーします。
塗りムラを防ぐためのコツ
最も日焼けしやすいのは、分け目、つむじ、そして生え際です。特に薄毛が進行している方は、頭頂部全体が危険ゾーンです。
片方の手で髪の毛をかき分けながら、露出した頭皮にスプレーしていくのが最も確実です。分け目を変えながら、頭皮全体にジグザグにかけるイメージで行いましょう。
スプレーした後に軽く指の腹でなじませると、より均一になりますが、こすりすぎないよう注意してください。
塗り直しの適切な頻度
日焼け止めは、汗や皮脂、摩擦によって時間とともに落ちてしまいます。SPF値が高いからと安心せず、こまめな塗り直しが必要です。
目安として、2~3時間おきに塗り直すのが理想です。特に屋外で汗をかいた後や、タオルで頭を拭いた後は、必ず塗り直しましょう。
塗り直しの際も、可能であれば一度汗や皮脂を軽くティッシュなどで押さえてからスプレーすると、より密着しやすくなります。
頭皮用日焼け止めのNGな使い方
| NGな使い方 | 理由 | 正しい対策 |
|---|---|---|
| 髪の上から全体にかけるだけ | 髪がガードしてしまい、肝心の頭皮に届いていない。 | 髪をかき分け、頭皮に直接スプレーする。 |
| 振らずにすぐに使う | 成分が分離しており、十分な紫外線防御効果が得られない。 | カチカチと音が鳴るまで、使用直前によく振る。 |
| 朝塗ったきりで塗り直さない | 汗や皮脂で流れ落ちてしまい、午後には効果が薄れている。 | 2~3時間おきを目安にこまめに塗り直す。 |
日焼け止め以外の紫外線対策とアフターケア
頭皮を守る方法は、日焼け止めスプレーだけではありません。他の対策と組み合わせることで、防御力は格段に上がります。
また、万が一焼けてしまった後のケアも重要です。
帽子による物理的な防御
最も簡単で効果的なのが、帽子をかぶることです。物理的に紫外線をシャットアウトできます。ただし、帽子選びには注意が必要です。
帽子選びで重視したい点
- UVカット加工(UPF50+など)
- 通気性(メッシュ素材、通気孔)
- 色(濃い色の方が紫外線防止効果は高いが、熱を吸収しやすい)
- つばの広さ(広いほど顔や首筋もカバーできる)
注意点は、帽子の中が蒸れやすいことです。長時間かぶりっぱなしにすると、汗や皮脂で雑菌が繁殖し、かえって頭皮環境を悪化させる可能性があります。
適度に脱いで換気し、清潔に保つことが大切です。日焼け止めスプレーと帽子を併用するのが最強の対策と言えるでしょう。
日傘の活用メリット
近年は「日傘男子」という言葉も登場し、男性が日傘を使うことへの抵抗感も薄れてきました。
日傘は、頭皮だけでなく顔や体全体を紫外線から守れる上に、直射日光を遮ることで体感温度を下げる効果も期待できます。 帽子のように蒸れる心配がないのも大きなメリットです。
選ぶ際は、UVカット率が高く、遮光性・遮熱性に優れたもの、そして持ち歩きやすい軽量でコンパクトなタイプがおすすめです。
頭皮が日焼けしてしまった場合の対処法
対策をしていても、うっかり焼けてしまうことはあります。頭皮がヒリヒリする、赤いと感じたら、すぐに応急処置を行いましょう。
頭皮の日焼け後のケア手順
| ステップ | 具体的な方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 1.冷やす | 冷たい水で濡らしたタオルや、保冷剤をタオルで包んだものを頭皮に当てる。 | 保冷剤や氷を直接当てないこと(凍傷のリスク)。 |
| 2.優しく洗う | 当日のシャンプーは、低刺激・アミノ酸系のものを使い、ぬるま湯で優しく洗う。 | 熱いお湯、爪を立てる、強くこするのは絶対に避ける。 |
| 3.保湿する | 頭皮用のローションや、敏感肌用の化粧水などで、失われた水分を補給する。 | アルコールやメントール配合のものは刺激になるため避ける。 |
炎症がひどい場合や、水ぶくれができた場合は、自己判断せず速やかに皮膚科を受診してください。
よくある質問
- 頭皮用日焼け止めは毎日使うべきですか?
-
紫外線の強さや、屋外で過ごす時間によります。春先から秋口にかけては、紫外線量が増えるため、日常的に使うことを推奨します。
特に通勤や外出で10分以上屋外に出る場合は、習慣にすると良いでしょう。薄毛が気になる部分は皮膚が露出しやすいため、特に注意が必要です。
- スプレータイプ以外に頭皮用はありますか?
-
数は少ないですが、存在します。分け目などに直接塗れるスティックタイプや、液状で先端がノズルになっているタイプ、パウダータイプなどがあります。
スプレーの飛び散りが気になる方や、特定の場所(分け目など)にピンポイントでしっかり塗りたい方には、そうしたタイプも選択肢になります。
- 使用期限切れの日焼け止めは使えますか?
-
使用しないでください。未開封で3年、開封後は半年~1年が一般的な目安ですが、保管状況によっても異なります。
古い日焼け止めは、紫外線防御効果が低下しているだけでなく、成分が酸化・変質して肌トラブルを引き起こす可能性が非常に高くなります。
頭皮はデリケートなため、毎シーズン新しいものを購入することをおすすめします。
- 日焼け止めはシャンプーだけで落ちますか?
-
「シャンプーで落ちる」と記載のある製品であれば、基本的には落ちます。
ただし、スタイリング剤や他の頭皮ケア製品と混ざっている場合や、皮脂量が多い方は、一度のシャンプーでは不十分なことがあります。
洗い上がりがベタつく、スッキリしないと感じる場合は、二度洗いするか、頭皮用のクレンジングオイルなどをシャンプー前に使用することも検討してください。
洗浄不足が最も避けるべきことですので、丁寧に洗い流しましょう。
Reference
FUNG, Ernest S.; PARKER, Jillian A.; MONNOT, Andrew D. Evaluating the impact of hair care product exposure on hair follicle and scalp health. Alternatives to Laboratory Animals, 2023, 51.5: 323-334.
TRÜEB, Ralph M., et al. Scalp condition impacts hair growth and retention via oxidative stress. International journal of trichology, 2018, 10.6: 262-270.
TRÜEB, Ralph M. Effect of ultraviolet radiation, smoking and nutrition on hair. Curr Probl Dermatol, 2015, 47: 107-120.
MIRMIRANI, Paradi; VANDERWEIL, Stefan G. Frontal fibrosing alopecia with involvement of the central hair part: distribution of hair loss corresponding to areas of sunscreen application. Dermatology Online Journal, 2020, 26.11.
DAVIS, Michael G., et al. Scalp application of antioxidants improves scalp condition and reduces hair shedding in a 24‐week randomized, double‐blind, placebo‐controlled clinical trial. International Journal of Cosmetic Science, 2021, 43: S14-S25.
ALDOORI, N., et al. Frontal fibrosing alopecia: possible association with leave‐on facial skin care products and sunscreens; a questionnaire study. British Journal of Dermatology, 2016, 175.4: 762-767.
DRAELOS, Zoe Diana. Sunscreens and hair photoprotection. Dermatologic clinics, 2006, 24.1: 81-84.
SANTOS, Júlia Scherer; BARRADAS, Thais Nogueira; TAVARES, Guilherme Diniz. Advances in nanotechnology‐based hair care products applied to hair shaft and hair scalp disorders. International journal of cosmetic science, 2022, 44.3: 320-332.
CEDIRIAN, Stephano, et al. The exposome impact on hair health: non-pharmacological management. Part II⋆. Anais Brasileiros de Dermatologia, 2025.