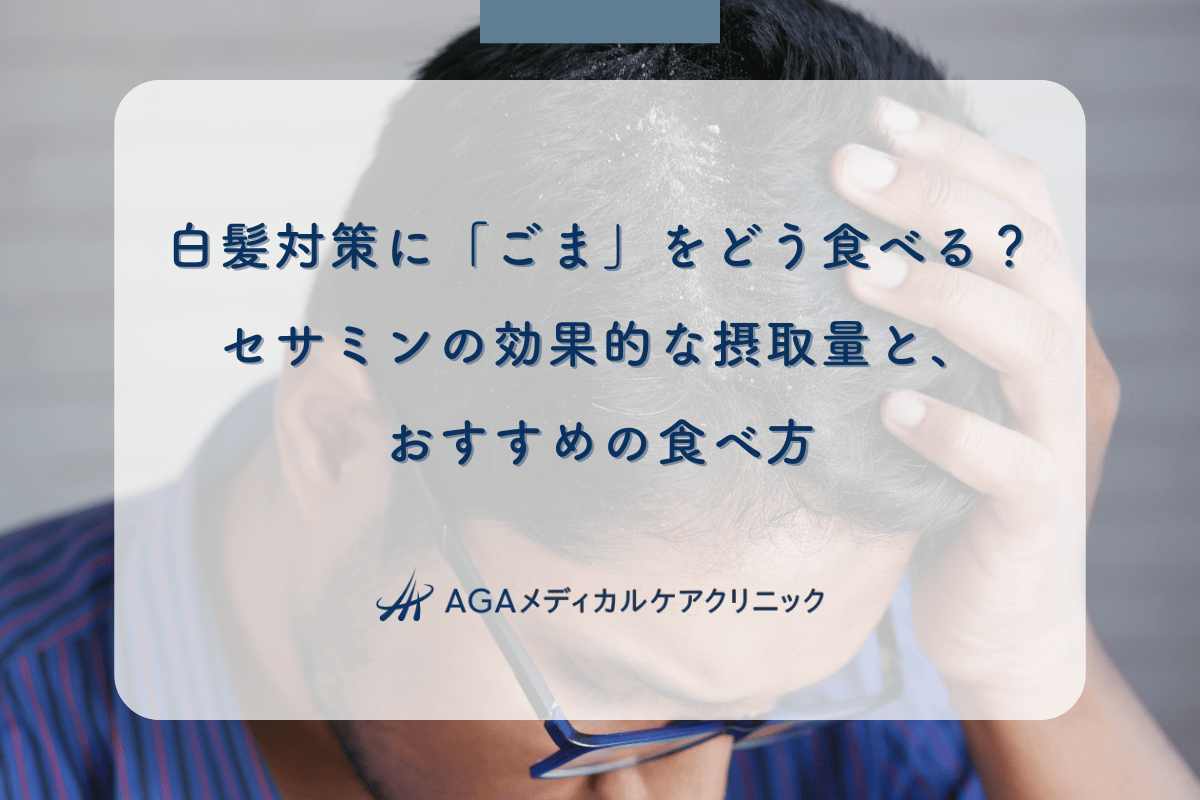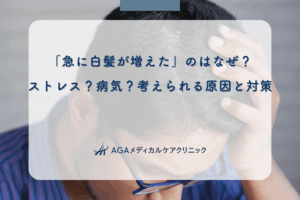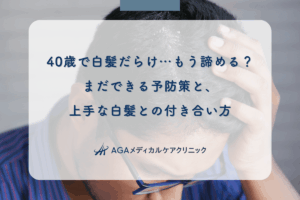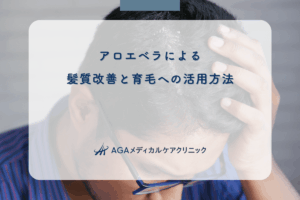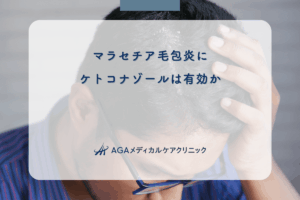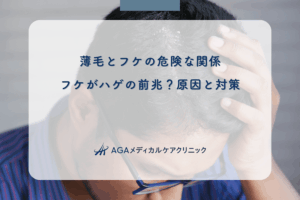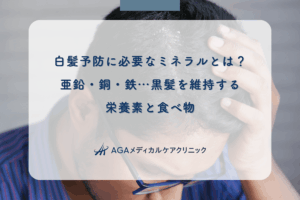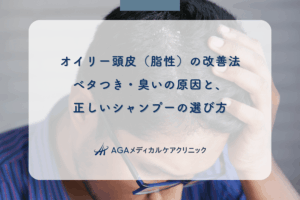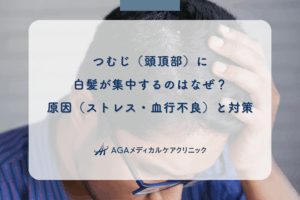最近、鏡を見るたびに白髪が気になり始めた、あるいは白髪予防に関心がある男性も多いのではないでしょうか。
白髪対策として「ごま」が良いと聞いたことはあっても、なぜ良いのか、どう食べれば効率的なのか具体的には知らない方もいるかもしれません。
ごまに含まれる「セサミン」をはじめとする栄養素は、確かに白髪対策の強い味方となり得ます。しかし、ただやみくもに食べるだけでは、その力を十分に引き出せないかもしれません。
この記事では、なぜごまが白髪対策に注目されるのか、その理由と、セサミンの効果的な摂取量、そして毎日続けやすいおすすめの食べ方について、男性の視点から詳しく解説します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
なぜ「ごま」が白髪対策に注目されるのか?
髪の色を決めるメラニン色素
私たちの髪が黒いのは、「メラニン」という色素のおかげです。このメラニンは、髪の毛の根元、毛球部にある「メラノサイト(色素形成細胞)」によって生成されます。
白髪は、このメラノサイトの働きが何らかの理由で低下したり、メラノサイト自体が減少したりすることで、メラニン色素が作られなくなり、髪に色がつかないまま生えてくる状態を指します。
年齢を重ねることが主な原因とされていますが、それ以外にも様々な要因が関係しています。
メラノサイトの働きと白髪の関係
メラノサイトが正常に働くためには、十分な栄養と健康な頭皮環境が必要です。しかし、年齢とともにメラノサイト自体の機能は低下しやすくなります。
また、頭皮の血流が悪くなると、メラノサイトに必要な栄養素が届きにくくなり、メラニンの生成が滞る原因にもなります。
したがって、白髪対策とは、このメラノサイトの働きをいかに維持し、サポートするかという点が非常に重要になります。
ごまに含まれる栄養素の力
ごまは、古くから健康食材として知られる通り、豊富な栄養素を含んでいます。特に注目したいのが、ごま特有の成分である「セサミン」です。
セサミンは、強力な抗酸化作用を持つことで知られています。
さらに、良質なたんぱく質、ビタミンE、ビタミンB群、カルシウム、鉄分、亜鉛など、髪の健康を維持するために必要な栄養素がバランスよく含まれています。
これらの栄養素が総合的に働くことで、白髪対策をサポートすると期待されています。
白髪を引き起こす主な要因
白髪の最も大きな原因は加齢によるものですが、それ以外にも無視できない要因がいくつかあります。
これらの要因が複雑に絡み合い、メラノサイトの働きを低下させ、白髪を引き起こすと考えられています。
白髪に関わる要因の概要
| 要因 | 概要 |
|---|---|
| 遺伝的要因 | 白髪になりやすい体質、始まる時期などは遺伝的な影響があると考えられています。 |
| ストレス | 過度な精神的ストレスは自律神経のバランスを乱し、頭皮の血流を悪化させる可能性があります。 |
| 栄養不足 | 髪の健康やメラニンの生成に必要な栄養素(たんぱく質、ミネラル、ビタミン)が不足すること。 |
| 生活習慣 | 睡眠不足、喫煙、過度な飲酒、運動不足なども、頭皮環境や血流に悪影響を与えると考えられています。 |
ごまに含まれる栄養素は、特に「栄養不足」の面からアプローチし、メラノサイトの働きをサポートするのに役立ちます。
白髪対策の鍵「セサミン」の抗酸化作用とは
セサミンの基礎知識
セサミンは、「ゴマリグナン」と呼ばれるごま特有の成分群の一種です。ごま一粒の中に、ゴマリグナン全体でもわずか1%未満しか含まれていない希少な成分ですが、その健康効果は非常に注目されています。
セサミンは、摂取すると体内で強力な抗酸化物質として働く能力を持っていることが、さまざまな研究で示されています。
活性酸素が頭皮に与える影響
私たちは呼吸によって酸素を取り込みますが、その過程で一部の酸素は「活性酸素」という非常に酸化力の強い物質に変わります。
活性酸素は、体内に侵入したウイルスや細菌を攻撃する重要な役割も持ちますが、紫外線、ストレス、不規則な生活などで過剰に発生すると、正常な細胞まで傷つけてしまいます。
この「酸化ストレス」が、老化や様々な不調の原因の一つとされています。
頭皮も例外ではなく、活性酸素によってメラノサイトがダメージを受けると、その機能が低下し、メラニンを正常に作れなくなり、白髪の原因になると考えられています。
セサミンによる抗酸化サポート
セサミンが白髪対策で注目される最大の理由は、この活性酸素の働きを抑制する強力な「抗酸化作用」です。
セサミンは、他の多くの抗酸化物質が水溶性であったり、体内の特定の場所でしか働けなかったりするのに対し、脂溶性でありながら主に肝臓で代謝されることで、体の隅々までその抗酸化作用を届けやすいというユニークな特徴があります。
これにより、頭皮や毛根の細胞を活性酸素のダメージから守り、メラノサイトが健康に働く環境を維持するサポートが期待できるのです。
メラノサイトを守る働き
セサミンの抗酸化作用は、白髪の直接的な原因となるメラノサイトの機能低下を防ぐ上で重要です。
メラノサイトが活性酸素による酸化ダメージを受け続けると、メラニンを生成する能力が徐々に衰えてしまいます。
セサミンがこの酸化ストレスを軽減することで、メラノサイトは本来の働きを維持しやすくなり、結果として白髪の予防や進行を遅らせる可能性が期待されます。
セサミンだけじゃない!ごまが持つ髪に良い栄養素
髪の主成分「たんぱく質」
髪の毛の約90%は「ケラチン」という複数のアミノ酸が結合したたんぱく質でできています。ごまには、植物性食品の中でも比較的良質なたんぱく質が豊富に含まれています(重量の約20%)。
良質なたんぱく質を摂取することは、丈夫で健康な髪を育てるための大前提です。
たんぱく質が不足すると、髪が細くなったり、ツヤが失われたりするだけでなく、新しい髪の成長自体が妨げられる可能性があります。
血行を促進する「ビタミンE」
ビタミンEは「若返りのビタミン」とも呼ばれ、セサミン同様、強い抗酸化作用を持つ脂溶性ビタミンです。それと同時に、末梢血管を拡張させ、血流をスムーズにする働きがあります。
頭皮の血行が良くなることで、髪の成長やメラニンの生成に必要な栄養素や酸素が、毛根の末端にあるメラノサイトまでしっかりと運ばれるようになります。
セサミンとビタミンEは、一緒に摂取することで相乗効果が期待できるとも言われています。
代謝を助ける「ビタミンB群」
ごまには、ビタミンB1、B2、B6、ナイアシンなどのビタミンB群も含まれています。
ビタミンB群は、私たちが摂取したたんぱく質や脂質、糖質といった栄養素の代謝を助ける「補酵素」として働きます。
特にビタミンB2やB6は、頭皮の皮脂バランスを整えたり、摂取したたんぱく質が髪の毛(ケラチン)に再合成されるのを助けたりする重要な役割があり、健康な頭皮環境と髪の成長に必要です。
ミネラルの役割「亜鉛・鉄・カルシウム」
ごまには、髪の健康に重要なミネラルも豊富に含まれています。特に注目したいのが亜鉛、鉄、そしてカルシウムです。
ごまに含まれる主要ミネラルと髪への役割
| ミネラル | 髪への主な役割 |
|---|---|
| 亜鉛 | たんぱく質の合成(ケラチンの生成)に深く関わります。不足すると髪の成長が遅れることがあります。 |
| 鉄 | 血液中のヘモグロビンの材料となり、頭皮を含む全身への酸素運搬を助けます。 |
| カルシウム | メラノサイトがメラニンを生成する際の細胞の働きに関与すると言われています。 |
これらのミネラルがどれか一つでも不足すると、髪の成長サイクルやメラニンの生成に支障をきたし、抜け毛や白髪の原因にもなり得ます。
ごまは、これらのミネラルをバランスよく補給できる優れた食材です。
効果的なセサミンの摂取量「一日どれくらい」?
セサミンの摂取目安量
セサミンの摂取目安量として、健康維持や抗酸化作用を期待する上で「一日あたり10mg」が推奨されることが多いです。
これはセサミン単体での量であり、ごまから摂取する場合は他の栄養素とのバランスも考慮する必要があります。
サプリメントなどでセサミンをピンポイントで摂取する方法もありますが、まずは食品から摂ることが基本となります。
ごまに換算するとどれくらい?
セサミンは、前述の通りごま一粒にわずか0.5%〜1%程度しか含まれていません。仮にセサミンの含有率を0.5%と仮定すると、セサミン10mgを摂取するためには、単純計算で約20gのごまが必要になります。
含有率が1%であれば10gです。
ごまの種類や産地によっても含有量は異なりますが、一般的に「一日あたり10g〜20g」のごまを摂取することが一つの目安となります。
ごまの量とカロリーの目安
| ごまの量 | 重量(目安) | カロリー(目安) |
|---|---|---|
| 大さじ1杯 | 約9g〜10g | 約54kcal〜60kcal |
| 大さじ2杯 | 約18g〜20g | 約108kcal〜120kcal |
セサミン10mgを確実に摂ることを目指す場合、大さじ1〜2杯程度を毎日の食事に取り入れるのが現実的なラインと言えるでしょう。
摂取の上限と注意点
ごまは栄養価が非常に高い一方で、その成分の約50%は脂質で構成されており、カロリーも決して低くありません。
白髪対策に良いからといって食べ過ぎると、カロリーオーバーとなり、体重増加につながる可能性があります。
また、脂質が多いため、一度に大量に食べると消化不良を起こし、胃がもたれたり、お腹を下したりする原因にもなります。
何事も「適量」が大切であり、一日大さじ1〜2杯(10g〜20g)程度を目安に、毎日継続して摂取することを心がけましょう。
継続することが最も重要
白髪対策は、薬のようにすぐに結果が出るものではありません。ごまに含まれるセサミンやその他の栄養素によるサポートは、あくまで長期的な体質改善や健康維持の一環です。
大切なのは、一度にたくさん食べることではなく、適量を毎日コツコツと続けることです。数日食べたからといって、すぐに白髪が減るわけではありません。
無理のない範囲で食生活に取り入れ、それを習慣化することを目指しましょう。
ごまの栄養を効率よく摂る「食べ方」の工夫
「すりごま」がおすすめな理由
ごまの粒は、非常に硬い皮(種皮)で覆われています。
この皮は人間の消化酵素では分解されにくいため、「粒のまま(いりごまなど)」の状態で食べても、せっかくの栄養素、特にセサミンやビタミンEなどが十分に消化・吸収されずに、そのまま体外へ排出されてしまうことがほとんどです。
ごまの栄養を効率よく摂取するためには、この硬い皮を砕いて中身を吸収しやすくする「すりごま」の状態にして食べることが最もおすすめです。
「いりごま」と「洗いごま」の違い
市販されているごまには「いりごま」と「洗いごま」がありますが、そのまま食べる場合は「いりごま」を選びます。「洗いごま」は生の状態なので、食べる前にフライパンなどで加熱(煎る)する必要があります。
風味を最も楽しむには、いりごまを購入し、食べる直前に自分ですり鉢でするのが一番ですが、毎日の手軽さを重視するなら、市販されている「すりごま」を常備しておくと非常に便利です。
「ねりごま(ペースト)」の活用
「ねりごま」は、ごまをすり潰してペースト状にしたものです。すりごま以上に細かくなっているため、消化吸収の面では非常に優れています。油分が分離しやすい特性がありますが、栄養は丸ごと摂取できます。
ドレッシングやタレ、和え物はもちろん、牛乳や豆乳に混ぜてドリンクにするなど、液状のものにも溶けやすく、活用の幅が広いのも魅力です。
ただし、すりごまよりも脂質を感じやすいため、使う量には注意しましょう。
ごまの加工状態と特徴
| 種類 | 状態 | 栄養吸収のしやすさと使い方 |
|---|---|---|
| 洗いごま | 生の状態 | 吸収しにくい。加熱(煎る)が必要。 |
| いりごま | 煎った状態(粒) | 吸収しにくい。風味付けには良いが、栄養摂取目的では非効率。 |
| すりごま | 煎ってすった状態(粉末) | 吸収されやすい。最もおすすめ。和え物やふりかけに便利。 |
| ねりごま | ペースト状 | 非常に吸収されやすい。タレやドレッシング、ドリンクに。 |
加熱による影響は?
セサミン自体は、熱に対して比較的安定した成分とされています。そのため、ごまを煎ったり、料理に加えて加熱したりしても、その抗酸化作用が大きく損なわれることは少ないと考えられています。
ただし、ビタミンB群など他の栄養素の中には熱に弱いものも含まれています。とはいえ、日常的な料理(和え物や味噌汁に入れる程度)の範囲であれば、過度に神経質になる必要はありません。
栄養を効率よく摂るには「する(すりごま)」か「練る(ねりごま)」が鍵と覚えておきましょう。
白髪対策におすすめ!ごま(セサミン)の食べ合わせ
ビタミンEとの相乗効果
セサミンとビタミンEは、どちらも強力な抗酸化作用を持つ成分です。研究によれば、この二つを一緒に摂ることで、お互いの働きを高め合い、より強い抗酸化サポートが期待できると言われています。
ごま自体にもビタミンEは含まれていますが、ビタミンEを多く含む他の食材と組み合わせることで、さらにその効果を高めることができます。
ごまと一緒に摂りたいビタミンE
- アーモンド、ピーナッツなどのナッツ類
- アボカド
- かぼちゃ、赤ピーマン
- 植物油(オリーブオイル、ひまわり油など)
例えば、ごまとアーモンドを砕いてサラダにトッピングしたり、かぼちゃの煮物にごまを和えたりするのは、非常に良い組み合わせです。
たんぱく質との組み合わせ
髪の主成分である「ケラチン(たんぱく質)」をしっかり摂ることも、白髪対策や健康な髪を育てるためには絶対に必要です。
ごまに含まれるたんぱく質は植物性ですが、必須アミノ酸の一部(リジンなど)が少なめです。
そこで、動物性たんぱく質(肉、魚、卵)や、他の植物性たんぱく質(大豆製品)と組み合わせることで、アミノ酸バランスが向上し、体内で効率よくたんぱく質を利用できます。
おすすめのたんぱく質源
納豆にごまを混ぜる、豆腐の冷奴にごまダレをかける、鶏肉や豚肉の料理(棒棒鶏やしゃぶしゃぶ)にごまダレを使う、卵焼きにごまを混ぜるなど、日常的にたんぱく質とごまをセットで摂ることを意識しましょう。
ミネラルの吸収を助ける工夫
ごまに含まれる亜鉛や鉄といったミネラルは、ビタミンCやクエン酸(酸味)と一緒に摂ることで、体内への吸収率が上がるとされています。
一方で、食物繊維やフィチン酸(穀類や豆類に多い)は、これらのミネラルの吸収をやや妨げることがあります。
ミネラルの吸収率を高める組み合わせ
| 栄養素 | 多く含む食材例 | 組み合わせ例 |
|---|---|---|
| ビタミンC | ピーマン、ブロッコリー、柑橘類 | ピーマンやブロッコリーのごま和え。 |
| クエン酸 | 酢、梅干し、レモン | ごまを使った酢の物(わかめ、きゅうり等)。 |
例えば、定番の「ほうれん草のごま和え」に、食べる直前に少しレモン汁を搾ったり、「わかめときゅうりの酢の物」にごまをたっぷり入れたりするのは、ミネラルの吸収効率を高める上でも非常に理にかなった食べ方です。
毎日の習慣に!簡単なごま摂取レシピ
定番「ごま和え」
最も王道な食べ方です。ほうれん草や小松菜、いんげん、にんじん、ブロッコリーなど、お好みの野菜を茹でて、すりごま、醤油、砂糖(またはみりん)で和えるだけです。
野菜に含まれるビタミンやミネラルも同時に摂取でき、副菜として非常に優秀です。野菜の種類を変えることで、飽きずに続けやすいのも大きな魅力です。
かけるだけ「ふりかけ・トッピング」
最も手軽で、毎日続けやすい方法が、すりごまをそのまま様々な料理にかけることです。
「かけるだけ」の活用例
- 白米や玄米にふりかける(塩と混ぜて「ごま塩」にしても良い)。
- 納豆や冷奴に、ネギなどの薬味と一緒にかける。
- 味噌汁やスープに、食べる直前にスプーン一杯加える。
- サラダにドレッシングと一緒にかける。
このように、いつもの食事に「プラスワン」する感覚で取り入れると、無理なく習慣化できます。風味も良くなり、食事の満足度も上がります。
ドリンクで摂る「ごまバナナ豆乳」
朝食や間食として、ドリンクで摂るのもおすすめです。ミキサー(ブレンダー)があれば簡単に作れます。
材料(1人分)
豆乳(または牛乳)を150ml〜200ml、バナナを1/2本〜1本、そして「すりごま」または「ねりごま」を大さじ1杯入れ、ミキサーで撹拌します。
お好みではちみつやきなこを加えても美味しく、たんぱく質をさらに強化できます。忙しい朝でも、これ一杯でセサミンとたんぱく質、ビタミン、ミネラルを効率よく補給できます。
「万能ごまダレ」を常備する
市販のゴマだれも便利ですが、自分で作っておくと添加物を気にせず、好みの味に調整できます。「ねりごま」を使ったタレは、様々な料理に使えて便利です。
自家製ごまダレの例(作りやすい分量)
ねりごま(大さじ3)、醤油(大さじ2)、酢(大さじ1)、砂糖(またはみりん)(大さじ1)、(お好みで)ごま油やだし汁(少々)。
これらを滑らかになるまでよく混ぜ合わせるだけで完成です。冷蔵庫で数日間保存可能です。サラダ、温野菜、しゃぶしゃぶ、冷やし中華、棒棒鶏(バンバンジー)など、幅広く活用できます。
白髪対策に戻る
よくある質問
- 黒ごま、白ごま、金ごま、どれが一番白髪に良いですか?
-
ごまの種類(黒・白・金)によって、白髪対策の鍵となる「セサミン(ゴマリグナン)」の含有量に大きな差は無いとされています。
そのため、白髪対策という点では、どのごまを選んでも大きな違いはないと考えて良いでしょう。ただし、栄養成分にはわずかな違いがあります。
黒ごまは皮の部分にアントシアニン(ポリフェノールの一種)を含み、白ごまは脂質の割合がやや高め、金ごまは香りが豊かといった特徴があります。
風味の好みや料理に合わせて使い分けるのがおすすめです。大切なのは種類よりも「すりごま」や「ねりごま」の形態で、しっかり栄養を吸収できる形で摂ることです。
- ごまを食べ過ぎるとどうなりますか?
-
ごまはその成分の約50%が脂質でできており、カロリーが高い(大さじ1杯で約60kcal)食品です。
一日大さじ1〜2杯(10g〜20g)程度が適量ですが、これを超えて大量に食べ続けると、カロリーオーバーによる体重増加につながる可能性があります。
また、脂質が多いため、一度に大量に食べると消化不良を起こし、胃がもたれたり、お腹を下したりする原因にもなります。何事も適量を守ることが健康には重要です。
- ごまを毎日食べると、どれくらいで白髪への効果が期待できますか?
-
ごまの摂取は、白髪を直接「治す」ための治療ではなく、あくまで白髪の「予防」や、頭皮環境を健やかに保つための「栄養サポート」です。
すでに白髪になってしまった髪が、ごまを食べたからといって黒髪に戻ることは基本的にはありません(稀に栄養状態の改善で根元から黒くなる例もあるとされますが、一般的ではありません)。
ごまの栄養素、特にセサミンの抗酸化作用によってメラノサイトの働きをサポートし、これから新しく生えてくる髪が白髪になるのを遅らせたり、防いだりすることを期待するものです。
ヘアサイクル(髪が生え変わる周期)や体質改善には時間がかかるため、数週間や数ヶ月で劇的な変化を感じることは難しいでしょう。
最低でも半年から1年、あるいはそれ以上、健康習慣の一つとして長く続けることが重要です。
- セサミンのサプリメントと、ごまを食べるのはどちらが良いですか?
-
セサミンを手軽に効率よく摂取したい場合、サプリメントの活用も一つの有効な方法です。
サプリメントであれば、ごまの脂質やカロリーを気にすることなく、安定した量のセサミンを摂取できます。
一方、ごまを「食品」として食べる最大の利点は、セサミンだけでなく、髪の材料となる良質なたんぱく質、血行を助けるビタミンE、代謝に必要なビタミンB群、そして亜鉛や鉄といった各種ミネラルも同時にバランスよく摂取できる点です。
白髪対策はセサミンだけが全てではなく、こうした総合的な栄養バランスが頭皮環境を整える上で非常に重要です。
まずは食事から「すりごま」や「ねりごま」を取り入れることを基本とし、食生活が不規則でごまを毎日摂るのが難しい場合に、サプリメントで補うという考え方が現実的かもしれません。
Reference
MANOSROI, Jiradej, et al. 5α-reductase inhibition and melanogenesis activity of sesamin from sesame seeds for hair cosmetics. Chiang Mai J Sci, 2015, 42.3: 669-80.
SUBRAHMANIYAN, K., et al. A comprehensive review on nutritional and antioxidant properties of Sesame (Sesamum indicum L.) seed oil with its therapeutic utilization as phytomedicine. Annals of Phytomedicine, 2024, 13.2: 1-9.
GUPTA, Arti; KUMAR, Pentapati Siva Santosh. Ameliorating Effects of Sesame Oil Against Toxicity. In: Sesame: Sustainable Production and Applications. Singapore: Springer Nature Singapore, 2025. p. 209-229.
YADAV, Mahipat S.; KUSHWAHA, Neeti; MAURYA, Neelesh K. The Influence of Diet, Lifestyle, and Environmental Factors on Premature Hair Greying: An Evidence-Based Approach. Archives of Clinical and Experimental Pathology, 2025, 4.1.
KHATOON, Shabana. AN INSIGHT INTO SESAMOL: PHARMACOLOGICAL ACTIVITIES, AND FUTURE RESEARCH PROSPECTS. 2022. PhD Thesis. Department of Zoology, Aligarh Muslim University, Aligarh, India.
TAKEMOTO, Daisuke, et al. Sesame lignans and vitamin E supplementation improve subjective statuses and anti-oxidative capacity in healthy humans with feelings of daily fatigue. Global journal of health science, 2015, 7.6: 1.
MYSORE, Venkataram; ARGHYA, Arpita. Hair oils: indigenous knowledge revisited. International journal of trichology, 2022, 14.3: 84-90.
NAMIKI, Mitsuo. The chemistry and physiological functions of sesame. Food reviews international, 1995, 11.2: 281-329.
YASEEN, Ghulam, et al. Sesame (Sesamum indicum L.). In: Green Sustainable Process for Chemical and Environmental Engineering and Science. Elsevier, 2021. p. 253-269.