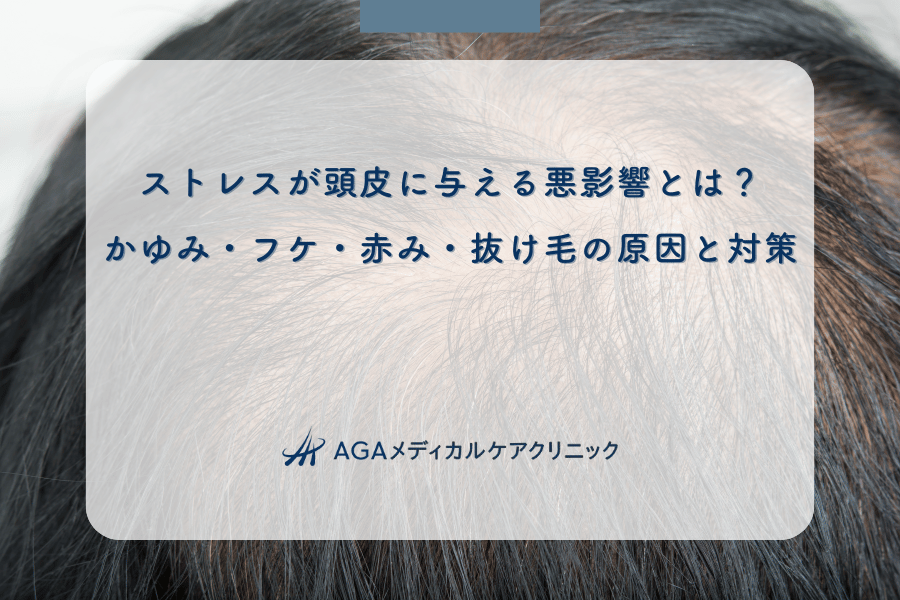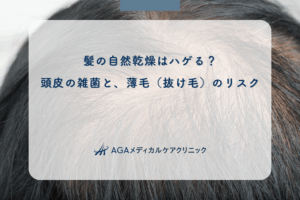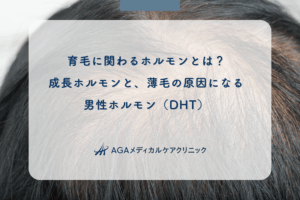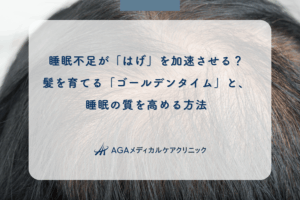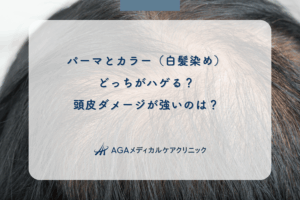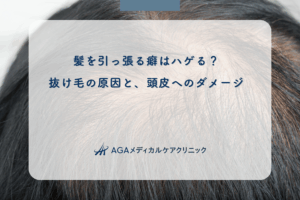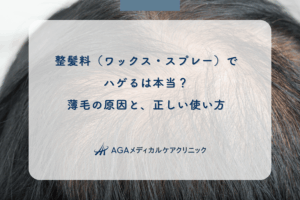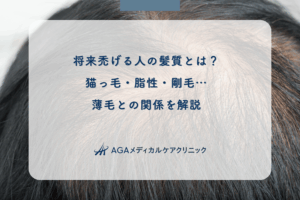現代社会を生きる男性にとって、ストレスは避けて通れない問題です。仕事、人間関係、将来への不安など、日々感じるプレッシャーが、知らず知らずのうちに心身を蝕んでいきます。
そして、その影響が顕著に現れる場所の一つが「頭皮」です。最近、「頭がかゆい」「フケが目立つ」「抜け毛が増えた気がする」と感じていませんか。
それはもしかすると、ストレスが発する危険信号かもしれません。この記事では、ストレスがなぜ頭皮トラブルを引き起こすのか、その具体的な症状と原因を詳しく解説します。
さらに、今日から実践できる対策法まで、あなたの悩みに寄り添いながら丁寧に紹介します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
ストレスが頭皮に与える深刻な影響
多くの方が漠然と「ストレスは髪に悪い」というイメージを持っていますが、具体的にどのような影響があるのでしょうか。
ストレスは単なる精神的な問題に留まらず、体内で複雑な反応を引き起こし、頭皮環境を直接的に悪化させます。この関係性を理解することが、対策への第一歩となります。
なぜストレスが頭皮トラブルを引き起こすのか
私たちがストレスを感じると、体は「緊急事態」と判断し、防御反応を示します。この反応が、頭皮の健康を維持するために必要な体の正常な働きを妨げてしまうのです。
特に、自律神経やホルモンバランスの乱れは、頭皮環境に即座に影響を与えます。ストレスが慢性化すると、頭皮は常に緊張状態にさらされ、さまざまなトラブルが発生しやすい土壌ができあがります。
自律神経の乱れと血行不良
強いストレスを受けると、自律神経のうち交感神経が優位な状態が続きます。交感神経は血管を収縮させる働きを持つため、頭皮の毛細血管も細くなります。
その結果、髪の毛の成長に必要不可欠な栄養素や酸素が、毛根(毛母細胞)まで十分に行き渡らなくなります。これが「血行不良」の状態です。
栄養不足に陥った毛髪は細く弱々しくなり、正常なヘアサイクルを維持できず、抜け毛や薄毛の原因となります。
ホルモンバランスの変動
ストレスはホルモンバランスにも大きな影響を及ぼします。特に男性ホルモンの一種であるジヒドロテストステロン(DHT)は、AGA(男性型脱毛症)の主な原因物質として知られています。
ストレスが直接的にDHTを増やすわけではありませんが、ストレス対抗ホルモンである「コルチゾール」の分泌が続くと、ホルモン全体のバランスが崩れやすくなります。
また、コルチゾールは皮脂腺の働きを活発化させる作用もあり、皮脂の過剰分泌を招き、脂漏性のフケやかゆみを引き起こす一因にもなります。
免疫力の低下と頭皮環境
慢性的なストレスは、体全体の免疫力を低下させます。免疫力が落ちると、外部からの刺激に対する防御機能、いわゆる「バリア機能」が弱まります。
頭皮も同様で、バリア機能が低下すると、普段は問題にならないようなわずかな刺激(紫外線、乾燥、シャンプーの洗い残しなど)にも過敏に反応し、赤みや炎症を引き起こしやすくなります。
さらに、頭皮の常在菌(マラセチア菌など)のバランスが崩れ、異常繁殖することでフケやかゆみが悪化するケースもあります。
ストレスによる主な頭皮トラブル【症状別】
ストレスが原因で引き起こされる頭皮トラブルは多岐にわたります。
ここでは、代表的な症状を個別に見ていきながら、なぜストレスがそれらを引き起こすのかを詳しく解説します。ご自身の症状と照らし合わせて確認してください。
かゆみ(痒み)の原因
ストレスを感じると、頭皮がピリピリ、ムズムズとかゆくなることがあります。これは、ストレスによる血行不良や免疫力低下に加え、知覚神経が過敏になることが関係しています。
通常なら気にならない程度の刺激にも、神経が過剰に反応してかゆみ信号を発してしまうのです。
また、かゆみを感じて頭皮を掻きむしると、頭皮が傷つき、さらに炎症が悪化するという悪循環に陥りやすいため注意が必要です。
フケ(脂漏性・乾燥性)の発生
フケには、皮脂の過剰分泌による「脂漏性(しろうせい)フケ」と、頭皮の乾燥による「乾燥性フケ」があります。ストレスは、ホルモンバランスの乱れから皮脂分泌を過剰にし、脂漏性フケの原因となります。
このタイプのフケはベタベタしており、毛穴を詰まらせる原因にもなります。一方で、ストレスによる血行不良は頭皮のターンオーバー(新陳代謝)を乱します。
ターンオーバーが早すぎると、未熟な角質が剥がれ落ち、カサカサした乾燥性フケとして現れます。
頭皮の赤みと炎症
ストレスによる免疫力の低下やバリア機能の低下は、頭皮を無防備な状態にします。そこに皮脂の過剰分泌や乾燥、外部刺激が加わることで、頭皮は炎症を起こしやすくなります。
これが「赤み」の正体です。赤みは、頭皮がSOSを発しているサインであり、放置すると炎症が慢性化し、脂漏性皮膚炎などの皮膚疾患に発展する可能性もあります。
抜け毛・薄毛の進行
ストレスは、抜け毛や薄毛の強力な引き金となります。前述の血行不良による栄養不足は、毛母細胞の働きを鈍らせ、髪の毛の「成長期」を短縮させます。
その結果、髪が十分に太く長く成長する前に「退行期」「休止期」へと移行してしまい、抜け落ちてしまうのです。これがストレスによる抜け毛の主な原因です。
また、ストレスがAGA(男性型脱毛症)の進行を早める可能性も指摘されています。
ストレス関連で考えられる脱毛のタイプ
| 脱毛のタイプ | 主な特徴 | ストレスとの関連 |
|---|---|---|
| AGA(男性型脱毛症) | 生え際の後退や頭頂部の薄毛 | ホルモンバランスの乱れが進行を助長する可能性 |
| 円形脱毛症 | 突然、円形や楕円形に髪が抜ける | 自己免疫疾患の一種。ストレスが引き金と強く疑われる |
| 休止期脱毛症 | 頭部全体の髪が均一に薄くなる | 強いストレスにより毛髪が一斉に休止期に入り抜ける |
ストレスが引き起こす頭皮の悪循環
ストレスによる頭皮トラブルは、一度発生すると改善が難しく、さらなる問題を引き起こす「悪循環」に陥りやすい特徴があります。
この負の連鎖を断ち切ることが、健康な頭皮を取り戻す鍵となります。
頭皮環境の悪化
ストレスによる血行不良、皮脂の過剰分泌、バリア機能の低下は、それぞれが独立した問題ではなく、相互に関連し合っています。
例えば、皮脂が過剰になると、それをエサにする常在菌が増殖し、炎症を引き起こします。炎症が起こればバリア機能はさらに低下し、外部刺激に弱くなります。
このように、一つのトラブルが次のトラブルを呼び、頭皮環境はどんどん悪化していきます。
皮脂の過剰分泌と乾燥
「皮脂が多い(ベタつく)」ことと「乾燥している(カサつく)」ことは、一見すると正反対の現象に思えます。しかし、ストレス下の頭皮では、この二つが同時に起こることがあります。
ストレスで皮脂分泌が活発になる一方で、血行不良やターンオーバーの乱れによって頭皮内部の水分保持能力は低下します(インナードライ)。
肌表面はベタついているのに内部は乾燥しているという、非常に不安定な状態です。この状態は、かゆみやフケを悪化させる大きな要因となります。
バリア機能の低下
健康な頭皮は、皮脂膜と角質層によって構成される「バリア機能」によって守られています。これにより、外部からの刺激(紫外線、化学物質、雑菌など)の侵入を防ぎ、内部の水分蒸発を防いでいます。
しかし、ストレスはこのバリア機能を著しく低下させます。バリア機能が壊れた頭皮は、いわば“鎧を脱いだ”状態であり、わずかな刺激でも炎症やかゆみを引き起こします。
頭皮バリア機能が低下しているサイン
| サイン | 具体的な状態 | 考えられる原因 |
|---|---|---|
| 敏感になる | シャンプーや整髪料がしみる | 角質層の乱れ、皮脂膜の不足 |
| 乾燥・つっぱり感 | 洗髪後に頭皮がつっぱる感じがする | 水分保持能力の低下 |
| フケの増加 | 乾燥したフケ、またはベタつくフケ | ターンオーバーの乱れ、皮脂バランスの崩れ |
トラブルが更なるストレスを生む心理
頭皮トラブルの最も厄介な点は、その症状自体が新たなストレス源となることです。
「フケがスーツの肩に落ちていないか」「頭皮の赤みや薄毛を他人に見られているのではないか」といった不安や焦りが、さらなる精神的ストレスとなります。
この心理的負担が、自律神経やホルモンバランスを一層乱し、頭皮環境をさらに悪化させるという、まさに「負のスパイラル」を生み出してしまうのです。
今すぐ始めたいストレス対策【セルフケア編】
頭皮トラブルの根本原因であるストレスをゼロにすることは難しいかもしれません。しかし、ストレスと上手に付き合い、心身への影響を最小限に抑えることは可能です。
日常生活の中で意識的にリラックスする時間を作り、ストレス耐性を高める習慣を身につけましょう。
質の高い睡眠を確保する方法
睡眠は、心身の疲労を回復させ、自律神経のバランスを整えるために最も重要です。特に、髪の成長を促す「成長ホルモン」は、入眠後の深い睡眠中に最も多く分泌されます。
単に長く寝るのではなく、「質」の高い睡眠を心がけましょう。寝る1〜2時間前からはスマートフォンやPCの画面を見るのを避け、リラックスできる環境を整えることが大切です。
毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きる規則正しい生活リズムも、体内時計を整え、睡眠の質を高めます。
リラクゼーション習慣の導入
日々の生活の中に、意図的に「何もしない時間」や「リラックスする時間」を取り入れましょう。自分が「心地よい」と感じることを習慣にすることが、ストレス軽減につながります。
難しく考える必要はありません。深呼吸をする、好きな音楽を聴く、温かいお風呂にゆっくり浸かるなど、簡単なことで構いません。
日常でできる簡単なリラックス法
- 腹式呼吸(5分間)
- ぬるめのお湯(38〜40度)での入浴
- アロマテラピー(ラベンダーなど)
- 軽いストレッチ
適度な運動のすすめ
運動は、ストレス発散に非常に効果的です。特に、ウォーキングやジョギング、水泳などのリズミカルな有酸素運動は、幸せホルモンと呼ばれる「セロトニン」の分泌を促し、精神的な安定をもたらします。
また、運動によって全身の血流が良くなることは、もちろん頭皮の血行改善にも直結します。無理に激しい運動をする必要はなく、「少し汗ばむ程度」の運動を週に2〜3回、継続することが重要です。
エレベーターではなく階段を使うなど、日常の活動量を増やすことからも始められます。
ストレス源との向き合い方
ストレスの原因(ストレッサー)が明確な場合は、それ自体を解決または回避する努力も必要です。しかし、現代社会において、すべてのストレス源をなくすことは現実的ではありません。
大切なのは、「物事の捉え方」を変えてみることです。
「完璧を目指しすぎない」「他人の評価を気にしすぎない」「自分一人で抱え込まない」といった考え方も、ストレスを溜め込まないためには有効です。
信頼できる友人や家族に話を聞いてもらうだけでも、心は軽くなるものです。
頭皮環境を整える食生活の見直し
ストレスに対抗し、健康な頭皮と髪を育てるためには、体の内側からのケア、すなわち「食生活」が極めて重要です。
ストレスを感じると、食事が偏ったり、暴飲暴食に走ったりしがちですが、そんな時こそ意識して栄養バランスを整える必要があります。
頭皮ケアに必要な栄養素
髪の毛は主に「ケラチン」というタンパク質でできています。そのため、良質なタンパク質の摂取は必須です。
また、タンパク質の合成を助ける亜鉛や、頭皮の血行を促進するビタミンE、皮脂の分泌をコントロールするビタミンB群なども、頭皮環境を健やかに保つために欠かせない栄養素です。
頭皮と髪の健康を支える主な栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食材 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料 | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉(赤身)、ナッツ類 |
| ビタミンB群 | 皮脂分泌の調整、新陳代謝の促進 | 豚肉、レバー、うなぎ、マグロ、納豆 |
避けるべき食習慣
一方で、頭皮環境を悪化させる食習慣もあります。
脂っこい食事(揚げ物やファストフード)や、糖分の多いお菓子、刺激物(香辛料など)の過剰摂取は、皮脂の分泌を必要以上に増やし、頭皮の炎症を招く原因となります。
また、アルコールの飲み過ぎは、体内でビタミンやミネラルを大量に消費してしまうため、髪に必要な栄養が不足する原因にもなります。
ストレス発散のための暴飲暴食は、結果的に頭皮環境を悪化させることを覚えておきましょう。
水分補給の重要性
頭皮も肌の一部であり、健康を保つためには十分な水分が必要です。体が水分不足になると、頭皮も乾燥しやすくなり、バリア機能の低下や乾燥性フケの原因となります。
特にストレスを感じている時は、体が水分を消費しやすい状態にあるとも言われます。喉の渇きを感じる前に、こまめに水分を補給する習慣をつけましょう。
一度にがぶ飲みするのではなく、コップ一杯程度の水を1日に何回かに分けて飲むのが効果的です。ジュースやコーヒーではなく、常温の水や白湯を選ぶと良いでしょう。
正しいヘアケアで頭皮を守る
ストレスによって敏感になっている頭皮は、日々のヘアケアによるダメージも受けやすくなっています。刺激を与えず、清潔に保ち、血行を促進する「守り」と「攻め」のケアが重要です。
育毛剤を使っている方も、その土台となる頭皮環境が整っていなければ、十分な効果は期待できません。
シャンプー選びのポイント
毎日使うシャンプーは、頭皮環境に最も大きな影響を与えるアイテムの一つです。
洗浄力が強すぎるシャンプー(高級アルコール系など)は、必要な皮脂まで奪い去り、頭皮の乾燥やバリア機能の低下を招きます。
ストレスで頭皮が敏感になっている時は、肌に優しいアミノ酸系の洗浄成分を使用したシャンプーを選ぶことを推奨します。
また、フケやかゆみが気になる場合は、有効成分(抗炎症成分や殺菌成分)が配合された薬用シャンプー(医薬部外品)も選択肢になります。
頭皮の状態に合わせたシャンプー選び
| 頭皮の状態 | 推奨される洗浄成分 | その他の特徴 |
|---|---|---|
| 乾燥・敏感 | アミノ酸系(ココイル〜など) | 保湿成分配合、低刺激処方 |
| ベタつき・脂性 | アミノ酸系、または適度な洗浄力のもの | 皮脂を適切に除去、毛穴詰まり予防 |
| フケ・かゆみ | 薬用(抗真菌・抗炎症成分配合) | 原因菌(マラセチア)の増殖抑制 |
負担をかけない洗髪方法
洗い方も重要です。熱すぎるお湯(40度以上)は頭皮を乾燥させるため、38度程度のぬるま湯を使います。
シャンプーは直接頭皮につけず、手のひらでしっかりと泡立ててから、指の腹を使って頭皮をマッサージするように優しく洗います。爪を立ててゴシゴシ洗うのは、頭皮を傷つけるため厳禁です。
シャンプー剤やコンディショナーが残らないよう、すすぎは時間をかけて丁寧に行いましょう。
洗髪後は、すぐにドライヤーで乾かします。濡れたまま放置すると雑菌が繁殖しやすくなり、臭いやかゆみの原因となります。
頭皮マッサージの効果とやり方
ストレスで硬くなりがちな頭皮をほぐし、血行を促進するためには、頭皮マッサージが効果的です。血流が改善すれば、毛根に栄養が行き渡りやすくなります。
シャンプー中や、育毛剤を塗布した後に行うのがおすすめです。リラックス効果も高いため、ストレスケアの一環としても役立ちます。
自宅でできる簡単な頭皮マッサージ
| ステップ | 方法 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. ほぐす | 両手の指の腹で、頭皮全体を掴むように圧迫 | 頭蓋骨から頭皮を引きはがすイメージで |
| 2. 引き上げる | 生え際から頭頂部に向かって、指の腹で円を描く | ゆっくりと引き上げるように |
| 3. 押す | 頭頂部や後頭部など、気持ち良いと感じる部分を押す | 息を吐きながらゆっくり圧をかける |
育毛剤の活用も選択肢に
ストレスによる血行不良や頭皮環境の悪化が気になる場合、育毛剤(医薬部外品)の使用も有効な対策です。
育毛剤には、血行促進成分や抗炎症成分、保湿成分などが配合されており、頭皮環境を整え、抜け毛を予防し、健やかな髪の毛が育つのを助ける働きがあります。
特に、ストレスによる抜け毛や薄毛の初期段階であれば、こうしたセルフケアとしての育毛剤が力を発揮します。自分の頭皮の状態に合った製品を選び、継続して使用することが大切です。
ストレス性頭皮トラブルのサインと専門家への相談
セルフケアは非常に重要ですが、症状が悪化する場合や、自分での判断が難しい場合は、ためらわずに専門家の助けを求めるべきです。早期の対応が、深刻な状態への進行を防ぎます。
セルフケアの限界を知る
ストレス対策やヘアケアを見直しても、1〜2ヶ月以上フケやかゆみ、赤みが改善しない場合、または抜け毛が明らかに減らない場合は、セルフケアの限界かもしれません。
特に、かゆみが我慢できず掻きむしってしまう、じゅくじゅくとしたフケが出る、抜け毛の範囲が広がっているといった場合は、早急な対応が必要です。
専門家への相談を検討する目安
- 強いかゆみが続く
- フケが異常に多い(肩に積もる)
- 頭皮の赤みや湿疹が広がっている
- 抜け毛が急激に増えた
皮膚科受診のタイミング
頭皮のかゆみ、フケ、赤み、湿疹といった症状は、「脂漏性皮膚炎」や「接触性皮膚炎」などの皮膚疾患の可能性があります。これらはストレスが引き金になることも多いですが、自己判断は禁物です。
まずは皮膚科を受診し、医師の診断を受けましょう。必要に応じて、炎症を抑える外用薬(ステロイドなど)や、菌の増殖を抑える抗真菌薬が処方されます。
適切な治療を受けることで、不快な症状を迅速に改善することが可能です。
専門クリニックで受ける相談
抜け毛や薄毛の悩みが深刻な場合は、皮膚科に加えて、AGA(男性型脱毛症)や薄毛治療を専門とするクリニックに相談するのも一つの方法です。
これらのクリニックでは、頭皮の状態を詳細に診断する機器(マイクロスコープなど)が揃っており、医師による問診と合わせて、薄毛の原因をより深く特定します。
ストレスによるものなのか、AGAが進行しているのか、あるいはその両方なのかを判断し、個々の状態に合わせた治療法(内服薬、外用薬、生活指導など)を提案してくれます。
主な相談先とその特徴
| 相談先 | 主な対象症状 | 主な対応 |
|---|---|---|
| 皮膚科 | かゆみ、フケ、赤み、炎症、湿疹 | 診断、外用薬・内服薬の処方(保険診療中心) |
| 薄毛専門クリニック | 抜け毛、薄毛、AGA | 詳細な頭皮診断、専門的な治療薬の処方(自由診療中心) |
Q&A
最後に、ストレスと頭皮に関してよく寄せられる質問にお答えします。
- ストレスを感じなくなれば、頭皮トラブルはすぐに治りますか?
-
ストレスが原因の場合、ストレス源がなくなったり、ストレスコーピング(対処)がうまくいったりすると、症状が改善に向かうことは多いです。
しかし、一度乱れた頭皮環境やヘアサイクルが正常に戻るには時間がかかります。特に髪の毛には「毛周期」があるため、抜け毛が減ったと実感するまでには数ヶ月単位の時間が必要です。
ストレス対策と並行して、頭皮ケアや生活習慣の改善を根気強く続けることが重要です。
- 頭皮のかゆみに市販薬を使っても良いですか?
-
一時的な軽いかゆみであれば、市販のかゆみ止めローションなどを使用することも一つの方法です。ただし、漫然と使い続けるのは推奨できません。
市販薬を数日使用しても改善しない場合や、赤みやフケを伴う場合は、原因が他にある可能性(皮膚炎など)も考えられるため、皮膚科を受診してください。
自己判断で強い薬を使い続けると、かえって頭皮を傷めることもあります。
- ストレスによる抜け毛は元に戻りますか?
-
ストレスが原因の「休止期脱毛症」や、自己免疫疾患とされる「円形脱毛症」の場合、ストレス要因が取り除かれ、適切な治療やケアを行えば、再び毛髪が生えてくる可能性は高いです。
ただし、AGA(男性型脱毛症)が合併している場合、ストレスがなくなってもAGA自体の進行は止まりません。
ストレスはAGAの進行を早める一因となるため、ストレスケアは続けつつ、AGAの専門的な対策(育毛剤の使用やクリニックでの相談)も必要に応じて検討しましょう。
- 食事や睡眠以外で、簡単にできるストレスケアはありますか?
-
「呼吸」を意識することをおすすめします。ストレスを感じている時、人の呼吸は浅く早くなりがちです。
意識的に「腹式呼吸」(鼻からゆっくり息を吸ってお腹を膨らませ、口から時間をかけてゆっくり吐き出す)を行うと、副交感神経が優位になり、心身がリラックス状態に切り替わります。
仕事の合間や寝る前など、1回数分でも良いので試してみてください。また、趣味に没頭する時間を作ることも、ストレスから意識をそらす上で非常に有効です。
Reference
MALTA JR, Mauri; CORSO, German. Understanding the Association Between Mental Health and Hair Loss. Cureus, 2025, 17.5.
MOHAMED, Noha E., et al. Female pattern hair loss and negative psychological impact: possible role of brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Dermatology Practical & Conceptual, 2023, 13.3: e2023139.
AHN, Dongkyun, et al. Psychological stress-induced pathogenesis of alopecia areata: autoimmune and apoptotic pathways. International Journal of Molecular Sciences, 2023, 24.14: 11711.
GOKALP, Hilal. Psychosocial aspects of hair loss. In: Hair and scalp disorders. IntechOpen, 2017.
TOADER, Mihaela Paula, et al. Unraveling the psychological impact of telogen effluvium: Understanding hair loss beyond the scalp. Bulletin of Integrative Psychiatry, 2024, 1.
PETERS, Eva MJ, et al. Hair and stress: a pilot study of hair and cytokine balance alteration in healthy young women under major exam stress. PloS one, 2017, 12.4: e0175904.
PHILLIPS, T. Grant; SLOMIANY, W. Paul; ALLISON, Robert. Hair loss: common causes and treatment. American family physician, 2017, 96.6: 371-378.
HADSHIEW, Ina M., et al. Burden of hair loss: stress and the underestimated psychosocial impact of telogen effluvium and androgenetic alopecia. Journal of investigative dermatology, 2004, 123.3: 455-457.
CHENG, Yi, et al. Psychological stress impact neurotrophic factor levels in patients with androgenetic alopecia and correlated with disease progression. World journal of psychiatry, 2024, 14.10: 1437.
ACCORSI, Daniela X., et al. COVID-19 Stress on Mental and Hair Health: A Marker for Diseases in the Post-Pandemic Era. Coronaviruses, 2022, 3.3: 65-75.