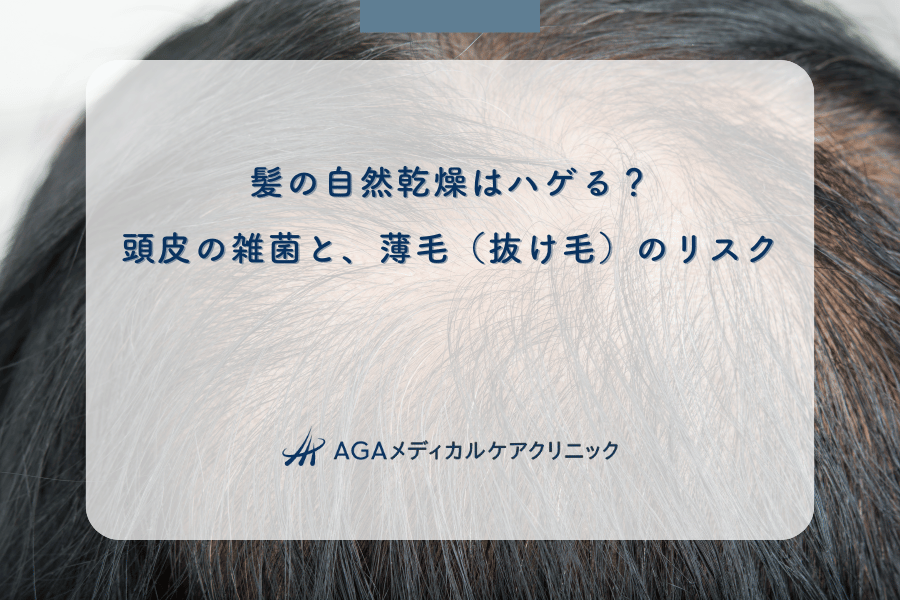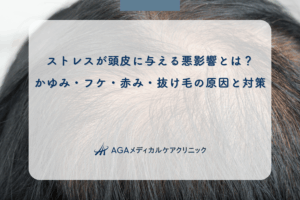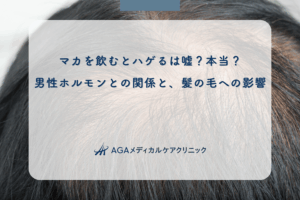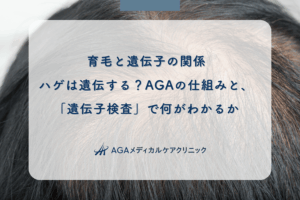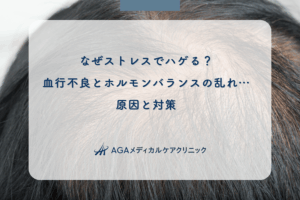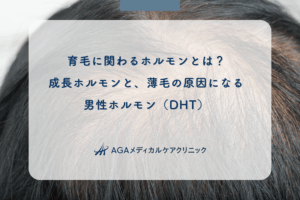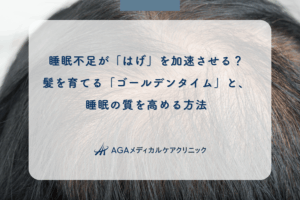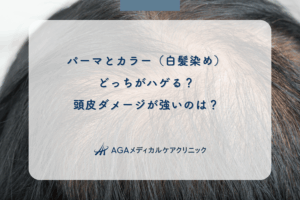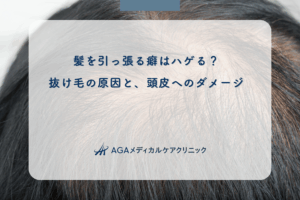お風呂上がり、髪を乾かすのが面倒で自然乾燥にしていませんか?「髪を自然乾燥させるとハゲる」という噂を聞いたことがあるかもしれません。
この噂が本当なのか、不安に感じている方も多いでしょう。この記事では、「髪 自然 乾燥 はげる」という疑問に焦点を当て、髪を濡れたまま放置することの危険性を深掘りします。
頭皮の雑菌繁殖、血行不良、髪へのダメージなど、自然乾燥が引き起こす可能性のある頭皮トラブルと、それが薄毛や抜け毛のリスクにどうつながるのかを詳しく解説します。
薄毛を予防し、健やかな頭皮を保つための正しいヘアケア方法も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
「髪の自然乾燥でハゲる」は本当?噂の真相
多くの男性が一度は耳にしたことがある「自然乾燥はハゲる」という言葉。この噂は、果たして医学的な根拠があるのでしょうか。それとも単なる都市伝説なのでしょうか。
このセクションでは、髪の自然乾燥と薄毛の直接的な関係について、その真相を明らかにします。
結論 自然乾燥が直接ハゲる原因ではない
まず結論から言うと、髪を自然乾燥させたからといって、それが「直接的」にハゲる(AGA:男性型脱毛症など)原因になるわけではありません。
AGAは、遺伝的要因や男性ホルモンの影響が主な原因であり、髪の乾かし方だけで発症するものではありません。したがって、「自然乾燥=ハゲる」と短絡的に結びつけるのは正確ではありません。
しかし薄毛のリスクを高める可能性は高い
ただし、「直接の原因ではない」からといって安心するのは早計です。自然乾燥は、ハゲる直接の原因にはならなくとも、薄毛や抜け毛を助長する「頭皮環境の悪化」を引き起こす重大なリスク要因です。
髪が濡れた状態が長時間続くと、頭皮にとって非常に不衛生な状態となり、健やかな髪の成長を妨げる様々なトラブルを招く可能性があります。
なぜ「自然乾燥はハゲる」と言われるのか
では、なぜこれほどまでに「自然乾燥はハゲる」と言われるようになったのでしょうか。
それは、自然乾燥によって引き起こされる頭皮トラブルが、結果として「抜け毛の増加」や「髪のボリュームダウン」につながりやすいからです。
髪が細くなったり、抜け毛が増えたりすれば、見た目として薄毛が進行したように感じます。この「薄毛に見える状態」が、「ハゲる」という言葉と結びついたと考えられます。
頭皮環境の悪化が抜け毛につながる
髪の毛は、頭皮という「土壌」から生えています。土壌の状態が悪ければ、良い作物が育たないのと同じで、頭皮環境が悪化すれば、健康な髪は育ちません。
自然乾燥は、この大切な土壌を荒廃させる行為と言えます。雑菌の繁殖、血行不良、頭皮の冷えなど、様々な悪影響が複合的に絡み合い、最終的に抜け毛のリスクを高めてしまうのです。
髪を自然乾燥させる具体的なリスク
髪を濡れたまま放置する「自然乾燥」。この習慣が、具体的にどのようなリスクを頭皮や髪にもたらすのでしょうか。
ここでは、自然乾燥が引き起こす三つの主要なリスク「雑菌の繁殖」「血行不良」「キューティクルへのダメージ」について詳しく解説します。
頭皮の雑菌が繁殖しやすくなる
私たちの頭皮には、もともと多くの常在菌が存在しています。これらがバランスを保っている間は問題ありません。しかし、髪を自然乾燥させると、このバランスが崩れやすくなります。
濡れた頭皮は、雑菌にとって「高温多湿」で「栄養豊富」な最高の繁殖環境となってしまうのです。
雑菌のエサとなる皮脂と水分
頭皮からは常に皮脂が分泌されています。シャンプーで落としきれなかった皮脂や、新しく分泌された皮脂が、濡れた髪の水分と混ざり合います。
これが、雑菌、特にカビの一種であるマラセチア菌などのエサとなります。水分とエサが豊富な状態が続けば、雑菌は爆発的に増殖します。
マラセチア菌と脂漏性皮膚炎
特に注意が必要なのがマラセチア菌です。この菌が異常繁殖すると、皮脂を分解する過程で遊離脂肪酸という刺激物質を生成します。これが頭皮を刺激し、炎症を引き起こします。
この状態が「脂漏性皮膚炎(しろうせいひふえん)」であり、強いかゆみやフケ、赤みを伴い、悪化すると抜け毛の原因にもなります。
頭皮の臭いやかゆみの発生
雑菌が皮脂や汗を分解する際、不快な臭い(雑菌臭)が発生します。いわゆる「生乾きの臭い」と同じ原理です。また、雑菌の繁殖やその代謝物が頭皮を刺激し、かゆみを引き起こします。
かゆいからといって頭皮を掻きむしると、頭皮が傷つき、さらに炎症が悪化するという悪循環に陥ります。
頭皮が冷えて血行不良になる
濡れた髪は、気化熱(水分が蒸発する際に熱を奪う現象)によって頭皮の温度を急速に奪います。特に冬場や冷房の効いた部屋では、頭皮は想像以上に冷え切ってしまいます。
この「冷え」が、髪の成長に深刻な影響を与えます。
血行不良が毛根に与える影響
頭皮が冷えると、体は体温を逃がさないように血管を収縮させます。頭皮には毛細血管が張り巡らされていますが、これらが収縮すると血流が悪くなります。
これが「血行不良」の状態です。髪の毛の成長を司る「毛母細胞」は、この毛細血管から栄養や酸素を受け取って活動しています。
栄養が届かない髪の毛
血行不良に陥ると、毛母細胞へ届くはずの栄養や酸素が不足します。栄養不足の状態では、毛母細胞は活発に細胞分裂を行うことができず、健康で太い髪の毛を作り出せなくなります。
結果として、髪が細くなったり、成長が途中で止まってしまったり(成長期の短縮)、抜け毛が増える原因となります。
キューティクルが剥がれやすくなる
自然乾燥は、頭皮だけでなく「髪の毛そのもの」にも大きなダメージを与えます。
髪の毛の表面は、「キューティクル」というウロコ状の組織で覆われており、これが髪の内部を守る鎧の役割を果たしています。
濡れた髪の無防備な状態
キューティクルは、髪が濡れると水分を含んで柔らかくなり、開いた状態になります。これは非常に無防備な状態で、少しの摩擦でも傷つきやすく、剥がれやすいのです。
自然乾燥は、この無防備な状態が長時間続くことを意味します。
摩擦によるダメージの蓄積
髪が濡れたまま寝てしまうと、枕や寝具との摩擦でキューティクルは深刻なダメージを受けます。
開いたキューティクルがめくれたり、剥がれたりすると、髪の内部にある水分やタンパク質が流出しやすくなります。
髪のパサつきや切れ毛の原因
キューティクルが損傷すると、髪はツヤを失い、パサパサとした手触りになります。ダメージが蓄積すれば、髪は強度を失い、切れ毛や枝毛の原因となります。
髪が切れたり細くなったりすれば、全体のボリュームが減少し、薄毛の印象を強めてしまいます。
雑菌が引き起こす頭皮トラブル
「髪を自然乾燥させると雑菌が繁殖する」と聞いても、具体的にどのような問題が起こるのかイメージしにくいかもしれません。
ここでは、雑菌がどのように頭皮環境を悪化させ、薄毛につながるトラブルを引き起こすのかを解説します。
頭皮の常在菌バランス
健康な頭皮にも、多種多様な「常在菌」が存在しています。これらの菌は、互いに牽制し合いながらバランスを保ち、外部からの病原菌の侵入を防ぐバリア機能の一部を担っています。
しかし、このバランスは非常にデリケートで、環境の変化によって簡単に崩れてしまいます。
雑菌が異常繁殖する環境
常在菌のバランスが崩れ、特定の菌(特にマラセチア菌など)が異常に増殖する主な原因は、頭皮の「湿度」と「栄養」です。
自然乾燥は、まさにこの二つの条件を同時に満たしてしまいます。
湿度と温度がカギ
濡れた髪によって、頭皮は長時間「蒸れた」状態になります。特に髪の毛が密集している部分は乾きにくく、菌にとって格好の棲家となります。
体温によって適度な温度も保たれるため、菌は急速に繁殖活動を始めます。
洗い残しや古い皮脂
シャンプーのすすぎ残しや、酸化した古い皮脂は、雑菌の絶好のエサとなります。
自然乾燥で水分が供給されると、これらのエサを求めて雑菌が活発化し、その数を増やしていきます。
雑菌による具体的な症状
雑菌が異常繁殖すると、頭皮は炎症を起こし、様々な不快な症状が現れます。これらは頭皮環境が悪化している明確なサインです。
頭皮の赤みとかゆみ
最も一般的な症状が、頭皮の赤みとかゆみです。これは、雑菌が生成する刺激物質や、菌そのものに対する体の防御反応(炎症)によって引き起こされます。
かゆみで頭皮を掻くと、角質層が傷つき、さらに雑菌が侵入しやすくなります。
フケの増加(脂性と乾性)
フケは、頭皮のターンオーバー(新陳代謝)が乱れることで発生します。雑菌の刺激によってターンオーバーが異常に早まると、未熟な角質が剥がれ落ち、フケとして目立つようになります。
ベタベタとした「脂性フケ」は、特にマラセチア菌の増殖と関連が深いです。
脂漏性皮膚炎への移行リスク
これらの炎症やかゆみ、フケが慢性化した状態が「脂漏性皮膚炎」です。この皮膚炎は治りにくく、放置すると炎症によって毛根がダメージを受け、抜け毛(脱毛)を引き起こす可能性があります。
自然乾燥の習慣は、この脂漏性皮膚炎の大きな誘因となります。
雑菌と頭皮環境の悪化
雑菌の繁殖が頭皮環境に与える影響をまとめます。
| 雑菌の種類(例) | 主なエサ | 引き起こす可能性のある症状 |
|---|---|---|
| マラセチア菌 | 皮脂 | 脂漏性皮膚炎、フケ(脂性)、かゆみ |
| アクネ菌 | 皮脂 | 頭皮ニキビ、炎症 |
| 黄色ブドウ球菌 | 皮脂、汗、傷口 | 炎症、かゆみ、毛嚢炎(もうのうえん) |
なぜ頭皮の血行不良が薄毛につながるのか
自然乾燥による「頭皮の冷え」が血行不良を招くことは前述の通りです。では、なぜ血行不良がそれほどまでに薄毛や抜け毛のリスクを高めるのでしょうか。
ここでは、髪の成長と血流の密接な関係について解説します。
髪の毛が成長する仕組み
髪の毛は、毛穴の奥にある「毛包(もうほう)」という器官で作られます。毛包の最深部には「毛乳頭(もうにゅうとう)」があり、その周りを「毛母細胞(もうぼさいぼう)」が取り囲んでいます。
この毛母細胞が、髪の毛の元となる細胞です。
毛母細胞への栄養供給ルート
毛母細胞は、毛乳頭を通る毛細血管から酸素と栄養素を受け取り、活発に細胞分裂を繰り返すことで髪の毛を成長させます。
つまり、髪の成長に必要なすべてのエネルギーは「血液」によって運ばれてくるのです。
血液が運ぶ酸素と栄養素
血液は、私たちが食事から摂取したタンパク質(アミノ酸)、ビタミン、ミネラルといった栄養素と、呼吸によって取り入れた酸素を、体の隅々まで運ぶ役割を担っています。
毛母細胞は、体の中でも特に細胞分裂が活発な場所の一つであり、常に大量の栄養と酸素を必要としています。
頭皮の冷えが血管を収縮させる
自然乾燥によって頭皮が冷えると、毛細血管は収縮します。血管が細くなれば、当然ながらそこを流れる血液の量も減少します。これが血行不良の状態です。
必要な栄養や酸素が毛母細胞に十分に届かなくなってしまいます。
血行不良が引き起こすヘアサイクルの乱れ
髪の毛には「ヘアサイクル(毛周期)」があり、「成長期(髪が伸びる時期)」「退行期(成長が止まる時期)」「休止期(髪が抜け落ちる準備をする時期)」を繰り返しています。
成長期の短縮
栄養不足に陥った毛母細胞は、その活動を維持することが難しくなります。その結果、本来であれば数年間続くはずの「成長期」が短縮されてしまいます。
髪が十分に太く、長く成長する前に、次の「退行期」へと移行してしまうのです。
休止期から抜け毛へ
成長期が短くなると、相対的に「休止期」にとどまる髪の割合が増えます。休止期の髪は、やがて新しい髪に押し出されるか、少しの刺激で抜け落ちます。
これにより、抜け毛が増加し、新しく生えてくる髪は細く弱々しいため、全体として薄毛が目立つようになります。
自然乾燥による血行不良は、このようにヘアサイクルを乱し、薄毛を進行させる要因となります。
髪のダメージと薄毛の関係
自然乾燥は頭皮だけでなく、髪そのものにもダメージを与えます。傷んだ髪は、たとえ毛量が減っていなくても「薄毛」の印象を強くしてしまいます。
キューティクルの損傷が、どのように薄毛の見た目やリスクに関係するのかを見ていきましょう。
キューティクルの重要な役割
髪の表面を覆うキューティクルは、髪の生命線とも言える重要な部分です。単なる表面のカバーではなく、髪の健康を維持するために能動的な役割を持っています。
髪の内部を守る鎧
キューティクルは硬いタンパク質でできており、外部の物理的な刺激(摩擦など)や化学的な刺激(紫外線、ヘアカラー剤など)から、髪の内部にある柔らかい「コルテックス」を守る鎧の役割を果たしています。
水分とタンパク質の流出を防ぐ
コルテックスには、髪のしなやかさや強度を保つための水分やタンパク質(ケラチン)が詰まっています。
キューティクルが整然と閉じていることで、これらの大切な成分が外部に流出するのを防いでいます。
自然乾燥がキューティクルを傷つける理由
髪が濡れると、キューティクルは水分を吸って膨張し、ウロコが開いた状態になります。この状態は非常にデリケートで、ダメージを受けやすいのです。
濡れた状態での摩擦
自然乾燥は、この「キューティクルが開いた状態」を長時間維持することを意味します。
その間に、服を着替えたり、タオルが肩に触れたりするだけでも、摩擦によってキューティクルは傷つき、剥がれていきます。
枕や寝具とのこすれ
特に最悪なのが、髪が濡れたまま寝ることです。睡眠中、無意識のうちに何度も寝返りを打ちます。
そのたびに、開いたキューティクルが枕やシーツにこすりつけられ、深刻なダメージを受けます。一度剥がれたキューティクルは再生しません。
ダメージヘアが薄毛に見える理由
キューティクルが損傷し、内部のタンパク質や水分が流出した髪は、様々な「老化した」状態を見せます。これが薄毛の印象につながります。
髪のハリ・コシの低下
髪の内部がスカスカになると、髪は強度を失い、ハリやコシがなくなります。健康な髪のように根元から立ち上がることができず、ペタッと寝てしまいやすくなります。
これにより、頭皮が透けて見えやすくなります。
ボリュームダウンによる印象
髪一本一本が細くなり、パサつきやうねりが出ることで、髪全体のまとまりがなくなり、ボリュームが失われます。
実際の髪の本数が減っていなくても、全体的なボリューム感が低下することで、「薄くなった」と感じさせてしまうのです。
頭皮と髪の乾燥対策比較
髪を乾かす様々な方法が、頭皮と髪にどのような影響を与えるかを比較してみましょう。
| 乾かし方 | 頭皮への影響 | 髪(キューティクル)への影響 |
|---|---|---|
| 自然乾燥 | 雑菌繁殖リスク(高) 血行不良リスク(高) | ダメージリスク(高) (長時間濡れた状態での摩擦) |
| タオルドライのみ | 雑菌繁殖リスク(中) 血行不良リスク(中) | ダメージリスク(中) (摩擦による) |
| ドライヤー(温風) | 乾燥リスク(中) (当てすぎに注意) | 熱ダメージリスク(中) (距離と時間に注意) |
この表からもわかるように、どの方法にも一長一短がありますが、「自然乾燥」は頭皮と髪の両方にとって最もリスクが高い選択肢です。
リスクを最小限に抑えるためには、タオルドライとドライヤーを正しく組み合わせることが重要です。
薄毛リスクを減らす正しい髪の乾かし方
自然乾燥が頭皮と髪に多くのリスクをもたらすことは明らかです。では、薄毛や抜け毛のリスクを減らすためには、どのように髪を乾かすのが正解なのでしょうか。
ここでは、頭皮と髪を守るための「正しい髪の乾かし方」を3つのステップで紹介します。
ステップ1 タオルドライで水分を徹底的に取る
ドライヤーの時間を短縮し、熱によるダメージを最小限に抑えるために、最初のタオルドライが非常に重要です。目的は「髪から水滴が落ちない」状態にすることです。
吸水性の高いタオルを選ぶ
ゴシゴシこすらなくても水分を吸い取れるよう、マイクロファイバータオルなど、吸水性に優れたタオルを選ぶことをお勧めします。
清潔なタオルを使うことも、雑菌の付着を防ぐ上で大切です。
ゴシゴシこすらず押さえるように
最もやってはいけないのが、タオルで髪をゴシゴシと擦ることです。濡れた髪は摩擦に弱いため、キューティクルを傷つけてしまいます。
タオルで頭皮と髪を優しく挟み込み、ポンポンと押さえるようにして水分をタオルに移し取ります。
頭皮の水分もしっかり拭き取る
髪の毛だけでなく、頭皮の水分もしっかりと拭き取ります。
指の腹を使ってタオルの上から頭皮をマッサージするように拭くと、水分が取れると同時に血行促進にもつながります。
ステップ2 ドライヤーですばやく乾かす
タオルドライで大まかな水分を取ったら、すぐにドライヤーを使って乾かします。濡れた状態を1分1秒でも短くすることが、雑菌の繁殖を防ぐカギです。
ドライヤー前のヘアケア
ドライヤーの熱から髪を守るため、洗い流さないトリートメント(ヘアオイルやミルク)を毛先中心につけるのも良い方法です。
ただし、頭皮に直接つくと毛穴詰まりの原因になる可能性があるため、つけすぎには注意しましょう。
根本(頭皮)から乾かす
多くの人が毛先から乾かしがちですが、乾かす順番は「根本(頭皮)→中間→毛先」が鉄則です。最も乾きにくく、雑菌が繁殖しやすい頭皮と根本を先に集中的に乾かします。
毛先は熱ダメージを受けやすいため、最後にある程度乾いていれば十分です。
ドライヤーと頭皮の適切な距離
熱による頭皮や髪へのダメージを防ぐため、ドライヤーは頭皮から最低でも20cm程度は離して使います。
一箇所に集中して熱風を当て続けるのではなく、ドライヤーを小刻みに振りながら、全体に風が行き渡るようにします。
ステップ3 温風と冷風の使い分け
最近のドライヤーには、温風と冷風の切り替え機能がついています。これを使いこなすことで、仕上がりが大きく変わります。
8割乾いたら冷風に切り替え
全体が8割から9割程度乾いたら、温風から冷風に切り替えます。「オーバードライ(乾かしすぎ)」は、髪や頭皮の乾燥を招き、逆効果です。
少し湿り気が残っているかな、という程度で温風を止めましょう。
冷風でキューティクルを引き締める
冷風には、温風で開いたキューティクルを引き締める効果があります。キューティクルが閉じることで、髪の内部の水分が閉じ込められ、ツヤが出ます。
また、頭皮に残った熱を冷ますことで、寝る前の不快な蒸れを防ぎます。
オーバードライ(乾かしすぎ)を防ぐ
冷風を当てることで、髪の水分量を適切に保ち、乾かしすぎを防ぐことができます。仕上がりがパサパサにならず、まとまりやすい髪になります。
ドライヤー使用時の注意点
正しいドライヤーの使い方を、再度ポイントでまとめます。
| ポイント | 理由 | 具体的な方法 |
|---|---|---|
| 距離を保つ | 熱ダメージ(タンパク変性)を防ぐため | 髪や頭皮から20cm以上離す |
| 乾かす順番 | 雑菌繁殖の温床となる根本を優先するため | 頭皮・根本 → 中間 → 毛先 |
| 冷風で仕上げる | キューティクルを引き締め、ツヤを出すため | 8〜9割乾いたら冷風に切り替える |
自然乾燥以外の薄毛予防と頭皮ケア
髪を正しく乾かすことは、薄毛予防の非常に重要なステップです。
しかし、それだけで万全とは言えません。健やかな頭皮環境を維持し、強い髪を育てるためには、日々の生活習慣全体を見直すことが大切です。
ここでは、ドライヤー以外の頭皮ケアと薄毛予防策を紹介します。
正しいシャンプー方法の見直し
毎日行っているシャンプーが、実は頭皮に負担をかけているかもしれません。皮脂を落としつつ、必要な潤いを守る洗い方が重要です。
予洗い(お湯洗い)の重要性
シャンプー剤をつける前に、38度程度のぬるま湯で1〜2分かけて頭皮と髪をしっかりすすぐ「予洗い」を行います。これだけで、髪についたホコリや汗、皮脂汚れの7割程度は落ちると言われています。
予洗いをしっかり行うことで、シャンプーの泡立ちが良くなり、洗浄成分による頭皮への刺激を減らせます。
シャンプーの泡立て方
シャンプー剤を原液のまま頭皮につけるのは避けてください。刺激が強すぎたり、すすぎ残しの原因になったりします。手のひらでしっかりと泡立ててから、髪全体になじませます。
泡がクッションとなり、洗髪時の摩擦ダメージを防ぎます。
すすぎ残しを防ぐ
洗う時間(1分)の倍以上(2〜3分)の時間をかけて、シャンプー剤やコンディショナーが頭皮に残らないよう、徹底的にすすぎます。
特に、生え際、耳の後ろ、襟足はすすぎ残しが多い部分なので、意識して洗い流しましょう。シャンプー剤の残りは、毛穴詰まりや雑菌のエサとなり、頭皮トラブルの原因となります。
誤ったシャンプー方法と正しい方法
日々のシャンプー習慣を見直すために、一般的な誤りと正しい方法を比較します。
| 項目 | 誤った方法 | 正しい方法 |
|---|---|---|
| 予洗い | すぐにシャンプーをつける | 1〜2分お湯でしっかり流す |
| 泡立て | 頭皮で直接泡立てる | 手のひらで泡立ててから髪につける |
| 洗い方 | 爪を立ててゴシゴシ洗う | 指の腹でマッサージするように洗う |
| すすぎ | 短時間で簡単に済ませる | ぬめりがなくなるまでしっかりすすぐ |
食生活と睡眠の改善
髪は、私たちが食べたものから作られています。また、睡眠中に分泌される成長ホルモンが髪の成長を促します。内側からのケアも、薄毛予防には必要です。
髪に必要な栄養素
髪の毛の主成分は「ケラチン」というタンパク質です。そのため、良質なタンパク質(肉、魚、卵、大豆製品)の摂取が基本となります。
また、タンパク質の合成を助ける「亜鉛」(牡蠣、レバー、ナッツ類)や、頭皮の血行を良くする「ビタミンE」(アーモンド、アボカド)、皮脂のバランスを整える「ビタミンB群」(豚肉、マグロ)も重要です。
髪の成長に必要な主な栄養素
- タンパク質(髪の主成分)
- 亜鉛(タンパク質の合成を助ける)
- ビタミン群(頭皮環境の維持)
頭皮環境を整える栄養素
特に頭皮環境の維持に関わる栄養素の例です。
| 栄養素 | 期待される役割 | 多く含む食品例 |
|---|---|---|
| ビタミンB群 | 皮脂分泌の調整、代謝促進 | 豚肉、レバー、マグロ、納豆 |
| ビタミンC | コラーゲン生成、抗酸化 | ピーマン、ブロッコリー、キウイ |
| ビタミンE | 血行促進、抗酸化 | アーモンド、アボカド、うなぎ |
成長ホルモンと頭皮環境
髪の毛の成長や頭皮の修復は、主に睡眠中に行われます。特に、入眠後(特に夜10時〜深夜2時)に多く分泌される「成長ホルモン」が、毛母細胞の分裂を活発にします。
睡眠不足が続くと、成長ホルモンの分泌が減少し、髪の成長が妨げられ、頭皮の修復も遅れます。質の良い睡眠を十分にとることが大切です。
ストレス管理と適度な運動
心身の健康状態も、頭皮環境に直結しています。
自律神経と血行
過度なストレスは、自律神経のバランスを乱します。交感神経が優位な状態(緊張・興奮状態)が続くと、血管が収縮し、頭皮の血行不良を引き起こします。
これが毛母細胞への栄養供給を妨げます。リラックスできる時間を作り、自律神経のバランスを整えることが重要です。
運動による血流促進
ウォーキングやジョギングなどの適度な有酸素運動は、全身の血行を促進します。もちろん、頭皮への血流改善にも効果が期待できます。
運動はストレス発散にもつながるため、心身両面から頭皮環境をサポートします。
薄毛を加速させる習慣に戻る
Q&A
最後に、髪の自然乾燥や薄毛に関するよくある質問にお答えします。
- 髪が短い男性でも自然乾燥はダメですか?
-
はい、髪の長さに関わらずお勧めしません。髪が短いと毛先はすぐに乾くかもしれませんが、問題は「頭皮」です。
髪が密集している頭皮部分は乾きにくく、雑菌の繁殖や冷えによる血行不良のリスクは、髪が長い人と同じように存在します。
短髪の方でも、タオルドライの後、ドライヤーで頭皮を中心にすばやく乾かすことを推奨します。
- 夏場でもドライヤーは必要ですか?
-
必要です。夏場は気温と湿度が高く、雑菌が最も繁殖しやすい季節です。自然乾燥に任せると、汗や皮脂と混ざり合い、頭皮環境は急速に悪化します。
臭いやかゆみの原因にもなりやすいです。暑いからといって自然乾燥にせず、ドライヤー(特に仕上げの冷風)を活用して、頭皮を清潔でサラリとした状態に保ちましょう。
- ドライヤーの熱はハゲる原因になりませんか?
-
ドライヤーの使い方を誤れば、熱が頭皮や髪にダメージを与え、抜け毛や髪の損傷の原因になる可能性はあります。
しかし、「正しい使い方」をすれば、そのリスクは最小限に抑えられます。
重要なのは「適切な距離(20cm以上)を保つこと」「一箇所に当て続けないこと」「オーバードライ(乾かしすぎ)を避けること」です。
自然乾燥のリスク(雑菌、血行不良、摩擦)と比較すれば、正しくドライヤーを使う方が、頭皮と髪の健康にとって格段に有益です。
- どうしてもドライヤーを使えない時はどうすればいいですか?
-
旅行先やジムなどでドライヤーが使えない場合もあるかもしれません。その場合は、まず吸水性の高いタオル(マイクロファイバーなど)で、できる限り徹底的に水分を拭き取ります。
特に頭皮の水分を念入りに拭き取ってください。その後は、風通しの良い場所でできるだけ早く乾かすよう努め、濡れたまま長時間放置したり、そのまま寝たりすることは絶対に避けてください。
これはあくまで緊急避難的な対処法であり、日常的に行うべきではありません。
Reference
GÓMEZ-ARIAS, Pedro J., et al. Association between scalp microbiota imbalance, disease severity, and systemic inflammatory markers in alopecia areata. Dermatology and therapy, 2024, 14.11: 2971-2986.
BIFULCO, Guglielmo, et al. Postbiotics for hair and scalp microbiome balance. dermatitis, 2022, 5: 8.
MAYER, Wolfgang, et al. Biomolecules of fermented tropical fruits and fermenting microbes as regulators of human hair loss, hair quality, and scalp microbiota. Biomolecules, 2023, 13.4: 699.
POLAK‐WITKA, Katarzyna, et al. The role of the microbiome in scalp hair follicle biology and disease. Experimental Dermatology, 2020, 29.3: 286-294.
SHAH, Rohan R., et al. Scalp microbiome: a guide to better understanding scalp diseases and treatments. Archives of dermatological research, 2024, 316.8: 495.
SHAO, Siqi, et al. Multidimensional Research on Hair Loss in Young Chinese Females With Oily Scalps. Journal of Cosmetic Dermatology, 2025, 24.9: e70426.
TSAI, Wen-Hua, et al. Heat-killed Lacticaseibacillus paracasei GMNL-653 ameliorates human scalp health by regulating scalp microbiome. BMC microbiology, 2023, 23.1: 121.
POLAK-WITKA, Katarzyna. Development of new methods for compartment-specific analyses of the hair follicle microbiome and associated inflammatory mediators. 2023. PhD Thesis.
RASHEEDKHAN REGINA, Viduthalai, et al. Decoding scalp health and microbiome dysbiosis in dandruff. bioRxiv, 2024, 2024.05. 02.592279.
YAN, Xiaoxi, et al. Evaluation, Symptoms, Influencing Factors, and Prospects of Sensitive Scalp: A Literature Review. Cosmetics, 2025, 12.6: 236.