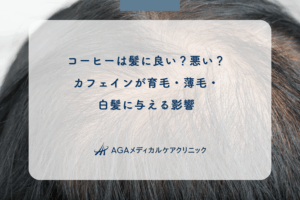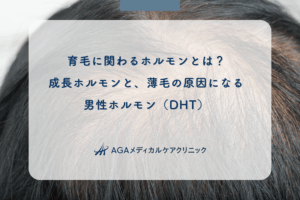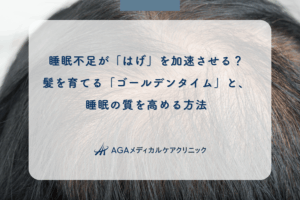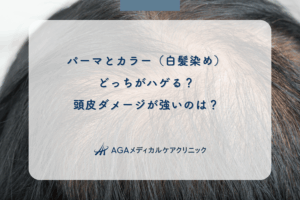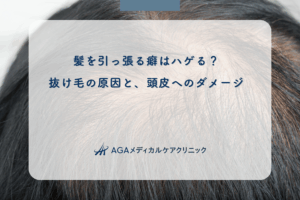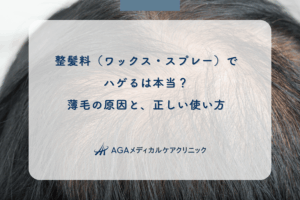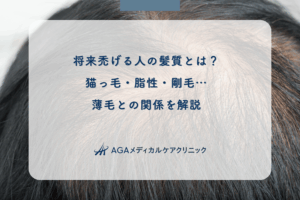「最近抜け毛が増えた」「頭皮の血行不良を解消したい」と悩んでいる方は多いでしょう。薄毛や抜け毛の原因は遺伝やホルモンバランスの乱れなど様々ですが、実は日々の運動習慣も深く関わっています。
運動不足は全身の血流を滞らせ、頭皮へ栄養を運ぶ機能を低下させるため、薄毛の進行を早める一因になりかねません。
しかし、適切な運動を取り入れれば、血行を促進し、育毛に必要な栄養や酸素を毛根へ届けやすくできます。
この記事では、「はげ運動」や「はげ防止運動」といったキーワードで検索している方々に向けて、運動不足と薄毛の関係性を医学的な観点から深掘りします。
さらに、自宅で簡単に取り組める具体的な運動やストレッチ、運動の効果を最大化する生活習慣との組み合わせ方まで、親切丁寧に解説します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
運動不足が薄毛につながる医学的な根拠
運動不足は、見た目の体型変化だけでなく、頭皮の健康にも間接的に大きな影響を及ぼします。
薄毛の原因は多岐にわたりますが、運動が不足すると引き起こされる体の変化が、結果として毛髪の成長サイクルを乱してしまうのです。
ここでは、運動不足が薄毛につながる主な医学的な根拠について詳しく解説します。
血行不良と頭皮への栄養供給の関係
髪の毛が成長するためには、毛根にある毛母細胞が活発に細胞分裂する必要があります。この毛母細胞に栄養と酸素を供給するのが血液です。運動不足の状態が続くと、全身の血行が悪くなります。
特に心臓から遠い頭皮は血流が滞りやすく、毛母細胞へ必要な栄養が十分に届かなくなります。
髪の毛の主成分はケラチンというタンパク質ですが、これらを合成するためのアミノ酸や、代謝に必要なビタミン、ミネラルなどが、血液を通じて運ばれます。
血行が悪い状態では、たとえ栄養豊富な食事を摂っていても、その恩恵を頭皮が受け取れず、結果として細く弱い髪しか育たなかったり、成長期が短縮されたりする現象が起こります。
適度な運動は心肺機能を高め、全身の血流を改善するため、この栄養供給の「輸送ライン」を正常化するために必要です。
ストレスと自律神経の乱れが髪に与える影響
運動は、単に体を動かすこと以上の精神的な効果を持ちます。運動不足は、ストレスホルモンであるコルチゾールの過剰な分泌を招きやすい傾向があります。
長期的なストレスは自律神経のバランス、特に交感神経を優位にし、血管を収縮させて血行不良を引き起こします。
自律神経は、交感神経(活動・緊張)と副交感神経(休息・リラックス)の二つから成り立ちます。
適度な運動、特にリズミカルな有酸素運動は、セロトニンなどの気分を安定させる神経伝達物質の分泌を促し、自律神経のバランスを整えます。
バランスが整うと、夜間の睡眠中に副交感神経が優位になり、頭皮の血管が広がりやすくなるため、育毛に良い影響を与えるのです。
運動習慣がホルモンバランスにもたらす変化
薄毛の大きな原因の一つに、男性ホルモン由来のジヒドロテストステロン(DHT)の存在があります。DHTは毛乳頭細胞に作用し、髪の成長を抑制します。
運動とホルモンバランスの関係は複雑ですが、激しすぎる運動は一時的にテストステロンレベルを上げる可能性があります。
しかし、継続的で中程度の強度の運動は、全身の代謝を改善し、ホルモンバランスの急激な変動を抑える方向に作用すると考えられます。
特に、運動による質の高い睡眠の確保は、成長ホルモンの分泌を促します。成長ホルモンは、毛髪を含む全身の細胞修復や再生に深く関わっているため、結果的に健康な髪の成長をサポートするのです。
運動によって内分泌系の健康を維持することは、薄毛対策において大切です。
育毛のために取り入れるべき「はげ防止運動」の基本原則
薄毛対策を目的とした運動は、単に体を疲れさせるだけでなく、頭皮の血行促進と全身の健康改善に焦点を当てる必要があります。
ここでは、育毛効果を期待できる「はげ防止運動」の基本的な考え方と具体的な運動方法を紹介します。
育毛に重要な運動の強度と頻度
育毛を目的とする場合、運動の「質」と「継続性」が重要です。
激しい筋力トレーニングは、かえって体に大きな負担をかけ、薄毛の主な原因とされる男性ホルモンの影響を強める可能性も否定できません。育毛に望ましいのは、中程度の強度の有酸素運動です。
具体的には、「少し息が上がるが、隣の人と会話ができる程度」の運動強度を目安にしましょう。頻度は、週に3回から5回程度、1回あたり30分以上継続することが望ましいとされます。
毎日続けることが理想ですが、無理なく習慣化できる頻度から始めることが大切です。継続することで、基礎代謝が上がり、常に良い血流を維持できるようになります。
血流改善に特化した有酸素運動の紹介
頭皮の血流を効果的に改善するためには、全身の血流を良くする有酸素運動が適しています。体内の酸素利用効率を高め、心臓から遠い末端の血管まで血液を行き渡らせる効果があるからです。
代表的な有酸素運動として、ウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリングなどがあげられます。
特にウォーキングは体への負担が少なく、特別な道具も不要なため、運動を始めるきっかけとして優れています。
歩く際に、ただ漫然と歩くのではなく、少し早歩きを意識し、腕を大きく振ることで、全身の筋肉を使い、血流促進効果を高めます。
ストレス軽減に役立つ運動の考え方
前述の通り、ストレスは薄毛の大きな原因です。運動には、このストレスを軽減する優れた効果があります。
特に、自然の中で行う運動や、ヨガ、太極拳のような呼吸を意識する運動は、精神的なリラックス効果が高いです。
運動中は、ネガティブな思考から解放され、運動自体に意識を集中できます。
この「運動瞑想」とも言える状態が、心の緊張を解きほぐし、結果として自律神経のバランスを整え、頭皮の血流改善にも寄与します。
運動を選ぶ際は、心から楽しめるものを選ぶことが継続の鍵となります。
運動の種類別と育毛への効果
| 運動の種類 | 主な育毛への作用 | 推奨頻度・時間 |
|---|---|---|
| ウォーキング/ジョギング | 全身の血行促進、ストレス軽減 | 週3〜5回、30分以上 |
| 水泳/サイクリング | 全身持久力向上、心肺機能強化 | 週2〜3回、45分程度 |
| ヨガ/ストレッチ | 自律神経調整、リラックス効果、血流改善 | 毎日10〜20分 |
自宅で簡単にできる血行促進のための運動とストレッチ
ジムに通う時間がない、外で運動するのは気が進まないという方でも、自宅や職場の休憩時間に簡単に取り組める血行促進運動はたくさんあります。
これらの運動は、特別な器具を使わず、短時間で効果を得られるため、忙しい現代人にとって非常に有用です。
頭皮の血流を促す首・肩周りのストレッチ
頭皮への血流は、首や肩周りの筋肉の緊張によって妨げられがちです。特にデスクワークなどで長時間同じ姿勢を続けていると、これらの筋肉が凝り固まり、血流が悪くなります。
これを解消するためには、定期的なストレッチが非常に効果的です。
首をゆっくりと前後左右に倒したり、大きく回したりするストレッチは、凝り固まった筋肉をほぐし、頭部への血液の流れを物理的に改善します。
また、肩甲骨を意識して回す運動や、両手を組んで頭上で伸びをする運動も、首や肩の緊張を和らげ、頭皮への血流をスムーズにするために大切です。
これらのストレッチは、休憩時間などにこまめに取り入れるようにしましょう。
副交感神経を優位にするリラックス運動
薄毛対策の観点から見ると、運動の目的は「体を疲れさせること」ではなく「リラックスさせること」も含まれます。
副交感神経を優位にすることは、血管を拡張させ、結果として頭皮の血流を良くするために重要です。
そのために有効なのが、深い呼吸と組み合わせた運動です。例えば、簡単な腹式呼吸をしながらのウォーキングや、ゆっくりとしたペースでの太極拳やヨガのポーズなどです。
特に、就寝前には、深呼吸を取り入れた軽いストレッチや瞑想を行うことで、副交感神経を優位にし、質の高い睡眠を促すことができます。
良質な睡眠は、髪の成長に必要な成長ホルモンの分泌に直結するため、非常に重要です。
継続するために取り入れたい運動の工夫
どんなに良い運動でも、継続できなければ意味がありません。運動を習慣化するためには、日々の生活に自然に組み込む工夫が必要です。
- エレベーターを使わず階段を利用する
- 通勤時に一駅分歩く習慣をつける
- テレビを見ながら腹筋やスクワットを行う
これらの工夫は、「運動するぞ」と意気込まなくても、日々の動作の延長として運動を取り入れることができます。
また、運動した内容を簡単なメモに残したり、スマートフォンアプリで記録したりするのも良いでしょう。小さな達成感の積み重ねが、長期的な継続のモチベーション維持につながります。
効果を最大化する育毛運動の適切なタイミングと習慣
育毛のための運動効果を最大限に引き出すためには、運動そのものだけでなく、運動を行うタイミングや、それに付随する生活習慣が重要になります。
運動と他の習慣を組み合わせることで、体全体の健康状態が向上し、結果として髪の成長を力強くサポートします。
運動前後の水分補給と栄養摂取の重要性
運動によって血流が良くなると、発汗量が増えます。汗と一緒に、体内の水分だけでなく、ミネラルなどの重要な栄養素も失われます。
運動前後に適切な水分補給を行うことは、血液の濃度を保ち、血流のスムーズさを維持するために必要です。水分が不足すると血液がドロドロになり、せっかく運動しても血行が悪くなる可能性があります。
また、運動後は、疲労した筋肉の修復や、失われたエネルギーを補給するために、栄養摂取が大切です。特に、髪の毛の原料となるタンパク質を意識的に摂るようにしましょう。
運動後の30分から1時間以内は、栄養が吸収されやすいゴールデンタイムと言われるため、このタイミングでのプロテインやアミノ酸の摂取は非常に効果的です。
運動と連携させたい水分・栄養摂取
| タイミング | 目的 | 推奨する摂取内容 |
|---|---|---|
| 運動前 | 血液循環の準備 | 水、またはスポーツドリンク |
| 運動中 | 脱水防止、ミネラル補給 | 水、または電解質を含む飲み物 |
| 運動後 | 筋肉修復、髪の原料補給 | タンパク質(プロテイン)、ビタミンB群 |
運動後の入浴と睡眠が育毛に与える影響
運動で体が温まり、血流が良くなった状態を、さらに高めるのが入浴と睡眠です。運動後の温かい湯船に浸かることは、全身の緊張を解きほぐし、血行をさらに促進します。
この時、頭皮の血管も広がりやすくなるため、育毛剤を使用するタイミングとしても効果的です。
そして、最も大切なの良質な睡眠です。運動によって適度な疲労感を得ることで、夜間の睡眠の質が向上します。前述の通り、髪の成長を促す成長ホルモンは、深い睡眠(ノンレム睡眠)中に多く分泌されます。
運動後の体の状態を整え、質の高い睡眠を確保することは、薄毛対策において運動と同じくらい重要であると理解しましょう。
運動習慣を途切れさせないための計画の立て方
運動を「一時的なイベント」で終わらせず、「生涯の習慣」にするためには、無理のない計画を立てることが求められます。最初に高すぎる目標を設定すると、達成できなかった時の挫折感が大きくなります。
最初の1ヶ月は「週に3回、15分のウォーキング」など、必ず達成できる簡単な目標から始めます。目標を達成できたら、徐々に「週4回、20分に増やす」といった形で、負荷を段階的に上げるようにしましょう。
また、体調が優れない日は思い切って休むことも、長期的な継続には大切です。運動が義務ではなく、生活の一部として自然に組み込まれるように工夫しましょう。
薄毛対策に役立つ運動と食事の相乗効果
髪の毛は、摂取した栄養から作られます。運動によって全身の代謝が上がり、血流が改善しても、その血液に乗せる「材料」が不足していれば、十分な育毛効果は期待できません。
運動で体内の吸収率が高まっている状態を活かし、適切な食事を摂ることで、薄毛対策の相乗効果を生み出します。
髪の成長をサポートする三大栄養素
髪の毛を構成する主成分はタンパク質であり、髪の成長には、タンパク質、ビタミン、ミネラルの三大栄養素が欠かせません。
良質なタンパク質は、肉、魚、卵、大豆製品からバランス良く摂取しましょう。特に、アミノ酸のバランスが良い食材を選ぶことが重要です。
また、タンパク質の合成を助けるビタミンB群や、毛母細胞の働きを活性化する亜鉛などのミネラルも、積極的に食事に取り入れることが大切です。
運動によって代謝が上がっているときは、これらの栄養素を効率よく取り込むチャンスです。
運動時に消費されるミネラルとビタミンの補給
運動をすると、汗によって多くのミネラル(特に亜鉛やマグネシウム)が体外へ排出されます。亜鉛は、髪の主成分であるケラチンの合成に深く関わる重要なミネラルです。
これが不足すると、髪の生成が滞る可能性があります。
運動後は、牡蠣、牛肉、レバー、ナッツ類など、亜鉛を多く含む食品を意識して摂るようにしましょう。また、血流改善を助けるビタミンEや、頭皮の健康を保つビタミンA・Cなども、薄毛対策において重要です。
これらのビタミンは、抗酸化作用も持つため、頭皮の老化を防ぐ上でも役立ちます。
育毛を支える栄養素と食材
| 栄養素 | 主な育毛への働き | 代表的な食材 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の原料(ケラチン) | 鶏むね肉、卵、大豆製品 |
| 亜鉛 | ケラチン合成の補酵素 | 牡蠣、牛肉、レバー |
| ビタミンB群 | エネルギー代謝、頭皮の健康維持 | 玄米、豚肉、魚介類 |
運動習慣が健康的な体重維持に果たす役割
肥満は、血行不良や生活習慣病のリスクを高めるだけでなく、ホルモンバランスの乱れにもつながり、薄毛を進行させる一因となり得ます。
適度な運動を習慣化することは、健康的な体重を維持し、全身の代謝機能を正常に保つために非常に大切です。
特に内臓脂肪の過剰な蓄積は、炎症を引き起こし、全身の健康を害します。運動による脂肪燃焼効果は、血液をサラサラに保ち、頭皮を含む全身への血流を改善します。
結果として、運動は薄毛対策だけでなく、健康寿命を延ばす上でも重要な役割を果たすのです。
運動だけでは不足する場合の追加の対策
運動は薄毛対策の土台作りに欠かせませんが、AGA(男性型脱毛症)のように遺伝やホルモンが深く関わる場合、運動だけでは十分な効果を得られないこともあります。
ここでは、運動習慣と組み合わせて、さらに育毛効果を高めるための追加対策について解説します。
市販の育毛剤を効果的に使用する方法
運動によって頭皮の血行が良くなっている状態は、育毛剤の成分を頭皮に浸透させやすい環境を作ります。育毛剤は、主に血行促進や頭皮環境の改善を目的とした成分を含んでいます。
運動後の入浴で頭皮が清潔になり、血行も良くなっているタイミングで育毛剤を使用することが、効果を最大化する鍵です。
育毛剤を使用する際は、必ず用法・用量を守り、優しくマッサージしながら塗布するようにしましょう。強く擦りすぎるマッサージは、かえって頭皮を傷つけ、炎症を起こす原因になりかねません。
運動後のケアとして、リラックスした状態で行うことが大切です。
育毛剤の効果的な使用ポイント
| 実施事項 | 目的 | 注意点 |
|---|---|---|
| 使用タイミング | 血行促進状態の利用 | 運動後、入浴後の清潔な頭皮 |
| 塗布方法 | 成分の浸透促進 | 指の腹で優しくマッサージ |
| 継続期間 | 毛髪サイクルの調整 | 最低でも4〜6ヶ月は継続 |
専門クリニックでの相談を検討する基準
以下のような症状が見られる場合は、セルフケアの限界と判断し、専門のクリニックに相談することを検討すべきです。
* 抜け毛の量が急に増え、改善の兆しが見えない * 生え際や頭頂部の薄毛が明らかに進行している * 頭皮に炎症やかゆみ、痛みなどのトラブルがある
専門クリニックでは、薄毛の原因を正確に診断し、個々の症状に合わせた治療法(投薬など)を提案します。運動習慣は、クリニックでの治療効果をサポートする土台となります。
運動を続けながら、専門家のアドバイスを取り入れることで、より確実な対策を講じることができます。
運動と組み合わせたいその他の生活習慣の見直し
薄毛対策は、運動、食事、睡眠、そしてストレス管理の総合的な取り組みが求められます。運動習慣を身につけることに成功したら、その他の生活習慣も見直しましょう。
特に、喫煙や過度の飲酒は、血管を収縮させたり、体内の栄養吸収を妨げたりするため、せっかくの運動効果を打ち消してしまう可能性があります。
また、紫外線による頭皮へのダメージも無視できません。屋外で運動する際は、帽子を着用するなど、頭皮を保護する対策も合わせて実施することが重要です。
運動不足解消ではげを防ぐ具体的な習慣化の秘訣
運動を継続するためには、強い意志だけでなく、生活の中に取り込みやすい具体的な「秘訣」を知ることが大切です。
ここでは、運動を「やらなければならないこと」から「やりたいこと」に変えるための方法を紹介します。
モチベーションを維持する目標設定の方法
運動のモチベーションを維持するためには、「SMARTの法則」を応用した目標設定が有効です。
SMARTの法則に基づいた目標設定
| 要素 | 意味 | 具体例 |
|---|---|---|
| S (Specific) | 具体的である | 「体重を2kg減らす」 |
| M (Measurable) | 測定可能である | 「週に3回、30分散歩する」 |
| A (Achievable) | 達成可能である | 「現在の体調で無理なくできる」 |
| R (Relevant) | 関連性がある | 「健康的な体で薄毛対策を行う」 |
| T (Time-bound) | 期限がある | 「3ヶ月後までに達成する」 |
漠然と「運動する」ではなく、「3ヶ月後までに週に3回、30分の早歩きを習慣化する」といった具体的な目標を設定することで、何をすべきかが明確になり、達成度を測定できるため、モチベーションを維持しやすくなります。
運動を趣味として楽しむための提案
薄毛対策という目的だけでなく、運動そのものを楽しむ視点を持つことで、継続性は格段に向上します。
例えば、今まで興味がなかったスポーツ(卓球、バドミントン、登山など)に挑戦してみるのも良いでしょう。
また、音楽を聴きながらのウォーキングや、動画を見ながらのストレッチなど、運動以外の楽しみを組み合わせるのも一つの方法です。
運動を「つらいもの」ではなく、「リフレッシュや気分転換の時間」として捉え直すことで、自然と運動を求めるようになります。
運動仲間を見つけるメリット
一人で運動を続けるのが難しいと感じる場合は、友人や家族を誘って一緒に運動するのも有効な手段です。
運動仲間がいると、お互いに励まし合ったり、運動の進捗を報告し合ったりすることで、モチベーションを維持しやすくなります。
また、地域のスポーツクラブやサークルに参加するのも良いでしょう。新しい人間関係の中で運動に取り組むことで、運動自体が単なる薄毛対策ではなく、生活の楽しみの一つになります。
他人との約束は、自分との約束よりも破りにくいものです。運動をサボりそうになった時の歯止めとしても役立ちます。
Q&A
薄毛対策としての運動に関して、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- 運動はAGAによる薄毛にも効果がありますか?
-
AGAは男性ホルモンや遺伝が主な原因であるため、運動だけで薄毛を完全に治すことは難しいです。
しかし、運動によって血行が改善され、頭皮環境が整うことで、AGA治療薬の効果を高める土台作りにはなります。
運動はあくまで補助的な役割と捉え、専門的な治療と並行して取り組むことが大切です。
- 筋力トレーニングは薄毛を悪化させると聞きましたが本当ですか?
-
筋力トレーニング、特に高負荷の無酸素運動は、一時的に男性ホルモン(テストステロン)の分泌を促す可能性があります。
テストステロンの一部は、薄毛の原因となるDHTに変換されるため、「筋トレは薄毛を悪化させる」と言われることがあります。
しかし、中程度の筋トレであれば問題ない場合が多く、全身の代謝向上というメリットもあります。過度な負荷をかけすぎず、有酸素運動とバランス良く行うことが重要です。
- どのような運動が最も育毛に良い影響を与えますか?
-
育毛に最も良い影響を与えるのは、血流促進とストレス軽減を目的とした中程度の有酸素運動です。
具体的には、少し息が上がる程度のウォーキングやジョギング、水泳などが挙げられます。
これらに加えて、首や肩の緊張をほぐすストレッチや、リラックス効果の高いヨガなどを組み合わせることで、より効果を高めることができます。
- 運動を始めたらすぐに効果を実感できますか?
-
運動を始めてすぐに髪が生えるといった直接的な効果は期待できません。
髪の毛には成長サイクルがあり、運動によって頭皮環境が改善されても、その影響が新しい髪として現れるまでには、通常3ヶ月から半年以上の時間が必要です。
焦らず、まずは運動を継続することを目標にし、長期的な視点で取り組む姿勢が大切です。
- 運動する時間がない場合、どうすれば良いですか?
-
運動する時間が取れない場合でも、日常生活の中で運動量を増やす工夫が有効です。
例えば、エレベーターやエスカレーターを使わずに階段を使う、一駅分歩く、通勤中に簡単なストレッチを行うなどです。
これらの「ながら運動」を積み重ねることで、血流改善効果を得ることができます。また、就寝前の10分間のストレッチだけでも、リラックス効果と血流促進に役立ちます。
Reference
KWAK, In-Sil; PARK, Sang-Hee. The effects of combined exercise and scalp care on the scalp and hair condition of male with alopecia. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 2021, 25.1: 993-998.
HALL, Rebecca R., et al. Hair care practices as a barrier to physical activity in African American women. JAMA dermatology, 2013, 149.3: 310-314.
WOLFF, Hans; FISCHER, Tobias W.; BLUME-PEYTAVI, Ulrike. The diagnosis and treatment of hair and scalp diseases. Deutsches Ärzteblatt International, 2016, 113.21: 377.
PHILLIPS, T. Grant; SLOMIANY, W. Paul; ALLISON, Robert. Hair loss: common causes and treatment. American family physician, 2017, 96.6: 371-378.
HUEBSCHMANN, Amy G., et al. “My hair or my health:” overcoming barriers to physical activity in African American women with a focus on hairstyle-related factors. Women & health, 2016, 56.4: 428-447.
JOSEPH, Rodney P., et al. Hair as a barrier to physical activity among African American women: a qualitative exploration. Frontiers in public health, 2018, 5: 367.
HUANG, Xinlyu, et al. Application of non-pharmacologic therapy in hair loss treatment and hair regrowth. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2024, 1701-1710.
RAJOO, Yamuna, et al. The relationship between physical activity levels and symptoms of depression, anxiety and stress in individuals with alopecia Areata. BMC psychology, 2019, 7.1: 48.
NATARELLI, Nicole; GAHOONIA, Nimrit; SIVAMANI, Raja K. Integrative and mechanistic approach to the hair growth cycle and hair loss. Journal of clinical medicine, 2023, 12.3: 893.
PRICE, Vera H. Treatment of hair loss. New England Journal of Medicine, 1999, 341.13: 964-973.