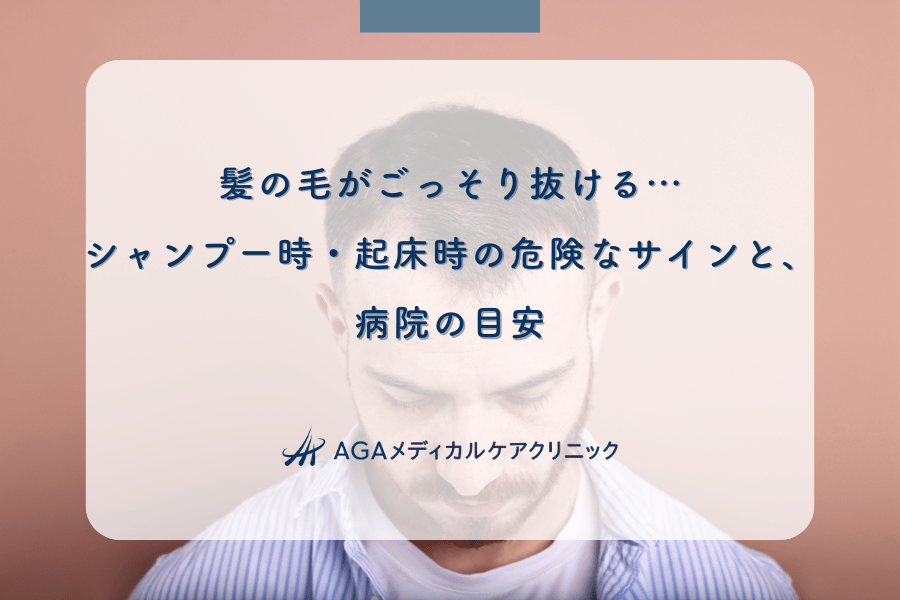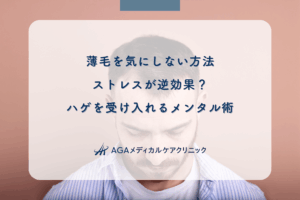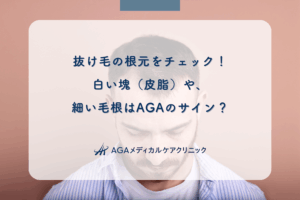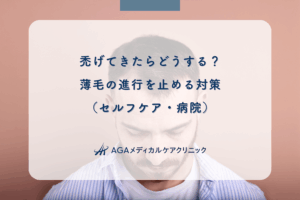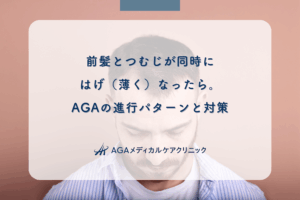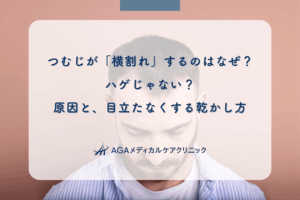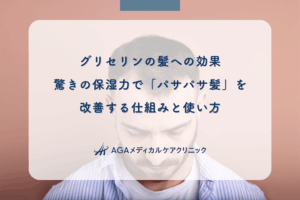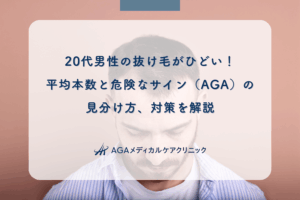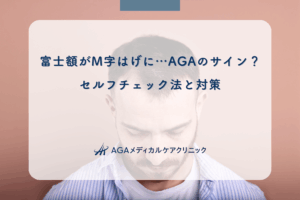シャンプー中や朝起きた時、排水溝や枕にごっそりと抜けた髪の毛を見て、言葉にならない不安を感じていませんか。その抜け毛、本当に大丈夫でしょうか。
この記事では、髪の毛がごっそり抜ける状態が示す危険なサインやその背景にある多様な原因、そして病院を受診すべき目安について詳しく解説します。
自分の今の状態を正しく知り、適切な対応を早期に始めることで、将来の髪を守る大切な第一歩を踏み出せます。まずは、その抜け毛が発している危険なサインを見極めることが重要です。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
「髪の毛がごっそり抜ける」と感じる瞬間
日常生活の中で、ふとした瞬間に「髪の毛がごっそり抜けた」と感じ、不安がよぎることがあります。
多くの人が経験する典型的な場面と、正常な範囲の抜け毛との違いについて理解を深めましょう。
シャンプー時の排水溝を見て愕然
一日の汚れを洗い流すシャンプー時は、抜け毛を最も実感しやすい瞬間です。髪を洗っている最中、指に絡みつく毛や、洗い流した後に排水溝に溜まる毛の量を見て、驚く人は少なくありません。
毎日目にする光景だからこそ、少しの変化にも敏感になりがちです。特に、以前よりも明らかに量が増えたと感じた場合、強い不安を覚えることになります。
朝起きた時の枕を見て不安に
朝、目を覚まして枕を見ると、そこに散らばる髪の毛。一本や二本なら気にならなくても、まとまった本数が落ちていると「寝ている間にこんなに抜けたのか」と心配になります。
枕カバーの色によっては抜け毛が目立ちやすく、必要以上に多く抜けていると感じることもありますが、これが毎日続くようであれば注意が必要です。
手ぐしを通した時の指への絡まり
日中に何気なく髪をかきあげたり、手ぐしを通したりした際に、指に数本の髪の毛が絡んでくることがあります。これも抜け毛を意識する瞬間です。
特に、スタイリング剤をつけていない乾いた髪でさえ、手を通すたびに抜けるようだと、髪全体のボリュームダウンにもつながるのではないかと心配になるものです。
正常な抜け毛と危険な抜け毛の違い
人の髪の毛は、ヘアサイクル(毛周期)によって毎日自然に抜け落ちています。
全ての毛が抜け落ちているわけではなく、成長し、やがて抜け、また新しく生えるというサイクルを繰り返しているのです。
正常な範囲内での抜け毛と、注意すべき危険な抜け毛には違いがあります。
正常範囲と注意が必要な抜け毛の目安
| 項目 | 正常な抜け毛 | 危険な抜け毛のサイン |
|---|---|---|
| 1日の本数 | 約50本〜100本程度 | 明らかに100本を超える(例:200本以上) |
| 抜け毛の毛根 | 白っぽく丸みがある(毛根鞘) | 毛根がない、または黒く小さい |
| 抜け毛の太さ | 太くしっかりしている | 細く短い毛、うぶ毛のような毛が多い |
1日に抜ける本数には個人差があり、季節によっても変動します。
しかし、上記の表にあるように、抜ける本数が急激に増えたり、抜け毛の質(毛根の状態や太さ)に変化が見られたりする場合は、何らかの異常が起きているサインかもしれません。
なぜ髪の毛はごっそり抜けるのか?その原因
髪の毛がごっそり抜ける背景には、様々な原因が隠れています。一つの要因だけではなく、複数が絡み合っていることも少なくありません。
代表的な原因を知り、自分の状況と照らし合わせてみましょう。
ヘアサイクル(毛周期)の乱れとは
髪の毛には「成長期」「退行期」「休止期」というサイクルがあります。健康な状態では、ほとんどの髪(約85〜90%)が成長期にあり、数年かけて太く長く成長します。
しかし、何らかの原因でこのサイクルが乱れると、成長期が短縮されます。その結果、髪が十分に成長する前に退行期や休止期に移行してしまい、細く短いまま抜け落ちる毛が増えるのです。
これが「ごっそり抜ける」と感じる一因です。
髪の毛のヘアサイクル
| 段階 | 期間の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 成長期 | 2年〜6年 | 髪が活発に成長する期間。全体の約85〜90%。 |
| 退行期 | 約2週間 | 髪の成長が止まり、毛根が退縮し始める。 |
| 休止期 | 約3ヶ月〜4ヶ月 | 髪が抜け落ちるのを待つ期間。新しい髪の準備が始まる。 |
男性ホルモンの影響(AGA)
成人男性の抜け毛で最も多い原因の一つがAGA(男性型脱毛症)です。
これは、男性ホルモンの一種であるテストステロンが、特定の酵素(5αリダクターゼ)と結びついてジヒドロテストステロン(DHT)に変化することが引き金となります。
このDHTが毛根の受容体と結合すると、髪の成長期を短縮させる信号が出され、抜け毛が進行します。特に前頭部や頭頂部から薄くなる特徴があり、遺伝的な要因も関与すると考えられています。
生活習慣の乱れによる影響
日々の生活習慣も、髪の健康に深く関わっています。頭皮も体の一部であり、不健康な生活は頭皮環境の悪化や髪の成長に必要な栄養不足を招きます。
栄養バランスの偏り
髪の毛は主にケラチンというタンパク質でできています。
過度なダイエットや偏った食事により、タンパク質や、その合成を助ける亜鉛、ビタミン類が不足すると、健康な髪を作ることが難しくなります。
特に外食やインスタント食品が多いと、脂質や糖質の過剰摂取につながり、頭皮の皮脂バランスを崩す原因にもなります。
睡眠不足の影響
髪の成長を促す成長ホルモンは、主に睡眠中に分泌されます。
特に夜22時から深夜2時の間がゴールデンタイムといわれることがありますが、時間帯よりも「質の良い睡眠を十分にとる」ことが重要です。
睡眠不足が続くと、成長ホルモンの分泌が減少し、髪の成長や頭皮のターンオーバー(新陳代謝)に悪影響を与えます。
喫煙と飲酒
喫煙は血管を収縮させ、頭皮への血流を悪化させます。血流が悪くなると、髪の成長に必要な栄養素や酸素が毛根まで届きにくくなります。
適度な飲酒は問題ないとされますが、過度な飲酒は肝臓でアルコールを分解する際に、髪に必要なアミノ酸やビタミンを消費してしまうため、注意が必要です。
ストレスが頭皮に与える影響
精神的なストレスも抜け毛の大きな要因です。強いストレスを感じると、自律神経のバランスが乱れ、交感神経が優位な状態が続きます。これにより血管が収縮し、頭皮の血行不良を引き起こします。
また、ストレスはホルモンバランスの乱れにもつながり、頭皮環境を悪化させ、抜け毛を促進することがあります。円形脱毛症のように、急激なストレスが原因でごっそり抜けるケースも存在します。
シャンプー時・起床時に見るべき危険なサイン
抜け毛の「本数」だけに注目しがちですが、それ以外にも注意深く観察すべき「危険なサイン」があります。
シャンプー時や起床時に、抜け毛の質や頭皮の状態も併せてチェックする習慣をつけましょう。
抜け毛の本数以外のチェックポイント
前述の通り、1日100本程度までは正常な抜け毛の範囲内とされることが多いです。しかし、本数だけでなく「抜け毛の質」の変化が、より重要なサインとなることがあります。
シャンプー時や枕に残った抜け毛を、ただ捨てるのではなく、少し観察してみてください。
抜け毛の「質」に注目する
抜けた髪の毛が、どのような状態であるかを確認します。健康な髪は太く、ハリやコシがありますが、危険なサインとして抜けている毛は、細く、弱々しいことが多いです。
抜け毛の質チェック
| チェック項目 | 危険なサインの可能性 | 考えられる状態 |
|---|---|---|
| 毛の太さ | 細く短い毛、うぶ毛のような毛が多い | ヘアサイクルが乱れ、成長期が短縮している |
| 毛根の状態 | 毛根が付いていない、または黒く小さい | 毛根が弱っている、または成長途中で抜けている |
| 毛根の形 | 毛根の先端が尖っている、いびつ | 何らかのダメージや異常で抜けた可能性がある |
正常な休止期で抜けた毛の毛根は、白っぽく丸みを帯びた「毛根鞘(もうこんしょう)」という組織が付着しているのが一般的です。
これがない、または極端に小さい場合は注意が必要です。
頭皮の状態をセルフチェック
抜け毛は、その土台である頭皮環境の悪化によって引き起こされることも多々あります。鏡を使って、自分の頭皮の色や状態を確認してみましょう。
頭皮の色と状態の目安
| 頭皮の色 | 状態 | 考えられる原因 |
|---|---|---|
| 青白い色 | 健康な状態 | 血行が良く、透明感がある |
| 黄色っぽい色 | 注意 | 皮脂の酸化、血行不良、生活習慣の乱れ |
| 赤っぽい色 | 危険なサイン | 炎症、かゆみ、血行不良、刺激 |
健康な頭皮は青白い色をしています。黄色っぽくなっている場合は皮脂の分泌が過剰であったり、新陳代謝が滞っていたりする可能性があります。
赤みがある場合は、炎症を起こしているサインであり、早急なケアが必要です。
フケやかゆみはSOSのサインか
フケやかゆみも頭皮環境の悪化を示す重要なサインです。フケには種類があり、それぞれ原因が異なります。
乾燥性のフケ
カサカサとした細かいフケが出る場合、頭皮が乾燥している可能性があります。洗浄力の強すぎるシャンプーの使用や、空気の乾燥、洗いすぎが原因であることが多いです。
脂性(しせい)のフケ
ベタベタとした湿ったフケが出る場合、皮脂の過剰分泌が考えられます。
脂っこい食事の偏りや、洗い残し、ホルモンバランスの乱れなどが原因で、雑菌(マラセチア菌など)が繁殖しやすい状態になっている可能性があります。
脂漏性皮膚炎などの病気につながることもあるため、注意が必要です。
これらフケやかゆみを伴う抜け毛は、頭皮環境がかなり悪化している証拠であり、対策を講じる必要があります。
髪の毛がごっそり抜けるのを放置するリスク
「そのうち治まるだろう」と、髪の毛がごっそり抜ける状態を放置してしまうと、様々なリスクを招く可能性があります。
早期に対処しなかった場合、どのような事態が考えられるでしょうか。
薄毛が進行してしまう可能性
最も直接的なリスクは、薄毛がそのまま進行してしまうことです。特にAGA(男性型脱毛症)が原因である場合、放置すると症状は徐々に進行していきます。
ヘアサイクルが乱れたまま元に戻らず、成長期が短縮され続けることで、新しく生えてくる髪よりも抜け落ちる髪のほうが多くなり、全体的なボリュームダウンや地肌の露出が目立つようになります。
頭皮環境のさらなる悪化
フケやかゆみ、頭皮の赤みといったサインを放置すると、頭皮環境はさらに悪化します。
脂漏性皮膚炎などの皮膚疾患が慢性化し、炎症が続くことで毛根がダメージを受け、健康な髪が育ちにくい土壌になってしまいます。
一度悪化した頭皮環境を正常に戻すには時間がかかるため、問題が小さいうちに対処することが重要です。
隠れた病気の可能性
抜け毛は、単なる髪の問題ではなく、体内の異常を知らせるサインである可能性もあります。例えば、甲状腺機能の異常(亢進症や低下症)は、髪の毛の成長に影響を与え、抜け毛を引き起こすことがあります。
また、自己免疫疾患(円形脱毛症など)や、特定の薬剤の副作用、極度の栄養障害などが原因であることも。
ごっそり抜けるという症状の裏に、専門的な治療を必要とする病気が隠れているリスクも考慮しなくてはなりません。
精神的な負担の増大
抜け毛が増え、見た目の変化が現れ始めると、それは大きな精神的ストレスとなります。
人前に出るのが億劫になったり、他人の視線が気になったりすることで、自信を喪失してしまうケースも少なくありません。
この精神的なストレスが、さらに自律神経のバランスを崩し、血行不良を招くなどして、抜け毛を悪化させるという悪循環に陥る可能性もあります。
病院(皮膚科・AGAクリニック)を受診する目安
抜け毛の増加に気づいた時、セルフケアで様子を見るべきか、専門の病院を受診すべきか、迷う人も多いでしょう。ここでは、病院での相談を検討すべき目安について解説します。
どれくらい抜けたら受診すべきか
明確に「1日に何本抜けたら受診」という基準はありません。しかし、以下のような状態が続く場合は、受診を検討する目安となります。
- 明らかに以前より抜け毛の量が増え、それが2〜3ヶ月以上続いている
- 1日に200本を超えるような抜け毛が連日ある
- 髪全体のボリュームが減り、地肌が透けて見えるようになってきた
本数だけでなく、前述した「抜け毛の質(細く短い毛が多い)」や「頭皮の状態(赤み、フケ、かゆみがひどい)」の変化も重要な判断材料です。
抜け毛以外のこんな症状が出たら要注意
抜け毛と同時に、体調に他の変化が現れた場合は、皮膚科や内科など、適切な診療科の受診が必要です。
- 急激な体重の増減
- 異常な倦怠感、疲れやすさ
- 頭皮以外の体毛の変化
これらの症状は、甲状腺疾患など内科的な病気のサインである可能性もあります。抜け毛だけでなく、体全体の調子にも目を向けてください。
病院ではどんな検査や治療を行うのか
専門のクリニックや皮膚科では、まず抜け毛の原因を特定するための診察や検査を行います。治療法は原因によって異なります。
主な検査と治療の例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 問診 | 抜け毛が始まった時期、生活習慣、既往歴、家族歴などを確認 |
| 視診・触診 | 頭皮の状態(色、炎症の有無)、毛髪の密度、抜け毛のパターンを直接確認 |
| マイクロスコープ検査 | 特殊なカメラで頭皮や毛根の状態を拡大して詳細に観察 |
| 血液検査 | ホルモンバランスや、甲状腺機能、栄養状態(鉄分、亜鉛など)を確認 |
| AGAの治療例 | 内服薬(5αリダクターゼ阻害薬など)や外用薬(ミノキシジルなど)の処方 |
早期受診の重要性
抜け毛や薄毛の悩みは、早期に対処するほど、進行を食い止めたり、改善したりできる可能性が高まります。
特にAGAは進行性のため、放置している間に毛根の機能が低下しきってしまうと、治療の効果が出にくくなることもあります。
「まだ大丈夫」と自己判断せず、不安を感じたら一度専門家に相談することが、将来の髪を守るために非常に大切です。
自宅でできる抜け毛対策と頭皮ケア
病院での治療と並行して、または抜け毛が気になり始めた段階で、自宅でできる頭皮ケアや生活習慣の見直しも重要です。
日々の積み重ねが、健康な頭皮環境と髪を育む土台となります。
正しいシャンプー方法の見直し
毎日行うシャンプーは、頭皮環境に最も大きな影響を与える習慣の一つです。洗いすぎも、洗い残しも頭皮トラブルの原因となります。
シャンプーの基本的な手順
- ブラッシング:洗う前に髪のもつれを解き、ホコリや汚れを浮かせる
- 予洗い:シャンプー剤をつける前に、ぬるま湯(38度程度)で頭皮と髪をしっかり濡らし、汚れの大部分を落とす
- 泡立て:シャンプー剤を手のひらでよく泡立ててから、髪ではなく頭皮につける
- 洗う:指の腹を使って、頭皮をマッサージするように優しく洗う。爪を立てないこと
- すすぎ:シャンプー剤が残らないよう、時間をかけて念入りにすすぐ。特に生え際や耳の後ろは残りやすいので注意
シャンプーは1日1回を基本とし、自分の頭皮タイプ(乾燥肌、脂性肌など)に合った洗浄成分のものを選ぶことも大切です。
食生活で意識すべきこと
健康な髪は、日々の食事から摂取する栄養素によって作られます。特定の食品だけを食べるのではなく、バランスの良い食事を心がけることが基本です。
髪の成長に必要な主な栄養素
| 栄養素 | 主な役割 | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉、ナッツ類 |
| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を促す、皮脂の調節 | 豚肉、レバー、青魚、納豆 |
質の良い睡眠を確保する
睡眠中に分泌される成長ホルモンは、頭皮や髪の細胞の修復・再生に欠かせません。単に長く寝るだけでなく、「質の良い睡眠」を確保することが重要です。
寝る直前のスマートフォンやパソコンの使用は避け、リラックスできる環境を整えましょう。毎日決まった時間に寝て、決まった時間に起きる、規則正しい生活リズムも自律神経を整える上で役立ちます。
頭皮マッサージは効果があるか
頭皮マッサージは、頭皮の血行を促進し、毛根に栄養を届けやすくする助けとなります。また、リラックス効果により、ストレスの緩和にもつながる可能性があります。
シャンプー時や、育毛剤を塗布した際などに、指の腹で優しく頭皮全体をもみほぐすように行うと良いでしょう。
ただし、強くこすりすぎたり、爪を立てたりすると、逆に頭皮を傷つけてしまうため、力加減には注意が必要です。
将来の髪のために育毛剤で頭皮環境を整える
抜け毛の予防や、今ある髪を健やかに育むためには、日々の頭皮ケアが重要です。その選択肢の一つとして、育毛剤の使用があります。
育毛剤の役割を正しく理解し、自分の目的に合ったものを選びましょう。
育毛剤の役割と期待できること
育毛剤は、医薬品である「発毛剤」とは異なり、主に「今ある髪の毛を健康に育てる」ことや「抜け毛を予防する」ことを目的としています。
頭皮の血行を促進したり、頭皮環境を清潔に保ち、うるおいを与えたりすることで、髪が育ちやすい土壌を整えるサポートをします。
医薬品ではありませんが、抜け毛予防や毛髪の成長促進(※育毛剤の効能効果の範囲内)のために、日々のケアに取り入れる選択肢の一つです。
自分に合った育毛剤の選び方
育毛剤には様々な種類があり、配合されている成分によって特徴が異なります。自分の頭皮の状態や悩みに合わせて選ぶことが大切です。
育毛剤の主な有効成分と役割の例
| 成分の系統 | 期待される役割 | 主な成分例 |
|---|---|---|
| 血行促進 | 毛根への栄養補給をサポート | センブリエキス、ビタミンE誘導体 |
| 抗炎症 | フケやかゆみを抑え、頭皮環境を整える | グリチルリチン酸ジカリウム |
| 保湿 | 乾燥から頭皮を守り、柔軟に保つ | ヒアルロン酸、コラーゲン、セラミド |
例えば、頭皮の乾燥が気になる人は保湿成分が豊富なもの、フケやかゆみが気になる人は抗炎症成分が配合されたもの、といった選び方ができます。
育毛剤を使い始めるタイミング
育毛剤は、髪が薄くなってから使うもの、というイメージがあるかもしれませんが、頭皮環境を整える「予防」の観点から、抜け毛が気になり始めた段階や、将来のために頭皮ケアを始めたいと思ったタイミングで使い始めるのがおすすめです。
頭皮環境が大きく悪化する前にケアを始めることが、健やかな髪を維持するために重要です。
育毛剤使用時の注意点
育毛剤は、一度や二度使っただけですぐに変化が現れるものではありません。ヘアサイクルを考慮すると、最低でも3ヶ月から6ヶ月程度は継続して使用することが推奨されます。
また、使用方法を守り、清潔な頭皮に使用することが基本です。肌に合わないと感じた場合(かゆみや赤みが出た場合)は、すぐに使用を中止し、必要であれば皮膚科医に相談してください。
Q&A
- 抜け毛は一度始まったらもう止まらない?
-
抜け毛の原因によります。AGA(男性型脱毛症)のように進行性のものもありますが、その場合でも早期に適切な対策(専門的な治療など)を始めることで、進行を遅らせたり、現状を維持したりすることは期待できます。
一時的なストレスや生活習慣の乱れが原因であれば、その原因を取り除くことで抜け毛が改善する場合も多くあります。あきらめずに、まずは原因を知ることが大切です。
- 食事を変えれば抜け毛は減る?
-
食事は髪の健康に深く関係しています。
髪の材料となるタンパク質や、その働きを助ける亜鉛、ビタミン類などをバランス良く摂取することは、健康な髪を育む土台作りのために非常に重要です。
栄養バランスの取れた食事が頭皮環境を整えます。ただし、抜け毛の原因がAGAや他の病気である場合、食事の改善だけですべての抜け毛問題が解決するわけではありません。
あくまで対策の基本の一つと考えてください。
- 帽子をかぶると抜け毛が増えるのは本当?
-
帽子をかぶること自体が、直接的に抜け毛を増やすわけではありません。
むしろ、紫外線から頭皮を守るという点ではメリットもあります。ただし、長時間帽子をかぶり続けることで頭皮が蒸れ、汗や皮脂によって雑菌が繁殖しやすい環境になることはあります。
これが頭皮トラブル(かゆみ、炎症など)を引き起こし、結果として抜け毛に影響を与える可能性は否定できません。
通気性の良い素材を選んだり、こまめに汗を拭いたり、帽子自体を清潔に保つ工夫が必要です。
- 家族に薄毛の人がいなくても安心できない?
-
薄毛には遺伝的な要因が関与することが知られていますが、それが全てではありません。
遺伝的な要因がないと感じている人でも、後天的な要因、例えば過度なストレス、偏った食生活、睡眠不足、不適切な頭皮ケアなどが積み重なることで、ヘアサイクルが乱れ、抜け毛が増えることは十分にあり得ます。
遺伝はあくまで一因であり、日々の生活習慣や頭皮環境への配慮が重要です。
Reference
BLUME‐PEYTAVI, Ulrike, et al. S1 guideline for diagnostic evaluation in androgenetic alopecia in men, women and adolescents. British Journal of Dermatology, 2011, 164.1: 5-15.
ALESSANDRINI, A., et al. Common causes of hair loss–clinical manifestations, trichoscopy and therapy. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2021, 35.3: 629-640.
SPRINGER, Karyn; BROWN, Matthew; STULBERG, Daniel L. Common hair loss disorders. American family physician, 2003, 68.1: 93-102.
PHILLIPS, T. Grant; SLOMIANY, W. Paul; ALLISON, Robert. Hair loss: common causes and treatment. American family physician, 2017, 96.6: 371-378.
LIAMSOMBUT, Somprasong, et al. Sleep quality in men with androgenetic alopecia. Sleep and Breathing, 2023, 27.1: 371-378.
WINLAND-BROWN, Jill E.; PORTER, Brian Oscar. COMMON COMPLAINTS. Primary Care: Art and Science of Advanced Practice Nursing, 2015, 149.
ANASTASSAKIS, Konstantinos. Androgenetic Alopecia from A to Z. Switzerland: Springer, 2022.
SADGROVE, Nicholas, et al. An updated etiology of hair loss and the new cosmeceutical paradigm in therapy: Clearing ‘the big eight strikes’. cosmetics, 2023, 10.4: 106.
CRANWELL, William; SINCLAIR, Rodney. Male androgenetic alopecia. 2015.
BUCKLEY, David. Hair Loss and Hair Growth. In: Textbook of Primary Care Dermatology. Cham: Springer International Publishing, 2021. p. 347-359.