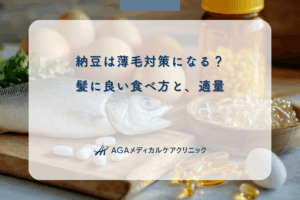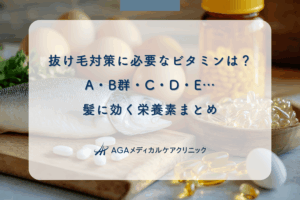鏡を見るたびに気になる、抜け毛や髪のボリューム。その悩み、もしかしたら毎日の「食べ物」が関係しているかもしれません。
薄毛予防というと育毛剤や頭皮マッサージを思い浮かべがちですが、髪も私たちの体の一部であり、日々の食事から作られています。
この記事では、薄毛予防と食べ物の関係を深く掘り下げ、髪の成長に必要な栄養素、積極的に摂りたい食事、そして避けるべきNGな食生活について詳しく解説します。
食生活を見直すことは、今日から始められる大切なヘアケアです。内側からのアプローチで、健やかな髪を育む第一歩を踏み出しましょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
なぜ食べ物が薄毛予防に関係するのか
薄毛や抜け毛の悩みは、多くの男性にとって深刻な問題です。その原因は遺伝やストレス、生活習慣など様々ですが、中でも「食事」は髪の健康状態に直接的な影響を与える重要な要素です。
なぜ食べ物が薄毛予防にこれほどまで関係するのか、その理由を基本的なところから見ていきましょう。
髪の毛も体の一部食事から作られる
非常に基本的なことですが、髪の毛は私たちが毎日口にする食べ物から得られる栄養素を基に作られています。
皮膚や爪と同じように、髪もタンパク質(主にケラチン)で構成されており、その成長にはビタミンやミネラルなど多岐にわたる栄養が必要です。
食事が偏ったり、栄養が不足したりすると、体は生命維持に重要な臓器へ優先的に栄養を送ります。その結果、髪の毛のような末端の部分は後回しにされがちです。
栄養が届かなければ、髪は細く弱々しくなり、正常な成長が妨げられ、結果として薄毛につながる可能性があります。
頭皮環境と栄養バランスの深い関係
健康な髪は、健康な頭皮という「土壌」から育ちます。頭皮の状態は、食事内容によって大きく左右されます。
例えば、脂っこい食事や糖分の多い食事を続けると、皮脂の分泌が過剰になり、頭皮がべたついたり、毛穴が詰まったりすることがあります。
毛穴の詰まりは炎症を引き起こし、髪の成長を妨げる原因となります。逆に、必要な栄養素が不足すると頭皮が乾燥し、フケやかゆみが発生しやすくなります。
このように、栄養バランスの取れた食事は、健やかな頭皮環境を維持するためにも重要です。
栄養不足が引き起こすヘアサイクルの乱れ
髪には「成長期」「退行期」「休止期」というヘアサイクル(毛周期)があります。健康な髪は、数年間にわたる成長期を経て、自然に抜け落ち、また新しい髪が生えてくるというサイクルを繰り返します。
しかし、食事からの栄養供給が不足すると、このヘアサイクルが乱れやすくなります。
特に髪の成長に必要なタンパク質や亜鉛、ビタミンなどが足りないと、本来長く続くはずの「成長期」が短縮され、髪が十分に太く長く成長する前に「退行期」や「休止期」に移行してしまいます。
その結果、細く短い毛が増え、全体のボリュームが失われて薄毛が目立つようになるのです。
髪の成長に必要不可欠な栄養素トップ3
薄毛予防のために食生活を見直す上で、特に意識して摂取したい栄養素があります。
髪の健康を支えるために、特に重要な3つの栄養素「タンパク質」「ビタミン」「ミネラル(亜鉛)」の働きについて解説します。
髪の成長を支える主な栄養素
| 栄養素 | 髪への主な働き | 含まれる主な食品例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料となる。 | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |
| ビタミン群 | 頭皮環境を整え、タンパク質の代謝を助ける。 | 緑黄色野菜、レバー、ナッツ類、豚肉 |
| ミネラル(亜鉛) | タンパク質の合成を助け、ヘアサイクルを正常に保つ。 | 牡蠣、レバー、赤身肉、ナッツ類 |
髪の主成分「タンパク質」(ケラチン)
髪の毛の約90%以上は、「ケラチン」というタンパク質でできています。このケラチンを体内で生成するためには、食事から十分なタンパク質を摂取することが絶対条件です。
タンパク質が不足すると、髪の材料が足りない状態になり、新しい髪が作られにくくなったり、生えてきても細く弱い髪になったりします。
肉、魚、卵、大豆製品など、良質なタンパク質源を毎日の食事にバランスよく取り入れることが、薄毛予防の基本中の基本と言えます。
頭皮の健康を守る「ビタミン群」
ビタミンは、体の機能を正常に保つために必要な栄養素であり、髪と頭皮の健康にも深く関わっています。特にビタミンB群(B2、B6など)は、タンパク質の代謝を助け、ケラチンの生成をサポートします。
また、皮脂の分泌をコントロールし、頭皮環境を健やかに保つ働きもあります。
ビタミンEは血行を促進する働きがあり、頭皮の毛細血管まで栄養を運ぶのを助けます。ビタミンCはコラーゲンの生成を助け、丈夫な頭皮を作るのに役立ちます。
これらのビタミンは相互に作用するため、単体ではなく「ビタミン群」としてバランスよく摂取することが大切です。
栄養を運ぶサポート役「ミネラル(特に亜鉛)」
ミネラルもまた、髪の健康維持に欠かせない栄養素です。中でも「亜鉛」は、タンパク質が髪の毛(ケラチン)に再合成される際に重要な役割を果たします。
亜鉛が不足すると、せっかくタンパク質を摂取しても、効率よく髪の毛を作ることができません。
また、亜鉛はヘアサイクルを正常に保つためにも必要です。不足すると成長期が短くなり、抜け毛が増える原因にもなります。
亜鉛は体内で作ることができず、汗などで失われやすいため、食事から意識的に補給する必要があります。
薄毛予防のために積極的に摂りたい食べ物
必要な栄養素がわかったところで、次にそれらの栄養素を豊富に含む具体的な食べ物を見ていきましょう。毎日の献立に上手に取り入れて、内側から髪を育てましょう。
良質なタンパク質を含む食材
タンパク質は髪の主原料です。動物性タンパク質と植物性タンパク質をバランスよく摂ることが理想です。
良質なタンパク質源の例
| 食材カテゴリー | 代表的な食材 | 摂取時のポイント |
|---|---|---|
| 肉類 | 鶏むね肉、ささみ、赤身肉、レバー | 脂身の少ない部位を選ぶ。レバーは亜鉛やビタミンも豊富。 |
| 魚介類 | アジ、サバ、イワシ(青魚)、鮭、牡蠣 | 青魚は血流を良くするEPA・DHAも含む。牡蠣は亜鉛が豊富。 |
| 卵・大豆製品 | 卵、豆腐、納豆、豆乳 | 卵は完全栄養食に近い。大豆イソフラボンも摂取できる。 |
特に大豆製品に含まれる「大豆イソフラボン」は、男性ホルモンの働きを調整するのに役立つ可能性が指摘されており、薄毛予防の観点からも注目されています。
ビタミン豊富な緑黄色野菜と果物
ビタミン群は頭皮環境を整え、タンパク質の働きを助けます。特に色の濃い緑黄色野菜には、ビタミンA(皮膚や粘膜を健康に保つ)やビタミンC、Eが豊富に含まれています。
意識したい緑黄色野菜
- ほうれん草
- ニンジン
- ブロッコリー
- ピーマン
- カボチャ
これらの野菜を毎日の食事に加えることで、頭皮の新陳代謝を促し、健康な状態を保つサポートをします。
果物もビタミンCやポリフェノールを摂取できますが、糖分も含まれるため食べ過ぎには注意しましょう。
注目ビタミンと主な役割
| ビタミン名 | 髪への主な役割 | 豊富な食材 |
|---|---|---|
| ビタミンA | 頭皮の新陳代謝を促し、潤いを保つ。 | レバー、ニンジン、ほうれん草、うなぎ |
| ビタミンB群 | タンパク質の代謝、皮脂分泌の調整。 | 豚肉、レバー、マグロ、カツオ、納豆 |
| ビタミンE | 血行を促進し、頭皮に栄養を届ける。 | アーモンド、ナッツ類、アボカド、植物油 |
亜鉛を多く含む食べ物
亜鉛はタンパク質の合成に必須のミネラルです。不足しないよう、日頃から意識して摂取したい栄養素です。
亜鉛の王様と呼ばれるのが「牡蠣」です。牡蠣は非常に多くの亜鉛を含んでおり、薄毛予防の観点からは積極的に摂りたい食材の筆頭です。
ただし、毎日食べるのは難しいため、他の食材からも補給することが大切です。
「レバー(特に豚)」や「牛肉(赤身)」にも亜鉛は豊富です。また、手軽に摂れる食材として「ナッツ類(アーモンドやカシューナッツ)」「ごま」「煮干し」なども良い亜鉛の供給源となります。
血行促進を助ける食材
どんなに栄養バランスの取れた食事をしても、その栄養が頭皮まで届かなければ意味がありません。栄養は血液によって全身に運ばれるため、血行を促進することも薄毛予防には重要です。
ビタミンE(ナッツ類、アボカドなど)や、青魚(サバ、イワシなど)に含まれるEPA・DHAは、血液をサラサラにし、血流を改善する働きが期待できます。
また、「生姜」や「唐辛子(カプサイシン)」なども体を温め、一時的に血行を促進するのに役立ちます。
ただし、唐辛子などの刺激物は、摂りすぎると胃腸に負担をかけたり、頭皮に逆に刺激となったりする可能性もあるため、適量を心がけましょう。
要注意!薄毛のリスクを高めるNGな食生活
髪に良い食べ物を摂るのと同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが、「髪に悪い食生活」を避けることです。
知らず知らずのうちに頭皮環境を悪化させ、薄毛を進行させる可能性のあるNGな食生活について確認しましょう。
避けるべき食事パターンと髪への影響
| NGな食事パターン | 主な原因 | 頭皮・髪への影響 |
|---|---|---|
| 脂質の過剰摂取 | 揚げ物、ジャンクフード、脂身の多い肉 | 皮脂の過剰分泌、毛穴の詰まり、頭皮の炎症。 |
| 糖分の過剰摂取 | 菓子類、清涼飲料水、甘いパン | 皮脂の分泌増加、糖化による頭皮の老化促進。 |
| 塩分の過剰摂取 | 加工食品、ラーメンの汁、味の濃い外食 | 血流の悪化、高血圧による血行不良。 |
過剰な脂質の摂取(揚げ物・ジャンクフード)
フライドポテトや唐揚げ、ラーメン、スナック菓子など、脂質の多い食べ物を頻繁に摂る食生活は、薄毛予防の観点からは最も避けたい習慣の一つです。
脂質を過剰に摂取すると、血液中の中性脂肪やコレステロールが増加し、血液がドロドロになりがちです。これにより、頭皮の毛細血管まで十分な酸素や栄養が届きにくくなります。
さらに、体内で処理しきれなかった脂質は、皮脂として体外に排出されやすくなります。
頭皮の皮脂分泌が過剰になると、毛穴が詰まり、雑菌が繁殖しやすくなるため、脂漏性皮膚炎などの頭皮トラブルを引き起こし、抜け毛の原因となります。
糖分の摂りすぎが招く頭皮トラブル
甘いお菓子やジュース、菓子パンなどの糖分も、摂りすぎには注意が必要です。糖分は体内でエネルギーとして利用されますが、過剰に摂取すると、中性脂肪として蓄積されます。
これは脂質の摂りすぎと同様に、血流の悪化につながります。
また、糖分は皮脂腺を刺激し、皮脂の分泌を促す作用もあります。さらに、糖分が体内のタンパク質と結びつく「糖化」という現象は、体の老化を促進します。
頭皮も皮膚の一部であるため、糖化が進むと頭皮が硬くなり、弾力性が失われ、健康な髪が育ちにくい環境になってしまいます。
塩分の過剰摂取と血流への影響
日本人の食生活は、醤油や味噌、漬物、加工食品などにより、塩分を摂りすぎる傾向にあります。塩分を過剰に摂取すると、体は水分を溜め込みやすくなり、「むくみ」を引き起こします。
それだけでなく、塩分の摂りすぎは高血圧の大きな原因となります。高血圧の状態が続くと、血管に負担がかかり、動脈硬化が進みやすくなります。
特に頭皮のような末端にある毛細血管は影響を受けやすく、血流が悪化して栄養が届きにくくなる可能性があります。ラーメンの汁を全部飲む、味付けの濃いものを好むといった習慣は見直すことが賢明です。
アルコールの飲み過ぎとビタミンの消費
適度なアルコールはリラックス効果や血行促進につながることもありますが、飲み過ぎは禁物です。
アルコールを体内で分解する際には、ビタミンB群や亜鉛といった、髪の毛の生成に必要な栄養素が大量に消費されてしまいます。
せっかく食事で摂取した貴重な栄養素が、アルコールの分解に使われてしまい、髪まで回らなくなってしまうのです。
また、過度な飲酒は睡眠の質を低下させ、髪の成長を妨げることにもつながります。お酒はほどほどにし、休肝日を設けるなどの工夫が必要です。
栄養素を効率よく摂取する食事のコツ
髪に良い食材を知り、NGな食生活を避けることがわかっても、それをどう実践すれば良いか悩むかもしれません。
ここでは、栄養素を効率よく摂取し、薄毛予防につなげるための食事のコツを紹介します。
バランスの良い食事とは(一汁三菜のすすめ)
薄毛予防のために特定の食材だけを食べる「ばっかり食べ」は、かえって栄養バランスを崩す原因となります。大切なのは、様々な食材を組み合わせてバランスよく食べることです。
日本の伝統的な食事スタイルである「一汁三菜」(ご飯+汁物+主菜1品+副菜2品)は、理想的な栄養バランスを実現しやすい形式です。
- 主食(ご飯・パンなど):エネルギー源
- 主菜(肉・魚・卵・大豆製品):タンパク質源
- 副菜(野菜・海藻・きのこ類):ビタミン・ミネラル・食物繊維源
このように、毎回の食事で「主食・主菜・副菜」を揃えることを意識するだけで、自然とタンパク質、ビタミン、ミネラルをバランスよく摂取できます。
食べる順番と血糖値コントロール
同じ内容の食事でも、食べる順番を工夫することで、栄養の吸収や体に与える影響が変わってきます。薄毛予防の観点から意識したいのは「血糖値の急上昇を抑えること」です。
空腹時にいきなりご飯やパンなどの炭水化物(糖質)を食べると、血糖値が急上昇します。
血糖値が急激に上がると、それを下げるためにインスリンというホルモンが大量に分泌されますが、このインスリンは皮脂腺を刺激する作用も持つため、頭皮の皮脂分泌増加につながる可能性があります。
食事の際は、まず「野菜や海藻類(食物繊維)」から食べ始め、次に「肉や魚(タンパク質・脂質)」、最後に「ご飯やパン(炭水化物)」という順番を意識しましょう。
食物繊維が糖の吸収を穏やかにし、血糖値の急上昇を防ぐのに役立ちます。
間食や夜食の賢い選び方
仕事の合間や夜遅くにお腹が空いた時、何を選ぶかも重要です。スナック菓子やカップラーメン、甘いジュースは、脂質や糖分、塩分が過剰であり、薄毛予防にはNGな選択です。
間食や夜食を摂る場合は、髪や体に良いものを選びましょう。
間食におすすめの食べ物
| おすすめの間食 | 主な栄養素 | 選ぶポイント |
|---|---|---|
| 素焼きナッツ類 | ビタミンE、亜鉛、良質な脂質 | 塩や油で味付けされていないものを選ぶ。 |
| ヨーグルト(無糖) | タンパク質、カルシウム | 無糖タイプを選び、甘みは果物で足す。 |
| 小魚(煮干し) | カルシウム、タンパク質、亜鉛 | 塩分が控えめなものを選ぶ。 |
これらの食品は、空腹を満たしつつ、髪に必要な栄養素も補給できます。ただし、いずれも食べ過ぎには注意し、適量を心がけましょう。
食事以外で見直したい薄毛予防の生活習慣
薄毛予防は「食べ物」が非常に重要ですが、それだけで万全というわけではありません。食事改善の効果を最大限に引き出すためにも、その他の生活習慣も見直すことが大切です。
質の高い睡眠と髪の成長
髪の毛は、私たちが寝ている間に成長します。特に、入眠後に訪れる深いノンレム睡眠中に「成長ホルモン」が最も多く分泌されます。
この成長ホルモンが、頭皮の細胞分裂を促し、髪の毛の成長やダメージの修復を行います。
睡眠不足が続いたり、夜更かしをして睡眠のリズムが乱れたりすると、成長ホルモンの分泌が妨げられます。これにより、ヘアサイクルが乱れ、髪が十分に育たないまま抜けやすくなってしまいます。
毎日6〜7時間程度のまとまった睡眠時間を確保し、就寝前のスマートフォン操作を控えるなど、睡眠の「質」を高める工夫をしましょう。
適度な運動による血行促進
デスクワークが中心で体を動かす機会が少ない人は、全身の血流が滞りやすくなっています。特に頭皮は心臓から遠い位置にあるため、血行不良の影響を受けやすい部位です。
ウォーキングやジョギング、ストレッチなどの適度な「有酸素運動」は、全身の血行を促進し、頭皮の毛細血管まで酸素と栄養を届けるのに役立ちます。
運動を習慣にすることで、血流が改善されるだけでなく、ストレス解消にもつながり、一石二鳥の効果が期待できます。無理のない範囲で、日常生活に運動を取り入れましょう。
ストレス管理と頭皮への影響
精神的なストレスも、薄毛の大きな要因となります。強いストレスを感じると、自律神経のバランスが乱れ、交感神経が優位な状態が続きます。交感神経が優位になると、血管が収縮し、血流が悪化します。
その結果、頭皮への栄養供給が滞り、髪の成長が妨げられます。また、ストレスはホルモンバランスの乱れを引き起こしたり、睡眠の質を低下させたりすることもあります。
現代社会でストレスをゼロにすることは難しいですが、自分なりのストレス解消法を見つけることが重要です。
趣味に没頭する時間を作る、ゆっくり入浴する、友人と話すなど、心身をリラックスさせる時間を持つことを意識しましょう。
食事に戻る
よくある質問
- 特定の食べ物だけを食べ続ければ効果はありますか?
-
いいえ、特定の食べ物だけを摂取しても、薄毛予防の効果は限定的です。例えば、髪に良いとされる亜鉛を豊富に含む牡蠣だけを毎日食べても、他の栄養素が不足すれば健康な髪は育ちません。
髪の成長にはタンパク質、ビタミン、ミネラルなど多くの栄養素が複雑に関わり合っています。バランスの取れた食事が何よりも大切です。
- サプリメントで栄養を補うのはどうですか?
-
忙しくてどうしても食事が偏りがちな場合、サプリメントで不足しがちな栄養素(特に亜鉛やビタミンB群など)を補うのは一つの方法です。ただし、サプリメントはあくまで「補助」です。
基本は日々の食事から栄養を摂ることを第一に考え、食事で補いきれない部分をサポートする目的で利用しましょう。過剰摂取はかえって体に負担をかけることもあるため、目安量を守ることも重要です。
- 食生活を改善してからどれくらいで変化を感じますか?
-
食生活の改善による変化は、すぐには現れにくいものです。
なぜなら、現在生えている髪の毛はすでに完成したものであり、食事の影響はこれから新しく生えてくる髪や、頭皮環境に現れるからです。
髪にはヘアサイクルがあり、成長期は数年に及びます。最低でも3ヶ月から半年程度は、根気よくバランスの取れた食事を続けることが大切です。
- 外食が多い場合の注意点は何ですか?
-
外食は、一般的に脂質、糖分、塩分が多くなりがちで、野菜(ビタミン・ミネラル)が不足しやすい傾向があります。
外食が多い場合は、丼ものやラーメンなどの単品メニューを避け、野菜の小鉢やサラダを追加できる定食スタイルのメニューを選びましょう。
また、揚げ物を避け、蒸し料理や焼き魚を選ぶなど、調理法にも気を配ることが大切です。
- 水をたくさん飲むことは薄毛予防になりますか?
-
直接的に髪を生やす効果はありませんが、十分な水分補給は健康維持と血流改善の基本です。水分が不足すると血液が濃くなり、血流が悪化しやすくなります。
頭皮の毛細血管までスムーズに栄養を運ぶためにも、適度な水分補給は重要です。ジュースやお酒ではなく、常温の水や白湯、ノンカフェインのお茶などでこまめに水分を摂ることをおすすめします。
Reference
GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.
RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.
GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.
RAJPUT, Rajendrasingh. A scientific hypothesis on the role of nutritional supplements for effective management of hair loss and promoting hair regrowth. J Nutrition Health Food Sci, 2018, 6.3: 1-11.
RAJENDRASINGH, J. R. Role of non-androgenic factors in hair loss and hair regrowth. J Cosmo Trichol, 2017, 3.2: 118.
TRÜEB, Ralph M. The hair cycle and its relation to nutrition. In: Nutrition for Healthy Hair: Guide to Understanding and Proper Practice. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 37-109.
GOLDBERG, Lynne J.; LENZY, Yolanda. Nutrition and hair. Clinics in dermatology, 2010, 28.4: 412-419.
GOWDA, Dinesh; PREMALATHA, V.; IMTIYAZ, D. B. Prevalence of nutritional deficiencies in hair loss among Indian participants: results of a cross-sectional study. International journal of trichology, 2017, 9.3: 101-104.
OLSEN, Elise A., et al. Evaluation and treatment of male and female pattern hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2005, 52.2: 301-311.
TRÜEB, Ralph M. Nutritional disorders of the hair and their management. In: Nutrition for Healthy Hair: Guide to Understanding and Proper Practice. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 111-223.