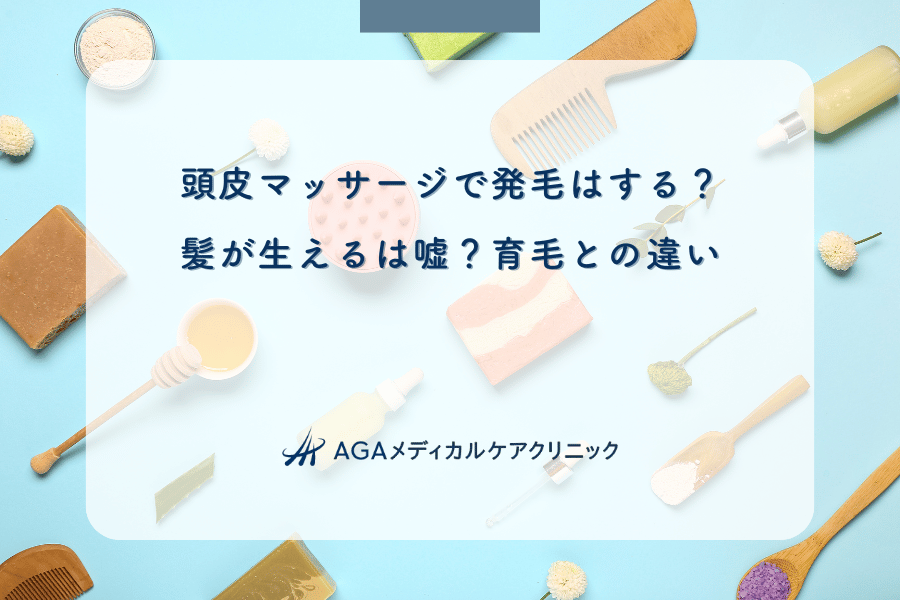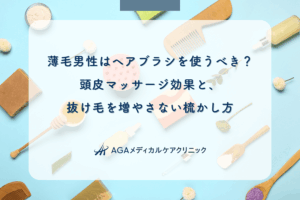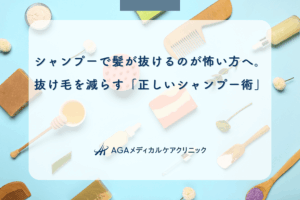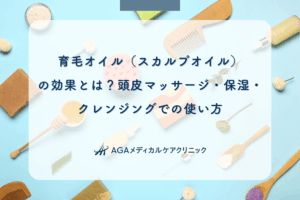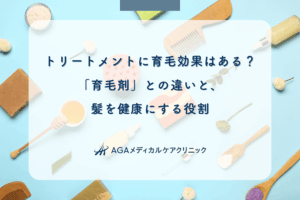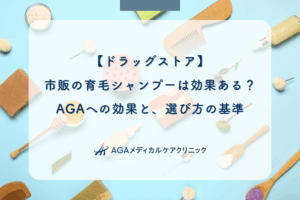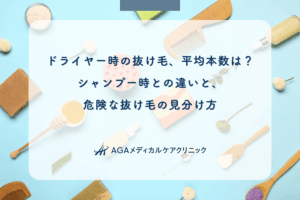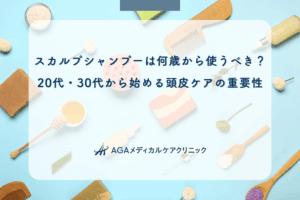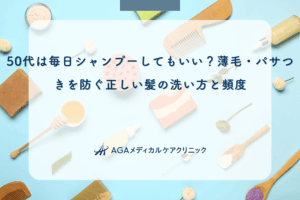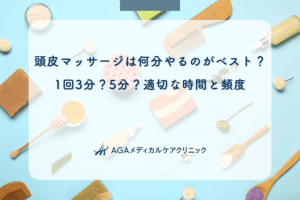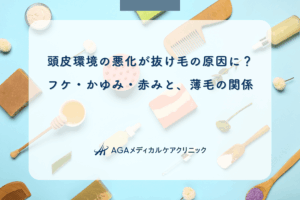鏡を見るたびに気になる頭頂部や生え際。「頭皮マッサージで発毛する」という話を耳にしたけれど、本当に効果があるのか、単なる噂(うわさ)なのか、疑問に感じていませんか。
薄毛や抜け毛の悩みは深刻ですが、誤った情報に振り回されたくないものです。
この記事では、「頭皮マッサージと発毛」の真実について、医学的な観点や「育毛」との違いを交えながら、詳しく解説します。
この記事を読めば、あなたが今抱えている疑問が解消し、自分に合った正しい頭皮ケアを見つけるための第一歩を踏み出せるはずです。
結論から言うと、頭皮マッサージ単体での「発毛」は難しいものの、「育毛」環境を整える上で非常に重要な役割を果たします。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
頭皮マッサージと「発毛」の本当の関係
薄毛対策として広く知られている頭皮マッサージですが、「発毛」という言葉とセットで語られることが多くあります。しかし、この関係性については正確な理解が必要です。
多くの人が期待する「発毛」と、頭皮マッサージがもたらす実際の効果には、少し認識のズレがあるかもしれません。
ここでは、頭皮マッサージがなぜ注目され、頭皮に対してどのような影響を与えるのかを明らかにします。
なぜ頭皮マッサージが注目されるのか
頭皮マッサージが注目を集める背景には、その手軽さと、頭皮環境への良好な影響が期待できる点があります。
特別な器具を必要とせず、自宅でシャンプーのついでやリラックスタイムに行えることが、多くの人にとって魅力的に映ります。
また、現代社会特有のストレスや長時間のデスクワークによる血行不良が、頭皮環境に悪影響を与えていると感じる人が増えていることも、要因の一つでしょう。
頭皮を直接刺激することで、これらの問題を少しでも改善したいというニーズが高まっています。
「発毛」の定義とは
まず、「発毛」という言葉の定義を明確にすることが重要です。一般的に「発毛」とは、毛髪が抜けてしまった毛穴から、再び新しい毛が生えてくること、あるいは毛髪の量を全体的に増やすことを指します。
特に、AGA(男性型脱毛症)などの影響でヘアサイクルが乱れ、産毛(うぶげ)のまま抜けてしまう状態から、太く健康な毛髪が再び生える状態に戻すことを期待する場合に使われます。
この定義は、単に今ある毛が伸びること(育毛)とは区別されます。
頭皮マッサージで期待できる主な効果
頭皮マッサージに期待できる最も大きな効果は、「頭皮環境の改善」です。これには、血行の促進、頭皮の柔軟性の向上、毛穴の汚れの除去サポート、そしてリラクゼーション効果などが含まれます。
これらの効果は、健康な髪が育つための土台作りに役立ちます。
ただし、これらはあくまで「育毛環境」を整えるものであり、マッサージ自体が直接的に新しい毛を生み出す「発毛」作用を持つわけではない点に注意が必要です。
頭皮マッサージによる主な期待効果
| 期待効果 | 概要 | 毛髪への影響 |
|---|---|---|
| 血行促進 | 頭皮の毛細血管の血流を促す | 毛母細胞への栄養供給サポート |
| 頭皮の柔軟化 | 硬くなった頭皮をほぐす | 健康な毛髪が育つ土壌作り |
| リラクゼーション | 緊張を緩和し、ストレスを軽減 | ストレスによる血行不良の緩和 |
血行促進が頭皮に与える影響
毛髪は、毛根の最深部にある毛乳頭(もうにゅうとう)細胞が、毛細血管から栄養素や酸素を受け取ることで成長します。
頭皮マッサージによって血行が促進されると、この毛乳頭細胞へ送られる栄養素の量が増加することが期待できます。
頭皮が硬くなっていたり、血行が悪かったりすると、必要な栄養が十分に行き渡らず、毛髪の成長が妨げられる可能性があります。
マッサージは、この「栄養輸送ルート」を整える手助けをすると考えられます。
「頭皮マッサージで髪が生える」は嘘?真実?
「頭皮マッサージだけで発毛する」という表現は、多くの人の期待をあおる一方で、誤解も生んでいます。
この疑問に答えるためには、現在の医学的な知見と、「発毛」という言葉の使われ方を整理する必要があります。果たして、頭皮マッサージは薄毛に悩む人々の救世主となるのでしょうか。
それとも、単なる気休めに過ぎないのでしょうか。
医学的根拠の現状
現状、「頭皮マッサージ自体が発毛効果を持つ」と断言できる、強固な医学的根拠(エビデンス)は限定的です。
いくつかの研究で、マッサージによる血流増加や、毛髪の太さへの影響が示唆されていますが、それがAGAなどの脱毛症に対して、医薬品(ミノキシジルやフィナステリドなど)と同等の「発毛」効果を持つとまでは証明されていません。
多くの専門家は、マッサージを「発毛」の主軸としてではなく、あくまで頭皮環境を整える「補助的なケア」として位置づけています。
誤解を生む「発毛」という言葉
問題は、「発毛」という言葉が非常に広範な意味で使われる点にあります。
前述の通り、医学的には「新たに毛を生やすこと」を指しますが、一般的には「抜け毛が減った」「髪にハリが出た」といった状態の変化も「発毛した」と捉えられがちです。
頭皮マッサージによって頭皮環境が改善し、既存の毛髪が健康に育つ(=育毛)ことで、全体的なボリューム感がアップし、それがあたかも「発毛した」かのように感じられるケースは十分に考えられます。
この認識の差が、「嘘か真実か」という議論を生む一因となっています。
育毛剤との併用で変わる期待値
頭皮マッサージの価値は、育毛剤と併用することで高まります。育毛剤の多くは、頭皮の血行を促進したり、毛母細胞に栄養を与えたりする成分を含んでいます。
マッサージによって頭皮の血流が良くなっている状態で育毛剤を使用することで、有効成分がより効率的に角質層まで浸透し、その効果を発揮しやすくなる可能性があります。
また、マッサージで頭皮を柔らかく保つことも、育毛剤の浸透を助けると考えられます。単体での「発毛」は難しくても、育毛ケアの一環としては大きな意味を持ちます。
マッサージによる頭皮環境の改善とは
頭皮環境の改善とは、具体的にはどのような状態を指すのでしょうか。主に「血行が良いこと」「頭皮が柔らかいこと」「毛穴が清潔であること」「適度な潤いがあること」などが挙げられます。
頭皮マッサージは、特に血行促進と柔軟性の向上に寄与します。頭皮が硬い状態は、血流が滞っているサインでもあります。
マッサージで物理的にほぐすことで、緊張が解け、血流が回復し、結果として毛髪が育ちやすい環境(土壌)が整うのです。
「発毛」と「育毛」の決定的な違い
薄毛対策を考える上で、「発毛」と「育毛」の違いを理解しておくことは非常に重要です。この二つは似ているようで、その目的とアプローチが根本的に異なります。
頭皮マッサージがどちらに分類されるのかを知ることで、自分の目的に合った正しいケアを選択できるようになります。
発毛とは(新しい毛を生やす)
「発毛」は、文字通り「毛を発する」、つまり新しい毛髪を生み出すことを目的とします。
これは、何らかの理由(主にAGAなど)でヘアサイクルが停止したり、極端に短くなったりして、毛髪が失われた毛穴から、再び毛髪を再生させることを目指すアプローチです。
日本皮膚科学会のガイドラインでも推奨されているミノキシジルの外用や、フィナステリド・デュタステリドの内服(これらは医師の処方が必要)などが、この「発毛」を目的とした治療に分類されます。
「攻めのケア」とも言えるでしょう。
育毛とは(今ある毛を育てる)
一方、「育毛」は「毛を育てる」ことを目的とします。現在生えている毛髪を、太く、長く、健康に育てること、そして、抜け毛を予防し、頭皮環境を健やかに保つことを目指します。
ヘアサイクルが正常に機能するように、頭皮の血行を促進したり、毛髪に必要な栄養を補給したり、頭皮の炎症を抑えたりするケアがこれにあたります。
多くの市販の育毛剤(医薬部外品)や、頭皮マッサージ、生活習慣の改善は、この「育毛」の範疇(はんちゅう)に含まれます。「守りと育てのケア」と言えます。
「発毛」と「育毛」の比較
| 項目 | 発毛 | 育毛 |
|---|---|---|
| 目的 | 新しい毛髪を生やす・増やす | 今ある毛髪を健康に育てる・抜け毛を防ぐ |
| 主なアプローチ | 医薬品(ミノキシジル、フィナステリド等) | 医薬部外品(育毛剤)、頭皮マッサージ、生活改善 |
| 分類 | 主に「治療」の領域 | 主に「予防・ケア」の領域 |
頭皮マッサージが分類されるのはどちらか
ここまでの説明でお分かりの通り、頭皮マッサージは、その主な効果(血行促進、頭皮環境の改善)から考えて、明確に「育毛」のカテゴリーに分類されます。
マッサージ自体が毛母細胞に直接働きかけて新たな毛髪を生み出す「発毛」作用を持つわけではなく、あくまで毛髪が育ちやすい良好な「土壌(頭皮環境)」を作るためのサポート役です。
この点を誤解していると、マッサージだけで髪が生えると過度な期待を抱き、結果的に失望することになりかねません。
自身の目的に合ったケアの選び方
もしあなたが「明らかに薄毛が進行している」「抜け毛の量が異常に多い」と感じており、「失われた毛髪を取り戻したい(=発毛)」と強く願うのであれば、頭皮マッサージや市販の育毛剤だけに頼るのではなく、まずは皮膚科やAGA専門クリニックの医師に相談することを推奨します。
一方で、「最近髪にハリがなくなってきた」「抜け毛を予防したい」「頭皮環境を良くしたい(=育毛)」という段階であれば、セルフケアとして頭皮マッサージや育毛剤の導入は非常に有効な手段となります。
自分の現状と目的を正しく見極めることが大切です。
効果を高める頭皮マッサージの正しいやり方
頭皮マッサージは「育毛」環境を整える上で有効ですが、その効果は「やり方」によって大きく左右されます。間違った方法では、効果がないばかりか、かえって頭皮を傷つけてしまう可能性もあります。
ここでは、頭皮環境を健やかに保つための、正しいマッサージの基本を紹介します。
マッサージを行う前の準備
マッサージを始める前に、まずは手を清潔に洗いましょう。爪が伸びていると頭皮を傷つける原因になるため、短く切っておくことが重要です。
リラックスした状態で行うことが望ましいため、深呼吸をして体の力を抜きましょう。
また、乾いた頭皮に強い摩擦を加えるとダメージになることがあるため、入浴中や、育毛剤・頭皮用ローションを塗布した後など、頭皮が湿っているか、滑りが良い状態で行うのが理想的です。
基本の指の動かし方と圧の強さ
マッサージには、指の腹(指紋がある部分)を使います。爪を立てないように注意してください。基本的な動作は、「頭皮を動かす」ことです。
指の腹を頭皮にしっかりと密着させたら、頭蓋骨(ずがいこつ)から頭皮を擦り剥がすようなイメージで、小さく円を描くように動かします。
この時、指が頭皮の表面を滑る(擦る)のではなく、頭皮そのものを動かす意識が大切です。
圧の強さは、「痛気持ちいい」と感じる程度が目安です。強すぎると頭皮や毛細血管にダメージを与える可能性があるため、力任せに行うのは避けましょう。
マッサージの部位と順番の例
| 順番 | 部位 | 主な動かし方 |
|---|---|---|
| 1 | 生え際(額〜こめかみ) | 指の腹で円を描くようにほぐす |
| 2 | 側頭部(耳の上) | 両手で頭を包むように圧をかけながら引き上げる |
| 3 | 頭頂部 | 指を組み、手のひらの付け根で左右から圧をかける |
| 4 | 後頭部(襟足) | 指の腹で下から上に向かって揉みほぐす |
マッサージに適したタイミング(入浴中・入浴後)
マッサージを行うタイミングとして最も推奨されるのは、入浴中です。体が温まることで全身の血行が良くなっており、頭皮も柔らかくほぐれやすい状態です。
シャンプーの泡をクッションにして行うと、摩擦によるダメージを最小限に抑えられます。ただし、すすぎ残しがないよう、マッサージ後はしっかり洗い流してください。
また、入浴後、タオルドライをして頭皮が清潔になった状態で行うのも良いタイミングです。この場合は、育M剤や頭皮用ローションを塗布してから行うと、成分の浸透を助け、指の滑りも良くなります。
1回あたりの時間と頻度の目安
何事も「やりすぎ」は禁物です。頭皮マッサージも同様で、長時間行うほど効果が出るわけではありません。1回あたりの時間は、全体で3分から5分程度を目安にしましょう。
それ以上長く行うと、かえって頭皮に負担がかかり、炎症や皮脂の過剰分泌を引き起こす可能性があります。頻度については、毎日行うのが理想的ですが、難しければ2〜3日に1回でも構いません。
大切なのは、短時間でも継続することです。毎日の習慣として、無理なく取り入れられる範囲で行いましょう。
頭皮マッサージを行う際の注意点
頭皮環境を整えるために始めたマッサージが、逆効果になってしまっては元も子もありません。良かれと思ってやっていることが、実は頭皮や毛髪にダメージを与えているケースも少なくないのです。
ここでは、頭皮マッサージを行う上で、特に注意すべき点を解説します。
やりすぎが逆効果になる理由
前述の通り、マッサージのやりすぎは禁物です。適度な刺激は血行を促進しますが、過度な刺激は頭皮にとって「攻撃」と認識されます。
強すぎる圧や長時間の摩擦は、頭皮の防御反応を引き起こし、角質を厚くしたり、皮脂を過剰に分泌させたりする原因となります。
また、毛細血管を傷つけたり、炎症を引き起こしたりするリスクもあります。皮脂が過剰になると毛穴が詰まりやすくなり、炎症が起これば、それは抜け毛の直接的な原因にもなり得ます。
あくまで「優しく」「適度な時間」を守ることが重要です。やりすぎは厳禁です。
爪を立ててはいけない(頭皮を傷つけるリスク)
これは基本中の基本ですが、非常に重要な注意点です。マッサージは必ず「指の腹」で行い、絶対に爪を立ててはいけません。
頭皮は顔の皮膚よりもデリケートな部分があり、爪で引っかくと、目に見えない無数の小さな傷がつきます。
その傷から雑菌が侵入すると、毛嚢炎(もうのうえん)などの頭皮トラブルを引き起こし、抜け毛の原因となります。
かゆいからといって爪で掻きながらマッサージするなどは、もってのほかです。常に清潔な手で、指の腹を使うことを徹底してください。
頭皮に異常がある場合は避ける
頭皮に湿疹、かゆみ、赤み、フケ、炎症、傷など、何らかの異常が見られる場合は、頭皮マッサージを一旦中止してください。
マッサージによる刺激が、これらの症状をさらに悪化させる可能性が高いからです。
例えば、脂漏性皮膚炎(しろうせいひふえん)や乾燥による炎症が起きている場合、マッサージの物理的な刺激が炎症を広げてしまうことがあります。
まずは皮膚科を受診し、頭皮の状態を正常に戻すことを最優先にしてください。自己判断でマッサージを続けるのは危険です。
頭皮の異常と対処法
| 異常のサイン | 考えられる状態 | 対処法 |
|---|---|---|
| 赤み、強いかゆみ | 炎症、皮膚炎 | マッサージを中止し、皮膚科を受診 |
| カサブタ、傷 | 物理的な損傷 | 治癒するまでマッサージを避ける |
| 大量のフケ(乾燥・脂性) | ターンオーバーの乱れ | シャンプーの見直し、場合により受診 |
マッサージだけではAGAは改善しない
これは非常に重要な点です。もしあなたの薄毛の原因がAGA(男性型脱毛症)である場合、頭皮マッサージ「だけ」で症状が改善することはありません。
AGAは、男性ホルモン(DHT:ジヒドロテストステロン)が毛乳頭細胞の受容体と結合し、毛髪の成長期を極端に短くしてしまう疾患です。
頭皮マッサージで血行を良くしても、このAGAの根本的な進行を止めることはできません。
AGAの治療には、前述したフィナステリドやデュタステリドの内服(DHTの生成を抑制する)や、ミノキシジルの外用(毛母細胞に働きかける)といった、医学的根拠のある治療が必要です。
マッサージは、あくまでこれらの治療の「補助」として、育毛環境を整える役割と割り切る必要があります。
頭皮マッサージ以外の育毛アプローチ
頭皮マッサージは、健康な髪を育てるための土壌作りに役立ちますが、育毛は「総合戦」です。
マッサージだけに頼るのではなく、多角的なアプローチを取り入れることで、より効果的なケアが可能になります。頭皮の外側からのケアだけでなく、体の内側からのケアも同様に重要です。
育毛剤の役割と選び方
育毛剤(医薬部外品)は、頭皮マッサージと並ぶ育毛ケアの柱です。その主な役割は、頭皮の血行を促進し、毛母細胞に栄養を与え、頭皮環境を清潔に保ち、炎症を抑えることにあります。
自分の頭皮の状態に合わせて選ぶことが大切です。
例えば、乾燥が気になる人は保湿成分(セラミド、ヒアルロン酸など)が配合されたもの、皮脂が多い人は皮脂抑制や抗炎症成分(グリチルリチン酸ジカリウムなど)が含まれたものを選ぶと良いでしょう。
頭皮マッサージと併用することで、成分の浸透を助け、相乗効果が期待できます。
生活習慣の見直し(食事・睡眠)
毛髪は、私たちが摂取した栄養素から作られています。外側からどれだけケアしても、内側からの栄養が不足していれば、健康な髪は育ちません。
特に、毛髪の主成分であるタンパク質(ケラチン)や、その合成を助ける亜鉛、ビタミンB群などを意識的に摂取することが重要です。
また、睡眠中に分泌される成長ホルモンは、毛母細胞の分裂を促進し、毛髪の成長に深く関わっています。質の良い睡眠を十分にとることは、何よりの育毛ケアと言えます。
偏った食事や睡眠不足は、頭皮環境を確実に悪化させます。
毛髪の成長に必要な主な栄養素
| 栄養素 | 主な役割 | 多く含む食品例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 毛髪の主成分(ケラチン)の材料 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成(ケラチン)を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉(赤身) |
| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝、皮脂分泌の調整 | 豚肉、マグロ、レバー、納豆 |
ストレス管理の重要性
過度なストレスは、自律神経のバランスを崩し、血管を収縮させて血行不良を引き起こします。頭皮の血行が悪くなれば、毛根に十分な栄養が届かなくなり、抜け毛や薄毛の原因となります。
また、ストレスはホルモンバランスの乱れにもつながり、皮脂の過剰分泌などを引き起こすこともあります。
現代社会でストレスをゼロにすることは難しいですが、自分なりのリラックス方法を見つけ、溜め込まないようにすることが大切です。
適度な運動、趣味の時間、ゆっくりと入浴することなども、有効なストレス管理法です。頭皮マッサージ自体にも、高いリラクゼーション効果があります。
専門クリニックでの相談
セルフケアを続けていても抜け毛が減らない、あるいは薄毛が明らかに進行していると感じる場合は、早めに専門家(皮膚科やAGA専門クリニック)に相談することを強く推奨します。
前述の通り、特にAGAは進行性の脱毛症であり、自己流のケアでは進行を止めることができません。
専門医の診断を受けることで、自分の薄毛の本当の原因が分かり、医学的根拠に基づいた適切な治療(内服薬、外用薬など)を受けることができます。
早期の対処が、将来の毛髪を守る上で最も重要です。
頭皮マッサージと併用したい頭皮ケア
頭皮マッサージの効果を最大限に引き出し、健康な育毛環境を維持するためには、日々の基本的な頭皮ケアが欠かせません。
特にシャンプーや保湿、紫外線対策は、マッサージと密接に関連する重要な要素です。これらのケアを適切に行うことで、マッサージの土台となる頭皮を常に良い状態に保ちます。
正しいシャンプーの方法
シャンプーの最大の目的は、頭皮の余分な皮脂や汚れを落とし、清潔に保つことです。しかし、洗いすぎや間違った洗い方は、必要な皮脂まで奪い、頭皮の乾燥やバリア機能の低下を招きます。
- シャンプー前には、ぬるま湯で髪と頭皮を十分に予洗いし、汚れの大半を落とします。
- シャンプーは手のひらでよく泡立ててから、髪ではなく頭皮につけ、指の腹で優しくマッサージするように洗います。
- すすぎは、洗い以上に時間をかけ、シャンプー剤が頭皮に残らないよう、徹底的に行います。
この「優しく洗う」「しっかりすすぐ」が、頭皮マッサージの効果を活かすための基本です。
頭皮の保湿ケアの必要性
頭皮も顔の皮膚とつながっており、乾燥します。頭皮が乾燥すると、バリア機能が低下して外部からの刺激に弱くなり、かゆみやフケの原因となります。
また、乾燥を防ごうと皮脂が過剰に分泌されることもあります。洗髪後や、空気が乾燥する季節には、頭皮用のローションや保湿美容液を使用して、潤いを補給することが大切です。
頭皮マッサージの後に保湿ケアを行うと、血行が良くなった状態で水分と栄養を補給できるため、より効果的です。特に、育毛剤に保湿成分が含まれているものを選ぶのも良い方法です。
紫外線対策(帽子や日傘)
頭皮は、体の中で最も太陽に近く、紫外線の影響を直接受けやすい場所です。紫外線は、頭皮に炎症を引き起こす(日焼け)だけでなく、毛母細胞にダメージを与え、毛髪の成長を妨げる可能性があります。
また、頭皮の乾燥や老化を促進し、健康な髪が育つ環境を損ないます。
外出時には、帽子をかぶる、日傘をさす、または頭皮用の日焼け止めスプレーを使用するなどして、頭皮を紫外線から守る意識を持つことが、育毛ケアの一環として非常に重要です。
頭皮マッサージに戻る
よくある質問
頭皮マッサージに関して、多くの方が抱く疑問についてお答えします。正しい知識を持って、日々のケアに取り組みましょう。
- 頭皮マッサージはいつから効果が出始めますか?
-
頭皮マッサージは、医薬品のように即効性があるものではありません。その目的は、髪が育つ土壌である頭皮環境を、時間をかけてゆっくりと改善していくことにあります。
血行促進やリラクゼーション効果は、マッサージ直後から感じることもありますが、それが抜け毛の減少や髪質の変化として表れるには、最低でも3ヶ月から6ヶ月程度は継続することが必要です。
ヘアサイクル(毛髪が生え変わる周期)を考慮し、焦らず気長に続けることが大切です。
- マッサージ器具(ブラシなど)は使った方が良いですか?
-
マッサージ器具(スカルプブラシやマッサージャーなど)は、正しく使えば、手で行うよりも効率的に頭皮を刺激し、毛穴の汚れを落とす手助けになります。
しかし、素材が硬すぎたり、力を入れすぎたりすると、かえって頭皮を傷つける原因にもなります。
使用する場合は、シリコン製などの柔らかい素材のものを選び、肌あたりを確かめながら優しく使用してください。
最終的には、自分の手で行う感覚が一番分かりやすく安全であるとも言えます。器具を使う場合も、基本は「優しく」です。
- 頭皮が硬いと薄毛になりやすいというのは本当ですか?
-
頭皮が硬い状態は、多くの場合、頭皮の血行不良や、筋肉(帽状腱膜:ぼうじょうけんまく)の緊張、または頭皮の乾燥やむくみを示しています。
血行不良は、毛根へ栄養を運ぶ上で妨げとなるため、「頭皮が硬い=薄毛になりやすい」という関連性は高いと考えられます。
頭皮マッサージは、この硬くなった頭皮を物理的にほぐし、血流を改善させるのに役立ちます。
自分の頭皮を触ってみて、以前より硬い、または動かないと感じる場合は、血行不良のサインかもしれません。
- 育毛剤はマッサージの前後どちらで使うのが良いですか?
-
一般的には、頭皮マッサージの「後」に育毛剤を使用することを推奨します。
マッサージによって頭皮の血行が促進され、毛穴の汚れも浮きやすい状態になっているため、その後に育毛剤を塗布することで、有効成分が角質層まで浸透しやすくなると考えられます。
ただし、製品によっては(例えば、マッサージ用のオイルやローションなど)、マッサージ「中」や「前」に使用するものもあります。
基本的には、使用する育毛剤やローションのメーカーが推奨する方法に従うのが一番です。
- マッサージをやめたらどうなりますか?
-
頭皮マッサージによって維持されていた良好な血行や頭皮の柔軟性は、マッサージをやめれば、徐々に元の状態に戻っていくと考えられます。
特に、日々の生活習慣(ストレス、長時間のデスクワークなど)が血行不良を招きやすいものである場合、何もしなければ再び頭皮は硬くなり、血流も滞りがちになるでしょう。
マッサージは「治療」ではなく「継続的なケア」です。育毛環境を良好に保つためには、運動や食生活の改善と同様に、習慣として生活に取り入れることが望ましいです。
Reference
ENGLISH, Robert S.; BARAZESH, James M. Self-assessments of standardized scalp massages for androgenic alopecia: Survey results. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 167-178.
BOWERS, R. E. Partial alopecia due to scalp massage. British Journal of Dermatology, 1950, 62.6: 262-264.
KOYAMA, Taro, et al. Standardized scalp massage results in increased hair thickness by inducing stretching forces to dermal papilla cells in the subcutaneous tissue. Eplasty, 2016, 16: e8.
TKACHENKO, Elizabeth, et al. Complementary and alternative medicine for alopecia areata: A systematic review. Journal of the American Academy of Dermatology, 2023, 88.1: 131-143.
CHO, Young Hye, et al. Effect of pumpkin seed oil on hair growth in men with androgenetic alopecia: a randomized, double‐blind, placebo‐controlled trial. Evidence‐Based Complementary and Alternative Medicine, 2014, 2014.1: 549721.
CRANWELL, William; SINCLAIR, Rodney. Male androgenetic alopecia. 2015.
KWAK, In-Sil; PARK, Sang-Hee. The effects of combined exercise and scalp care on the scalp and hair condition of male with alopecia. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 2021, 25.1: 993-998.
SINCLAIR, Rodney. Male pattern androgenetic alopecia. Bmj, 1998, 317.7162: 865-869.
MARTÍN, Ángel García, et al. Topically applied magnetized saline water activates autophagy in the scalp and increases hair count and hair mass index in men with mild-to-moderate androgenetic alopecia. Cureus, 2023, 15.11.
NESTOR, Mark S., et al. Treatment options for androgenetic alopecia: Efficacy, side effects, compliance, financial considerations, and ethics. Journal of cosmetic dermatology, 2021, 20.12: 3759-3781.