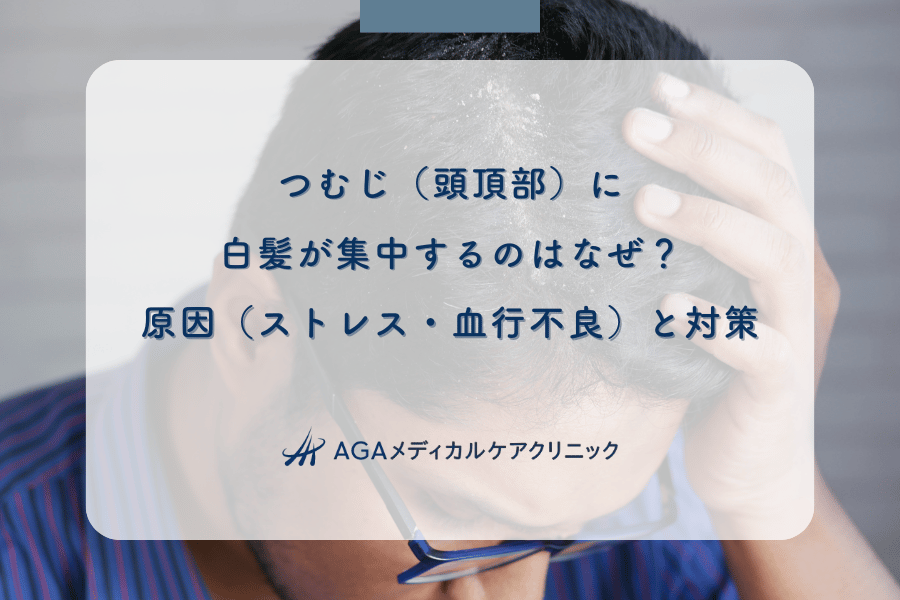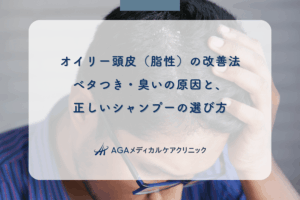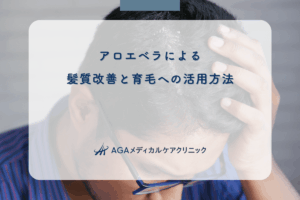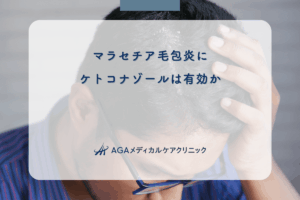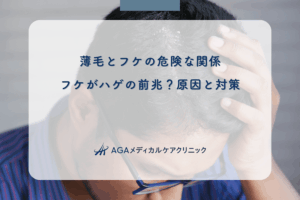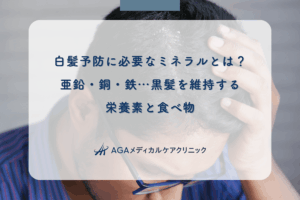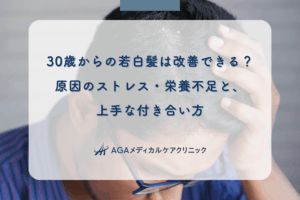ふと鏡を見たとき、あるいは家族から指摘されたとき、つむじ(頭頂部)に集まる白髪にドキッとした経験はありませんか。
他の場所より目立つ気がして、「自分だけなぜ?」「何か悪いサインだろうか」と不安になるかもしれません。そのお悩み、多くの方が感じています。
この記事では、つむじ(頭頂部)に白髪が目立ちやすい理由から、その背景にあるストレスや血行不良といった主な原因、そして今日から始められる具体的な対策まで、あなたの疑問に丁寧にお答えします。
この記事を読めば、白髪の不安が和らぎ、前向きな頭皮ケアを始めるきっかけが見つかるはずです。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
つむじ(頭頂部)に白髪が目立つと感じる理由
「最近、特につむじの白髪が増えた気がする」と感じる方は少なくありません。しかし、本当に頭頂部だけに白髪が「集中」しているのでしょうか。
まずは、なぜつむじ(頭頂部)の白髪が目立ちやすいのか、その理由を探ります。
鏡で見やすい場所だから
つむじや頭頂部は、洗面台の鏡など、日常生活で自分自身をチェックする際に比較的目に入りやすい場所です。
特に合わせ鏡を使ったり、スマートフォンのカメラで頭頂部を撮影したりすると、その状態が鮮明にわかります。
一方で、後頭部や側頭部の内側などは、自分では確認しにくいため、白髪が増えていても気づきにくい傾向があります。
つまり、他の場所にも同様に白髪は生えているものの、確認しやすい頭頂部が「特に目立つ」と感じる可能性があります。
髪の分け目で目立ちやすい
つむじは髪の毛が渦を巻くように生えているため、地肌が見えやすい部分です。また、多くの場合、つむじを起点にして髪の分け目ができます。
白髪は根元から白くなるため、髪が密集している部分では黒髪に隠れていても、分け目やつむじ周辺では根元の白さが際立ちやすく、数本あるだけでも目立ってしまうのです。
髪全体の白髪の割合は低くても、たまたま分け目周辺に生えていると、実際の数以上に多く見えてしまいます。
他人の視線が集まりやすい
頭頂部は、他人の視線が集まりやすい場所でもあります。
立っているとき、自分より背の高い人からはもちろん、座っているときやエスカレーターなどで後ろに人が立った場合など、頭頂部は無意識のうちに人目に触れています。
自分では見えなくても、他人からの視線を感じることで、「頭頂部を見られているのではないか」という意識が働き、白髪への不安が増すことも考えられます。
白髪が集中しているわけではない可能性
前述の理由から、実際には頭部全体に均等に白髪が発生し始めていても、つむじ(頭頂部)が最も「目立つ」場所であるため、そこに「集中している」と認識しやすいのです。
もちろん、後述する血行不良や紫外線の影響などで、頭頂部の頭皮環境が他の部位より悪化し、結果的に白髪がやや多く発生する可能性も否定できません。
しかし、多くの場合、目立ちやすさが「集中している」という感覚を生み出している主要な理由と考えられます。まずは冷静に、ご自身の頭皮全体の状態を把握することが大切です。
そもそも白髪ができる仕組みとは
つむじの白髪について考える前に、なぜ髪の毛は白くなるのか、その基本的な仕組みを理解しておくことが重要です。白髪は、髪の色素が失われた状態を指します。
髪の色を決めるメラニン色素
私たちの髪の毛は、もともと生まれる時点では色を持っていません。
毛球と呼ばれる髪の毛の根元の部分で髪が作られる際、「メラノサイト」という色素細胞が作り出す「メラニン色素」が取り込まれることで、黒や褐色などの髪色がつきます。
このメラニン色素には、主に以下の二種類があります。
- ユーメラニン(黒〜褐色系)
- フェオメラニン(赤〜黄色系)
これらのメラニンの量やバランスによって、人それぞれの生まれ持った髪の色が決まります。
メラノサイトの働きと色素の生成
メラノサイトは、毛根の奥深く、毛母細胞(髪の毛を作り出す細胞)の間に存在しています。
髪の毛が成長するサイクル(ヘアサイクル)に合わせて活動し、チロシンというアミノ酸を原料に、チロシナーゼという酵素の働きを借りてメラニン色素を生成します。
そして、新しく作られる髪の毛の細胞に、生成したメラニン色素を受け渡していきます。この一連の流れがスムーズに行われることで、健康な黒髪が育ちます。
メラノサイトの機能低下や減少が白髪の原因
白髪が発生する直接的な原因は、このメラノサイトの働きが何らかの理由で低下したり、メラノサイトの数自体が減少したりすることにあります。
メラノサイトが活動を停止すると、メラニン色素の生成が行われなくなります。また、メラノサイトが枯渇してしまうと、色素を作り出す細胞そのものが存在しなくなります。
その結果、新しく生えてくる髪の毛は色素を受け取ることができず、色のない状態、つまり白髪として生えてくるのです。
髪の毛1本1本の色素事情
白髪は、ある日突然すべての髪が白くなるわけではなく、毛根ごと、1本1本単位で発生します。
メラノサイトの活動が低下した毛根からは白髪が生え、まだ元気なメラノサイトが残っている毛根からは黒髪が生えます。これが、黒髪と白髪が混在する状態です。
加齢やその他の要因によって、活動を停止するメラノサイトが増えていくと、徐々に白髪の割合が増加していきます。
つむじ(頭頂部)の白髪につながる主な原因
では、なぜメラノサイトの働きが低下し、白髪が発生するのでしょうか。特につむじ(頭頂部)の状態にも影響を与えると考えられる、主な原因について解説します。
原因①ストレスの影響
精神的なプレッシャーや過度な緊張状態が続くと、白髪の原因になるといわれます。ストレスは、私たちの体にさまざまな影響を及ぼし、頭皮環境にも決して良くありません。
自律神経の乱れと血行不良
強いストレスを感じると、体は緊張状態に対応するために交感神経が優位になります。交感神経が活発になると、血管が収縮し、血流が悪化しやすくなります。
頭皮、特に頭頂部は毛細血管が多く集まる場所でありながら血流が滞りやすい特徴があるため、ストレスによる血管収縮の影響を強く受ける可能性があります。
血行不良については、次の項目で詳しく解説します。
ストレスによる活性酸素の増加
ストレスは体内で「活性酸素」を過剰に発生させる原因にもなります。活性酸素は、本来、体内に侵入したウイルスなどを攻撃する役割を持ちますが、増えすぎると正常な細胞まで攻撃してしまいます。
毛根にあるメラノサイトも例外ではなく、活性酸素によってダメージを受けると、色素を正常に作り出す機能が低下したり、細胞自体が老化したりする可能性があります。
これが白髪の引き金の一つになると考えられています。
原因②頭皮の血行不良
頭皮の血行不良は、白髪や薄毛など、多くの髪の悩みに共通する重要な原因です。特に頭頂部への影響は大きいと考えられます。
栄養素や酸素が毛根に届きにくい
髪の毛の成長や、メラニン色素の生成に必要な栄養素(タンパク質、ビタミン、ミネラルなど)や酸素は、すべて血液によって毛根の毛母細胞やメラノサイトに運ばれます。
しかし、頭皮の血行が悪くなると、これらの重要な成分が毛根まで十分に行き渡らなくなります。
栄養不足に陥ったメラノサイトは、メラニン色素を活発に作り出すことができず、結果として白髪の発生につながります。
頭頂部の血流の特徴
頭頂部は、心臓から最も遠い位置にあることに加え、重力の影響を受けやすく、もともと血流が滞りやすい部位です。
さらに、頭頂部には「帽状腱膜(ぼうじょうけんまく)」という硬い膜が広がっており、その下には筋肉がほとんど存在しません。
そのため、他の部位のように筋肉のポンプ作用による血流促進が期待できず、一度血行不良になると改善しにくい傾向があります。
原因③加齢による自然な変化
白髪の最大の原因は、多くの場合「加齢」です。年齢を重ねるとともに、体のさまざまな機能が自然と低下していきます。メラノサイトも同様で、加齢によって色素を作り出す能力が徐々に低下していきます。
また、メラノサイト自体を生み出す「色素幹細胞」も、加齢とともに枯渇していくことが研究でわかっています。これにより、新しいメラノサイトが補充されなくなり、白髪が増加していきます。
これは自然な生理現象であり、個人差はありますが誰にでも起こり得ます。
原因④遺伝的な要因
白髪の発生時期や進行の早さには、遺伝的な要因も強く関わっていると考えられています。ご両親や祖父母など、近親者に白髪が多い、あるいは若白髪があった場合、ご自身も同様の傾向を持つ可能性があります。
これは、メラノサイトの活動性や寿命、またはストレスへの感受性など、白髪に関連する体質が遺伝するためと推測されています。
ただし、遺伝がすべてではなく、後天的な生活習慣や環境要因も大きく影響します。
ストレスと白髪の関係を深掘り
前述の通り、ストレスは白髪の大きな原因の一つです。ここでは、ストレスがどのようにしてメラノサイトに影響を与えるのか、もう少し詳しく見ていきましょう。
交感神経と副交感神経のバランス
私たちの体は、活動時に優位になる「交感神経」と、リラックス時に優位になる「副交感神経」という二つの自律神経によってバランスが保たれています。
しかし、慢性的なストレスにさらされると、交感神経が常に優位な状態(緊張状態)が続いてしまいます。このバランスの乱れが、体のさまざまな不調を引き起こします。
ストレスが引き起こす血管収縮
交感神経が優位になると、体は「闘争か逃走か」のモードに入り、筋肉への血流を優先させるため、末梢の血管、特に皮膚や頭皮の毛細血管を収縮させます。
この状態が長く続くと、頭皮は慢性的な血行不良に陥ります。毛根にあるメラノサイトは、栄養不足と酸素不足の状態にさらされ、色素を生成する力を失っていきます。
特につむじ(頭頂部)は血流が滞りやすいため、この影響が顕著に現れる可能性があります。
精神的ストレスと身体的ストレス
ストレスには、仕事のプレッシャーや人間関係の悩みといった「精神的ストレス」だけでなく、過労、睡眠不足、不規則な生活、喫煙、過度な飲酒といった「身体的ストレス」も含まれます。
どちらのストレスも自律神経のバランスを乱し、血行不良や活性酸素の増加を引き起こす原因となります。
ストレス要因の例
現代社会では、さまざまなストレス要因が存在します。自分では気づかないうちに蓄積していることもあるため、注意が必要です。
| ストレスの種類 | 主な要因 | 体への影響(白髪関連) |
|---|---|---|
| 精神的ストレス | 仕事の責任、人間関係、将来への不安、家庭問題 | 交感神経の緊張、血管収縮、睡眠の質の低下 |
| 身体的ストレス | 長時間労働、睡眠不足、不規則な食生活、喫煙 | 血行不良、活性酸素の増加、栄養バランスの乱れ |
| 環境的ストレス | 騒音、気温の変化、紫外線、大気汚染 | 自律神経の乱れ、頭皮への直接的ダメージ(紫外線) |
血行不良が頭頂部に与える影響
つむじ(頭頂部)の白髪を語る上で、「血行不良」はストレスと並んで最も重要なキーワードです。なぜ頭頂部は血行不良に陥りやすいのか、その影響を詳しく解説します。
頭頂部が血行不良になりやすい理由
頭頂部の頭皮は、他の部位と比較していくつかの不利な条件を持っています。
心臓から遠い位置
頭頂部は、文字通り体の最も高い位置にあります。心臓から送り出された血液が、重力に逆らって到達する必要があるため、血流の勢いが弱まりやすい場所です。
血圧が低い人や、心臓のポンプ機能が弱い人は、特に頭頂部まで十分な血液が届きにくい傾向があります。
頭皮の筋肉が少ない
顔や首には多くの表情筋や筋肉がありますが、頭頂部からおでこにかけては「帽状腱膜」という硬い繊維質の膜に覆われています。この部分には筋肉がほとんど存在しません。
手足や他の部位は、筋肉を動かすことで血管が刺激され、血流が促進される「筋ポンプ作用」が働きますが、頭頂部ではその恩恵がほとんど得られません。
そのため、血流が一度滞ると、自力で回復しにくいのです。
血行不良がメラノサイトに及ぼす影響
血行不良は、メラノサイトの活動に深刻な影響を与えます。
メラノサイトがメラニン色素を作るには、原料となる「チロシン(アミノ酸)」や、その化学反応を助ける酵素「チロシナーゼ」の働きを活性化させるための「銅」などのミネラルが必要です。
これらの栄養素はすべて血液によって運ばれます。血流が滞ると、メラノサイトは「兵糧攻め」のような状態に陥り、色素を作る工場を稼働できなくなってしまいます。
これが、白髪が発生する直接的な引き金となります。
デスクワークや長時間の同じ姿勢
デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続けていると、首や肩の筋肉が緊張し、硬直しがちです。
首や肩のコリは、頭部へとつながる太い血管を圧迫し、頭皮全体の血流を悪化させる大きな原因となります。
特にスマートフォンを長時間見続ける「スマホ首」は、首への負担が大きく、頭皮の血行不良を招きやすいため注意が必要です。
血行不良のサイン
ご自身の頭皮が血行不良に陥っていないか、セルフチェックしてみましょう。以下のようなサインが見られる場合、注意が必要です。
| チェック項目 | 状態 | 血行の状態 |
|---|---|---|
| 頭皮の色 | 青白い、または黄色っぽい・茶色っぽい | 健康な頭皮は青白い。黄色や茶色は血行不良や代謝の低下を示唆。 |
| 頭皮の硬さ | 指で押しても動かない、硬く突っ張っている | 血行が良い頭皮は、柔らかく弾力があり、指で動かすとよく動く。 |
| 頭皮の温度 | 触ると冷たく感じる | 血流が十分に行き届いていないと、頭皮の温度が低下しやすい。 |
白髪対策のために今日からできること
つむじ(頭頂部)の白髪の原因として、ストレスや血行不良、加齢、遺伝などを挙げました。
遺伝や加齢は変えることが難しいですが、ストレスケアや血行促進など、日々の生活習慣を見直すことで、頭皮環境を健やかに保ち、白髪の進行を緩やかにすることは期待できます。
対策①食生活の見直し
髪の毛やメラニン色素は、私たちが食べたものから作られています。バランスの取れた食事は、健やかな髪を育む基本です。
メラニン色素の生成を助ける栄養素
白髪対策として、特に意識して摂取したい栄養素があります。これらはメラノサイトの働きをサポートし、色素生成を助けます。
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食材 |
|---|---|---|
| チロシン(アミノ酸) | メラニン色素の原料となる。 | チーズ・乳製品、大豆製品、たけのこ、バナナ、アボカド |
| 銅(ミネラル) | チロシナーゼ(酵素)の働きを活性化させ、チロシンからメラニンを作るのを助ける。 | レバー、牡蠣、ナッツ類、大豆製品、エビ |
| 亜鉛(ミネラル) | 髪の主成分であるケラチンの合成に必要。新陳代謝を促す。 | 牡蠣、レバー、牛肉(赤身)、チーズ、卵黄 |
| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を助け、タンパク質の代謝に関わる。 | 豚肉、レバー、うなぎ、マグロ、カツオ、納豆、卵 |
血行を促進する食べ物
頭皮の血行を良くするためには、血液をサラサラに保ち、血管を健やかにする栄養素も重要です。ビタミンEは「若返りのビタミン」とも呼ばれ、末梢血管を広げて血流を改善する働きがあります。
アーモンドなどのナッツ類、アボカド、かぼちゃなどに多く含まれます。また、青魚に含まれるEPAやDHAは、血液の流動性を高める効果が期待できます。
避けた方が良い食習慣
栄養バランスを考えるのと同時に、頭皮環境に悪影響を与える可能性のある食習慣は見直すことが賢明です。
| 食習慣 | 懸念される影響 | 対策 |
|---|---|---|
| 脂っこい食事(動物性脂肪)の過剰摂取 | 皮脂の過剰分泌を招き、頭皮環境を悪化させる。血液の粘度を高める可能性。 | 揚げ物やファストフードは控えめに。植物性油や魚の油を意識する。 |
| 糖分の過剰摂取 | 皮脂の分泌を促進する。過剰な糖は体内でタンパク質と結びつき「糖化」を起こし、細胞の老化を早める可能性。 | 甘いお菓子やジュース類は適量にする。 |
| 過度な飲酒・喫煙 | 飲酒(分解時)や喫煙は体内で活性酸素を大量に発生させる。喫煙は血管を収縮させ、血行を著しく悪化させる。 | 休肝日を設け、適量を守る。禁煙を目指す。 |
対策②ストレスケアとリラックス
ストレスが白髪の原因になる以上、そのケアは非常に重要です。自律神経のバランスを整え、副交感神経が優位になるリラックスした時間を意識的に作ることが大切です。
自分に合ったストレス解消法を見つける
ストレスをゼロにすることは難しいですが、溜め込まないようにこまめに発散することが重要です。
軽い運動(ウォーキング、ヨガ)、趣味への没頭、友人との会話、ゆっくりと入浴する、好きな音楽を聴くなど、自分が「心地よい」と感じる時間を見つけましょう。
大切なのは、交感神経の緊張を解きほぐすことです。
質の高い睡眠を確保する
睡眠は、心身のストレスをリセットし、細胞の修復・再生を行うための最も重要な時間です。睡眠中には成長ホルモンが分泌され、頭皮や髪の新陳代謝が活発になります。
メラノサイトの働きを正常に保つためにも、十分な睡眠時間を確保し、その「質」を高めることが求められます。
睡眠の質を高めるポイント
| カテゴリ | 具体的な行動 | 目的 |
|---|---|---|
| 就寝前の習慣 | 就寝1〜2時間前に入浴(ぬるめのお湯)。就寝1時間前からはスマホやPCを避ける。 | 深部体温を下げ、リラックス神経(副交感神経)を優位にする。ブルーライトによる覚醒を防ぐ。 |
| 日中の行動 | 日中は適度に体を動かす。朝に太陽の光を浴びる。 | 適度な疲労感は入眠を助ける。体内時計をリセットし、夜の自然な眠気を促す。 |
| 環境整備 | 寝室を暗く、静かで快適な温度・湿度に保つ。 | 五感への刺激を減らし、深くリラックスできる環境を作る。 |
対策③頭皮の血行促進マッサージ
血行不良が起きやすい頭頂部には、外部からのアプローチとして頭皮マッサージが有効です。硬くなった頭皮をほぐし、血流を直接的に促します。
簡単な頭皮マッサージの方法
シャンプー中や、入浴後で体が温まっているときに行うのが効果的です。指の腹を使い、爪を立てずに優しく行います。
まずは側頭部や後頭部から始め、頭全体の血流を促してから、最後に頭頂部を優しく揉みほぐします。つむじ周辺は、指の腹で小さな円を描くように、あるいは頭皮を寄せるように動かすと良いでしょう。
気持ち良いと感じる程度の強さが適切です。
マッサージの適切な頻度とタイミング
毎日続けることが理想ですが、無理のない範囲で行いましょう。1回あたり3〜5分程度を目安にします。シャンプー時や、仕事の合間にリフレッシュとして行うのも良い方法です。
ただし、強く擦りすぎたり、長時間やりすぎたりすると、かえって頭皮に負担をかける可能性があるため注意が必要です。
マッサージの際の注意点
- 爪を立てず、必ず指の腹を使う。
- 頭皮を強く擦らない(髪の毛が抜ける原因に)。
- 「痛い」と感じるほど強く押さない。
対策④紫外線対策の重要性
見落としがちですが、紫外線は頭皮にとって大きなストレス要因です。つむじ(頭頂部)は、顔の2倍以上の紫外線を浴びているともいわれます。
紫外線が頭皮に与えるダメージ
紫外線を浴びると、頭皮で大量の活性酸素が発生します。この活性酸素が毛根のメラノサイトを直接攻撃し、その機能を低下させたり、損傷させたりすることがわかっています。
これが白髪の一因となります。また、紫外線は頭皮を乾燥させ、バリア機能を低下させるため、頭皮環境全体の悪化にもつながります。
帽子や日傘、頭皮用日焼け止めの活用
日差しの強い日(特に春〜夏)に外出する際は、帽子や日傘を使用して、頭頂部を物理的に保護することが最も効果的です。帽子は通気性の良いものを選び、蒸れに注意しましょう。
最近では、スプレータイプの頭皮・髪用の日焼け止めもありますので、分け目やつむじ周辺に活用するのも良い対策です。
育毛剤や白髪ケア製品の活用
セルフケアと並行して、専用のケア製品を取り入れることも、健やかな頭皮環境を維持するための一つの方法です。
特に男性用の育毛剤メディアとして、これらの製品の役割について触れておきます。
育毛剤の役割と頭皮環境
多くの男性用育毛剤は、直接的に白髪を黒くするものではありません。
その主な目的は、「頭皮環境を整え、血行を促進し、毛根に栄養を与え、抜け毛を防ぎ、健やかな髪の毛の成長(育毛)をサポートすること」にあります。
しかし、この「血行促進」や「頭皮環境の正常化」というアプローチは、白髪の原因である血行不良や栄養不足の改善にも間接的に貢献する可能性があります。
メラノサイトが活動しやすい環境を整えるという意味で、育毛ケアは白髪対策の土台作りともいえます。
白髪ケアに特化した製品の選び方
最近では、白髪へのアプローチを前面に出した頭皮用エッセンスやローションなども増えています。
これらは、メラノサイトの働きに着目した成分や、抗酸化作用の高い成分、血行促進成分などを配合していることが多いです。
ご自身の頭皮の状態(乾燥、皮脂過多など)に合わせて選ぶことが大切です。
ケア製品の主な成分
頭皮ケア製品を選ぶ際の参考に、代表的な成分のカテゴリーと期待される役割を紹介します。
| 成分カテゴリー | 期待される役割 | 代表的な成分例 |
|---|---|---|
| 血行促進成分 | 頭皮の毛細血管の血流を促し、毛根への栄養供給をサポートする。 | センブリエキス、ビタミンE誘導体、ニコチン酸アミド |
| 抗炎症・保湿成分 | 頭皮の炎症や乾燥を抑え、健やかな頭皮環境を維持する。 | グリチルリチン酸2K、ヒアルロン酸、セラミド |
| メラノサイト関連成分 | (製品により異なるが)メラノサイトの働きや色素生成をサポートするとされる成分。 | ホップエキス、サンショウエキス、アシタバエキスなど(各メーカー独自) |
白髪染めや白髪隠しという選択肢
すでに生えてしまった白髪を黒く戻すことは、現在のところ非常に難しいのが現実です。
根本的な対策を続けつつ、見た目の印象をすぐに改善したい場合は、白髪染め(ヘアカラー)や、一時的に白髪を隠すヘアマスカラ、ヘアファンデーションなどを活用するのも現実的かつ有効な選択肢です。
頭皮への負担が少ない製品を選び、使用方法を守って上手に付き合っていくことが重要です。これらを使用する場合でも、土台となる頭皮のケアは継続して行いましょう。
白髪の原因に戻る
よくある質問
- つむじの白髪は抜くと増えますか?
-
「白髪を抜くと増える」というのは医学的な根拠のない俗説です。
白髪を1本抜いても、その毛穴から次に生えてくる毛が白髪である可能性は高いですが、周りの毛穴に影響して白髪が増えることはありません。
ただし、毛を抜く行為は毛根や頭皮にダメージを与え、炎症を起こしたり、毛周期を乱したりする可能性があります。
場合によっては、その毛穴から髪が生えてこなくなる(薄毛)リスクもあるため、抜くのは避けてください。気になる場合は、根元近くでハサミでカットするのが良いでしょう。
- 白髪は黒髪に戻る可能性がありますか?
-
加齢や遺伝によってメラノサイト自体が枯渇してしまった場合、残念ながら黒髪に戻すのは困難です。
しかし、一時的な強いストレスや、極端な栄養不足によってメラノサイトの機能が「休止」しているだけの場合、その原因が取り除かれれば、再びメラニン色素を作り出し、黒髪が再生する可能性はゼロではありません。
ただし、非常に稀なケースであり、過度な期待は禁物です。まずは、これ以上白髪を増やさないための予防ケアが現実的です。
- 特定の食べ物で白髪が急に増えることはありますか?
-
特定の食べ物を一度食べたからといって、急に白髪が増えることは考えにくいです。
しかし、偏った食生活が長期間続くと、栄養バランスが崩れ、頭皮環境やメラノサイトの活動に悪影響を及ぼす可能性はあります。
例えば、脂質や糖質の過剰摂取、ビタミンやミネラルの不足が慢性化すれば、白髪のリスクを高める一因となり得ます。バランスの取れた食事を継続することが重要です。
- 頭皮マッサージはどれくらい続ければよいですか?
-
頭皮マッサージは、薬のように即効性があるものではありません。目的は、硬くなった頭皮をほぐし、血行をじっくりと改善していくことにあります。
そのため、短期間で効果を判断せず、日々の習慣として気長に続けることが大切です。
まずは3ヶ月から半年程度、毎日の習慣として取り入れ、頭皮が柔らかくなってきたか、抜け毛の状態はどうかなど、長期的な視点で変化を見ていくことをお勧めします。
- 育毛剤は白髪にも良い影響がありますか?
-
前述の通り、多くの育毛剤の主目的は「育毛」や「発毛促進」であり、白髪を黒くする効果を直接うたったものではありません。
しかし、育毛剤に含まれる血行促進成分や抗炎症成分が頭皮環境を健やかに保つことは、メラノサイトが働きやすい環境を維持することにもつながります。
白髪も薄毛も、根本には頭皮の血行不良や栄養不足が関わっていることが多いため、頭皮全体の健康を底上げするという点で、間接的に良い影響を与える可能性は期待できます。
Reference
TRÜEB, Ralph M. Oxidative stress in ageing of hair. International journal of trichology, 2009, 1.1: 6-14.
MIRMIRANI, Paradi. Age-related hair changes in men: mechanisms and management of alopecia and graying. Maturitas, 2015, 80.1: 58-62.
SEIBERG, M. Age‐induced hair greying–the multiple effects of oxidative stress. International journal of cosmetic science, 2013, 35.6: 532-538.
YADAV, Mahipat S.; KUSHWAHA, Neeti; MAURYA, Neelesh K. The Influence of Diet, Lifestyle, and Environmental Factors on Premature Hair Greying: An Evidence-Based Approach. Archives of Clinical and Experimental Pathology, 2025, 4.1.
TRÜEB, R. M. The impact of oxidative stress on hair. International journal of cosmetic science, 2015, 37: 25-30.
O’SULLIVAN, James DB, et al. The biology of human hair greying. Biological Reviews, 2021, 96.1: 107-128.
TRÜEB, Ralph; HOFFMANN, Rolf. Aging of hair. In: Textbook of Men’s Health and Aging. CRC Press, 2007. p. 715-728.
PUNSAR, SVEN MATTAS. Head hair in males: relations of baldness, grayness, and hair size to some anthropometric, clinical, and other characteristics. Helsingin Yliopisto (Finland), 1980.
TRÜEB, Ralph M. Understanding pattern hair loss—hair biology impacted by genes, androgens, prostaglandins and epigenetic factors. Indian Journal of Plastic Surgery, 2021, 54.04: 385-392.
TRÜEB, Ralph M.; LEE, Won-Soo. Male alopecia. Guide to successful management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2014.