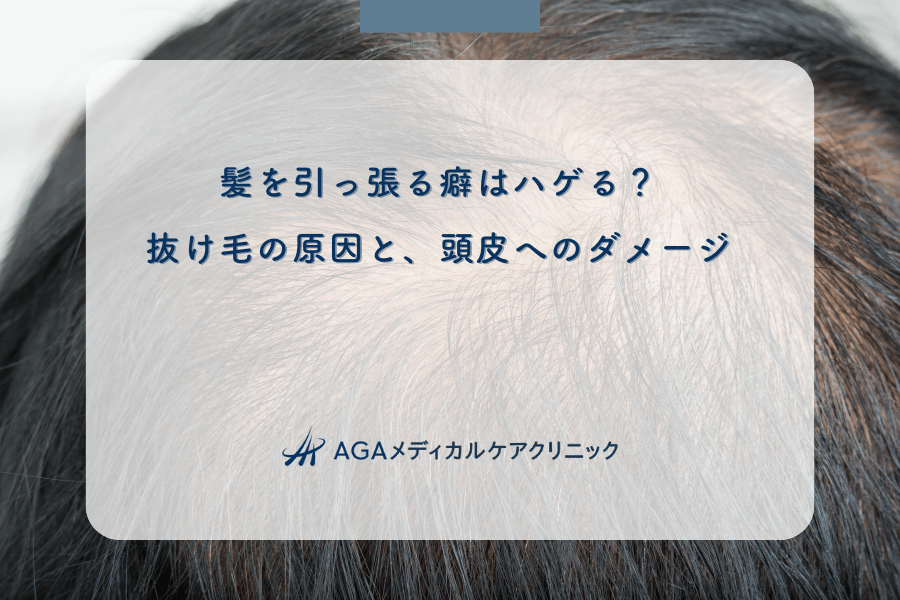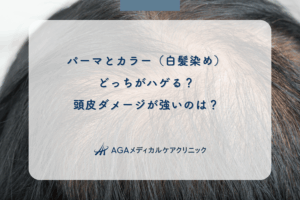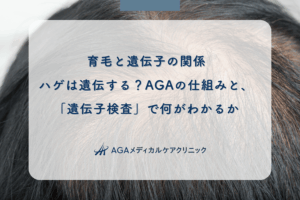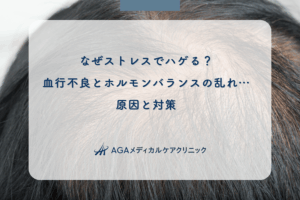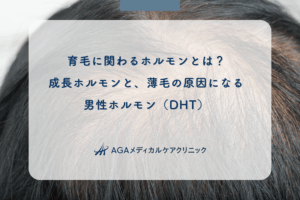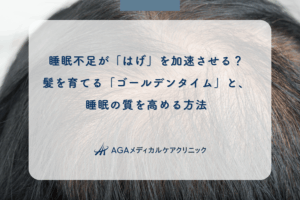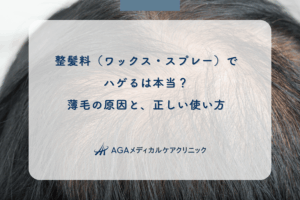ふとした瞬間に、無意識に自分の髪を引っ張っている。そんな癖に心当たりはありませんか。
特にストレスを感じた時などに出てしまうその癖が、「もしかしてハゲる原因になるのでは?」と不安に感じている方もいらっしゃるかもしれません。
髪を引っ張る行為は、単なる癖で済まない場合があり、実際に頭皮や毛根にダメージを与え、抜け毛や薄毛につながる可能性があります。
この記事では、髪を引っ張る癖がなぜ頭皮に悪いのか、どのようなダメージを引き起こすのか、そしてその癖とどう向き合い、大切な髪と頭皮を守るためにどのようなケアが必要なのかを詳しく解説します。
あなたの不安を解消し、健やかな頭皮環境を取り戻すための一歩を一緒に踏み出しましょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
「髪を引っ張る癖」とは?抜毛症(トリコチロマニア)の可能性
髪を引っ張るという行為は、多くの人が無意識のうちに行ってしまうことがあります。しかし、この単純に見える癖が、実は深刻な問題のサインである可能性も秘めています。
まずは、この癖の背景にあるもの、特に「抜毛症(ばつもうしょう)」との関連について理解を深めましょう。
無意識に髪を引っ張っていませんか
考え事をしている時、緊張している時、あるいは退屈している時など、特定の状況で髪をねじったり、引っ張ったりする癖を持つ人は少なくありません。
多くの場合、これは一時的なものであり、本人も自覚していないか、または軽い癖程度に捉えています。しかし、この「無意識」というのがポイントです。
自覚がないままに繰り返される物理的な刺激は、知らず知らずのうちに頭皮や毛根に負担を蓄積させていきます。
まずはご自身が「いつ」「どのような状況で」髪を触っているか、引っ張っているかを意識してみることが、問題解決の第一歩となります。
抜毛症(トリコチロマニア)とは何か
髪を引っ張る癖がエスカレートし、「髪を抜きたい」という衝動を抑えられず、実際に抜いてしまう行為を繰り返す場合、それは「抜毛症(トリコチロマニア)」と呼ばれる精神疾患の一つである可能性があります。
抜毛症は、単なる癖ではなく、衝動制御障害の一種とされています。髪を抜く前の緊張感や不安感、そして抜いた後の解放感や満足感が特徴です。
この行為が長期間続くと、特定の部位の髪が明らかに薄くなるなど、外見にも影響が現れます。自分でコントロールすることが難しく、専門的な対応が必要になるケースも多いのです。
癖と抜毛症の違い
では、単なる「癖」と「抜毛症」はどこが違うのでしょうか。最も大きな違いは、「衝動のコントロール」と「結果の重大さ」にあります。
癖の場合、意識すればやめられたり、引っ張る強さが弱かったりすることが多いです。
一方、抜毛症は、やめたいと思っていてもやめられない強い衝動を伴い、結果として目に見える脱毛斑(髪が抜けて地肌が見える部分)が生じることが一般的です。
また、抜毛症の方は抜いた毛を観察したり、口に入れたりする(食毛症)といった行動を伴うこともあります。
癖と抜毛症の比較
| 特徴 | 単なる癖 | 抜毛症(トリコチロマニア) |
|---|---|---|
| 意識 | 無意識が多いが、意識すれば中断可能 | 強い衝動を伴い、中断が困難 |
| 行為 | 引っ張る、ねじる程度が多い | 毛を抜き取る行為が中心 |
| 結果 | 切れ毛や軽いダメージ程度 | 明らかな脱毛斑、薄毛 |
ストレスとの関連性
髪を引っ張る癖も、抜毛症も、その背景には多くの場合、ストレスや不安、緊張、退屈などが関わっていると考えられています。
ストレス社会と呼ばれる現代において、私たちは日々さまざまな精神的負荷にさらされています。
そうした負荷に対する一つの対処行動(コーピング)として、無意識に髪を触る、引っ張るという行為が現れることがあります。
これが一時的なものであれば大きな問題にはなりにくいですが、ストレスが慢性的になると、癖も常態化し、やがて抜毛症へと移行していくリスクも否定できません。
自分のストレス状態を把握し、適切に発散する方法を見つけることは、髪を守る上でも非常に重要です。
髪を引っ張ると本当にハゲるのか?
「髪を引っ張る癖はハゲる?」という疑問は、この癖を持つ方にとって最も気になるところでしょう。
結論から言うと、その可能性は十分にあります。髪を引っ張るという物理的な行為は、頭皮と毛根に対して私たちが思う以上に深刻な影響を及ぼすのです。
ここでは、その具体的な理由について掘り下げていきます。
牽引性(けんいんせい)脱毛症のリスク
髪を引っ張る行為によって引き起こされる薄毛や抜け毛の多くは、「牽引性脱毛症」と呼ばれるものです。
これは、髪が長期間にわたって物理的に引っ張られ続けることで、毛根や頭皮がダメージを受け、髪が抜けたり、生えてこなくなったりする状態を指します。
ポニーテールやきついお団子ヘアなどを長期間続けている人にも見られる脱毛症ですが、自分の手で髪を引っ張る癖も、同様かそれ以上に強い局所的な牽引力を発生させ、牽引性脱毛症を引き起こす大きな原因となります。
髪を引っ張る行為が頭皮に与える影響
髪を引っ張ると、その力は直接、髪の毛の根元にある毛穴、そしてその奥にある毛根部に伝わります。頭皮は非常にデリケートな組織です。
繰り返し引っ張られることで、頭皮の皮膚が微細に損傷したり、炎症を起こしたりします。また、頭皮が常に緊張状態にさらされることで、表面が硬くなり、血行が悪化する可能性もあります。
頭皮の健康状態は、髪の毛の成長に直結しているため、頭皮へのダメージはそのまま薄毛のリスクにつながります。
毛根への直接的なダメージ
髪の毛は、毛根の最も奥にある「毛乳頭」や「毛母細胞」といった組織の働きによって成長しています。毛乳頭が毛細血管から栄養を受け取り、毛母細胞が分裂・増殖することで髪の毛が作られます。
しかし、髪を強く引っ張る行為は、この大切な毛根部を物理的に傷つけたり、正常な位置からずらしたりする可能性があります。
特に、無理やり髪を引き抜く行為は、毛根部を包む「毛包(もうほう)」ごと引きはがしてしまうことになりかねません。
毛根部が深刻なダメージを受けると、毛母細胞の働きが停止し、その毛穴からは二度と髪が生えてこなくなる可能性もゼロではないのです。
髪の毛のライフサイクル(毛周期)の乱れ
健康な髪の毛には、「成長期(髪が伸びる時期)」「退行期(成長が止まる時期)」「休止期(髪が抜ける準備をする時期)」という毛周期と呼ばれるライフサイクルがあります。
通常、髪の毛の大半(約85~90%)は成長期にあり、数年かけて太く長く成長します。
しかし、髪を引っ張る物理的な刺激が繰り返し加わると、まだ成長期にある髪の毛が強制的に引き抜かれたり、毛根がダメージを受けて成長期が短縮されたりすることがあります。
その結果、髪が十分に成長する前に抜け落ちてしまい、全体の髪の量が減ったり、細く短い髪の毛ばかりが目立つようになったりします。これが、薄毛(ハゲる)状態へとつながっていくのです。
毛周期の段階と引っ張る行為の影響
| 毛周期の段階 | 正常な状態 | 髪を引っ張った場合の影響 |
|---|---|---|
| 成長期 | 数年間続き、髪が太く長く成長する | 強制的に引き抜かれ、期間が短縮する |
| 退行期 | 数週間程度。毛根が退縮する | ダメージにより早期に移行する可能性 |
| 休止期 | 数ヶ月程度。自然に抜け落ちる | ―(この時期の毛は抜けやすい) |
髪を引っ張る癖による頭皮と髪への具体的なダメージ
髪を引っ張るという行為が、牽引性脱毛症のリスクを高めることは前述の通りです。では、具体的に頭皮や髪の毛はどのようなダメージを受けているのでしょうか。
ここでは、目に見えにくい部分で起きている深刻な変化について解説します。
毛穴(毛包)の炎症と損傷
髪を引っ張る力は、毛穴(毛包)に直接作用します。毛穴は単なる穴ではなく、髪の毛を支え、育てるための重要な器官です。
強い力で繰り返し引っ張られると、毛穴の入り口や内部の組織が傷つき、炎症を起こすことがあります。
これが「毛包炎(もうほうえん)」です。毛包炎が起きると、毛穴の周りが赤く腫れたり、かゆみや痛みを感じたりすることがあります。
炎症が慢性化すると、毛包の組織が破壊され、髪の毛を正常に育てることができなくなります。
さらに、炎症が治癒する過程で毛穴が瘢痕化(はんこんか)し、硬くふさがってしまうと、その毛穴からの発毛は永久に停止してしまう危険性があります。
頭皮の硬化と血行不良
私たちの頭皮は、適度な弾力と柔らかさを持っているのが健康な状態です。この弾力性のおかげで、頭皮の下にある毛細血管は圧迫されずに、毛根に必要な栄養や酸素を十分に届けることができます。
しかし、髪を引っ張る癖で頭皮が常に緊張状態にあると、筋肉がこわばり、皮膚そのものも硬くなっていきます。これを「頭皮の硬化」と呼びます。
頭皮が硬くなると、その下を走る毛細血管が圧迫され、血流が悪化します。血行不良は、毛根部への栄養供給を滞らせる最大の要因の一つです。
どれだけ良い食事を摂っても、栄養が毛根に届かなければ、髪の毛は痩せ細り、やがて抜け落ちてしまいます。
切れ毛や枝毛の増加
髪を引っ張る行為は、毛根だけでなく、生えている髪の毛(毛幹)そのものにもダメージを与えます。
特に、髪をねじりながら引っ張る癖がある場合、髪の毛の表面を覆っているキューティクルが剥がれたり、傷ついたりします。キューティクルは髪の内部の水分やタンパク質を守る鎧のような役割をしています。
この鎧が傷つくと、内部の成分が流出し、髪は乾燥してもろくなります。その結果、少しの力でもプツンと切れてしまう「切れ毛」や、毛先が裂けてしまう「枝毛」が急増します。
髪が薄く見える原因は、抜け毛だけでなく、このように髪が途中で切れてしまうことにもあるのです。
新しい髪の毛の質の低下
髪を引っ張る癖が長期間続くと、毛根は常にダメージを受け続けることになります。ダメージを受けた毛根、特に髪の製造工場である毛母細胞は、その働きが低下していきます。
たとえ髪が抜け落ちた後に新しい髪が生えてこようとしても、毛根が弱っているため、以前のような太く健康な髪を作ることができません。
新しく生えてくる髪は、細く、弱々しく、色も薄い「産毛(うぶげ)」のような質の低い髪になってしまうことがあります。
このような細い髪は成長途中で抜けやすく、また頭皮を覆い隠す力も弱いため、全体として薄毛が進行したように見えてしまいます。
頭皮・毛髪へのダメージの種類
| ダメージの対象 | 具体的な症状 | 髪への影響 |
|---|---|---|
| 毛穴(毛包) | 炎症(毛包炎)、瘢痕化 | 発毛の停止、永久脱毛のリスク |
| 頭皮全体 | 硬化、血行不良 | 毛根への栄養不足、髪の成長阻害 |
| 髪の毛(毛幹) | キューティクルの損傷 | 切れ毛、枝毛の増加、髪のやせ細り |
牽引性脱毛症以外の脱毛症との違い
薄毛や抜け毛の原因は、髪を引っ張ることだけではありません。男性の薄毛にはさまざまな種類があり、それぞれ原因や対処法が異なります。
髪を引っ張る癖による「牽引性脱毛症」と、他の代表的な脱毛症との違いを理解することは、ご自身の状態を正しく把握し、適切なケアを選択するために重要です。
男性型脱毛症(AGA)との比較
男性の薄毛の悩みとして最も多いのが「男性型脱毛症(AGA:Androgenetic Alopecia)」です。AGAは、男性ホルモン(特にジヒドロテストステロン:DHT)と遺伝的要因が大きく関わっています。
DHTが毛根にある受容体と結合することで、髪の毛の成長期が極端に短くなり、髪が太く長く成長する前に抜け落ちてしまいます。
AGAは主に前頭部(生え際)や頭頂部(つむじ周り)から薄毛が進行するのが特徴です。
一方、牽引性脱毛症は、髪を引っ張っている特定の部位(例えば、いつも同じ場所を引っ張る癖があればその場所)が局所的に薄くなります。
原因が物理的な刺激であるため、AGA治療薬(フィナステリドやデュタステリドなど)の効果は期待できません。
牽引性脱毛症とAGAの主な違い
| 項目 | 牽引性脱毛症 | 男性型脱毛症(AGA) |
|---|---|---|
| 主な原因 | 物理的な牽引(引っ張る力) | 男性ホルモン(DHT)と遺伝 |
| 薄毛の部位 | 引っ張っている特定の局所 | 前頭部(生え際)、頭頂部 |
| 主な対策 | 原因となる牽引をやめる、頭皮ケア | AGA治療薬の内服、外用薬の使用 |
円形脱毛症との比較
「円形脱毛症」は、ある日突然、コインのような円形または楕円形の脱毛斑が発生する疾患です。
これは自己免疫疾患の一つと考えられており、何らかの原因で免疫機能に異常が生じ、自分の毛根を異物と間違えて攻撃してしまうことで髪が抜けます。
単発型、多発型、全頭型など、症状はさまざまです。牽引性脱毛症も局所的に髪が抜けますが、その原因は免疫異常ではなく明確な物理的刺激です。
また、円形脱毛症の脱毛斑は、境界が比較的はっきりしていることが多いのに対し、牽引性脱毛症や抜毛症による脱毛斑は、毛が途中で切れていたり、まだらに残っていたりすることが多いという違いもあります。
粃糠(ひこう)性脱毛症との比較
「粃糠性脱毛症」は、頭皮の異常、特に大量のフケ(粃糠)が原因で起こる脱毛症です。
頭皮のターンオーバー(新陳代謝)が乱れ、乾燥したフケや脂っぽいフケが毛穴を塞ぎ、頭皮環境が悪化することで炎症が起き、抜け毛が増加します。
頭皮全体にかゆみや赤みを伴うことが多いのが特徴です。牽引性脱毛症は、フケが直接的な原因ではなく、あくまでも外的な力が原因です。
ただし、髪を引っ張る癖のある人が頭皮を触りすぎることで頭皮環境が悪化し、粃糠性脱毛症を併発する可能性はあります。
いずれにせよ、頭皮環境を清潔で健康に保つことは、どのタイプの脱毛症予防においても基本となります。
髪を引っ張る癖をやめたい方へ 今日からできる対策
髪を引っ張る癖が頭皮や髪に悪いと分かっていても、無意識の行動や長年の習慣を変えるのは簡単なことではありません。
しかし、意識と工夫次第で、その癖をコントロールし、軽減することは可能です。ここでは、今日から始められる具体的な対策を紹介します。
まずは癖を自覚することから
対策の第一歩は、自分が「いつ、どんな時に、どのように」髪を引っ張っているかを正確に把握することです。無意識の行動を意識化するためには、記録をつけるのが効果的です。
「ストレスを感じた会議中に」「一人でリラックスしている時にテレビを見ながら」など、具体的な状況をメモしてみましょう。
自分が癖が出やすいパターンを客観的に知ることで、「あ、今引っ張りそうだ」と事前に察知し、行動を制止するきっかけを作ることができます。
鏡をデスクに置いたり、家族や同僚に指摘してもらったりするのも良い方法です。
ストレス管理とリラックス方法
髪を引っ張る行為の多くは、ストレスや不安、緊張の表れです。したがって、癖そのものを無理に抑え込もうとするよりも、その根本原因であるストレスを上手に管理することが重要です。
自分なりのリラックス方法を見つけ、日常生活に組み込みましょう。
例えば、深呼吸をする、軽い運動(ウォーキングなど)で体を動かす、趣味に没頭する時間を作る、ゆっくりと入浴するなど、心身の緊張をほぐす時間を持つことが大切です。
ストレスを感じた時に、髪を引っ張る代わりに行う行動(ハンドグリップを握る、ガムを噛むなど)を決めておく「代替行動」も有効です。
ストレス軽減のための簡単な習慣
| 習慣 | 期待できること | 具体例 |
|---|---|---|
| 適度な運動 | 気分のリフレッシュ、緊張緩和 | 1日20分のウォーキング、ストレッチ |
| 十分な睡眠 | 心身の疲労回復、精神安定 | 毎日同じ時間に寝て起きる |
| 趣味の時間 | ストレスからの解放、没頭 | 音楽鑑賞、読書、ガーデニング |
物理的に髪に触れない工夫
意識やストレス管理と並行して、物理的に髪に触りにくくする環境を作ることも助けになります。
例えば、自宅でリラックスしている時など、癖が出やすい時間帯には帽子をかぶったり、ヘアバンドをしたりするのも一つの方法です。
また、就寝中に無意識に引っ張ってしまう場合は、ナイトキャップを試してみるのも良いでしょう。髪が長い人は、きつくない程度にまとめておくことで、指が髪に入り込むのを防げます。
また、指先を使う癖がある場合は、指にテーピングをしたり、手袋をしたりすることで、髪を引っ張る感覚を変え、癖を自覚しやすくする方法もあります。
癖対策の物理的アプローチ
- 帽子やヘアバンドの着用
- ナイトキャップの使用
- 指先へのテーピングや手袋
専門家への相談も選択肢に
これらのセルフケアを試みても、髪を引っ張る癖がやめられない、あるいは抜毛症の疑いが強い場合は、一人で抱え込まずに専門家に相談することを強く推奨します。
まずは皮膚科を受診し、頭皮の状態や脱毛の状況を診断してもらいましょう。牽引性脱毛症かどうか、他の脱毛症が隠れていないかを診てもらうことが大切です。
また、癖の背景に強いストレスや精神的な要因があると感じる場合は、心療内科や精神科、あるいはカウンセリングといった選択肢もあります。
癖を治すことは、髪を守るだけでなく、ご自身の心の健康を守ることにもつながります。
頭皮ダメージをケアし育毛環境を整える方法
髪を引っ張る癖を改善する努力と同時に、これまでに受けてしまった頭皮のダメージをケアし、髪が再び健やかに育つための「土壌」を整えることも非常に重要です。
傷ついた頭皮はデリケートになっているため、優しくいたわるケアを心がけましょう。
傷ついた頭皮の保湿ケア
髪を引っ張ることで炎症を起こしたり、硬くなったりした頭皮は、乾燥しやすい状態になっています。
頭皮が乾燥すると、かゆみが発生し、さらに掻きむしってしまうことでダメージが悪化するという悪循環に陥りがちです。洗髪後は、頭皮も顔の皮膚と同じように保湿ケアが必要です。
アルコール(エタノール)の含有量が少ない、低刺激性の頭皮用ローションやエッセンスを選び、指の腹で優しくなじませましょう。
ヒアルロン酸やセラミドなどの保湿成分が配合されたものがお勧めです。これにより頭皮のバリア機能が整い、外部からの刺激に強い健康な状態を目指せます。
正しいシャンプーの方法
毎日のシャンプーは、頭皮の汚れを落とすために必要ですが、洗いすぎや洗い方が間違っていると、かえって頭皮を傷つける原因になります。
特にダメージを受けている頭皮には、洗浄力が強すぎるシャンプー(高級アルコール系など)は避け、アミノ酸系などのマイルドな洗浄成分のシャンプーを選ぶと良いでしょう。
洗う際は、爪を立てずに指の腹を使い、頭皮をマッサージするように優しく揉み洗いします。泡立てをしっかり行い、泡で汚れを包み込むように洗うのがコツです。
すすぎ残しは炎症やかゆみの原因になるため、シャンプー剤が頭皮に残らないよう、ぬるま湯で時間をかけて丁寧に洗い流してください。
頭皮マッサージによる血行促進
硬くなった頭皮をほぐし、血行を促進するためには、頭皮マッサージが効果的です。ただし、強くこすったり、爪を立てたりするのは逆効果です。
シャンプー中、あるいは保湿ローションをつけた後などに、指の腹を使って頭皮全体を優しく動かすイメージで行います。
側頭部、前頭部、頭頂部、後頭部と、場所を分けて、それぞれ円を描くように揉みほぐしたり、頭皮全体を掴んでゆっくりと引き上げたりするのも良いでしょう。
リラックスした状態で行うことで、ストレス緩和にもつながります。毎日数分でも継続することが、頭皮環境の改善につながります。
頭皮ケアのポイント
| ケアの種類 | 目的 | 注意点 |
|---|---|---|
| 保湿 | 乾燥を防ぎ、バリア機能を整える | 低刺激性のローションを使用する |
| シャンプー | 汚れを落とし、清潔に保つ | 優しく洗い、すすぎ残しをしない |
| マッサージ | 血行を促進し、頭皮を柔らかくする | 爪を立てず、指の腹で優しく行う |
育毛剤使用の検討
頭皮環境を整えるケアと合わせて、育毛剤の使用を検討するのも一つの方法です。育毛剤の主な目的は、「抜け毛を防ぎ、今ある髪を健やかに育てる」ことです。
髪を引っ張ることでダメージを受けた頭皮の炎症を抑えたり、血行を促進したり、毛根に栄養を与えたりする成分が含まれた育毛剤は、頭皮環境の正常化をサポートしてくれます。
ただし、育毛剤はあくまでも「育毛環境を整える」ものであり、癖そのものを治すものではありません。また、毛根が完全に死滅してしまった(瘢痕化した)毛穴から髪を生やすことはできません。
癖を治す努力と頭皮ケアを基本とした上で、補助的なサポートとして活用するのが賢明です。
育毛剤選びで注目したい成分
髪を引っ張る癖によるダメージをケアし、育毛環境を整えるために育毛剤の使用を考える場合、どのような成分に着目すればよいでしょうか。
牽引によるダメージの特徴である「炎症」「血行不良」「毛根の弱り」にアプローチできる成分が配合されているかどうかが、一つの目安となります。
頭皮の炎症を抑える成分
髪を引っ張る物理的な刺激は、毛穴やその周辺の頭皮に微細な炎症を引き起こしがちです。炎症が続くと頭皮環境が悪化し、健やかな髪の成長を妨げます。
そのため、この炎症を鎮める「抗炎症成分」が重要です。代表的な成分としては、「グリチルリチン酸ジカリウム(グリチルリチン酸2K)」や「アラントイン」などがあります。
これらは医薬部外品の育毛剤に有効成分として配合されることが多く、頭皮の赤みやかゆみを抑え、穏やかな状態に整える働きが期待できます。
血行を促進する成分
頭皮が硬くなり、血行不良に陥っていると、毛根にある毛母細胞に十分な栄養や酸素が届きません。髪の成長には豊富な血流が不可欠です。
そこで、頭皮の血管を拡張させたり、血流を促したりする「血行促進成分」が役立ちます。
代表的な成分には、「センブリエキス」「ニンジンエキス(オタネニンジン根エキス)」「ビタミンE誘導体(酢酸トコフェロールなど)」があります。
これらの成分が頭皮の血流をサポートし、毛根の活動に必要なエネルギーを届けやすくします。
毛母細胞の活性化を助ける成分
度重なるダメージで弱ってしまった毛根、特に髪の毛を生み出す「毛母細胞」の働きをサポートする成分も大切です。毛母細胞が活発に分裂・増殖することが、太く丈夫な髪の成長につながります。
「パントテニルエチルエーテル(パンテノール)」や、アデノシン(資生堂が開発した成分)などは、毛母細胞に直接働きかけたり、エネルギー代謝を促したりすることで、発毛促進や育毛をサポートするとされています。
これらの成分が、弱った毛根に活力を与える手助けをします。
育毛剤の主な有効成分(目的別)
| 目的 | 代表的な成分例 | 期待される働き |
|---|---|---|
| 抗炎症 | グリチルリチン酸2K、アラントイン | 頭皮の炎症や荒れを鎮める |
| 血行促進 | センブリエキス、ビタミンE誘導体 | 頭皮の血流を改善し、栄養を届ける |
| 毛母細胞活性 | パントテニルエチルエーテル、アデノシン | 毛根の働きを活発にし、育毛を促す |
薄毛を加速させる習慣に戻る
よくある質問
- 髪を引っ張るのをやめたら髪はまた生えてきますか?
-
髪を引っ張るのをやめることで、毛根へのダメージがなくなれば、髪が再び生えてくる可能性は十分にあります。
ただし、これは毛根(毛包)が破壊されておらず、まだ髪を生み出す機能が残っている場合に限ります。
長期間にわたって強く引き抜き続け、毛穴が炎症や瘢痕化(はんこんか)によって完全にふさがってしまった場合、その毛穴から髪が再生するのは困難になることがあります。
癖をやめてから数ヶ月は、頭皮が回復する期間として様子を見る必要があります。
- 抜毛症は自分で治せますか?
-
抜毛症は、単なる癖ではなく、精神的な要因や衝動制御の問題が関わる疾患です。軽度の場合、ストレス管理や行動の自覚といったセルフケアで衝動が和らぐこともあります。
しかし、多くの場合、自分の意志だけではコントロールが難しく、やめられない自分を責めてさらにストレスが悪化するという悪循環に陥りがちです。
衝動が抑えられない、日常生活に支障が出ている、脱毛斑が広がっているといった場合は、無理をせず、皮膚科や心療内科、精神科などの専門家に相談することが、改善への近道となります。
- 育毛剤は抜毛症にも効果がありますか?
-
育毛剤は、抜毛症そのもの(=髪を抜きたいという衝動や行為)を治療するものではありません。したがって、育毛剤を使っても髪を抜く癖が治るわけではありません。
ただし、髪を抜いてしまった後の頭皮の炎症を抑えたり、残っている毛やこれから生えてくる毛のために頭皮環境を整えたりするという「補助的なケア」としては役立つ可能性があります。
まずは抜毛行為を止めること、あるいは減らすことが最優先であり、育毛剤の使用は、皮膚科医と相談の上で検討するのが良いでしょう。
- 髪を引っ張る以外に避けるべき頭皮に悪い習慣はありますか?
-
頭皮の健康を害する習慣はいくつかあります。例えば、かゆいからといって爪を立てて頭皮を強く掻きむしる行為は、頭皮を傷つけ炎症の原因となります。
また、洗浄力の強すぎるシャンプーでの洗いすぎや、熱すぎるお湯での洗髪は、頭皮の必要な皮脂まで奪い、乾燥やバリア機能の低下を招きます。
不規則な生活習慣、睡眠不足、栄養バランスの偏った食事、過度な飲酒や喫煙も、全身の血行を悪化させ、頭皮環境や髪の成長に悪影響を及ぼすため、見直しが必要です。
頭皮に負担をかけるその他の習慣
習慣 頭皮への主な悪影響 爪を立てて頭を掻く 頭皮の損傷、炎症、雑菌の侵入 熱いお湯での洗髪 頭皮の乾燥、皮脂の過剰除去 睡眠不足・偏った食事 血行不良、毛根への栄養不足
Reference
UZUNCAKMAK, Tugba Kevser, et al. Trichotillomania and Traction Alopecia. In: Hair and Scalp Disorders. IntechOpen, 2017.
EVERETT, Gregory J.; JAFFERANY, Mohammad; SKURYA, Jonathon. Recent advances in the treatment of trichotillomania (hair‐pulling disorder). Dermatologic therapy, 2020, 33.6: e13818.
PENZEL, Fred. The hair-pulling problem: A complete guide to trichotillomania. Oxford University Press, 2003.
ROMANOV, Dmitry V., et al. Trichotillomania (hair pulling disorder). In: Psychodermatology in clinical practice. Cham: Springer International Publishing, 2021. p. 197-213.
DOGRU, Hicran. Traction alopecia secondary to obsessive-compulsive disorder. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2023, 89.4: 592-594.
ALESSANDRINI, A., et al. Common causes of hair loss–clinical manifestations, trichoscopy and therapy. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2021, 35.3: 629-640.
SHARQUIE, Khalifa E., et al. Traction alopecia: clinical and cultural patterns. Indian Journal of Dermatology, 2021, 66.4: 445.
MELO, Daniel Fernand
es, et al. Trichotillomania: what do we know so far?. Skin appendage disorders, 2022, 8.1: 1-7.
JAJU, Priyanka. Evaluation of Trichoscopic Patterns in Patchy Hair Loss: a Case Series Study. 2018. PhD Thesis. Rajiv Gandhi University of Health Sciences (India).
HAUTMANN, Giuseppe; HERCOGOVA, Jana; LOTTI, Torello. Trichotillomania. Journal of the American Academy of Dermatology, 2002, 46.6: 807-826.