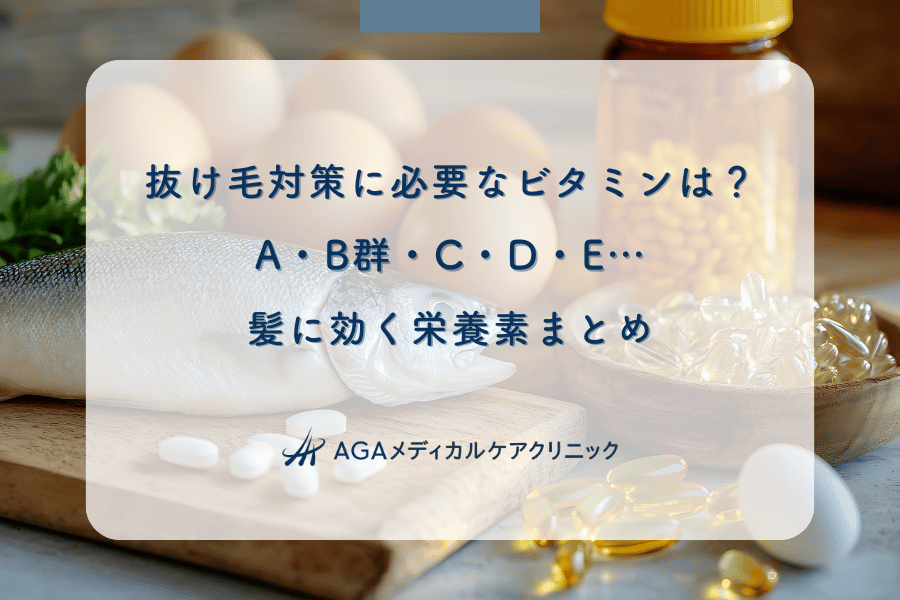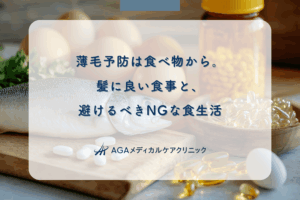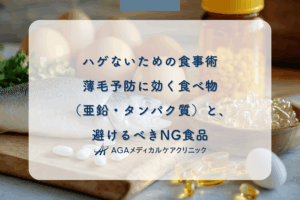最近、シャンプーやブラッシング時の抜け毛が増えたと感じていませんか?鏡を見るたびに、以前より髪のボリュームが減ったように感じ、不安になっているかもしれません。
その原因、もしかしたら毎日の食事での「ビタミン不足」にある可能性も考えられます。髪の健康は、体の内側からの栄養状態と密接に結びついています。
この記事では、抜け毛とビタミンの関係を深掘りし、特に髪の健康に必要とされるビタミンA、B群、C、D、Eなどの栄養素について、それぞれの働きや摂取方法を詳しく解説します。
ご自身の食生活を見直すヒントが見つかるはずです。正しい知識で、内側からのヘアケアを始めましょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
ビタミン不足は抜け毛の原因になる?髪と栄養素の深い関係
髪の成長には多くの栄養素が必要であり、ビタミンが不足するとヘアサイクルが乱れ、頭皮環境が悪化し、結果として抜け毛につながる可能性があります。
髪は体の一部であり、健康な髪を育むためには、健康な体、特に健康な頭皮が土台となります。その土台を作る上で、ビタミンは非常に重要な働きを担っています。
髪の毛が作られる仕組み
髪の毛は、毛穴の奥にある「毛包」という場所で作られます。
毛包の最も深い部分にある「毛母細胞」が、毛細血管から運ばれてくる栄養素や酸素を受け取り、活発に細胞分裂を繰り返すことで、髪の毛は押し上げられるように伸びていきます。
この時、髪の主成分となる「ケラチン」というタンパク質が合成されます。健康な髪が育つためには、この毛母細胞の活動がスムーズに行われることが重要です。
なぜビタミンが髪に必要なのか
ビタミンは、体内でエネルギーを生み出したり、体の調子を整えたりするのに必要な栄養素です。
髪の毛に関して言えば、ビタミンは直接髪の材料になるわけではありませんが、髪の成長を多角的にサポートする「縁の下の力持ち」のような存在です。
例えば、タンパク質がケラチンに変わるのを助けたり、頭皮の血行を促進して毛母細胞に栄養を届けやすくしたり、頭皮環境を健やかに保ったりと、その役割は多岐にわたります。
ビタミン不足が引き起こす頭皮トラブル
特定のビタミンが不足すると、頭皮に様々なトラブルが起こりやすくなります。例えば、皮脂の分泌が過剰になったり、逆に乾燥してフケやかゆみが出たりすることがあります。
また、頭皮の血行が悪くなると、毛母細胞に必要な栄養が十分に行き渡らず、髪の成長が妨げられ、細く弱い髪しか生えてこなくなったり、成長途中で抜けてしまったり(抜け毛)することにつながります。
抜け毛対策に重要なビタミンAとその働き
ビタミンAは、頭皮の健康維持とターンオーバー(新陳代謝)を正常に保つために重要な役割を果たします。
皮膚や粘膜を丈夫にし、潤いを保つ働きがあるため、健康な頭皮環境の維持に寄与します。
頭皮の潤いを保つ
ビタミンAは、皮脂腺の働きを正常に保つのに役立ちます。皮脂は、頭皮を乾燥や外部の刺激から守る天然のバリア機能を持っています。
ビタミンAが不足すると、皮脂の分泌がうまくいかず頭皮が乾燥し、フケやかゆみの原因となることがあります。
逆に、過剰な皮脂は毛穴を詰まらせる可能性もありますが、ビタミンAは細胞の健康を保つことで、このバランスを整えるのを助けます。
毛母細胞の働きをサポート
ビタミンAには、細胞の分化や増殖をコントロールする働きがあります。髪の毛を作り出す毛母細胞も、活発な細胞分裂を繰り返しています。
ビタミンAは、この毛母細胞が正常に働くことをサポートし、健康な髪の成長を促すと考えられています。
ビタミンAを多く含む食品
ビタミンAは、動物性食品に含まれる「レチノール」と、緑黄色野菜などに含まれ体内でビタミンAに変わる「β-カロテン」の2種類から摂取できます。
レチノールは吸収率が高いですが、β-カロテンは必要に応じて体内で変換されるため、過剰摂取の心配が少ないとされています。
ビタミンAを多く含む主な食品
| 食品名 | 種類 | 特徴 |
|---|---|---|
| 鶏レバー・豚レバー | 動物性(レチノール) | 非常に多く含みます。 |
| うなぎ | 動物性(レチノール) | 蒲焼などで摂取しやすいです。 |
| にんじん・かぼちゃ | 植物性(β-カロテン) | 緑黄色野菜の代表例です。 |
| ほうれん草・小松菜 | 植物性(β-カロテン) | おひたしや炒め物で。 |
ビタミンA摂取の注意点
ビタミンAは「脂溶性ビタミン」の一つで、体内に蓄積されやすい性質を持っています。
そのため、サプリメントなどで一度に大量に摂取すると、過剰症(頭痛、吐き気、皮膚のかさつきなど)を引き起こす可能性があります。
特に動物性食品からのレチノール摂取には注意が必要です。通常の食事で緑黄色野菜からβ-カロテンを摂る分には、過剰症の心配はほとんどありません。
髪の成長を支えるビタミンB群の力
ビタミンB群は、髪の主成分であるタンパク質の代謝や、頭皮の健康維持に深く関わっており、抜け毛対策には欠かせない栄養素群です。
ビタミンB群は単独ではなく、お互いに協力し合って働くため、バランスよく摂取することが大切です。
ビタミンB2(リボフラビン)の役割
ビタミンB2は「発育のビタミン」とも呼ばれ、皮膚や粘膜の健康維持に重要な働きをします。
特に皮脂の分泌をコントロールする役割があり、不足すると頭皮が脂っぽくなったり、逆に乾燥したりと不安定になりがちです。
頭皮の脂漏性皮膚炎(フケや炎症)と関連があるとも言われており、頭皮環境を整える上で必要です。
ビタミンB6(ピリドキシン)の役割
ビタミンB6は、タンパク質の代謝に深く関わっています。
髪の毛の約90%はケラチンというタンパク質でできていますが、ビタミンB6は、食事から摂ったタンパク質をアミノ酸に分解し、それをケラチンとして再合成する過程を助けます。
つまり、髪の材料を作るサポート役です。また、ビタミンB2と同様に皮脂のバランスを整える働きもあります。
ビタミンB12(コバラミン)と葉酸
ビタミンB12と葉酸は、どちらも赤血球の生成に必要不可欠なビタミンです。血液中の赤血球は、全身に酸素を運ぶ重要な役割を担っています。頭皮の毛母細胞も、活動するために多くの酸素を必要とします。
ビタミンB12や葉酸が不足して赤血球がうまく作られないと(貧血)、頭皮が酸素不足・栄養不足に陥り、毛母細胞の働きが低下して抜け毛につながる可能性があります。
ビタミンB群を多く含む食品群
| ビタミン名 | 主な働き | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| ビタミンB2 | 皮脂の調節、皮膚・粘膜の健康維持 | レバー、うなぎ、卵、納豆、乳製品 |
| ビタミンB6 | タンパク質(ケラチン)の合成サポート | かつお、まぐろ、バナナ、鶏ささみ |
| ビタミンB12 | 赤血球の生成サポート | しじみ、あさり、レバー、さんま |
| 葉酸 | 赤血球の生成サポート、細胞分裂 | レバー、枝豆、ほうれん草、海苔 |
頭皮環境を整えるビタミンCとビタミンE
ビタミンCとビタミンEは、その強い抗酸化作用により、頭皮の老化を防ぎ、血行を促進することで健康な髪を育む環境を整えます。
これらは「若返りのビタミン」とも呼ばれ、頭皮の健康維持に貢献します。
ビタミンCの働き
ビタミンCは、体内でコラーゲンを生成するのに必須の栄養素です。コラーゲンは、皮膚や血管を丈夫にする働きがあります。
頭皮も皮膚の一部であり、コラーゲンがしっかりしていると、弾力のある健康な頭皮を保つことができます。
また、毛母細胞に栄養を送る毛細血管もコラーゲンからできているため、ビタミンCは血流の基盤を支える役割も持ちます。さらに、ストレスへの抵抗力を高めたり、鉄分の吸収を助けたりする働きもあります。
ビタミンEの働き
ビタミンEは、末梢血管を拡張させ、血液の流れをスムーズにする働きがあります。
頭皮には毛細血管が張り巡らされていますが、ビタミンEを摂取することで、この毛細血管の血流が改善し、毛母細胞に酸素や栄養素が届きやすくなります。
また、ビタミンEは強力な抗酸化作用を持ち、体内の活性酸素から細胞を守ります。
活性酸素は頭皮の細胞を老化させ、毛母細胞の働きを低下させる原因となるため、ビタミンEによる抗酸化は抜け毛予防に重要です。
ビタミンCとEは一緒に摂ると効果的
ビタミンCとビタミンEは、一緒に摂取することで相乗効果が期待できます。
ビタミンEは活性酸素を除去する際に自ら酸化されてしまいますが、ビタミンCはその酸化されたビタミンEを元の状態に戻す(還元する)働きがあります。
つまり、ビタミンCがあることで、ビタミンEがより長く抗酸化作用を発揮し続けることができるのです。
ビタミンC・Eを多く含む食品
| ビタミン名 | 多く含む食品例 | 特徴 |
|---|---|---|
| ビタミンC | ピーマン、ブロッコリー、キウイ、柑橘類 | 水溶性で熱に弱い。生で食べるのが効率的。 |
| ビタミンE | アーモンド、うなぎ、アボカド、植物油 | 脂溶性。油と一緒に摂ると吸収率アップ。 |
あまり知られていない?ビタミンDと髪の健康
ビタミンDは、一般的にカルシウムの吸収を助け、骨の健康を保つために重要なビタミンとして知られていますが、近年の研究で、髪の毛の成長サイクルにも関与している可能性が示唆されています。
ビタミンDと毛包の関係
髪の毛は「成長期」「退行期」「休止期」というヘアサイクルを繰り返しています。
ビタミンDは、このヘアサイクルを正常に開始させるために、毛包(髪を作る器官)内の細胞に働きかける可能性が指摘されています。
ビタミンDを受け取る受容体が毛包にも存在することがわかっており、ビタミンDが不足すると、新しい髪の成長期への移行がスムーズにいかなくなる可能性が考えられています。
ビタミンD不足のリスク
ビタミンDが不足している状態が、一部の脱毛症(特に円形脱毛症など)と関連があるのではないかという研究報告もあります。
ただし、ビタミンD不足が直接的に男性型脱毛症(AGA)のような抜け毛の原因になるかどうかについては、まだ研究途上であり、明確な結論は出ていません。
しかし、健康なヘアサイクルを維持するために、ビタミンDが一定の役割を果たしている可能性は高いと言えるでしょう。
ビタミンDの主な摂取源
ビタミンDは、他のビタミンと異なり、食事から摂取する方法と、日光(紫外線)を浴びることで皮膚で合成される方法の2通りがあります。
ビタミンDの摂取方法
| 摂取方法 | 主な例 | ポイント |
|---|---|---|
| 食事から摂取 | サケ、イワシ、サンマなどの魚類 | 特に青魚に多く含まれます。 |
| 食事から摂取 | きくらげ、しいたけなどのきのこ類 | 天日干しされたものは特に豊富です。 |
| 日光浴 | 適度な日光浴(1日15分〜30分程度) | 窓越しでは効果が薄いです。 |
日光浴の重要性
現代人は室内で過ごす時間が長く、日焼け対策を徹底していることもあり、ビタミンDが不足しがちと言われています。
食事からの摂取に加え、日焼け止めを塗らない状態で手のひらや腕などに適度な日光を浴びることも、ビタミンDを確保する上で有効な手段です。
ただし、日焼けによる皮膚へのダメージを避けるため、真夏の長時間の直射日光などは避ける必要があります。
ビタミンだけじゃない!抜け毛対策に必要なその他の栄養素
抜け毛対策にはビタミンが重要ですが、髪の毛そのものを作る材料や、ビタミンの働きを助けるミネラルなど、他の栄養素も同様に大切です。
ビタミンはあくまでサポート役であり、主役となる栄養素がなければ健康な髪は育ちません。
髪の主成分「タンパク質(ケラチン)」
髪の毛の約90%は「ケラチン」というタンパク質でできています。いくらビタミンを摂取しても、大元の材料であるタンパク質が不足していれば、髪の毛を作ることはできません。
日々の食事で、肉、魚、卵、大豆製品などから良質なタンパク質をしっかり摂取することが、抜け毛対策の基本中の基本です。
ミネラルの重要性「亜鉛」
亜鉛は、タンパク質の合成に深く関わるミネラルです。特に、食事から摂ったタンパク質をケラチンに変える際に、亜鉛は酵素の働きを助ける重要な役割を担います。
亜鉛が不足すると、うまくケラチンが作れなくなり、髪の成長が妨げられたり、脱毛が起こりやすくなったりします。日本人男性は亜鉛が不足しがちとも言われており、意識的な摂取が求められます。
ミネラルの重要性「鉄分」
鉄分は、血液中のヘモグロビン(赤血球)の主成分です。前述の通り、ヘモグロビンは頭皮の毛母細胞に酸素を運ぶ役割を担っています。
鉄分が不足すると貧血状態となり、頭皮が酸欠・栄養不足に陥り、髪が細くなったり抜けやすくなったりします。特に男性でも、無理なダイエットや偏食で不足することがあります。
髪に必要な主な栄養素まとめ
| 栄養素名 | 主な働き | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料 | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |
| 亜鉛 | ケラチンの合成をサポート | 牡蠣、レバー、牛肉(赤身)、チーズ |
| 鉄分 | 血液の材料(酸素運搬) | レバー、赤身肉、ほうれん草、あさり |
髪の成長を支える基本要素
- タンパク質(材料)
- 亜鉛(合成サポート)
- ビタミン群(環境整備・代謝促進)
ビタミンを効率よく摂取する食事と注意点
必要なビタミンを効率よく摂取するには、特定の食品に偏らず、多様な食材を組み合わせたバランスの良い食事を心がけることが基本です。
サプリメントに頼る前に、まずは日々の食生活を見直すことが重要です。
バランスの良い食事とは
バランスの良い食事の基本は、「主食(ごはん、パンなど)」「主菜(肉、魚、卵、大豆製品)」「副菜(野菜、きのこ、海藻)」をそろえることです。
このようにして、エネルギー源となる炭水化物、髪の材料となるタンパク質、そして体の調子を整えるビタミンやミネラルを過不足なく摂取しやすくなります。
調理法によるビタミンの損失
ビタミンは調理法によって失われやすいものもあります。
特にビタミンB群やビタミンCなどの「水溶性ビタミン」は、水に溶けやすく熱にも弱いため、茹でる・煮るといった調理法では煮汁に溶け出してしまいます。
スープごと飲める調理法や、蒸す、炒めるといった短時間で加熱する方法が適しています。
一方、ビタミンA、D、E、Kなどの「脂溶性ビタミン」は、油と一緒に摂ることで吸収率が高まります。
例えば、にんじん(β-カロテン)は、油で炒めたり、ドレッシングをかけたりして食べると効率的です。
水溶性・脂溶性ビタミンの特徴
| 分類 | 主なビタミン | 調理のポイント |
|---|---|---|
| 水溶性ビタミン | B群、C | 水洗いは手早く。加熱は短時間。煮汁も活用。 |
| 脂溶性ビタミン | A、D、E、K | 油を使った調理(炒める、揚げる)で吸収率アップ。 |
サプリメント利用の考え方
どうしても食事が偏りがちで、必要なビタミンを十分に摂取するのが難しい場合は、サプリメントで補うことも一つの方法です。
しかし、サプリメントはあくまで「栄養補助食品」であり、食事の代わりにはなりません。基本は食事から摂ることを目指しましょう。
また、前述の通り、脂溶性ビタミン(A、D、E、K)は体内に蓄積されやすいため、サプリメントでの過剰摂取には特に注意が必要です。
摂取する場合は、製品に記載されている目安量を必ず守るようにしてください。
食事改善の第一歩
- 様々な色の野菜を食卓に取り入れる
- インスタント食品や加工食品を控える
- 肉、魚、大豆製品を偏りなく食べる
栄養素に戻る
抜け毛対策ビタミンに関するよくある質問
抜け毛やビタミン摂取に関して、多くの方が抱く疑問についてお答えします。
- サプリメントを飲めば抜け毛は止まりますか?
-
サプリメントはあくまで栄養補助です。
もし抜け毛の原因が特定のビタミン不足だけにある場合は改善が期待できるかもしれませんが、抜け毛の原因はAGA(男性型脱毛症)、ストレス、生活習慣の乱れなど様々です。
栄養不足以外の原因である場合、サプリメントだけで抜け毛を止めるのは困難です。
まずはバランスの取れた食事が基本であり、抜け毛が続く場合は専門医への相談も検討してください。
- 特定のビタミンだけを大量に摂る方が効果的ですか?
-
いいえ、効果的ではありません。栄養素は体内で互いに協力し合って働いています。例えば、タンパク質を髪に変えるにはビタミンB6や亜鉛が必要ですし、血行を良くするにはビタミンEが役立ちます。
特定のビタミンだけを大量に摂取しても、他の栄養素が不足していれば十分な効果は期待できません。
むしろ脂溶性ビタミンのように、過剰摂取が健康被害につながる場合もあります。バランスが最も重要です。
- 野菜をたくさん食べればビタミンは十分ですか?
-
野菜はビタミンCやA(β-カロテン)、葉酸などの重要な摂取源ですが、ビタミンB12(主に動物性食品)やビタミンD(魚やきのこ類)など、野菜だけでは不足しやすいビタミンもあります。
また、髪の主成分であるタンパク質も必要です。野菜をしっかり摂ることは大切ですが、それだけでなく肉、魚、卵、乳製品などもバランスよく取り入れることが健康な髪を育むことにつながります。
- 食事改善を始めてからどれくらいで効果が出ますか?
-
髪にはヘアサイクル(成長期・退行期・休止期)があるため、食事改善の効果が目に見える形で現れるまでには時間がかかります。今生えている髪の毛は、数ヶ月前に作られたものです。
食事改善によってまず頭皮環境が整い、その健康な頭皮から新しく生えてくる髪が健康になります。
一般的に、頭皮環境の改善には数ヶ月、髪質の変化を感じるには半年から1年程度かかるとも言われています。焦らず継続することが重要です。
Reference
WANG, Ruilong, et al. Micronutrients and Androgenetic Alopecia: A Systematic Review. Molecular Nutrition & Food Research, 2024, 68.22: 2400652.
KONDRAKHINA, Irina N., et al. A cross-sectional study of plasma trace elements and vitamins content in androgenetic alopecia in men. Biological Trace Element Research, 2021, 199.9: 3232-3241.
ALMOHANNA, Hind M., et al. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 51-70.
RAJENDRASINGH, J. R. Role of non-androgenic factors in hair loss and hair regrowth. J Cosmo Trichol, 2017, 3.2: 118.
KONDRAKHINA, Irina N., et al. Evaluation of the effectiveness of personalized treatment of trace element and vitamin status in men with initial stages of androgenic alopecia treated with conservative therapy. Annals of the Russian academy of medical sciences, 2021, 76.6: 604-611.
AKBAŞ, Ayşe; KILINÇ, Fadime. The Role of Micronutrients in Young Men Presenting with Hair Loss. Turkiye Klinikleri Journal of Dermatology, 2021, 31.1.
FAMENINI, Shannon; GOH, Carolyn. Evidence for supplemental treatments in androgenetic alopecia. J Drugs Dermatol, 2014, 13.7: 809-812.
VARMA, Kshitij S., et al. Vitamins as Nutraceuticals for Baldness. In: Preventive and Therapeutic Role of Vitamins as Nutraceuticals. Apple Academic Press, 2024. p. 211-233.
PYI, Phoe. Effectiveness of the combination treatment of Korean red ginseng and vitamin B5 in androgenetic alopecia. 2024. PhD Thesis. Mae Fah Luang University. Learning Resources and Educational Media Centre.
RAJPUT, Rajendrasingh. A scientific hypothesis on the role of nutritional supplements for effective management of hair loss and promoting hair regrowth. J Nutrition Health Food Sci, 2018, 6.3: 1-11.