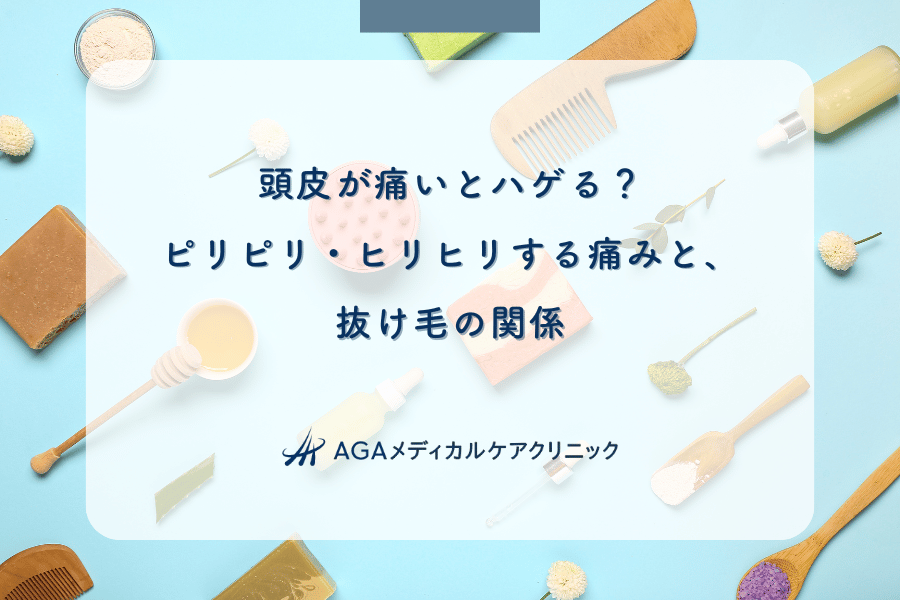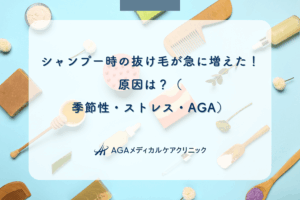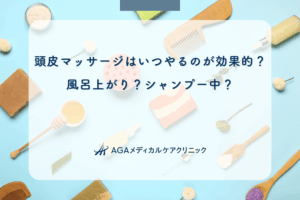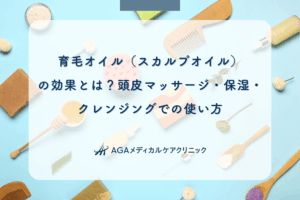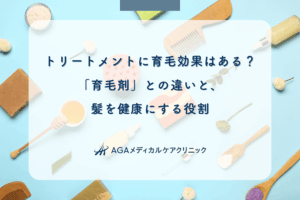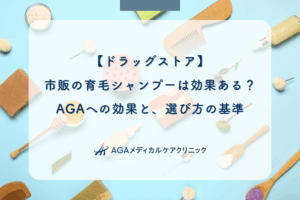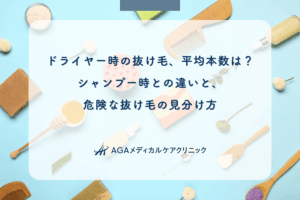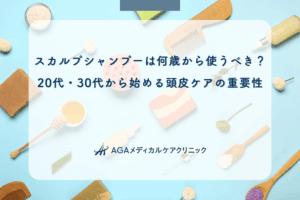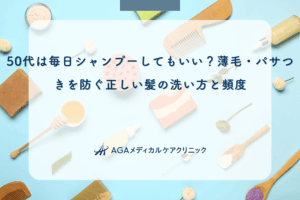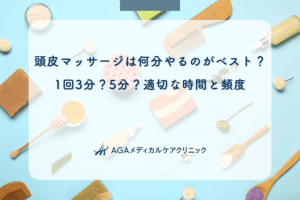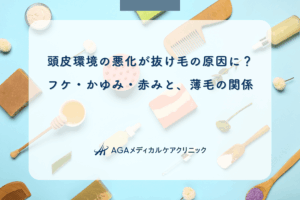ふとした瞬間に頭皮がピリピリと痛む、シャンプーがヒリヒリしみる。そんな経験はありませんか。
「この痛み、もしかしてハゲる前兆なのでは?」と不安に感じる方も多いでしょう。確かに、頭皮の痛みは放置してよいサインではありません。
この記事では、なぜ頭皮が痛くなるのか、そしてその痛みが抜け毛や薄毛とどう関係しているのかを詳しく掘り下げます。
頭皮が発するSOSを見逃さず、原因を突き止め、今日からできる具体的な対策を学ぶことで、健やかな頭皮環境を取り戻す第一歩としましょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
頭皮の痛みが「ハゲる」サインとなる可能性
頭皮にピリピリ、ヒリヒリとした痛みを感じる場合、それは「ハゲる」こと、つまり抜け毛や薄毛が進行するサインである可能性は否定できません。
痛み自体が直接的に毛髪を抜けさせるわけではありませんが、痛みを引き起こしている根本的な原因が、毛髪の成長を妨げる劣悪な頭皮環境を示しているからです。
痛みと抜け毛の直接的な関係
頭皮の「痛み」は、多くの場合、炎症や刺激、乾燥などによって引き起こされます。これらの状態は、毛髪が育つ土壌である頭皮の健康状態が損なわれていることを意味します。
例えば、炎症が起きていれば、毛根部の毛母細胞の活動が阻害される可能性があります。
また、乾燥が進めば頭皮のバリア機能が低下し、外部からの刺激を受けやすくなり、正常なヘアサイクル(毛周期)が乱れることにつながります。
このように、痛みの原因が頭皮環境を悪化させ、結果として抜け毛を誘発し、薄毛の進行につながると考えられます。
頭皮環境の悪化が痛みを引き起こす
健康な頭皮は青白く、適度な潤いと弾力があります。しかし、何らかの原因で頭皮のターンオーバー(新陳代謝)が乱れたり、皮脂の分泌バランスが崩れたりすると、頭皮環境は悪化します。
例えば、皮脂が過剰に分泌されれば毛穴が詰まり、雑菌が繁殖して炎症(痛み・かゆみ)を引き起こします。
逆に皮脂が少なすぎると頭皮は乾燥し、外部刺激に敏感になってピリピリとした痛みを感じやすくなります。この「痛みを感じる状態」自体が、すでに頭皮環境が悪化している証拠です。
なぜピリピリ・ヒリヒリと感じるのか
ピリピリ・ヒリヒリといった感覚は、主に頭皮の神経が刺激を受け取っているサインです。これは、頭皮の表面を保護している「バリア機能」が低下している場合に顕著になります。
健康な頭皮は皮脂膜と角質層によって守られていますが、シャンプーのしすぎや紫外線、体調不良などによってこのバリアが壊れると、通常なら何でもないはずの刺激(シャンプーの成分、汗、風など)に対しても、神経が過敏に反応し、痛みとして感知してしまうのです。
頭皮が痛くなる主な原因の特定
頭皮の痛みは、単一の原因ではなく、複数の要因が絡み合って発生することが多いです。
主な原因としては、頭皮自体の皮膚トラブル、不適切なヘアケア、そして体内の問題を反映する生活習慣の乱れが挙げられます。
これらの原因が頭皮のバリア機能を低下させ、炎症や乾燥を引き起こし、痛みとして現れます。
皮膚炎や湿疹による炎症
頭皮の痛みの原因として非常に多いのが、皮膚炎や湿疹です。特に「脂漏性皮膚炎」は、皮脂の多い部分に発生しやすく、フケや赤み、かゆみ、そして痛みを伴います。
これは、皮脂をエサにするマラセチアという真菌(カビの一種)の異常増殖が関わっているとされます。
また、シャンプーや整髪料、ヘアカラー剤などに含まれる化学物質が肌に合わず、「接触性皮膚炎(かぶれ)」を起こし、ヒリヒリとした痛みや水ぶくれを生じることもあります。
乾燥によるバリア機能の低下
冬場の空気の乾燥や、洗浄力の強すぎるシャンプーによる皮脂の取りすぎは、頭皮の乾燥を招きます。頭皮が乾燥すると、表面の角質層がめくれ上がり、外部からの刺激を直接受けやすくなります。
これが、頭皮のバリア機能の低下です。バリア機能が低下した頭皮は非常に無防備な状態であり、わずかな刺激でも神経が反応し、ピリピリとした痛みを感じるようになります。
間違ったヘアケア(シャンプーなど)
良かれと思って行っているヘアケアが、逆に頭皮を痛めつけているケースも少なくありません。
例えば、1日に何度もシャンプーをする、爪を立ててゴシゴシと強く洗う、熱すぎるお湯ですすぐ、といった行為は、必要な皮脂まで奪い去り、頭皮を乾燥させたり、角質層を傷つけたりします。
また、自分の頭皮タイプ(脂性肌、乾燥肌など)に合っていないシャンプーを使い続けることも、頭皮トラブルと痛みの原因となります。
頭皮タイプとシャンプー選びのミスマッチ
| 頭皮タイプ | 起こりやすい問題 | 間違ったシャンプー選び |
|---|---|---|
| 脂性肌 | 皮脂詰まり、ベタつき、脂漏性皮膚炎 | 保湿系・しっとり系のシャンプー |
| 乾燥肌 | フケ、かゆみ、バリア機能低下(痛み) | 洗浄力が強すぎる高級アルコール系シャンプー |
| 敏感肌 | 炎症、赤み、かぶれ(痛み) | 刺激成分(香料・着色料・防腐剤)が多いもの |
生活習慣の乱れ(ストレス・食生活)
頭皮も体の一部であり、全身の健康状態と密接に関連しています。精神的なストレスは、自律神経やホルモンバランスを乱します。
その結果、血管が収縮して頭皮の血行が悪くなったり、皮脂の分泌が過剰になったりすることがあります。
血行不良は毛根への栄養供給を滞らせ、皮脂の過剰分泌は毛穴の詰まりや炎症を引き起こし、結果として痛みや抜け毛につながります。
また、脂っこい食事や糖分の多い食事、ビタミン・ミネラルの不足といった食生活の乱れも、頭皮環境を悪化させる大きな要因です。
【原因別】痛みの種類と潜むリスク
頭皮の痛みの「感じ方」は、その原因を探る上で重要な手がかりとなります。
ピリピリ、ヒリヒリ、あるいはズキズキといった痛みの違いによって、頭皮がどのような状態に置かれているのか、どのようなリスクが潜んでいるのかをある程度推測することができます。
ピリピリする痛み(乾燥・刺激)
針で軽く刺されるような、断続的で表面的なピリピリとした痛みは、主に頭皮の乾燥とバリア機能の低下が原因と考えられます。
空気が乾燥する季節や、洗浄力の強いシャンプーを使った後に感じやすいのが特徴です。この状態を放置すると、頭皮はさらに乾燥し、フケやかゆみを併発しやすくなります。
また、外部からの刺激に無防備なため、わずかなことで炎症を起こし、抜け毛につながるリスクが高まります。
ヒリヒリする痛み(炎症・日焼け)
日焼けした肌のような、持続的で熱を帯びたヒリヒリとした痛みは、頭皮が炎症を起こしているサインです。
シャンプーやヘアカラー剤による「かぶれ(接触性皮膚炎)」や、夏の強い紫外線による「日焼け(日光皮膚炎)」が主な原因です。炎症が起きているということは、頭皮の細胞がダメージを受けている証拠です。
この炎症が毛根にまで及ぶと、毛髪の成長が妨げられ、急性(円形脱毛症など)または慢性的な抜け毛を引き起こす危険性があります。
ズキズキする痛み(神経痛の可能性)
頭皮の表面ではなく、奥の方で脈打つようにズキズキと痛む場合、それは皮膚の問題ではなく、「神経痛」の可能性があります。
代表的なものに「後頭神経痛」があり、後頭部から頭頂部、時には側頭部にかけて痛みが走ります。
これは、ストレスや長時間の同じ姿勢(デスクワークなど)による首や肩のコリが原因で、頭部へ向かう神経が圧迫されて起こります。
直接的にハゲる原因ではありませんが、痛みのストレスや血行不良が、間接的に頭皮環境に悪影響を与える可能性はあります。
かゆみを伴う痛み(脂漏性皮膚炎など)
強いかゆみと共に、掻きむしった後がヒリヒリと痛む場合は、「脂漏性皮膚炎」や「アトピー性皮膚炎」などの皮膚疾患が強く疑われます。
特に脂漏性皮膚炎は、ベタついたフケを伴うことが多く、皮脂の過剰分泌とマラセチア菌の増殖が関わっています。かゆくて掻いてしまうと、頭皮のバリア機能がさらに破壊され、炎症が悪化します。
この悪循環が続くと、毛穴が炎症で塞がったり、毛根がダメージを受けたりして、抜け毛が著しく増加することがあります。
痛みの感覚と主な原因のまとめ
| 痛みの感覚 | 主な原因 | 潜むリスク |
|---|---|---|
| ピリピリ | 乾燥、バリア機能低下 | フケ、かゆみ、軽度の炎症 |
| ヒリヒリ | 炎症(日焼け、かぶれ) | 毛根へのダメージ、急性抜け毛 |
| ズキズキ | 神経痛、血行不良 | ストレス、間接的な頭皮環境悪化 |
| かゆみ+痛み | 脂漏性皮膚炎、アトピー | 慢性的な炎症、脱毛の進行 |
頭皮の痛みを放置する危険性
頭皮の痛みは、「今はまだ我慢できる」と軽視されがちですが、それは体からの重要な警告サインです。この痛みを放置することは、将来的に深刻な抜け毛や薄毛につながる危険性をはらんでいます。
痛みの裏には頭皮環境の重大な悪化が隠れており、時間と共にその問題は深刻化します。
抜け毛・薄毛の進行
最も恐れるべきは、抜け毛の増加と薄毛の進行です。前述の通り、痛みは炎症、乾燥、血行不良といった、毛髪の成長にとって最悪な環境の表れです。
炎症が続けば毛母細胞は正常に働けず、乾燥で頭皮が硬くなれば新しい毛髪が生えにくくなります。血行不良は毛髪への栄養補給を断ちます。
これらの要因が複合的に作用し、今生えている毛髪の寿命を縮め(早期の脱毛)、新しく生えてくる毛髪を弱く細くし(軟毛化)、最終的に「ハゲる」という状態を加速させます。
慢性的な頭皮トラブルへの発展
一時的な痛みや炎症も、放置すれば慢性化します。例えば、脂漏性皮膚炎を放置すると、炎症が常に続く状態となり、完治が難しくなります。
乾燥も同様で、慢性的な乾燥肌は、常に外部からの刺激に弱い敏感肌へと体質を変えてしまう可能性があります。
一度慢性化した頭皮トラブルは、改善までに長い時間と労力を要し、その間も抜け毛のリスクは高止まりしたままになります。
ヘアサイクルの乱れ
毛髪には、「成長期」(毛が育つ期間)、「退行期」(成長が止まる期間)、「休止期」(毛が抜け落ちる期間)というヘアサイクルがあります。
健康な頭皮であれば、ほとんどの毛髪(約85-90%)が2年~6年の「成長期」にあります。しかし、頭皮環境が悪化し、炎症や栄養不足が続くと、この「成長期」が大幅に短縮されます。
毛髪が十分に太く長く成長する前に「退行期」「休止期」へと移行してしまうため、抜け毛が増える一方で、生えてくる毛は細く弱々しくなります。
これが、薄毛の典型的な進行パターンです。
ヘアサイクルが乱れる流れ
| ステップ | 頭皮の状態 | 毛髪への影響 |
|---|---|---|
| 初期(痛み発生) | 炎症、乾燥、血行不良 | 毛根部へのストレス増加 |
| 中期(放置) | 頭皮環境の慢性的な悪化 | 成長期が短縮し始める |
| 後期(薄毛進行) | 毛母細胞の活力低下、毛穴の萎縮 | 抜け毛増加、毛髪の軟毛化 |
自宅でできる頭皮の痛み応急ケア
頭皮に痛みを感じたら、専門医の診断を受けるのが最善ですが、すぐに病院に行けない場合もあります。そのような時、症状を悪化させないために自宅でできる応急的なケア方法を知っておくことが重要です。
ただし、これらはあくまで一時的な対処であり、根本的な解決ではないことを理解してください。
まずは頭皮を冷やすべき?
痛みがヒリヒリとして熱を帯びている場合、例えば日焼けやヘアカラー直後の炎症が疑われる場合は、冷やすことが有効です。
清潔なタオルで包んだ保冷剤や、冷水で濡らして固く絞ったタオルを優しく当てることで、炎症を鎮め、痛みを和らげることが期待できます。
ただし、冷やしすぎは血行を悪くする可能性もあるため、短時間(数分程度)に留めましょう。
一方で、乾燥や血行不良によるピリピリとした痛みの場合、冷やすことは逆効果になることもあるため、自己判断は禁物です。
刺激の少ないシャンプーの選び方
痛みがある時のシャンプーは、頭皮への刺激を最小限に抑えることが最優先です。
洗浄力が強い「高級アルコール系」(ラウリル硫酸Na、ラウレス硫酸Naなど)のシャンプーは避け、「アミノ酸系」(ココイルグルタミン酸Na、ラウロイルメチルアラニンNaなど)や「ベタイン系」の、マイルドな洗浄成分を使用したものを選びましょう。
また、香料、着色料、防腐剤(パラベンなど)、エタノール(アルコール)などが含まれていない、敏感肌向けの低刺激処方・無添加処方のものが望ましいです。
シャンプーの洗浄成分比較
| 成分タイプ | 特徴 | 痛みがある頭皮への適性 |
|---|---|---|
| 高級アルコール系 | 洗浄力が高く、安価。泡立ちが良い。 | 不向き(刺激が強く、乾燥を招きやすい) |
| アミノ酸系 | 洗浄力がマイルド。保湿性が高い。 | 適している(低刺激で優しく洗える) |
| ベタイン系 | アミノ酸系よりさらにマイルド。ベビー用にも使われる。 | 非常に適している(刺激を最小限にしたい場合) |
保湿ローションによるケア
乾燥によるピリピリとした痛みには、保湿が効果的です。シャンプー後、ドライヤーで髪を乾かした(ただし乾かしすぎない)後に、頭皮専用の保湿ローションや化粧水を使用します。
ここでもシャンプーと同様、アルコール(エタノール)フリーで、セラミド、ヒアルロン酸、グリセリンなどの保湿成分が配合された、低刺激性のものを選びます。
ローションを指の腹で優しく頭皮になじませ、マッサージは行わず、そっと押さえるように塗布するのがコツです。
育毛剤の使用は痛い時どうする?
すでに育毛剤を使用している方が頭皮に痛みを感じた場合、その使用を続けるべきか否かは、非常に悩ましい問題です。
育毛剤は頭皮環境を整えるものですが、痛みがある状態では、その成分が逆に刺激となり、症状を悪化させる可能性があります。
痛む頭皮に育毛剤は逆効果か
結論から言えば、痛みや炎症がある頭皮に育毛剤を使用するのは、逆効果になる可能性が高いです。
多くの育毛剤には、血行促進成分(センブリエキスなど)や、清涼感を与えるためのアルコール(エタノール)、メントールなどが含まれています。
これらの成分は、健康な頭皮には有効でも、バリア機能が低下して敏感になっている頭皮には強い刺激となり、ヒリヒリとした痛みを増強させたり、炎症を悪化させたりする原因になります。
使用を一時中断する判断基準
育毛剤を使用していて、あるいは使用し始めたタイミングで頭皮に痛み(ピリピリ、ヒリヒリ)、かゆみ、赤みなどの異常を感じた場合は、直ちに使用を中断するべきです。
これは、育毛剤の特定の成分に対するアレルギー反応(接触性皮膚炎)か、あるいは既存の頭皮トラブルを悪化させているサインです。
使用を中断し、数日経っても症状が改善しない場合や、悪化する場合は、育毛剤のボトルを持参の上、皮膚科を受診してください。
育毛剤の成分が刺激になるケース
特に注意が必要なのは、アルコール(エタノール)を高濃度で含む育毛剤です。
エタノールは殺菌作用や清涼感、成分の浸透補助のために配合されますが、揮発する際に頭皮の水分を奪い、乾燥を助長します。乾燥してバリア機能が低下している頭皮には、この上ない刺激となります。
また、メントールやカプサイシン(トウガラシエキス)などの刺激で血行を促すタイプの成分も、炎症がある頭皮には不向きです。
注意すべき育毛剤の成分例
| 成分名(例) | 一般的な配合目的 | 痛みがある頭皮への影響 |
|---|---|---|
| エタノール(アルコール) | 清涼感、殺菌、浸透補助 | 強い刺激、乾燥の助長 |
| メントール | 清涼感、かゆみ止め | 強い刺激、炎症を悪化させる可能性 |
| 香料・着色料 | 使用感の向上 | アレルギー(かぶれ)の原因になる可能性 |
頭皮の痛みと抜け毛の専門家相談
セルフケアを試みても痛みが改善しない、あるいは痛みに加えて明らかに抜け毛が増えてきた場合は、自己判断を続けるのは危険です。
頭皮の痛みや抜け毛は、皮膚疾患や、時には内科的な問題のサインである可能性もあります。早めに専門家である皮膚科医に相談することが、早期解決と将来の薄毛予防への最短距離です。
皮膚科を受診する目安
以下のような症状が見られる場合は、セルフケアを中止し、速やかに皮膚科を受診してください。
- 痛みが1週間以上続く
- 我慢できないほどの強い痛みや、ズキズキする痛みがある
- 痛みだけでなく、強いかゆみ、大量のフケ、赤み、腫れ、水ぶくれ、じゅくじゅくした湿疹を伴う
- セルフケア(シャンプー変更など)をしても症状が悪化する
- 痛みと共に、明らかに抜け毛が急増した(例:シャンプー時、枕元など)
どのような症状を伝えるべきか
診察時には、医師に正確な情報を伝えることが重要です。以下の点を整理しておくとスムーズです。
- いつから痛むか(昨日から、1ヶ月前から)
- どのような痛みか(ピリピリ、ヒリヒリ、ズキズキ)
- 痛む頻度(常に痛む、シャンプー時だけ痛む)
- 痛む場所(頭頂部、後頭部、全体)
- 痛み以外の症状(かゆみ、フケ、赤み、抜け毛)
- 最近変えたこと(シャンプー、整髪料、ヘアカラー、生活習慣、ストレスの有無)
- 現在使用している育毛剤や薬
専門医が行う頭皮診断とは
皮膚科では、まず問診と視診(医師が直接頭皮の状態を目で見る)を行います。必要に応じて、ダーモスコープ(拡大鏡)を使い、毛穴の状態、炎症の程度、頭皮の色、フケの状態などを詳細に観察します。
これにより、脂漏性皮膚炎、接触性皮膚炎、乾燥性湿疹などの皮膚疾患の診断を行います。
場合によっては、真菌(カビ)の有無を調べるためにフケを採取したり、アレルギーを特定するためにパッチテストを行ったりすることもあります。
これらの診断に基づき、抗炎症薬(ステロイド外用薬など)や抗真菌薬、保湿剤などが処方されます。
頭皮環境と保湿に戻る
Q&A
- 頭皮が痛い時、シャンプーは毎日すべき?
-
一概には言えません。皮脂が多くてベタつく脂性肌タイプの方や、汗を多くかいた日は、低刺激のシャンプーで優しく洗う方がよいでしょう。
皮脂や汚れを放置すると、雑菌が繁殖し炎症を悪化させるからです。一方で、乾燥が原因で痛む場合は、毎日洗うと必要な皮脂まで奪い、かえって乾燥を悪化させる可能性があります。
その場合は、1日おきにするか、お湯だけで優しくすすぐ「湯シャン」の日を設けるなどの調整が必要です。
自分の頭皮の状態を見ながら、洗いすぎず、汚れたままにしないバランスを見つけることが重要です。
- 痛みに効く市販薬はありますか?
-
頭皮の痛みの原因によって使用すべき薬は異なります。
例えば、乾燥による軽いかゆみやピリピリ感であれば、非ステロイド系の鎮痒成分や保湿成分が入ったローションタイプのかゆみ止めが使える場合があります。
しかし、炎症(赤み、腫れ)が強い場合や、脂漏性皮膚炎が疑われる場合は、自己判断で市販薬を使うと悪化する危険があります。
特にステロイド系の薬は、原因によっては(例:真菌)逆効果になることもあります。痛みが続く場合は、市販薬に頼る前にまず皮膚科で正しい診断を受けることを強く推奨します。
- 食生活で気をつけることは?
-
頭皮の健康は、食生活と密接に関わっています。
皮脂の分泌を過剰にする脂っこい食事(揚げ物、スナック菓子など)、糖分の多い食事(甘いお菓子、ジュースなど)、刺激物(香辛料など)は、炎症を悪化させる可能性があるため、痛む時は特に控えるべきです。
逆に、頭皮のターンオーバーや毛髪の生成を助けるビタミンB群(レバー、納豆、卵など)、ビタミンC(野菜、果物)、タンパク質(肉、魚、大豆製品)、亜鉛(牡蠣、ナッツ類)などをバランス良く摂取することが大切です。
- 痛みは治ったが抜け毛が減らない場合は?
-
頭皮の痛み(炎症や乾燥)が治まっても、抜け毛がすぐに止まらないケースはあります。
これは、ダメージを受けた頭皮環境が回復し、乱れたヘアサイクルが正常に戻るまでに時間がかかるためです。
炎症によって一度「休止期」に入ってしまった毛髪は、炎症が治まっても数ヶ月は抜け続けます。
ただし、痛みが治まってから3ヶ月以上経っても抜け毛が減らない、あるいは薄毛が進行しているように感じる場合は、AGA(男性型脱毛症)など、痛みとは別の原因による薄毛が進行している可能性が考えられます。
その場合は、皮膚科またはAGA専門のクリニックに相談することをお勧めします。
Reference
ALESSANDRINI, A., et al. Common causes of hair loss–clinical manifestations, trichoscopy and therapy. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2021, 35.3: 629-640.
TRÜEB, Ralph M., et al. The Hair and Scalp in Systemic Infectious Disease. In: Hair in Infectious Disease: Recognition, Treatment, and Prevention. Cham: Springer International Publishing, 2023. p. 303-365.
TRÜEB, Ralph M. Is androgenetic alopecia a photoaggravated dermatosis?. Dermatology, 2003, 207.4: 343-348.
OIWOH, Sebastine Oseghae, et al. Androgenetic alopecia: A review. Nigerian Postgraduate Medical Journal, 2024, 31.2: 85-92.
WOLFF, Hans; FISCHER, Tobias W.; BLUME-PEYTAVI, Ulrike. The diagnosis and treatment of hair and scalp diseases. Deutsches Ärzteblatt International, 2016, 113.21: 377.
CRANWELL, William; SINCLAIR, Rodney. Male androgenetic alopecia. 2015.
ASFOUR, Leila; CRANWELL, William; SINCLAIR, Rodney. Male androgenetic alopecia. Endotext [Internet], 2023.
BURRONI, Anna Graziella, et al. Sensitive scalp: an epidemiologic study in patients with hair loss. Dermatology Reports, 2022, 14.3: 9408.
MOGHADAM-KIA, Siamak; FRANKS, Andrew G. Autoimmune disease and hair loss. Dermatologic clinics, 2013, 31.1: 75-91.
WILLIMANN, Barbara; TRÜEB, Ralph M. Hair pain (trichodynia): frequency and relationship to hair loss and patient gender. Dermatology, 2002, 205.4: 374-377.