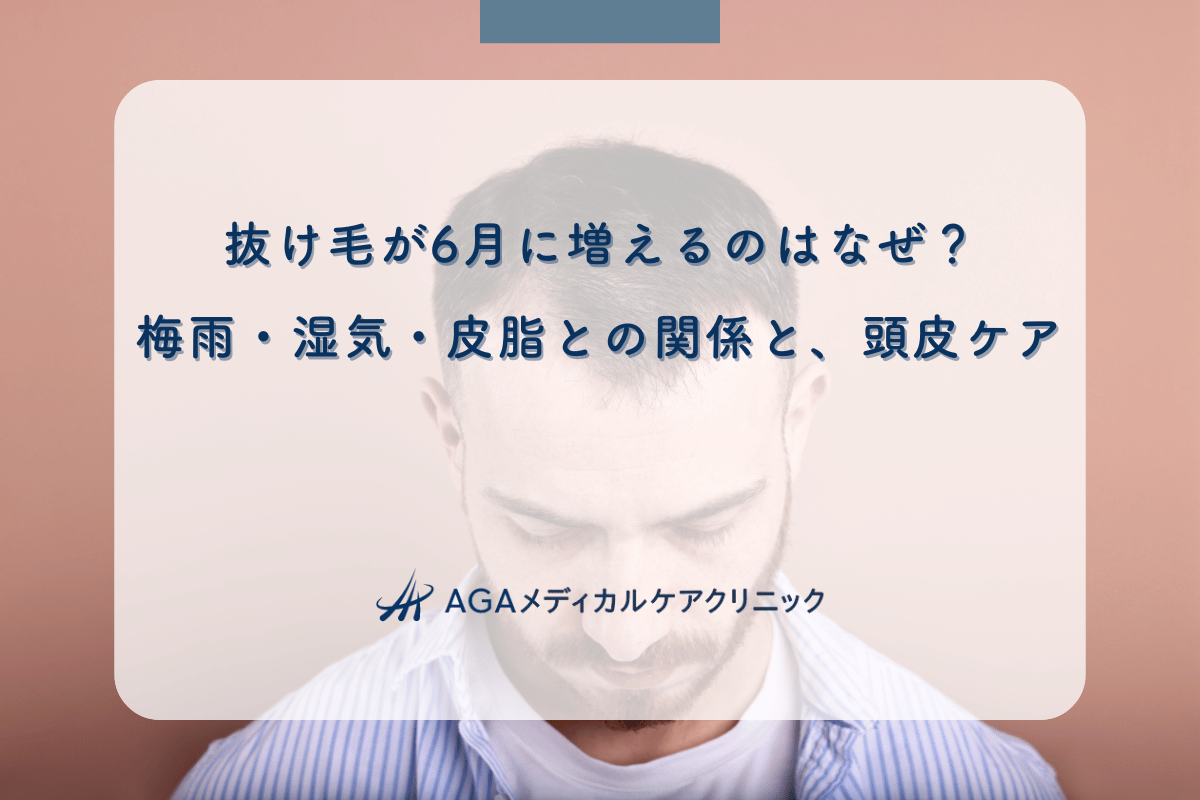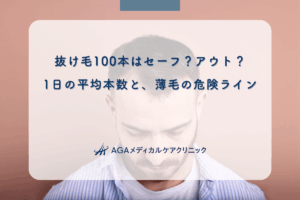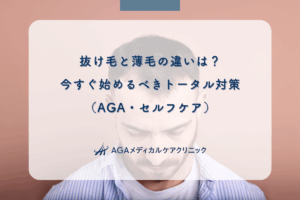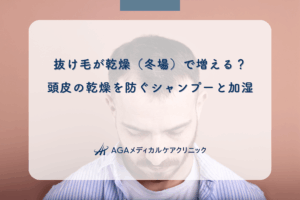「最近、抜け毛が増えたかも…」特に6月に入ってから、そう感じることはありませんか?鏡を見るたび、シャンプーやブラッシングのたびに、ごそっと抜ける髪の毛に不安になるその気持ち、よくわかります。
実は、6月に抜け毛が増えると感じるのには、梅雨特有の「湿気」や「皮脂」、そして「紫外線」が大きく関係している可能性があります。
この記事では、なぜ6月に抜け毛が目立つのか、その原因となる気候的要因と頭皮環境の関係を詳しく解説します。さらに、今日から始められる具体的な頭皮ケア方法もご紹介します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
6月の抜け毛「増えたかも?」その感覚の正体
6月になると抜け毛が増える、というのは単なる気のせいではなく、多くの人が感じる季節的な現象の一つと考えられます。
春から夏へと移り変わるこの時期は、頭皮環境にとって過酷な要因が揃いやすいためです。具体的にどのような感覚なのか、そしてその背景にある要因を見ていきましょう。
排水溝や枕に残る髪の毛
抜け毛の増加を最も実感しやすいのは、やはり日々の生活シーンです。
朝起きたときに枕についている髪の毛の本数、シャンプーの際に指に絡みつく髪の毛、そして排水溝にたまる髪の毛の量。
これらが普段より明らかに多いと感じたとき、「抜け毛が増えた」と認識します。
特に6月はジメジメとした気候も相まって、視覚的にも精神的にも不快感が増し、より一層抜け毛が気になりやすくなる時期とも言えます。
季節性と抜け毛のウワサ
一般的に、髪の毛には「ヘアサイクル(毛周期)」があり、1日に50本から100本程度は自然に抜け落ちると言われています。
このサイクルは季節によっても変動し、特に「春」と「秋」は抜け毛が増加しやすい時期として知られています。春は、冬の間に蓄積されたダメージや、新陳代謝が活発になる影響が考えられます。
6月は春の延長線上、あるいは夏の入り口として、この変動の影響を受けている可能性があります。
6月特有の頭皮環境リスク
春や秋の一般的な季節変動に加えて、6月には日本特有の「梅雨」という大きな環境変化が待ち受けています。
この時期の気候的特徴が、頭皮環境に直接的な影響を及ぼし、抜け毛を誘発する引き金となるのです。
6月の主な気候的特徴
| 気候要因 | 特徴 | 頭皮への影響(例) |
|---|---|---|
| 高湿度(梅雨) | ジメジメとした空気が続く | 頭皮の蒸れ、雑菌の繁殖 |
| 気温の上昇 | 夏日や真夏日も増え始める | 皮脂や汗の分泌増加 |
| 紫外線 | 5月頃から急激に強まる | 頭皮や毛髪へのダメージ |
なぜ6月は抜け毛が増加傾向にあるのか
6月の抜け毛は、主に「湿気」「皮脂」「紫外線」という3つの外的要因が複雑に絡み合うことで引き起こされます。
これらの要因がどのように頭皮環境を悪化させ、抜け毛につながるのかを詳しく解説します。
梅雨の「湿気」が頭皮に与える影響
6月の日本を象徴するのが梅雨です。連日続く高い湿度は、洗濯物が乾きにくいだけでなく、私たちの頭皮環境にも深刻な影響を与えます。
湿度が高いと、汗や皮脂が蒸発しにくくなり、頭皮が常にジメジメとした「蒸れた」状態になります。この環境は、頭皮トラブルを引き起こす雑菌にとって、非常に好ましい住処となってしまいます。
頭皮の常在菌バランス
私たちの頭皮には、多種多様な「常在菌」が存在し、互いにバランスを取りながら皮膚の健康を保っています。
しかし、湿度と温度が高い環境が続くと、特定の菌、特に「マラセチア菌(カビの一種)」などが異常増殖しやすくなります。
マラセチア菌は皮脂をエサに増殖し、フケやかゆみ、炎症(脂漏性皮膚炎など)の原因となることがあります。
こうした頭皮の炎症は、毛根にダメージを与え、健康な髪の成長を妨げ、結果として抜け毛を増加させる一因となります。
雑菌の増殖とニオイ
湿気によって頭皮が蒸れると、皮脂や汗、古い角質などが混ざり合い、雑菌がそれを分解することで不快な「ニオイ」も発生しやすくなります。
ニオイが気になるからといって、シャンプーでゴシゴシと洗いすぎると、かえって頭皮を守るために必要な皮脂まで奪ってしまい、乾燥やさらなる皮脂の過剰分泌を招く悪循環に陥ることもあります。
気温上昇に伴う「皮脂」の過剰分泌
6月は梅雨の時期であると同時に、気温もぐんぐん上昇し、夏日(25℃以上)や真夏日(30℃以上)になる日も増えてきます。
気温が上がると、体温調節のために汗をかくのと同様に、頭皮の皮脂腺も活発になり、皮脂の分泌量が増加します。
皮脂の役割と過剰な状態
| 皮脂の役割 | 皮脂が過剰な場合の問題点 |
|---|---|
| 頭皮や髪の保湿(バリア機能) | 毛穴詰まり |
| 外部の刺激からの保護 | 雑菌の繁殖(フケ・かゆみ) |
| 髪にツヤを与える | 炎症(脂漏性皮膚炎) |
毛穴詰まりと炎症のリスク
皮脂は本来、頭皮を守るために必要ですが、過剰に分泌されると問題を引き起こします。余分な皮脂が古い角質やホコリなどと混ざり合い、毛穴を塞いでしまう「角栓」を形成することがあります。
毛穴が詰まると、髪の毛の健やかな成長が妨げられるだけでなく、詰まった毛穴の中で雑菌が繁殖し、炎症(毛嚢炎など)を引き起こす原因にもなります。
この炎症が、抜け毛や薄毛に直結する可能性があります。
皮脂の酸化が招く頭皮ダメージ
分泌された皮脂は、空気に触れる時間が長くなると「酸化」します。
特に気温と湿度が高い6月は、皮脂が酸化しやすい条件が揃っています。酸化した皮脂(過酸化脂質)は、頭皮にとって強い刺激物となり、細胞にダメージを与えたり、炎症を引き起こしたりします。
この「頭皮のサビ」とも言える状態が、毛根の働きを弱らせ、抜け毛を促進すると考えられています。
意外な伏兵「紫外線」も6月は要注意
梅雨の時期は曇りや雨の日が多いため、紫外線のことを忘れがちです。しかし、6月の紫外線量はすでに真夏並みに強く、曇りの日でも晴天時の60%以上、雨の日でも30%程度の紫外線が降り注いでいます。
頭部は体の中で最も太陽に近い位置にあるため、紫外線の影響を直接受けやすい場所です。
6月から本格化する紫外線の量
気象庁のデータを見ても、紫外線(UV-B)は5月頃から急激に強くなり、6月には年間でもピークに近いレベルに達します。
梅雨の晴れ間に浴びる紫外線は特に強烈であり、短時間でも頭皮や毛髪は大きなダメージを受けてしまいます。
紫外線が毛髪に与えるダメージ
髪の毛自体も、紫外線によってダメージを受けます。髪の毛の主成分であるタンパク質(ケラチン)は、紫外線によって変性し、キューティクルが剥がれやすくなります。
その結果、髪の内部の水分が失われ、パサつき、枝毛、切れ毛といったトラブルが増加します。髪が弱ることは、将来的な抜け毛のリスクを高めることにもつながります。
紫外線による頭皮の日焼けと乾燥
頭皮も顔や腕と同じ皮膚であり、紫外線を浴びれば「日焼け」をします。日焼けした頭皮は、軽いやけどと同じ状態で、赤くなったり、ヒリヒリとした痛みを伴ったりします。
この炎症が治まる過程で、頭皮は乾燥し、バリア機能が低下します。
乾燥した頭皮は、外部からの刺激に敏感になり、かゆみやフケが発生しやすくなるだけでなく、毛根にもダメージが及び、ヘアサイクルが乱れて抜け毛が増える原因となります。
6月の抜け毛対策① 毎日のシャンプーを見直す
6月の過酷な頭皮環境を乗り切るためには、毎日の「シャンプー」が最も重要なケアとなります。
湿気や皮脂、汗、紫外線ダメージなどで汚れた頭皮を清潔に保ち、健やかな状態にリセットすることが抜け毛対策の基本です。
ただし、間違った方法では逆効果になるため、正しい知識を身につけましょう。
頭皮環境を整える正しい洗い方
シャンプーは髪の毛を洗うというよりも、「頭皮を洗う」ことを意識します。以下の手順で、頭皮の汚れを丁寧に、かつ優しく洗い流しましょう。
まず、シャンプーをつける前に、ぬるま湯(38℃程度)で頭皮と髪をしっかりと予洗いします。これだけで汗やホコリなどの汚れの多くは落ちると言われています。
次に、シャンプーを手のひらでよく泡立ててから、髪ではなく頭皮につけます。指の腹を使って、頭皮全体をマッサージするように優しく揉み洗いします。
爪を立ててゴシゴシ洗うのは、頭皮を傷つける原因になるため絶対にやめましょう。
皮脂は取りすぎてもダメ?洗浄成分の選び方
6月は頭皮がベタつきやすいため、洗浄力の強いシャンプーを選びがちです。
しかし、皮脂を必要以上に取り除いてしまうと、頭皮が乾燥し、それを補おうとしてかえって皮脂分泌が過剰になる「インナードライ」状態を招くことがあります。
自分の頭皮の状態に合った洗浄成分を選ぶことが大切です。
シャンプー選びのポイント
| シャンプーの種類 | 主な洗浄成分(例) | 特徴・おすすめの頭皮タイプ |
|---|---|---|
| 高級アルコール系 | ラウレス硫酸Naなど | 洗浄力が強く泡立ちが良い。脂性肌向けだが、乾燥肌は注意。 |
| アミノ酸系 | ココイルグルタミン酸Naなど | 洗浄力がマイルドで低刺激。保湿性も。乾燥肌・敏感肌向け。 |
| 石けん系 | 石ケン素地、脂肪酸Na | 洗浄力はやや強め。さっぱりした洗い上がり。 |
ベタつきが気になる場合でも、洗浄力がマイルドなアミノ酸系シャンプーで丁寧に洗うことを基本とし、週に1〜2回、頭皮クレンジング用のシャンプーを取り入れるなどの工夫も良いでしょう。
すすぎ残しは頭皮トラブルの元
シャンプーやコンディショナーの成分が頭皮に残っていると、それが毛穴詰まりや炎症、かゆみ、フケの原因となります。特に生え際や耳の後ろ、首筋などはすすぎ残しやすい部分です。
洗う時にかけた時間の「2倍」の時間を目安に、ぬるま湯で徹底的にすすぎましょう。頭皮にぬめり感がなくなるまで、しっかり洗い流すことが重要です。
髪を乾かすことの重要性
シャンプー後、髪が濡れたまま放置するのは絶対に避けましょう。濡れた頭皮は湿度が非常に高い状態であり、まさに雑菌が繁殖するための温床となります。
また、髪のキューティクルが開いたままになり、ダメージを受けやすくなります。シャンプー後は、まず清潔なタオルで頭皮の水分を優しく吸い取り、その後すぐにドライヤーで乾かします。
ドライヤーは頭皮から20cm以上離し、同じ場所に熱風が当たり続けないよう、小刻みに動かしながら全体を乾かしましょう。
8割程度乾いたら、冷風に切り替えて頭皮の熱を冷まし、キューティクルを引き締めると良いでしょう。
6月の抜け毛対策② 頭皮環境を内側から整える生活習慣
頭皮ケアは、シャンプーなどの外側からのアプローチだけでなく、体の中から環境を整えることも同じくらい重要です。
特に6月は、梅雨による気圧の変動や寝苦しさから、自律神経が乱れやすい時期でもあります。日々の生活習慣を見直し、健やかな髪を育む土台を作りましょう。
健やかな髪を育む睡眠
髪の毛は、私たちが寝ている間に分泌される「成長ホルモン」によって成長・修復されます。特に、入眠から最初の3時間(ノンレム睡眠中)に成長ホルモンの分泌が最も活発になると言われています。
睡眠不足が続いたり、睡眠の質が低下したりすると、この成長ホルモンの分泌が妨げられ、ヘアサイクルが乱れ、抜け毛や髪質の低下につながります。
6月は寝苦しい日も増えますが、寝室の温度や湿度をエアコンで調整し、毎日6〜7時間程度の質の良い睡眠を確保するよう心がけましょう。
食生活と頭皮の健康
髪の毛も皮膚も、私たちが食べたものから作られています。バランスの取れた食事は、健康な頭皮環境の維持に必要です。
特に、髪の主成分であるタンパク質、その合成を助ける亜鉛、頭皮の血行を良くするビタミンEなどを意識して摂取することが大切です。
頭皮と髪のための栄養素
| 栄養素 | 主な役割 | 多く含む食品(例) |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の毛の主成分(ケラチン) | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉、ナッツ類 |
| ビタミンB群 | 皮脂分泌のコントロール、代謝促進 | 豚肉、レバー、マグロ、納豆 |
| ビタミンA/C/E | 抗酸化作用、血行促進 | 緑黄色野菜、果物、ナッツ類 |
控えたい食習慣
一方で、脂っこい食事やインスタント食品、糖分の多いお菓子やジュースの摂りすぎは、皮脂の過剰分泌を招き、頭皮環境を悪化させる可能性があります。
また、過度なアルコール摂取や喫煙も、血行不良やビタミン不足を引き起こし、髪の成長を妨げるため、控えることが望ましいです。
6月は冷たい飲み物やさっぱりした麺類などに偏りがちですが、栄養バランスを意識しましょう。
ストレス管理とリフレッシュ法
精神的なストレスは、自律神経のバランスを崩し、血管を収縮させます。その影響で、頭皮への血流が悪化し、毛根に十分な栄養が届かなくなり、抜け毛の原因となると考えられています。
また、ストレスは皮脂の分泌を促進するホルモンにも影響を与えることがあります。梅雨のジメジメした気候は、それ自体がストレスの原因にもなり得ます。
自分なりのリフレッシュ法を見つけ、ストレスを溜め込まないことが大切です。
ストレス解消のヒント
- 趣味に没頭する時間を作る
- 湯船にゆっくり浸かる
- 軽いストレッチやヨガを行う
- 友人と話す
血行促進につながる適度な運動
適度な運動は、全身の血行を促進し、頭皮にも栄養素を届けやすくします。また、運動による心地よい疲労感は、睡眠の質を高める効果も期待できます。
激しい運動である必要はなく、ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動を週に数回、継続的に行うことが重要です。
雨で外に出られない日は、室内でのストレッチや筋力トレーニングでも構いません。体を動かすことで、ストレス解消にもつながります。
育毛剤や頭皮マッサージは有効か
セルフケアを続けても抜け毛が減らない、あるいはもっと積極的にケアしたい場合、育毛剤の使用や頭皮マッサージの導入も選択肢となります。
ただし、それぞれの役割を正しく理解して使うことが大切です。
育毛剤が持つ役割
育毛剤は、現在生えている髪の毛を健康に育て、抜け毛を予防することを主な目的としています。
医薬部外品に分類されるものが多く、含まれる有効成分によって、頭皮の血行促進、毛根への栄養補給、フケやかゆみの防止、皮脂分泌の抑制など、さまざまな角度から頭皮環境を整える働きが期待できます。
6月のベタつく頭皮に適した、さっぱりとした使用感のものを選ぶのも良いでしょう。
頭皮マッサージの目的と方法
頭皮マッサージは、硬くなった頭皮をほぐし、血行を促進することを目的として行います。血流が改善することで、毛根に必要な栄養や酸素が行き渡りやすくなります。
シャンプー時や、育毛剤を塗布した後に行うのが効果的です。指の腹を使い、頭皮全体を優しく掴むように動かしたり、下から上へ引き上げたりするようにマッサージします。
爪を立てたり、強く擦ったりしないよう注意が必要です。リラックス効果も高いため、ストレスケアの一環としても役立ちます。
セルフケアで改善が見られない場合
抜け毛の原因は、6月の環境要因だけでなく、男性型脱毛症(AGA)や他の皮膚疾患、あるいは内科的な問題が隠れている場合もあります。
正しいシャンプーや生活改善、育毛剤の使用を一定期間(少なくとも3ヶ月〜6ヶ月)続けても、抜け毛の量が明らかに減らない、あるいは薄毛が進行していると感じる場合は、自己判断で悩まずに、皮膚科や薄毛治療を専門とするクリニックに相談することを推奨します。
季節・ストレス・生活習慣に戻る
Q&A
- 6月を過ぎれば抜け毛は自然に減りますか?
-
6月特有の湿気や気温上昇が原因で一時的に抜け毛が増えている場合、梅雨が明けて夏本番となり、適切な頭皮ケアを続けることで、頭皮環境が安定し、抜け毛が落ち着く可能性はあります。
ただし、夏の強い紫外線や汗によるダメージも新たな抜け毛の原因となり得るため、継続的なケアが重要です。秋にも抜け毛が増えやすい時期があるため、油断は禁物です。
- 梅雨時期はシャンプーの回数を増やしても良いですか?
-
頭皮のベタつきが非常に気になる場合、1日に2回シャンプーをしたくなるかもしれませんが、基本的には1日1回、夜に丁寧に行うことを推奨します。
洗浄力の強いシャンプーで洗いすぎると、頭皮の必要な皮脂まで奪ってしまい、乾燥や皮脂の過剰分泌を招く恐れがあります。
日中のベタつきが気になる場合は、ぬるま湯で軽くすすぐ、または頭皮用の拭き取りシートなどを活用する方が、頭皮への負担が少ない場合があります。
- 頭皮のベタつきは体質だから改善しませんか?
-
皮脂の分泌量には個人差があり、体質的な要因も確かにあります。しかし、すべてが体質とは限りません。
6月のような高温多湿の環境要因、脂っこい食事中心の食生活、睡眠不足、ストレスなどが、皮脂分泌を過剰にしている可能性もあります。
シャンプー方法や生活習慣を見直すことで、ベタつきが軽減されるケースは多くあります。諦めずに、まずはできるケアから試してみることが大切です。
- 育毛剤はどれくらい続ければ変化を感じますか?
-
育毛剤は、頭皮環境を整え、今ある髪を健康に育てるためのものです。
髪の毛にはヘアサイクルがあるため、使い始めてすぐに抜け毛が劇的に減ったり、髪が太くなったりといった変化を感じることは稀です。
多くの場合、頭皮環境の改善や抜け毛の予防といった効果を実感するには、最低でも3ヶ月から6ヶ月程度の継続使用が必要と言われています。
焦らず、毎日のケアとして習慣づけることが重要です。もし使用中に頭皮にかゆみや赤みなどが出た場合は、使用を中止し専門医に相談してください。
Reference
RAJKUMAR, Shruthi Sukumarapillai. Seasonal Variation in the Incidence of Skin Diseases. 2024. Master’s Thesis. Lithuanian University of Health Sciences (Lithuania).
ANASTASSAKIS, Konstantinos. The role of solar radiation in AGA/FPHL. In: Androgenetic Alopecia From A to Z: Vol. 1 Basic Science, Diagnosis, Etiology, and Related Disorders. Cham: Springer International Publishing, 2022. p. 263-271.
PASSERON, Thierry, et al. Clinical and biological impact of the exposome on the skin. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2020, 34: 4-25.
TRÜEB, Ralph M. Is androgenetic alopecia a photoaggravated dermatosis?. Dermatology, 2003, 207.4: 343-348.
CEDIRIAN, Stephano, et al. The exposome impact on hair health: etiology, pathogenesis and clinical features‒Part I. Anais Brasileiros de Dermatologia, 2025, 100.1: 131-140.
TRÜEB, Ralph M., et al. The Hair and Scalp in Systemic Infectious Disease. In: Hair in Infectious Disease: Recognition, Treatment, and Prevention. Cham: Springer International Publishing, 2023. p. 303-365.
PIÉRARD-FRANCHIMONT, Claudine; QUATRESOOZ, Pascale; PIÉRARD, Gérald E. Effect of UV radiation on scalp and hair growth. In: Aging hair. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010. p. 113-121.
PIÉRARD-FRANCHIMONT, C., et al. Androgenic alopecia and stress-induced premature senescence by cumulative ultraviolet light exposure. Exogenous Dermatology, 2002, 1.4: 203-206.
GERASYMCHUK, Marta, et al. Sex-Dependent Skin Aging and Rejuvenation Strategies. Dermato, 2023, 3.3: 196-223.
SAMRA, Tara; LIN, Rachel R.; MADERAL, Andrea D. The effects of environmental pollutants and exposures on hair follicle pathophysiology. Skin Appendage Disorders, 2024, 10.4: 262-272.