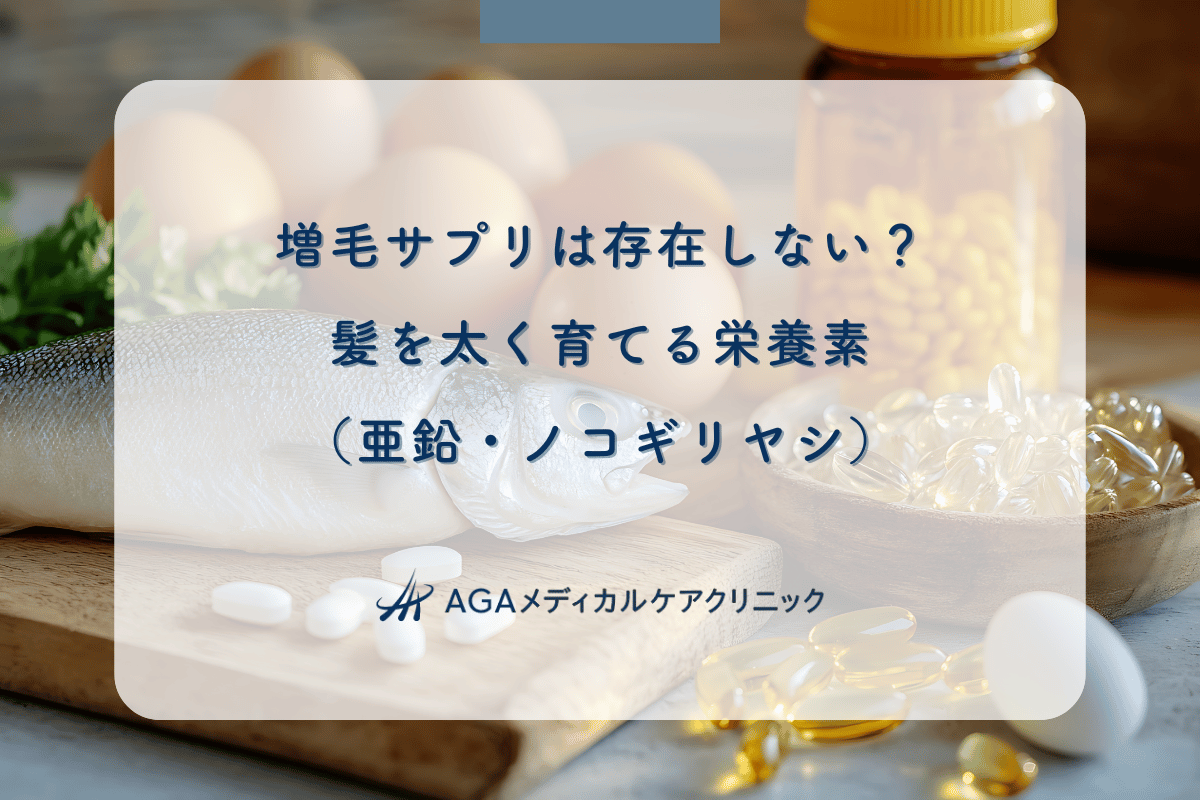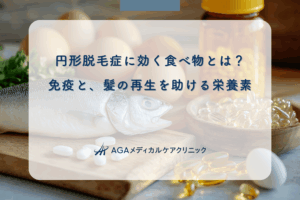「飲むだけで髪が増える」そんな魔法のような「増毛サプリ」を探していませんか。
鏡を見るたびに感じる不安や、シャンプーのたびに気づく変化に、手軽な対策を求めてしまうお気持ちは、とてもよくわかります。ですが、本当にサプリメントで髪を「増やす」ことは可能なのでしょうか。
この記事では、まず「増毛サプリ」という言葉の真実について切り込みます。
そして、髪が「増える」のではなく、今ある髪を「太く」「健やかに育てる」ために本当に大切な栄養素、特に注目される亜鉛やノコギリヤシの働きについて、詳しく解説していきます。
この記事を読み終える頃には、サプリメントと正しく向き合い、ご自身のヘアケアに必要な知識が身についているはずです。
遠回りに見えるかもしれませんが、髪のために、まずは正しい知識から始めましょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
「増毛サプリ」は存在するのか?その真実
結論から申し上げますと、髪を「増毛」させる(=髪の毛の本数を増やす)ことを医学的に証明されたサプリメントは、現在のところ存在しません。
サプリメントは、あくまでも「栄養補助食品」であり、医薬品とは明確に異なるものです。
髪の成長に必要な栄養素を補うことはできますが、それ自体が発毛を促したり、髪を増やしたりするわけではありません。
サプリメントは「栄養補助食品」という位置づけ
私たちが日常で目にする「サプリメント」は、法律上「食品」に分類されます。
特定の栄養成分が濃縮された錠剤やカプセル状のものを指しますが、その目的は日々の食事で不足しがちな栄養素を補うことです。
病気の治療や予防を目的とした「医薬品」とは根本的に異なります。そのため、「髪が生える」「増毛する」といった医薬品的な効果を謳うことは認められていません。
もしそのような表現を見かけた場合、それは誇大な広告である可能性が高いと考えましょう。
育毛剤や発毛剤との根本的な違い
髪へのアプローチとして、サプリメントの他に「育毛剤」や「発毛剤」があります。これらはサプリメントと混同されがちですが、役割が全く異なります。
「発毛剤」は、医薬品(第一類医薬品など)に分類されます。代表的な成分であるミノキシジルなど、毛母細胞の働きを活性化させ、新しい髪を生み出す(発毛)効果が認められています。
これは医師や薬剤師の管理のもとで使用するものです。
一方、「育毛剤」は医薬部外品に分類されるものが多く、主な目的は「今ある髪を育てる」ことです。頭皮の血行を促進したり、頭皮環境を清潔に保ったりすることで、抜け毛を防ぎ、髪の成長をサポートします。
サプリメントは、これらとは異なり、体の「内側」から髪の材料となる栄養を補給する役割を担います。
発毛剤・育毛剤・サプリメントの役割の違い
| 分類 | 主な目的 | アプローチ |
|---|---|---|
| 発毛剤(医薬品) | 新しい髪を生やす(発毛) | 毛母細胞の活性化など |
| 育毛剤(医薬部外品) | 今ある髪を育て、抜け毛を防ぐ(育毛) | 頭皮環境改善、血行促進 |
| サプリメント(食品) | 栄養素の補給 | 体の中から栄養をサポート |
なぜ「増毛サプリ」という言葉が広まったのか
では、なぜ「増毛サプリ」という言葉をよく耳にするのでしょうか。これは、髪の悩みが深いほど、手軽に解決したいという消費者の心理が働くためと考えられます。
また、一部の製品が「髪に良い」とされる成分を含んでいることから、そのイメージが先行し、「増毛」という期待感と結びついて広まった側面もあります。
しかし、前述の通り、栄養補給が髪の成長環境をサポートすることはあっても、直接的に「増毛」に繋がるわけではない、という事実は理解しておく必要があります。
髪が育つ仕組みと栄養素の役割
髪の健康を考える上で、サプリメント(栄養素)がどのような役割を果たすのかを理解することは重要です。髪は、体の一部であり、その成長には多くの栄養素が必要です。
栄養素は、髪の「材料」となったり、髪が育ちやすい「環境」を整えたりするために使われます。
髪の主成分はケラチン(タンパク質)
髪の毛の約90%は、「ケラチン」というタンパク質で構成されています。ケラチンは18種類のアミノ酸が結合してできており、このケラチンが作られなければ、髪は成長できません。
つまり、日々の食事から十分なタンパク質(アミノ酸)を摂取することが、健やかな髪を育てるための大前提となります。いくら頭皮ケアを頑張っても、肝心の材料が不足していては、元気な髪は育ちにくいのです。
ヘアサイクル(成長期・退行期・休止期)とは
髪は、一定の周期(ヘアサイクル)に従って、生えたり抜けたりを繰り返しています。このサイクルは大きく3つの期間に分けられます。
- 成長期(2年〜6年):髪が活発に成長する期間。全体の約85%〜90%がこの状態です。
- 退行期(約2週間):髪の成長が止まり、毛根が縮小していく期間。
- 休止期(約3ヶ月〜4ヶ月):髪が抜け落ちるのを待つ期間。この後、再び新しい髪が成長期に入ります。
薄毛や抜け毛の悩みは、このヘアサイクルが乱れ、髪が十分に太く長く育つ前(成長期)に、早く抜けてしまう(退行期・休止期)ことで起こるケースが多くあります。
栄養不足が引き起こす髪への影響
栄養不足は、このヘアサイクルに直接的な影響を与えます。例えば、過度なダイエットや偏った食生活でタンパク質やビタミン、ミネラルが不足すると、体は生命維持に重要な臓器へ優先的に栄養を送ります。
その結果、髪の毛(毛母細胞)への栄養供給は後回しにされがちです。
栄養が届かなければ、毛母細胞の活動は低下し、髪の成長期が短くなったり、新しく生えてくる髪が細く弱々しくなったりする可能性があります。
栄養素は「髪の材料」であり「育つ環境」を整えるもの
サプリメントで補う栄養素の役割は、大きく分けて2つあります。
1つ目は、先述のケラチン(タンパク質)のように、髪そのものを作る「材料」となることです。
2つ目は、髪が育つための「環境」を整えることです。例えば、頭皮の血流を良くしたり、毛母細胞の分裂をサポートしたりする栄養素がこれにあたります。
サプリメントは、これら食事だけでは不足しがちな栄養素を効率よく補い、髪が健やかに育つ土台作りを助けるものと理解しましょう。
髪を太く育てるために注目したい栄養素「亜鉛」
髪の成長をサポートする栄養素の中でも、特に「亜鉛」は重要なミネラルの一つです。亜鉛は、髪の主成分であるケラチンの合成に深く関わっており、不足すると髪の健康に影響が出やすいと考えられています。
亜鉛が髪の成長に必要な理由
亜鉛の主な働きは、タンパク質の合成を助けることです。食事から摂取したタンパク質(アミノ酸)を、髪の毛のケラチンへと再合成する作業に、亜鉛は欠かせません。
また、亜鉛は細胞分裂を正常に行うためにも必要です。髪の毛は毛母細胞が分裂を繰り返すことで成長していくため、亜鉛が不足すると、この細胞分裂が滞り、髪の成長が妨げられる可能性があります。
さらに、亜鉛はヘアサイクルを正常に保つためにも役立つとされています。
亜鉛不足のサインと食生活
亜鉛は体内で作ることができず、汗や尿と共に排出されやすいため、不足しやすいミネラルの一つです。
特に、加工食品やインスタント食品に偏った食生活を送っている人、お酒をよく飲む人、過度なダイエットをしている人は亜鉛が不足しやすい傾向にあります。
亜鉛が不足すると、髪の毛が細くなったり、抜け毛が増えたりするだけでなく、味覚障害、皮膚炎、免疫力の低下など、体の様々な部分に不調が現れることがあります。
亜鉛を多く含む食品
亜鉛は、日々の食事から意識的に摂取することが大切です。特に魚介類や肉類に多く含まれています。
亜鉛を豊富に含む主な食品例
| 食品カテゴリー | 主な食品 | 特徴 |
|---|---|---|
| 魚介類 | 牡蠣(かき)、うなぎ、たらこ | 牡蠣は特に含有量が多い |
| 肉類 | 牛肉(特に赤身)、レバー(豚・鶏) | 動物性タンパク質と共に摂れる |
| その他 | チーズ、卵黄、納豆、ごま | 日常的に取り入れやすい |
サプリで亜鉛を補う際の注意点
食事だけで十分な亜鉛を摂取するのが難しい場合、サプリメントで補うのも一つの方法です。しかし、亜鉛は摂取量が多すぎても問題(過剰摂取)を引き起こす可能性があります。
亜鉛を過剰に摂取すると、銅や鉄といった他の重要なミネラルの吸収を妨げてしまうことがあります。その結果、貧血や免疫機能の低下などを招く恐れがあります。
厚生労働省が定める成⼈男性の耐容上限量(1日あたり40mg〜45mg程度)を超えないよう、サプリメントのパッケージに記載されている摂取目安量を守ることが重要です。
もう一つの注目成分「ノコギリヤシ」とは
亜鉛と並んで、男性のヘアケア関連のサプリメントでよく目にする成分が「ノコギリヤシ(ソーパルメット)」です。これは北米に自生するヤシ科の植物で、その果実から抽出したエキスが利用されます。
ノコギリヤシに期待される働き
ノコギリヤシは、古くから北米の先住民によって、男性の健康維持、特に泌尿器系の悩み(前立腺肥大など)のために利用されてきました。
近年、このノコギリヤシが男性の薄毛、特にAGA(男性型脱毛症)に対しても何らかの働きかけをするのではないかと注目を集めています。
ただし、その働きについては、まだ研究途上の部分も多く、医薬品のような明確な発毛効果が認められているわけではありません。あくまでも、健康維持をサポートする食品成分として捉える必要があります。
5αリダクターゼへのアプローチとは
ノコギリヤシが注目される背景には、AGAの主な原因とされる「5αリダクターゼ」という酵素への関与が示唆されている点があります。
AGAは、男性ホルモンの一種である「テストステロン」が、この5αリダクターゼによって、より強力な「ジヒドロテストステロン(DHT)」に変換されることで進行します。
DHTが毛乳頭細胞にある受容体と結びつくと、髪の成長期が短くなり、髪が細く、短くなる「軟毛化」が進んでしまいます。
ノコギリヤシエキスに含まれる成分(β-シトステロールなど)が、この5αリダクターゼの働きを阻害するのではないか、という研究報告があり、DHTの生成を抑える可能性が期待されています。
ノコギリヤシはAGA(男性型脱毛症)にどう関わるか
ノコギリヤシが5αリダクターゼの働きを抑制する可能性があるとはいえ、それがAGAの「治療」に直結するわけではありません。
AGA治療薬として承認されているフィナステリドやデュタステリドも同様の作用(5αリダクターゼ阻害)を持ちますが、ノコギリヤシは医薬品ではなく食品成分です。
その働きは医薬品に比べて穏やかであると考えられる一方、体質によっては体に合わない場合もあります。
AGAの進行が気になる場合は、自己判断でサプリメントに頼るのではなく、まずは専門のクリニックで医師の診断を受けることが賢明です。
亜鉛とノコギリヤシの主な働き(比較)
| 成分 | 分類 | 期待される主な働き |
|---|---|---|
| 亜鉛 | ミネラル(必須栄養素) | ケラチン(タンパク質)の合成サポート、細胞分裂の正常化 |
| ノコギリヤシ | 植物エキス(食品成分) | 5αリダクターゼの働きを阻害する可能性(研究段階) |
亜鉛・ノコギリヤシ以外の重要な栄養素
髪を太く育てるためには、亜鉛やノコギリヤシだけを摂取していれば良いというわけではありません。様々な栄養素が互いに連携しあって、初めて髪の健康は維持されます。
バランスの取れた栄養補給が大切です。
タンパク質(すべての基本)
繰り返しになりますが、髪の主成分はケラチンというタンパク質です。タンパク質が不足すれば、髪の材料そのものが足りない状態になります。
肉、魚、卵、大豆製品など、良質なタンパク質を毎日の食事でしっかり摂ることが基本中の基本です。
特に、ケラチンの生成に重要な役割を持つアミノ酸(メチオニン、シスチンなど)も意識するとよいでしょう。
ビタミンB群(代謝をサポート)
ビタミンB群は、私たちが摂取した栄養素(タンパク質、脂質、炭水化物)をエネルギーに変える「代謝」に欠かせない栄養素です。
特にビタミンB2やB6は、タンパク質の代謝や頭皮の皮脂バランスを整える働きに関与します。ビタミンB7(ビオチン)も、皮膚や髪の健康維持を助けるビタミンとして知られています。
これらが不足すると、頭皮環境の悪化や、髪の成長がスムーズに進まない原因にもなり得ます。
ビタミンE(血流サポート)
ビタミンEは「若返りのビタミン」とも呼ばれ、強い抗酸化作用を持つことが特徴です。体のサビつき(酸化)を防ぐほか、末梢血管を広げて血流を良くする働きがあります。
頭皮の毛細血管の血流が良くなれば、毛母細胞に酸素や栄養素が届きやすくなります。その結果、髪が健やかに育つための環境が整います。
アーモンドなどのナッツ類や、植物油、アボカドなどに多く含まれます。
髪の成長を支える主な栄養素まとめ
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| ビタミンB群 | 栄養素の代謝、頭皮環境の維持 | レバー、豚肉、マグロ、納豆 |
| ビタミンE | 血行促進、抗酸化作用 | ナッツ類、植物油、アボカド |
サプリメントの選び方と正しい向き合い方
市場には数多くのヘアケア関連サプリメントが出回っており、どれを選べばよいか迷うかもしれません。
「増毛サプリ」という言葉に惑わされず、ご自身の目的(=栄養補給)に合った製品を冷静に選ぶ視点が重要です。
「増毛」ではなく「栄養補給」目的で選ぶ
まず大前提として、「増毛」や「発毛」を謳う製品は避けましょう。サプリメントは医薬品ではありません。目的はあくまで「髪の成長に必要な栄養素を補うこと」です。
ご自身の食生活を振り返り、不足していると感じる栄養素(例えば、魚をあまり食べないからビタミンB群が不足しているかも、など)を補えるような成分が含まれているかを確認しましょう。
成分表示(含有量)を確認する
サプリメントを選ぶ際は、パッケージの裏にある「栄養成分表示」を必ず確認しましょう。亜鉛やビタミンなど、目的の成分がどれだけ含まれているか(含有量)をチェックします。
単に「ノコギリヤシ配合」と書かれているだけでなく、1日あたりの摂取目安量で、どの成分が何mg摂れるのかが明記されている製品を選びましょう。
含有量が極端に少ない製品は、期待する栄養補給ができない可能性があります。
サプリメント選びの確認ポイント
| 確認項目 | チェックする理由 | 具体例 |
|---|---|---|
| 成分と含有量 | 必要な栄養素が十分入っているか | 亜鉛10mg/日、ノコギリヤシエキス320mg/日など |
| 添加物 | 不要な添加物が少なく、シンプルな処方か | 着色料、香料、保存料など |
| 製造・品質管理 | 安全に製造されているか | 国内製造、GMP認定工場など |
国内製造やGMP認定マークなども参考に
毎日口にするものだからこそ、安全性も考慮したいポイントです。必須ではありませんが、一つの目安として「国内製造」であるか、あるいは「GMP認定工場」で製造されているかを確認するのもよいでしょう。
GMP(GoodManufacturingPractice)とは、原材料の受け入れから製造、出荷までの全工程において、製品が「安全」に作られ、「一定の品質」が保たれるようにするための製造工程管理基準です。
この認定を受けている工場は、品質管理の体制が整っていると判断できます。
サプリはあくまで「補助」食事バランスが基本
最も大切なことは、サプリメントに頼りすぎないことです。サプリは魔法の薬ではなく、あくまで食事の「補助」です。
私たちの体は、特定の栄養素だけを大量に摂取するよりも、多様な食品からバランスよく栄養を摂ることで、その機能を最もよく発揮します。
まずは日々の食事を見直し、その上で不足分をサプリで補う、という順番を間違えないようにしましょう。
サプリだけに頼らない髪のための生活習慣
髪の健康は、栄養素だけで決まるものではありません。日々の生活習慣全体が、頭皮環境や髪の成長に大きく影響します。
サプリメントによる栄養補給と並行して、生活全体を見直すことが、健やかな髪を育てる近道です。
バランスの取れた食事が最も重要
サプリメントの項目でも触れましたが、基本は「食事」です。特定の食品ばかりを食べるのではなく、「主食・主菜・副菜」を揃えることを意識しましょう。
髪の材料となるタンパク質(主菜)、エネルギー源となる炭水化物(主食)、そして体の調子を整えるビタミン・ミネラル(副菜)をバランスよく摂ることが、髪だけでなく体全体の健康維持に繋がります。
栄養バランスを意識した食事メニュー例
| 食事 | 主食(炭水化物) | 主菜(タンパク質) | 副菜(ビタミン・ミネラル) |
|---|---|---|---|
| 朝食 | ごはん | 納豆、焼き鮭、卵焼き | わかめの味噌汁、ほうれん草のおひたし |
| 昼食 | 玄米(またはそば) | 豚肉の生姜焼き | キャベツの千切り、キノコのソテー |
| 夕食 | (軽めに) | 鶏むね肉の蒸し物、豆腐 | 温野菜サラダ(ブロッコリー、人参など) |
質の高い睡眠の確保
髪は、私たちが寝ている間に成長します。睡眠中には「成長ホルモン」が分泌され、このホルモンが毛母細胞の分裂を促し、髪の成長やダメージの修復を行います。
特に、入眠から最初の3時間は「ゴールデンタイム」とも呼ばれ、成長ホルモンの分泌が最も活発になります。夜更かしを避け、毎日決まった時間に、深く質の高い睡眠をとるよう心がけましょう。
寝る前のスマートフォン操作は、睡眠の質を下げるため控えるのが賢明です。
ストレス管理と適度な運動
強いストレスは、自律神経のバランスを崩し、血管を収縮させる原因となります。頭皮の血管が収縮すると血流が悪化し、毛母細胞に十分な栄養が届かなくなってしまいます。
これが抜け毛や髪の成長不良に繋がることがあります。
自分なりのストレス解消法を見つけることが大切です。また、ウォーキングやジョギングなどの適度な運動は、全身の血流を良くするだけでなく、気分転換にもなり、ストレス軽減に役立ちます。
ストレスサインの例
- 寝つきが悪い、または眠りが浅い
- イライラしやすくなった
- 食欲がない、または食べ過ぎてしまう
- 何事にもやる気が出ない
これらのサインに気づいたら、意識的にリラックスする時間を作りましょう。
頭皮環境を整える正しいヘアケア
髪が育つ土壌である「頭皮」の環境を整えることも重要です。皮脂や汚れが毛穴に詰まると、炎症を起こしたり、髪の健やかな成長を妨げたりすることがあります。
ただし、洗いすぎは禁物です。皮脂を落としすぎると、頭皮が乾燥し、かえって皮脂の過剰分泌を招くこともあります。
ご自身の頭皮タイプ(乾燥肌、脂性肌など)に合ったシャンプーを選び、優しくマッサージするように洗い、すすぎ残しがないよう十分注意しましょう。
サプリメントに戻る
Q&A
- サプリを飲めばすぐに髪は太くなりますか?
-
いいえ、すぐには変わりません。サプリメントは食品であり、栄養状態が改善されてから、それが髪の成長に反映されるまでには時間がかかります。
髪は1ヶ月に約1cmしか伸びません。ヘアサイクルを考慮すると、何らかの変化を感じるとしても、最低でも3ヶ月から6ヶ月は継続して様子を見る必要があります。
- どのくらいの期間飲み続ければよいですか?
-
サプリメントは薬ではないため、「いつまで」という明確な期間はありません。基本的には、ご自身の食生活で不足しがちな栄養を補うためのものです。
まずは数ヶ月単位で継続し、体調や髪の状態を見ながら、続けるかどうかを判断するとよいでしょう。それ以上に、バランスの取れた食事や生活習慣を継続することの方が重要です。
- サプリの副作用が心配です
-
サプリメントは食品ですので、基本的に重い副作用の心配は少ないとされています。
しかし、体質に合わない(アレルギーなど)場合や、特定の成分(特に亜鉛などのミネラル)を過剰摂取した場合は、胃腸の不快感や、他の栄養素の吸収阻害などを引き起こす可能性があります。
必ず1日の摂取目安量を守り、複数のサプリを併用する場合は成分の重複に注意してください。不安な場合は医師や薬剤師に相談しましょう。
- 育毛剤とサプリは併用してもよいですか?
-
はい、併用しても問題ない場合がほとんどです。育毛剤は頭皮(外側)から、サプリメントは栄養補給(内側)からと、アプローチする場所が異なるためです。
ただし、発毛剤(医薬品)を使用している場合は、念のため医師に相談してからサプリメントを併用することをおすすめします。
- 食事だけで必要な栄養素を摂るのは難しいですか?
-
バランスの取れた食事を毎日3食続けることができれば、食事だけで必要な栄養素の多くを摂ることは可能です。
しかし、現代の食生活では、外食や加工食品が多くなりがちで、特定の栄養素(特にビタミンやミネラル)が不足しやすくなっているのも事実です。
サプリメントは、その「不足分」を補うための便利な手段として活用しましょう。
Reference
RAJPUT, Rajendrasingh. A scientific hypothesis on the role of nutritional supplements for effective management of hair loss and promoting hair regrowth. J Nutrition Health Food Sci, 2018, 6.3: 1-11.
WANG, Ruilong, et al. Micronutrients and Androgenetic Alopecia: A Systematic Review. Molecular Nutrition & Food Research, 2024, 68.22: 2400652.
FAMENINI, Shannon; GOH, Carolyn. Evidence for supplemental treatments in androgenetic alopecia. J Drugs Dermatol, 2014, 13.7: 809-812.
DRAKE, Lara, et al. Evaluation of the safety and effectiveness of nutritional supplements for treating hair loss: a systematic review. JAMA dermatology, 2023, 159.1: 79-86.
KONDRAKHINA, Irina N., et al. Plasma zinc levels in males with androgenetic alopecia as possible predictors of the subsequent conservative therapy’s effectiveness. Diagnostics, 2020, 10.5: 336.
GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.
RAJENDRASINGH, J. R. Role of non-androgenic factors in hair loss and hair regrowth. J Cosmo Trichol, 2017, 3.2: 118.
SIAVASH, Mansour; TAVAKOLI, Fereshteh; MOKHTARI, Fatemeh. Comparing the effects of zinc sulfate, calcium pantothenate, their combination and minoxidil solution regimens on controlling hair loss in women: a randomized controlled trial. Journal of Research in Pharmacy Practice, 2017, 6.2: 89-93.
KLEIN, Elizabeth J., et al. Supplementation and hair growth: a retrospective chart review of patients with alopecia and laboratory abnormalities. JAAD international, 2022, 9: 69-71.
ALMOHANNA, Hind M., et al. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 51-70.