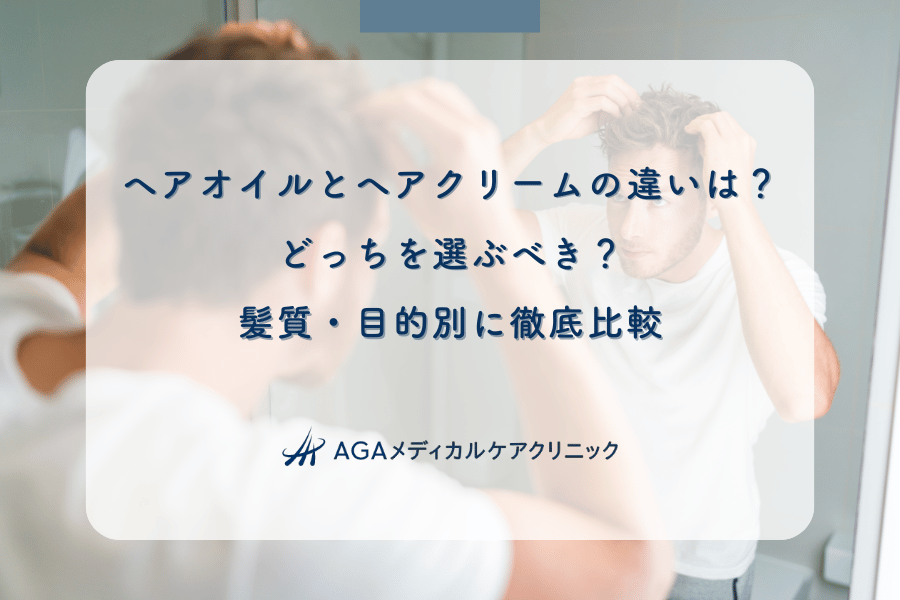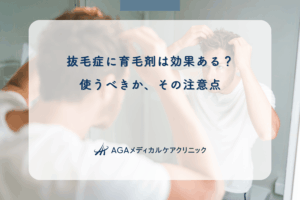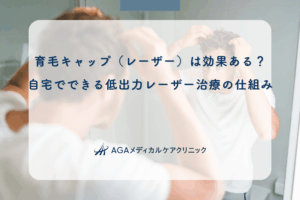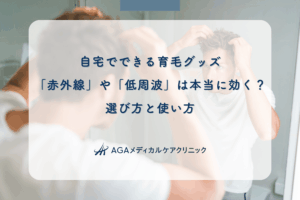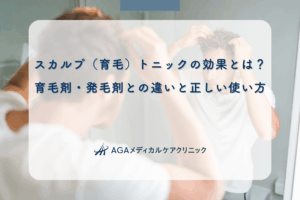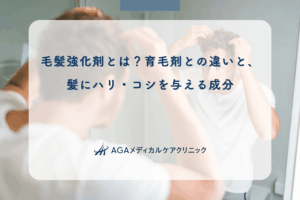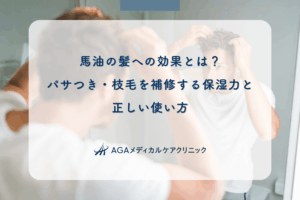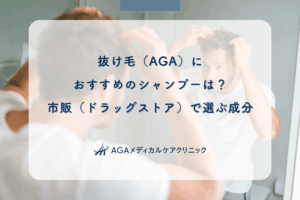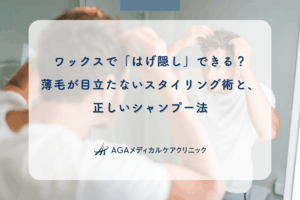ヘアオイルとヘアクリーム、どちらを使えばいいか悩んでいませんか?「髪が広がるからオイル?」「パサつくからクリーム?」と、なんとなく選んでいる方も多いかもしれません。
ですが、髪質や目指す仕上がりによって、適したアイテムは異なります。
この記事では、ヘアオイルとヘアクリームの根本的な違いから、髪質別・目的別の選び方、さらには効果的な使い方までを徹底的に比較・解説します。
あなたに本当に合ったヘアケアアイテムを見つけ、日々のスタイリングやヘアケアを格上げしましょう。正しい選択が、自信の持てる健やかな髪への第一歩です。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
ヘアオイルとヘアクリームの基本的な違い
ヘアオイルとヘアクリームの最も大きな違いは、その主成分とテクスチャ、そして髪へ働きかける主な効果です。ヘアオイルは油分が主体で、髪の表面をコーティングすることに優れています。
一方、ヘアクリームは水分と油分がバランスよく含まれており、髪内部への浸透力が高く、保湿や補修を得意とします。
主成分とテクスチャの違い
ヘアオイルは、その名の通り「油」が主成分です。アルガンオイルやホホバオイルなどの植物性オイル、またはミネラルオイル(鉱物油)などがベースになっています。
テクスチャはサラサラとした軽いものから、重めでとろみのあるものまで様々ですが、基本的には油特有の質感です。
対してヘアクリームは、「水分」と「油分」が乳化技術によってクリーム状になっている製品です。水分を含むため、オイルよりもみずみずしく、軽いテクスチャのものが多く見られます。
油分だけでなく、保湿成分や補修成分も配合しやすいのが特徴です。
髪への主な効果
ヘアオイルの主な効果は「コーティング」です。髪1本1本の表面を油膜で覆うことにより、キューティクルを保護し、髪内部の水分蒸発を防ぎます。
また、光を反射しやすくするため、美しいツヤが出るのも大きな特徴です。ドライヤーの熱や紫外線、摩擦といった外部からのダメージを防ぐ役割も期待できます。
ヘアクリームの主な効果は「保湿」と「補修」です。水分と油分、さらにケラチンやセラミドなどの補修成分を髪の内部に届けやすいのが強みです。
髪のパサつきを抑え、内側からうるおいを与えてしっとりとまとまりやすい状態に導きます。オイルほどの強いツヤは出にくいですが、自然な仕上がりになります。
ヘアオイルとヘアクリームの基本比較
| 項目 | ヘアオイル | ヘアクリーム |
|---|---|---|
| 主成分 | 油分(植物性・鉱物性) | 水分+油分 |
| 主な効果 | コーティング・ツヤ出し・保護 | 保湿・補修・まとまり |
| テクスチャ | サラサラ〜重め(油状) | みずみずしい(クリーム状) |
向いている髪質と悩み(概要)
ヘアオイルは、コーティング力が高いため、髪が太い方、毛量が多い方、そして髪の広がりやうねりを抑えたい方に向いています。
また、髪にツヤが欲しい、指通りを良くしたいという悩みにも応えてくれます。
ヘアクリームは、保湿力と補修力に優れるため、髪が細い方、猫っ毛の方、そしてダメージによるパサつきや乾燥が気になる方におすすめです。
重くなりにくく、自然なボリューム感を保ちながらケアできます。
ヘアオイルの特徴とメリット・デメリット
ヘアオイルは、植物性または鉱物性の油を主成分とし、髪の表面を強力にコーティングすることで、髪にツヤを与え、外部の刺激から守るスタイリング剤・ヘアケア剤です。
特に乾燥や熱から髪を保護する能力に優れています。
ヘアオイルの主な効果とメリット
ヘアオイル最大のメリットは、その「ツヤ出し効果」と「保護能力」です。髪表面を均一にコーティングするため、光が当たることで輝くようなツヤ髪を演出できます。
特に、濡れ感のあるスタイリングや、髪をサラサラに見せたい場合に活躍します。
また、油膜がドライヤーやヘアアイロンの熱、紫外線、乾燥した外気などから髪を守ります。キューティクルが整うことで、指通りが滑らかになり、髪のまとまりも良くなります。
湿気による髪の広がりを抑える効果も期待できるため、雨の日のスタイリングにも役立ちます。
ヘアオイルのデメリットと注意点
ヘアオイルのデメリットは、量の調節が難しい点です。特に髪が細い方や毛量が少ない方がつけすぎると、髪が油っぽく見えたり、ボリュームダウンしてしまったりする原因になります。
ベタつきやすいという側面もあるため、自分の髪質に合ったテクスチャ(重め・軽め)を選ぶ必要があります。
また、頭皮に直接つけると毛穴を詰まらせる可能性があるため、基本的には毛先を中心に使用します。
補修成分よりもコーティング成分がメインの製品が多いため、髪の内部補修を第一に考える場合は、成分の確認が重要です。
ヘアオイルがおすすめな人
以下のような髪質や悩みを持つ人には、ヘアオイルが特におすすめです。
- 髪にツヤと輝きが欲しい人
- 髪が広がりやすく、うねりを抑えたい人
- ドライヤーやヘアアイロンを頻繁に使う人
- 指通りを良くし、サラサラの質感を目指す人
髪が太く、毛量が多い方でも、重めのオイルを使えばしっかりとまとまりを出すことができます。逆に、髪が細い方は、サラッとした軽いテクスチャのオイルを少量から試すのが良いでしょう。
ヘアクリームの特徴とメリット・デメリット
ヘアクリームは、水分と油分がバランスよく配合されたヘアケア剤で、髪内部に浸透して水分や栄養を補給する能力に優れています。髪をしっとりとまとめ、パサつきを抑える効果が期待できます。
ヘアクリームの主な効果とメリット
ヘアクリームの最大のメリットは、その高い「保湿力」と「補修効果」です。水分と油分を同時に髪に供給できるため、乾燥してパサついた髪にうるおいを与えます。
セラミドやケラチンといった補修成分を含んでいる製品も多く、ダメージケアにも適しています。
また、オイルに比べてテクスチャが軽く、髪に馴染ませやすいのも特徴です。つけすぎてもベタつきにくく、自然なまとまり感と柔らかい質感に仕上がります。
パーマのカールを出すスタイリングや、自然な毛流れを作りたい場合にも使いやすいアイテムです。
ヘアクリームのデメリットと注意点
ヘアクリームのデメリットとしては、ヘアオイルほどの強いツヤが出にくい点が挙げられます。あくまでも自然なツヤ感であり、光り輝くような仕上がりを求める場合には物足りなさを感じるかもしれません。
また、製品によってはセット力がほとんどないものもあります。スタイリング剤としてのキープ力を求める場合は、ワックスなどが配合されたタイプを選ぶ必要があります。
水分を多く含むため、湿気が多い日にはオイルに比べて広がりを抑える力が弱い場合もあります。
ヘアクリームがおすすめな人
以下のような髪質や悩みを持つ人には、ヘアクリームが特におすすめです。
- 髪のパサつきや乾燥が気になる人
- ダメージヘアの補修・ケアをしたい人
- 自然なまとまりと柔らかい質感が欲しい人
- 髪が細く、オイルだと重くなりすぎる人
特に軟毛・猫っ毛の方は、ボリュームを失わずに保湿ケアができるヘアクリームが重宝します。
【髪質別】ヘアオイルとヘアクリームの選び方
自分の髪質を正しく理解し、それに合わせてヘアオイルかヘアクリームかを選ぶことが、理想の髪の状態に近づくための重要なポイントです。髪質によって適したアイテムは異なります。
剛毛・くせ毛・多毛の人
髪が太く、量が多く、広がりやすい剛毛・くせ毛・多毛タイプの方には、髪をしっかりとコーティングし、ボリュームを抑えてくれる「重めのヘアオイル」がおすすめです。
油分の力で髪の水分バランスを整え、湿気による広がりも防ぎます。
ただし、髪の内部が乾燥している(剛毛でパサつく)場合は、まず「ヘアクリーム」で内部に水分を補給してから、仕上げに少量のオイルで蓋をするという使い方も有効です。
軟毛・猫っ毛・細毛の人
髪が細く、柔らかく、ボリュームが出にくい軟毛・猫っ毛タイプの方には、「ヘアクリーム」がおすすめです。保湿しながらも重くなりすぎず、自然なふんわり感を保ちやすいからです。
もしオイルを使いたい場合は、ベタつきの少ない「軽いテクスチャのヘアオイル」を選びましょう。毛先だけに少量をつけることで、パサつきを抑えつつボリュームダウンを防げます。
ダメージ毛・乾燥毛の人
カラーやパーマ、日々の熱ダメージなどで髪が傷んでいるダメージ毛や、元々乾燥しやすい髪質の方には、「補修成分入りのヘアクリーム」が第一選択となります。髪の内部に水分と栄養を届け、内側からケアすることが重要です。
ドライヤー前には必ずクリームで保湿・補修をし、乾かした後に毛先のまとまりやツヤが足りない場合に「ヘアオイル」を少量追加するのが良いでしょう。
髪質別おすすめ早見表
| 髪質 | おすすめの選択 | 理由 |
|---|---|---|
| 剛毛・多毛・くせ毛 | 重めのヘアオイル | 広がりを抑え、ツヤとまとまりを与えるため。 |
| 軟毛・細毛・猫っ毛 | ヘアクリーム | 重くならずに保湿し、自然なボリュームを保つため。 |
| ダメージ毛・乾燥毛 | 補修系ヘアクリーム | 内部に水分と栄養を補給し、補修するため。 |
【目的別】ヘアオイルとヘアクリームの選び方
髪をどのように仕上げたいか、どのような悩みを解決したいかという「目的」によっても、ヘアオイルとヘアクリームの選び方は変わります。
自分のなりたいスタイルやケアの優先順位を明確にしましょう。
濡れ感・ツヤ感を出したい場合
トレンドの「濡れ髪」スタイルや、輝くようなツヤ感を最優先するなら、「ヘアオイル」一択です。
特にスタイリング向けの重め(ウェット)なテクスチャのオイルは、少量で簡単に束感とツヤを演出できます。光を反射する力が強いため、髪を美しく見せる効果が高いです。
髪の広がりやパサつきを抑えたい場合
この目的の場合、髪質によって選択が変わります。
髪が太く・多くて広がる場合は、「重めのヘアオイル」が適しています。髪表面をしっかりコーティングし、重さでボリュームダウンさせます。
髪が細い、またはダメージでパサついて広がる場合は、「ヘアクリーム」が適しています。内部から保湿することでパサつきを抑え、自然にまとまる髪に導きます。
クリームでまとまりきらない場合に、毛先だけ軽いオイルを足すのも良い方法です。
髪を保湿・補修したい場合
日々のダメージケアや、髪の根本的な乾燥対策をしたい場合は、「ヘアクリーム」が最も適しています。
水分と補修成分(ケラチン、セラミドなど)を髪内部に浸透させる能力は、オイルよりもクリームの方が高い傾向にあります。
特にアウトバストリートメント(洗い流さないトリートメント)として使うなら、クリームタイプを選ぶと良いでしょう。
目的別おすすめ早見表
| 目的 | おすすめの選択 | 理由 |
|---|---|---|
| ツヤ・濡れ感 | ヘアオイル | 油分によるコーティングで光を反射させるため。 |
| 保湿・内部補修 | ヘアクリーム | 水分と補修成分を髪内部に浸透させやすいため。 |
| 広がりを抑える | 剛毛:オイル / 軟毛:クリーム | 髪質に合わせた抑え方が必要なため。 |
スタイリング剤として使いたい場合
スタイリング目的の場合、どちらも使用可能です。
「ヘアオイル」は、ツヤ出し、束感、濡れ感、アホ毛を抑える、といった用途に向いています。髪に「動き」や「キープ力」を与える効果はほとんどありません。
「ヘアクリーム」は、自然なまとまり、毛流れの調整、パーマのカールを出す、といった用途に適しています。製品によっては軽いワックスのように使えるものもありますが、キープ力は一般的に弱めです。
ヘアオイルとヘアクリームの正しい使い方
ヘアオイルもヘアクリームも、その効果を最大限に引き出すためには、適切な量とタイミングで使用することが大切です。どちらも基本は「毛先中心」につけることを意識しましょう。
ヘアオイルの適切な使い方
ヘアオイルを使うタイミングは、主に「タオルドライ後の濡れた髪」と「スタイリングの仕上げ」の2つです。
濡れた髪に使う場合は、ドライヤーの熱から髪を守る目的があります。ショートで1プッシュ、ロングで2〜3プッシュ程度を手のひらに伸ばし、毛先を中心にもみ込むようになじませます。
根元につけるとベタつくので避けましょう。
乾いた髪に使う場合は、ツヤ出しやまとまりを出す目的です。ごく少量(半プッシュ程度)を手のひらによく伸ばし、髪の表面や毛先をなでるようにつけます。
ヘアクリームの適切な使い方
ヘアクリームも、主に「タオルドライ後の濡れた髪」に使います。保湿・補修成分を内部に浸透させるのに効果的です。
量はパール粒1〜2個分程度(製品による)を手のひらに取ります。ダメージが気になる毛先から中間にかけて、髪を握るようになじませていきます。オイル同様、根元への塗布は避けます。
乾いた髪のパサつきが気になる時に、追加で少量をつけるのも有効です。
使用タイミングとポイント
| タイミング | ヘアオイル | ヘアクリーム |
|---|---|---|
| タオルドライ後 | 熱からの保護・指通りUP | 内部保湿・補修 |
| 乾いた髪(朝) | ツヤ出し・束感・広がり抑制 | パサつき抑制・自然なまとまり |
| つける場所 | 毛先〜中間(根元NG) | 毛先〜中間(根元NG) |
併用は可能?その場合の順番とコツ
ヘアオイルとヘアクリームの併用は可能です。特に髪のダメージや乾燥がひどい方におすすめの方法です。
順番が重要で、基本的には「先にクリーム、後にオイル」です。
まず、タオルドライ後の濡れた髪に「ヘアクリーム」をなじませ、髪内部に水分と補修成分を届けます。その後、ドライヤーで乾かします。
ドライヤー後、または完全に乾かす直前に「ヘアオイル」を毛先中心にごく少量なじませます。こうすることで、クリームで補給したうるおいや成分に蓋をし、さらにツヤとまとまりを与えます。
両方とも量を多く使いすぎると重くなるため、それぞれ単体で使う時よりも少なめの量を心がけてください。
ヘアオイル・ヘアクリーム選びで注目したい成分
ヘアオイルやヘアクリームを単なるスタイリング剤としてだけでなく、ヘアケアの一環として選ぶのであれば、配合されている成分にも注目することが重要です。自分の髪の悩みや目的に合った成分を見つけましょう。
ヘアオイルで注目の成分
ヘアオイルのベースとなるオイルには、大きく分けて植物性と鉱物性があります。
植物性オイルは、髪へのなじみや保湿効果が期待できます。
代表的なものとして、保湿力が高く髪に栄養を与える「アルガンオイル」、人間の皮脂に近く馴染みが良い「ホホバオイル」、古くから日本で使われツヤ出し効果が高い「ツバキオイル」などがあります。
鉱物性オイル(ミネラルオイル)は、髪表面のコーティング力とツヤ出し効果が非常に高いのが特徴です。
主な植物性オイルと特徴
| オイルの種類 | 主な特徴 | 向いている髪質 |
|---|---|---|
| アルガンオイル | 保湿力、栄養価が高い | ダメージ毛、乾燥毛 |
| ホホバオイル | 皮脂に近く、なじみが良い | 全ての髪質、頭皮ケア(※) |
| ツバキオイル | 高いツヤ出し効果、保湿 | 剛毛、ツヤが欲しい髪 |
ヘアクリームで注目の成分
ヘアクリームは水分ベースであるため、様々な水溶性の保湿・補修成分を配合しやすいのが強みです。
保湿成分としては、「セラミド」「ヒアルロン酸」「コラーゲン」などが代表的です。これらは髪の水分を保ち、しっとりとした質感を与えます。
補修成分としては、「加水分解ケラチン」や「アミノ酸」などが挙げられます。これらは髪の主成分であるタンパク質を補い、ダメージホールを埋めて髪にハリやコシを与えます。
シリコンとノンシリコンの違いと選び方
シリコン(ジメチコン、シクロメチコンなど)は、髪の表面をコーティングし、指通りを良くしたり、ツヤを出したりする成分です。熱や摩擦から髪を守る効果も高いです。
即効性のある手触りの良さを求めるならシリコン入りが適しています。
ノンシリコンは、シリコンを配合していない製品です。仕上がりが軽く、ふんわりしやすいのが特徴です。髪が細い方や、ボリュームダウンしたくない方に好まれます。
ただし、シリコンの代わりに別のコーティング成分(植物性オイルなど)が使われていることが一般的です。
シリコン自体が髪や頭皮に悪影響を与えるわけではありませんが、洗い残しがあるとベタつきの原因になることもあります。自分の好みや髪質に合わせて選びましょう。
スカルプトニックに戻る
よくある質問
ヘアオイルとヘアクリームの違いや選び方、使い方に関して、多くの方が抱く疑問やよくある質問にお答えします。日々のヘアケアの参考にしてください。
- ヘアオイルとヘアクリームはどちらが育毛に良いですか?
-
ヘアオイルもヘアクリームも、基本的には既存の髪(毛幹)をケアするためのものであり、直接的な「育毛」効果(髪を生やす、増やす)を謳うものではありません。
育毛とは、頭皮環境を整え、毛根の働きをサポートすることです。ただし、髪を健やかに保つことは、抜け毛や切れ毛を防ぐ上で重要です。
頭皮マッサージ用のオイルなども存在しますが、育毛を主目的とする場合は、育毛剤や発毛剤の使用を検討するのが適切です。
- 朝と夜、どちらで使うのが効果的ですか?
-
どちらにも役割があるため、目的に応じて使い分けるのが効果的です。夜(お風呂上がり)の使用は、「ヘアケア」が主な目的です。
濡れた髪にクリームやオイルをつけることで、ドライヤーの熱から髪を守り、保湿・補修成分を浸透させます。朝の使用は、「スタイリング」が主な目的です。
乾いた髪にツヤを出したり、まとまりを与えたり、日中の紫外線や乾燥から守るために使います。
- 頭皮についても大丈夫ですか?
-
ほとんどのヘアオイルやヘアクリームは、髪の毛先や中間部への使用を前提としています。頭皮(地肌)に意図的につけることは推奨されません。
特に油分が多いオイルは、毛穴詰まりやベタつきの原因になる可能性があります。ただし、製品によっては「頭皮マッサージOK」や「スカルプケア兼用」と記載されているものもあります。
その場合は、用法を守って使用してください。基本的には「頭皮にはつけない」と覚えておくと良いでしょう。
- 使用量の目安はどれくらいですか?
-
使用量は髪の長さ、毛量、そして製品のテクスチャ(重さ)によって大きく変わります。一般的な目安として、ヘアオイルはショートで1プッシュ、ミディアム〜ロングで2〜3プッシュ。
ヘアクリームはパール粒1〜2個分程度です。まずは少量から試し、足りなければ少しずつ足していくのが失敗しないコツです。
「少し物足りないかな?」くらいで留めておくのが、ベタつきを防ぐポイントです。
- 香りの選び方にポイントはありますか?
-
香りはヘアケアのモチベーションを保つ上で重要な要素です。
リラックスしたい夜のケアにはラベンダーやカモミールなどのハーブ系、朝のスタイリングには気分を上げるシトラス系やフローラル系など、使うシーンで選ぶのも一つの方法です。
また、香水や他のスタイリング剤と香りが混ざるのが苦手な方は、無香料タイプを選ぶと良いでしょう。
Reference
YORK, Katherine, et al. A review of the treatment of male pattern hair loss. Expert opinion on pharmacotherapy, 2020, 21.5: 603-612.
OLSEN, Elise A., et al. Evaluation and treatment of male and female pattern hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2005, 52.2: 301-311.
ZANZOTTERA, F., et al. Efficacy of a nutritional supplement, standardized in fatty acids and phytosterols, on hair loss and hair health in both women and men. J Cosmo Trichol, 2017, 3.121: 2.
MANABE, Motomu, et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of male‐pattern and female‐pattern hair loss, 2017 version. The Journal of Dermatology, 2018, 45.9: 1031-1043.
SOMASUNDARAM, Arun; MURUGAN, Kalaiarasi. Current trends in hair care in men. Cosmoderma, 2024, 4.
GUPTA, Aditya K.; TALUKDER, Mesbah. Topical finasteride for male and female pattern hair loss: is it a safe and effective alternative?. Journal of cosmetic dermatology, 2022, 21.5: 1841-1848.
BANKA, Nusrat; BUNAGAN, MJ Kristine; SHAPIRO, Jerry. Pattern hair loss in men: diagnosis and medical treatment. Dermatologic clinics, 2013, 31.1: 129-140.
DRAKE, Lara, et al. Evaluation of the safety and effectiveness of nutritional supplements for treating hair loss: a systematic review. JAMA dermatology, 2023, 159.1: 79-86.
IBRAHIM, Ibrahim M., et al. Pumpkin seed oil vs. minoxidil 5% topical foam for the treatment of female pattern hair loss: a randomized comparative trial. Journal of cosmetic dermatology, 2021, 20.9: 2867-2873.
SHAHTALEBI, Mohammad Ali; SADAT-HOSSEINI, Atefeh; SAFAEIAN, Leila. Preparation and evaluation of clove oil in emu oil self-emulsion for hair conditioning and hair loss prevention. Journal of HerbMed Pharmacology, 2016, 5.2: 72-77.