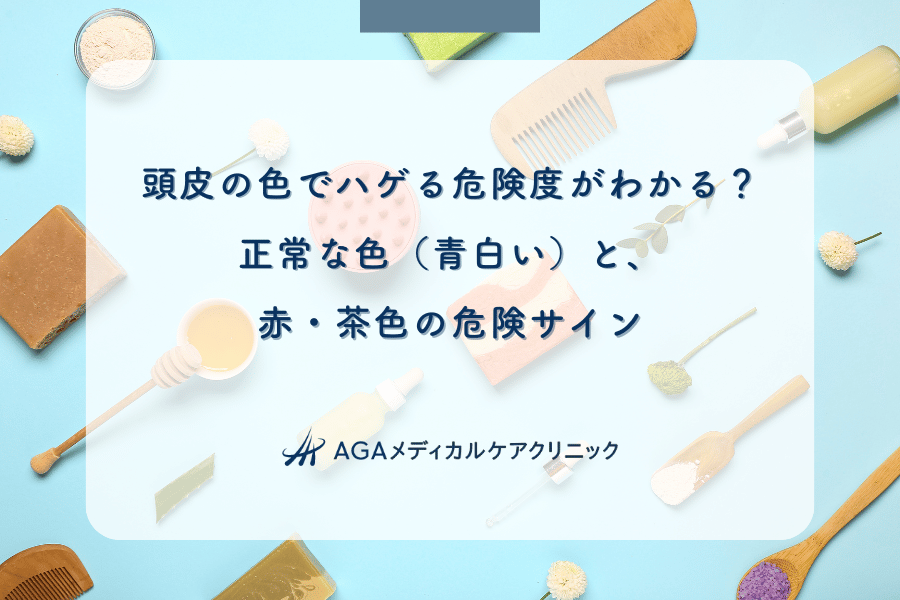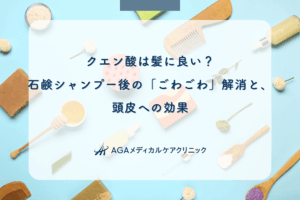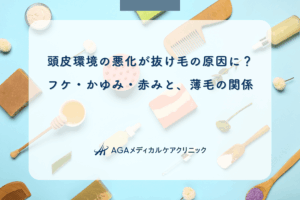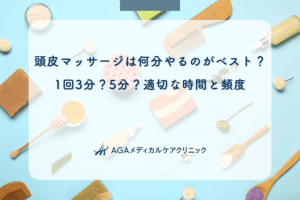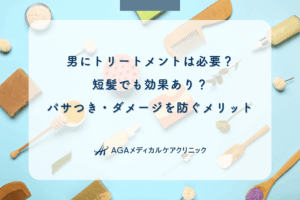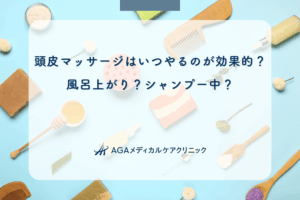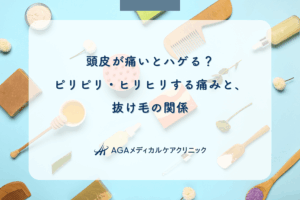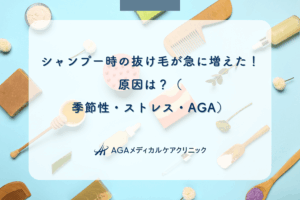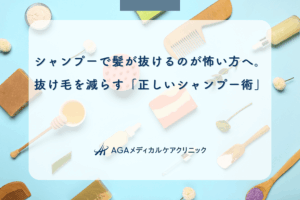ふと鏡を見たとき、自分の頭皮の色が気になったことはありませんか?「最近抜け毛が増えたかも…」と感じている方にとって、頭皮の色は重要なサインかもしれません。
頭皮が赤いや茶色っぽいのは、はげる危険信号なのでしょうか。この記事では、正常な頭皮の色である「青白い」状態と、注意が必要な「赤」「茶色」の状態について徹底解説します。
ご自身の頭皮の状態を知り、適切なケアを始めることで、健やかな髪を育む頭皮環境を取り戻す第一歩になります。この記事を読んで、頭皮の色に関する疑問や不安を解消しましょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
あなたの頭皮は何色?セルフチェックの方法
自分の頭皮の色を正確に把握することが、ヘアケアの第一歩です。頭皮の色は、現在の頭皮環境の健康状態を映し出すバロメーターの役割を果たします。
なぜ頭皮の色が重要なのか
頭皮は髪の毛が生える土壌です。土壌の状態が悪ければ、健康な作物が育たないのと同じで、頭皮環境が悪化すると健康な髪は育ちにくくなります。
頭皮の色は、その環境が良い状態か、何か問題が起きているかを目で見て判断できる数少ない手がかりの一つです。
色が正常でない場合、それは薄毛や抜け毛につながる何らかのトラブルが進行している可能性を示唆しています。
鏡を使った簡単なチェック方法
一番手軽な方法は、鏡を使って直接見ることです。合わせ鏡(三面鏡や、手鏡と洗面台の鏡を組み合わせる)を使うと、自分では見えにくい頭頂部や後頭部も確認しやすくなります。
髪の毛をかき分けて、地肌の色をしっかりと観察してください。
チェックする最適なタイミングと場所
頭皮のチェックは、シャンプー前とシャンプー後の両方で行うのが理想です。シャンプー前は日中の汚れや皮脂の分泌状態がわかります。
シャンプー後は、頭皮がリセットされた清潔な状態の色を確認できます。場所は、照明が明るく、色が正確に判断できる洗面所や自室が良いでしょう。自然光の下で確認できるとなお良いです。
スマホカメラを使った撮影のコツ
鏡では見づらい場合、スマートフォンのカメラ機能が非常に役立ちます。インカメラではなく、高画質な背面のカメラを使いましょう。
頭皮にピントが合うように、少し距離を取ったり、ズーム機能を調整したりしてください。フラッシュを使うと色が飛んでしまうことがあるため、明るい部屋でフラッシュなしで撮影するのがコツです。
撮影した画像を拡大すれば、毛穴の状態や細かな色の変化も確認できます。定期的に撮影して比較するのも良い方法です。
正常な頭皮の色「青白い」状態とは
健康な頭皮の理想的な色は「青白い」状態です。これは、頭皮が透明感があり、皮下の毛細血管がわずかに透けて見える状態を指します。
「青白い」が健康なサインである理由
青白く見えるのは、頭皮のキメが整っており、十分な水分が保たれている証拠です。また、血行が良好で、血液が滞りなく流れていることを示しています。
この状態であれば、髪の毛の成長に必要な栄養素が毛根(毛母細胞)までしっかりと届けられています。
毛細血管が透けて見える状態
健康な頭皮は適度な厚みと透明感を持っています。そのため、その下にある毛細血管の色がうっすらと透けて見え、結果として青白く(または白っぽく)見えます。
逆に、炎症や血行不良があると、この透明感が失われたり、他の色に変わったりします。
健康な頭皮のその他の特徴(弾力・うるおい)
色だけでなく、他の要素も健康な頭皮の指標となります。
頭皮の弾力チェック
指の腹で頭皮を軽く押してみてください。健康な頭皮は適度な弾力があり、押した後にすぐに元に戻ります。
もし頭皮が硬く、動かない感じがするなら、血行が悪くなっているか、乾燥している可能性があります。
頭皮のうるおいチェック
頭皮を触ったときに、カサカサしすぎず、かといってベタベタもしない、適度なしっとり感があるのが理想です。
乾燥しすぎているとフケの原因になり、ベタつきすぎていると毛穴の詰まりや炎症の原因になります。
頭皮の健康サイン
| 項目 | 健康な状態 | 注意が必要な状態 |
|---|---|---|
| 色 | 青白い、透明感がある | 赤い、茶色い、黄色い |
| 弾力 | 指で押すと弾力がある | 硬い、動かない、ブヨブヨしている |
| 状態 | 適度なうるおい、ベタつかない | 乾燥(フケ)、過度なベタつき |
危険サイン「赤い」頭皮が示すもの
頭皮が「赤い」または「ピンク色」になっている場合、それは頭皮が「炎症」を起こしているサインです。
何らかの刺激によって皮膚がSOSを出している状態であり、はげ(薄毛)につながる危険性が高まっています。
頭皮が赤くなる主な原因「炎症」
炎症は、外部からの刺激や内部の問題に対して、体の防御反応が働いている証拠です。頭皮で炎症が続くと、毛根がダメージを受け、健康な髪の毛が育ちにくくなります。
かゆみやフケを伴うことも多く、これらを放置すると抜け毛が進行する可能性があります。
皮脂の過剰分泌と赤み(脂漏性皮膚炎)
皮脂が過剰に分泌されると、それをエサにする常在菌(マラセチア菌など)が異常繁殖し、その代謝物が頭皮を刺激して炎症を引き起こすことがあります。
これが「脂漏性皮膚炎」と呼ばれる状態で、頭皮の赤み、かゆみ、ベタついたフケが特徴です。皮脂の分泌が多い男性は特に注意が必要です。
間違ったヘアケアによる刺激
日常のヘアケアが原因で炎症を引き起こしているケースも少なくありません。
洗浄力の強すぎるシャンプー
頭皮の必要な皮脂まで奪ってしまい、バリア機能が低下。結果、外部からの刺激を受けやすくなり赤みが出ます。
ゴシゴシ洗い
爪を立てて洗ったり、力を入れすぎたりすると、頭皮が傷つき、そこから炎症が起こります。シャンプーは指の腹で優しくマッサージするように洗うのが基本です。
すすぎ残し
シャンプーやコンディショナーの成分が頭皮に残ると、それが刺激となって炎症やかゆみを引き起こします。特に生え際や耳の後ろはすすぎ残しが多い場所です。
紫外線ダメージと日焼け
顔の5倍以上の紫外線を浴びるとも言われる頭皮は、日焼けしやすい部位です。紫外線によって頭皮が日焼け(軽いやけど)を起こすと、赤くなります。
このダメージが蓄積すると、頭皮が硬くなり、血行も悪化。光老化が進み、薄毛の原因となります。特に髪の分け目や頭頂部は注意が必要です。
危険サイン「茶色い(黄ばんだ)」頭皮が示すもの
頭皮が「茶色い」または「黄色っぽい(黄ばんだ)」場合、それは主に「血行不良」や「皮脂の酸化」を示しています。
髪に必要な栄養が届きにくい状態であり、これもはげ(薄毛)のリスクを高めるサインです。
「茶色い(黄ばんだ)」は血行不良のサイン
頭皮の血行が悪くなると、血液がうっ滞し、本来排出されるべき老廃物が溜まりやすくなります。
また、新鮮な酸素や栄養が届きにくくなるため、頭皮の細胞の活力が失われ、新陳代謝(ターンオーバー)が低下します。その結果、頭皮がくすんで茶色っぽく見えてしまうのです。
皮脂の酸化と汚れの蓄積
分泌された皮脂が毛穴や頭皮表面に残り、時間とともに空気に触れて「酸化」すると、黄色っぽい「過酸化脂質」という物質に変化します。これが頭皮の黄ばみや茶色っぽさの原因となります。
過酸化脂質は頭皮を刺激し、炎症を引き起こしたり、毛穴を塞いで髪の成長を妨げたりする厄介な存在です。シャンプーで汚れを落としきれていない場合にも蓄積しやすくなります。
生活習慣の乱れ(睡眠不足・ストレス)
睡眠不足や過度なストレスは、自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させて血行不良を引き起こします。血行が悪くなれば、当然頭皮は茶色っぽくくすんできます。
また、ストレスは皮脂の分泌を過剰にすることもあり、酸化を助長する要因にもなります。
頭皮の色別・危険サイン早見表
| 頭皮の色 | 状態 | 主な原因 |
|---|---|---|
| 赤い | 炎症 | 皮脂過剰、間違ったケア、紫外線 |
| 茶色い・黄色い | 血行不良・酸化 | 皮脂の酸化、生活習慣の乱れ、老化 |
| 青白い | 健康 | 良好な血行、適度な水分 |
代謝の低下とターンオーバーの乱れ
頭皮も肌の一部であり、一定の周期(約28日〜40日)で新しい細胞に生まれ変わる「ターンオーバー」を繰り返しています。
しかし、血行不良や栄養不足、加齢などによって代謝が低下すると、このターンオーバーが乱れます。古い角質がうまく剥がれ落ちずに蓄積し、頭皮がくすんで茶色く見える原因になります。
頭皮の色と「はげ(薄毛)」の直接的な関係
頭皮の色が正常(青白い)でないことは、それ自体が直接「はげ(薄毛)」の原因ではありませんが、薄毛が進行しやすい「頭皮環境の悪化」を示しています。
頭皮環境の悪化は、髪の成長を著しく妨げる要因となります。
頭皮環境の悪化が毛髪の成長を妨げる
髪の毛は、頭皮の下にある毛包(もうほう)で作られます。毛包の最深部にある毛母細胞が、毛細血管から栄養を受け取って分裂・増殖することで髪は成長します。
しかし、頭皮の色が赤いや茶色い状態(=頭皮環境が悪い状態)では、このシステムが正常に機能しにくくなります。
頭皮環境と毛髪成長への影響
| 頭皮環境 | 状態 | 毛髪への影響 |
|---|---|---|
| 良好 (青白い) | 血行良好、栄養十分 | 正常な成長サイクル、太く健康な髪 |
| 不良 (赤・茶) | 炎症、血行不良、栄養不足 | 成長サイクルの短縮、細く弱い髪、抜け毛 |
赤い頭皮が引き起こす抜け毛
赤い頭皮(炎症状態)では、かゆみを伴うことが多く、無意識に掻いてしまうことで頭皮や毛根が傷つき、物理的に髪が抜けやすくなります。
また、炎症自体が毛母細胞の働きを弱らせ、髪の成長期を短縮させてしまう可能性があります。成長しきる前に髪が抜けてしまうため、全体的に薄くなったように感じます。
茶色い頭皮が引き起こす栄養不足
茶色い頭皮(血行不良・酸化状態)では、毛母細胞への栄養補給が滞りがちです。髪の毛は血液から栄養をもらって成長するため、栄養が不足すれば、当然ながら細く、弱々しい髪しか作れなくなります。
また、皮脂が酸化して毛穴を塞ぐと、髪の正常な発毛を物理的に阻害することもあります。
AGA(男性型脱毛症)との関連性
男性の薄毛の多くはAGA(男性型脱毛症)が原因です。AGAは男性ホルモンの影響によるもので、頭皮の色が直接の原因ではありません。
しかし、AGAが進行している人の頭皮が、皮脂の過剰分泌などで赤みがかっていたり、血行不良で茶色っぽくなっていたりするケースは少なくありません。
頭皮環境の悪化がAGAの進行を早める可能性は否定できず、AGA治療と並行して頭皮環境を整えることは非常に重要です。
頭皮の色を正常(青白い)に戻すためのケア方法
頭皮の色が赤や茶色になっていても、諦める必要はありません。適切なケアを行うことで、健康な「青白い」頭皮を目指すことは可能です。日々の積み重ねが重要になります。
正しいシャンプーの選び方と洗い方
頭皮ケアの基本は毎日のシャンプーです。
シャンプーの選び方
洗浄力が強すぎるシャンプー(高級アルコール系など)は避け、頭皮への刺激が少ないアミノ酸系やベタイン系の洗浄成分を使ったシャンプーを選びましょう。
赤みが気になる方は抗炎症成分(グリチルリチン酸2Kなど)、黄ばみが気になる方は皮脂の酸化を防ぐ成分や保湿成分が配合されたものが良いでしょう。
正しい洗い方
シャンプーは以下の手順で行いましょう。
- 予洗い: シャンプーをつける前に、ぬるま湯(38度前後)で頭皮と髪をしっかりと濡らし、表面の汚れを落とします。
- 泡立て: シャンプーは手のひらでよく泡立ててから、頭皮につけます。
- 洗う: 指の腹を使い、頭皮を優しくマッサージするように洗います。爪を立てるのは厳禁です。
- すすぎ: 洗う時間の2倍以上を目安に、シャンプー剤が残らないよう徹底的にすすぎます。
頭皮マッサージによる血行促進
頭皮が硬い、または茶色っぽい(血行不良)方には、頭皮マッサージが効果的です。血行を促進し、頭皮を柔らかくすることで、栄養が行き渡りやすくなります。
シャンプー中や、育毛剤をつけた後に行うのが良いでしょう。指の腹で頭皮全体を掴むようにし、下から上へ、円を描くように優しく動かします。毎日数分でも続けることが大切です。
バランスの取れた食事と栄養素
髪の毛はタンパク質(ケラチン)でできており、その生成にはビタミンやミネラルが必要です。
健やかな髪を育む主な栄養素
| 栄養素 | 役割 | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| ビタミンB群 | 頭皮の代謝促進、皮脂調整 | 豚肉、レバー、マグロ、納豆 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、牛肉、レバー、チーズ |
偏った食事は避け、これらの栄養素をバランス良く摂取することを心がけてください。特に脂っこい食事や糖分の多い食事は、皮脂の過剰分泌につながるため控えめにしましょう。
育毛剤の活用と頭皮へのアプローチ
セルフケアの一環として、育毛剤を取り入れるのも一つの方法です。
育毛剤には、血行を促進する成分、頭皮の炎症を抑える成分、毛母細胞の働きを助ける成分などが配合されています。
育毛剤の選び方
ご自身の頭皮の状態に合わせて選びましょう。
- 赤い頭皮: 抗炎症成分、保湿成分が含まれるもの。
- 茶色い頭皮: 血行促進成分、抗酸化成分が含まれるもの。
育毛剤は、頭皮が清潔な状態(シャンプー後、しっかり乾かした後)で使用するのが最も効果的です。
説明書に従い、適量を頭皮に直接塗布し、マッサージするようになじませてください。
生活習慣で見直すべきポイント
頭皮環境は、日々の生活習慣と密接に関連しています。頭皮の色を改善し、はげ(薄毛)を予防するためには、ヘアケアだけでなく、体全体を健康に保つ意識が重要です。
質の高い睡眠の確保
髪の毛は、私たちが寝ている間に成長します。特に、入眠から最初の3時間程度に多く分泌される「成長ホルモン」が、毛母細胞の分裂を活発にします。
睡眠不足が続くと、成長ホルモンの分泌が減少し、頭皮のターンオーバーも乱れがちになります。
毎日6〜7時間程度の十分な睡眠時間を確保し、就寝前のスマホ操作を控えるなど、睡眠の「質」にもこだわりましょう。
ストレス管理とリラックス法
過度なストレスは、自律神経のバランスを崩し、血管を収縮させます。その結果、頭皮の血行が悪化し、栄養が届きにくくなります。
また、ストレスは男性ホルモンのバランスにも影響を与え、皮脂の分泌を増加させることもあります。自分に合った方法で、ストレスを溜め込まないように工夫することが大切です。
おすすめのリラックス法
| リラックス法の例 | 期待できること |
|---|---|
| 湯船にゆっくり浸かる | 副交感神経を優位にし、血行を促進する |
| 軽い運動(ウォーキング、ストレッチ) | 気分転換と血流改善 |
| 趣味の時間を持つ | ストレス原因から意識をそらす |
適度な運動の習慣化
運動不足は、全身の血行不良を招きます。デスクワークが多い方は特に、意識して体を動かす必要があります。
ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は、全身の血流を改善し、頭皮への血行促進にもつながります。
また、適度な運動はストレス解消にも役立ちます。週に2〜3回、30分程度から始めてみましょう。
喫煙と飲酒の影響
喫煙と過度な飲酒は、頭皮環境にとってマイナスに働きます。
喫煙と過度な飲酒がもたらす影響
| 項目 | 頭皮・毛髪への主な影響 |
|---|---|
| 喫煙 (タバコ) | ニコチンによる血管収縮(血行不良)。ビタミンCの破壊(抗酸化力低下)。 |
| 過度な飲酒 | アルコールの分解にビタミンやアミノ酸が大量に消費される(栄養不足)。睡眠の質の低下。 |
タバコに含まれるニコチンは、血管を強力に収縮させ、頭皮の血行を著しく悪化させます。また、過度なアルコール摂取は、髪の栄養となるビタミンやアミノ酸を体内で大量に消費してしまいます。
禁煙を心がけ、飲酒は適量(ビール中瓶1本、日本酒1合程度)に留めることが望ましいです。
頭皮環境と保湿に戻る
よくある質問
- 頭皮の色はどれくらいの頻度でチェックすべきですか?
-
毎日チェックするのが理想ですが、難しい場合は週に1回程度、シャンプーの際などに鏡やスマホで確認する習慣をつけると良いでしょう。
頭皮の状態は日々変化するため、定期的に観察し、小さな変化に気づくことが早期対策につながります。
- 頭皮が赤いのですがすぐにはげますか?
-
頭皮が赤いからといって、すぐに(明日・明後日)はげるわけではありません。
しかし、赤みは「炎症」という危険サインであり、その状態を放置すれば、毛根がダメージを受け続け、数ヶ月後、数年後に抜け毛や薄毛が進行するリスクは高まります。
早めにシャンプーを見直す、生活習慣を改善するなどのケアを始めることが重要です。
- 頭皮の色は自分でケアすれば改善しますか?
-
軽度な赤みや茶色い(黄ばんだ)状態であれば、シャンプー方法の改善、食生活や睡眠などの生活習慣の見直し、育毛剤の使用といったセルフケアで改善する可能性は十分にあります。
ただし、かゆみやフケがひどい場合、長期間改善が見られない場合は、脂漏性皮膚炎など他の皮膚疾患の可能性もあるため、専門のクリニック(皮膚科など)に相談することをおすすめします。
- 育毛剤はどの色の頭皮でも使っていいですか?
-
基本的にはどの色の頭皮でも使用できますが、選び方が重要です。赤い(炎症がある)頭皮に、刺激の強いアルコール(エタノール)が多く含まれる育毛剤を使用すると、症状が悪化する可能性があります。
赤みが強い場合は、まず炎症を抑えることを優先し、低刺激性のものや抗炎症成分が配合された育毛剤を選ぶと良いでしょう。
茶色い(血行不良)頭皮には、血行促進成分が配合された育毛剤が適しています。
Reference
ALESSANDRINI, A., et al. Common causes of hair loss–clinical manifestations, trichoscopy and therapy. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2021, 35.3: 629-640.
ASHWINI, P. An Observational Study to Evaluate Hemoglobin and Serum Ferritin Levels in Apparently Healthy Adults and its Correlation with Hair Loss. 2019. PhD Thesis. Rajiv Gandhi University of Health Sciences (India).
TRÜEB, Ralph M., et al. The Hair and Scalp in Systemic Infectious Disease. In: Hair in Infectious Disease: Recognition, Treatment, and Prevention. Cham: Springer International Publishing, 2023. p. 303-365.
WOLFF, Hans; FISCHER, Tobias W.; BLUME-PEYTAVI, Ulrike. The diagnosis and treatment of hair and scalp diseases. Deutsches Ärzteblatt International, 2016, 113.21: 377.
VISHU, Michelle. Trichoscopic Analysis of Female Pattern Hair Loss and Correlation of Findings with Disease Severity: A Cross-Sectional Study. 2019. PhD Thesis. Rajiv Gandhi University of Health Sciences (India).
RUDNICKA, Lidia, et al. The role of trichoscopy beyond hair and scalp diseases: A review. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2023, 37.8: 1473-1479.
KN, Shobha Rani. Histopathological Study of Scalp Biopsy Specimen Along with Estimation of Serum Ferritin and Thyroid Profile in Females with Diffuse Hair Loss. 2018. PhD Thesis. Rajiv Gandhi University of Health Sciences (India).
TRÜEB, Ralph M.; GAVAZZONI DIAS, Maria Fernanda Reis. Fungal diseases of the hair and scalp. In: Hair in infectious disease: recognition, treatment, and prevention. Cham: Springer International Publishing, 2023. p. 151-195.
TRÜEB, Ralph M.; LEE, Won-Soo. Male alopecia. Guide to successful management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2014.
KHARE, Soumil, et al. Dermoscopy of hair and scalp disorders (Trichoscopy) in skin of color–a systematic review by the International Dermoscopy Society “Imaging in Skin of Color” Task Force. Dermatology Practical & Conceptual, 2023, 13.4 Suppl 1: e2023310S.