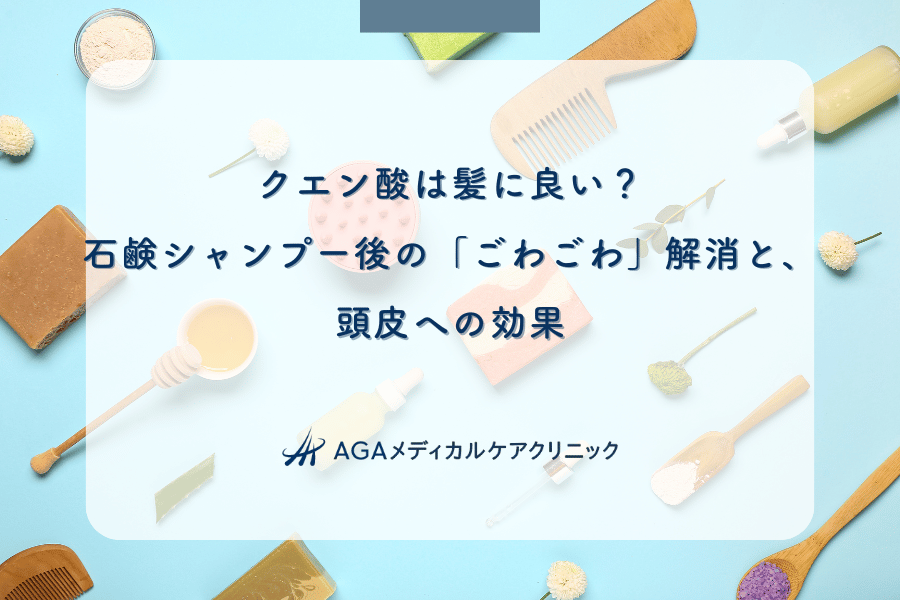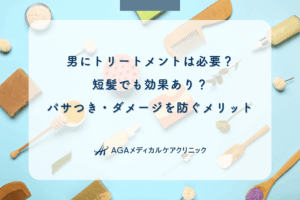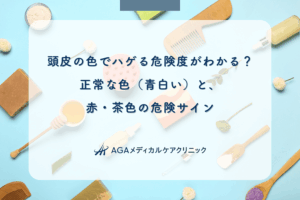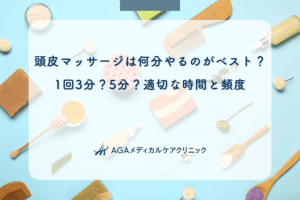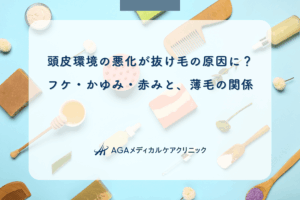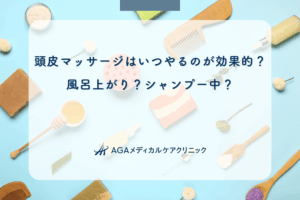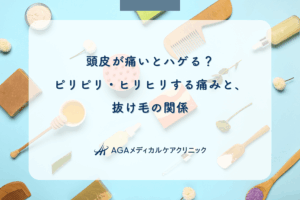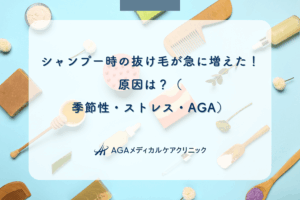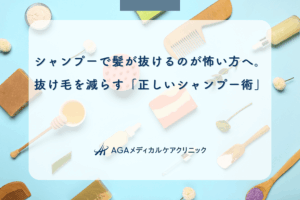石鹸シャンプーを使った後の髪のごわごわ感、気になりますよね。指通りが悪く、本当にこれで良いのか不安になるかもしれません。実はその悩み、「クエン酸」が解決の鍵になるかもしれません。
この記事では、クエン酸が髪の毛にどのような効果をもたらすのか、特に石鹸シャンプー後の中和作用や、頭皮環境への影響について詳しく解説します。
クエン酸の正しい使い方から注意点までを網羅し、あなたが健やかな髪と頭皮を目指すための情報を提供します。最終的に、クエン酸があなたのヘアケアの一助となるか判断できるでしょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
そもそもクエン酸とは?その基本的な性質
クエン酸は、レモンや梅干しなどに含まれる酸っぱい成分として知られる有機酸の一種です。化学的には「ヒドロキシ酸」に分類され、爽やかな酸味を持つことから食品添加物として広く利用されています。
また、水に溶けやすく、金属イオンを封鎖する性質(キレート作用)を持つため、掃除や水垢落としにも活用されるなど、私たちの生活の様々な場面で役立っています。
クエン酸はどこに含まれている?
クエン酸は自然界、特に柑橘系の果物に豊富に含まれています。代表的なのはレモンやライム、グレープフルーツなどです。また、梅干しの強い酸味もクエン酸によるものです。
私たちの体内でも、エネルギーを生み出す「クエン酸回路」という重要な代謝経路の中心的な役割を担っており、生命活動に欠かせない成分です。
クエン酸を多く含む食品の例
| 食品名 | 特徴 | クエン酸含有量の目安 |
|---|---|---|
| レモン・ライム | 柑橘類の中でも特に含有量が多い | 果汁中に数%程度 |
| 梅干し | 日本の伝統的な食品で酸味が強い | 品種や製法による |
| その他柑橘類 | オレンジ、みかん、グレープフルーツなど | レモンよりは少ないが含まれる |
食品や掃除だけじゃないクエン酸の用途
クエン酸の用途は非常に多岐にわたります。食品分野では、酸味料、pH調整剤、保存料などとして飲料や菓子、ジャムなどに使われます。
健康食品としても、疲労回復を助けるとされることからサプリメントなどに配合されます。工業分野では、洗剤の成分として水垢を落としたり、金属のサビ取りに使われたりします。
そして、美容分野でも化粧品のpH調整剤や、ピーリング剤の成分として利用されることがあります。このように、クエン酸はその化学的性質から多様な分野で活躍しています。
クエン酸が酸性であることの意味
クエン酸は水に溶けると酸性を示します。物質の性質を酸性・中性・アルカリ性で示す指標をpH(ピーエイチ)と呼びますが、クエン酸水溶液は低いpH値(酸性)を示します。
この「酸性」であるという性質が、ヘアケア、特に石鹸シャンプー後のケアにおいて重要な意味を持ちます。アルカリ性に傾いたものを中和し、元の弱酸性の状態に戻す働きが期待できるのです。
クエン酸が髪の毛にもたらす主な効果
クエン酸が髪の毛にもたらす最も代表的な効果は、石鹸シャンプーによってアルカリ性に傾いた髪の毛を中和し、開いたキューティクルを引き締めることです。
その結果、髪のごわごわ感やきしみを和らげ、指通りを滑らかにする働きが期待できます。髪の毛は本来、弱酸性(pH4.5〜5.5程度)が最も安定した状態とされています。
石鹸シャンプー後の「ごわごわ」はなぜ起こる?
石鹸シャンプーの主成分である「石鹸(脂肪酸ナトリウムや脂肪酸カリウム)」は、水に溶けるとアルカリ性を示します。
このアルカリ性の洗浄剤で髪を洗うと、髪の毛の表面を覆っているウロコ状の「キューティクル」が開いてしまいます。
キューティクルが開くと、髪の内部の水分やタンパク質が流出しやすくなるだけでなく、ウロコ同士が引っかかりやすくなり、それが「ごわごわ」や「きしみ」といった感触の原因となります。
また、水道水に含まれるカルシウムイオンやマグネシウムイオンと石鹸が反応すると、「石鹸カス(金属石鹸)」と呼ばれる水に溶けにくい物質が生成されます。
これが髪の毛に付着することも、ごわつきの一因となります。
アルカリ性を中和しキューティクルを引き締める
ここでクエン酸の出番です。酸性のクエン酸水溶液(クエン酸リンス)をアルカリ性に傾いた髪の毛に使用すると、化学的な中和反応が起こります。
髪の毛のpHが本来の弱酸性に戻ることで、開いていたキューティクルがキュッと引き締まります。キューティクルが整然と閉じることで、髪の表面が滑らかになり、ごわごわ感やきしみが大幅に改善されます。
これは、石鹸シャンプーを使う上で非常に重要なケアと言えるでしょう。
髪の毛のpHと状態
| pHの状態 | 髪の毛の状態 | 主な要因 |
|---|---|---|
| 弱酸性 (pH4.5-5.5) | 最も安定的(等電点) | 健康な髪、クエン酸リンス後 |
| アルカリ性 (pH7以上) | キューティクルが開く、膨張する | 石鹸シャンプー、パーマ、カラー剤 |
| 強酸性 (pH4未満) | 過度に収れんする可能性 | 高濃度の酸性リンスなど |
髪の毛の指通りとツヤへの影響
キューティクルが引き締まり、髪の表面が滑らかになることは、指通りやツヤにも直結します。キューティクルが整っていると、髪の毛同士の摩擦が減り、手ぐしやブラシが通りやすくなります。
また、髪の表面に当たった光が均一に反射するため、自然なツヤ(天使の輪)が生まれやすくなります。逆にキューティクルが開いたままだと、光が乱反射してしまい、髪がパサついて見える原因にもなります。
クエン酸リンスが髪に良いとされる理由
クエン酸リンスが「髪に良い」とされる最大の理由は、石鹸シャンプーでアルカリ性に傾いた髪を、ダメージを受けにくい弱酸性の状態へ迅速に戻すことができる点にあります。
合成シャンプーに含まれるようなシリコン(ジメチコンなど)によるコーティングとは異なり、髪の毛そのものの状態を安定させるアプローチです。
また、石鹸カスの一部をクエン酸が分解・除去する助けにもなると言われています。
クエン酸の頭皮への効果と影響
クエン酸は、髪の毛だけでなく頭皮に対しても、その酸性の性質による良い影響を与える可能性があります。
主に、頭皮のpHバランスを弱酸性に保つ手助けをしたり、収れん作用によって頭皮を引き締めたりする効果が期待されます。健やかな頭皮環境は、健やかな髪を育む土台として非常に重要です。
ただし、濃度や使用方法には注意が必要です。
頭皮のpHバランスとクエン酸
健康な頭皮も、髪の毛と同様に弱酸性(pH5.0前後)に保たれています。この弱酸性の環境は、皮膚のバリア機能を維持し、外部からの刺激や雑菌の繁殖を防ぐ「皮脂膜」の働きにとって望ましい状態です。
石鹸シャンプーを使用すると、頭皮も一時的にアルカリ性に傾きます。クエン酸リンスを髪だけでなく頭皮にも行き渡らせることで、頭皮のpHを速やかに弱酸性に戻す手助けになります。
収れん作用による頭皮の引き締め
クエン酸には「収れん作用」があります。これは、タンパク質を変性させて組織を引き締める働きのことを指します。
適度な収れん作用は、頭皮の毛穴を引き締め、過剰な皮脂分泌を抑えるのに役立つと考えられます。
ただし、濃度が高すぎると刺激になり、逆に頭皮を乾燥させてしまう可能性もあるため、適切な濃度で使用することが大切です。
頭皮の雑菌繁殖とクエン酸
頭皮には常在菌が存在しますが、アルカリ性に傾くと、一部の雑菌(例えばアルカリ性を好む菌)が繁殖しやすい環境になる可能性があります。
頭皮を弱酸性に保つことは、こうした雑菌の異常な繁殖を抑え、頭皮環境のバランスを維持することに繋がります。
クエン酸によるpH調整は、間接的に頭皮の衛生環境を良好に保つサポートをすると言えるでしょう。
フケやかゆみへの間接的なアプローチ
フケやかゆみの原因は様々ですが、頭皮環境の乱れが要因の一つとなることがあります。
例えば、石鹸シャンプー後にアルカリ性に傾いたままでいると、頭皮が乾燥しやすくなったり、バリア機能が低下したりして、かゆみや乾燥によるフケが出やすくなることも考えられます。
クエン酸で適切に中和ケアを行うことは、こうしたアルカリ性由来のトラブルを防ぎ、結果としてフケやかゆみの予防に繋がる可能性があります。
頭皮環境を左右する要因
- 皮脂の分泌量
- 頭皮のpHバランス
- 常在菌のバランス
石鹸シャンプーとクエン酸リンスの正しい使い方
クエン酸の効果を最大限に引き出し、トラブルを避けるためには、石鹸シャンプーとクエン酸リンスを正しく使うことが重要です。特にクエン酸リンスは、濃度とすすぎがポイントになります。
自己流で行う前に、基本的な手順を確認しておきましょう。
石鹸シャンプーの基本的な洗い方
石鹸シャンプーは、一般的な合成シャンプーとは使い勝手が異なる場合があります。まず、洗う前にブラッシングで髪のほこりや絡まりを取り、お湯でしっかりと予洗い(湯シャン)をします。
こうすることで、汚れの大部分が落ち、石鹸の泡立ちが良くなります。石鹸シャンプーを手に取り、直接髪につけるのではなく、手のひらや泡立てネットでよく泡立ててから髪と頭皮につけます。
指の腹を使って頭皮をマッサージするように優しく洗い、髪の毛自体は泡で包み込むように洗います。ゴシゴシと髪をこすり合わせるのはキューティクルを傷める原因になるため避けましょう。
すすぎは、石鹸分や石鹸カスが残らないよう、時間をかけて念入りに行います。
クエン酸リンスの簡単な作り方
クエン酸リンスは簡単に手作りできます。基本的な材料は「クエン酸」と「水(洗面器一杯程度のお湯)」だけです。
クエン酸は薬局やスーパー、100円ショップなどで(食用または掃除用として)入手できますが、ヘアケアに使う場合は、添加物のない純粋なクエン酸(結晶または粉末)を選ぶと良いでしょう。
クエン酸リンスの基本比率
| 用意するもの | 量の目安 | ポイント |
|---|---|---|
| 洗面器 | 1杯 | お湯(ぬるま湯)を入れる |
| クエン酸(粉末/結晶) | 小さじ半分〜1杯程度 | 髪の長さや量、ごわつき具合で調整 |
| (お好みで)グリセリン | 数滴 | 保湿効果を加えたい場合 |
洗面器にお湯を張り、クエン酸を入れてよく溶かします。この時、クエン酸の量が多すぎないように注意が必要です。濃度が高すぎると髪や頭皮への刺激になる可能性があります。
最初は少なめ(耳かき1〜2杯程度や小さじ半分弱)から試し、髪のごわつきが解消される自分に合った量を見つけるのが良いでしょう。
クエン酸リンスを使用するタイミングと量
クエン酸リンスは、石鹸シャンプーを「しっかりとすすいだ後」に使用します。
シャンプーの泡が完全に切れてから、用意しておいたクエン酸リンスを髪全体、そして頭皮にもいきわたるようにゆっくりとかけます。
髪が長い場合は、洗面器の中で髪を泳がせるようにすると均一になじみやすいです。髪の毛がキュッと締まるような、指通りがスッと変わる感覚があれば、中和されている証拠です。
しっかりとすすぐことの重要性
クエン酸リンスをなじませた後は、「必ず」お湯で再度しっかりとすすぎます。クエン酸の成分が髪や頭皮に残ったままだと、酸による刺激で頭皮が荒れたり、髪が乾燥したりする原因になりかねません。
特に髪の生え際や襟足などはすすぎ残しが多い部分なので、意識して洗い流してください。中和が目的ですので、トリートメントのように長時間放置する必要は全くありません。
なじませたら、すぐにすすぐ、と覚えておきましょう。
クエン酸使用時の注意点とデメリット
クエン酸は正しく使えば非常に有用ですが、使い方を誤ると髪や頭皮に負担をかける可能性があります。特に「濃度」と「すすぎ」は、クエン酸リンスを利用する上での重要な注意点です。
デメリットも理解した上で、適切に取り入れることが大切です。人によっては肌に合わない場合もあります。
濃度が高すぎることのリスク
クエン酸リンスが髪に良いからといって、濃度を高くすればするほど効果が上がるわけではありません。むしろ逆効果になる危険性があります。
クエン酸は強い酸性物質ですので、濃度が高すぎると(pHが低くなりすぎると)、髪のタンパク質を過度に収れんさせ、髪を硬くしたり、もろくしたりする可能性があります。
また、頭皮への刺激が強くなり、かゆみ、赤み、乾燥、フケなどの頭皮トラブルを引き起こす原因にもなります。「ごわつきが取れれば良い」という意識で、必ず薄めて使用してください。
目に入った場合の対処法
クエン酸水溶液が目に入ると、強い刺激を感じ、目の粘膜を傷つける恐れがあります。リンスを行う際は、目に入らないように細心の注意を払いましょう。
もし目に入ってしまった場合は、こすらずに、すぐに大量の清浄な水(またはぬるま湯)で15分以上洗い流してください。
痛みや違和感が残る場合は、速やかに眼科医の診察を受けるようにしてください。
敏感肌・乾燥肌の人が気をつけること
頭皮がもともと敏感な方や、乾燥しやすい方がクエン酸リンスを使用する場合は、特に注意が必要です。通常よりも低い濃度から試すことをお勧めします。
例えば、洗面器一杯のお湯に対して耳かき1杯程度のごく少量から始め、頭皮や髪の状態に異常が出ないか注意深く観察してください。
少しでも刺激を感じる、かゆみが出る、フケが増えるなどの症状が出た場合は、使用を中止し、濃度を下げるか、別の方法を検討する必要があります。
クエン酸使用時のセルフチェック
| チェック項目 | 確認するポイント | 異常時の対応 |
|---|---|---|
| 濃度 | 濃すぎないか?(推奨量か) | 薄める、または使用中止 |
| 刺激 | 頭皮がピリピリしないか? | すぐに洗い流し、使用中止 |
| すすぎ | リンス後に十分すすいでいるか? | より念入りにすすぐ |
クエン酸が合わないケース
全ての人にクエン酸リンスが合うわけではありません。体質やその時の頭皮の状態によっては、適切に使っていても肌トラブルが起こる可能性があります。
また、石鹸シャンプー自体が肌に合わず、クエン酸リンスを使っても頭皮環境が改善しないケースもあります。
クエン酸リンスを試しても髪のごわつきが改善しない、あるいは頭皮の状態が悪化するようであれば、無理に続けず、石鹸シャンプーやクエン酸リンスの使用を見直す勇気も必要です。
クエン酸以外で髪の「ごわごわ」を防ぐ方法
石鹸シャンプー後のごわごわ対策はクエン酸リンスが代表的ですが、それが唯一の方法ではありません。
クエン酸が肌に合わなかったり、手間がかかると感じたりする場合は、他の選択肢を検討するのも良いでしょう。石鹸シャンプーにこだわらない方法もあります。
石鹸シャンプー以外の選択肢
もし石鹸シャンプーのアルカリ性や石鹸カスの発生によるごわつきに悩まされているのであれば、洗浄成分の異なるシャンプーに変えるのが最も直接的な解決策かもしれません。
世の中には多様なシャンプーが存在します。
主なシャンプーの種類
- アミノ酸系シャンプー
- 高級アルコール系シャンプー
- ベタイン系シャンプー
特に「アミノ酸系シャンプー」は、洗浄力がマイルドで、髪や頭皮と同じ弱酸性のものが多く、洗い上がりがしっとりしやすい傾向があります。
頭皮環境を気にされる方や、髪のパサつきが気になる方には選択肢の一つとなるでしょう。
一般的なトリートメントやコンディショナーの役割
市販されている多くの一般的なシャンプー(合成シャンプー)は、弱酸性〜中性で作られているため、基本的にはクエン酸のような中和剤を必要としません。
その代わり、シャンプー後に「コンディショナー」や「トリートメント」を使用します。
これらには、カチオン界面活性剤(陽イオン界面活性剤)やシリコン、油分などが含まれており、髪の表面をコーティングして静電気を防ぎ、指通りを滑らかにし、髪を保護する役割を果たします。
石鹸シャンプーとクエン酸リンスのケアとは、根本的なアプローチが異なります。
お酢リンスとクエン酸リンスの違い
クエン酸リンスと同様に、石鹸シャンプー後の中和剤として「お酢(食酢)」を使う方法もあります。お酢の主成分は「酢酸」であり、クエン酸と同じく酸性です。
そのため、アルカリ性を中和し、キューティクルを引き締めるという基本的な働きはクエン酸リンスと共通しています。
お酢リンスとクエン酸リンスの比較
| 項目 | クエン酸リンス | お酢リンス |
|---|---|---|
| 主成分 | クエン酸 | 酢酸 |
| 形状 | 粉末・結晶(要溶解) | 液体(希釈して使用) |
| 匂い | ほぼ無臭 | お酢特有の匂い(乾けば消えやすい) |
| 入手性 | 薬局、スーパーなど | スーパーなど(穀物酢など) |
最大の違いは「匂い」でしょう。クエン酸はほぼ無臭ですが、お酢は特有のツンとした匂いがあります。
この匂いは、すすぎをしっかり行えば乾いた後にはほとんど残らないとされますが、匂いに敏感な方にとってはクエン酸の方が使いやすいかもしれません。
どちらも酸性であるため、濃度とすすぎには同様の注意が必要です。
クエン酸と育毛の関係性
クエン酸に、毛母細胞を活性化させるような「直接的な育毛効果」や「発毛効果」は、現在のところ科学的に認められていません。
しかし、クエン酸が持つ頭皮環境を整える働きは、健やかな髪が育つための「土台作り」として間接的に良い影響を与える可能性があります。
クエン酸に直接的な育毛効果はある?
前述の通り、クエン酸自体が髪を生やす指令を出したり、毛根に栄養を与えて発毛を促したりするという医学的根拠はありません。
育毛剤に含まれるミノキシジルやフィナステリドのような、薄毛治療に用いられる成分とは全く異なるものです。「クエン酸を使えば髪が増える」という期待は持つべきではありません。
頭皮環境を整えることの意義
クエン酸の役割は、あくまで「頭皮環境のサポート」です。
石鹸シャンプーによってアルカリ性に傾いた頭皮のpHを弱酸性に戻すこと、収れん作用で頭皮を適度に引き締めること、雑菌が繁殖しにくい弱酸性環境を維持すること。
これらはすべて、健やかな髪が育つための「土壌」を良好に保つことに繋がります。
畑の土壌が良くなければ良い作物が育たないように、頭皮環境が悪化している(乾燥、過剰な皮脂、フケ、かゆみなどがある)状態では、今ある髪の健康も損なわれやすく、新しい髪の成長にも悪影響が出かねません。
その土壌整備の一環として、クエン酸が役立つ場面がある、という位置づけです。
育毛剤や発毛剤との併用は可能か
クエン酸リンスと医薬品である発毛剤や、医薬部外品である育毛剤を併用すること自体は、時間を空ければ基本的には問題ないと考えられます。
ただし、重要な点がいくつかあります。 まず、クエン酸リンスを使用した後は、成分が頭皮に残らないよう、徹底的にすすぎを行う必要があります。
頭皮に酸が残った状態で育毛剤などを塗布すると、予期せぬ化学反応や刺激に繋がる可能性がゼロではありません。
また、育毛剤や発毛剤は、シャンプー・すすぎ・タオルドライの後の清潔な「乾いた」頭皮に使用するのが一般的です。
クエン酸リンスを使った場合でも、その後のすすぎと乾燥をしっかり行ってから、薬剤を使用するべきです。
頭皮に赤みや湿疹、傷などがある場合は、クエン酸リンスの使用自体が刺激になるため、控えるべきです。
特に皮膚科で薄毛治療を受けている方は、自己判断せず、医師にヘアケアの方法(石鹸シャンプーやクエン酸リンスの使用を含め)を相談することが最も安全で確実です。
頭皮環境と保湿に戻る
よくある質問
- クエン酸リンスは毎日使っても大丈夫?
-
石鹸シャンプーを毎日使うのであれば、その都度クエン酸リンスで中和ケアを行うこと自体は問題ありません。
石鹸シャンプーでアルカリ性に傾いた髪と頭皮を、そのまま放置する方が負担になる可能性があるためです。ただし、大切なのは「適切な濃度」と「十分なすすぎ」を毎日守ることです。
もし毎日の使用で頭皮の乾燥やかゆみなどを感じるようであれば、濃度を薄くするか、使用頻度を見直す必要があります。
- 市販のクエン酸(食用・掃除用)は髪に使えますか?
-
ヘアケア用として販売されているクエン酸もありますが、「食用」グレードのクエン酸(添加物が入っていない純粋なもの)であれば、髪に使用しても基本的には問題ありません。
「掃除用(工業用)」として販売されているものの中には、純度が低いものや、他の洗浄成分が混ざっている可能性も否定できないため、避けた方が無難です。
安全性を考慮し、パッケージの成分表示を確認し「クエン酸100%」や「食品添加物」と記載のあるものを選ぶことをお勧めします。
- クエン酸リンスの使用感で他に気をつけることは?
-
クエン酸リンスは、一般的なトリートメントやコンディショナーとは異なり、髪をシリコンなどでコーティングしてヌルヌルさせるものではありません。
あくまで中和が目的なので、仕上がりは「キュッ」とした感触や、素髪に近いサラッとした感触になります。この使用感を物足りない(パサつく)と感じる方もいます。
その場合は、タオルドライ後にヘアオイルや洗い流さないトリートメントを毛先中心につけるなど、別の形で油分や保湿を補うケアを組み合わせることも検討すると良いでしょう。
- クエン酸で髪の色が明るくなることはありますか?
-
非常に高濃度のクエン酸を長時間髪に付着させるなど、極端な使い方をすれば髪のメラニン色素に影響を与える可能性は理論上ゼロではありませんが、石鹸シャンプー後の中和に使う「ごく薄い濃度」のクエン酸リンスを「すぐに洗い流す」という通常の使い方で、髪の色が目に見えて明るくなる(脱色される)ことは、まず考えられません。
もし髪色の変化が気になる場合は、使用を中止してください。
Reference
SHI, Xiangguang, et al. Disrupted citric acid metabolism inhibits hair growth. The Journal of Dermatology, 2022, 49.10: 1037-1048.
ZHANG, Daijiazi; BAGHDADLI, Nawel; GREAVES, Andrew J. Reinforcing chemically treated human hair with citric acid. International Journal of Cosmetic Science, 2025.
MAYER, Wolfgang, et al. Biomolecules of fermented tropical fruits and fermenting microbes as regulators of human hair loss, hair quality, and scalp microbiota. Biomolecules, 2023, 13.4: 699.
LANJEWAR, Ameya, et al. Review on Hair Problem and its Solution. Journal of Drug Delivery and Therapeutics, 2020, 10.3: 322-329.
SOMASUNDARAM, Arun; MURUGAN, Kalaiarasi. Current trends in hair care in men. Cosmoderma, 2024, 4.
DE PAULA, Joane Nathache Hatsbach; BASÍLIO, Flávia Machado Alves; MULINARI-BRENNER, Fabiane Andrade. Effects of chemical straighteners on the hair shaft and scalp. Anais brasileiros de dermatologia, 2022, 97.2: 193-203.
DAVIS, Michael G., et al. Scalp application of antioxidants improves scalp condition and reduces hair shedding in a 24‐week randomized, double‐blind, placebo‐controlled clinical trial. International Journal of Cosmetic Science, 2021, 43: S14-S25.
TRÜEB, Ralph M. The hair cycle and its relation to nutrition. In: Nutrition for Healthy Hair: Guide to Understanding and Proper Practice. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 37-109.
DUBIEF, C., et al. Hair care products. In: The Science of Hair Care. CRC Press, 1986. p. 155-196.