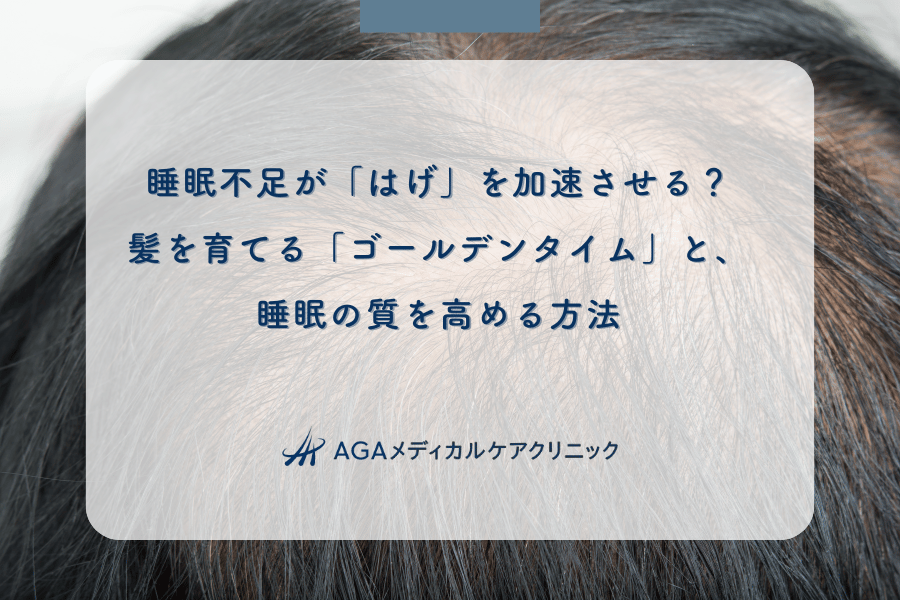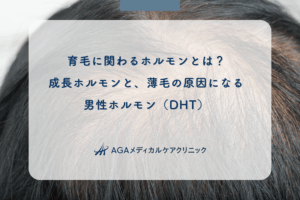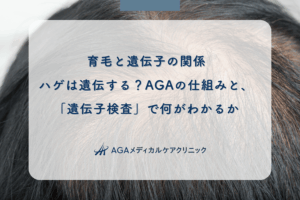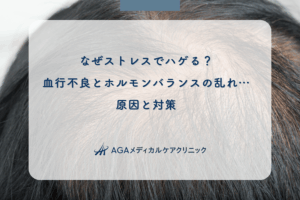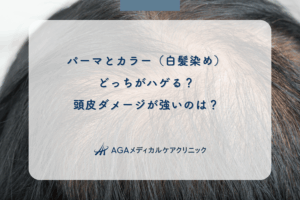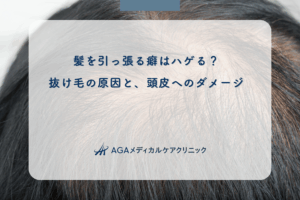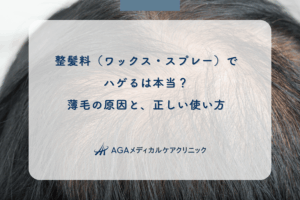鏡を見るたびに、髪のボリュームが減ってきたように感じる。枕についた抜け毛の数に、朝からため息が出る。もしかして、最近の忙しさによる「睡眠不足」が原因かもしれない……。
そんな不安を抱えていませんか。仕事やプライベートで忙しい日々を送る中、睡眠時間を確保するのは難しいものです。しかし、睡眠不足が「はげ」や薄毛の進行に影響を与える可能性は否定できません。
この記事では、睡眠と髪の健康がどのように関わっているのかを掘り下げ、髪を育てるために本当に大切な睡眠のポイント、そして今夜から実践できる睡眠の質を高める具体的な方法を紹介します。
この記事を読めば、睡眠への意識が変わり、健やかな髪を取り戻すための一歩を踏み出せるはずです。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
「はげ」と睡眠不足の気になる関係性
睡眠不足が続くと、髪の健康にさまざまな悪影響が及び、「はげ」の進行を早める可能性があります。
髪の成長に必要なホルモンの分泌が減少し、頭皮の血流が悪化するため、髪が十分に育ちにくくなるのです。
睡眠時間が短いとなぜ髪に悪いのか
睡眠時間が不足すると、体は生命維持に必要な活動を優先します。そのため、髪の毛のような生命維持に直接関わらない部分への栄養供給や修復活動は後回しにされがちです。
髪の毛は、毛根にある「毛母細胞」が細胞分裂を繰り返すことで成長します。この細胞分裂には、十分な栄養と酸素、そして成長ホルモンが必要です。
睡眠が足りないと、これらの供給が滞り、毛母細胞の活動が低下します。結果として、髪の毛が細くなったり、成長しきる前に抜け落ちたりすることが増え、薄毛や「はげ」が目立つようになるのです。
成長ホルモンと髪の成長
成長ホルモンは、その名の通り体の成長を促すだけでなく、成人の体においては細胞の修復や新陳代謝を活発にする重要な役割を担います。
髪の毛の成長にも深く関わっており、毛母細胞の分裂を促進し、タンパク質の合成を助けます。この成長ホルモンは、主に睡眠中に分泌されます。
特に、深いノンレム睡眠の段階で最も多く分泌されることが分かっています。
睡眠不足や睡眠の質が低い状態が続くと、成長ホルモンの分泌量が減少し、髪の成長が妨げられ、「はげ」の要因の一つとなります。
成長ホルモンの主な役割(髪関連)
| 役割 | 具体的な働き |
|---|---|
| 毛母細胞の活性化 | 毛母細胞の分裂を促し、髪の成長をサポートする。 |
| タンパク質合成の促進 | 髪の主成分であるケラチン(タンパク質)の合成を助ける。 |
| 頭皮の修復 | 日中に受けた紫外線や乾燥などのダメージから頭皮を修復する。 |
血流悪化が引き起こす頭皮への影響
睡眠不足は、自律神経のバランスを乱す大きな要因です。自律神経には、体を活動的にする「交感神経」と、リラックスさせる「副交感神経」があります。
通常、日中は交感神経が優位に、夜間や睡眠中は副交感神経が優位に働きます。しかし、睡眠不足が続くと交感神経が過剰に働き続け、血管が収縮しやすくなります。
特に頭皮の毛細血管は非常に細いため、この影響を受けやすいのです。血流が悪化した頭皮には、髪の成長に必要な栄養素や酸素が十分に行き渡らなくなります。
これが「はげ」や抜け毛、髪のやせ細りを引き起こす原因となります。
ストレスと睡眠不足の悪循環
ストレスを感じると、体は緊張状態になり交感神経が優位になります。その結果、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりと、睡眠の質が低下します。
そして、睡眠不足になると、今度はストレスを感じやすくなり、さらに睡眠の質が悪化するという悪循環に陥りがちです。
ストレス状態が続くと、ホルモンバランスが乱れたり、血管が収縮して頭皮の血流が悪くなったりと、髪にとって良くない状況が生まれます。
この悪循環を断ち切り、「はげ」の進行を防ぐためにも、睡眠の確保とストレス管理は非常に重要です。
髪を育てる「ゴールデンタイム」は本当に存在する?
「夜10時から深夜2時までは、髪のゴールデンタイム」という話を耳にしたことがあるかもしれません。
この時間帯に成長ホルモンが多く分泌されるためと言われていますが、現代の生活スタイルではこの時間に寝るのは難しい人も多いでしょう。
実際のところ、この「ゴールデンタイム」は、時間帯そのものよりも「睡眠の深さ」が重要です。
成長ホルモンが最も分泌される時間帯
成長ホルモンは、特定の時間帯に自動的に分泌されるわけではありません。最も多く分泌されるのは、「入眠後の最初の深いノンレム睡眠中」です。
つまり、夜10時に寝ても、深夜2時に寝ても、寝始めてから最初に訪れる深い眠りのタイミングで、成長ホルモンの分泌はピークを迎えます。
したがって、何時に寝るかということ以上に、いかに深く質の高い睡眠をとるかが、髪の成長にとっては大切なのです。
「シンデレラタイム」の真実
「夜10時から深夜2時」という時間帯は、美容業界などで「シンデレラタイム」と呼ばれ、肌の新陳代謝が活発になる時間として広まりました。
これが転じて、髪の成長にも良い時間帯とされるようになったと考えられます。しかし、これはあくまで生活リズムが整っていた時代の目安です。
現代人の多様なライフスタイルにおいては、この時間帯にこだわる必要は必ずしもないと言えます。
それよりも、毎日決まった時間に寝て、規則正しい睡眠リズムを作ることの方が、ホルモンバランスを整え、髪の健康を保つ上では効果的です。
時間帯よりも「眠り始めの90分」が重要な理由
睡眠には、浅い「レム睡眠」と深い「ノンレム睡眠」があり、これらが約90分のサイクルで繰り返されます。特に重要なのが、入眠後に最初に訪れるノンレム睡眠です。
この「眠り始めの約90分」は、睡眠全体の中で最も深い眠り(徐波睡眠)が得られる時間帯であり、成長ホルモンもこの時に集中的に分泌されます。
たとえ睡眠時間が短くても、この最初の90分間の質が高ければ、成長ホルモンの分泌をある程度確保できます。
逆に、寝つきが悪かったり、すぐに目が覚めたりして、この深い眠りが妨げられると、成長ホルモンの分泌が不足し、「はげ」に繋がる可能性があります。
睡眠サイクルの理解
私たちの睡眠は、一晩に「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」のサイクルを4~5回繰り返しています。
ノンレム睡眠はさらに眠りの深さによって段階が分かれており、入眠直後に最も深いノンレム睡眠が現れ、明け方になるにつれて浅くなっていきます。
一方、レム睡眠は体を休めつつ脳が活動している状態で、記憶の整理などを行っています。このサイクルが乱れると、睡眠の質は低下します。
睡眠の段階(レム・ノンレム)
| 睡眠の種類 | 特徴 | 髪への関わり |
|---|---|---|
| ノンレム睡眠 (深い) | 脳も体も深く休息。入眠直後に最も深くなる。 | 成長ホルモンが最も多く分泌され、細胞の修復や成長を促す。 |
| レム睡眠 (浅い) | 体は休息しているが、脳は活動。夢を見ることが多い。 | 記憶の整理や定着。直接的な髪の成長への関与は少ない。 |
睡眠の質が低いサインと髪への悪影響
睡眠時間が足りていても、質が低ければ意味がありません。
寝つきが悪い、夜中に目が覚める、朝起きても疲れが取れていないといったサインは、睡眠の質が低い可能性を示しており、これらは髪の健康にも悪影響を及ぼします。
寝つきが悪い・夜中に何度も目が覚める
布団に入ってから30分以上眠れない「入眠障害」や、睡眠中に何度も目が覚めてしまう「中途覚醒」は、睡眠の質が低い代表的なサインです。
これらの状態では、深いノンレム睡眠に達するまでに時間がかかったり、深い睡眠が妨げられたりするため、成長ホルモンの分泌が不十分になります。
また、眠りが浅い状態が続くと、交感神経が優位になりやすく、頭皮の血流が悪化し、「はげ」の原因となる毛母細胞の活動低下を招きます。
朝起きても疲れが取れていない
十分な時間寝たはずなのに、朝スッキリ起きられない、日中も強い眠気を感じる、体がだるいといった場合、「熟眠障害」の可能性があります。
これは、睡眠時間はとれていても、深い眠りが得られていない状態です。睡眠の最大の目的である「疲労回復」ができていない証拠であり、当然、髪の毛の成長や頭皮の修復も十分に行われていません。
このような状態が続けば、髪は栄養不足となり、細く弱々しくなってしまいます。
睡眠の質低下が招く頭皮環境の乱れ
睡眠の質が低いと、自律神経のバランスが崩れ、皮脂の分泌が過剰になったり、逆に乾燥しやすくなったりと、頭皮環境が不安定になります。
また、体の免疫機能も低下するため、頭皮が炎症を起こしやすくなったり、フケやかゆみが発生しやすくなったりします。不健康な頭皮環境は、健康な髪が育つ土壌を失うことと同じです。
「はげ」を予防し、健やかな髪を育てるためには、土壌である頭皮環境を整えることが重要であり、それには質の高い睡眠が欠かせません。
睡眠不足による頭皮トラブル例
| トラブル | 原因 |
|---|---|
| 皮脂の過剰分泌 | ホルモンバランスや自律神経の乱れ。 |
| 頭皮の乾燥・フケ | 新陳代謝(ターンオーバー)の乱れ、血行不良。 |
| かゆみ・炎症 | 免疫機能の低下、皮脂バランスの崩れ。 |
今夜から実践!睡眠の質を高めるための具体的な方法
睡眠の質を高めるためには、日中の過ごし方から就寝前の習慣、寝室の環境まで、総合的な見直しが必要です。
すぐに取り組める簡単なことから始めて、自分に合った方法を見つけましょう。
就寝前のリラックス習慣
寝る前に心身ともにリラックス状態を作ることは、スムーズな入眠と深い睡眠に繋がります。副交感神経を優位にし、自然な眠気を促すための習慣を取り入れましょう。
入浴のタイミングと温度
就寝の約90分前に、38~40度程度のぬるめのお湯に15分ほど浸かるのがおすすめです。
入浴によって一時的に上がった深部体温(体の内部の温度)が、就寝時にかけて下がっていく過程で、強い眠気が訪れます。熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまうため逆効果です。
時間がない場合は、足湯だけでも効果が期待できます。
リラックスできる過ごし方の例
- 穏やかな音楽を聴く
- アロマを焚く(ラベンダーなど)
- カフェインレスの温かい飲み物を飲む
- 軽いストレッチ
睡眠環境を整える
快適な睡眠環境は、五感(視覚、聴覚、触覚、嗅覚、温熱感覚)を刺激しない状態が理想です。寝室が「寝るための場所」として最適化されているか確認しましょう。
寝室の温度・湿度・光・音
寝室の環境は、睡眠の質に直接影響します。特にスマートフォンやPCから発せられるブルーライトは、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌を抑制するため、就寝1時間前からは見るのを控えるのが賢明です。
部屋の照明も、暖色系の間接照明などに切り替えて、徐々に暗くしていくと良いでしょう。
快適な寝室環境の目安
| 要素 | 目安 | ポイント |
|---|---|---|
| 温度 | 夏:25~27度 / 冬:18~20度 | エアコンや寝具で調整。 |
| 湿度 | 50~60% | 加湿器や除湿器を活用。 |
| 光 | 真っ暗または豆電球程度 | 遮光カーテンを利用。ブルーライトを避ける。 |
| 音 | 40デシベル以下(静かな図書館程度) | 耳栓やホワイトノイズマシンの利用も。 |
食事と飲み物の注意点
就寝直前の食事は、消化活動のために胃腸が働くため、内臓が休まらず睡眠が浅くなります。食事は就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。
また、特定の飲み物は睡眠を妨げるため、摂取する時間に注意が必要です。
カフェイン・アルコールの摂取タイミング
カフェインやアルコールは、睡眠の質を著しく低下させる可能性があります。
特にアルコールは、寝つきを良くするように感じられますが、実際には睡眠を浅くし、夜中に目が覚めやすくなる原因となります。
睡眠に影響する飲食物と対策
| 種類 | 影響 | 対策 |
|---|---|---|
| カフェイン | 覚醒作用。持続時間は4~8時間。 | 就寝の4時間前からは控える。(コーヒー、紅茶、緑茶など) |
| アルコール | 寝つきは早だが、睡眠が浅くなり中途覚醒が増える。 | 寝酒は避ける。飲む場合は就寝の3時間前まで。 |
| 就寝直前の食事 | 消化活動が睡眠を妨げる。 | 就寝の3時間前までに済ませる。 |
日中の過ごし方
夜の良質な睡眠は、日中の過ごし方によって作られます。特に「光」と「運動」が重要な鍵を握ります。朝起きたら、まずは太陽の光を浴びましょう。
太陽光を浴びることで、体内時計がリセットされ、夜になると自然にメラトニンが分泌されるようになります。
また、日中に適度な運動をすることも、夜の寝つきを良くし、睡眠を深くする効果があります。ウォーキングやジョギングなど、軽い有酸素運動を習慣づけることをおすすめします。
睡眠改善と併せて行いたい頭皮ケア
質の高い睡眠で体の内側から髪の成長をサポートすると同時に、外側からの頭皮ケアも行うことで、より効果的に「はげ」の予防・改善が期待できます。
頭皮環境を清潔に保ち、血行を促進することが基本です。
正しいシャンプーの方法
毎日のシャンプーは、頭皮の汚れや余分な皮脂を落とし、清潔に保つために重要です。
しかし、洗いすぎたり、爪を立ててゴシゴシ洗ったりすると、頭皮を傷つけ、必要な皮脂まで奪ってしまい、乾燥や炎症の原因になります。
指の腹で優しくマッサージするように洗い、すすぎ残しがないよう十分すぎるほどしっかりと洗い流すことが大切です。
シャンプー手順のポイント
- 洗う前にブラッシングでほこりを落とす
- お湯で十分に予洗いする
- シャンプーは手のひらで泡立ててから頭皮につける
- 指の腹で頭皮をマッサージするように洗う
- すすぎは時間をかけて丁寧に行う
頭皮マッサージのすすめ
頭皮マッサージは、硬くなった頭皮をほぐし、血行を促進するのに効果的です。血流が良くなれば、毛母細胞に栄養が行き渡りやすくなります。
シャンプー中や、育毛剤をつけた後など、リラックスしている時に行うのが良いでしょう。
指の腹を頭皮に密着させ、頭蓋骨から頭皮を動かすようなイメージで、気持ち良いと感じる強さで圧をかけたり、円を描いたりします。爪を立てないように注意してください。
育毛剤の活用
睡眠や生活習慣の改善、セルフケアを行っても、抜け毛や薄毛の進行が気になる場合は、育毛剤の使用を検討するのも一つの方法です。
育毛剤には、頭皮の血行を促進したり、毛母細胞の働きを活性化させたり、頭皮環境を整えたりする成分が含まれています。自分の頭皮の状態や、「はげ」の原因に合った製品を選ぶことが重要です。
睡眠改善で内側から、育毛剤で外側からアプローチすることで、相乗効果が期待できます。
睡眠だけじゃない?「はげ」のその他の要因
睡眠不足は「はげ」を加速させる一因ですが、薄毛や抜け毛の原因はそれだけではありません。
複数の要因が複雑に絡み合っていることが多いため、睡眠以外の要因についても理解しておくことが大切です。
遺伝的要因 (AGA)
男性の薄毛の最も一般的な原因は「AGA(男性型脱毛症)」です。
これは、男性ホルモン(テストステロン)が酵素(5αリダクターゼ)の働きによって「DHT(ジヒドロテストステロン)」という強力な男性ホルモンに変換され、このDHTが毛乳頭細胞にある受容体と結びつくことで、髪の成長サイクル(ヘアサイクル)を乱し、髪が太く長く成長する前に抜け落ちてしまう現象です。
このDHTへの感受性は遺伝的な要素が強いとされています。睡眠不足やストレスは、このAGAの進行を早める可能性がありますが、直接的な原因ではありません。
食生活の乱れ
髪の毛は、私たちが食べたものから作られています。
偏った食事や無理なダイエットで栄養が不足すると、髪の毛の主成分であるタンパク質(ケラチン)や、その合成を助けるビタミン、ミネラルが不足し、健康な髪が育ちません。
特に外食やコンビニ食が多い人は、脂質や糖質過多、ビタミン・ミネラル不足になりがちです。
髪の成長に必要な栄養素
| 栄養素 | 主な役割 | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料。 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける。 | 牡蠣、レバー、牛肉 |
| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝、皮脂分泌の調整。 | 豚肉、レバー、マグロ、カツオ |
過度なストレス
強いストレスを感じると、交感神経が優位になり、血管が収縮して頭皮の血流が悪化します。これは睡眠不足と同様に、髪の成長に必要な栄養が届きにくくなる原因です。
また、ストレスはホルモンバランスの乱れを引き起こし、皮脂の過剰分泌や頭皮環境の悪化を招くこともあります。ストレスが原因で円形脱毛症を発症するケースも知られています。
喫煙・飲酒習慣
喫煙は、ニコチンの作用によって全身の血管を収縮させ、血流を著しく悪化させます。もちろん頭皮の毛細血管も例外ではありません。
また、タバコに含まれる多くの有害物質は、髪の成長に必要なビタミン類を大量に消費・破壊してしまいます。
過度な飲酒は、アルコールの分解のために肝臓で多くの栄養素(特にビタミンや亜鉛)が使われるため、髪に回る栄養が不足しがちになります。
「はげ」を気にするのであれば、禁煙や節酒は重要な対策となります。
それでも改善しない場合は?
睡眠の質を高め、生活習慣を見直し、セルフケアを行っても、抜け毛や薄毛の改善が見られない場合、他の原因が隠れている可能性があります。
一人で悩み続けず、専門家の助けを借りることも検討しましょう。
睡眠障害の可能性
寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める、朝起きられないといった症状が長期間続く場合、単なる睡眠不足ではなく、「睡眠時無呼吸症候群」や「不眠症」などの睡眠障害の可能性があります。
睡眠障害は、低酸素状態や交感神経の過緊張を引き起こし、髪だけでなく全身の健康に重大な影響を及ぼします。
いびきがひどい、日中の眠気が異常に強いなどの症状があれば、まずは睡眠専門のクリニックを受診し、検査を受けることを推奨します。
専門クリニックへの相談
「はげ」の原因がAGA(男性型脱毛症)である場合、睡眠や生活習慣の改善だけでは、進行を止めることは難しいです。AGAは進行性の脱毛症であり、放置すると薄毛は徐々に広がっていきます。
最近では、薄毛治療を専門に行うクリニックが増えており、医師による診断のもと、医学的根拠に基づいた治療を受けることができます。
自分の薄毛の原因が何なのかを正確に知るためにも、一度専門医に相談してみる価値はあります。
AGA治療の選択肢
AGA治療は、主に内服薬や外用薬を用いて行われます。内服薬は、AGAの原因であるDHTの生成を抑える働きがあり、抜け毛を減らし、ヘアサイクルを正常に戻す効果が期待できます。
外用薬(塗り薬)は、頭皮の血流を改善し、毛母細胞の働きを活性化させることで、発毛を促進します。これらの治療は、早期に開始するほど効果が出やすいとされています。
睡眠改善と並行して専門的な治療を行うことで、より確かな改善が期待できるでしょう。
ストレス・睡眠・運動不足に戻る
よくある質問
- 毎日何時間寝れば十分ですか?
-
必要な睡眠時間には個人差がありますが、一般的に成人では6時間から8時間程度が目安とされています。ただし、時間よりも「質」が重要です。
朝起きた時に「よく寝た」と感じられるか、日中に強い眠気で困ることがないかが、自分にとって十分な睡眠がとれているかのバロメーターになります。
時間確保が難しい場合でも、「眠り始めの90分」の質を高めることを意識してください。
- 週末の寝だめは効果がありますか?
-
平日の睡眠不足を週末の「寝だめ」で解消しようとする人もいますが、あまりおすすめできません。
寝だめをすると、体内時計のリズムが大きく乱れてしまい、かえって週明けの月曜日に体がだるくなる(社会的ジェットラグ)ことがあります。
平日の睡眠不足は、週末にまとめて取り戻すのではなく、毎日少しずつでも質の高い睡眠を確保することで解消するのが理想です。
もし寝だめをする場合でも、いつもより1~2時間程度長く寝る程度にとどめ、起きる時間はなるべく変えないようにするのがコツです。
- 昼寝は髪に良いですか?悪いですか?
-
日中の適度な昼寝(15~20分程度の短い仮眠)は、午後の眠気を解消し、パフォーマンスを向上させる効果があります。
その結果、夜の睡眠の質が高まるなら、間接的に髪にも良い影響があると言えます。ただし、30分以上の長い昼寝や、夕方以降の昼寝は、夜の睡眠を妨げる原因になるため避けるべきです。
昼寝をするなら、午後3時までに、20分以内と決めて行うと良いでしょう。
- 睡眠導入剤の使用は髪に影響しますか?
-
医師の処方のもと、用法・用量を守って適切に睡眠導入剤を使用する場合、それが直接的に「はげ」の原因になることは考えにくいです。
むしろ、重度の不眠症で全く眠れない状態が続く方が、髪を含めた全身の健康に悪影響を及ぼします。
睡眠薬に頼ることで質の高い睡眠が確保できるようになるのであれば、結果的に髪にとってもプラスになる可能性があります。
ただし、自己判断での使用や長期の連用は避け、必ず医師に相談しながら使用してください。
Reference
NATARELLI, Nicole; GAHOONIA, Nimrit; SIVAMANI, Raja K. Integrative and mechanistic approach to the hair growth cycle and hair loss. Journal of clinical medicine, 2023, 12.3: 893.
ILIAS, Ioannis, et al. Complexity and non-linear description of diurnal cortisol and growth hormone secretory patterns before and after sleep deprivation. Endocrine Regulations, 2002, 36.2: 63-72.
HORESH, Elijah J.; CHÉRET, Jérémy; PAUS, Ralf. Growth hormone and the human hair follicle. International journal of molecular sciences, 2021, 22.24: 13205.
GRYMOWICZ, Monika, et al. Hormonal effects on hair follicles. International journal of molecular sciences, 2020, 21.15: 5342.
REDWINE, Laura, et al. Effects of sleep and sleep deprivation on interleukin-6, growth hormone, cortisol, and melatonin levels in humans. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2000, 85.10: 3597-3603.
JANKOWSKI, Konrad S., et al. Chronotype, social jetlag and sleep loss in relation to sex steroids. Psychoneuroendocrinology, 2019, 108: 87-93.
VAN CAUTER, Eve; LEPROULT, Rachel; PLAT, Laurence. Age-related changes in slow wave sleep and REM sleep and relationship with growth hormone and cortisol levels in healthy men. Jama, 2000, 284.7: 861-868.
BEROUKHIM, Gabriela; ESENCAN, Ecem; SEIFER, David B. Impact of sleep patterns upon female neuroendocrinology and reproductive outcomes: a comprehensive review. Reproductive biology and endocrinology, 2022, 20.1: 16.
LI, Pengjun, et al. Sleep deprivation modifies noise-induced cochlear injury related to the stress hormone and autophagy in female mice. Frontiers in Neuroscience, 2019, 13: 1297.
JIAO, Yang, et al. Sleep disorders impact hormonal regulation: unravelling the relationship among sleep disorders, hormones and metabolic diseases. Diabetology & Metabolic Syndrome, 2025, 17.1: 305.