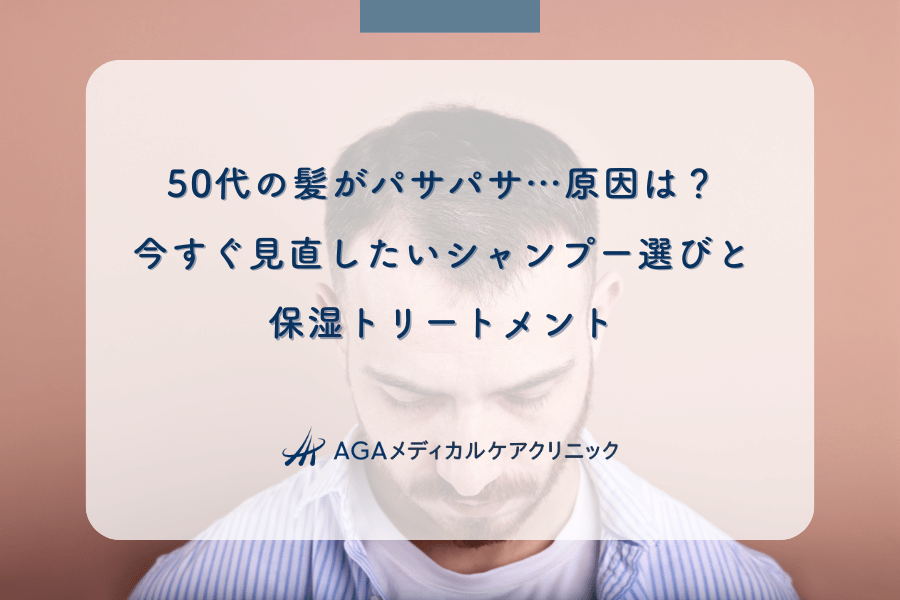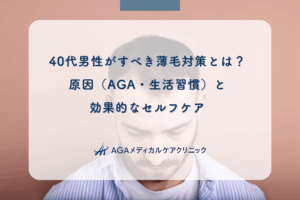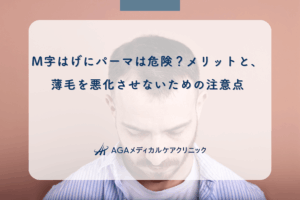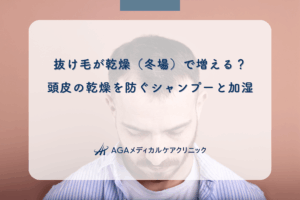「最近、髪がパサパサしてまとまらない…」50代を迎え、そんな悩みを抱えていませんか。かつてのツヤやハリが失われ、スタイリングもうまくいかないと、気分も沈みがちです。
そのパサつき、実は年齢によるものだけではないかもしれません。
この記事では、50代の髪がパサパサになる主な原因を深掘りし、今すぐ見直すべきシャンプー選びのポイント、そして潤いを取り戻すための効果的な保湿トリートメントの方法まで、具体的に解説します。毎日のヘアケアを見直すことで、髪の状態は改善できます。
今日からできる対策で、潤いのある健康的な髪を取り戻しましょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
50代の髪がパサパサになる主な原因とは
50代の髪がパサパサになるのは、加齢による頭皮環境の変化と髪内部の水分・油分の減少が大きく関係しています。
年齢を重ねることで、体内で起こるさまざまな変化が、髪質に直接影響を与えるのです。
加齢による頭皮の乾燥
年齢とともに、頭皮の皮脂分泌量は減少する傾向にあります。皮脂は、頭皮の水分蒸発を防ぎ、外部の刺激から守る天然のバリア(皮脂膜)の役割を担っています。
この皮脂が減ることで頭皮は乾燥しやすくなり、結果として、そこから生えてくる髪も水分が不足し、パサついた状態になりやすいのです。
特に男性は、もともと皮脂が多い傾向にありますが、50代以降はそのバランスが崩れやすくなります。
髪内部の水分保持力の低下
髪の毛は、主に「ケラチン」というタンパク質で構成されています。
健康な髪は、内部に水分を保持するための成分(例えばセラミドやCMCと呼ばれる脂質)が整然と並び、キューティクルによって守られています。
しかし、加齢によってこれらの成分が減少したり、キューティクルがダメージを受けて剥がれやすくなったりします。
すると、髪内部の水分が流出しやすくなり、髪が本来持つ水分保持力を失い、パサつきやゴワつきを感じるようになります。
ホルモンバランスの変化
50代は、男女ともにホルモンバランスが大きく変動する時期です。
特に男性ホルモン(テストステロン)と女性ホルモン(エストロゲン)のバランスの変化は、髪の成長サイクル(ヘアサイクル)に影響を与えます。
髪が太く長く成長する「成長期」が短くなり、髪が十分に育たないまま細くなったり、うねりを伴って生えてきたりすることがあります。
細くうねった髪は、まとまりにくく、光も乱反射するため、余計にパサついて見えてしまいます。
血行不良による栄養不足
髪は、毛根にある毛母細胞が、毛細血管から運ばれてくる栄養素と酸素を受け取って成長します。
しかし、加齢や運動不足、ストレス、食生活の乱れなどによって頭皮の血行が悪くなると、髪の成長に必要な栄養素が毛根まで十分に行き渡らなくなります。
栄養不足の状態が続くと、毛母細胞は活発に働けず、結果として生えてくる髪は弱く、細く、パサついた髪質になりやすいのです。
パサつきを悪化させるNGヘアケア習慣
良かれと思って続けている毎日のケアが、実は髪のパサつきを助長している可能性があります。
洗浄力の強すぎるシャンプーや間違った洗い方、ドライヤーの使い方は、50代のデリケートな頭皮と髪にとって大きな負担となります。
洗浄力の強すぎるシャンプーの使用
「頭皮のベタつきやニオイが気になるから」と、洗浄力の非常に強いシャンプー(高級アルコール系など)を毎日使っていませんか。
確かに洗い上がりのスッキリ感は得られますが、これらのシャンプーは頭皮を守るために必要な皮脂まで根こそぎ奪い取ってしまうことがあります。
皮脂を失った頭皮はバリア機能が低下し、ますます乾燥します。乾燥した頭皮は、潤いのある健康な髪を育てられません。
熱いお湯でのシャンプー
熱いお湯(例えば40度以上)で髪を洗うと、さっぱりとして気持ちが良いかもしれません。しかし、高温のお湯は頭皮の保湿成分(天然保湿因子やセラミドなど)を必要以上に流出させてしまいます。
シャワーの温度設定は、体温より少し高めの38度程度のぬるま湯にするのが、頭皮と髪の潤いを守る上で重要です。
髪をゴシゴシ擦る洗い方
髪は濡れると、表面のキューティクルが開いて非常にデリケートな状態になります。
この時に、爪を立てて頭皮を掻いたり、髪の毛同士を掴んでゴシゴシと擦り合わせたりする洗い方は、キューティクルを傷つけ、剥がしてしまう最大の原因です。
キューティクルが傷つくと、内部のタンパク質や水分が流出し、パサつきや枝毛・切れ毛を招きます。
ドライヤーの当てすぎと自然乾燥
シャンプー後、ドライヤーの熱風を同じ箇所に長時間当てすぎると、髪のタンパク質が熱によって変性(いわゆる「タンパク変性」)を起こし、髪が硬くなり、パサつきが悪化します。
かといって、面倒だからと自然乾燥させるのも問題です。
髪が濡れたままの時間が長いと、雑菌が繁殖しやすくなり頭皮トラブルの原因になるほか、キューティクルが開いたままの状態が続くため、摩擦によるダメージを受けやすくなります。
50代のパサつき髪に適したシャンプー選び
50代のシャンプー選びは、「洗浄力」よりも「保湿力」と「頭皮への優しさ」を優先することが重要です。
洗浄成分に注目し、アミノ酸系やベタイン系といったマイルドな洗い上がりの製品を選びましょう。
洗浄成分で選ぶアミノ酸系・ベタイン系
シャンプーの品質は、洗浄成分(界面活性剤)でほぼ決まると言っても過言ではありません。50代の乾燥しがちな頭皮には、必要な潤いを残しつつ、汚れだけを優しく落とす洗浄成分が適しています。
主な洗浄成分の特徴
| 洗浄成分の種類 | 特徴 | こんな人向け |
|---|---|---|
| アミノ酸系 (ココイル~、ラウロイル~など) | 洗浄力がマイルドで保湿力が高い。弱酸性で頭皮への刺激が少ない。 | 乾燥肌、敏感肌、パサつきが気になる人 |
| ベタイン系 (~ベタイン、~アラニンなど) | ベビーシャンプーにも使われるほど低刺激。アミノ酸系と併用されることも多い。 | 特に刺激を避けたい人、頭皮が荒れやすい人 |
| 高級アルコール系 (ラウリル硫酸~、ラウレス硫酸~) | 洗浄力が非常に高く、泡立ちが良い。皮脂をしっかり落とす。 | 脂性肌、ワックスなどを多用する人(ただし毎日の使用は注意) |
保湿・補修成分の有無をチェック
洗浄成分と合わせて、どのような保湿成分や補修成分が含まれているかも確認しましょう。髪と頭皮に潤いを与える「セラミド」「ヒアルロン酸」「コラーゲン」「グリセリン」などは代表的な保湿成分です。
また、髪の主成分である「ケラチン(加水分解ケラチン)」や、ダメージを補修する「ヘマチン」「ペリセア」などが配合されていると、洗いながら髪のコンディションを整える助けになります。
シリコン(ジメチコンなど)の役割を理解する
「ノンシリコン」が一時期流行しましたが、シリコン(ジメチコン、シクロペンタシロキサンなど)が必ずしも悪いわけではありません。
シリコンは髪の表面をコーティングし、指通りを滑らかにし、摩擦によるダメージを防ぐ役割があります。
パサつきや広がりがひどい場合、シリコン入りのシャンプーやコンディショナーを使うことで、手触りが劇的に改善することも多いです。
ただし、頭皮にシリコンが残留すると毛穴詰まりの原因にもなり得るため、すすぎは通常よりも丁寧に行うことが大切です。
頭皮環境を整える成分
50代は頭皮環境も乱れがちです。
フケやかゆみを防ぐ抗炎症成分「グリチルリチン酸2K」や、頭皮の血行を促進する「センブリエキス」「ビタミンE誘導体」など、頭皮環境を健やかに保つための成分が配合された薬用シャンプー(医薬部外品)を選ぶのも良い選択肢です。
今日から実践正しいシャンプーの方法
シャンプーは「髪」ではなく「頭皮」を洗うものです。どんなに良いシャンプーを使っても、洗い方が間違っていては効果が半減します。
正しい手順で頭皮の汚れをしっかり落とし、髪へのダメージを最小限に抑える洗い方を身につけましょう。
ブラッシングと予洗いの徹底
シャンプーをする前に、まずは乾いた状態で髪をブラッシングします。このブラッシングによって、髪表面のホコリや汚れを浮かせ、髪の絡まりをほどくことができます。
次に、シャンプーをつける前に、ぬるま湯(38度程度)で頭皮と髪をしっかりと「予洗い」します。目安は1分半から2分程度。
これだけでも髪についた汚れの7割程度は落ちると言われており、シャンプーの泡立ちも格段に良くなります。
シャンプーは手のひらで泡立てる
シャンプーの原液を直接頭皮につけるのは避けてください。洗浄成分が濃縮されたまま一箇所につくと、刺激になったり、すすぎ残しの原因になったりします。
適量を手のひらに取り、少量のお湯を加えながら両手で軽くなじませ、ある程度泡立ててから頭皮の数カ所(側頭部、後頭部、頭頂部など)に分けてつけていきます。
指の腹でマッサージするように洗う
洗い方の基本は、指の腹を使うことです。絶対に爪を立ててはいけません。頭皮を傷つけ、炎症の原因となります。
指の腹を頭皮に密着させ、頭蓋骨を動かすようなイメージで、下から上へ(襟足から頭頂部へ)と小刻みに動かしながらマッサージするように洗います。
特に洗い残しやすい襟足や耳の後ろ、生え際は意識して丁寧に洗いましょう。髪の毛自体は、頭皮を洗った泡が流れていくだけで十分汚れは落ちます。ゴシゴシと擦る必要はありません。
すすぎは「洗い」の2倍の時間をかける
シャンプーで最も重要なのが「すすぎ」です。シャンプー成分や汚れが頭皮や髪に残っていると、かゆみ、フケ、乾燥、ニオイなど、あらゆる頭皮トラブルの原因となります。
泡が消えてからもしばらく、目安としてはシャンプーで洗っていた時間の2倍以上の時間をかけて、徹底的にすすぎます。
生え際、耳の後ろ、襟足は特に念入りに、シャワーヘッドを地肌に近づけるようにして洗い流しましょう。
パサつきを集中ケアする保湿トリートメント
髪のパサつきを改善するには、シャンプーで汚れを落とした後の保湿トリートメントが欠かせません。
髪内部に失われた水分と油分を補給し、キューティクルを整えて保護する役割を果たします。
インバストリートメントの役割
浴室で使うヘアケア剤には、主に「コンディショナー(またはリンス)」と「トリートメント(またはヘアマスク)」があります。
50代のパサつきケアには、両者の違いを理解して使い分けることが重要です。
コンディショナーとトリートメントの主な違い
| 種類 | 主な役割 | 使用頻度 |
|---|---|---|
| コンディショナー(リンス) | 髪の「表面」をコーティングし、指通りを良くし、摩擦を防ぐ。 | 毎日(シャンプーの直後) |
| トリートメント(ヘアマスク) | 髪の「内部」に保湿・補修成分を浸透させ、ダメージをケアする。 | 週に1~3回(集中ケアとして) |
パサつきが特に気になる場合は、普段はコンディショナーで表面を整え、週に数回、コンディショナーの代わりにトリートメント(ヘアマスク)で集中的に内部補修を行うのがおすすめです。
効果を高める塗布と放置時間
トリートメントは、まずシャンプー後に髪の水気を軽めに切ってから塗布します。ダメージが最も出やすい毛先を中心に、髪の中間までしっかりともみ込むようになじませます。
根元や頭皮にはつけないように注意してください(頭皮用のトリートメントを除く)。塗布した後、すぐに洗い流さず、5分から10分程度放置することで、成分が髪内部へ浸透しやすくなります。
その際、蒸しタオルやシャワーキャップで髪全体を包むと、温度と湿度で浸透効果がさらに高まります。
洗い流さないトリートメント(アウトバス)の活用
お風呂上がりのケアも、パサつき対策には極めて重要です。
タオルドライ後の濡れた髪に「洗い流さないトリートメント(アウトバストリートメント)」を使用することで、ドライヤーの熱から髪を守り、乾燥を防ぎます。
また、朝のスタイリング時や日中のパサつきが気になる時に使うことで、紫外線や乾燥、摩擦といった外部刺激からも髪を守ってくれます。
洗い流さないトリートメントのタイプ別特徴
| タイプ | 特徴 | おすすめの髪質 |
|---|---|---|
| オイルタイプ | 保湿力とコーティング力が最も高い。髪にツヤを与え、広がりを抑える。 | パサつきが強い、髪が太い・硬い、広がりやすい髪 |
| ミルクタイプ | 水分と油分をバランス良く補給できる。しっとりするがベタつきにくい。 | 細毛、軟毛、オイルの重さが苦手な人 |
| ミスト(スプレー)タイプ | 手軽に水分を補給できる。軽い仕上がり。寝癖直しにも使いやすい。 | ダメージが軽い、ボリュームを維持したい人 |
生活習慣の見直しで内側から髪をケア
健康的な髪は、日々の生活習慣によって育まれます。
高価なヘアケア製品を使うことも大切ですが、それ以上に食事、睡眠、ストレス管理といった内側からのケアが、頭皮環境と髪質に直結する重要な要素です。
髪の材料となる栄養素の摂取
髪の毛の約90%は「ケラチン」というタンパク質でできています。そのため、まずは髪の材料となる良質なタンパク質(肉、魚、卵、大豆製品)を毎日の食事でしっかり摂取することが基本です。
タンパク質が不足すると、髪が細くなったり、パサついたりする原因となります。
髪の健康を支える栄養素
| 栄養素 | 働き | 主な食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分となる。 | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |
| 亜鉛 | タンパク質(ケラチン)の合成を助ける。 | 牡蠣、レバー、牛肉(赤身)、チーズ |
| ビタミンB群 (B2, B6など) | 頭皮の皮脂バランスを整え、代謝を促す。 | 豚肉、レバー、青魚(サバ・イワシ)、納豆、バナナ |
質の良い睡眠の確保
髪の成長や頭皮のターンオーバー(新陳代謝)を促す「成長ホルモン」は、私たちが眠っている間に最も多く分泌されます。
特に夜22時から翌2時の間は「髪のゴールデンタイム」とも呼ばれ、この時間帯に深い眠りについていることが理想的です。
50代になると睡眠が浅くなりがちですが、毎日決まった時間に寝る、寝る前のスマートフォン操作を控えるなど、睡眠の質を高める工夫が必要です。
血行を促進する適度な運動と頭皮マッサージ
頭皮の毛細血管に栄養を届けるには、全身の血行が良い状態を保つことが大切です。
デスクワークが多い人は特に血行が滞りがちなので、ウォーキングやストレッチなどの軽い有酸素運動を日常に取り入れましょう。
また、シャンプー時やリラックスタイムに、指の腹で頭皮全体を優しく動かす頭皮マッサージも、頭皮の血流改善に役立ちます。
ストレス管理と紫外線対策
過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させて血行不良を招いたり、皮脂の分泌バランスを崩したりします。
趣味の時間を持つ、ゆっくり入浴するなど、自分なりの方法でリラックスする時間を作ることが重要です。
また、見落としがちなのが紫外線対策。紫外線は肌だけでなく、髪のタンパク質にもダメージを与え、乾燥やパサつきを招きます。外出時は帽子や日傘、髪用のUVカットスプレーなどを活用しましょう。
どうしても改善しない場合の選択肢
セルフケアを徹底しても髪のパサつきやうねりが改善しない、あるいは抜け毛や薄毛も同時に進行している場合は、専門家の知見を借りることも一つの方法です。
一人で抱え込まず、適切な対処を検討しましょう。
美容室でのサロントリートメント
美容室で行う「システムトリートメント」は、市販のトリートメントよりも高濃度の補修成分や保湿成分を、専用の機材や技術を用いて髪の深部まで浸透させる専門的なケアです。
髪の状態に合わせて複数の薬剤を使い分けるため、施術直後の手触りやまとまりの良さといった即効性を感じやすいのが特徴です。
ただし、効果は永久ではないため、美しい状態を維持するには月に1回程度、定期的に施術を受ける必要があります。
育毛剤(医薬部外品)の使用
パサつきだけでなく、髪のハリ・コシの低下、ボリュームダウン、抜け毛といった悩みも同時に抱えている場合、頭皮環境そのものを改善し、育毛・発毛を促進する「育毛剤(医薬部外品)」の使用を検討するのも良いでしょう。
育毛剤には、頭皮の血行を促進したり、毛母細胞の働きを助けたりする有効成分が含まれています。製品によっては頭皮の保湿成分も豊富に配合されており、乾燥対策と育毛ケアを同時に行えます。
育毛剤に含まれる主な有効成分の例
| 成分の系統 | 期待される働き | 主な成分例 |
|---|---|---|
| 血行促進 | 頭皮の血流を改善し、栄養を届きやすくする。 | センブリエキス、ビタミンE誘導体、ニコチン酸アミド |
| 抗炎症 | 頭皮の炎症やフケ・かゆみを抑え、環境を整える。 | グリチルリチン酸2K、アラントイン |
| 毛母細胞活性 | 髪の元となる細胞の働きを助ける。 | t-フラバノン、アデノシン、パントテニルエチルエーテル |
専門クリニックへの相談
髪のパサつきが極端で、セルフケアではどうにもならない場合や、明らかに抜け毛が増えて薄毛(AGA:男性型脱毛症など)が進行していると感じる場合は、皮膚科やAGA専門クリニックで医師の診断を仰ぐことを推奨します。
パサつきの原因が、単なる乾燥ではなく、別の皮膚疾患やAGAによる髪質の変化である可能性も考えられます。
専門医であれば、現在の頭皮や髪の状態を正確に診断し、必要に応じて内服薬(フィナステリド、デュタステリドなど)や外用薬(ミノキシジルなど)といった医学的根拠に基づいた治療(発毛剤など)を提案してくれます。
Q&A
50代の髪のパサつきに関して、多くの方が抱く疑問にお答えします。日々のケアの参考にしてください。
- 白髪染めはパサつきの原因になりますか?
-
はい、原因の一つになり得ます。白髪染め(特にアルカリカラー)は、薬剤の力で髪のキューティクルを開き、内部に色を浸透させます。
その際、髪内部のタンパク質や脂質も一緒に流出しやすくなるため、繰り返すことで髪はダメージを受け、パサつきやすくなります。
染める頻度を美容師と相談して調整したり、髪への負担が少ないヘアマニキュアやカラートリートメントを選んだり、美容室で染める際は必ずトリートメントをセットで行うなどの工夫が必要です。
- 髪のうねりもパサつきと関係がありますか?
-
深く関係しています。
50代になると、加齢によって毛穴自体がたるんで歪んだり、髪内部の水分と油分のバランスが崩れたりすることで、「エイジング毛」と呼ばれる、チリチリとしたり、大きくうねったりする髪質に変化することがあります。
うねった髪は、表面が均一でないために光が乱反射しやすく、ツヤがなくパサついて見えてしまいます。また、直毛の部分と比べて水分保持力も低い傾向にあります。
- ヘアオイルは毎日使っても良いですか?
-
はい、パサつきが気になる場合は毎日使用することをおすすめします。特に効果的なのは、お風呂上がりのタオルドライ後、ドライヤーで乾かす前です。
濡れた髪にヘアオイルをなじませることで、熱から髪を守る保護膜となり、水分の過度な蒸発を防ぐことができます。
ただし、つけすぎるとベタつきや重さの原因になるため、まずは1プッシュ程度を手のひらに伸ばし、毛先を中心にもみ込むようにして、少量から試してください。
- 食生活で特に気をつけることは何ですか?
-
まずは髪の主成分であるタンパク質を、朝・昼・晩の食事で欠かさず摂ることです。肉、魚、卵、大豆製品など、動物性と植物性のタンパク質をバランス良く取り入れましょう。
加えて、そのタンパク質を髪の毛(ケラチン)に合成するのを助ける「亜鉛」(牡蠣、レバー、牛肉など)や、頭皮の新陳代謝をサポートする「ビタミンB群」(豚肉、レバー、納豆、青魚など)も意識して摂取することが大切です。
- 頭皮マッサージはどれくらいの頻度で行えば良いですか?
-
毎日行うのが理想的です。難しければ2日に1回でも構いませんので、習慣化することが重要です。最も手軽なのは、シャンプーのついでに行う方法です。
指の腹で頭皮をしっかりと掴み、頭蓋骨から頭皮を剥がすようなイメージで、前後左右にゆっくりと動かします。時間は1~2分程度で十分です。
力を入れすぎず、「痛気持ちいい」と感じる程度の強さで行ってください。血行を促進し、頭皮を柔らかく保つ助けになります。
Reference
TRÜEB, Ralph; HOFFMANN, Rolf. Aging of hair. In: Textbook of Men’s Health and Aging. CRC Press, 2007. p. 715-728.
OLSEN, Elise A., et al. Evaluation and treatment of male and female pattern hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2005, 52.2: 301-311.
TRÜEB, Ralph M. Pharmacologic interventions in aging hair. Clinical Interventions in Aging, 2006, 1.2: 121-129.
MANABE, Motomu, et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of male‐pattern and female‐pattern hair loss, 2017 version. The Journal of Dermatology, 2018, 45.9: 1031-1043.
BANKA, Nusrat; BUNAGAN, MJ Kristine; SHAPIRO, Jerry. Pattern hair loss in men: diagnosis and medical treatment. Dermatologic clinics, 2013, 31.1: 129-140.
YORK, Katherine, et al. A review of the treatment of male pattern hair loss. Expert opinion on pharmacotherapy, 2020, 21.5: 603-612.
RASSMAN, William R.; BERNSTEIN, Robert M. Hair loss and replacement for dummies. John Wiley & Sons, 2008.
TRÜEB, Ralph M. Hair Aging and Anti-Aging Strategies. In: Hair and Scalp Disorders. CRC Press, 2018. p. 297-316.
TRÜEB, Ralph M.; LEE, Won-Soo. Male alopecia. Guide to successful management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2014.
DUBIEF, C., et al. Hair care products. In: The Science of Hair Care. CRC Press, 1986. p. 155-196.