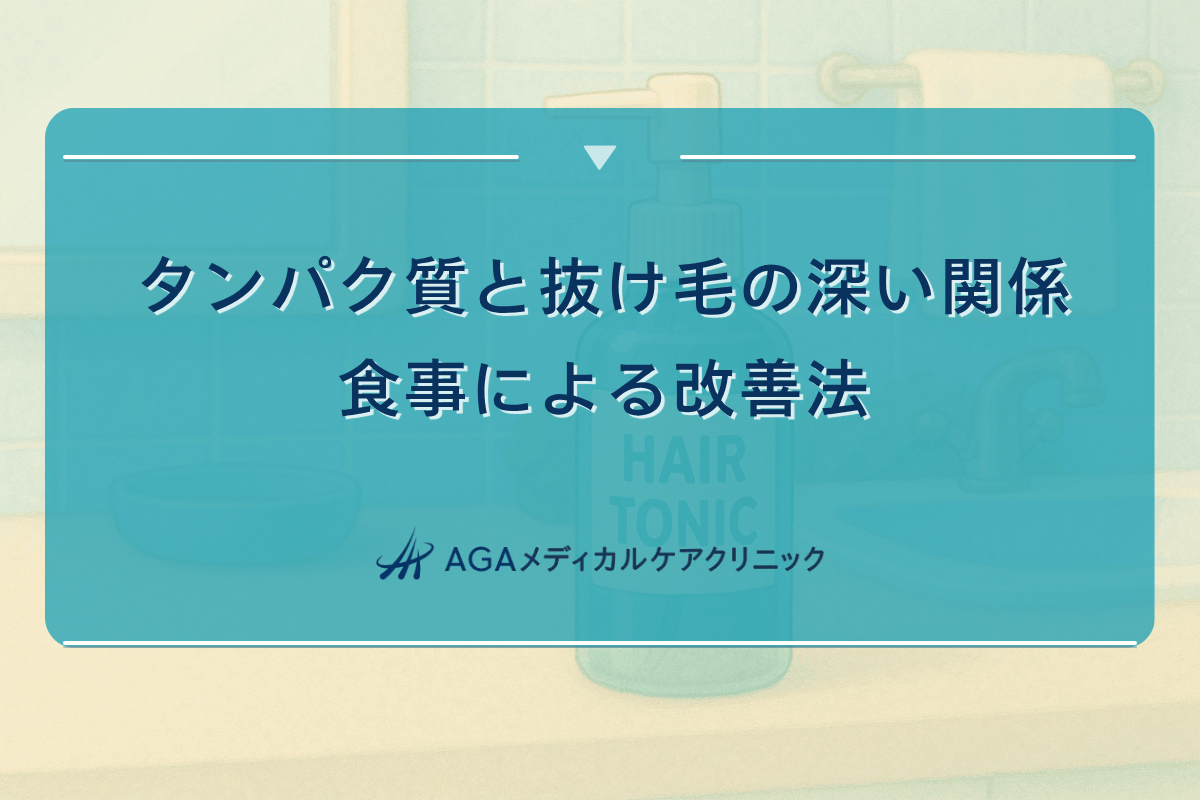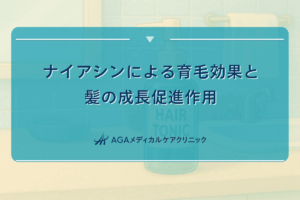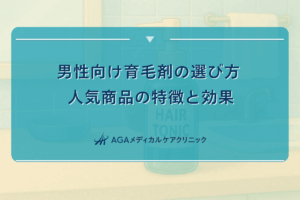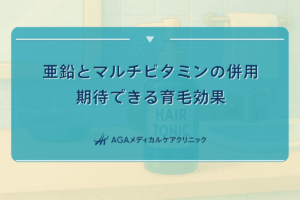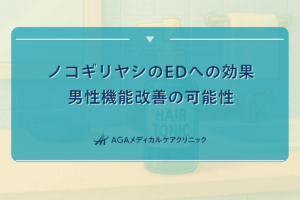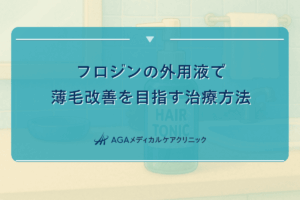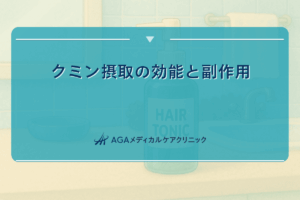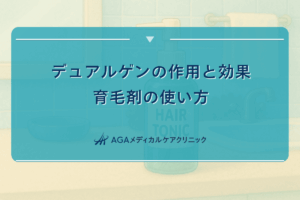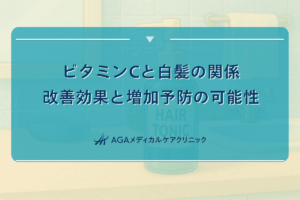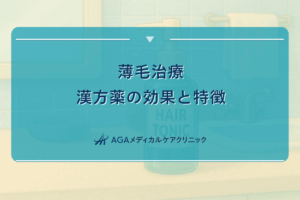鏡を見るたびに気になる髪のボリュームや、枕元に落ちている抜け毛の数に不安を感じていませんか。
「もしかして、AGAかも」と心配になる一方で、日々の食事内容がおろそかになっていることに心当たりがある方も多いのではないでしょうか。
実は丈夫で健康な髪を育てるためには、体の材料となる「タンパク質」が十分に足りていることが大前提です。
この記事ではタンパク質不足がなぜ抜け毛を引き起こすのかという理由から、効率よく髪に栄養を届けるための具体的な食事法までを詳しく解説します。
毎日の食事を少し見直すだけで将来の髪への投資につながります。まずは髪と食事の密接な関係を知り、今日からできる対策を始めましょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
なぜタンパク質不足が抜け毛を招くのか
私たちの体は食べたものから作られており、髪の毛も例外ではありません。
タンパク質が不足すると体は生命維持に関わる重要な臓器へ優先的に栄養を回すため、直接命に関わらない髪の毛への栄養供給は後回しになってしまいます。
その結果、髪は栄養不足に陥り、細く弱くなって抜けやすくなるのです。ここでは髪の構造と体の栄養配分の仕組みから、その理由を深く掘り下げていきます。
髪の主成分ケラチンとタンパク質の関係
髪の毛の構成成分の大部分、実に9割近くを占めているのが「ケラチン」という種類のタンパク質です。このケラチンは食事から摂取したタンパク質が体内でアミノ酸に分解され、再び合成されることで作られます。
つまり、原料となるタンパク質が食事から十分に入ってこなければ、健康なケラチンを合成することが難しくなります。
ケラチンが不足した髪は内部がスカスカの状態になりやすく、ハリやコシが失われ、少しの刺激でも切れ毛や抜け毛につながってしまいます。
丈夫で太い髪を育てるには、常に良質なタンパク質を供給し続けることが重要です。
体内でタンパク質が使われる優先順位
摂取したタンパク質は体内で生命維持に欠かせない部分から優先的に使われていくという原則があります。心臓や脳、内臓、血液、筋肉などが最優先され、皮膚や爪、そして髪の毛などは優先順位が低くなります。
体が「生きるために必要だ」と判断する箇所へ栄養が集中するため、タンパク質の摂取量がギリギリ、あるいは不足している状態では、末端にある髪の毛まで栄養が行き渡りません。
ダイエットなどで極端な食事制限をした際に肌荒れや抜け毛が起こりやすいのは、こうした体が持つ防衛的な栄養配分の仕組みが働いているためです。
無理なダイエットが引き起こす悪循環
短期間で体重を落とそうとする無理なダイエットは、抜け毛の大きな原因となります。
食事全体の量を減らすことでタンパク質だけでなく、ビタミンやミネラルといった髪の成長に必要な栄養素も同時に不足しがちです。
さらに、急激な体重減少は体に大きなストレスを与え、ホルモンバランスを乱す原因にもなります。
栄養不足とストレスのダブルパンチによりヘアサイクル(毛周期)が乱れ、成長期が短縮されて十分に育っていない髪が抜け落ちてしまうのです。
健康的な髪を維持しながらスリムな体型を目指すなら、必要な栄養素を確保した上での計画的な食事管理が求められます。
抜け毛予防に必要な1日のタンパク質摂取量
髪の健康を守るために、私たちは毎日どれくらいのタンパク質を摂る必要があるのでしょうか。厚生労働省が発表している基準などを参考に、一般的な成人が目指すべき摂取量の目安を知っておきましょう。
また、生活スタイルや運動量によっても必要量は変化します。自身の状況に合わせて、適切な量を把握することが大切です。
成人男性・女性の推奨摂取量
日本人の食事摂取基準によると、1日に推奨されるタンパク質の摂取量は、年齢や性別によって異なります。一般的な活動レベルの成人男性であれば1日約60〜65g、成人女性であれば約50gが目安とされています。
これはあくまで「健康を維持するために最低限必要な量」であり、髪の悩みを積極的に改善したい場合や、体の大きさによっては、もう少し多めの摂取を意識しても良いでしょう。
毎食手のひら一枚分程度のタンパク質源(肉、魚、卵、大豆製品など)を取り入れることで、おおよその推奨量を満たすことができます。
性別・年齢別のタンパク質摂取推奨量(1日あたり)
| 年齢階級 | 男性(推奨量) | 女性(推奨量) |
|---|---|---|
| 18〜64歳 | 65g | 50g |
| 65歳以上 | 60g | 50g |
| 備考 | 妊婦・授乳婦はさらに付加量が必要 | |
運動習慣による必要量の違い
日常的にスポーツジムに通っていたり、肉体労働をしていたりする人は、筋肉の修復や維持のためにより多くのタンパク質を消費します。
そのため、一般的な推奨量よりも多くのタンパク質を摂取する必要があります。
運動習慣がある場合、体重1kgあたり1.2g〜2.0g程度のタンパク質を目安にすると良いと言われています。例えば体重60kgの人なら、1日に72g〜120g程度が必要です。
運動をしているのに抜け毛が気になるという方は、消費量に対して摂取量が追いついていない可能性も考えられます。
摂取量が不足しているサイン
体がタンパク質不足に陥ると、抜け毛以外にもさまざまなサインが現れます。
例えば、爪が割れやすくなる、肌が乾燥して荒れやすくなる、筋肉量が落ちて代謝が下がる、疲れがなかなか取れない、集中力が続かないといった症状です。
これらのサインは、体が「栄養が足りていない」と訴えている証拠でもあります。髪の悩みに加えて、こうした体の不調を感じる場合は、意識的にタンパク質の摂取量を増やしてみることをお勧めします。
良質なタンパク質を含む食材リスト
一口にタンパク質といっても、その種類や含まれるアミノ酸のバランスは食材によって異なります。効率よく体内で利用される「良質なタンパク質」を選ぶことが、健康な髪作りへの近道です。
ここでは動物性と植物性のそれぞれの特徴と、積極的に摂りたい食材について具体的に紹介します。
動物性タンパク質のメリットとおすすめ食材
肉類、魚介類、卵、乳製品などに含まれる動物性タンパク質は、体内での利用効率が非常に高いのが特徴です。
髪の構成成分である必須アミノ酸をバランスよく含んでいるものが多く、少量でも効率的にタンパク質を補給できます。特に赤身の肉やレバーには、髪の成長に欠かせない鉄分や亜鉛も豊富に含まれています。
ただし、脂質の多い部位ばかりを食べ過ぎるとカロリーオーバーになる可能性があるため、ヒレ肉や鶏むね肉、ささみなど、高タンパク・低脂質な部位を選ぶ工夫も大切です。
植物性タンパク質のメリットとおすすめ食材
大豆製品(納豆、豆腐、豆乳など)や穀物などに含まれる植物性タンパク質は低脂質で低カロリーなものが多く、ヘルシーにタンパク質を摂取できるのがメリットです。
特に大豆に含まれるイソフラボンは女性ホルモンに似た働きをするとされ、ホルモンバランスの乱れが気になる方にも嬉しい食材です。
動物性タンパク質に比べて一部のアミノ酸が少ない傾向にありますが、さまざまな食材を組み合わせて食べることで、その欠点を補うことができます。
動物性タンパク質と植物性タンパク質の比較
| 比較項目 | 動物性タンパク質 | 植物性タンパク質 |
|---|---|---|
| 主な食材 | 肉、魚、卵、乳製品 | 大豆製品、穀類、ナッツ類 |
| 吸収速度 | 比較的速い | 比較的穏やか |
| 特徴 | 必須アミノ酸が豊富だが脂質も多め | 低脂質・低カロリーで食物繊維も豊富 |
アミノ酸スコアとは?質の良いタンパク質の見分け方
「アミノ酸スコア」とは、食品に含まれる必須アミノ酸のバランスを数値化したものです。100に近いほど体内で効率よく利用できる良質なタンパク質であることを示します。
肉、魚、卵、牛乳、大豆などは、アミノ酸スコアが100の優秀な食品です。一方、米や小麦などの穀類は一部のアミノ酸が不足しているためスコアが低くなりますが、スコア100の食品と組み合わせて食べることで、食事全体の栄養価を高めることができます。
毎日の食事では特定のものに偏らず、アミノ酸スコアの高い食材を主菜に取り入れることを意識しましょう。
タンパク質の吸収率を高める食べ合わせ
せっかく良質なタンパク質を摂取しても、体がうまく吸収・利用できなければ意味がありません。タンパク質の働きを助け、髪への合成を促進するためには、他の栄養素との「食べ合わせ」が鍵となります。
相性の良い栄養素を一緒に摂ることで、育毛効果をより高めることが期待できます。
ビタミンB6との相乗効果
ビタミンB6は、摂取したタンパク質をアミノ酸に分解・再合成する過程で補酵素として働きます。つまり、タンパク質を髪の毛に変えるための「代謝」をサポートする重要な栄養素です。
ビタミンB6が不足すると、いくらタンパク質を摂っても効率よく髪の毛の材料として使われません。
マグロやカツオなどの魚類、レバー、バナナなどに多く含まれているので、タンパク質源と一緒にこれらの食材を食べるのがおすすめです。
亜鉛と一緒に摂るべき理由
亜鉛は再合成されたアミノ酸からケラチンを作り出す際に必要不可欠なミネラルです。亜鉛がなければ、髪の主成分であるケラチンをうまく合成することができません。
また、AGA(男性型脱毛症)の原因物質の一つとされる酵素の働きを抑制する作用もあると言われています。
牡蠣(かき)や牛肉、ナッツ類などに多く含まれていますが、吸収率があまり高くないため、吸収を助けるビタミンCやクエン酸と一緒に摂るなどの工夫も有効です。
タンパク質と相性の良い栄養素
| 栄養素名 | 主な働き | 多く含む食材例 |
|---|---|---|
| ビタミンB6 | タンパク質の代謝を助ける | マグロ、レバー、バナナ、玄米 |
| 亜鉛 | ケラチンの合成を促進する | 牡蠣、牛肉、ウナギ、アーモンド |
| ビタミンC | 亜鉛の吸収を高め、コラーゲン生成を助ける | キウイ、ブロッコリー、柑橘類 |
消化を助ける酵素を含む食品
胃腸の働きが弱っていると、タンパク質の消化吸収率が低下してしまいます。食事の際にタンパク質分解酵素を含む食材を一緒に摂ることで胃腸への負担を減らし、効率的な消化をサポートできます。
例えば、パイナップル(ブロメライン)、キウイ(アクチニジン)、生姜(ジンジバイン)、舞茸(マイタケプロテアーゼ)などが代表的です。
特に肉料理などのメインディッシュと一緒に、これらの食材を使ったソースや付け合わせを取り入れると良いでしょう。
コンビニや外食で賢くタンパク質を摂るコツ
自炊をする時間がなく、コンビニや外食に頼りがちな忙しい方でも、選び方次第で十分なタンパク質を確保することは可能です。
最近では健康志向の高まりもあり、手軽にタンパク質が摂れる商品やメニューが増えています。毎日のランチや夕食で少し意識を変えるだけで、髪に必要な栄養をチャージできます。
コンビニで選ぶべき高タンパク商品
コンビニエンスストアは、優秀なタンパク質源の宝庫です。定番のサラダチキンだけでなく、ゆで卵、焼き魚のパック、豆腐バー、ギリシャヨーグルト、カニカマ、ちくわなどの練り物も手軽なタンパク源となります。
おにぎりを選ぶ際も、ツナや鮭、納豆巻きなどを選ぶと良いでしょう。カップスープやお味噌汁を追加するだけでも、満足感と栄養価をプラスできます。
パッケージの裏にある栄養成分表示を見て、タンパク質(Protein)の量を確認する習慣をつけるのもおすすめです。
外食メニュー選びのポイント
外食時は単品メニューよりも定食スタイルを選ぶのが基本です。ご飯、味噌汁、主菜、副菜が揃った定食なら、栄養バランスが整いやすくなります。
主菜は揚げ物よりも焼き物や刺身などを選ぶと余分な脂質を抑えられます。
丼ものや麺類などの単品メニューを頼む場合はトッピングで卵や納豆、チャーシューなどを追加したり、サイドメニューで冷奴や枝豆を頼んだりして、不足しがちなタンパク質を補う工夫をしましょう。
コンビニで手軽に買える高タンパク食品例
| 食品カテゴリー | おすすめ商品例 | 期待できるタンパク質量(目安) |
|---|---|---|
| 総菜・加工肉 | サラダチキン、炭火焼き鳥 | 約15g〜25g |
| 卵・乳製品 | ゆで卵、ギリシャヨーグルト、プロセスチーズ | 約6g〜10g |
| 大豆製品・その他 | 納豆巻き、冷奴パック、プロテインバー | 約7g〜15g |
間食におすすめのタンパク質源
小腹が空いた時の間食も、髪への栄養補給のチャンスです。スナック菓子や甘い菓子パンの代わりに、タンパク質が豊富なものを選びましょう。
素焼きのアーモンドやくるみなどのナッツ類、小魚アーモンド、高カオカチョコレート、チーズ、豆乳などは、手軽に食べられて栄養価も高い優秀な間食です。
最近ではコンビニでも買えるプロテインドリンクも種類が豊富なので、好みの味を見つけて常備しておくのも良い方法です。
タンパク質摂取の注意点と過剰摂取のリスク
「髪に良いなら、たくさん摂ればいい」と考えるかもしれませんが、何事もバランスが重要です。タンパク質の過剰摂取は体に負担をかける可能性があります。
適切な量を適切なタイミングで摂るための注意点を知っておきましょう。
一度に吸収できる量には限界がある
人間の体が一度の食事で効率よく吸収・利用できるタンパク質の量には限界があり、一般的には約20g〜30g程度と言われています。
一度に大量の肉を食べてもすべてが身になるわけではなく、余剰分は体外へ排出されるか、脂肪として蓄積されてしまいます。
朝食は軽く済ませ、夕食でドカ食いするといった偏った摂り方ではなく、朝・昼・晩の3食に分けてこまめに摂取する方が、体内のアミノ酸濃度を一定に保ち、髪へ安定して栄養を届けることができます。
カロリーオーバーや内臓疲労の可能性
タンパク質を多く含む食材、特に肉類は部位によっては脂質も多く含んでいます。タンパク質摂取を意識するあまり、脂質の摂りすぎでカロリーオーバーになり、肥満につながるリスクもあります。
また、タンパク質を分解・代謝する過程で、肝臓や腎臓には一定の負担がかかります。
通常量の食事であれば問題ありませんが、極端な過剰摂取を長期間続けると、内臓疲労を引き起こす可能性もゼロではありません。
持病がある方は医師に相談の上、摂取量を調整することが大切です。
サプリメントやプロテインの正しい活用法
食事だけで必要量を摂るのが難しい場合、プロテインパウダーやアミノ酸サプリメントは非常に便利な補助食品です。
しかし、これらはあくまで「食事の補助」として捉えるべきです。食事をおろそかにしてサプリメントだけに頼ると、他の微量栄養素が不足する恐れがあります。
基本はバランスの取れた3食の食事をベースにし、運動後や忙しい朝など、どうしても食事が不十分になるタイミングで賢く活用するのが理想的です。
過剰摂取で注意したい体のサイン
- 体重や体脂肪の増加
- 胃腸の不調(消化不良など)
- 肝臓や腎臓の数値異常(健康診断などで指摘された場合)
食事以外で見直すべき抜け毛の原因
食生活の改善は非常に有効な抜け毛対策ですが、それだけで全ての悩みが解決するわけではありません。髪の健康は日々の生活習慣全体と密接に関わっています。
食事による内側からのケアと並行して、外側からのケアや生活リズムの見直しも行うことで、より効果的な対策となります。
睡眠不足が髪の成長を妨げる
髪の毛が最も活発に成長するのは、寝ている間です。特に深い眠りについている時に分泌される「成長ホルモン」は毛母細胞の分裂を促し、髪を太く長く育てる役割を担っています。
慢性的な睡眠不足や質の悪い睡眠は、この成長ホルモンの分泌を低下させ、髪の成長を妨げてしまいます。
日付が変わる前に就寝する、寝る直前のスマートフォンの使用を控えるなど、良質な睡眠を確保する工夫も立派な育毛ケアの一つです。
ストレスとホルモンバランスの乱れ
強いストレスを感じると、自律神経が乱れて血管が収縮し、頭皮への血流が悪化します。血流が滞ると食事で摂った栄養が毛根までスムーズに届きません。
また、ストレスはホルモンバランスにも影響を与え、AGAの進行を早める可能性も指摘されています。
趣味の時間を持つ、適度な運動をする、ゆっくり入浴するなど、自分なりのリラックス方法を見つけて、ストレスを溜め込まない生活を心がけましょう。
間違ったヘアケア習慣
頭皮環境が悪化していると、健康な髪は育ちにくくなります。
洗浄力の強すぎるシャンプーで必要な皮脂まで洗い流して乾燥させてしまったり、逆に洗髪不足で皮脂が毛穴に詰まったりすることも抜け毛の原因になります。
また、爪を立てて洗う、熱すぎるシャワーですすぐ、ドライヤーを近づけすぎるといった間違った習慣も頭皮を傷めます。
自分の頭皮タイプに合ったシャンプーを選び、優しく丁寧に洗う正しいヘアケアを実践することが大切です。
見直したい生活習慣チェックリスト
| カテゴリー | チェック項目 |
|---|---|
| 睡眠 | 毎日6時間以上の睡眠時間を確保できているか |
| ストレス | 自分なりのストレス解消法を持っているか |
| 運動 | 週に数回、軽く汗をかく程度の運動をしているか |
| 嗜好品 | 過度な喫煙や飲酒を控えているか |
タンパク質と抜け毛に関するよくある質問
- タンパク質をたくさん摂れば、すでに抜けた髪も生えてきますか?
-
食事の改善は今ある髪を元気に保ち、これから生えてくる髪を丈夫にするための予防・維持対策が中心です。
すでに進行してしまった薄毛部分から新しい髪を劇的に生やすことは、食事だけでは難しい場合があります。
発毛を強く望む場合は、専門のクリニックで適切な診断と治療を受けることを検討してください。
- 卵は1日1個までと聞きますが、もっと食べても大丈夫ですか?
-
健康な方であれば、1日に卵を複数個食べても血中コレステロール値に大きな影響はないという研究報告が近年増えています。
卵はアミノ酸スコア100の非常に優秀なタンパク源であり、髪に必要なビオチンなども含んでいます。他の食事とのバランスを考えながら、1日2個程度を目安に取り入れても問題ない場合が多いでしょう。
- 豆乳を毎日飲むと抜け毛は減りますか?
-
豆乳に含まれる大豆イソフラボンは、AGAの原因に関わるホルモンの働きを穏やかにする効果が期待されており、サポート的な役割を果たします。
しかし、飲むだけで劇的に抜け毛が減る特効薬ではありません。あくまでバランスの良い食事の一部として、継続的に取り入れることが大切です。
- 食生活を変えてから、どのくらいで効果を感じられますか?
-
髪の毛は1ヶ月に約1cm程度しか伸びません。食生活を改善しても、その影響を受けた新しい髪が成長し、目に見えて変化を実感できるまでには時間がかかります。
個人差はありますが、最低でも3ヶ月から半年程度は継続して様子を見る必要があります。焦らずじっくりと取り組む姿勢が重要です。
参考文献
GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.
RUSHTON, D. H., et al. Causes of hair loss and the developments in hair rejuvenation. International journal of cosmetic science, 2002, 24.1: 17-23.
MAHBOUB, Nadine, et al. Nutritional status and eating habits of people who use drugs and/or are undergoing treatment for recovery: a narrative review. Nutrition reviews, 2021, 79.6: 627-635.
GARG, Suruchi; SANGWAN, Ankita. Dietary protein deficit and deregulated autophagy: a new clinico-diagnostic perspective in pathogenesis of early aging, skin, and hair disorders. Indian Dermatology Online Journal, 2019, 10.2: 115-124.
AGHA-MOHAMMADI, Siamak; HURWITZ, Dennis J. Potential impacts of nutritional deficiency of postbariatric patients on body contouring surgery. Plastic and reconstructive surgery, 2008, 122.6: 1901-1914.
GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.