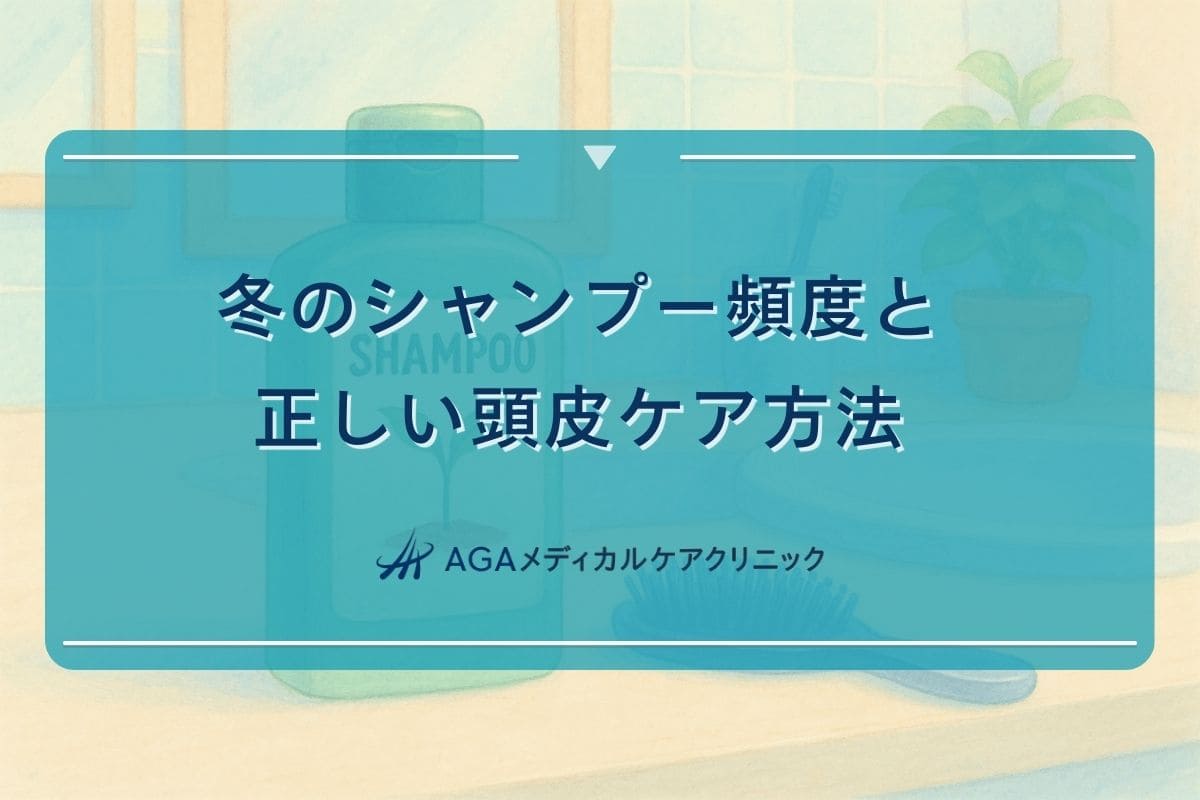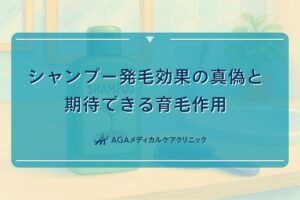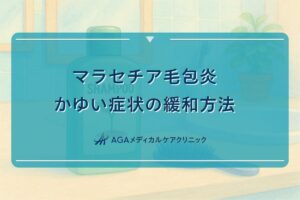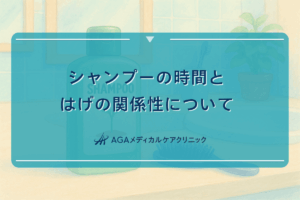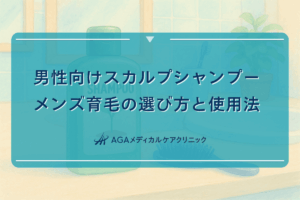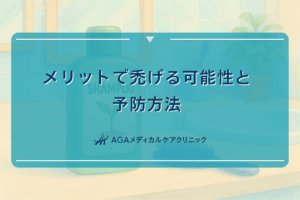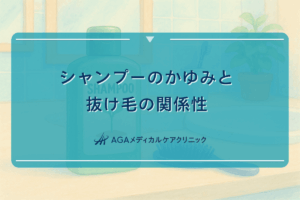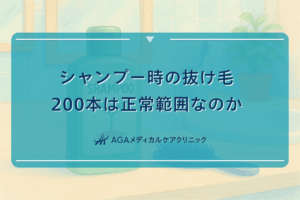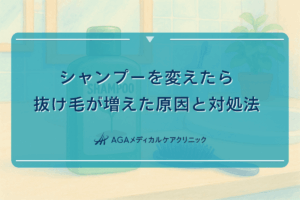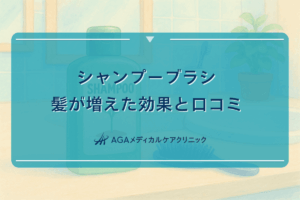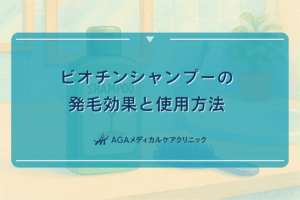冬になると、空気の乾燥とともに頭皮のフケやかゆみが気になりませんか。「夏のように汗をかかないからシャンプーは毎日しなくても良いのでは?」と考える方もいるかもしれません。
しかし、冬の頭皮は乾燥と血行不良、そして室内外の寒暖差による蒸れなど、実は過酷な環境にさらされています。
間違ったシャンプー頻度やヘアケアはこれらの頭皮トラブルを悪化させ、抜け毛や薄毛の原因にもなりかねません。
この記事では冬の頭皮環境に合わせた最適なシャンプー頻度と、髪と頭皮を健やかに保つための正しいケア方法を専門的な視点から詳しく解説します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
冬の頭皮環境 なぜトラブルが起きやすいのか
冬は夏とは異なる要因で頭皮トラブルが起こりやすい季節です。主な原因は「乾燥」と「血行不良」にあります。
空気の乾燥と頭皮の水分不足
冬の空気は湿度が低く、非常に乾燥しています。肌がカサカサするのと同様に頭皮も水分を奪われ、乾燥しやすくなります。
頭皮が乾燥するとバリア機能が低下し、外部からのわずかな刺激にも敏感に反応して、かゆみやフケ(乾性フケ)を引き起こす原因となります。
暖房による血行不良
寒い屋外と暖房の効いた室内との急激な温度差は自律神経のバランスを乱し、血管の収縮を招きます。このことにより、頭皮の毛細血管の血流が悪化しやすくなります。
血行不良は髪の成長に必要な栄養素が毛根に届きにくくなるため、抜け毛や髪の成長阻害に直結します。
冬の主な頭皮トラブルとその原因
| トラブル | 主な原因 |
|---|---|
| かゆみ・乾性フケ | 空気の乾燥による頭皮の水分不足 |
| 抜け毛・髪の成長不良 | 寒暖差による血行不良、栄養不足 |
| ベタつき・湿性フケ | 乾燥による皮脂の過剰分泌、帽子の蒸れ |
皮脂の過剰分泌と乾燥の悪循環
頭皮は乾燥すると潤いを補おうとして、逆に皮脂を過剰に分泌することがあります。この過剰な皮脂が毛穴に詰まったり、酸化したりすることで、ベタつきやニオイ、湿ったフケ(脂性フケ)の原因となります。
乾燥しているのにベタつくという、悪循環に陥りやすいのが冬の頭皮の特徴です。
帽子やマフラーによる蒸れ
防寒対策として帽子をかぶる機会が増えますが、暖房の効いた室内で長時間かぶったままでいると頭皮が蒸れて雑菌が繁殖しやすい環境になります。
この蒸れも、かゆみや炎症、ニオイの原因となるため注意が必要です。
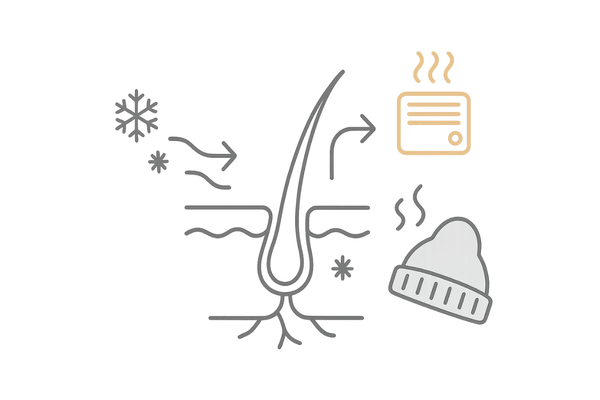
冬のシャンプー頻度 毎日は洗いすぎ?
汗をかく量が減る冬はシャンプーの頻度を減らした方が良いと考える方もいますが、一概にそうとは言えません。
基本的には毎日洗うことが推奨されますが、ご自身の頭皮タイプに合わせて調整することが大切です。
基本は1日1回が原則
冬でも頭皮からは皮脂や汗が分泌され、外気のホコリや汚れが付着します。これらの汚れを放置すると、毛穴詰まりや雑菌繁殖の原因となります。
そのため頭皮のタイプに関わらず、1日の汚れをその日のうちにリセットするという観点から、1日1回のシャンプーが基本となります。
乾燥肌・敏感肌の人の場合の調整法
頭皮が特に乾燥しやすく、毎日洗うと逆にかゆみやフケが悪化するという方は2日に1回に頻度を調整することも選択肢の一つです。
ただし、その場合は洗浄力の非常にマイルドなシャンプーを選び、洗わない日はぬるま湯で丁寧に頭皮をすすぐ「湯シャン」を取り入れるなどの工夫が必要です。
頭皮タイプ別 冬のシャンプー頻度の目安
| 頭皮タイプ | 推奨頻度 | 注意点 |
|---|---|---|
| 普通肌・脂性肌 | 1日1回 | 汚れをしっかり落とし、保湿も行う |
| 乾燥肌・敏感肌 | 1日1回~2日に1回 | 洗浄力の優しいシャンプーを使用する |
シャンプーをしない日がもたらすリスク
シャンプーをしない日が続くと酸化した皮脂や汚れが毛穴を塞ぎ、炎症(脂漏性皮膚炎など)を引き起こすリスクが高まります。
また、頭皮の常在菌バランスが崩れ、フケやかゆみが悪化することもあります。
健康な頭皮環境を維持するためには、適切な頻度で清潔を保つことが重要です。
間違いだらけの冬のシャンプー その洗い方、頭皮を傷つけています
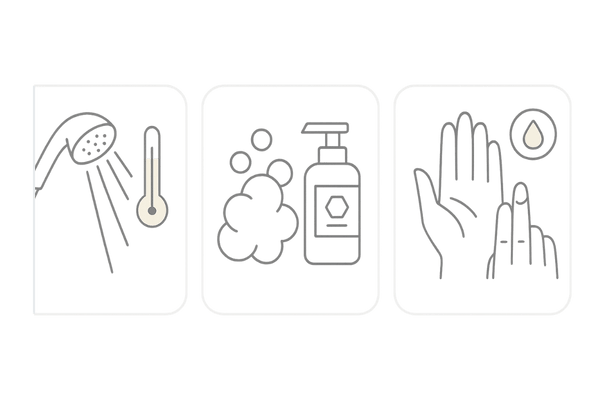
シャンプーは毎日していても、その「洗い方」が間違っていると、かえって頭皮の乾燥やトラブルを助長してしまいます。
冬にやりがちなNGな洗い方を確認してみましょう。
熱すぎるお湯での洗髪
寒い冬は、つい熱いお湯でシャワーを浴びたくなりますが、40度以上のお湯は頭皮に必要な皮脂まで奪い去り、乾燥を急激に進行させます。
洗髪に適した温度は、体温より少し高めの38度前後のぬるま湯です。
洗浄力の強すぎるシャンプーの常用
夏と同じように、爽快感の強い洗浄力の高いシャンプーを使い続けていませんか。冬の乾燥した頭皮には刺激が強すぎ、バリア機能を低下させる原因になります。
保湿成分が配合されたアミノ酸系などのマイルドな洗浄成分のシャンプーを選ぶことが大切です。
冬に避けたいシャンプーの成分
- 高級アルコール系洗浄成分(ラウレス硫酸Naなど)
- 強い清涼成分(メントールなど)
爪を立てたゴシゴシ洗い
かゆみがある時など、つい爪を立てて力強く洗いたくなりますが、これは頭皮を傷つける最も危険な行為です。
目に見えない無数の傷ができ、そこから炎症が起きたり、バリア機能がさらに低下したりします。必ず指の腹を使って優しく洗いましょう。
髪と頭皮を守る 冬の正しいシャンプー手順

頭皮への負担を最小限に抑え、汚れをしっかり落とすための正しいシャンプーの手順をマスターしましょう。少しの工夫で、洗い上がりの頭皮の状態は大きく変わります。
洗髪前のブラッシングの重要性
シャンプー前に乾いた髪を優しくブラッシングすることで髪の絡まりをほどき、表面のホコリや汚れを大まかに落とすことができます。
このひと手間でシャンプー時の泡立ちが良くなり、髪への摩擦も軽減できます。
ぬるま湯での予洗いと泡立て
シャンプー剤をつける前に、38度程度のぬるま湯で1〜2分かけて頭皮と髪を十分に濡らします。これだけで汚れの7割程度は落ちると言われています。
シャンプーは直接頭皮につけず、手のひらでよく泡立ててから髪に乗せましょう。
指の腹を使ったマッサージ洗い
泡立てたシャンプーを髪全体に行き渡らせたら、指の腹を使って頭皮を優しくマッサージするように洗います。
生え際から頭頂部へ、襟足から頭頂部へと下から上に向かってジグザグに動かすと、血行促進効果も期待できます。
正しいシャンプーの洗い方
| 手順 | ポイント |
|---|---|
| 1. ブラッシング | 乾いた髪の状態でホコリを落とす |
| 2. 予洗い | ぬるま湯で1~2分、十分に濡らす |
| 3. 洗う | よく泡立て、指の腹でマッサージするように |
「寒いから」の油断が命取り – 冬のドライヤー習慣が薄毛を加速させる
冬のヘアケアで見落とされがちながら、実は頭皮環境に深刻な影響を与えているのが「髪の乾かし方」です。
「寒いから、つい半乾きで済ませてしまう」「早く乾かしたいから、熱風をずっと当てている」。その何気ない習慣が、あなたの薄毛の悩みを深くしているかもしれません。
自然乾燥が引き起こす雑菌繁殖と頭皮の冷え
「ドライヤーの熱は髪に悪い」と考え、自然乾燥に任せていませんか。濡れたままの頭皮は雑菌が繁殖するための温床です。雑菌が繁殖すると、かゆみやフケ、ニオイの原因となります。
さらに、水分が蒸発する際に頭皮の熱を奪う「気化熱」により、頭皮が冷えて血行不良を招きます。これは髪の成長にとって致命的です。
熱風の当てすぎによるオーバードライ
早く乾かしたい一心で、ドライヤーの熱風を同じ場所に集中して当て続けるのも危険です。頭皮の水分が過剰に奪われ、「オーバードライ」という極度の乾燥状態に陥ります。
このオーバードライは乾性フケや強いかゆみを引き起こし、頭皮のバリア機能を著しく低下させます。
ドライヤーのNGな使い方
| NGな使い方 | 頭皮への悪影響 |
|---|---|
| 自然乾燥・半乾き | 雑菌の繁殖、頭皮の冷えによる血行不良 |
| 熱風の集中・近距離での使用 | オーバードライによる乾燥、炎症 |
温風と冷風を使い分けるプロのテクニック
正しい乾かし方の鍵は「温風と冷風の使い分け」にあります。まずはドライヤーを頭皮から20cm以上離し、髪の根元に温風を当てて頭皮全体を素早く乾かします。
頭皮が8割方乾いたら冷風に切り替えて髪全体を乾かし、キューティクルを引き締めます。このひと手間で髪のツヤを保ちながら、頭皮の乾燥を防ぐことができます。

シャンプー後の保湿ケアで乾燥に打ち勝つ
洗顔後に化粧水で肌を保湿するのと同じように、シャンプー後の頭皮にも保湿ケアが必要です。乾燥を防ぎ、バリア機能を高めるためのひと手間を加えましょう。
タオルドライの正しい方法
ドライヤーの時間を短縮し、熱によるダメージを減らすためにも、タオルドライは重要です。
ゴシゴシと擦るのではなく、タオルで頭を包み込み、指の腹で優しく頭皮をマッサージするように水分を吸い取ります。
髪の毛はタオルで挟んでポンポンと軽く叩くように拭きましょう。
頭皮用保湿ローションの選び方
頭皮用の保湿剤にはローション、エッセンス、スプレーなど様々なタイプがあります。
ベタつきが少なく、セラミドやヒアルロン酸、コラーゲンといった保湿成分が配合されているものを選びましょう。
アルコール(エタノール)の配合が少ない、低刺激性の製品がおすすめです。
頭皮用保湿剤の選び方
- 低刺激性(アルコールフリーなど)
- 高保湿成分(セラミドなど)配合
- ベタつかないテクスチャー
保湿剤の正しい塗布方法
タオルドライ後、ドライヤーで乾かす前に使用します。髪をかき分けて、乾燥が気になる部分を中心に保湿剤のノズルを直接頭皮につけて塗布します。
その後、指の腹で優しくマッサージするようになじませると、血行促進効果も得られます。
育毛シャンプーの使い方に戻る
冬のシャンプーと頭皮ケアに関するQ&A
冬のシャンプーや頭皮ケアについて、患者さんからよくいただく質問にお答えします。
- 冬は朝シャンと夜シャン、どちらが良いですか?
-
断然、夜のシャンプーをおすすめします。
1日の活動で付着した皮脂や汚れをその日のうちに洗い流すことが頭皮を清潔に保つ基本です。
また、睡眠中に髪の成長が促されるため、就寝前に頭皮をクリーンな状態にしておくことが重要です。
朝シャンは時間がないと半乾きになりやすく、頭皮が冷える原因にもなります。
- フケやかゆみがひどい場合、シャンプーを変えるべきですか?
-
はい、シャンプーが肌に合っていない可能性があります。まずは洗浄力がマイルドで保湿成分が配合されたアミノ酸系のシャンプーに変えてみましょう。
それでも改善しない場合は、フケの原因菌(マラセチア菌など)の増殖を抑える抗真菌成分が配合された薬用シャンプーを試すのも一つの方法です。
症状が続く場合は脂漏性皮膚炎などの可能性もあるため、専門医にご相談ください。
- 加湿器は頭皮の乾燥対策に有効ですか?
-
はい、非常に有効です。特に就寝中に暖房を使用する場合、室内の空気はかなり乾燥します。
加湿器を使って寝室の湿度を50〜60%程度に保つことは、喉や肌だけでなく頭皮の乾燥を防ぐ上でも効果が期待できます。
- 冬に帽子をかぶるとハゲるというのは本当ですか?
-
帽子をかぶること自体が直接的にハゲる原因になるわけではありません。むしろ、冬の寒さや乾燥、紫外線から頭皮を守るという点ではメリットもあります。
問題となるのは、長時間かぶり続けることによる「蒸れ」です。室内に入ったらこまめに帽子を脱ぐ、通気性の良い素材を選ぶといった工夫をすれば、過度に心配する必要はありません。
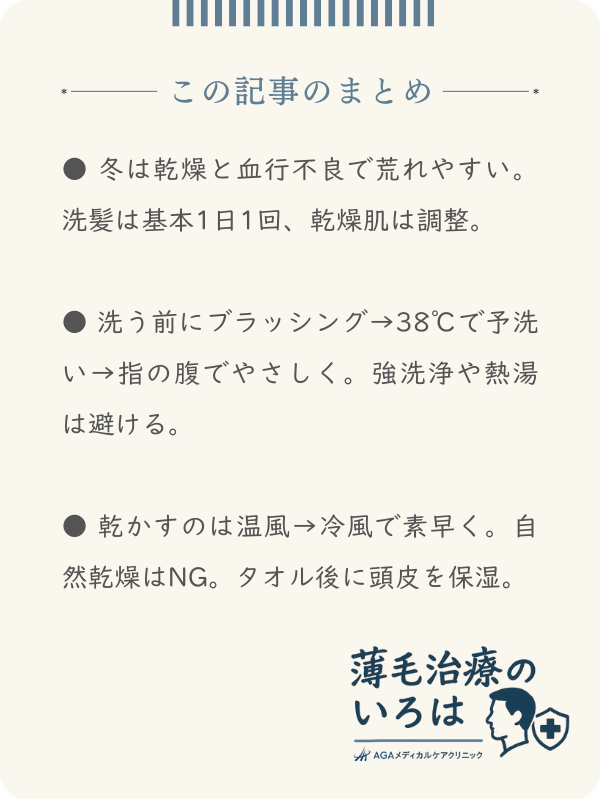
以上
参考文献
OSHIMA, Mika, et al. Improvement of Scalp Condition and Quality of Life through Proper Skin Care of Dry Scalp. Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications, 2014, 4.4: 284-292.
TAKEDA, M., et al. The cleaning effect of shampooing care by adenosine triphosphate bioluminescence system. J Nurs Care S, 2012, 2: 2167-1168.
SADGROVE, Nicholas, et al. An updated etiology of hair loss and the new cosmeceutical paradigm in therapy: Clearing ‘the big eight strikes’. cosmetics, 2023, 10.4: 106.
KIM, Sehyun, et al. Understanding the characteristics of the scalp for developing scalp care products. Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications, 2021, 11.3: 204-216.
PUNYANI, Supriya, et al. The impact of shampoo wash frequency on scalp and hair conditions. Skin appendage disorders, 2021, 7.3: 183-193.
BEAUQUEY, Bernard. Scalp and hair hygiene: shampoos. The science of hair care, 2005, 83-127.