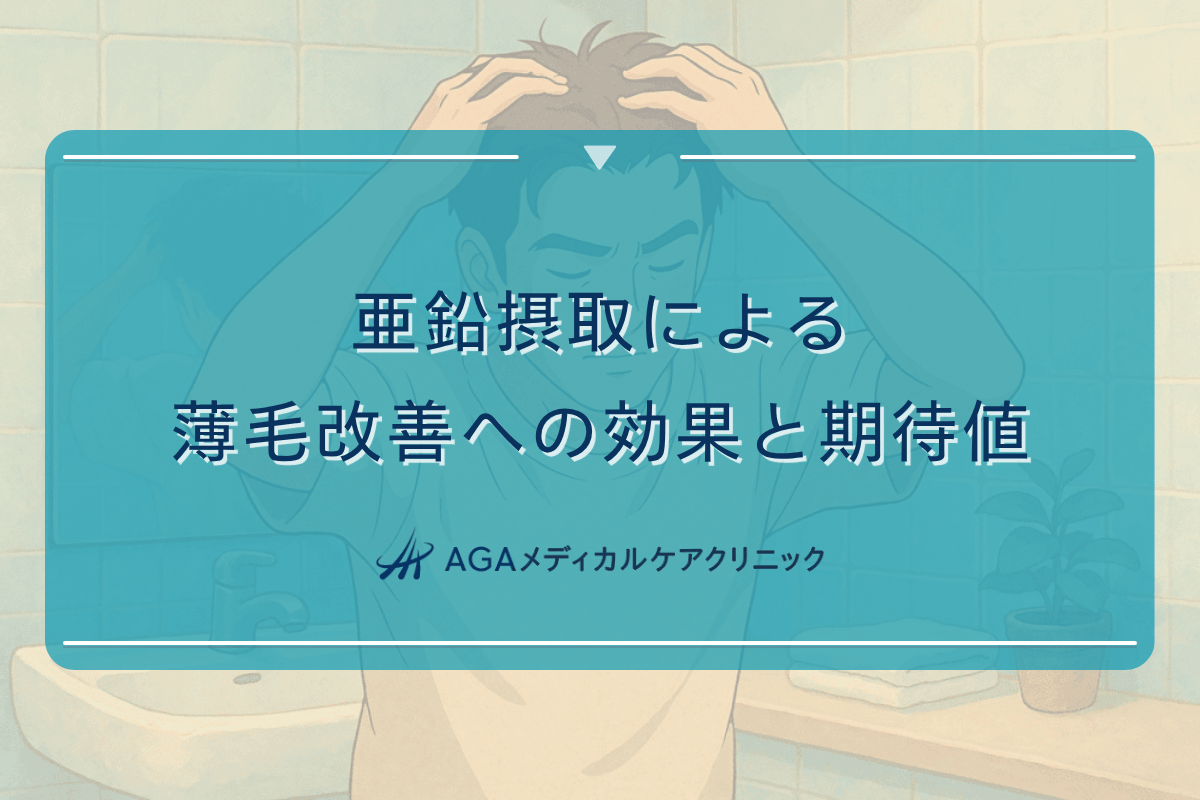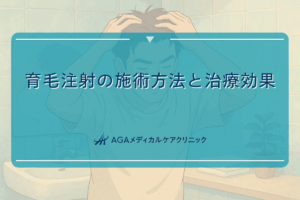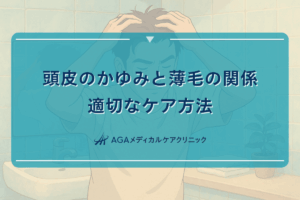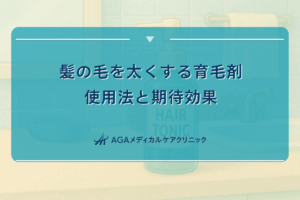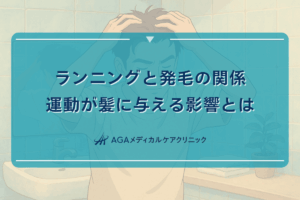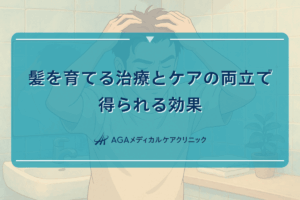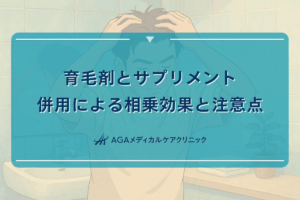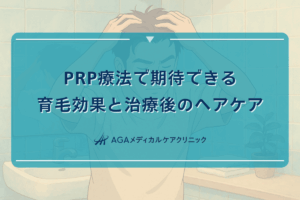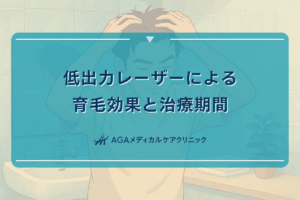健康や男性機能の維持に重要とされる「亜鉛」。近年この亜鉛が薄毛や抜け毛の改善にも効果が期待できるとして注目されています。
しかし、「本当に髪に良いのか」「サプリメントを飲めば髪は生えるのか」といった疑問を持つ方も少なくありません。
この記事では亜鉛が髪の健康、特に男性の薄毛に対してどのように関わるのかを医学的観点から解説します。
亜鉛の正しい知識を身につけ、効果的な摂取方法と薄毛改善への現実的な期待値について理解を深めましょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
亜鉛と髪の健康 – なぜ男性に重要なのか
亜鉛は体内で作り出すことのできない必須ミネラルの一つであり、全身の細胞の成長と分裂に深く関わっています。
特に髪の健康を維持し、男性特有の薄毛に対抗する上で非常に重要な役割を担っています。
髪の主成分ケラチンの合成に不可欠な亜鉛
髪の毛の約90%は「ケラチン」というタンパク質でできています。食事から摂取したタンパク質を髪の毛の材料であるケラチンへと再合成する際に、亜鉛は酵素の働きを助ける補酵素として機能します。
いくらタンパク質を摂取しても、亜鉛が不足しているとこの合成作業が滞り、強く健康な髪を作ることができません。
亜鉛の体内での主な働き
| 分類 | 主な働き |
|---|---|
| 細胞分裂・新陳代謝 | 新しい細胞の生成をサポート(髪、皮膚、爪など) |
| 免疫機能 | 免疫細胞の活性化を助ける |
| ホルモン作用 | 男性ホルモンの代謝、インスリンの合成などに関与 |
AGAの原因物質を抑制する働き
男性の薄毛の主な原因であるAGA(男性型脱毛症)は男性ホルモンのテストステロンが「5αリダクターゼ」という酵素によって、より強力なDHT(ジヒドロテストステロン)に変換されることで進行します。
亜鉛には、この5αリダクターゼの働きを抑制する作用があることが研究で示唆されています。
このことから、亜鉛を適切に摂取することはAGAの進行を緩やかにする一助となる可能性があります。

亜鉛が不足しやすい現代の食生活
亜鉛は加工食品の製造過程で失われやすい栄養素です。また、インスタント食品やファストフードに含まれる食品添加物の中には亜鉛の吸収を妨げるものもあります。
外食や加工食品に偏った食生活を送っていると、知らず知らずのうちに亜鉛不足に陥りやすいのが現状です。
亜鉛不足が引き起こす身体と髪へのサイン
亜鉛が不足すると私たちの身体は様々なサインを発します。髪の変化だけでなく、全身の状態にも注意を向けてみましょう。
髪の変化 – 抜け毛、細毛、白髪
亜鉛不足のサインが顕著に現れやすいのが髪です。ケラチンの合成がうまくいかなくなることで髪の成長が妨げられ、抜け毛や細毛につながります。
また、髪の色素であるメラニンを生成する細胞の働きも低下するため、白髪が増える一因となることもあります。
皮膚や爪に現れる異常
亜鉛は新陳代謝が活発な部位で多く消費されるため、皮膚や爪にも影響が出やすいです。
肌荒れや湿疹、傷の治りが遅くなる、爪に白い斑点や線が現れる、爪がもろくなる、といった症状は亜鉛不足のサインかもしれません。
亜鉛不足のセルフチェック
| 部位 | 主なサイン |
|---|---|
| 髪 | 抜け毛の増加、髪が細くなった、白髪が増えた |
| 皮膚 | 肌荒れ、ニキビ、傷の治りが遅い |
| 爪 | 白い斑点ができる、もろく割れやすい |
| その他 | 味が分かりにくい、風邪をひきやすい、疲れやすい |

味覚障害や免疫力の低下
舌にある味を感じる細胞「味蕾(みらい)」は新陳代謝が非常に速いため、亜鉛が不足すると機能が低下し、味が分かりにくくなる「味覚障害」を引き起こします。
また、免疫細胞の働きにも亜鉛は重要で、不足すると免疫力が低下して風邪をひきやすくなったり、感染症にかかりやすくなったりします。
亜鉛を多く含む食品と効率的な摂取方法
亜鉛は日々の食事から意識的に摂取することが基本です。ここでは亜鉛が豊富な食材と、その吸収率を高めるための工夫を紹介します。
亜鉛が豊富な食材一覧
亜鉛は肉類、魚介類、種実類など幅広い食品に含まれています。特に牡蠣は「亜鉛の王様」と呼ばれるほど含有量が多いことで知られています。
亜鉛を多く含む食品の例
| 食品カテゴリー | 主な食品 |
|---|---|
| 魚介類 | 牡蠣、うなぎ、いわし、たらこ |
| 肉類 | 牛赤身肉、豚レバー、鶏肉 |
| その他 | 高野豆腐、カシューナッツ、卵、チーズ |
吸収率を高める栄養素 – ビタミンCとクエン酸
亜鉛は比較的吸収率が低いミネラルですが、特定の栄養素と一緒に摂ることで吸収率を高めることができます。
ビタミンCやクエン酸は亜鉛を溶けやすい形に変え、体内への吸収を助ける働きがあります。レモンや梅干しなどを食事に取り入れるのがお勧めです。
吸収を妨げる成分 – フィチン酸とタンニン
一方で、亜鉛の吸収を阻害する成分も存在します。穀類や豆類に多く含まれるフィチン酸や、コーヒーやお茶に含まれるタンニンは、亜鉛と結合して吸収を妨げます。
食事中や食後すぐの濃いお茶やコーヒーの摂取は避けた方が賢明です。
亜鉛の吸収を助ける・妨げる成分
| 分類 | 成分 | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| 吸収を助ける | ビタミンC | レモン、ブロッコリー、ピーマン |
| クエン酸 | 梅干し、柑橘類、酢 | |
| 吸収を妨げる | フィチン酸 | 玄米、豆類、インスタント食品 |
| タンニン | コーヒー、緑茶、紅茶 |

サプリメントによる亜鉛摂取の注意点
食事だけで十分な亜鉛を摂取するのが難しい場合、サプリメントの活用も一つの方法です。
しかし、やみくもに摂取するのは禁物です。正しい知識を持って利用しましょう。
1日の摂取推奨量と上限量
厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準」では成人男性の亜鉛の推奨量は1日11mg、耐容上限量は40〜45mgとされています。
サプリメントを利用する際は、この上限量を超えないように注意が必要です。
成人男性の亜鉛摂取量の目安(1日あたり)
| 項目 | 摂取量 |
|---|---|
| 推奨量 | 11mg |
| 耐容上限量 | 40〜45mg |
過剰摂取が招くリスクと副作用
亜鉛を長期間にわたって過剰に摂取すると、様々な健康上のリスクが生じます。特に他の重要なミネラルである「銅」や「鉄」の吸収を阻害してしまうことが大きな問題です。
これにより、貧血や免疫機能の低下、善玉コレステロールの減少などを引き起こす可能性があります。
- 銅欠乏による貧血、白血球減少
- 鉄の吸収阻害
- 胃の不快感、吐き気、下痢
- 善玉(HDL)コレステロールの低下
サプリメントの選び方と飲むタイミング
亜鉛サプリメントには、グルコン酸亜鉛やクエン酸亜鉛など吸収率を高める工夫がされたものがあります。成分表示を確認して選ぶと良いでしょう。
飲むタイミングとしては、胃への負担を減らし、吸収を妨げる食事の影響を受けにくい食後がお勧めです。
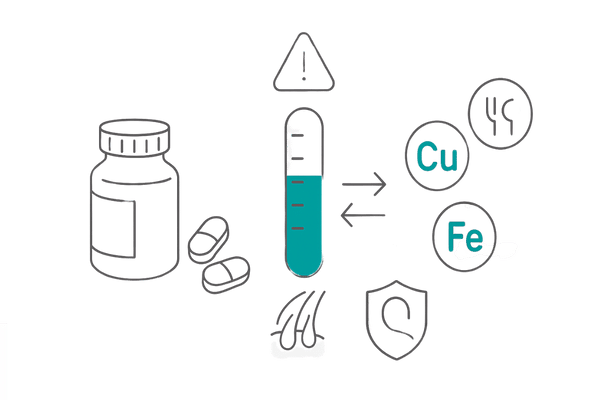
「とりあえず亜鉛」の落とし穴 – 自己判断の前に知るべきこと
「薄毛には亜鉛が良いらしい」という情報を目にし、すぐにサプリメントを試してみようと考える方は多いでしょう。
その行動力は素晴らしいものですが、少しだけ立ち止まって考えてみてください。その「とりあえず」が、かえって悩みを深くしてしまう可能性があるのです。
なぜサプリを飲んでも効果を感じないのか
期待を込めてサプリを飲み始めたものの、「数週間経っても、数ヶ月経っても、何も変わらない…」。そう感じてがっかりした経験はありませんか。
その原因はあなたの抜け毛が、そもそも亜鉛不足だけが問題ではなかったからかもしれません。あるいは摂取量が不適切であったり、吸収を妨げる生活習慣があったりする可能性も考えられます。
抜け毛の原因は亜鉛不足だけではない現実
男性の薄毛の大部分は遺伝や男性ホルモンの影響によるAGA(男性型脱毛症)です。その他にもストレス、生活習慣の乱れ、頭皮環境の悪化など、抜け毛の原因は複雑に絡み合っています。
亜鉛不足は、それら数ある要因の一つに過ぎません。根本的な原因を見ずに亜鉛の摂取という一つの対策だけで全てを解決しようとすることは、的の外れた努力になってしまう危険性があります。
期待と現実のギャップがもたらす心理的負担
「これを飲めばきっと良くなる」という期待が大きいほど、効果が見えない時の失望感は大きくなります。
そして、「自分には効果がないんだ」「もう何をしても無駄なのかもしれない」と、さらなるストレスや不安を抱え込むことになりかねません。
この心理的な負担は血行不良などを通じて、かえって髪の健康に悪影響を及ぼすという悪循環を生むことさえあります。
専門医の診断が最適な解決策への近道である理由
自己判断で様々な対策を試すことは時間とお金を浪費し、精神的にも疲弊してしまう可能性があります。
専門のクリニックでは問診や頭皮診断、必要であれば血液検査などを通じて、あなたの薄毛の根本原因を突き止めます。
亜鉛が本当に不足しているのか、AGAがどの程度進行しているのか、他に改善すべき点はないのか。正確な診断に基づいて、あなただけの治療計画を立てることが、悩みを解決する最も確実で効率的な道筋なのです。
クリニックで行う亜鉛に関連した薄毛治療
薄毛の専門クリニックでは、亜鉛という栄養素の観点からも多角的なアプローチを行います。自己流のケアとの違いを解説します。
血液検査による栄養状態の正確な把握
クリニックでは、まず血液検査によって体内の亜鉛やその他のミネラル、ビタミンの数値を正確に測定します。
「なんとなく足りないかも」という推測ではなく、客観的なデータに基づいて本当に栄養素が不足しているのか、どの程度補う必要があるのかを判断します。
栄養指導とサプリメントの処方
検査結果に基づき、医師や管理栄養士が具体的な食事内容のアドバイスを行います。その上で食事だけでは補給が難しい場合には、医療機関でのみ扱える高品質なサプリメントを処方することもあります。
市販品と異なり、成分の含有量や吸収率が考慮されたものを適切な量だけ摂取できるのが利点です。
医療機関での栄養アプローチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 血液検査 | 亜鉛、鉄、ビタミンなどの血中濃度を測定し、栄養状態を客観的に評価する |
| 食事指導 | 検査結果に基づき、個人の食生活に合わせた具体的な改善案を提案する |
| サプリメント処方 | 不足している栄養素を補うため、品質と含有量が保証された医療用サプリを処方する |
亜鉛補充とAGA治療薬の併用効果
もし薄毛の原因がAGAであると診断された場合、亜鉛の補充と並行してフィナステリドやデュタステリドといったAGA治療薬の服用を提案します。
AGAの進行を薬で食い止めながら亜鉛で髪の成長の土台を整える。この両輪からのアプローチが薄毛改善の相乗効果を生み出します。
自分でできる育毛ケアに戻る
よくある質問
- 亜鉛を摂り始めてからどのくらいで効果が出ますか?
-
効果を実感するまでの期間には個人差がありますが、一般的には3ヶ月から6ヶ月程度の継続が必要です。
髪にはヘアサイクル(毛周期)があり、新しい髪が成長して目に見える長さになるまでには時間がかかります。まずは、焦らずに継続することが大切です。
- 亜鉛サプリはいつ飲むのが効果的ですか?
-
食後に摂取することをお勧めします。亜鉛は空腹時に摂取すると胃に負担をかけ、吐き気などの不快感を引き起こすことがあります。
また、コーヒーやお茶に含まれるタンニンは亜鉛の吸収を妨げるため、食中や食後すぐの摂取は避けるのが賢明です。
- 亜鉛の過剰摂取で抜け毛が増えることはありますか?
-
直接的に抜け毛を増やすというよりは、健康への悪影響が懸念されます。
亜鉛を過剰に摂取すると、銅や鉄といった他の必須ミネラルの吸収が阻害されます。特に銅が欠乏すると、髪の健康維持にも影響が出る可能性があります。
サプリメントを利用する際は、必ず上限量を守ってください。
- 亜鉛を摂ればAGAは治りますか?
-
いいえ、亜鉛だけでAGAを完治させることはできません。亜鉛にはAGAの原因物質の働きを抑制する可能性が示唆されていますが、その効果は限定的です。
AGAの進行を本格的に食い止めるには、専門のクリニックで処方される内服薬などの医学的治療が必要です。亜鉛はあくまで治療をサポートするものとお考えください。
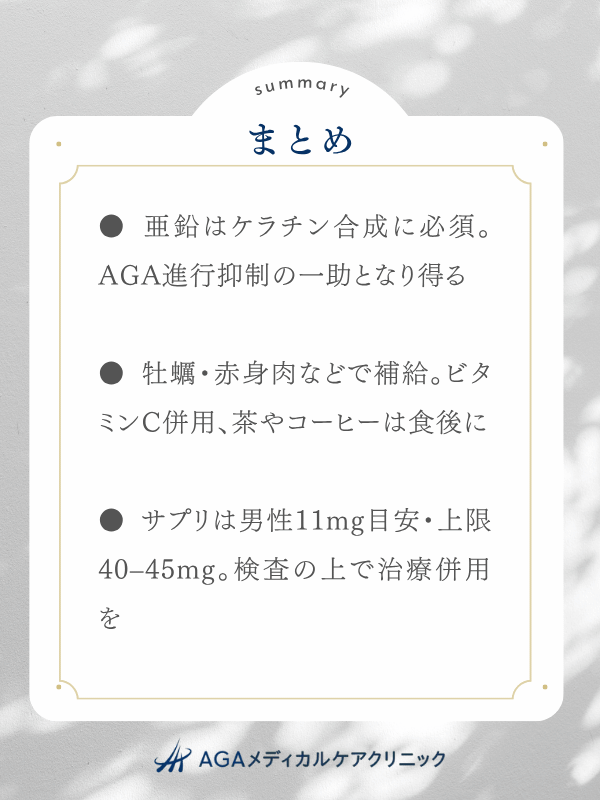
参考文献
DRAKE, Lara, et al. Evaluation of the safety and effectiveness of nutritional supplements for treating hair loss: a systematic review. JAMA dermatology, 2023, 159.1: 79-86.
MOUSSA, Noura Hussein Abbas Mahmoud; HAWAS, Amal Wagdy Abdelaziz; EL-KAMEL, Mohammed Fawzy. Evaluation of Serum Zinc Level in Patients with Pattern Hair Loss (A Case-Controlled Study). Egyptian Journal of Hospital Medicine, 2024, 94.1: 369-374.
THOMPSON, Jordan M., et al. The role of micronutrients in alopecia areata: a review. American journal of clinical dermatology, 2017, 18.5: 663-679.
WANG, Ruilong, et al. Micronutrients and Androgenetic Alopecia: A Systematic Review. Molecular Nutrition & Food Research, 2024, 68.22: 2400652.
KHAN, Zafar Ullah. THE EFFICACY OF ORAL ZINC SULFATE IN PATIENTS OF PATCHY ALOPECIA AREATA PRESENTING IN A TERTIARY CARE HOSPITAL. 2021.
KONDRAKHINA, Irina N., et al. A cross-sectional study of plasma trace elements and vitamins content in androgenetic alopecia in men. Biological Trace Element Research, 2021, 199.9: 3232-3241.