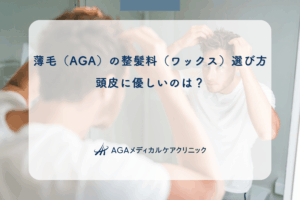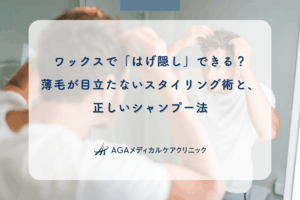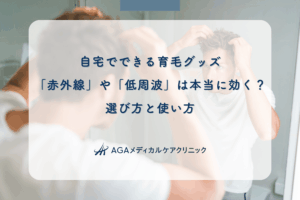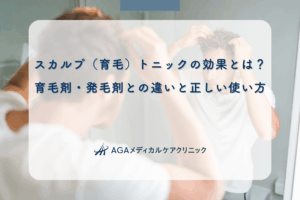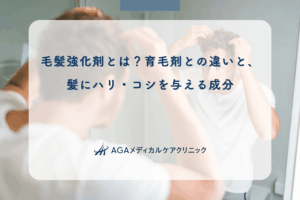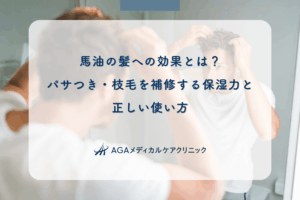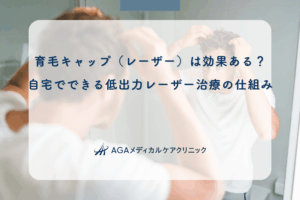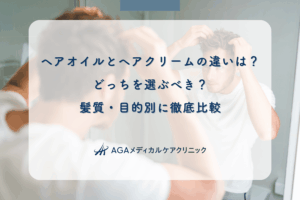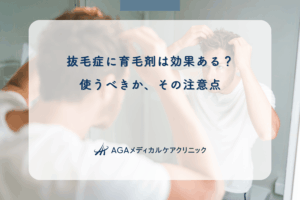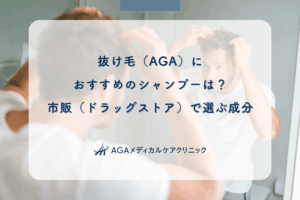「養毛剤とは何か」「育毛剤とは何が違うのか」といった疑問を抱いている方は少なくありません。
特にフケやかゆみ、頭皮の乾燥といったトラブルを抱えている方にとって、養毛剤は日々の頭皮ケアを充実させる重要なアイテムになり得ます。
養毛剤は、単に髪の毛を育てるためのものではなく、健康な髪の毛が生えるための土壌、すなわち頭皮環境を健やかに整えることを主な目的とします。
本記事では、養毛剤の基本的な定義から、フケやかゆみを防ぐために配合されている有効成分、効果を最大限に引き出すための正しい使い方、そして自分に合った製品を選ぶための重要なポイントまで、親切丁寧にご紹介します。
読者の皆さまが養毛剤を正しく理解し、毎日の頭皮ケアに取り入れることで、清潔で快適な頭皮環境を維持できるよう、具体的な情報を提供します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
養毛剤(ヘアトニック)とは何か?育毛剤との明確な違い
養毛剤と育毛剤はしばしば混同されがちですが、その目的や期待できる効果、法律上の分類には明確な違いがあります。
これらを理解することは、自分の頭皮や髪の毛の状態に合わせて適切な製品を選ぶ上で非常に重要です。
養毛剤は、主に頭皮の環境を整えることに重点を置き、すでに生えている髪の毛を健やかに保ち、抜け毛を予防する役割を担います。
養毛剤の定義と主な役割
養毛剤、あるいはヘアトニックは、頭皮にうるおいを与え、フケやかゆみを抑え、髪の毛のハリやコシを保つことを目的とした製品です。
頭皮の乾燥を防ぎ、皮脂バランスを整えることで、毛根の活動をサポートし、抜け毛を防ぐための環境を構築します。
養毛剤は「医薬部外品」または「化粧品」に分類され、頭皮の美容液やローションのような役割を担うと言えるでしょう。
頭皮をリフレッシュさせ、清潔に保つ効果も高く、特に洗髪後のリフレッシュや頭皮のにおい対策として日常的に利用されています。
育毛剤が持つ作用と目的
一方で育毛剤は、養毛剤よりも一歩踏み込んだ目的を持ちます。その目的は、薄毛や脱毛の進行を予防し、発毛を促す、または既存の髪の毛の成長を助けることです。
育毛剤も主に「医薬部外品」に分類されますが、中には「医薬品」として発毛作用が認められた成分を含む製品もあります。
育毛剤は、血行を促進する成分や、毛乳頭細胞に働きかけて髪の毛の成長期を延長させる成分などを配合し、養毛剤よりも積極的に髪の毛の成長サイクルに影響を与えることを目指します。
医薬部外品と化粧品の分類
養毛剤と育毛剤の分類は、配合されている成分が持つ効能・効果によって決められます。
医薬部外品の役割
医薬部外品は、厚生労働大臣が認めた特定の「有効成分」が一定濃度で配合されており、人体に対する作用が緩和で、予防や衛生を目的とするものです。
養毛剤や育毛剤として販売される製品の多くは、この医薬部外品に該当し、「育毛・養毛」「フケ・かゆみの防止」「脱毛の予防」といった効能効果を表示できます。
化粧品の役割
化粧品は、身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、健やかに保つことを目的としています。
養毛剤の中には、医薬部外品の有効成分を含まず、頭皮の保湿や清浄といった目的で「化粧品」として販売されるものもあります。
化粧品に分類される養毛剤は、頭皮のコンディションを整える上で有用ですが、医薬部外品のような「育毛」や「脱毛の予防」といった具体的な効能効果を謳うことはできません。
養毛剤と育毛剤の比較
養毛剤と育毛剤の主な違いをまとめた表を示します。
| 項目 | 養毛剤(ヘアトニック) | 育毛剤 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 頭皮環境の整備、フケ・かゆみ防止、既存毛の維持 | 薄毛・脱毛の予防、発毛促進のサポート |
| 分類 | 医薬部外品または化粧品 | 医薬部外品または医薬品 |
| 作用 | 頭皮への栄養補給、保湿、清浄作用が中心 | 血行促進、毛根活性化など、成長サイクルへの働きかけ |
養毛剤が頭皮環境にもたらす効果とその成分
養毛剤は、頭皮の様々なトラブルに対応するために、多岐にわたる成分をバランス良く配合しています。
特にフケやかゆみといった不快な症状の解消、そして健康な髪の毛の土台作りに役立つ成分が重要視されます。
フケやかゆみを抑える成分
フケやかゆみは、頭皮の乾燥や、マラセチア菌などの常在菌の異常な増殖、皮脂の過剰分泌、あるいは炎症など、様々な原因によって引き起こされます。
養毛剤は、これらの原因にアプローチする有効成分を配合することで、頭皮を清潔かつ健やかに保ちます。
抗炎症作用を持つ成分
グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)やアラントインなどの成分は、頭皮の炎症を鎮め、かゆみの発生を抑える作用があります。
炎症が原因で発生するかゆみや赤みに対して効果を発揮し、頭皮のバリア機能の回復をサポートします。
殺菌作用を持つ成分
ピロクトンオラミンやサリチル酸などの成分は、フケの原因となるマラセチア菌などの常在菌の過剰な増殖を抑制します。
これにより、菌の代謝物が引き起こす炎症やフケの発生を予防し、頭皮を衛生的に保ちます。
フケ・かゆみ対策の有効成分
頭皮の不快な症状を抑えるために、養毛剤によく配合される主な有効成分をまとめました。
| 成分名 | 主な作用 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| グリチルリチン酸ジカリウム | 抗炎症 | 頭皮の赤み、かゆみの鎮静 |
| ピロクトンオラミン | 殺菌、抗真菌 | フケの原因菌の増殖抑制 |
| センブリエキス | 血行促進 | 頭皮の血流改善、新陳代謝の促進 |
頭皮の保湿と柔軟性を保つ成分
頭皮の乾燥は、フケやかゆみの直接的な原因となるだけでなく、頭皮のバリア機能を低下させ、外部刺激を受けやすい状態にしてしまいます。
健康な髪の毛を育てるためには、頭皮に適度なうるおいと柔軟性を持たせることが重要です。
水分保持力を高める成分
ヒアルロン酸、セラミド、コラーゲンといった成分は、頭皮の角質層に浸透し、高い保水力で頭皮のうるおいを保持します。
これにより、乾燥による細かいフケの発生を防ぎ、頭皮のつっぱり感を和らげます。
エモリエント作用を持つ成分
天然由来のオイルやスクワランなどは、頭皮表面に保護膜を形成し、水分蒸発を防ぐとともに、頭皮を柔らかく保つ役割を果たします。
柔軟な頭皮は、栄養分が毛根まで届きやすい状態を作り出します。
清涼感を与える成分
多くの養毛剤には、使用感の向上と頭皮のリフレッシュを目的として、清涼感を与える成分が配合されています。
メントールとエタノール
メントールは、塗布時にひんやりとした感覚を与え、頭皮を爽快にします。また、エタノール(アルコール)は、成分の溶解助剤として使われるほか、揮発する際に熱を奪うことで清涼感を生み出します。
これらの成分は、特に脂性肌や夏場の使用において、頭皮をすっきりさせたいというニーズを満たします。ただし、敏感肌の方やアルコールに弱い方は、これらの成分の配合量に注意して選ぶ必要があります。
効果的な養毛剤の使い方と正しい塗布方法
養毛剤の効果を最大限に引き出すためには、ただ塗るだけでなく、正しいタイミングで適切な量を、正しい方法で頭皮に届けることが大切です。
使用方法を誤ると、成分が毛穴に詰まったり、頭皮を刺激したりする可能性があるため、手順を守って使用しましょう。
塗布の適切なタイミングと頻度
養毛剤を塗布する最も効果的なタイミングは、頭皮が最も清潔で、成分が浸透しやすい状態にあるときです。
入浴後のゴールデンタイム
一般的に、シャンプー後の清潔な頭皮に塗布するのが最良とされます。シャンプーで頭皮の汚れや余分な皮脂が洗い流され、毛穴がきれいになっているため、養毛剤の成分が浸透しやすくなります。
ただし、タオルドライで髪の毛と頭皮の水分をしっかり拭き取ってから使用することが重要です。水分が多すぎると養毛剤が薄まり、効果が薄れてしまいます。
朝のスタイリング前の利用
朝のスタイリング前も、頭皮のリフレッシュやにおい対策として適したタイミングです。
ただし、朝は少量にとどめ、頭皮になじませる程度に留めることで、スタイリング剤や日中の皮脂と混ざるのを防ぎます。
頻度の目安
多くの養毛剤は、朝晩の1日2回の使用を推奨しています。製品に記載されている使用頻度と量を守り、毎日継続して使うことで、頭皮環境の維持に繋げます。
頭皮マッサージの相乗効果
養毛剤を塗布した後、頭皮マッサージを組み合わせることで、養毛剤の効果を高められます。
マッサージには、頭皮の血行を促進し、硬くなった頭皮を柔らかくする効果があります。
血行促進の重要性
頭皮の血行が良くなると、毛根に必要な酸素や栄養素がスムーズに運ばれるようになり、髪の毛の成長をサポートします。また、マッサージによるリラックス効果は、ストレスによる頭皮の緊張を和らげることにも役立ちます。
マッサージの手順
マッサージは、指の腹を使い、頭皮全体を優しく動かすように行うことが重要です。
爪を立てたり、強く擦りすぎたりすると、頭皮を傷つけたり、炎症を引き起こしたりする原因になります。特に硬くなりがちな頭頂部や、血行が滞りやすい首の付け根あたりを重点的に行いましょう。
効果を高めるマッサージ手順
養毛剤を塗布した後に試していただきたい簡単なマッサージの手順をまとめました。
| 手順 | ポイント | 時間 |
|---|---|---|
| 1.生え際から頭頂部へ | 指の腹を使い、円を描くように優しく持ち上げる | 約1分 |
| 2.側頭部から頭頂部へ | 耳の上あたりから、頭頂部に向かって揉みほぐす | 約1分 |
| 3.後頭部から首筋へ | 首の付け根に向かって押し下げるようにほぐす | 約30秒 |
養毛剤を使う前の準備
養毛剤の成分を頭皮にしっかりと浸透させるためには、塗布前の準備が非常に大切です。
頭皮を清潔に保つ
まず、シャンプーで頭皮の皮脂や汚れをきれいに洗い流します。古い皮脂や整髪料の残りカスが毛穴を塞いでいると、せっかくの養毛剤の有効成分が十分に届かなくなってしまいます。
タオルドライの徹底
洗髪後は、吸水性の高いタオルで頭皮と髪の毛の水分を丁寧に拭き取ります。水滴が垂れない程度に水分を取り除くことで、養毛剤が水で薄まるのを防ぎ、適量を頭皮に留めることができます。
養毛剤を使用する前に準備すべき項目は以下の通りです。
- シャンプーで頭皮の汚れを完全に除去すること
- タオルドライで水分をしっかりと拭き取ること
これらの準備を行うことで、養毛剤の成分がより効果的に頭皮に作用する土台を作ります。
養毛剤を選ぶ際に確認すべきポイント
数多くの養毛剤が市場に出回っている中で、自分の頭皮の状態や目的に合わない製品を選んでしまうと、期待した効果が得られないどころか、かえって頭皮トラブルを引き起こす可能性もあります。
養毛剤を選ぶ際には、いくつかの重要なポイントを確認しましょう。
自分の頭皮タイプに合わせた選び方
頭皮の状態は、乾燥肌、脂性肌、敏感肌など、人によって大きく異なります。
養毛剤は、そのベースとなる成分やテクスチャーが頭皮タイプに合わせて作られているため、自分のタイプを把握することが重要です。
乾燥肌・敏感肌の方
乾燥肌や敏感肌の方は、保湿成分が豊富に配合され、アルコール(エタノール)や香料、着色料などの刺激となる可能性のある成分の配合が控えめな製品を選ぶと良いでしょう。
オイルベースやローションタイプの、頭皮に優しくうるおいを与えるものが適しています。
脂性肌の方
皮脂の分泌が多い脂性肌の方は、さっぱりとした使用感で、清涼感のある成分が配合されたスプレータイプやトニックタイプが適しています。
過剰な皮脂分泌を抑える成分や、頭皮を清潔に保つ殺菌作用のある成分が含まれているかを確認しましょう。
頭皮タイプ別推奨養毛剤
頭皮のタイプ別に、選ぶべき養毛剤の特性をまとめた表をご覧ください。
| 頭皮タイプ | 主な特徴 | 推奨される養毛剤の特性 |
|---|---|---|
| 乾燥肌 | 細かく白いフケ、頭皮のつっぱり感 | 高保湿、低刺激、アルコール控えめ |
| 脂性肌 | べたつき、黄色っぽいフケ、頭皮のにおい | 清涼感、皮脂抑制成分、さっぱりした使用感 |
| 敏感肌 | かゆみ、赤み、すぐに刺激を感じる | 無香料・無着色、天然由来成分、アレルギーテスト済み |
配合されている有効成分の確認
製品のパッケージや成分表示を確認し、自分の解決したい問題にアプローチする有効成分が配合されているかをチェックします。
フケ・かゆみ対策の場合
フケやかゆみを主に対策したい場合は、「グリチルリチン酸ジカリウム」や「ピロクトンオラミン」などの抗炎症・殺菌成分が含まれているかを最優先で確認しましょう。
血行促進を重視する場合
頭皮環境を整え、健康な髪の毛を維持したい場合は、「センブリエキス」や「トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE誘導体)」など、血行を促進する成分が配合されているかを確認します。
これらの成分は、頭皮への栄養供給をスムーズにするのをサポートします。
継続しやすいテクスチャーや香りの選択
養毛剤は、毎日継続して使用することで初めて効果を発揮するものです。そのため、使用感や香りが自分の好みに合っているかどうかも、選ぶ上での重要な要素となります。
テクスチャーの好み
ベタつくのが苦手な方は、サラッとした水のようなテクスチャーのトニックタイプを。
頭皮にしっかりうるおいを与えたい方は、とろみのあるローションタイプを選ぶなど、季節や好みに合わせて選びましょう。
香りの有無と種類
養毛剤には、メントールなどの清涼感のある香り、無香料、シトラス系やウッディ系といったリラックス効果を狙った香りが付いているものがあります。
毎日の習慣としてストレスなく続けられるよう、自分の嗅覚に合うものを選びましょう。
頭皮ケアの基本 養毛剤とシャンプーの連携
養毛剤の効果を最大限に引き出し、フケやかゆみのない健康な頭皮環境を築くためには、シャンプーとの連携が不可欠です。
シャンプーは頭皮の土台を準備する役割を、養毛剤はその土台に栄養と保護を与える役割を担います。
正しいシャンプーの手順
毎日のシャンプーは、ただ髪の毛を洗うだけでなく、頭皮の汚れをしっかりと落とし、清潔に保つための儀式として捉える必要があります。
予洗いの徹底
シャンプーをつける前に、ぬるま湯で2〜3分かけて髪の毛と頭皮をしっかりと洗い流す「予洗い」が重要です。これにより、汚れの約7〜8割を落とせると言われています。
泡立てと指の腹での洗浄
シャンプーは手のひらでしっかりと泡立ててから頭皮に乗せます。洗う際は、爪を立てずに指の腹を使い、頭皮をマッサージするように優しく洗いましょう。
すすぎ残しは厳禁
シャンプー成分が頭皮に残っていると、それが刺激となり、フケやかゆみ、炎症の原因になります。
特に耳の周りや生え際、後頭部はすすぎ残しやすいため、時間をかけて念入りに洗い流しましょう。
正しいシャンプーの際に意識すべき重要点をまとめました。
- シャンプー前の丁寧な予洗い
- 爪を立てず指の腹で優しく洗うこと
- すすぎ残しがないよう徹底すること
シャンプー選びの重要性
養毛剤の効果を高めるためには、頭皮タイプに合ったシャンプーを選ぶことも大切です。
洗浄力が強すぎるシャンプーは、必要な皮脂まで洗い流してしまい、頭皮の乾燥やバリア機能の低下を招きます。
アミノ酸系シャンプーの活用
頭皮への負担を軽減し、保湿を重視したい場合は、洗浄力がマイルドなアミノ酸系シャンプーを選ぶと良いでしょう。これは、敏感肌や乾燥肌の方に特に推奨されます。
薬用シャンプーの利用
フケやかゆみの症状が強い場合は、有効成分(ピロクトンオラミン、ミコナゾール硝酸塩など)が配合された薬用シャンプーを一時的に使うことも検討しましょう。
シャンプー選びのチェックポイント
養毛剤との相性や頭皮環境を考慮したシャンプー選びのポイントをまとめました。
| チェックポイント | 確認すべき内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 洗浄成分 | アミノ酸系、石鹸系などマイルドな成分 | 高級アルコール系は洗浄力が強すぎる場合がある |
| 薬用成分 | 抗炎症、殺菌成分の有無 | 有効成分が肌に合うか少量で試す |
| 頭皮タイプ | 乾燥肌用、脂性肌用、敏感肌用 | 自分の頭皮の状況に合わせて選ぶ |
頭皮と髪の毛の乾燥対策
シャンプーと養毛剤の使用に加え、頭皮と髪の毛を過度に乾燥させないことも、健康な頭皮環境を維持する上で重要です。
ドライヤーの適切な使い方
洗髪後、髪の毛を自然乾燥させるのは避け、すぐにドライヤーで乾かしましょう。濡れた状態の頭皮は雑菌が繁殖しやすく、また髪の毛のキューティクルが開いてダメージを受けやすい状態です。
ドライヤーを使う際は、頭皮から20〜30cmほど離し、温風を同じ場所に当て続けないよう注意しましょう。仕上げに冷風を使うと、キューティクルが閉じ、髪の毛にツヤを与えられます。
養毛剤を習慣化するための継続の重要性
養毛剤は、数日で劇的な変化をもたらすものではありません。
頭皮環境の改善は時間を要するものであり、長期的な視点での継続的なケアが、望む結果を得るための鍵となります。
養毛剤の効果が現れるまでの期間
髪の毛には成長サイクル(毛周期)があり、新しい髪の毛が生え、成長し、抜け落ちるというサイクルを繰り返します。
養毛剤が作用し、頭皮環境が改善されて、その影響が新しい髪の毛に現れるまでには、ある程度の期間が必要です。
毛周期との関係
一般的に、髪の毛の毛周期は数か月から数年かかると言われています。
養毛剤は、主にこの毛周期の土台となる頭皮を健康に保つため、効果を実感できるようになるまでには、最低でも3か月から6か月の継続的な使用が必要と考えるべきです。
焦らず、日々の習慣として取り組むことが大切です。
長期的な視点での頭皮ケア
養毛剤の使用は、単なる一時的な対策ではなく、頭皮の健康を維持するための日々のセルフケアの一環です。
老化や環境の変化への対応
年齢を重ねるにつれて、頭皮の皮脂分泌量や水分保持能力は変化します。また、季節やストレスといった外部環境も頭皮に影響を与えます。
養毛剤を継続して使うことで、こうした変化に対して頭皮が適応するのを助け、健やかな状態を保ちやすくします。
予防としての役割
フケやかゆみといったトラブルが解消された後も、使用を続けることで、それらの再発を防ぐ「予防」としての役割を果たします。
健康な頭皮を維持し、将来的な髪の毛のトラブルを未然に防ぐために、養毛剤の習慣化は重要です。
頭皮ケアの長期目標
長期的な視点で養毛剤を継続使用することで達成できる目標をまとめました。
| 期間 | 期待できる頭皮の変化 | 具体的な目標 |
|---|---|---|
| 3ヶ月〜6ヶ月 | フケ・かゆみの減少、頭皮の乾燥改善 | 頭皮環境の土台を安定させる |
| 6ヶ月〜1年 | 髪の毛のハリ・コシの向上、抜け毛の減少 | 既存の髪の毛の質を健やかに保つ |
| 1年〜 | 頭皮トラブルの再発予防、頭皮の若々しさ維持 | 頭皮ケアを生活習慣として確立する |
日常生活での頭皮環境への配慮
養毛剤の効果を最大限に引き出すには、製品の使用だけでなく、日常生活での配慮も重要になります。
バランスの取れた食事
髪の毛の主成分はタンパク質であり、その生成にはビタミンやミネラルが必要です。バランスの取れた食事は、頭皮と髪の毛に必要な栄養を体内から供給する基本となります。
特に亜鉛やビタミンB群などは、頭皮の健康維持に役立つと言われています。
質の高い睡眠
睡眠中に分泌される成長ホルモンは、細胞の修復や再生を促します。
頭皮も例外ではなく、良質な睡眠は、養毛剤によって与えられた栄養を活かし、頭皮細胞が正常に機能するために大切です。
ストレスの管理
過度なストレスは、自律神経やホルモンバランスを乱し、血行不良を引き起こす原因となり得ます。血行不良は頭皮への栄養供給を妨げ、頭皮環境の悪化につながります。
適度な運動や趣味などを通じて、日常的にストレスを解消する習慣を持つことが重要です。
スカルプトニックに戻る
よくある質問
- 養毛剤はどれくらいの量を使えば良いですか?
-
使用量は製品によって異なりますが、一般的には頭皮全体に薄く行き渡る程度が目安です。多すぎるとべたつきの原因になることがあり、少なすぎると十分な効果が期待できません。
製品パッケージに記載されている使用量を守り、特に気になる部分には指の腹で馴染ませるように塗布してください。
- 養毛剤はいつまで使い続ける必要がありますか?
-
養毛剤は、頭皮環境を維持・改善するためのものです。
フケやかゆみの予防、既存の髪の毛のハリ・コシを保つという目的から、日常のスキンケアと同様に、使い続けることが推奨されます。
使用をやめると、頭皮環境が元に戻り、再びトラブルが発生する可能性があります。
- 頭皮に傷や湿疹がある場合でも使用できますか?
-
頭皮に傷や湿疹、炎症などの異常がある場合は、刺激となる可能性があるため、使用を控えてください。
症状を悪化させる恐れがあるため、皮膚科などの専門医に相談し、症状が治まってから使用を再開するのが安全です。
- 養毛剤を使えば髪の毛は太くなりますか?
-
養毛剤は、頭皮環境を整え、すでに生えている髪の毛を健康的に保つことを主な目的としています。
その結果として、髪の毛にハリやコシが出て、ボリュームアップしたように感じることはありますが、医学的に髪の毛を太くする効果が認められているわけではありません。
太さや本数そのものを改善したい場合は、育毛剤や医薬品の選択も視野に入れる必要があります。
- 養毛剤と整髪料を一緒に使っても問題ありませんか?
-
養毛剤は頭皮に、整髪料は髪の毛に使うものなので、併用は可能です。ただし、養毛剤を塗布する際は、頭皮に成分が届くよう、整髪料を使う前に使用してください。
また、整髪料が頭皮に付着しすぎると、毛穴詰まりの原因となるため、注意が必要です。
Reference
T. CHIU, Chin-Hsien; HUANG, Shu-Hung; D. WANG, Hui-Min. A review: hair health, concerns of shampoo ingredients and scalp nourishing treatments. Current pharmaceutical biotechnology, 2015, 16.12: 1045-1052.
SOMBOONWATTHANAKUL, Issaraporn, et al. Development of rice by-products based hair tonic mixed with traditional thai herbal extracts: a sustainable approach for hair care. Biomedical and Pharmacology Journal, 2024, 17.1: 203-216.
XIAO, Lei, et al. A Timosaponin B‐II containing scalp care solution for improvement of scalp hydration, dandruff reduction, and hair loss prevention: A comparative study on healthy volunteers before and after application. Journal of Cosmetic Dermatology, 2021, 20.3: 819-824.
GOSWAMI, Bittu; MUKHOPADHYAY, Sayantan. A brief review on “Herbal Hair Tonic”. International journal of health sciences, 2022, 6.S4: 7094-7109.
BARAK-SHINAR, Deganit; GREEN, Lawrence J. Scalp seborrheic dermatitis and dandruff therapy using a herbal and zinc pyrithione-based therapy of shampoo and scalp lotion. The Journal of clinical and aesthetic dermatology, 2018, 11.1: 26.
ISWANDI, Ridho; SUHUD, Usep. Sustainable Herbal Hair Tonic for Middle-Aged Health and Wellness. Economic, Management, Business and Accountancy International Journal, 2025, 2.1: 35-44.
CHOI, Dong‐Gi; SHIN, Woo‐Chul. Botanical Extract–Infused Shampoo and Hair Tonic for Hair Loss in Androgenetic Alopecia: A TREND‐Compliant, Prospective Single‐Arm Preexperimental Study. Journal of Cosmetic Dermatology, 2025, 24.6: e70273.
SETIAWAN, Mochammad Agung Dhani. The Effectiveness of Aloe Vera in Multiple Moist Spray Products as a Hair Tonic to Reduce Students Scalp Irritation. Jurnal Kesehatan Komunitas Indonesia, 2024, 4.2: 142-149.
LOURITH, Nattaya; KANLAYAVATTANAKUL, Mayuree. Hair loss and herbs for treatment. Journal of cosmetic dermatology, 2013, 12.3: 210-222.
ALIUDIN, Nur Amalina; DAVID, Sheba Rani; RAJABALAYA, Rajan. Formulation and in Vitro Efficacy Evaluation of Polyherbal Hair Tonics for Enhancing Hair Health on Various Hair Types. Biomedical and Pharmacology Journal, 2024, 17.4: 2643-2660.