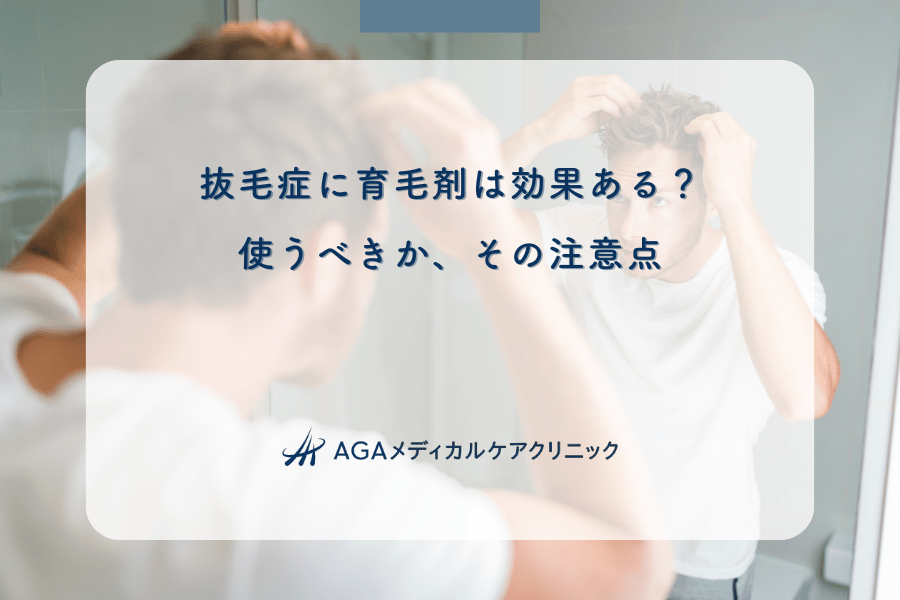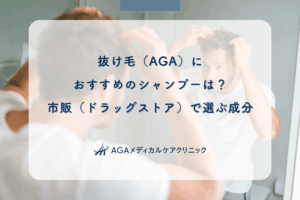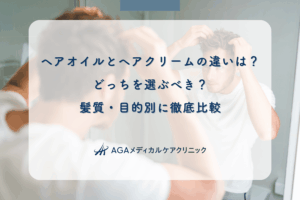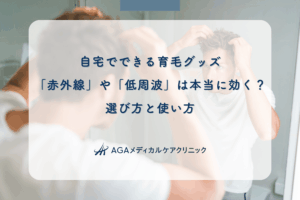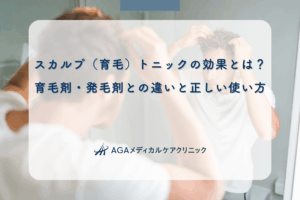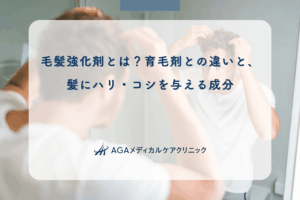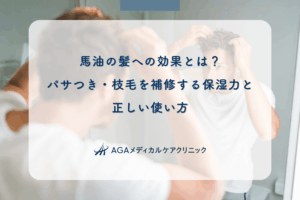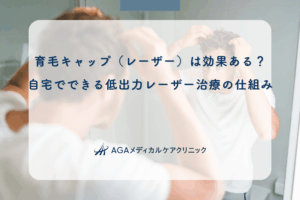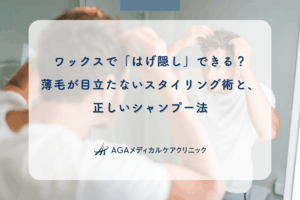「また髪を抜いてしまった…」抜毛症に悩む中で、ふと鏡を見て薄くなった部分が気になり、育毛剤の使用を考えるのは自然な気持ちです。
しかし、それが本当に抜毛症による悩みに効果があるのか、逆に頭皮を傷つけてしまわないか、不安に感じる方も多いでしょう。
この記事では、抜毛症の方が育毛剤を使うべきか、その効果の可能性と、使用を決めた場合に守るべき具体的な注意点について詳しく解説します。
ご自身の髪と頭皮を守るための正しい知識を得て、状況を改善するための一歩を踏出しましょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
抜毛症とはどのような状態か
抜毛症(ばつもうしょう)は、自分自身の髪の毛を意図せず、あるいは衝動的に引き抜いてしまう行為を繰り返す状態を指します。
この行為がやめられず、結果として脱毛斑(髪の毛が薄くなったり、なくなったりした部分)が生じることが特徴です。多くの場合、ストレスや不安が引き金になると考えられています。
抜毛症の基本的な定義
抜毛症は、精神医学的には「衝動制御の障害」の一つとして分類されることがあります。
本人は髪を抜く行為を「やめたい」と思っていても、特定の状況や感情になると無意識に、あるいは強い衝動に駆られて抜いてしまいます。
抜く瞬間やその直後に一時的な解放感や満足感を得ることがありますが、後になって後悔や自己嫌悪を感じるケースも少なくありません。
主な症状と特徴
症状の現れ方には個人差がありますが、頭頂部や側頭部の髪を抜くことが多い傾向にあります。眉毛やまぶたの毛(まつ毛)を抜く場合もあります。
抜毛行為は、リラックスしている時(テレビを見ている時、読書中など)や、逆に強いストレスを感じている時に起こりやすいです。
抜いた後の毛髪の毛根部を眺めたり、食べたりする(食毛症)といった行動を伴うこともあります。
抜毛症が起こる背景
抜毛症が始まる正確な原因は完全には解明されていませんが、複数の要因が関わっていると考えられています。遺伝的な要因、脳内の化学物質のバランス、そして環境的なストレスが挙げられます。
特に、家庭環境や学校、職場での人間関係による精神的な緊張や不安が、抜毛行為の引き金となったり、症状を悪化させたりすることが指摘されています。
AGA(男性型脱毛症)との違い
抜毛症による脱毛と、AGA(男性型脱毛症)による脱毛は、原因も見た目も異なります。AGAは男性ホルモンの影響で髪の成長サイクルが乱れ、髪が細く短くなり、徐々に薄くなる状態です。
一方、抜毛症は物理的に髪を引き抜くことによって生じる脱毛です。毛根自体がダメージを受けていなければ、抜毛行為が止まれば髪は再び生えてくる可能性があります。
抜毛症とAGAの主な違い
| 項目 | 抜毛症 | AGA(男性型脱毛症) |
|---|---|---|
| 原因 | 物理的な引き抜き行為(ストレス等が関与) | 男性ホルモン、遺伝的要因 |
| 脱毛部の特徴 | 不規則な形状、毛の長さが不揃い、切れ毛 | 生え際の後退、頭頂部の菲薄化 |
| 進行 | 抜毛行為の頻度や強さによる | ゆっくりと進行性 |
抜毛症に育毛剤は効果が期待できるのか
抜毛症で悩む方が育毛剤の使用を考えた場合、その効果は「抜毛行為そのものを止める効果」ではなく、「残っている髪や頭皮の環境を整える補助的な役割」として捉える必要があります。
育毛剤は抜毛症の根本的な原因である「抜く行為」を止めるものではありません。
育毛剤の基本的な役割
一般的に市販されている育毛剤(医薬部外品)の主な目的は、「今ある髪の毛を健康に保つこと」と「抜け毛を予防すること」です。
具体的には、頭皮の血行を促進したり、頭皮に栄養を与えたり、フケやかゆみを抑えて頭皮環境を清潔に保つ役割を持ちます。毛根が活動していることが前提となります。
抜毛症への直接的な効果は限定的
抜毛症の主な問題は、髪が自然に抜けることではなく、自分で引き抜いてしまうことです。
育毛剤を使っても、抜毛行為自体が続けば、髪が生えるスピードよりも抜くスピードが上回り、薄毛の状態は改善しません。
したがって、育毛剤が抜毛症の悩みを直接解決するというわけではありません。
育毛剤が役立つ可能性のあるケース
ただし、抜毛症の方が育毛剤を使うことが全く無意味というわけではありません。
例えば、抜毛行為が少しずつ減ってきており、残った髪や新しく生えてこようとする髪のために頭皮環境を整えたい、という場合には補助的に役立つ可能性があります。
また、抜毛行為によって頭皮に炎症やかゆみが生じている場合、それを鎮める成分(グリチルリチン酸2Kなど)を含む育毛剤が、頭皮の状態を改善する手助けになることもあります。
発毛剤(医薬品)との違い
育毛剤と混同されやすいものに「発毛剤(医薬品)」があります。発毛剤は、毛母細胞の働きを高め、新しい髪の毛を生やすことを目的としています。代表的な成分にミノキシジルがあります。
しかし、これも抜毛行為が続いている状態では効果を実感するのは難しく、抜毛症の治療として第一に選択されるものではありません。
育毛剤(医薬部外品)と発毛剤(医薬品)の目的
| 分類 | 主な目的 | 抜毛症への位置づけ |
|---|---|---|
| 育毛剤(医薬部外品) | 抜け毛予防、頭皮環境の改善 | 補助的(抜毛行為が減少傾向の場合) |
| 発毛剤(医薬品) | 新しい髪の毛の発毛促進 | 推奨されない(抜毛行為が優先課題) |
抜毛症の方が育毛剤を使うリスクと注意点
抜毛症の方が育毛剤の使用を検討する際は、効果への期待よりも先にリスクと注意点を理解することが非常に大切です。
抜毛症の根本的な問題は「髪を抜く行為」にあり、育毛剤の使用がその行為を助長したり、頭皮の状態を悪化させたりする可能性もゼロではありません。
頭皮への刺激による悪化の可能性
抜毛行為を繰り返している頭皮は、目に見えない小さな傷や炎症を抱えていることが多いです。
健康な頭皮であれば問題ない成分でも、傷ついた頭皮には刺激となり、かゆみや赤み、ヒリヒリ感を引き起こすことがあります。
特にアルコール(エタノール)を高濃度に含む製品は注意が必要です。かゆみが発生すると、それを気にしてさらに頭皮を触ってしまい、抜毛行為を誘発する悪循環に陥る危険があります。
抜毛行為が止まらない場合の問題
育毛剤を使い始めても、抜毛行為が止まらなければ、高価な育毛剤が無駄になってしまうだけでなく、精神的な負担も増大します。
「これを使っているのに良くならない」と焦りを感じ、それが新たなストレスとなって抜毛行為が悪化することも考えられます。
育毛剤は、抜毛行為を止めるための治療薬ではないことを認識しなくてはなりません。
成分が合わない場合のリスク
育毛剤に含まれる多くの成分が、すべての人に合うとは限りません。アレルギー体質の方や敏感肌の方は、特定の成分によってアレルギー反応(かぶれ)を起こす可能性があります。
抜毛症の方は、ただでさえ頭皮に意識が向きがちなため、少しの違和感でも大きなストレス源となり得ます。
育毛剤使用時の主なリスク
- 頭皮の傷や炎症への刺激
- アルコールなどによる乾燥やかゆみの誘発
- アレルギー成分によるかぶれ
過度な期待による精神的負担
「育毛剤を使えば、すぐに髪が生えてきて元の状態に戻る」と過度な期待を持つことは危険です。
髪にはヘアサイクル(毛周期)があり、抜いてしまった毛根が回復し、新しい髪が生えてくるまでには時間がかかります。
期待通りに改善しない現実を前にして、焦りや失望感が強まると、抜毛症の根本にある心理的な問題が悪化する可能性があります。
育毛剤使用の前に優先すべきこと
抜毛症による薄毛を改善したい場合、育毛剤に手を出す前に、まず取り組むべきは「髪を抜く行為」そのものを減らし、止めることです。
この根本的な問題に対処しなければ、どのようなヘアケア製品を使っても十分な効果は得られません。
抜毛行為の抑制が最優先
抜毛症の改善は、抜毛行為をコントロールすることから始まります。自分がどのような時に髪を抜いてしまうのか(ストレスを感じた時、手持ち無沙汰な時など)を客観的に把握することが第一歩です。
その状況を避ける工夫をしたり、髪を触る代わりに別の行動(ストレスボールを握る、指を動かす体操をするなど)に置き換える「習慣逆転法」などの対策が有効な場合があります。
専門医(皮膚科・心療内科)への相談
抜毛症は、皮膚の問題であると同時に、心の問題が深く関わっています。自分一人で抱え込まず、専門家の助けを借りることが重要です。
まずは皮膚科を受診し、頭皮の状態を診てもらい、脱毛が本当に抜毛症によるものか、他の脱毛症(円形脱毛症など)が隠れていないか診断を受けます。
同時に、抜毛行為が止められない背景にあるストレスや不安については、心療内科や精神科で相談することが、根本的な改善への近道となります。
頭皮環境を整える生活習慣
髪が健康に生えるためには、土壌である頭皮の状態を良好に保つことが必要です。育毛剤に頼るだけでなく、日々の生活習慣を見直すことも大切です。
特に、十分な睡眠、栄養バランスの取れた食事、適度な運動は、全身の血行を良くし、頭皮にも良い影響を与えます。
頭皮環境のための生活習慣ポイント
| 項目 | 具体的な内容 | 頭皮への影響 |
|---|---|---|
| 食事 | タンパク質、ビタミン、ミネラルをバランス良く | 髪の毛の材料となる栄養を補給 |
| 睡眠 | 質の良い睡眠を6〜8時間確保 | 成長ホルモンの分泌、頭皮の修復 |
| 運動 | ウォーキングなどの有酸素運動を習慣に | 全身の血行促進、ストレス発散 |
ストレス管理の重要性
抜毛行為の多くはストレスが引き金となっています。自分が何にストレスを感じているのかを理解し、それに対処する方法を見つけることが重要です。
リラックスできる時間(趣味、入浴、瞑想など)を意識的に作ることや、ストレスの原因となっている問題を整理し、解決策を探ることも必要です。
これもまた、専門のカウンセラーなどと協力して進めることが有効です。
もし育毛剤を使う場合に選びたい成分
抜毛行為がある程度収まり、専門医とも相談した上で、頭皮環境の改善を補助する目的で育毛剤の使用を検討する場合、その「成分」に注目することが大切です。
抜毛症の方は頭皮が敏感になっている可能性が高いため、刺激の強さよりも「頭皮をいたわる」ことを優先して選びます。
頭皮の炎症を抑える成分
抜毛行為によって引き起こされた頭皮の炎症や、かゆみを鎮める成分が含まれていると、頭皮を触る回数を減らす助けになるかもしれません。
代表的な抗炎症成分としては「グリチルリチン酸ジカリウム(グリチルリチン酸2K)」や「アラントイン」などがあります。これらは医薬部外品の育毛剤にもよく配合されています。
頭皮の保湿をサポートする成分
頭皮が乾燥すると、かゆみが出やすくなり、外部からの刺激にも弱くなります。頭皮の潤いを保つ保湿成分は、健やかな頭皮環境の維持に役立ちます。
「セラミド」「ヒアルロン酸」「コラーゲン」「アミノ酸類」などが代表的な保湿成分です。これらが頭皮のバリア機能をサポートします。
血行を促進する成分
頭皮の血行が良くなると、髪の成長に必要な栄養素が毛根に届きやすくなります。抜毛行為によってダメージを受けた毛根の回復をサポートする意味でも、血行促進は重要です。
「センブリエキス」「ニンジンエキス(オタネニンジン根エキス)」「ビタミンE誘導体(酢酸トコフェロール)」などが、血行促進作用を持つ成分として知られています。
育毛剤で注目したい成分の例
| 目的 | 成分例 | 期待される役割 |
|---|---|---|
| 抗炎症 | グリチルリチン酸2K | 頭皮の炎症やフケ・かゆみを抑える |
| 保湿 | セラミド、ヒアルロン酸 | 頭皮の乾燥を防ぎ、バリア機能を保つ |
| 血行促進 | センブリエキス、ビタミンE誘導体 | 毛根への栄養補給をサポートする |
刺激の少ない(アルコールフリーなど)製品の選び方
育毛剤には、清涼感を与えたり、成分を浸透させやすくしたりするために、アルコール(エタノール)が含まれていることが多いです。
しかし、抜毛症で敏感になった頭皮には、このアルコールが強い刺激となり、ヒリヒリ感や乾燥、かゆみを引き起こす原因になることがあります。
可能な限り「アルコールフリー」「低アルコール」「敏感肌用」と記載されている製品を選ぶことをお勧めします。
また、「パッチテスト済み」などの表記も参考になりますが、すべての人に刺激がないわけではないため、使用前には必ず目立たない部分で試す(パッチテスト)ことが賢明です。
育毛剤の正しい使い方と頭皮ケア
育毛剤を使うと決めた場合、その効果を最大限に引き出し、同時に頭皮トラブルを避けるためには、正しい使用方法と日常の頭皮ケアが重要になります。
特に抜毛症の方は、頭皮を「優しくいたわる」ことを常に意識する必要があります。
髪を抜いた直後の使用は避ける
髪を引き抜いた直後の毛穴は、傷口が開いているような状態です。そこに育毛剤を直接塗布すると、成分が過度な刺激となったり、雑菌が入り込んで炎症を起こしたりする原因になります。
万が一、髪を抜いてしまった場合は、その部分への育毛剤の使用は避け、頭皮が落ち着くのを待ってください。
清潔な頭皮に使用する
育毛剤は、シャンプー後で頭皮の汚れや皮脂が落ちた清潔な状態で使用するのが基本です。
タオルで髪の水分をしっかり拭き取り、ドライヤーで髪を乾かしてから(完全に乾かしきる手前、頭皮が湿っている程度が望ましい場合もあります。製品の指示に従ってください)、育毛剤を塗布します。
汚れが残っていると、育毛剤の浸透が悪くなるだけでなく、汚れと混ざって頭皮トラブルの原因にもなります。
優しくマッサージするように塗布する
育毛剤を頭皮に塗布した後は、指の腹を使って優しくマッサージします。これは育毛剤を頭皮全体に行き渡らせ、血行を促進する目的があります。
しかし、この時「爪を立てる」「強くこする」のは絶対にやめてください。抜毛症の方は、頭皮への刺激が抜毛行為の引き金になることもあるため、あくまで「優しく揉み込む」程度にとどめます。
頭皮マッサージの注意点
| 良い方法(推奨) | 悪い方法(避ける) |
|---|---|
| 指の腹を使う | 爪を立てる |
| 頭皮を動かすように優しく揉む | 頭皮を強くこする、叩く |
| リラックスして行う(1〜2分程度) | 長時間しつこく行う |
爪を立てないシャンプー方法
日々のシャンプーも、頭皮ケアの重要な一部です。育毛剤を使う使わないに関わらず、頭皮を傷つけない洗い方を習慣にすることが大切です。
シャンプー剤は手のひらでよく泡立ててから髪に乗せ、頭皮は指の腹を使って優しく洗います。かゆい部分があっても、爪を立ててゴシゴシ洗うのは厳禁です。
すすぎ残しは頭皮の刺激になるため、泡が完全になくなるまで、時間をかけて丁寧に洗い流してください。
抜毛症と向き合うための心構え
抜毛症の改善には時間がかかることが多く、育毛剤の使用や頭皮ケアと並行して、またはそれ以上に、ご自身の「心」とどう向き合うかが大切です。
焦りや自己嫌悪は、症状を悪化させる要因になりかねません。
自分を責めすぎないこと
髪を抜いてしまった時、「またやってしまった」「自分はダメだ」と強く責めてしまうと、それが新たなストレスとなり、さらに抜毛行為をエスカレートさせる悪循環に陥りがちです。
「抜いてしまう」のは、あなたの意志が弱いからではなく、ストレスや不安に対処するための一時的な防衛反応である側面もあります。
抜いてしまった事実はいったん受け止め、次にどうすれば抜かずに済むかを考えるように意識を切り替えましょう。
長期的な視点を持つ
抜毛症の改善も、髪の毛が再び生え揃うのも、一朝一夕にはいきません。
数週間や数ヶ月で完璧に治そうと焦るのではなく、「半年後、1年後には少しでも良くなっていたい」という長期的な視点を持つことが重要です。
育毛剤を使ったとしても、髪の成長には時間がかかります。日々の小さな浮き沈みに一喜一憂しすぎず、継続することが力になります。
小さな変化を記録する
改善が見えにくいと、途中で挫折しやすくなります。
「今日は抜かなかった時間がいつもより長かった」「抜かずに別の対処ができた」「頭皮のかゆみが少し減った」など、どんなに小さなことでも良いので、ポジティブな変化を記録する(手帳に書く、アプリに入力するなど)ことをお勧めします。
客観的な記録は、自分の頑張りを可視化し、治療やセルフケアを続けるモチベーション維持に役立ちます。
ポジティブな変化の記録例
- 抜毛行為の回数や時間の変化
- 抜毛衝動を感じた時の対処行動(成功例)
- 頭皮や髪の状態(写真、手触り)
スカルプトニックに戻る
よくある質問
- 抜毛症は治りますか?
-
抜毛症は、適切な対処と治療によって、症状を大幅に改善させたり、抜毛行為を止めたりすることが可能です。
「治る」という言葉の定義にもよりますが、多くの人がこの悩みから解放されています。
ただし、原因や症状の重さには個人差があるため、専門医(皮膚科や心療内科)と相談しながら、自分に合った方法で根気強く取り組むことが大切です。
- 育毛剤以外にできるセルフケアはありますか?
-
はい、あります。最も重要なセルフケアは、抜毛行為の引き金となるストレスを管理することです。
リラックスできる趣味の時間を確保する、適度な運動をする、十分な睡眠をとるなどが挙げられます。
また、物理的に髪を触りにくくするために、指先に絆創膏を貼る、手袋をする、帽子をかぶるなどの工夫も一時的に有効な場合があります。
- 育毛剤を使い始めてから抜け毛が増えた気がします?
-
育毛剤が直接の原因で抜け毛が増えることは考えにくいですが、いくつかの可能性があります。
一つは、育毛剤に含まれる成分(特にアルコールなど)が頭皮に合わず、炎症やかゆみを引き起こし、無意識に頭皮を触る回数が増えて抜毛を誘発しているケースです。
もう一つは、育毛剤のマッサージなどによって、抜けかけていた髪(抜毛行為で弱っていた髪)が抜けているだけかもしれません。
いずれにせよ、使用を続けて不安な場合は、一度使用を中止し、皮膚科医に相談してください。
- 家族や周りの人はどうサポートすれば良いですか?
-
ご家族や周囲の方が抜毛症について理解し、サポートすることは非常に重要です。まず、本人が抜毛行為を「やめたくてもやめられない」状態にあることを理解してください。
「やめなさい」と頭ごなしに叱責したり、監視したりすることは逆効果です。本人のストレスや不安に耳を傾け、安心できる環境を作ることが大切です。
また、専門医への受診をそっと促し、治療に寄り添う姿勢を見せることが助けになります。
Reference
EVERETT, Gregory J.; JAFFERANY, Mohammad; SKURYA, Jonathon. Recent advances in the treatment of trichotillomania (hair‐pulling disorder). Dermatologic therapy, 2020, 33.6: e13818.
MAJEED, Muhammed, et al. Clinical study to evaluate the efficacy and safety of a hair serum product in healthy adult male and female volunteers with hair fall. Clinical, cosmetic and investigational dermatology, 2020, 691-700.
SANI, Gabriele, et al. Drug treatment of trichotillomania (hair-pulling disorder), excoriation (skin-picking) disorder, and nail-biting (onychophagia). Current neuropharmacology, 2019, 17.8: 775-786.
DRAKE, Lara, et al. Evaluation of the safety and effectiveness of nutritional supplements for treating hair loss: a systematic review. JAMA dermatology, 2023, 159.1: 79-86.
YORK, Katherine, et al. A review of the treatment of male pattern hair loss. Expert opinion on pharmacotherapy, 2020, 21.5: 603-612.
BHATIA, Neal, et al. A Randomized, Double‐Blind, Placebo‐Controlled Study to Evaluate the Safety and Efficacy of a Nutraceutical Supplement With Standardized Botanicals in Males With Thinning Hair. Journal of Cosmetic Dermatology, 2025, 24.1: e16778.
PHILLIPS, T. Grant; SLOMIANY, W. Paul; ALLISON, Robert. Hair loss: common causes and treatment. American family physician, 2017, 96.6: 371-378.
SRIVASTAVA, Ankita; SRIVASTAVA, Ankur Kumar; PANT, A. B. Strategic Developments for Pre-clinical Safety/Efficacy Studies of Hair Care Products. In: Hair Care Products: Efficacy, Safety and Global Regulation. Singapore: Springer Nature Singapore, 2024. p. 223-273.
IORIZZO, Matilde; ORANJE, Arnold P. Current and future treatments of alopecia areata and trichotillomania in children. Expert Opinion on Pharmacotherapy, 2016, 17.13: 1767-1773.
ALESSANDRINI, A., et al. Common causes of hair loss–clinical manifestations, trichoscopy and therapy. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2021, 35.3: 629-640.