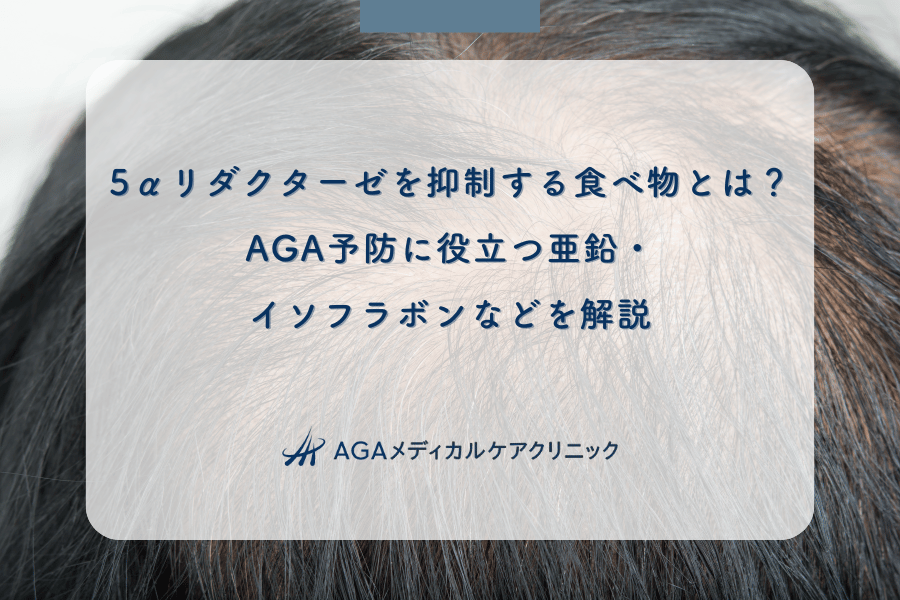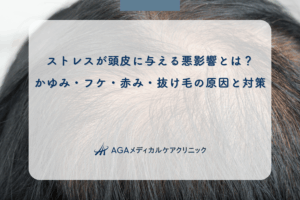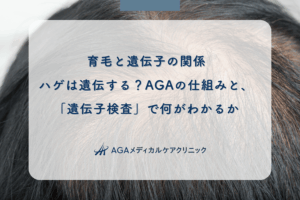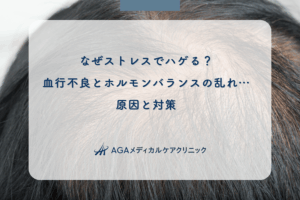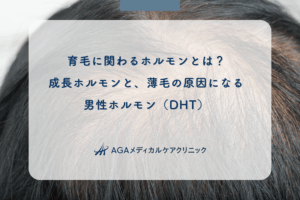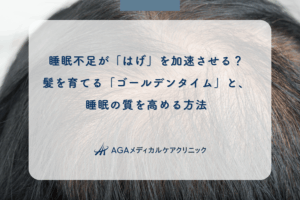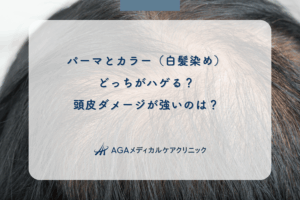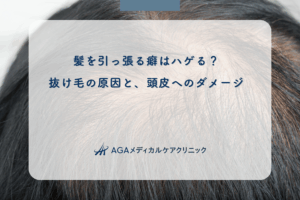薄毛や抜け毛の悩み、特にAGA(男性型脱毛症)の進行を気にされている方にとって、「5αリダクターゼ」という言葉は聞き覚えがあるかもしれません。
この酵素の働きをいかに抑えるかが、AGA予防の鍵の一つとされています。幸いなことに、私たちの日常の「食べ物」にも、この5αリダクターゼの働きに影響を与える可能性のある栄養素が含まれています。
この記事では、どのような食べ物や栄養素が5αリダクターゼの抑制に役立つ可能性があるのか、特に「亜鉛」や「イソフラボン」に焦点を当てて詳しく解説します。
食生活の見直しを通じて、AGA予防の一歩を踏み出しましょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
5αリダクターゼとは?AGA(男性型脱毛症)との関係性
AGA(男性型脱毛症)について調べ始めると、必ずと言っていいほど登場するのが「5αリダクターゼ(ゴアルファ・リダクターゼ)」という酵素です。
この酵素が、AGAの発症にどのように関わっているのでしょうか。まずは基本的な関係性から理解を深めていきましょう。
5αリダクターゼの役割と種類
5αリダクターゼは、体内で生成される酵素の一種です。その主な役割は、男性ホルモンである「テストステロン」を、より強力な男性ホルモンである「DHT(ジヒドロテストステロン)」に変換することです。
この変換作用自体は、男性らしい体つきの形成など、体の正常な機能の一部を担っています。
この酵素には「I型」と「II型」の2種類が存在し、それぞれ体内の異なる場所に分布しています。AGAとの関連では、特にII型の働きが注目されます。
5αリダクターゼI型とII型の分布
| 種類 | 主な分布場所 | AGAへの関与 |
|---|---|---|
| I型5αリダクターゼ | 全身の皮脂腺(頭皮含む)、肝臓など | 皮脂の分泌などに関与。AGAへの関与はII型より小さいと考えられています。 |
| II型5αリダクターゼ | 前頭部・頭頂部の毛乳頭細胞、前立腺、髭など | AGA(男性型脱毛症)の発症に強く関与するとされています。 |
AGAの発症に関わるDHT(ジヒドロテストステロン)
AGAは、思春期以降の男性に見られる進行性の脱毛症で、特定(そくてい)のパターンで薄毛が進行します。このAGAの引き金となるのが、前述のDHT(ジヒドロテストステロン)です。
DHTが毛根の受容体(アンドロゲンレセプター)と結合すると、毛髪の成長サイクルに悪影響を与えます。
具体的には、髪の毛が太く長く成長する「成長期」を短縮させ、毛が十分に育たないまま「退行期」「休止期」へと移行させてしまうのです。
これにより、毛が細く短くなり(軟毛化)、結果として地肌が目立つようになります。
なぜ5αリダクターゼの抑制がAGA予防につながるのか
ここまでの説明で、AGA発症の流れが見えてきたかと思います。
流れを整理すると、「テストステロン」が「5αリダクターゼ(特にII型)」によって「DHT」に変換され、その「DHT」が毛根に作用して薄毛が進行する、というものです。
つまり、この流れの大元である「5αリダクターゼ」の働きを抑制(阻害)できれば、DHTの生成量そのものを減らすことができます。
DHTが少なくなれば、毛根への悪影響も減少し、髪の成長期が正常に保たれやすくなります。これが、5αリダクターゼの抑制がAGAの予防や進行遅延に重要とされる理由です。
AGAの治療薬(フィナステリドやデュタステリドなど)も、この5αリダクターゼの働きを阻害することを目的としています。
そして、私たちの身近な「食べ物」に含まれる栄養素の中にも、この酵素の働きを穏やかに抑制する可能性が研究されているものがあるのです。
5αリダクターゼ抑制に役立つ栄養素
では、具体的にどのような栄養素が5αリダクターゼの抑制、ひいてはAGA予防に役立つと期待されているのでしょうか。
ここでは、研究などで注目されている主要な栄養素を紹介します。
亜鉛(ミネラル)
亜鉛は、体内の様々な酵素の働きに関わる必須ミネラルの一つです。髪の毛の主成分であるタンパク質(ケラチン)の合成にも必要であり、健康な髪を維持するために重要な栄養素です。
この亜鉛には、5αリダクターゼの働きを抑制する作用がある可能性が示唆されています。
特にII型の5αリダクターゼの活性を阻害する働きが注目されており、AGA予防の観点から積極的に摂取したいミネラルです。
ただし、体内で作り出すことができないため、食事から継続的に摂取する必要があります。
イソフラボン(ポリフェノール)
イソフラボンは、大豆などに多く含まれるポリフェノールの一種です。
化学構造が女性ホルモン(エストロゲン)と似ていることから、体内で女性ホルモンのような働き(エストロゲン様作用)をすることが知られています。
このイソフラボン(特にその代謝物であるエクオール)にも、5αリダクターゼの働きを抑制する可能性が指摘されています。
また、DHTが毛根の受容体と結合するのを妨げる働きも期待されており、二重の側面からAGA予防に貢献する可能性を秘めています。
アリシン
アリシンは、にんにくや玉ねぎなどのネギ類に含まれる、特有の香りのもととなる成分です。強力な抗酸化作用や血行促進作用で知られています。
アリシンそのものが直接5αリダクターゼを抑制するというよりは、一緒に摂取する栄養素、特にビタミンB群の吸収や働きを高めることで、間接的に頭皮環境の改善に寄与すると考えられます。
また、血行が良くなることで、頭皮に必要な栄養素が行き渡りやすくなる点も重要です。
その他の注目栄養素(ビタミン類など)
直接的に5αリダクターゼを抑制する働きは強くないかもしれませんが、髪の健康を維持し、頭皮環境を整えるためには他の栄養素も大切です。
特にビタミン類は、亜鉛やタンパク質の働きを助け、頭皮の状態を健やかに保つために役立ちます。
髪の健康を支えるビタミン
| 栄養素 | 期待される働き | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| ビタミンB群(B2,B6) | 皮脂の分泌調整、タンパク質の代謝促進 | レバー、マグロ、バナナ、卵 |
| ビタミンC | コラーゲン生成サポート、抗酸化作用 | ピーマン、ブロッコリー、キウイ |
| ビタミンE | 血行促進、抗酸化作用(過酸化脂質抑制) | アーモンド、うなぎ、アボカド |
これらの栄養素が不足すると、いくら亜鉛やイソフラボンを摂取しても、健康な髪は育ちません。バランス良くこれらの栄養素を摂取することが、AGA予防の土台となります。
5αリダクターゼ抑制が期待できる食べ物【亜鉛編】
5αリダクターゼ抑制に役立つ栄養素として「亜鉛」を紹介しました。では、亜鉛は具体的にどのような食べ物に多く含まれているのでしょうか。
日々の食事に取り入れやすい代表的な食品を見ていきましょう。
牡蠣(カキ)
亜鉛を豊富に含む食べ物の代表格が牡蠣です。「海のミルク」とも呼ばれるほど栄養価が高く、亜鉛の含有量は全食品の中でもトップクラスです。
生牡蠣やカキフライ、牡蠣鍋など、様々な調理法で楽しめます。特に冬場は旬を迎え、栄養価も高まります。
ただし、生食の場合は鮮度や衛生管理に十分注意し、体調が万全でない時は加熱して食べるようにしましょう。加熱しても亜鉛が全て失われるわけではありません。
亜鉛を豊富に含む主な食品
| 食品名 | 100gあたりの亜鉛含有量目安 | 摂取のポイント |
|---|---|---|
| 牡蠣(生) | 約14.5mg | 含有量はずば抜けて多い。季節や鮮度に注意。 |
| 豚レバー(生) | 約6.9mg | ビタミンAや鉄分も豊富。貧血予防にも。 |
| 牛肉(赤身・生) | 約4.5mg | 部位による。脂身の多い部位は避ける。 |
レバー(特に豚)
レバー類、特に豚レバーは亜鉛を多く含んでいます。同時に、髪の健康維持に役立つビタミンB群や鉄分も豊富なため、頭皮環境の改善や貧血予防にも役立つ優れた食材です。
レバーは特有の臭みがあるため、苦手な方もいるかもしれません。牛乳に浸して臭みを取ったり、生姜やニンニクなどの香味野菜と一緒に調理したりする(レバニラ炒めなど)と食べやすくなります。
ただし、レバーはビタミンAも非常に豊富なため、過剰摂取には注意が必要です。
牛肉(赤身)
牛肉も亜鉛の良い供給源です。特に脂身の少ない赤身の部位に多く含まれています。牛肉からは、髪の主成分であるタンパク質も同時に摂取できるため、効率的です。
ステーキやローストビーフ、煮込み料理などで取り入れるのが良いでしょう。
ただし、霜降り肉のような脂質の多い部位は、皮脂の過剰分泌につながる可能性もあるため、AGA予防の観点からは赤身肉を選ぶことを推奨します。
ナッツ類(アーモンド、カシューナッツなど)
間食やおつまみとして手軽に取り入れられるナッツ類も、亜鉛を含んでいます。特にカシューナッツやアーモンド、ピーナッツなどに比較的多く含まれます。
ナッツ類はビタミンEも豊富で、血行促進や抗酸化作用も期待できます。ただし、脂質も多くカロリーが高めなので、食べ過ぎには注意が必要です。1日に手のひらに軽く一杯程度を目安にすると良いでしょう。
塩分や油で加工されていない、素焼き(無塩)のタイプを選ぶのが望ましいです。
5αリダクターゼ抑制が期待できる食べ物【イソフラボン編】
次に、5αリダクターゼ抑制効果が期待されるもう一つの重要成分「イソフラボン」を多く含む食べ物を紹介します。イソフラボンは、主に大豆や大豆製品に含まれています。
大豆・大豆製品
イソフラボンを摂取する上で、最も基本的かつ重要な食材群が「大豆」そのものと、大豆を原料とする「大豆製品」です。
日本の伝統的な食生活(和食)には、これらの食材が豊富に使われており、私たちは比較的摂取しやすい環境にあります。
イソフラボンは、DHTの生成抑制だけでなく、女性ホルモン様作用により、男性ホルモンの影響を相対的に和らげる可能性も持っています。
日常的にこれらの食品を食卓に並べることが、AGA予防のサポートにつながります。
イソフラボンを豊富に含む主な食品
| 食品名 | 100gあたりのイソフラボン含有量目安 | 摂取のポイント |
|---|---|---|
| きな粉 | 約260mg | 牛乳やヨーグルトに混ぜて手軽に摂取可能。 |
| 納豆(1パック約45g) | 約30~35mg | 毎日続けやすい。発酵食品の利点も。 |
| 豆腐(木綿・半丁約150g) | 約40~45mg | 冷奴や味噌汁、麻婆豆腐など用途が広い。 |
納豆
納豆は、大豆イソフラボンを手軽に摂取できる非常に優れた発酵食品です。1パック(約45g)で、1日に推奨されるイソフラボン摂取量の一部を補うことができます。
イソフラボン以外にも、タンパク質、ビタミン、ミネラル、食物繊維、そして血流改善効果が期待されるナットウキナーゼなど、髪と体の健康に良い成分が豊富に含まれています。
朝食や夕食の定番として、毎日続けることを目指しましょう。
豆腐・豆乳
豆腐もまた、イソフラボン摂取に欠かせない大豆製品です。木綿豆腐、絹ごし豆腐どちらにも含まれています。冷奴や湯豆腐、味噌汁の具、炒め物など、調理のバリエーションが豊富で飽きずに続けやすいのが利点です。
また、飲料である「豆乳」も手軽な選択肢です。特に調整豆乳よりも、大豆の成分が多く残っている「無調整豆乳」の方が、イソフラボンを効率良く摂取できる傾向にあります。
朝食時や間食としてコップ一杯の豆乳を取り入れるのも良い習慣です。
5αリダクターゼ抑制を助けるその他の食べ物
亜鉛やイソフラボンの他にも、5αリダクターゼの働きや頭皮環境に良い影響を与える可能性のある食べ物が存在します。補助的な役割として、これらの食品も意識してみましょう。
にんにく・玉ねぎ(アリシン)
にんにくや玉ねぎ、長ネギなどに含まれる「アリシン」は、強い殺菌作用や抗酸化作用を持ちます。また、ビタミンB1の吸収を高め、疲労回復や新陳代謝の促進にも役立ちます。
直接的な5αリダクターゼ抑制作用は明確ではありませんが、血行を促進する働きが期待できます。頭皮の血流が改善すれば、毛根に栄養素が届きやすくなり、健康な髪の育成をサポートします。
亜鉛やタンパク質を多く含む肉料理やレバー料理(レバニラなど)と組み合わせることで、相乗効果も期待できるでしょう。
緑茶(カテキン)
緑茶に含まれるポリフェノールの一種「カテキン」(特にEGCG:エピガロカテキンガレート)にも、5αリダクターゼの働きを抑制する可能性があるという研究報告があります。
カテキンには強力な抗酸化作用もあり、頭皮の老化防止や炎症を抑える働きも期待されます。日本人にとって緑茶は非常に身近な飲み物であり、日常の水分補給として取り入れやすい点も魅力です。
ただし、カフェインも含まれているため、飲み過ぎや就寝前に飲むのは避けた方が良い場合もあります。
ノコギリヤシ(サプリメントでの摂取が一般的)
ノコギリヤシは、北米に自生するヤシ科の植物です。その果実のエキスには、5αリダクターゼ(特にII型)の働きを阻害する作用があるとして、古くから前立腺肥大の改善などに用いられてきました。
この働きがAGA予防にも応用できるのではないかと注目されています。
ただし、ノコギリヤシを「食べ物」として日常的に摂取することは困難です。そのため、摂取する場合は主にサプリメントを利用することになります。
ノコギリヤシ摂取時の留意点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 摂取形態 | 主にサプリメント(食品としての摂取は一般的でない) |
| 注意点 | 体質に合わない場合(胃腸の不快感など)があります。過剰摂取に注意し、目安量を守ることが重要です。 |
食事で5αリダクターゼ抑制を目指す際のポイント
これまで紹介したような、5αリダクターゼ抑制が期待できる食べ物を摂取することは大切です。しかし、ただそれだけを食べていれば良いというわけではありません。
AGA予防のための食生活には、いくつかの重要なポイントがあります。
バランスの取れた食事が基本
最も重要なことは、特定の栄養素に偏らず、体全体の健康を支える「バランスの取れた食事」を心がけることです。髪の毛も体の一部であり、体全体が健康でなければ、健やかな髪は育ちません。
亜鉛やイソフラボンも、タンパク質やビタミン、その他のミネラルが揃ってこそ、その能力を十分に発揮できます。食事の基本となる「主食・主菜・副菜」を揃えることを意識しましょう。
- 主食(炭水化物)ご飯、パン、麺類など。エネルギー源。
- 主菜(タンパク質)肉、魚、卵、大豆製品など。髪や体の材料。
- 副菜(ビタミン・ミネラル)野菜、海藻、きのこ類など。体の調子を整える。
この3つを毎食揃えることで、必要な栄養素を過不足なく摂取しやすくなります。
特定の食品ばかり食べるリスク
「牡蠣が亜鉛豊富だから」といって毎日牡蠣ばかり食べたり、「大豆が良いから」と豆腐ばかり食べたりする「ばっかり食べ」は、栄養の偏りを招きます。
例えば、亜鉛やビタミンA(レバーに多い)は、過剰に摂取すると体調不良(過剰症)を引き起こす可能性があります。また、特定の食品にアレルギー反応が出ることもあります。
様々な食品をローテーションしながら、多品目から栄養を摂ることを目指しましょう。その方が、結果的に5αリダクターゼ抑制に役立つ多様な成分を摂取することにもつながります。
脂質の多い食事や過度な飲酒の影響
5αリダクターゼ抑制に良い食べ物を摂る一方で、頭皮環境に悪影響を与える食習慣を続けていては、効果が半減してしまいます。特に注意したいのが、脂質の多い食事や過度な飲酒です。
揚げ物やファストフード、脂身の多い肉類などに含まれる動物性脂肪を過剰に摂取すると、皮脂の分泌が活発になり、頭皮がべたついたり、毛穴が詰まりやすくなったりします。
これは、抜け毛や炎症の原因となり得ます。
また、アルコールを分解する際には、体内の亜鉛が大量に消費されます。せっかく食事で亜鉛を補給しても、飲酒によって失われてしまっては意味がありません。
AGA予防のために見直したい食習慣
| 見直したい習慣 | 頭皮・髪への影響懸念 | 改善の方向性 |
|---|---|---|
| 高脂質な食事(揚げ物など) | 皮脂の過剰分泌、血行不良 | 和食中心、蒸す・茹でる調理法を選ぶ |
| 過度な飲酒 | 亜鉛の大量消費、肝臓への負担 | 休肝日を設け、適量を守る(ビール中瓶1本程度) |
| 糖分の過剰摂取 | 皮脂の増加、ビタミンB群の消費 | お菓子や甘いジュースを控える |
食べ物だけでAGA予防は十分か?
ここまで、5αリダクターゼを抑制する食べ物や栄養素について解説してきました。
しかし、「では、これらの食べ物をしっかり食べていればAGAは絶対に防げるのか?」と問われると、残念ながら「それだけでは不十分」と答えざるを得ません。
食事改善の役割と限界
食事によるAGA予防は、あくまで「体の内側から頭皮環境を整え、AGAが進行しにくい土台を作る」ためのサポート的な役割です。
AGAは遺伝的な要因やホルモンバランスが強く関与しているため、食事内容を改善したからといって、発症を完全に止めたり、すでに進行した薄毛を元に戻したりすることは困難です。
食事改善は、AGAの進行を「緩やかにする」可能性を追求するものであり、即効性のある「治療」とは異なります。この限界を理解した上で、日々の習慣として取り組むことが大切です。
生活習慣の見直し(睡眠・運動)
AGA予防には、食事以外の生活習慣も深く関わっています。特に「睡眠」と「運動」は重要です。
髪の成長を促す「成長ホルモン」は、主に睡眠中に分泌されます。睡眠不足が続くと、成長ホルモンの分泌が減少し、髪の成長が妨げられます。
質の良い睡眠を十分な時間(6〜7時間目安)確保するよう努めましょう。
また、適度な運動は全身の血行を促進します。これには当然、頭皮の血行促進も含まれます。ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動を習慣にし、毛根に栄養素が届きやすい状態を保ちましょう。
ストレス管理の重要性
ストレスもまた、AGAを悪化させる要因の一つです。強いストレスを感じると自律神経が乱れ、血管が収縮し、頭皮の血行不良を招きます。
また、ストレスはホルモンバランスの乱れにもつながり、皮脂の過剰分泌を引き起こすこともあります。
現代社会でストレスをゼロにすることは難しいですが、趣味の時間を持つ、リラックスできる入浴法を試す、深呼吸するなど、自分なりのストレス解消法を見つけ、溜め込まないように管理することが重要です。
気になる場合は専門家へ相談
食事や生活習慣の改善を続けていても、抜け毛や薄毛の進行が止まらない、あるいは不安が強い場合は、一人で抱え込まずに専門家へ相談することを強く推奨します。
皮膚科やAGA専門のクリニックでは、現在の頭皮や毛髪の状態を正確に診断し、医学的根拠に基づいたアドバイスや治療法(内服薬や外用薬など)を提案してくれます。
早期の対策が、将来の髪の状態を大きく左右します。食生活の改善と並行して、専門的なアプローチも検討に入れましょう。
薄毛の基礎知識に戻る
よくある質問
- これらの食べ物を食べれば髪は生えますか?
-
これらの食べ物は、5αリダクターゼの働きを抑制し、AGAの予防や進行を緩やかにすることをサポートする可能性がありますが、直接的に髪を生やす(発毛)効果を保証するものではありません。
髪の健康維持や頭皮環境を整える一助として捉えることが大切です。
- 効果を実感するまでにどれくらいかかりますか?
-
食事による体質や頭皮環境の変化は、非常にゆっくりとしたものです。数週間や数ヶ月で明確な変化を感じることは難しく、長期的な視点で継続することが重要です。
即効性を期待するものではなく、日々の予防習慣として取り入れましょう。
- サプリメントで摂取しても良いですか?
-
亜鉛やイソフラボン、ノコギリヤシなどはサプリメントとしても利用可能です。食事だけでは必要量を摂取し続けるのが難しい場合、サプリメントで補うことも一つの方法です。
ただし、過剰摂取は健康を害する可能性があるため、必ず目安量を守り、不明点があれば医師や薬剤師に相談しましょう。
- 逆にAGAを進行させる可能性のある食べ物はありますか?
-
直接的にAGAを進行させると断定できる食べ物はありません。しかし、動物性脂肪や糖分が多い食事は、皮脂の過剰分泌や血行不良を招き、頭皮環境を悪化させる可能性があります。
頭皮環境の悪化は、抜け毛や薄毛の要因の一つとなり得るため、バランスの悪い食事は避ける方が賢明です。
Reference
RU, Qi, et al. Effects of Camellia oleifera seed shell polyphenols and 1, 3, 6-tri-O-galloylglucose on androgenic alopecia via inhibiting 5a-reductase and regulating Wnt/β-catenin pathway. Fitoterapia, 2024, 177: 106116.
BASSINO, Eleonora; GASPARRI, Franco; MUNARON, Luca. Protective role of nutritional plants containing flavonoids in hair follicle disruption: A review. International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21.2: 523.
WEI, Grace; MARTIROSYAN, Danik. Hair loss: A review of the role of food bioactive compounds. Bioactive Compounds in Health and Disease-Online ISSN: 2574-0334; Print ISSN: 2769-2426, 2019, 2.5: 94-125.
TAN, Justin JY, et al. Bioactives in Chinese proprietary medicine modulates 5α-reductase activity and gene expression associated with androgenetic alopecia. Frontiers in Pharmacology, 2017, 8: 194.
PYI, Phoe. Effectiveness of the combination treatment of Korean red ginseng and vitamin B5 in androgenetic alopecia. 2024. PhD Thesis. Mae Fah Luang University. Learning Resources and Educational Media Centre.
CAO, ChunYu, et al. Effect of oleanolic acid on 5α-reductase activity, DPCs proliferation and gene expression correlated with androgenetic alopecia in vitro. Acta Med. Mediterr, 2019, 35: 2159-2165.
ILTAF, J., et al. Ficus benghalensis as Potential Inhibitor of 5a-Reductase for Hair Growth Promotion. Protective Effects of Medicinal Plant Extracts and Natural Compounds in Skin Disorders, 2022, 762829127.
TRAKOOLTHONG, Patarapan, et al. Antioxidant and 5α-Reductase inhibitory activity of Momordica charantia extract, and development and characterization of microemulsion. Applied Sciences, 2022, 12.9: 4410.
PARISI, Ortensia Ilaria, et al. Interconnected PolymerS TeChnology (IPSTiC): An effective approach for the modulation of 5α-reductase activity in hair loss conditions. Journal of Functional Biomaterials, 2018, 9.3: 44.
KUCA, Maciej, et al. Risk associated with the use of 5-alpha reductase inhibitors with minoxidil in treatment of male androgenetic alopecia-literature review. Journal of Pre-Clinical & Clinical Research, 2025, 19.1.