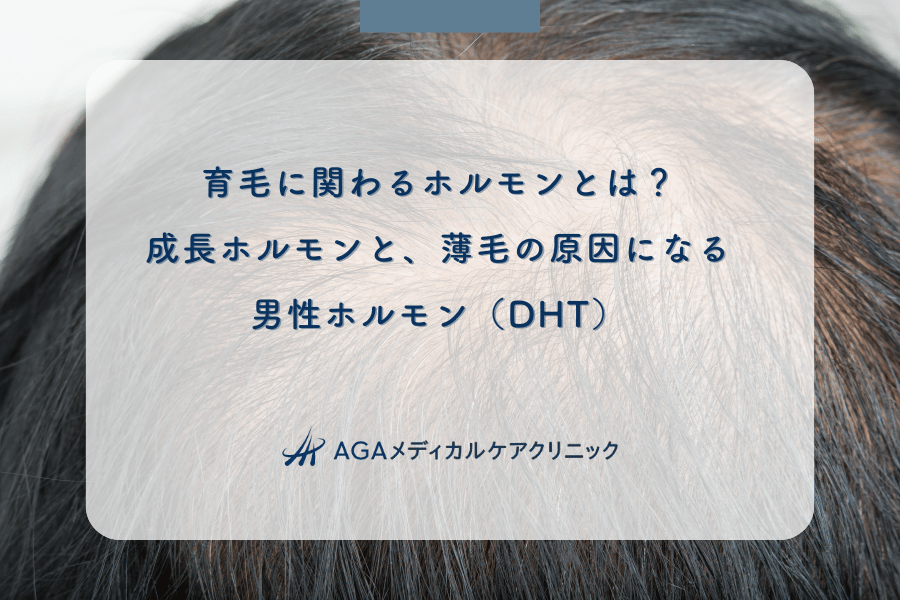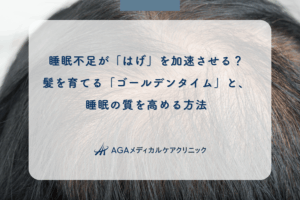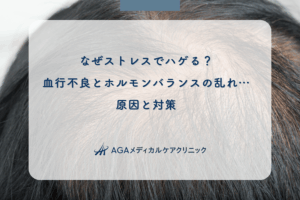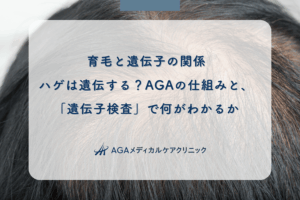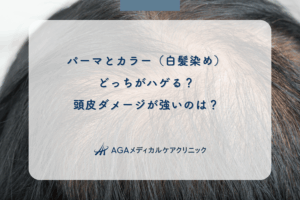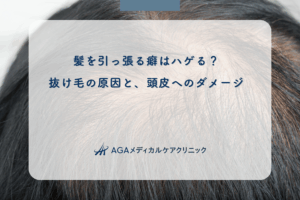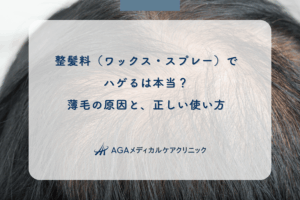最近、髪のボリュームが気になり始めた、または抜け毛が増えたと感じていませんか。その悩みの裏には、「ホルモン」が関係しているかもしれません。
この記事では、育毛に深く関わる2つの重要なホルモン、つまり髪の成長を助ける「成長ホルモン」と、薄毛の原因となり得る「男性ホルモン(DHT)」について、その役割とバランスの重要性を詳しく解説します。
ホルモンの働きを理解することは、あなたの髪の悩みを解決し、適切なヘアケアを見つけるための第一歩です。日々の生活で見直すべき点を知り、健やかな髪を取り戻すためのヒントを見つけていきましょう。
大切なのは、ホルモンバランスを意識した生活です。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
育毛とホルモンの基本的な関係
育毛には「成長ホルモン」と「男性ホルモン」という2種類のホルモンが深く関わっており、それぞれが髪の成長や脱毛に異なる形で影響を与えます。
これらがバランスよく働くことが、健康な髪を維持するために大切です。
ホルモンとは体内で作られる物質
ホルモンは、私たちの体の中の特定の臓器(内分泌腺)で作られ、血液によって全身に運ばれる化学物質です。体の様々な機能を調節するメッセンジャーのような役割を担っています。
例えば、体温の調節、代謝のコントロール、気分の変化など、私たちが生きていく上で欠かせない多くの働きを調整しています。
髪の毛の健康も、このホルモンの影響を強く受ける分野の一つです。髪の毛が成長したり、抜けたりするサイクルも、特定のホルモンからの指令によってコントロールされています。
そのため、ホルモンのバランスが崩れると、髪の毛の健康状態にも変化が現れやすくなります。
なぜホルモンが髪に影響するのか
髪の毛は、頭皮の下にある「毛包(もうほう)」という器官で作られます。毛包の根元には「毛乳頭(もうにゅうとう)」という部分があり、ここが髪の毛の成長の司令塔です。
毛乳頭の周りには「毛母細胞(もうぼさいぼう)」があり、この細胞が分裂・増殖することで髪の毛が作られます。
ホルモンは血液に乗って全身を巡り、頭皮の毛乳頭細胞にも到達します。毛乳頭細胞には、特定のホルモンを受け取るための「受容体(じゅようたい)」という鍵穴のようなものがあります。
ここに適切なホルモンが鍵としてカチッとはまると、毛母細胞に対して「髪を成長させなさい」という指令が出たり、逆に「成長を止めなさい(脱毛しなさい)」という指令が出たりします。
このように、ホルモンは髪の製造工場である毛包に直接アクセスし、その働きを左右する力を持っているのです。
育毛に影響する主な2つのホルモン
髪の健康、特に育毛の観点から注目すべきホルモンは、主に「成長ホルモン」と「男性ホルモン」の2つです。
成長ホルモンは、その名の通り体の成長を促すホルモンですが、大人になってからも細胞の修復や新陳代謝を活発にするために働き続けます。
髪にとっては、毛母細胞の活動を活発にし、髪の成長を「促進」する役割を持ちます。
一方、男性ホルモン(特に「ジヒドロテストステロン(DHT)」と呼ばれる強力なもの)は、特定の条件下で髪の成長を「妨害」し、脱毛を「促進」する原因になることがあります。
これが、いわゆる男性型脱毛症(AGA)の主な要因です。
育毛を考える上では、成長ホルモンの働きを助け、男性ホルモン(DHT)の悪い影響をいかに抑えるか、という2つの側面に注目する必要があります。
髪の成長サイクルとの関連
髪の毛には「ヘアサイクル(毛周期)」と呼ばれる寿命があります。1本の髪の毛は、「成長期(アネジェン)」、「退行期(カタジェン)」、「休止期(テロジェン)」という3つの段階を繰り返しています。
健康な髪の毛のほとんど(約85〜90%)は成長期にあり、この期間は2年〜6年続きます。この間、髪は太く長く成長します。その後、2週間ほどの退行期を経て、3〜4ヶ月の休止期に入ります。
休止期になると毛根は浅くなり、やがて新しい髪の毛に押し出されるようにして自然に抜け落ちます。
ホルモンは、このヘアサイクル、特に最も重要な「成長期」の長さに強く影響します。成長ホルモンは成長期を長く維持するように働き、男性ホルモン(DHT)は成長期を極端に短くしてしまうように働きます。
髪の成長を促す「成長ホルモン」の役割
成長ホルモンは、髪の毛を作り出す毛母細胞の活動を活発にし、髪の成長期を維持するために重要な働きを持つホルモンです。このホルモンの分泌が活発であることは、健やかな髪の成長に直結します。
成長ホルモンが育毛に与える影響
成長ホルモンは、脳下垂体から分泌され、全身の細胞の新陳代謝を促します。頭皮においては、毛乳頭細胞に働きかけ、毛母細胞の分裂を活発にする指令を出します。
この働きによって、髪の毛の主成分であるタンパク質(ケラチン)の合成が促進され、髪が太く、健康に育つのを助けます。
また、成長ホルモンは髪の成長期を長く保つためにも働きます。成長ホルモンが十分に分泌されていると、髪はしっかりと成長する時間を確保でき、抜けにくい丈夫な髪になります。
逆に、成長ホルモンの分泌が減少すると、毛母細胞の活動が鈍り、髪が細くなったり、成長が遅くなったりする可能性があります。
成長ホルモンの分泌と生活習慣
成長ホルモンの分泌は1日の中で変動があり、特に夜間の睡眠中に最も多く分泌されます。特に、眠りについてから最初の深いノンレム睡眠の間に、分泌のピークが訪れます。
かつては「夜10時から深夜2時までがゴールデンタイム」と言われていましたが、現在では時間帯そのものよりも「入眠後の最初の深い睡眠」が最も重要であると考えられています。
したがって、睡眠の「質」と「時間」の両方を確保することが、成長ホルモンの分泌を促し、育毛に良い影響を与えるためには非常に重要です。
不規則な生活や睡眠不足は、成長ホルモンの分泌を妨げ、髪の成長にも悪影響を及ぼす可能性があります。
成長ホルモンの分泌を促す生活習慣
成長ホルモンの分泌をサポートするためには、意識的な生活習慣の改善が効果的です。特に「睡眠」「食事」「運動」の3つの柱が基本となります。
睡眠の重要性
前述の通り、質の高い睡眠は成長ホルモン分泌の鍵です。毎日なるべく同じ時間に寝て、同じ時間に起きる規則正しい生活を心がけましょう。
寝る直前のスマートフォンやパソコンの使用は、ブルーライトが脳を覚醒させ、深い睡眠を妨げるため避けるのが賢明です。
リラックスできる音楽を聴く、温めのお風呂にゆっくり浸かるなど、自分なりのリラックス方法を見つけ、スムーズに入眠できる環境を整えましょう。
食事と成長ホルモン
バランスの取れた食事も、成長ホルモンの分泌と髪の健康を支えます。特に、髪やホルモンの材料となるタンパク質は重要です。また、成長ホルモンの分泌をサポートすると言われるアミノ酸(特にアルギニン、オルニチンなど)や、細胞の働きを助ける亜鉛などのミネラルも意識して摂取したい栄養素です。
成長ホルモン分泌をサポートする可能性のある栄養素
| 栄養素 | 主な役割 | 多く含む食品例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分、ホルモンの材料 | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |
| アルギニン | 成長ホルモン分泌促進(研究段階) | 鶏肉、大豆、ナッツ類、エビ |
| 亜鉛 | 細胞分裂、タンパク質合成サポート | 牡蠣、レバー、赤身肉、チーズ |
ただし、特定の食品ばかりを食べるのではなく、様々な食材からバランスよく栄養を摂ることが基本です。
加齢による成長ホルモンの減少と対策
残念ながら、成長ホルモンの分泌量は、思春期をピークに年齢とともに減少していきます。30代、40代と年齢を重ねるにつれて、その分泌量はピーク時の半分以下になることも珍しくありません。
この加齢による成長ホルモンの減少は、体の新陳代謝の低下を意味し、髪の毛にも「ハリやコシがなくなる」「髪が細くなる」「ボリュームが減る」といった形で現れやすくなります。
しかし、加齢による減少は避けられなくても、生活習慣の改善によって分泌をサポートすることは可能です。
年齢を重ねるほど、先ほど挙げた「質の高い睡眠」「バランスの取れた食事」「適度な運動」といった基本的な生活習慣を丁寧に見直すことが、髪の健康を維持する上でより一層重要になってきます。
薄毛の主な原因「男性ホルモン(DHT)」とは
男性ホルモンの一種であるテストステロンが特定の酵素と結びつくことで変化した「ジヒドロテストステロン(DHT)」が、男性型脱毛症(AGA)の主な原因物質です。
このDHTが、髪の成長を妨げる信号を出すことで薄毛が進行します。
男性ホルモン「テストステロン」の役割
まず理解しておきたいのは、男性ホルモン=悪ではない、ということです。
男性ホルモンの大部分を占める「テストステロン」は、主に精巣で作られ、男性らしい体つき(筋肉や骨格の発達)、性機能の維持、意欲や決断力といった精神面にも関わる、非常に重要なホルモンです。
テストステロンが豊富であること自体が、直接的に薄毛の原因になるわけではありません。むしろ、心身の健康を保つためには必要なホルモンです。
問題となるのは、このテストステロンが「ある物質」に変化したときです。
悪玉男性ホルモン「DHT」の生成
薄毛の引き金となるのは、「ジヒドロテストステロン(DHT)」と呼ばれる、テストステロンよりも強力な作用を持つ男性ホルモンです。
このDHTは、テストステロンが「5αリダクターゼ(ごアルファリダクターゼ)」という還元酵素と結びつくことによって生成されます。
この5αリダクターゼという酵素は、頭皮、特に前頭部や頭頂部の毛乳頭細胞に多く存在します。そのため、血中のテストステロンが頭皮に運ばれてくると、この酵素と反応し、DHTへと変換されてしまうのです。
このDHTこそが、AGAにおける「悪玉男性ホルモン」と呼ばれます。
5αリダクターゼとは
5αリダクターゼには、「Ⅰ型」と「Ⅱ型」の2種類が存在します。
Ⅰ型は、主に皮脂腺に多く存在し、皮脂の分泌に関わっています。全身の皮膚に分布していますが、頭皮にも存在します。
Ⅱ型は、主に前頭部や頭頂部の毛乳頭細胞や、前立腺などに多く存在します。男性型脱毛症(AGA)に強く関与しているのは、この「Ⅱ型」の5αリダクターゼであると考えられています。
5αリダクターゼの種類と特徴
| 種類 | 主な存在場所 | 関与する症状 |
|---|---|---|
| Ⅰ型 | 全身の皮脂腺、頭皮など | 皮脂分泌、ニキビなど |
| Ⅱ型 | 前頭部・頭頂部の毛乳頭、前立腺 | 男性型脱毛症(AGA)、前立腺肥大 |
DHTが髪の毛に与える影響
DHTが生成されると、それは毛乳頭細胞にある「男性ホルモン受容体(アンドロゲンレセプター)」という鍵穴に強力に結合します。この結合が、脱毛に向けたスイッチを押すことになります。
脱毛シグナルの発生
DHTが受容体と結合すると、毛乳頭細胞内では「TGF-β」や「DKK-1」といった「脱毛因子(脱毛シグナル)」が作り出されます。
これらの物質は、髪の毛を作り出す毛母細胞に対して、「もう増殖するな」「成長を止めろ」という強い指令を送ります。
ヘアサイクルの短縮
この脱毛シグナルを受け取った毛母細胞は、活発な細胞分裂をやめてしまいます。その結果、本来であれば2年〜6年続くはずの髪の「成長期」が、わずか数ヶ月〜1年程度にまで極端に短縮されてしまいます。
成長期が短くなると、髪の毛は太く長く成長する時間を失います。十分育つ前に退行期・休止期へと移行し、細く短い「産毛」のような状態(これを髪のミニチュア化と呼びます)のまま抜け落ちてしまいます。
この「成長期の短縮」と「髪のミニチュア化」が頭頂部や前頭部で繰り返されることで、地肌が目立つようになり、薄毛が進行していくのです。
DHTによるヘアサイクルの変化
| 項目 | 正常なヘアサイクル | AGAのヘアサイクル |
|---|---|---|
| 成長期 | 2年〜6年 | 数ヶ月〜1年 |
| 髪の状態 | 太く、長く成長する | 細く、短い産毛状(ミニチュア化) |
| 結果 | 健康な毛髪が維持される | 薄毛が徐々に進行する |
なぜDHTの影響には個人差があるのか
DHTによる薄毛の進行度合いには個人差があり、その主な理由は「5αリダクターゼの活性度」と「男性ホルモン受容体の感受性」が遺伝的に決まる部分が大きいからです。
つまり、DHTが作られやすいか、そしてDHTの影響を受けやすいか、という体質が人によって異なります。
遺伝的要因
男性型脱毛症(AGA)が遺伝的要素を強く持つことはよく知られています。親や祖父母に薄毛の人がいると、自分も薄毛になりやすいのではないかと心配する人も多いでしょう。
この遺伝が関わっているのが、まさにDHTの影響の受けやすさです。具体的には、以下の2つの遺伝的体質が大きく関わっています。
5αリダクターゼの活性度の違い
一つは、テストステロンをDHTに変換する酵素「5αリダクターゼ」の働きの強さ(活性度)です。
この酵素の活性が高い体質を遺伝的に受け継いでいる人は、同じ量のテストステロンがあっても、より多くのDHTを生成してしまいます。つまり、薄毛のリスクが高くなります。
特にAGAに強く関わるⅡ型5αリダクターゼの活性度は、優性遺伝(両親のどちらかから受け継げば発現しやすい)とされています。
男性ホルモン受容体の感受性の違い
もう一つ、さらに重要とされるのが、DHTを受け取る鍵穴である「男性ホルモン受容体」の感度の高さ(感受性)です。
たとえDHTが多く生成されたとしても、この受容体の感受性が低ければ、DHTが結合しにくく、脱毛シグナルも出にくいため、薄毛は進行しにくいです。
逆に、受容体の感受性が非常に高い体質を受け継いでいる人は、わずかな量のDHTであっても敏感に反応し、強い脱毛シグナルが発信されてしまいます。このため、薄毛が進行しやすくなります。
受容体の感受性と遺伝
この男性ホルモン受容体の感受性を決める遺伝子は、性染色体である「X染色体」上にあることがわかっています。男性はXY、女性はXXの性染色体を持ち、男性は母親からX染色体、父親からY染色体を受け継ぎます。
つまり、男性のX染色体は必ず母親由来です。そして、その母親のX染色体は、母親の父親(=母方の祖父)と母親の母親(=母方の祖母)から半分ずつ受け継いだものです。
このため、「薄毛は母方の家系から遺伝しやすい」と言われることがあります。
母方の祖父や、母親の兄弟(伯父・叔父)が薄毛である場合、そのX染色体を受け継いでいる可能性があり、受容体の感受性が高い体質(=薄毛になりやすい体質)である可能性を考える参考になります。
もちろん、遺伝だけがすべてではなく、環境要因も関わりますが、この2つの遺伝的要素がAGA発症の大きな土台となっていることは間違いありません。
成長ホルモンと男性ホルモンのバランス
育毛のためには、成長ホルモンの分泌を促し、DHTの過剰な働きを抑えることで、2つのホルモンのバランスを髪にとって良い状態に保つことが大切です。
どちらか一方だけではなく、両方のバランスが髪の健康を左右します。
ホルモンバランスが崩れる原因
ホルモンの分泌は、脳の視床下部や下垂体といった司令塔によって非常に繊細にコントロールされています。しかし、この司令塔の働きは、日々の生活習慣によって簡単に乱れてしまいます。
ホルモンバランスが崩れる主な原因としては、加齢による自然な変化のほかに、「過度なストレス」「睡眠不足」「不規則な食生活」「栄養の偏り」「運動不足」などが挙げられます。
これらは現代人にとって非常に身近な問題であり、誰もがバランスを崩す可能性を持っています。
ストレスとホルモンの関係
特に注意したいのが「ストレス」です。仕事や人間関係などで強いストレスを感じ続けると、体は常に緊張状態(交感神経が優位な状態)になります。
この緊張状態が続くと、ホルモン分泌の司令塔である視床下部や自律神経の働きが乱れます。その結果、成長ホルモンの分泌が抑制されたり、男性ホルモンのバランスが崩れたりすることがあります。
ストレスによる血行不良
ストレスは、ホルモンバランスを直接乱すだけでなく、間接的にも育毛に悪影響を与えます。強いストレスは血管を収縮させる作用があります。
頭皮の血管が収縮すると、血流が悪化します。血流が悪くなると、髪の毛の成長に必要な栄養素や酸素が毛乳頭や毛母細胞に十分に届かなくなってしまいます。
また、せっかく分泌された成長ホルモンも、血流に乗って頭皮に運ばれるため、血行不良はその効果を十分に発揮できなくする原因にもなります。
育毛におけるホルモンバランスの重要性
育毛を考えるとき、私たちは「髪を生やすこと(発毛)」と「髪が抜けるのを防ぐこと(脱毛予防)」の両方を考えなくてはなりません。
ここで、ホルモンの役割をもう一度整理してみましょう。
- 成長ホルモン:毛母細胞を活性化し、髪の成長を促す「攻め」の役割
- DHT(悪玉男性ホルモン):髪の成長期を短縮し、脱毛を促す「マイナス」の要因
健康な髪を育てるためには、成長ホルモンの「攻め」の力を最大限に引き出しつつ、DHTによる「マイナス」の影響を最小限に抑える必要があります。
例えば、生活習慣を整えて成長ホルモンの分泌を促しても、DHTの影響が非常に強ければ、髪は育つ前に抜け落ちてしまいます。
逆に、DHTの影響を抑えるケア(育毛剤の使用など)を始めても、睡眠不足や栄養不足で成長ホルモンが働かなければ、新しく健康な髪は育ちにくいでしょう。
つまり、髪の成長を「促進」する力と、脱毛を「抑制」する力のバランスを取ること。これこそが、育毛におけるホルモンバランスの最も重要なポイントです。
ホルモンバランスを整えるための生活習慣
ホルモンのバランスを整え、育毛に適した体内環境を作るためには、「睡眠」「食事」「運動」「ストレスケア」という4つの基本的な生活習慣を見直すことが重要です。
これらは髪だけでなく、全身の健康の土台となります。
質の高い睡眠を確保する
髪の成長を促す成長ホルモンは、深い睡眠中に最も多く分泌されます。単に長く寝るだけでなく、「質の高い」睡眠を確保することが大切です。
就寝の1〜2時間前にはぬるめのお風呂(38〜40度程度)にゆっくり浸かり、リラックスしましょう。寝る直前の飲食、カフェインやアルコールの摂取、スマートフォンの操作は睡眠の質を下げるため避けます。
寝室を暗く静かに保ち、快適な温度・湿度を維持することも、深い眠りにつながります。毎日決まった時間に寝て、決まった時間に起きるリズムを作ることを目指しましょう。
栄養バランスの取れた食事
私たちの体は、食べたものから作られています。髪もホルモンも例外ではありません。偏った食事はホルモンバランスを乱し、髪の材料不足を引き起こします。
特に重要なのは、髪の主成分である「タンパク質」(肉、魚、卵、大豆製品)です。
また、ホルモンの合成や代謝を助ける「ビタミンB群」(豚肉、レバー、マグロなど)や「亜鉛」(牡蠣、レバー、赤身肉)も必要です。
高脂肪・高糖質の食事は皮脂の過剰分泌につながり、頭皮環境を悪化させる可能性もあるため、摂りすぎには注意が必要です。
育毛サポートに期待される栄養素
| 栄養素 | 期待される役割 | 多く含む食品例 |
|---|---|---|
| タンパク質(ケラチン) | 髪の主成分、ホルモンの材料 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 亜鉛 | DHT生成抑制(研究)、タンパク質合成 | 牡蠣、レバー、赤身肉 |
| ビタミンB群(B2, B6など) | 代謝サポート、皮脂コントロール | 豚肉、マグロ、レバー、納豆、バナナ |
| イソフラボン | 5αリダクターゼの働きを抑制(研究) | 大豆、豆乳、豆腐、納豆 |
適度な運動の習慣化
運動不足は、血行不良やストレス蓄積の大きな原因となります。適度な運動は、これらの問題を解決し、間接的にホルモンバランスを整えるのに役立ちます。
特におすすめなのは、ウォーキング、ジョギング、サイクリングなどの「有酸素運動」です。これらの運動は、全身の血流を改善し、頭皮にもしっかりと栄養を届ける助けとなります。
また、適度な疲労は睡眠の質を高め、成長ホルモンの分泌を促すことにもつながります。
無理に激しい運動をする必要はありません。週に2〜3回、30分程度、軽く汗ばむくらいの運動を続けることを目標にしましょう。
効果的なストレスケア
現代社会においてストレスをゼロにすることは困難ですが、溜め込まずに上手に発散する方法を見つけることは可能です。ストレスは自律神経を乱し、ホルモンバランスを崩す最大の敵の一つです。
自分が「心地よい」と感じる時間を持つことが大切です。例えば、趣味に没頭する時間を作る、好きな音楽を聴く、自然の中で散歩する、ゆっくりと入浴する、瞑想やヨガで呼吸を整える、といったことです。
また、悩み事を一人で抱え込まず、信頼できる友人や家族に話を聞いてもらうだけでも、心は軽くなります。自分に合ったストレス解消法を見つけ、日常生活に組み込むことを意識しましょう。
ホルモンに着目した育毛剤の選び方
育毛剤の中には、ホルモンの観点から薄毛にアプローチする成分、特にDHTの生成を抑える働きや、毛母細胞の活性化をサポートする成分を含むものがあります。
自分の目的に合った成分が含まれているかを確認することが大切です。
育毛剤と発毛剤の違い
まず、言葉の定義をはっきりさせておく必要があります。ドラッグストアなどで一般的に販売されている製品は、「育毛剤(または養毛剤)」と「発毛剤」に大別されます。
「育毛剤」は、医薬部外品に分類されます。その主な目的は、今ある髪の毛を健康に保ち、抜け毛を防ぐこと(脱毛予防)、そして頭皮環境を整えて髪が育ちやすい土壌を作ることです。
一方、「発毛剤」は、医薬品(第1類医薬品)に分類されます。ミノキシジルなどの発毛有効成分を含み、毛母細胞に直接働きかけて、新しい髪の毛を生やし、育てる「発毛」効果が認められています。
この記事は男性用育毛剤メディアの記事であるため、ここでは「育毛剤(医薬部外品)」に含まれる成分について焦点を当てて解説します。
育毛剤に期待されるホルモン関連成分
育毛剤(医薬部外品)は医薬品ではないため、AGAの直接的な原因であるDHTの生成を強力にブロックしたり、発毛を強制したりする効果はありません。
しかし、含まれる成分の中には、植物エキスなどを由来とし、ホルモンバランスや毛母細胞に穏やかに働きかけることが期待されているものがあります。
例えば、5αリダクターゼの働きを阻害する可能性があるとして研究されている成分(オウゴンエキス、ヒオウギエキス、大豆イソフラボンなど)や、毛母細胞のエネルギー代謝を活発にする成分(t-フラバノン、アデノシンなど)が配合されている製品があります。
これらは、DHTの悪影響を「予防」したり、成長ホルモンが働きやすい環境を「サポート」したりする役割を期待するものです。
育毛剤に含まれることのあるホルモン関連アプローチ成分例
| アプローチ | 成分例(医薬部外品) | 期待される働き |
|---|---|---|
| 5αリダクターゼ阻害(研究) | オウゴンエキス、ヒオウギエキス、チョウジエキス | DHTの生成を抑えるサポート(予防) |
| 毛母細胞活性化 | t-フラバノン、アデノシン(※)、パントテニルエチルエーテル | 髪の成長を促す(細胞のエネルギー源) |
| 血行促進 | センブリエキス、ビタミンE誘導体、ニコチン酸アミド | 栄養やホルモンを毛根に届ける |
(※アデノシンは資生堂の製品では発毛促進有効成分として配合される場合もあります)
育毛剤選びのポイント
ホルモンへのアプローチを謳う成分だけに注目するのではなく、育毛剤は総合力で選ぶことが大切です。以下のポイントも合わせて確認しましょう。
1. 血行促進成分: センブリエキスやビタミンE誘導体など、頭皮の血流を良くする成分は、栄養を毛根に届けるために重要です。
2. 頭皮環境を整える成分: グリチルリチン酸ジカリウム(抗炎症)やヒアルロン酸(保湿)など、フケやかゆみを防ぎ、頭皮を清潔で潤いのある状態に保つ成分も必要です。
自分の頭皮タイプに合わせる
育毛剤は毎日使うものですから、使用感も重要です。自分が乾燥肌なのか、脂性肌なのか、または敏感肌なのかを理解しましょう。
脂性肌の人はさっぱりとしたリキッドタイプ、乾燥肌の人はとろみのあるローションタイプや保湿成分が豊富なものを選ぶとよいでしょう。
敏感肌の人は、アルコール(エタノール)フリーや、香料・着色料が無添加の低刺激な製品を選ぶことをおすすめします。
自分の頭皮状態と悩みに合わせて、多角的にサポートしてくれる育毛剤を選び、継続して使用することが何よりも大切です。
薄毛の基礎知識に戻る
Q&A
育毛とホルモンに関して、多くの方が疑問に思う点をまとめました。日々のケアの参考にしてください。
- 成長ホルモンを増やすサプリメントは髪に効きますか?
-
サプリメントはあくまで栄養補助食品であり、医薬品ではありません。
成長ホルモンの分泌をサポートするとされるアミノ酸(アルギニンやオルニチンなど)を含むものはありますが、それを飲んだからといって直接的に髪が生えたり、成長ホルモンが確実に増えたりすることを保証するものではありません。
育毛の基本は、あくまで睡眠や食事、運動といった生活習慣の改善です。サプリメントは、それらの補助として考えるのが良いでしょう。
- 女性ホルモンは育毛に関係ありますか?
-
はい、関係あります。女性ホルモン(エストロゲン)は、髪の成長期を持続させ、髪を豊かに保つ働きがあります。男性の体内にも微量に存在し、ホルモンバランス全体の一部を担っています。
男性の薄毛治療(AGA)で女性ホルモン剤を直接使用することはありませんが、体内のホルモンバランス全体が髪の健康に影響しているという意味で、無関係ではありません。
- 筋トレをするとテストステロンが増えて薄毛になりますか?
-
筋トレによってテストステロンの分泌が一時的に促進されることはありますが、それが直接的に薄毛(AGA)の悪化につながるという明確な証拠はありません。
AGAの主な原因は、テストステロンの「量」そのものよりも、それがDHTに「変換されやすいか(5αリダクターゼの活性)」、そしてDHTの影響を「受けやすいか(受容体の感受性)」という遺伝的な体質が大きいです。
むしろ、適度な運動は血行を促進し、ストレスを解消する面で、育毛にとってプラスに働く面も多いと考えられます。
- 育毛剤はいつから使い始めるべきですか?
-
薄毛や抜け毛が少しでも気になり始めたら、できるだけ早い段階でケアを始めることをおすすめします。
育毛剤(医薬部外品)の主な役割は、発毛ではなく、「抜け毛の予防」と「頭皮環境の整備」です。
深刻に進行してから対策するよりも、髪が健康なうちから、あるいは少し減ってきたと感じる初期段階から予防的に取り入れることで、健やかな髪を長く維持する助けになります。
- 食事でイソフラボンを摂るとDHTを減らせますか?
-
大豆などに含まれるイソフラボンには、DHTの生成に関わる5αリダクターゼの働きを穏やかに阻害する可能性が、いくつかの研究で示唆されています。
しかし、食事から摂取する量で、AGAの進行を劇的に止められるほどの強力な効果は期待できません。
納豆や豆腐などの大豆製品は、髪の材料となるタンパク質も豊富で健康にも良いため、あくまでバランスの良い食事の一環として、健康維持のために取り入れると良いでしょう。
Reference
ZHANG, Yingchun, et al. Serum levels of androgen-associated hormones are correlated with curative effect in androgenic alopecia in young men. Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research, 2018, 24: 7770.
URYSIAK-CZUBATKA, Izabela; KMIEĆ, Małgorzata L.; BRONIARCZYK-DYŁA, Grażyna. Assessment of the usefulness of dihydrotestosterone in the diagnostics of patients with androgenetic alopecia. Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii, 2014, 31.4: 207-215.
KASH, Natalie, et al. Clinical patterns of hair loss in men: is dihydrotestosterone the only culprit?. Dermatologic Clinics, 2021, 39.3: 361-370.
ENGLISH JR, Robert S. A hypothetical pathogenesis model for androgenic alopecia: Clarifying the dihydrotestosterone paradox and rate-limiting recovery factors. Medical hypotheses, 2018, 111: 73-81.
KAUFMAN, Keith D. Androgen metabolism as it affects hair growth in androgenetic alopecia. Dermatologic clinics, 1996, 14.4: 697-711.
YORK, Katherine, et al. A review of the treatment of male pattern hair loss. Expert opinion on pharmacotherapy, 2020, 21.5: 603-612.
DO, SANG-HWAN, et al. Improvement of Alopecia and Decreases in Hair Cortisol and Dihydrotestosterone Concentrations after the Topical Use of Plant Extracts in Men with Androgenetic Alopecia. Asian J Pharm Clin Res, 2021, 14.8: 71-79.
ANASTASSAKIS, Konstantinos. Hormonal and genetic etiology of male androgenetic alopecia. In: Androgenetic Alopecia From A to Z: Vol. 1 Basic Science, Diagnosis, Etiology, and Related Disorders. Cham: Springer International Publishing, 2022. p. 135-180.
VIERHAPPER, H., et al. Production rates of testosterone and of dihydrotestosterone in female pattern hair loss. Metabolism, 2003, 52.7: 927-929.
LOLLI, Francesca, et al. Androgenetic alopecia: a review. Endocrine, 2017, 57.1: 9-17.