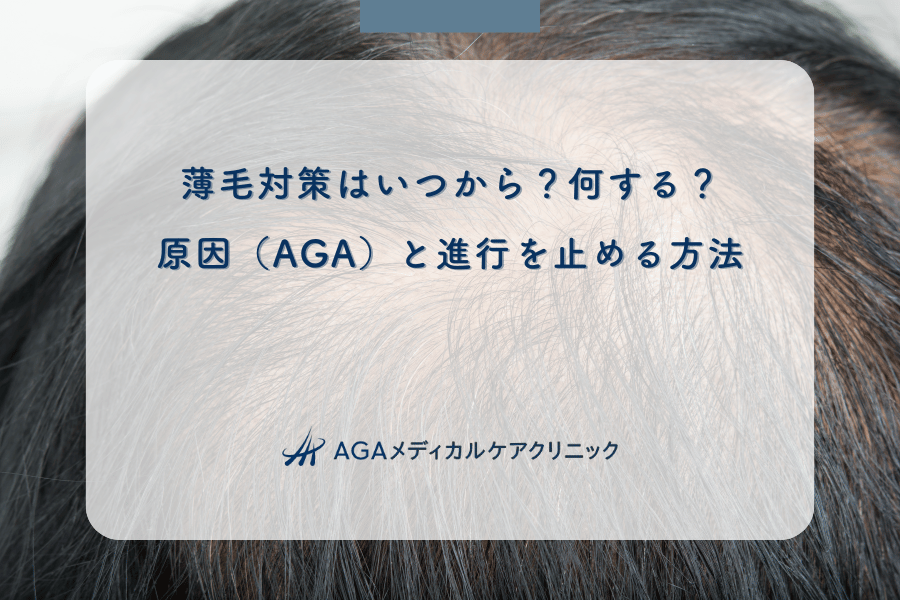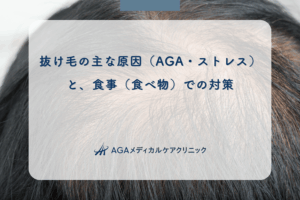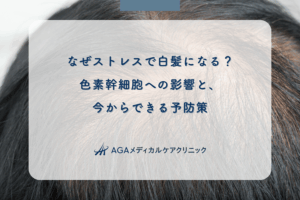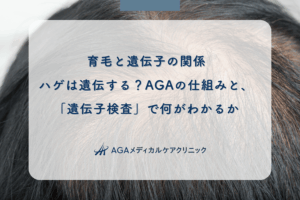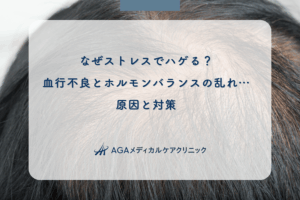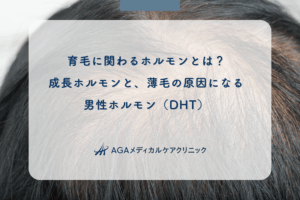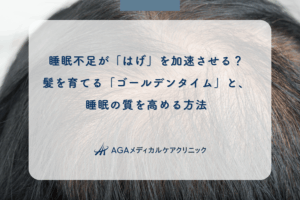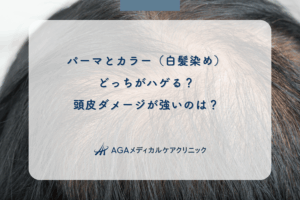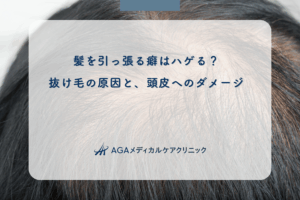「最近、抜け毛が増えた気がする」「髪のボリュームが減ってきたかも…」と感じていませんか。薄毛の悩みは、多くの男性にとって深刻な問題です。
しかし、いつから、何を対策すれば良いのか、その原因が何なのか、はっきり分からないまま不安を抱えている人も少なくありません。
この記事では、薄毛対策を始めるタイミング、具体的な対策方法、そして最も一般的な原因であるAGA(男性型脱毛症)の仕組みと、その進行を止めるためのアプローチについて、親切丁寧に解説します。
早期の理解と行動が、あなたの未来の髪を守る鍵となります。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
薄毛対策を意識し始めるサイン
薄毛対策は、早ければ早いほど良い結果につながりやすいです。しかし、具体的にどのような状態になったら「対策が必要」と判断すべきなのでしょうか。
日常生活で気づきやすい、いくつかのサインを紹介します。
抜け毛の増加が気になるとき
人は誰でも毎日ある程度の髪の毛が抜けます。一般的に、1日に50本から100本程度の抜け毛は自然なヘアサイクル(毛周期)の範囲内とされています。
しかし、シャンプーのときや朝起きたときの枕元で、明らかに以前より多くの髪の毛が抜けていると感じる場合、それは注意が必要なサインかもしれません。
特に、抜けた毛が細く短い「うぶ毛」のような毛が多い場合は、ヘアサイクルが乱れている可能性があります。
髪のボリュームダウンを感じたとき
「昔に比べて髪がペタッとする」「スタイリングがうまくいかない」といった感覚は、髪全体のボリュームが減少しているサインです。
これは、抜け毛が増えたことだけでなく、一本一本の髪の毛が細く(軟毛化)なっていることが原因の場合があります。髪が細くなると、全体の密度が低下し、地肌が目立ちやすくなります。
地肌が透けて見えるようになったとき
鏡を見たときや、他人から指摘されて、頭頂部やつむじ周り、または額の生え際の地肌が以前よりも透けて見えるようになった場合、薄毛が進行している可能性があります。
特に、髪が濡れているときや、特定の照明の下で地肌が目立つと感じたら、客観的に自分の頭皮の状態を確認してみることが重要です。
家族に薄毛の人がいる場合
薄毛、特にAGA(男性型脱毛症)は、遺伝的な要因が関与することが知られています。
父方、母方問わず、近親者に薄毛の人がいる場合、自分自身も将来的に薄毛になる可能性が他の人より高いと考えられます。
遺伝的な素因があると感じる場合は、まだ目立った症状が出ていなくても、早めに頭皮ケアや生活習慣に関心を持つことが賢明です。
なぜ薄毛は進行するのか?主な原因を探る
薄毛が進行する背景には、様々な要因が存在します。その中でも、男性の薄毛の大部分を占めると言われるのが「AGA(男性型脱毛症)」です。
ここでは、AGAの仕組みと、それ以外の原因について解説します。
最も多い原因「AGA(男性型脱毛症)」とは
AGAは「Androgenetic Alopecia」の略で、日本語では「男性型脱毛症」と呼ばれます。成人男性に見られる進行性の脱毛症で、思春期以降に発症し、徐々に薄毛が進行していく特徴があります。
額の生え際が後退していくタイプや、頭頂部が薄くなるタイプなど、進行のパターンには個人差があります。AGAは病気というよりは体質的な特徴と捉えられますが、放置すると薄毛は進行し続けます。
AGAの仕組み ホルモンと遺伝の影響
AGAの主な原因は、男性ホルモンの一種である「DHT(ジヒドロテストステロン)」です。体内の男性ホルモン「テストステロン」が、「5αリダクターゼ」という還元酵素と結びつくことでDHTが生成されます。
このDHTが、毛根にある「アンドロゲンレセプター(男性ホルモン受容体)」と結合すると、髪の成長期が短縮されます。
通常、髪の毛は2年から6年の成長期を経て太く長く育ちますが、AGAを発症すると、この成長期が数ヶ月から1年程度に短くなります。
その結果、髪が十分に育つ前に抜け落ち、細く短い毛が増えることで薄毛が目立つようになります。
5αリダクターゼの活性度やアンドロゲンレセプターの感受性は遺伝によって決まる部分が大きいため、AGAの発症には遺伝的要因が強く関与します。
AGAの進行パターンと分類
AGAの進行パターンは人によって異なりますが、特定のパターンに分類されることが多いです。これを視覚的に分類したものとして「ハミルトン・ノーウッド分類」が広く知られています。
自分の状態がどの段階にあるかを知る目安になります。
ハミルトン・ノーウッド分類の概要
| 進行パターン | 主な特徴 | 進行の傾向 |
|---|---|---|
| M字型 | 額(ひたい)の両サイド、いわゆる「そりこみ」部分から後退していく。 | 生え際がアルファベットの「M」のように見える。 |
| O字型 | 頭頂部(つむじ周辺)から円形に薄くなっていく。 | 自分では気づきにくく、他人からの指摘で発覚することも多い。 |
| U字型 (M+O) | 生え際の後退と頭頂部の薄毛が同時に進行する。 | 最終的に側頭部と後頭部の毛髪のみが残る形(U字)になりやすい。 |
AGA以外の薄毛の原因 生活習慣やストレス
AGAが男性の薄毛の主な原因ですが、それ以外にも薄毛を引き起こす要因は存在します。例えば、過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、頭皮の血行不良を招くことがあります。
血行が悪くなると、髪の成長に必要な栄養素が毛根に届きにくくなります。また、栄養バランスの偏った食事、睡眠不足、運動不足といった不健康な生活習慣も、頭皮環境や髪の健康状態に悪影響を与えます。
喫煙も血管を収縮させ、血行を妨げる要因の一つです。
薄毛対策は「気になったらすぐ」が鉄則
薄毛のサインに気づいたとき、多くの人が「まだ大丈夫だろう」「そのうち治るかもしれない」と考えがちです。
しかし、こと薄毛対策においては、この「様子見」が最も避けるべき行動です。対策を始めるタイミングについて解説します。
早期対策が重要な理由
AGAは進行性の脱毛症です。つまり、何も対策をしなければ、薄毛は徐々に、しかし確実に進行していきます。
髪の毛を作り出す「毛包(もうほう)」には寿命があり、AGAによってヘアサイクルが短縮され続けると、毛包はやがて髪の毛を作り出す能力を失ってしまいます。
一度活動を停止した毛包を再び活性化させるのは非常に困難です。そのため、毛包がまだ活動している早い段階で対策を始めることが、髪を維持するために極めて重要です。
薄毛の進行は止めるのが難しい
薄毛、特にAGAの進行を完全に「止める」ことは、現在の医学では難しい側面があります。多くの対策や治療の目的は、進行を「遅らせる」こと、そして現状を「維持・改善」することにあります。
対策を始めるのが遅れれば遅れるほど、元の状態に戻すことが難しくなり、満足のいく結果を得るために多くの時間と費用が必要になる可能性があります。
だからこそ、進行が緩やかな初期段階での対策開始が推奨されます。
対策開始の目安 年齢は関係ある?
薄毛対策を始めるのに「早すぎる」ということはありません。AGAは早い人では20代前半、あるいは10代後半から発症することもあります。「まだ若いから大丈夫」という考えは禁物です。
年齢に関わらず、本記事の最初で紹介したような「薄毛のサイン」を感じ取った時点が、対策を始めるべき最適なタイミングです。
40代、50代であっても、対策を始めるのに遅すぎることはありませんが、より良い結果を望むなら早期の行動が求められます。
まずは自分の状態を知ることから
「対策を始めよう」と思っても、自己流のケアが必ずしも正しいとは限りません。
まずは自分の薄毛の原因が本当にAGAなのか、それとも他の要因(生活習慣、ストレス、皮膚疾患など)なのかを正しく知ることが第一歩です。原因が異なれば、当然、有効な対策も異なります。
最近では、専門のクリニックで頭皮の状態を診断してもらったり、遺伝子検査などでAGAのリスクを調べたりすることも可能です。客観的な診断に基づいた対策こそが、遠回りに見えて最も確実な道です。
自分でできる初期の薄毛対策 生活習慣の改善
本格的な治療を始める前に、あるいは治療と並行して、自分自身で取り組める薄毛対策があります。それは「生活習慣の見直し」です。
髪も体の一部であり、健康な体づくりが健康な髪を育む土台となります。
髪の成長に必要な栄養素
髪の毛の主成分は「ケラチン」というタンパク質です。そのため、まずは良質なタンパク質を摂取することが基本です。しかし、タンパク質だけでは髪は作られません。
摂取したタンパク質を髪の毛に変えるためには、ビタミンやミネラル(特に亜鉛)の助けが必要です。
髪の健康をサポートする主な栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料となる。 | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助け、ヘアサイクルを正常に保つ。 | 牡蠣、レバー、牛肉、ナッツ類 |
| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を促し、皮脂のバランスを整える。 | 豚肉、レバー、マグロ、カツオ、玄米 |
これらの栄養素をバランス良く摂取することが大切です。特定の食品ばかりを食べるのではなく、多様な食材を取り入れた食事を心がけましょう。
逆に、脂っこい食事や糖分の多い間食は、皮脂の過剰分泌を招き、頭皮環境を悪化させる可能性があるため、控えるようにしましょう。
質の高い睡眠と適度な運動
髪の成長には「成長ホルモン」が深く関わっています。この成長ホルモンは、主に睡眠中に分泌されます。
特に、入眠後の深い睡眠時(ノンレム睡眠)に多く分泌されるため、睡眠時間だけでなく「睡眠の質」を高めることが重要です。
就寝前にスマートフォンやPCの画面を見るのを避け、リラックスできる環境を整えましょう。
また、適度な運動は全身の血行を促進します。頭皮も例外ではなく、運動によって血流が改善すれば、毛根に栄養素が届きやすくなります。
デスクワークが多い人は、意識的に体を動かす習慣を持つことが大切です。
ストレス管理の方法
過度なストレスは自律神経のバランスを崩し、血管を収縮させ、頭皮の血行不良を引き起こします。
現代社会でストレスをゼロにすることは難しいですが、自分なりの解消法を見つけ、溜め込まないようにすることが重要です。
ストレス対策の例
- 趣味の時間を持つ
- リラックスできる音楽を聴く
- ゆっくりと入浴する
- 軽いストレッチや瞑想
頭皮環境を整える正しいヘアケア
健康な髪は、健康な頭皮という「土壌」から育ちます。しかし、良かれと思って行っているヘアケアが、実は頭皮に負担をかけているケースも少なくありません。
薄毛対策の基本として、頭皮環境を整える正しいヘアケア方法を学びましょう。
シャンプーの選び方 頭皮タイプ別
シャンプーは、髪の汚れよりも「頭皮の汚れ」を落とすことを目的に選びます。
自分の頭皮タイプ(乾燥肌、脂性肌、敏感肌など)に合わないシャンプーを使い続けると、頭皮トラブルの原因となり、薄毛を助長することもあります。
頭皮タイプ別シャンプー選びの目安
| 頭皮タイプ | 特徴 | シャンプー選びのポイント |
|---|---|---|
| 脂性肌(オイリー) | 皮脂分泌が多く、ベタつきやすい。フケが湿っている。 | 洗浄力が比較的しっかりあり、皮脂を落とせるタイプ。(例:高級アルコール系、石けん系) |
| 乾燥肌(ドライ) | 皮脂が少なく、カサつきやすい。フケが乾燥している。 | 洗浄力がマイルドで、保湿成分が配合されているタイプ。(例:アミノ酸系) |
| 敏感肌 | 刺激に弱く、かゆみや赤みが出やすい。 | 低刺激性で、添加物(香料、着色料など)が少ないタイプ。 |
正しい髪の洗い方と乾かし方
シャンプーの選び方と同時に、「洗い方」も非常に重要です。ゴシゴシと強くこすると、頭皮を傷つけ、必要な皮脂まで奪ってしまいます。
指の腹を使い、マッサージするように優しく洗うことを心がけましょう。
正しいシャンプーの手順
| 手順 | ポイント |
|---|---|
| 1. ブラッシング | 乾いた髪の状態で、髪のもつれをほどき、ホコリを浮かせます。 |
| 2. 予洗い(湯洗い) | シャンプーをつける前に、ぬるま湯(38度程度)で頭皮と髪をしっかり洗い流します。これだけで汚れの多くは落ちます。 |
| 3. シャンプー | シャンプーを手のひらで泡立ててから、頭皮につけます。爪を立てず、指の腹で頭皮をマッサージするように洗います。 |
| 4. すすぎ | シャンプー剤が残らないよう、時間をかけて丁寧にすすぎます。特に生え際や耳の後ろは残りやすいので注意します。 |
シャンプー後は、タオルで優しく水分を拭き取り(ゴシゴシこすらない)、ドライヤーでしっかり乾かします。髪が濡れたまま放置すると、雑菌が繁殖しやすく、頭皮環境の悪化につながります。
ドライヤーは頭皮から20cmほど離し、熱が一点に集中しないように動かしながら乾かしましょう。
頭皮マッサージのすすめ
頭皮マッサージは、硬くなった頭皮をほぐし、血行を促進するのに役立ちます。シャンプー中や、育毛剤を塗布した後などに行うと良いでしょう。
指の腹を使って、頭皮全体を優しく動かすようにマッサージします。ただし、強く押しすぎたり、爪を立てたりすると逆効果になるため、力加減には注意が必要です。
本格的な薄毛対策 育毛剤と発毛剤
セルフケアだけでは薄毛の進行が止まらない、あるいはもっと積極的に対策したい場合、育毛剤や発毛剤の使用が選択肢に入ります。この二つは似ているようで、その目的と成分が異なります。
違いを正しく理解し、自分の目的に合ったものを選びましょう。
「育毛剤」の役割 頭皮環境を整える
育毛剤(医薬部外品)の主な目的は、「今ある髪の毛を健康に育てる」こと、そして「抜け毛を防ぐ」ことです。頭皮の血行を促進したり、毛根に栄養を与えたり、頭皮の炎症を抑えたりする成分が含まれています。
主に、頭皮環境を整えることで、髪が育ちやすい状態をサポートします。すでに生えている髪の毛のハリやコシを改善したい、あるいは将来の薄毛を予防したいという人に向いています。
「発毛剤」の役割 髪の成長を促す
発毛剤(第一類医薬品)は、その名の通り「新しい髪の毛を生やす(発毛を促す)」ことを目的としています。日本で現在、市販の発毛剤として認められている成分は「ミノキシジル」です。
ミノキシジルは、毛包に直接作用し、ヘアサイクルにおける成長期を延長させ、髪の成長を促す働きがあります。また、休止期にある毛包を活性化させ、新たな髪の毛の発毛をサポートします。
すでに薄毛が進行しており、髪の毛の量を増やしたいという明確な目的がある場合に適しています。
育毛剤と発毛剤の違い
育毛剤と発毛剤の最大の違いは、「目的」と「分類(医薬部外品か医薬品か)」です。発毛剤は医薬品であり、発毛効果が認められている反面、副作用のリスクも伴います。
一方、育毛剤は医薬部外品であり、効果は比較的緩やかですが、副作用のリスクは低いとされています。
育毛剤と発毛剤の比較
| 項目 | 育毛剤 | 発毛剤 (ミノキシジル配合) |
|---|---|---|
| 分類 | 医薬部外品 | 第一類医薬品 |
| 主な目的 | 育毛、抜け毛予防、頭皮環境の改善 | 発毛促進、脱毛の進行予防 |
| 主な作用 | 血行促進、栄養補給、抗炎症など | 毛包への直接作用、成長期の延長 |
自分に合った製品の選び方
どちらを選ぶべきか迷った場合は、自分の現在の状態と目的を明確にすることが重要です。
「抜け毛が増えた気がする」「髪にハリが欲しい」という予防や初期段階であれば「育毛剤」を、「明らかに地肌が目立つ」「髪の毛を増やしたい」という場合は「発毛剤」を検討するのが一般的です。
ただし、発毛剤(医薬品)を使用する際は、薬剤師から説明を受け、使用上の注意や副作用について正しく理解した上で使用する必要があります。
AGAの進行を止めるための専門的な方法
AGAは進行性のため、セルフケアや市販薬だけでは進行を十分に抑えられない場合があります。
より確実な対策を求める場合、あるいは薄毛が顕著に進行している場合は、専門のクリニック(皮膚科やAGA専門クリニック)での相談が重要になります。
専門クリニックでの相談という選択
専門のクリニックでは、医師が頭皮の状態を視診やマイクロスコープなどで詳細に確認し、問診を通じて薄毛の原因を探ります。
その上で、現在の薄毛がAGAによるものなのか、他の要因が関係しているのかを診断します。自己判断で誤った対策を続けるよりも、専門家による正しい診断を受けることが、効果的な対策への近道です。
治療を強要されることはありませんので、まずは自分の状態を正確に知るために相談してみることを推奨します。
AGA治療薬の種類と働き
現在、AGA治療の主流となっているのは「内服薬」と「外用薬」です。これらは科学的根拠に基づき、AGAの進行を抑え、発毛を促す効果が認められています。
主なAGA治療薬の種類
| 分類 | 主な成分名 | 主な働き |
|---|---|---|
| 内服薬 (5αリダクターゼ阻害薬) | フィナステリド、デュタステリド | AGAの原因であるDHTの生成を抑制し、ヘアサイクルを正常化させ、抜け毛を減らす。 |
| 外用薬 | ミノキシジル | 頭皮に直接塗布し、毛包に作用して血流を改善し、発毛を促進する。(市販の発毛剤より高濃度のものもあります) |
これらの治療薬は、医師の診断のもとで処方されます。特に内服薬は、AGAの根本的な原因(DHTの生成)にアプローチするため、進行を抑える上で非常に重要な役割を果たします。
外用薬と併用することで、より高い効果を期待できる場合もあります。
治療の継続性とその重要性
AGA治療は、一度始めたら根気強く継続することが何よりも重要です。治療薬の効果はすぐには現れません。ヘアサイクルが正常化し、新しい髪が育つのには時間がかかります。
多くの場合、効果を実感し始めるまでに最低でも3ヶ月から6ヶ月程度は必要とされます。
また、注意点として、これらの治療薬はAGAの進行を「抑えている」状態であり、AGAの体質そのものを「完治」させるものではありません。
そのため、医師の指示なく自己判断で服薬や塗布を中止すると、再びDHTが生成され始め、薄毛が元の状態に戻ってしまう可能性が高いです。
治療を続けるかどうかの判断は、必ず医師と相談の上で行ってください。
治療にかかる期間と費用の目安
前述の通り、治療は長期的に継続することが前提となります。期間としては、まずは6ヶ月から1年を目安に効果を見ていくのが一般的です。
費用は、治療内容(内服薬のみか、外用薬も併用するかなど)やクリニックによって異なります。多くの場合、月々数千円から数万円程度の費用がかかります。
治療を開始する前に、必要な費用や支払い方法について、クリニックにしっかりと確認しておくことが大切です。
薄毛の基礎知識に戻る
薄毛対策に関するよくある質問
- 薄毛対策を始めたらどれくらいで変化を感じますか?
-
対策の内容によって異なりますが、ヘアサイクル(髪が生え変わる周期)を考慮すると、目に見える変化を感じるまでには時間がかかります。
例えば、生活習慣の改善や育毛剤の使用であれば、まずは頭皮環境の改善(かゆみやフケの減少など)から始まり、髪のハリやコシの変化を感じるには数ヶ月かかることが一般的です。
AGA治療薬(内服薬や外用薬)を用いた場合でも、多くは最低3ヶ月から6ヶ月程度の継続使用で、抜け毛の減少やうぶ毛の増加といった初期の変化が報告されます。
焦らず、根気強く続けることが重要です。
- 育毛剤や治療薬の使用をやめるとどうなりますか?
-
育毛剤の使用をやめると、頭皮環境をサポートする効果がなくなり、元の状態に戻る可能性があります。
特にAGA治療薬(フィナステリドやミノキシジルなど)の場合、薬の効果によって抑えられていたAGAの進行が再び活発になります。
その結果、数ヶ月かけて再び抜け毛が増加し、薄毛が進行する可能性が非常に高いです。治療の中止や変更は、必ず自己判断せず、医師に相談してください。
- 生活習慣を改善するだけで薄毛は止まりますか?
-
薄毛の原因が主に生活習慣の乱れ(栄養不足、睡眠不足、ストレスなど)にある場合は、それらを改善するだけで抜け毛が減り、頭皮環境が健やかになることは十分に期待できます。
しかし、薄毛の主な原因がAGAである場合、生活習慣の改善はあくまで「頭皮環境を整えるサポート」であり、AGAの進行そのものを止める力は弱いと考えられます。
AGA対策には、DHTの生成を抑えるといった、AGAの仕組みに直接アプローチする方法(治療薬など)が必要となる場合が多いです。
- 専門クリニックではどのような検査をしますか?
-
まずは医師による問診が行われます。いつから薄毛が気になりだしたか、生活習慣、家族歴などを詳しく聞きます。
次に、視診や触診で頭皮の色や硬さ、毛穴の状態などを確認します。
多くのクリニックでは、マイクロスコープを使って頭皮や毛根の状態を拡大して詳細に観察し、AGA特有の軟毛化(髪が細くなる現象)が起きていないかなどをチェックします。
場合によっては、血液検査を行い、他の病気(甲状腺機能の異常など)が隠れていないか、また治療薬を使用できる健康状態かを確認することもあります。
Reference
PRICE, Vera H. Treatment of hair loss. New England Journal of Medicine, 1999, 341.13: 964-973.
BLUMEYER, Anja, et al. Evidence‐based (S3) guideline for the treatment of androgenetic alopecia in women and in men. JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, 2011, 9: S1-S57.
SHAPIRO, Jerry; WISEMAN, Marni; LUI, Harvey. Practical management of hair loss. Canadian Family Physician, 2000, 46.7: 1469-1477.
KANTI, Varvara, et al. Evidence‐based (S3) guideline for the treatment of androgenetic alopecia in women and in men–short version. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2018, 32.1: 11-22.
YORK, Katherine, et al. A review of the treatment of male pattern hair loss. Expert opinion on pharmacotherapy, 2020, 21.5: 603-612.
ROSS, Elizabeth K.; SHAPIRO, Jerry. Management of hair loss. Dermatologic clinics, 2005, 23.2: 227-243.
KINOSHITA-ISE, Misaki; FUKUYAMA, Masahiro; OHYAMA, Manabu. Recent advances in understanding of the etiopathogenesis, diagnosis, and management of hair loss diseases. Journal of Clinical Medicine, 2023, 12.9: 3259.
BLUME‐PEYTAVI, Ulrike, et al. S1 guideline for diagnostic evaluation in androgenetic alopecia in men, women and adolescents. British Journal of Dermatology, 2011, 164.1: 5-15.
NTSHINGILA, Sincengile, et al. Androgenetic alopecia: An update. JAAD international, 2023, 13: 150-158.
POZO-PÉREZ, Lorena; TORNERO-ESTEBAN, Pilar; LÓPEZ-BRAN, Eduardo. Clinical and preclinical approach in AGA treatment: a review of current and new therapies in the regenerative field. Stem cell research & therapy, 2024, 15.1: 260.