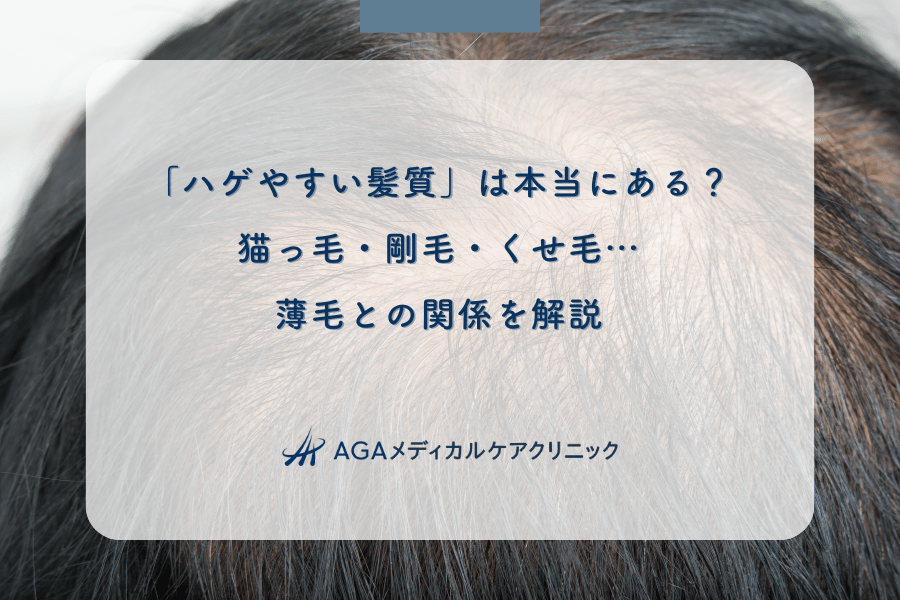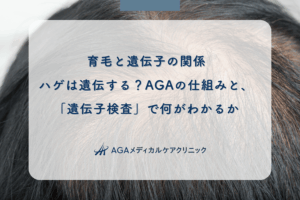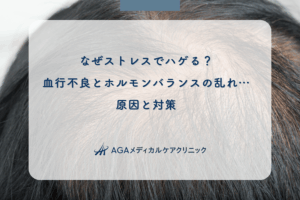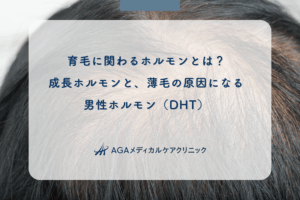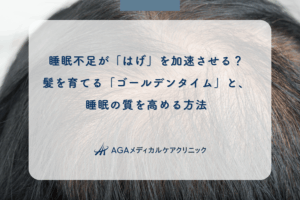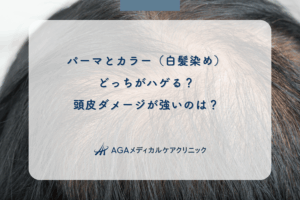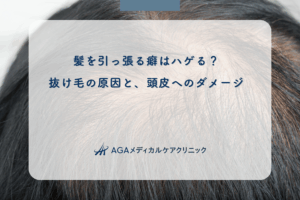長年「ハゲやすい髪質がある」という噂は根強く存在します。
特に猫っ毛、剛毛、そしてくせ毛といった特徴的な髪質を持つ方は、「この髪質だと将来薄毛になりやすいのではないか」と不安を感じるかもしれません。
しかし、結論から言えば、髪質そのものが薄毛を決定づける直接的な原因ではありません。
本記事では、「ハゲやすい髪質」の正体を徹底的に解き明かし、猫っ毛や剛毛、くせ毛といったそれぞれの髪質が、薄毛の進行や見た目にどのような影響を与えるのかを詳細に解説します。
髪質を理由に諦めるのではなく、正しい知識と対策で薄毛の不安を解消し、前向きなヘアケアに取り組むための情報を提供します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
髪質と薄毛の直接的な関係に対する誤解を解く
「ハゲやすい髪質」という認識が生まれる背景
多くの人が「ハゲやすい髪質」という言葉を信じる背景には、見た目の印象が大きく関わっています。
例えば、髪の毛が細い「猫っ毛」の人は、健康な状態でも地肌が透けて見えやすく、薄毛が進行しているように見えがちです。
一方で、髪の毛が太い「剛毛」の人は、髪の量が多く見え、薄毛の進行に気づきにくいという側面があります。
このように、髪質は「薄毛に見えるかどうか」という視覚的な要素に影響を与えるため、「特定の髪質=薄毛の原因」という誤解を生み出してきました。
しかし、これはあくまで視覚的な問題であり、髪の毛が生まれ持った太さや形状が、細胞レベルで脱毛を引き起こすわけではありません。
髪質が薄毛に直接影響を与えない理由
薄毛の約9割を占める男性型脱毛症(AGA)は、男性ホルモンの一種であるテストステロンが、5αリダクターゼという酵素によってジヒドロテストステロン(DHT)に変換され、このDHTが毛乳頭細胞に作用することで、髪の成長期を短くしてしまう現象です。
この一連の作用は、主に遺伝的要因とホルモンバランスによって決まり、髪の毛自体の太さや曲がり具合といった「髪質」が関与することはありません。
つまり、「ハゲ やすい 髪 質」という表現は、科学的な根拠に基づくものではなく、薄毛のリスクを測る指標にはならないのです。
薄毛対策を考える際には、髪質に惑わされず、AGAの根本原因に目を向ける必要があります。
薄毛の真の原因を知る重要性
薄毛の真の原因は、前述のAGAのほか、頭皮環境の悪化、生活習慣の乱れ、過度なストレスなどが複雑に絡み合っています。
髪質に不安を感じる人も、真の原因を理解することで、より効果的で適切な対策を講じることが可能になります。
髪質にまつわる誤解にとらわれることなく、薄毛のメカニズムと、それを防ぐための具体的な対策に焦点を当てることが、薄毛改善の鍵を握ります。
髪質の特徴と薄毛との直接的な関係
| 髪質の種類 | 薄毛への直接的影響 | 薄毛に見える可能性 |
|---|---|---|
| 猫っ毛(細い髪) | なし(遺伝やホルモンが主因) | 高い(地肌が透けやすい) |
| 剛毛(太い髪) | なし(遺伝やホルモンが主因) | 低い(進行に気づきにくい) |
| くせ毛(天然パーマ) | なし(遺伝やホルモンが主因) | 中程度(髪のボリュームに誤魔化される) |
猫っ毛(細い髪)が持つ薄毛との関係性
猫っ毛が薄毛に見えやすい理由
猫っ毛とは、一本一本の髪の毛が非常に細く、コシやハリが少ない髪質のことを指します。この髪質が薄毛に見えやすい最大の理由は、その細さにあります。
髪の毛が細いと、頭部全体の髪密度が同じでも、太い髪に比べて髪の毛と髪の毛の間に隙間ができやすく、光が地肌に届きやすくなります。
結果として、地肌の透け感が強調され、「密度が薄い」「薄毛が進行している」といった誤った印象を与えてしまいます。
特にトップや分け目の部分は、重力に逆らえずぺったりと寝てしまいやすいため、さらに薄毛の視覚効果を高めてしまうのです。
猫っ毛自体が薄毛の原因ではない
繰り返しになりますが、猫っ毛であること自体が薄毛を引き起こすわけではありません。髪の細さは、生まれ持った遺伝的要素によって決定され、AGAとは異なる要因で成り立っています。
しかし、猫っ毛の人は髪が柔らかく、物理的な摩擦やダメージに弱いため、不適切なヘアケアを行うとキューティクルが剥がれやすく、切れ毛や枝毛といった形で髪のボリュームを失いやすい傾向があります。
これは薄毛の原因ではありませんが、「髪の毛が少なくなる」という現象には繋がるため、猫っ毛の人は特に丁寧な扱いが大切になります。
猫っ毛特有の注意点と効果的なヘアケア
猫っ毛の人が薄毛対策を考える上では、「ボリュームを維持し、髪一本一本を強く育てること」が鍵となります。特に注意したいのは、頭皮の清潔を保ちつつ、髪に負担をかけすぎないことです。
猫っ毛の人が心がけるべきヘアケアのポイント
- シャンプーは指の腹で優しく洗うことを意識し、摩擦を避ける。
- トリートメントやコンディショナーは頭皮につけず、毛先中心に使用する。
- ドライヤーを使う際は、髪の根元から立ち上げるように乾かし、ボリュームを出す。
これらの対策は、猫っ毛特有のボリューム不足を解消し、髪の見た目を健康に保つ上で非常に有効です。
剛毛(太い髪)が持つ薄毛との関係性
剛毛が薄毛の進行に気づきにくい側面
剛毛とは、髪の毛一本一本が太く、ハリとコシが非常に強い髪質のことを指します。
剛毛の最大の利点は、髪の毛が太いため、全体的にボリューム感があり、薄毛が進行しても視覚的に目立ちにくいという点です。
例えば、AGAによって抜け毛が増えたり、髪の成長期が短くなりかけていても、残っている髪の毛が太く、周囲に立ち上がっているため、地肌が見えにくく、薄毛のサインを見逃しやすいことがあります。
これが、剛毛の人が「自分は薄毛とは無縁だ」と誤解し、対策の開始が遅れてしまう大きな要因となります。
太い髪でも薄毛が進行するメカニズム
剛毛であっても、薄毛の主原因であるAGAの進行は関係なく起こります。AGAの進行は毛根内の毛乳頭細胞の働きによって決まり、髪の毛の太さ(髪質)は影響しません。
薄毛が進行すると、まず髪の毛が細く短くなる「軟毛化」が起こります。剛毛の人でも、この軟毛化が始まると、やがて髪がコシを失い、猫っ毛のように地肌が透けやすくなっていきます。
そのため、「私は剛毛だから大丈夫」と過信せず、日頃から抜け毛の量や髪質の変化に注意深く目を向けることが重要です。
剛毛の頭皮環境を良好に保つ重要性
剛毛の人は、髪の毛が太い分、密集度が高くなり、熱や湿気が頭皮にこもりやすい傾向があります。
頭皮に熱や湿気がこもると、皮脂の過剰分泌や雑菌の繁殖を招きやすく、これが頭皮の炎症や臭い、ひいては脱毛を誘発する頭皮環境の悪化に繋がります。
そのため、剛毛の人は、髪の毛自体ではなく、頭皮環境のケアを最優先にする必要があります。
特にシャンプー後の乾燥は時間をかけて徹底的に行い、頭皮を清潔で健康な状態に保つことが、薄毛対策において大切です。
剛毛の人が特に注意すべき頭皮環境の問題
| 問題点 | 薄毛リスクを高める理由 | 対策の方向性 |
|---|---|---|
| 熱と湿気の停滞 | 雑菌の繁殖と炎症を招く | 徹底的な乾燥と通気性の確保 |
| 皮脂の過剰分泌 | 毛穴詰まりや酸化ストレスの増加 | 適切な洗浄と保湿 |
| 自己判断の遅れ | 初期AGAの発見遅延 | 定期的な頭皮チェック |
くせ毛(天然パーマ)と薄毛の関連性
くせ毛が薄毛と誤解されやすい見た目
くせ毛、いわゆる天然パーマは、髪の毛がS字状やZ字状に曲がって生える髪質です。
くせ毛は、直毛に比べて髪の毛同士が複雑に絡み合い、それが自然なボリューム感を生み出すため、薄毛の視覚的な進行を隠しやすい特徴があります。
一方で、髪の毛の生え癖が強い部分や、分け目などが波打つことで、地肌が部分的に見えやすくなることがあり、これが一時的に「薄毛になった」と誤解されることがあります。
くせ毛の人は、そのうねりによって髪の量が多く見えるため、薄毛の進行に気づきにくい傾向があるという点で、剛毛と似た側面を持っています。
くせ毛特有の頭皮への負担と薄毛リスク
くせ毛自体は薄毛の原因ではありませんが、その構造が頭皮に間接的な負担をかけることがあります。髪の毛が強くうねると、キューティクルが剥がれやすく、髪の毛が傷みやすい状態になります。
また、くせ毛は髪の毛が密集しやすく、シャンプーの泡が頭皮まで届きにくかったり、すすぎ残しが発生しやすかったりします。
これらのすすぎ残しや汚れは、頭皮の炎症を引き起こし、最終的に毛根の活動を妨げる要因となりえます。
そのため、くせ毛の人は特に、頭皮の奥までしっかり洗い、丁寧にすすぐことを重視する必要があります。
くせ毛を活かした薄毛対策
くせ毛の特性を活かすことで、薄毛の悩みを軽減できます。くせ毛が持つ自然なボリュームは、薄毛が進行しても視覚的にカモフラージュする強力な武器です。
くせ毛を活かすためのスタイリング術
くせ毛を活かした薄毛対策の鍵は、過度な矯正を避け、髪が持つ自然な動きを最大限に引き出すことです。
- パーマやストレートパーマをかけると髪が傷むため、なるべく自然な状態を保つ。
- ボリュームを出したい部分にはムースやワックスを使い、髪の立ち上がりを強調する。
さらに、くせ毛は乾燥しやすいため、保湿ケアを徹底することが、切れ毛を防ぎ、髪一本一本を強く保つ上で重要になります。
薄毛の最も重要な要因:男性ホルモンと遺伝
薄毛の9割を占めるAGA(男性型脱毛症)の基礎知識
薄毛の多くの原因は、髪質ではなく、AGA(男性型脱毛症)にあります。
AGAは成人男性の薄毛の大部分を占める進行性の脱毛症であり、その最大の原因は「ジヒドロテストステロン(DHT)」というホルモンです。
体内のテストステロンが5αリダクターゼという酵素と結びつくことでDHTが生成され、このDHTが毛乳頭細胞にある受容体と結合すると、髪の成長サイクルを乱します。
具体的には、通常2年から6年続く髪の成長期が数ヶ月から1年程度に短縮されてしまい、髪が太く長く育つ前に抜け落ちてしまうため、徐々に髪の毛が細く弱々しくなって、薄毛が進行していきます。
遺伝が髪質より薄毛に与える影響
「ハゲ やすい 髪 質」という考え方は誤りですが、「ハゲやすい体質」は存在し、それは主に遺伝によって決まります。薄毛に関する遺伝要素は、主に以下の2点に集約されます。
まず一つ目は、DHTを生成する上で重要な役割を果たす5αリダクターゼの活性度です。この酵素の働きが強いほど、DHTが多く生成されやすくなります。
二つ目は、DHTを受け取る毛乳頭細胞の「アンドロゲン受容体」の感受性の高さです。受容体の感受性が高いと、少量でもDHTの影響を受けやすく、薄毛が進行しやすくなります。
これら5αリダクターゼの活性度やアンドロゲン受容体の感受性は、遺伝によって受け継がれる可能性が高く、これが「薄毛の家系」と言われる所以です。
髪質ではなく、このホルモンの影響を受けやすい体質こそが、薄毛のリスクを決定づける最も重要な要因です。
生活習慣が薄毛の進行に及ぼす影響
AGAが薄毛の主原因であることは間違いありませんが、生活習慣は薄毛の進行速度や程度に大きく影響を及ぼします。
不規則な睡眠、栄養バランスの偏った食事、過度な飲酒や喫煙、そしてストレスの蓄積は、頭皮の血行を悪化させたり、髪の成長に必要な栄養素の供給を妨げたりします。
これらの生活習慣の乱れは、AGAの遺伝的素因を持つ人にとって、薄毛の進行を加速させるトリガーとなりえます。
AGAの根本治療と並行して、生活習慣を見直すことは、薄毛対策を成功させる上で非常に重要です。
薄毛の主要因を構成する要素
| 薄毛の原因 | 影響度(相対的) | 対策の方向性 |
|---|---|---|
| 男性ホルモン(AGA) | 高(根本原因) | 専門の医療アプローチ |
| 遺伝的要因 | 高(体質を決定) | 早期からの予防と対策 |
| 生活習慣の乱れ | 中(進行を加速) | 頭皮環境と体調の改善 |
健康な頭皮環境と薄毛の関係
皮脂の過剰分泌が引き起こす問題
健康な頭皮には適度な皮脂が必要ですが、過剰な皮脂分泌は薄毛のリスクを高める要因となります。
皮脂が過剰になると、毛穴が詰まりやすくなり、髪の毛の成長を妨げます。
さらに、皮脂が空気に触れて酸化したり、常在菌によって分解されたりすると、「過酸化脂質」や「脂肪酸」といった刺激性の物質に変化し、頭皮の炎症や痒みを引き起こします。
この炎症は、毛母細胞の働きを弱らせ、健康な髪が育ちにくい環境を作り出します。特に、脂っこい食事を好む人や、ストレスが多い人は、皮脂分泌が過剰になりやすいので注意が必要です。
血行不良が髪の成長を妨げる
髪の毛は、毛根にある毛乳頭細胞が血液から栄養を受け取ることで成長します。
そのため、頭皮の血行が不良になると、髪の成長に必要な酸素や栄養素が十分に運ばれなくなり、髪の成長サイクルが乱れてしまいます。
血行不良の原因としては、運動不足、喫煙、冷え、そして頭皮のコリなどが考えられます。
デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続けている人は、首や肩のコリから頭皮の血行不良を引き起こしている可能性が高く、薄毛対策として血行促進のケアを取り入れることが大切です。
健康な頭皮環境を維持する方法
薄毛対策において、頭皮環境の改善は髪質に関わらず非常に重要です。正しいシャンプーの方法、適度な頭皮マッサージ、そして乾燥を防ぐための保湿が三本柱となります。
シャンプーは一日一回、夜に行い、日中の汚れをしっかり落とすことが基本です。
健康な髪を育てるための頭皮マッサージ
頭皮マッサージは、血行を促進し、毛根に栄養を届けやすくするために有効です。
頭皮マッサージを行う際は、爪を立てずに指の腹を使い、頭皮全体を優しく動かすように揉みほぐします。特に、血行不良になりやすい側頭部や後頭部、そして頭頂部を意識して行うと効果が高まります。
マッサージは入浴中や入浴後の体が温まっている時に行うと、血行促進効果がさらに期待できます。
マッサージオイルや育毛剤を併用することで、頭皮への負担を減らしつつ、有効成分の浸透も助けることが可能です。
健康な頭皮環境の維持に必要なこと
| 要素 | 目的 | 具体的な行動 |
|---|---|---|
| 適切な洗浄 | 皮脂や汚れの除去 | 指の腹を使った丁寧なシャンプーとすすぎ |
| 血行促進 | 栄養素の供給 | 入浴中の頭皮マッサージ、適度な運動 |
| 保湿 | バリア機能の維持 | 乾燥対策のローションや育毛剤の使用 |
髪質に合わせた日常の薄毛対策
シャンプーの選び方と正しい洗髪方法
髪質や頭皮の状態によって、選ぶべきシャンプーは異なります。例えば、猫っ毛で髪のボリュームを出したい人は、髪にハリとコシを与えるアミノ酸系のシャンプーを選ぶと良いでしょう。
一方、剛毛で皮脂分泌が多い人は、洗浄力が高い成分を含みつつも、頭皮への刺激が少ないものが望ましいです。
正しい洗髪方法も、薄毛対策において非常に重要です。
- まずはぬるま湯で髪と頭皮を予洗いし、表面の汚れを落とします。
- シャンプーを手のひらでよく泡立て、泡で髪を包むように洗います。
- 指の腹を使って頭皮を優しく揉み洗いし、毛穴の汚れを浮かせます。
- シャンプー成分が頭皮に残らないよう、時間をかけて念入りにすすぎます。
特にすすぎ残しは、頭皮トラブルの大きな原因となるため、時間をかけて丁寧に行うことが大切です。
ドライヤーの使い方と髪へのダメージ軽減
洗髪後の髪は、キューティクルが開いて非常にデリケートな状態です。自然乾燥は頭皮の雑菌繁殖や冷えを招き、薄毛対策としては避けるべき行動です。
ドライヤーを使って速やかに乾かすことが重要ですが、使い方を間違えると髪や頭皮にダメージを与えてしまいます。
ドライヤー使用時の注意点
ドライヤーを使う際は、以下の点に注意することで、髪へのダメージを最小限に抑えられます。
- タオルドライでしっかりと水分を拭き取ることで、ドライヤーの使用時間を短くする。
- ドライヤーは頭皮から20cm程度離し、熱が一箇所に集中しないように常に動かす。
- まずは地肌を乾かすことを優先し、その後に髪全体を乾かす。
- 仕上げに冷風を当てることで、開いたキューティクルを引き締め、髪にツヤを与える。
特に猫っ毛の人は、根元から立ち上げるように乾かすことで、ボリュームアップ効果も得られます。
髪質別シャンプー選びの簡単なまとめ
| 髪質 | 主な悩み | 選ぶべきシャンプーの系統 |
|---|---|---|
| 猫っ毛 | ボリューム不足、ハリ・コシのなさ | アミノ酸系、ペプチド配合(補修・強化) |
| 剛毛 | 皮脂過多、頭皮のべたつき | サリチル酸などを含む洗浄力と殺菌力のバランスが取れたもの |
| くせ毛 | 乾燥、パサつき、うねり | 保湿成分(セラミド、ヒアルロン酸)が豊富なもの |
体の中から整える薄毛対策の土台
食生活と髪の成長に必要な栄養素
髪の毛は、私たちが食べたものから作られています。そのため、薄毛対策には、体の中から髪の成長を支える栄養素をバランス良く摂取することが大切です。
髪の主成分はケラチンというタンパク質であり、これを構成するアミノ酸を十分に供給する必要があります。さらに、タンパク質の合成や細胞の分裂を助けるビタミンやミネラルも重要です。
頭皮環境を改善し髪を育てる栄養素
特に積極的に摂取したい栄養素には、以下のようなものがあります。
- タンパク質: 髪の主成分。肉、魚、卵、大豆製品など。
- 亜鉛: ケラチンの合成に必要。牡蠣、レバー、ナッツ類など。
- ビタミンB群: 代謝を助け、頭皮の健康を保つ。緑黄色野菜、魚介類など。
特定の栄養素だけを大量に摂取するのではなく、これらの栄養素をバランス良く、毎日の食事から取り入れることが、薄毛対策の基礎を築きます。
睡眠の質を高める重要性
睡眠は、髪の成長を促す上で非常に重要な役割を果たします。髪の成長に深く関わる「成長ホルモン」は、主に深い睡眠(ノンレム睡眠)中に分泌されます。
この成長ホルモンが、毛母細胞の活動を活発にし、髪を太く長く育てる手助けをします。睡眠不足や質の低い睡眠が続くと、成長ホルモンの分泌が滞り、髪の成長サイクルが乱れて薄毛が進行しやすくなります。
質の高い睡眠のための行動
| 行動 | 効果 | 実施の目安 |
|---|---|---|
| 就寝前のスマホ使用を控える | メラトニン分泌を促し、入眠を助ける | 就寝1時間前まで |
| 軽い運動をする | 適度な疲労感で深い睡眠を誘う | 就寝3時間前まで |
| 寝室の温度・湿度を調整する | 快適な環境で睡眠の質を維持する | 一年を通じて適切な設定を心がける |
毎日十分な睡眠時間を確保し、その質を高める努力をすることで、体内から薄毛対策を強力にサポートすることができます。
ストレス管理と薄毛の関係
現代社会において、ストレスは薄毛の進行を加速させる大きな要因の一つです。過度なストレスは自律神経の乱れを引き起こし、血管を収縮させ、頭皮の血行不良を招きます。
また、ストレスはホルモンバランスにも影響を与え、一時的に抜け毛が増える「円形脱毛症」や「休止期脱毛症」の原因にもなりえます。
ストレスそのものを完全に排除することは難しいですが、自分なりの解消法を見つけ、ストレスを溜め込まないようにすることが大切です。
専門家への相談と薄毛治療の選択肢
薄毛治療を開始する適切なタイミング
「ハゲ やすい 髪 質」かどうかに関わらず、薄毛の兆候を感じたら、できるだけ早く専門家に相談することが、薄毛対策を成功させる鍵となります。
薄毛、特にAGAは進行性の疾患であり、一度進行してしまった毛根を元に戻すことは非常に困難です。
そのため、抜け毛が増えた、髪が細くなった、分け目が目立つようになったなど、初期の段階で専門医の診断を受け、適切な治療を開始することが重要です。
自己判断で市販の育毛剤を試す前に、まずは自分の薄毛の原因を知ることが、効果的な治療への第一歩です。
薄毛治療の主な選択肢
薄毛治療には、主に内服薬、外用薬、そして植毛や注入療法といった選択肢があります。
内服薬の代表的なものとしては、AGAの原因物質であるDHTの生成を抑制する薬があり、薄毛の進行を抑える目的で用いられます。
外用薬としては、毛母細胞を活性化し、発毛を促す成分を含むものが一般的です。
どの治療法が自分に合っているかは、薄毛の進行度や健康状態、生活背景によって異なります。専門医は、これらの情報を総合的に判断し、読者一人ひとりに合った治療方針を提案します。
適切なクリニックを選ぶポイント
薄毛治療を受けるクリニックを選ぶ際には、治療実績が豊富であること、医師やスタッフが親身になって話を聞いてくれること、そして治療費用が明確に提示されていることが重要です。
治療は長期間にわたることが多いため、通いやすさやプライバシーへの配慮も大切な要素となります。複数のクリニックを比較検討し、納得した上で治療を開始することが、成功に繋がります。
薄毛と遺伝子に戻る
よくある質問
- 「ハゲやすい髪質」は、食生活で変えられますか?
-
生まれ持った髪質、つまり髪の太さや形状そのものを、食生活によって根本的に変えることはできません。
しかし、食生活を改善することで、髪の毛が健康で丈夫に育ちやすくなり、一本一本にハリやコシが生まれることは期待できます。
結果として、髪全体にボリューム感が出て、薄毛に見えにくい状態を作ることは可能です。
髪の主成分であるタンパク質や、その合成を助ける亜鉛、ビタミンなどを意識的に摂取することが重要です。
- 猫っ毛でも将来薄毛にならない人はいるのでしょうか?
-
はい、猫っ毛だからといって必ずしも薄毛になるわけではありません。薄毛の主な原因は、髪質ではなく、AGAの遺伝的要因と男性ホルモンの影響です。
猫っ毛でも、AGAの遺伝的素因がなければ、生涯にわたって薄毛に悩まされないケースは多く存在します。
猫っ毛の人は地肌が透けやすいため薄毛に見えやすいだけなので、過度に心配せず、適切な頭皮ケアを続けることが大切です。
- くせ毛の人は薄毛の進行に気づきにくいというのは本当ですか?
-
はい、その傾向はあります。くせ毛はそのうねりによって髪の毛同士が複雑に絡み合い、直毛に比べて自然なボリューム感や立体感を出します。
そのため、薄毛が進行して髪の密度が低下し始めても、そのボリュームで地肌の露出が隠されやすく、初期の段階での変化に気づきにくいことがあります。
剛毛の人と同じく、日頃から鏡で頭皮の状態や抜け毛の量をチェックする習慣が必要です。
- 剛毛の場合、シャンプーは洗浄力が強いものを選んだほうが良いですか?
-
剛毛の人は髪が密集しやすく、頭皮に皮脂や汗がこもりやすい傾向があるため、洗浄力が適切なものを選ぶのは大切ですが、強すぎる洗浄力のシャンプーは頭皮に必要な皮脂まで奪ってしまい、乾燥やバリア機能の低下を招きます。
結果として、過剰な皮脂分泌や炎症を引き起こす可能性があるため、アミノ酸系など、頭皮に優しい成分を含みながらも、しっかりと洗浄できるバランスの取れたシャンプーを選ぶことが望ましいです。
- 薄毛対策のために、育毛剤と発毛剤はどちらを選ぶべきでしょうか?
-
育毛剤は、今生えている髪の毛を健康に保ち、抜け毛を防ぎ、頭皮環境を整えることを目的として使用します。
一方、発毛剤は、新しく髪の毛を生やすことを目的として使用され、一般的に医薬品成分が含まれます。
薄毛の初期段階で予防や現状維持を目指すなら育毛剤が適していますが、明らかに薄毛が進行しており、積極的な発毛を希望する場合は、専門医に相談の上で発毛剤やその他の治療薬の利用を検討するべきです。
- 日常的なストレス解消が薄毛対策につながるのはなぜでしょうか?
-
ストレスが蓄積すると、自律神経の働きが乱れ、交感神経が優位な状態が続きます。これにより血管が収縮し、頭皮への血流が悪化します。
髪の毛は血流から栄養を受け取って成長するため、血行不良は髪の成長を妨げ、薄毛の進行を加速させます。また、ストレスはホルモンバランスにも影響を及ぼします。
そのため、趣味や運動などで日頃から適切にストレスを解消し、心身ともにリラックスできる時間を持つことが、間接的ではありますが、薄毛対策として非常に重要となります。
- 遺伝による薄毛は、若いうちから対策すれば防げるのでしょうか?
-
遺伝的要因による薄毛(AGA)の素因を持っていても、早期から適切な対策を講じることで、その発症時期を遅らせたり、進行の程度を軽減したりすることは十分に可能です。
特にAGAは進行性であるため、症状が現れる前の予防的なケアや、初期段階での専門的な治療が極めて有効です。
生活習慣を整えて頭皮環境を良好に保つことに加え、遺伝的なリスクが高いと感じる場合は、早めに専門医に相談し、自分に合った予防策を立てることが賢明な判断と言えます。
- 「ハゲやすい髪質」だと思い込んでいますが、実際はAGA以外の原因も考えられますか?
-
はい、考えられます。薄毛や抜け毛の原因はAGAだけではありません。
例えば、過度なダイエットによる栄養不足、甲状腺機能の異常、皮膚炎などによる炎症、あるいは薬の副作用など、様々な要因で脱毛症が引き起こされることがあります。
ご自身の髪質を気にするあまり、自己判断で対策を限定せず、まずは皮膚科や薄毛専門のクリニックで正確な診断を受けることを強く推奨します。
これにより、ご自身の薄毛の真の原因に合わせた、最も効果的な対策を見つけ出すことができます。
Reference
SINCLAIR, Rodney; TORKAMANI, Niloufar; JONES, Leslie. Androgenetic alopecia: new insights into the pathogenesis and mechanism of hair loss. F1000Research, 2015, 4.F1000 Faculty Rev: 585.
ALESSANDRINI, A., et al. Common causes of hair loss–clinical manifestations, trichoscopy and therapy. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2021, 35.3: 629-640.
LOLLI, Francesca, et al. Androgenetic alopecia: a review. Endocrine, 2017, 57.1: 9-17.
WHITING, David A. Possible mechanisms of miniaturization during androgenetic alopecia or pattern hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2001, 45.3: S81-S86.
TRÜEB, Ralph M. Molecular mechanisms of androgenetic alopecia. Experimental gerontology, 2002, 37.8-9: 981-990.
HO, Chih-Yi, et al. Female pattern hair loss: an overview with focus on the genetics. Genes, 2023, 14.7: 1326.
OIWOH, Sebastine Oseghae, et al. Androgenetic alopecia: A review. Nigerian Postgraduate Medical Journal, 2024, 31.2: 85-92.
LIU, Yingzi, et al. Androgenetic alopecia. Nature Reviews Disease Primers, 2025, 11.1: 73.
KALIYADAN, Feroze; NAMBIAR, Ajit; VIJAYARAGHAVAN, Sundeep. Androgenetic alopecia: an update. Indian journal of dermatology, venereology and leprology, 2013, 79: 613.
KIDANGAZHIATHMANA, Ajithkumar; SANTHOSH, Parvathy. Pathogenesis of androgenetic alopecia. Clinical Dermatology Review, 2022, 6.2: 69-74.