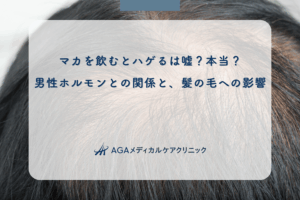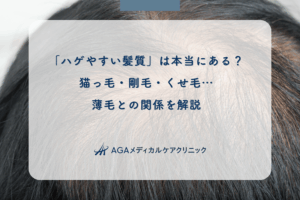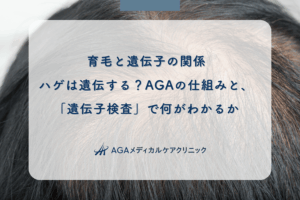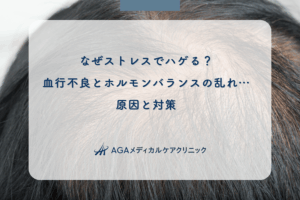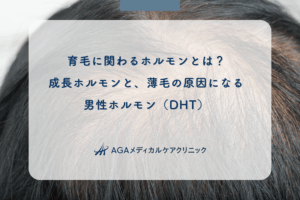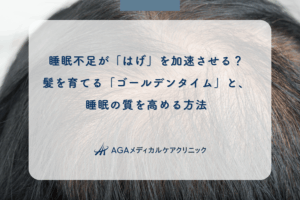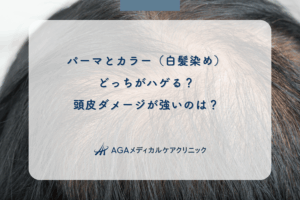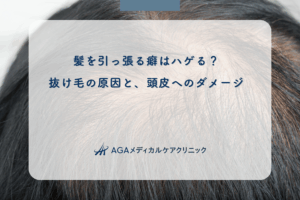「トリートメントを使うとハゲる」という噂を聞いて、毎日のヘアケアに不安を感じていませんか。
結論から申し上げると、トリートメントそのものが直接的な薄毛の原因になることはありません。
しかし、間違った使い方、特に「すすぎ残し」は頭皮環境を著しく悪化させ、結果として薄毛リスクを高める重大な要因になり得ます。
このすすぎ残しが毛穴に詰まり、炎症や酸化を引き起こす具体的な仕組みと、それを回避するためにあなたが今日から実践できる正しい使用方法を徹底的に解説します。
単に髪を美しくするだけでなく、未来の健康な髪を守るために必要な知識と行動を身につけ、安心してヘアケアを続けていきましょう。
あなたが抱える疑問や不安を解消し、読者に寄り添った親切丁寧な情報を提供することをお約束します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
トリートメントと薄毛の関係性誤解と真実
トリートメントが直接薄毛を引き起こすわけではない理由
トリートメントの主な目的は、髪の内部に栄養や保湿成分を浸透させ、表面をコーティングすることで、ダメージを補修し、指通りを良くすることです。
トリートメントに含まれる成分は、基本的に毛髪の補修を目的としており、毛根や毛乳頭といった発毛の司令塔に直接悪影響を与える構造にはなっていません。
薄毛の主要な原因は、男性ホルモンの影響(AGA)や遺伝、血行不良、栄養不足など、体内の要因や頭皮環境の悪化にあります。
トリートメントは髪の毛そのものに作用するため、理論上、これら薄毛の根本原因に直結するものではないと理解してください。
あなたが薄毛になった場合、トリートメントの使用が原因だと決めつける前に、生活習慣やホルモンバランスの変化など、他の要因を見直すことが大切です。
薄毛リスクを高める「すすぎ残し」の正体
トリートメント自体が薄毛の原因でないとしても、「使い方」を誤ると話は変わります。特に危険なのが「すすぎ残し」です。
トリートメントには、髪の滑らかさやまとまりを出すために、油分やシリコン、カチオン界面活性剤などが多く含まれています。
これらが頭皮や毛穴に残ってしまうと、非常に厄介な汚染物質に変わります。すすぎ残された油分や界面活性剤は、毛穴を物理的に塞ぎ、皮脂や老廃物と混ざり合って強固な栓を形成します。
この栓が毛穴の奥深くで炎症を誘発し、常在菌のバランスを崩し、結果として健康な髪の成長を妨げ、薄毛リスクを高めてしまうのです。
この物理的な「詰まり」こそが、トリートメントが薄毛に関係するという誤解を生む真実の要因です。
必要なのは「成分」ではなく「使い方」への意識
多くの男性は、トリートメントの「成分」にばかり意識が向きがちですが、薄毛対策という観点から見ると、最も重要視すべきは「使い方」です。
頭皮トラブルのほとんどは、成分に対するアレルギー反応ではなく、物理的な付着と残留によって引き起こされます。
たとえば、どんなに高級で頭皮に優しい成分のトリートメントを使ったとしても、頭皮にベッタリと塗りつけ、十分に洗い流さなければ、それは毛穴の詰まりの原因にしかなりません。
逆に、一般的なトリートメントであっても、毛先のみに塗布し、完璧なすすぎを心がけることで、リスクを限りなくゼロに近づけられます。
トリートメントは「頭皮ケア用品」ではなく「毛髪補修用品」であるという認識を持ち、頭皮を避けて使用する意識が重要です。
トリートメント成分に対する正しい認識
| 成分の種類 | 主な役割 | 毛髪への作用 |
|---|---|---|
| シリコン(ジメチコンなど) | 手触りの改善 | 髪表面をコーティングし、摩擦を軽減 |
| 油分・エモリエント剤 | 保湿・柔軟化 | 髪の水分蒸発を防ぎ、しなやかさを与える |
| カチオン界面活性剤 | 吸着・帯電防止 | 髪のマイナス電荷に吸着し、静電気を防ぐ |
毛穴に詰まる!トリートメントの「すすぎ残し」が引き起こす問題
毛穴詰まりが招く頭皮の炎症とフケ・かゆみ
すすぎ残しによって毛穴に油分や界面活性剤が詰まると、頭皮は慢性的な炎症状態に陥ります。
毛穴が塞がれることで、本来排出されるべき皮脂や汗、古い角質が毛穴内部に留まり、これを餌にしてマラセチア菌などの常在菌が異常増殖します。
この菌の過剰な増殖や、異物による刺激に対して、頭皮は防御反応として炎症を起こします。
炎症が起こると、頭皮のターンオーバーが乱れ、乾燥フケや脂性フケが大量に発生し、我慢できないほどのかゆみを引き起こします。
フケ・かゆみは薄毛のサインではありませんが、炎症によるダメージは毛母細胞の働きを鈍らせ、髪の成長サイクルを短縮し、結果的に薄毛を進行させてしまいます。
慢性的な炎症が髪に与える影響
炎症は単なる不快感にとどまりません。頭皮が赤みを帯びたり、ニキビのような吹き出物が発生したりするのは、炎症が深刻化している証拠です。
炎症によって頭皮の血流が悪化すると、毛母細胞に運ばれるはずの酸素や栄養素が不足し、髪の毛が細く、弱々しく成長するようになります。
この状態が長く続くと、成長期にある髪の毛が十分に太くなる前に抜け落ちてしまう「休止期脱毛」が増え、薄毛として顕在化するのです。
トリートメントの「すすぎ残し」は、まるで頭皮にとっての時限爆弾のようなものであり、時間をかけて薄毛の土壌を作り上げてしまいます。
酸化した油分が頭皮環境を悪化させる
トリートメントに含まれる油分が頭皮に残った状態で長時間放置されると、皮脂や空気中の酸素と反応して酸化が始まります。
この酸化によって生成される過酸化脂質は、頭皮細胞にとって非常に有害な物質です。過酸化脂質は細胞の老化を早めるだけでなく、頭皮のバリア機能を破壊し、雑菌が繁殖しやすい環境を作り出します。
酸化した油分が毛穴の奥でこびりつくと、通常のシャンプーではなかなか落ちにくくなり、悪臭の原因にもなります。
頭皮が酸化し、炎症が続くと、毛包組織全体がダメージを受け、健康な髪の毛を作り出す力が失われていきます。
薄毛対策を行う上で、頭皮の「抗酸化」環境を保つことは非常に大切であり、そのためにもトリートメントの残留は徹底的に防ぐべきです。
育毛剤の浸透を妨げるバリアの形成
薄毛対策として育毛剤や発毛剤を使用している人にとって、トリートメントのすすぎ残しは致命的な問題を引き起こします。
すすぎ残されたトリートメントの油分やコーティング成分は、頭皮表面に薄い膜(バリア)を形成します。この油膜は水溶性の育毛剤や有効成分の浸透を強力にブロックしてしまいます。
あなたが毎日高価な育毛剤を塗布していたとしても、その成分が毛根まで届かず、表面の油膜の上で蒸発しているだけでは、期待した効果は得られません。
育毛剤の効果を最大限に引き出すためには、シャンプーで頭皮を清潔にし、トリートメント成分を完全に洗い流した後、クリーンな頭皮状態で塗布することが必要です。
トリートメントの正しい使い方は、育毛剤の有効性を左右する重要な鍵となります。
すすぎ残しが招く頭皮トラブル
| トラブル名 | 原因 | 薄毛への影響 |
|---|---|---|
| 毛穴の詰まり | 油分、界面活性剤の残留 | 皮脂の排出を妨げ、炎症の土台を作る |
| 頭皮の炎症 | 常在菌の異常増殖、異物刺激 | 血行不良を招き、毛髪の成長を阻害 |
| 過酸化脂質生成 | 残った油分の酸化 | 頭皮細胞の老化を早め、毛包組織にダメージ |
薄毛リスクを回避するための正しいトリートメントの使い方
塗布する部位を毛先から中間に限定する
トリートメントを使う上で、最も意識すべきことは頭皮への付着を避けることです。トリートメントの役割は、あくまでもダメージを受けやすい「毛髪」を補修・保護することにあります。
塗布する理想的な部位は、髪のダメージが最も進行しやすい「毛先」から、根元から5センチ以上離れた「中間」までです。
根元に近い部分、特に頭皮から出る毛穴の出口付近は、髪の毛が最も健康で、コーティング成分を必要としません。
まず手のひらにトリートメントを適量出し、手のひら全体によく伸ばしてから、毛先を中心に揉み込むように馴染ませてください。
この段階で、手にトリートメントを付け足さず、残ったわずかな量で中間部分に薄く広げる程度に留めることが大切です。
頭皮への付着を防ぐための具体的なテクニック
トリートメントを塗布する際、指先ではなく、手のひら全体を使って髪の束を挟み込むように塗ると、頭皮への付着を大幅に防げます。
もし、トリートメントが頭皮に付着してしまったと感じたら、すぐにシャワーで軽く洗い流すか、シャンプーをする前に丁寧に指の腹で拭き取ってください。
特に、耳の後ろや襟足の生え際は、すすぎ残しが起こりやすい要注意エリアです。
トリートメントが毛穴に詰まることを防ぐため、これらのエリアは可能な限りトリートメントを塗布しないように注意を払ってください。
また、トリートメントを塗布した後、コーム(櫛)を使って髪全体に均一に行き渡らせる「コーミング」を行うと、無駄な付着を防ぎつつ、効果を高められます。
放置時間とすすぎの重要性
トリートメントの効果を高めるために、推奨されている放置時間を守ることは重要ですが、長く放置すればするほど効果が高まるわけではありません。
多くの場合、製品に記載されている数分間の放置時間で、成分は十分に髪の内部に浸透します。
過度な長時間放置は、トリートメントの油分が体温で溶け出し、頭皮に流れ落ちるリスクを高めます。放置時間が終わったら、すぐに徹底的なすすぎに移ってください。
すすぎはトリートメントの使用において最も重要な最終工程です。目視で泡やぬめりがなくなった後も、さらに1分間以上、熱すぎないぬるま湯で洗い流し続けることが大切です。
トリートメントの使用で避けたいNG行動
- シャンプー後の水分を十分に切らずに使用する
- 頭皮に直接トリートメントを揉み込む
- 推奨される放置時間を大幅に超えて放置する
トリートメントの正しい塗布部位
| 部位 | 塗布の是非 | 薄毛リスク |
|---|---|---|
| 頭皮・根元 | 不可 | 詰まりによる炎症リスクが高い |
| 中間部(根元から5cm~) | 少量塗布可 | 適度な保湿、ダメージ補修 |
| 毛先 | 推奨 | 重点的なダメージ補修が必要 |
完璧なすすぎを実現するための実践的な方法
理想的なすすぎ時間の目安
トリートメントのすすぎ時間は、シャンプーのすすぎ時間よりも長く設けることが基本中の基本です。目安としては、シャンプーで頭皮を洗う時間の2倍から3倍の時間をかける意識が必要です。
具体的には、髪の毛全体からぬめり感が消えたと感じてから、さらに最低でも1分半から2分間は、集中的にすすぎを続けてください。
特に、髪の毛が密集している後頭部や、トリートメント成分が流れ落ちて溜まりやすい首筋、耳周りのすすぎは念入りに行ってください。
この「+アルファ」のすすぎこそが、薄毛リスクを回避するための最大の防御策となります。面倒に感じるかもしれませんが、将来の髪の健康を守るための大切な時間だと捉えてください。
シャワーヘッドの角度と水圧を意識する
シャワーヘッドの使い方一つで、すすぎの効率は劇的に向上します。
シャワーヘッドは、上からではなく、下から上、つまり毛穴の奥を狙うようなイメージで当てることで、詰まりの原因となる残留物を押し出すように洗い流せます。
特に、頭皮に対して約45度の角度から水圧をかけると、毛穴の入口付近に残った油分やシリコンが流れやすくなります。
ただし、水圧が強すぎると頭皮を傷つける原因となるため、肌に心地よく感じる程度の優しい水圧に設定してください。
髪の毛だけでなく、頭皮全体に水をしっかりと行き渡らせるように、頭の各部位をブロックごとに分けてすすぎを行うのが効果的です。
指の腹を使った丁寧なマッサージ洗いの重要性
すすぎの際も、シャンプー時と同様に指の腹を使い、優しく頭皮をマッサージしながら洗い流すことが重要です。ただ水に当てるだけでは、頭皮に付着したトリートメント成分はなかなか落ちません。
指の腹で頭皮を軽く動かし、毛穴に詰まった残留物を物理的に剥がし出すイメージで丁寧に洗ってください。
爪を立てたり、ゴシゴシと力を入れすぎたりすると、頭皮を傷つけ、逆に炎症を招いてしまうため、あくまでも優しく、頭皮を動かすことを意識してください。
このマッサージ洗いは、血行促進効果も期待できるため、一石二鳥の薄毛対策となります。
すすぎの徹底チェックポイント
| チェック項目 | 状態 | 次の行動 |
|---|---|---|
| 指通り | 髪がきしみ始める(ぬめりがない) | 合格。終了して良い |
| 頭皮の触感 | 指の腹で触ってベタつきがない | 合格。終了して良い |
| すすぎ時間 | ぬめりが消えてから+1分以上 | 継続が必要か判断する |
薄毛予防のために見直したい!シャンプーとトリートメントの順番
シャンプーで頭皮の汚れを徹底的に除去する
薄毛対策の洗髪において、シャンプーの役割は頭皮の徹底的な洗浄にあります。トリートメントを使う以前に、まずシャンプーで毛穴の奥に詰まった皮脂や古い角質をしっかりと洗い流すことが重要です。
シャンプー前には、必ずぬるま湯で予洗いを1分程度行い、大まかな汚れを落としてください。シャンプー剤を手のひらで泡立ててから頭皮に乗せ、指の腹で優しく揉み込むように洗います。
この際、頭皮全体を動かすようにマッサージしながら洗うことで、血行が促進され、健康な髪の成長を助けます。
シャンプーの泡が頭皮に残ることも炎症の原因となるため、シャンプー後のすすぎも同様に念入りに行ってください。
洗髪後のタオルドライは摩擦を避ける
シャンプーとトリートメントの後のタオルドライの仕方にも、薄毛リスクを左右する重要なポイントがあります。濡れた髪はキューティクルが開いており、非常にデリケートな状態です。
この状態でタオルでゴシゴシと強く拭くと、摩擦によってキューティクルが剥がれ、切れ毛や枝毛の原因となります。また、頭皮に強い摩擦を加えると炎症を起こし、薄毛リスクを高めます。
タオルドライは、清潔なタオルで髪を挟み込み、ポンポンと優しく叩くようにして水分を吸い取ることが正しいやり方です。
特に毛量の多い方は、タオルで頭全体を包み込み、優しく押さえるようにして水分をオフしてください。
ドライヤーによる正しい乾燥方法
トリートメント後の髪は、自然乾燥させずにドライヤーで速やかに乾かすことが重要です。
髪の毛が濡れた状態が長く続くと、頭皮の温度が下がり、血行が悪くなるだけでなく、雑菌が繁殖しやすい環境を作り出してしまいます。
この雑菌の繁殖こそが、頭皮の炎症と薄毛リスクを増大させます。ドライヤーは髪から20cm程度離し、熱すぎない温風で根元から乾かし始めます。
全体が8割程度乾いたら、冷風に切り替えてキューティクルを引き締め、髪の水分を閉じ込めてください。この冷風仕上げは、トリートメントの効果を維持し、髪にツヤを与えるためにも重要です。
正しい洗髪手順とポイント
| 手順 | 目的 | 重要な行動 |
|---|---|---|
| 予洗い | 大きな汚れの除去、頭皮の軟化 | ぬるま湯で1分以上しっかりと |
| シャンプー | 頭皮の皮脂・汚れの洗浄 | 指の腹でマッサージ洗い。泡を完全に流す |
| トリートメント | 毛髪の補修、保湿 | 頭皮を避け、毛先中心に塗布 |
| すすぎ | トリートメント成分の完全除去 | シャンプーの2倍以上の時間。ぬめりが消えてから+1分 |
| 乾燥 | 雑菌繁殖の抑制、キューティクルの保護 | タオルドライ(叩く)、ドライヤー(根元から冷風で) |
トリートメント選びで薄毛リスクを抑えるポイント
薄毛が気になる男性が避けるべき成分
トリートメント成分そのものは薄毛の直接原因ではありませんが、頭皮に残りやすい成分や刺激の強い成分は、すすぎ残しが発生した場合に薄毛リスクを高めます。
特に注意すべきは、髪のコーティング力が非常に強く、水に溶けにくい高級アルコール系油分や特定のカチオン界面活性剤です。
これらは髪を滑らかにする効果が高い反面、頭皮に付着すると毛穴に固着しやすく、シャンプー後の残留リスクが高まります。
また、アルコール(エタノールなど)が高濃度で含まれている製品は、頭皮の乾燥を招き、バリア機能を低下させる恐れがあるため、避けた方が無難です。
頭皮に優しいノンシリコンや天然由来成分の選択
薄毛が気になる方は、可能であればノンシリコンのトリートメントを選択肢に入れてください。シリコン自体は悪者ではありませんが、水に溶けにくく、頭皮に残留した場合の毛穴詰まりリスクを避けるためです。
また、アミノ酸系や天然由来のオイル(ホホバオイル、アルガンオイルなど)を主成分とした製品は、比較的刺激が少なく、万が一頭皮に付着しても洗浄しやすい性質を持っています。
ただし、ノンシリコンでも油分は含まれているため、頭皮への塗布を避けるという使用ルールは守る必要があります。
製品パッケージの裏側をチェックし、シンプルな成分構成で、頭皮に負担をかけにくいものを選ぶことが大切です。
保湿成分と頭皮ケア成分のバランス
トリートメントを選ぶ際は、単に髪を補修する成分だけでなく、保湿成分と頭皮ケア成分がバランス良く配合されているかを確認してください。
薄毛対策において、頭皮の乾燥を防ぐための保湿は非常に重要です。グリセリン、ヒアルロン酸、セラミドなどの保湿成分は、頭皮の水分量を保ち、バリア機能をサポートします。
また、血行促進効果が期待できる天然エキス(センブリエキス、オタネニンジン根エキスなど)が配合されている製品を選ぶことで、髪への栄養供給を間接的にサポートできます。
トリートメントは髪のケアが主目的ですが、頭皮を健やかに保つための間接的なサポートも期待できる製品を選びましょう。
薄毛対策のためのトリートメント選びの着眼点
- 水に溶けにくい油分が多く含まれていないか
- 可能な限りノンシリコン製品を選択する
- 保湿成分や天然の頭皮ケア成分が配合されているか
薄毛対策で注目したい成分
| 分類 | 成分例 | 期待できる作用 |
|---|---|---|
| 保湿成分 | セラミド、ヒアルロン酸 | 頭皮のバリア機能をサポート |
| 天然オイル | ホホバオイル、アルガンオイル | 刺激が少なく、髪をしなやかに |
| 天然エキス | センブリエキス、オタネニンジンエキス | 血行促進のサポート(間接的な効果) |
健康な髪と頭皮を保つための生活習慣とホームケア
食事・睡眠・運動が髪の毛に与える影響
トリートメントの使い方を改善しても、土台となる身体が不健康であれば、薄毛の進行は止められません。健康な髪の毛は、あなたが摂取する栄養素から作られています。
特に、髪の主成分であるタンパク質、その合成を助ける亜鉛、頭皮の健康を保つビタミンB群をバランス良く摂取することが大切です。
また、質の高い睡眠は、成長ホルモンの分泌を促し、毛母細胞の活発な分裂をサポートします。最低でも6〜7時間の深い睡眠を確保してください。
適度な運動は、全身の血行を改善し、頭皮にまで栄養を行き渡らせる助けとなります。日常生活の中にこれらの健康的な習慣を取り入れることが、薄毛対策の根幹となります。
ストレスと血行不良が招く薄毛
過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させ、頭皮の血行不良を招きます。
髪の毛は血液から栄養を受け取っているため、血行が悪くなると栄養不足に陥り、細く弱々しい毛になってしまいます。
日々の生活の中でストレスを溜め込まないように、リラックスできる時間を作り、趣味や運動などで気分転換を図ることが大切です。
また、頭皮マッサージは、物理的に血行を促進する手軽で有効なホームケアです。指の腹で頭皮を優しく揉みほぐし、硬くなった頭皮を柔軟に保つことを心がけてください。
育毛剤の効果を最大限に引き出すための土台作り
トリートメントの正しい使い方と健康な生活習慣は、あなたが使用する育毛剤の効果を最大限に引き出すための強固な土台を作ります。
正しいすすぎで毛穴詰まりを防ぎ、清潔な頭皮環境を保つことで、育毛剤の有効成分が毛根までスムーズに浸透します。
また、食事や睡眠で体内の栄養状態を整え、血行を促進することで、育毛剤によって活性化された毛母細胞が、実際に太くて強い髪の毛を作り出すための十分なエネルギーを受け取れるようになります。
トリートメントの正しい使用と生活習慣の改善は、育毛剤を単なる「補助」ではなく「主役」として機能させるための重要な役割を担います。
髪の健康を支える栄養素と食材
| 栄養素 | 髪への作用 | 主な食材 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分、ケラチンの原料 | 肉類、魚介類、大豆製品 |
| 亜鉛 | タンパク質合成のサポート | 牡蠣、レバー、ナッツ類 |
| ビタミンB群 | 代謝を助け、頭皮の健康維持 | 卵、乳製品、緑黄色野菜 |
薄毛を加速させる習慣に戻る
質疑応答
- トリートメントをつけたままお風呂に長く浸かると薄毛になりますか?
-
トリートメントをつけたまま長時間お風呂に浸かるのは避けてください。
体温や浴室の温度でトリートメントの油分が溶け出しやすくなり、それが頭皮に流れ落ちて毛穴を塞ぐリスクが高まります。
毛穴詰まりから炎症を引き起こす可能性があるため、放置時間は製品の指示に従い、長くても5分程度に留め、その後すぐに完璧に洗い流すことが大切です。
- トリートメントとコンディショナーの違いは何ですか?薄毛対策としてはどちらが良いですか?
-
コンディショナーは髪の表面をコーティングして手触りを良くする「保護」が主な役割です。一方、トリートメントは髪の内部にまで浸透し、傷んだ部分を補修する「補修」が主な役割です。
薄毛対策という観点では、どちらも頭皮に付着すると毛穴詰まりのリスクがありますので、使い方を正しく守ることが重要です。
髪のダメージが少ない方はコンディショナーで十分ですが、ダメージが気になる方は補修力の高いトリートメントを毛先中心に使用してください。
- すすぎ残しがあると、髪の毛が細くなるのは本当ですか?
-
直接的に髪の毛が細くなるわけではありませんが、すすぎ残しによる頭皮の炎症や毛穴の詰まりが、結果として髪の成長を妨げ、細く弱々しい髪しか生えてこなくなる原因を作ります。
毛穴が健康な状態でないと、髪を太く成長させるための栄養や酸素が十分に届かなくなってしまうため、間接的に薄毛を進行させることになります。
- 男性でも毎日トリートメントを使う必要はありますか?
-
男性でも、パーマやカラーリングなどで髪がダメージを受けている場合や、乾燥によるパサつきが気になる場合は、毎日使用することをおすすめします。
ただし、髪が健康で特にダメージがない場合は、毎日ではなく、週に2〜3回のスペシャルケアとして使うだけでも十分です。
重要なのは頻度よりも、正しい使い方を徹底し、頭皮に残留させないことです。
- トリートメントを使う際に、お湯の温度は何度くらいが良いですか?
-
熱すぎるお湯は頭皮の皮脂を過剰に洗い流し、乾燥や炎症を引き起こす原因となります。
トリートメントを洗い流す際も含め、洗髪時の理想的なお湯の温度は、体温より少し温かい程度の38度から40度くらいが適切です。
この温度は、皮脂を効果的に溶かしながらも、頭皮に過度な刺激を与えない優しい温度です。
トリートメントとコンディショナーの違い
項目 トリートメント コンディショナー 主な目的 毛髪の内部補修 毛髪の表面保護 効果の持続性 比較的長い 一時的 毛穴詰まりリスク すすぎ残すと高い すすぎ残すと高い
Reference
WOLFF, Hans; FISCHER, Tobias W.; BLUME-PEYTAVI, Ulrike. The diagnosis and treatment of hair and scalp diseases. Deutsches Ärzteblatt International, 2016, 113.21: 377.
ALESSANDRINI, A., et al. Common causes of hair loss–clinical manifestations, trichoscopy and therapy. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2021, 35.3: 629-640.
FUNG, Ernest S.; PARKER, Jillian A.; MONNOT, Andrew D. Evaluating the impact of hair care product exposure on hair follicle and scalp health. Alternatives to Laboratory Animals, 2023, 51.5: 323-334.
WARSHAW, Erin M., et al. Tolerability of hair cleansing conditioners: a double-blind randomized, controlled trial designed to evaluate consumer complaints to the US Food and Drug Administration. Cutaneous and Ocular Toxicology, 2020, 39.2: 89-96.
GRAHAM, Shaveonté, et al. Differential diagnosis of posterior scalp hair loss. Archives of Dermatological Research, 2024, 316.10: 738.
SATAPATHY, Trilochan, et al. Impact of conventional and advanced therapies in functional hair follicular regeneration in pesticide-induced hair loss: a Pharmacological perspective of review. Journal of Drug Delivery & Therapeutics, 2025, 15.7.
SPERLING, Leonard C. Evaluation of hair loss. Current problems in Dermatology, 1996, 8.3: 99-136.
JIA, Lingling, et al. Alopecia Induced by Cosmetic Injection Procedures: A Comprehensive Review. Aesthetic Plastic Surgery, 2025, 1-14.
CAMACHO-MARTINEZ, Francisco M. Hair loss in women. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 19-32.
PULUMATI, Anika, et al. Fillers impacting follicles: the emerging complication of filler‐induced alopecia. International journal of dermatology, 2024, 63.9: 1131-1139.