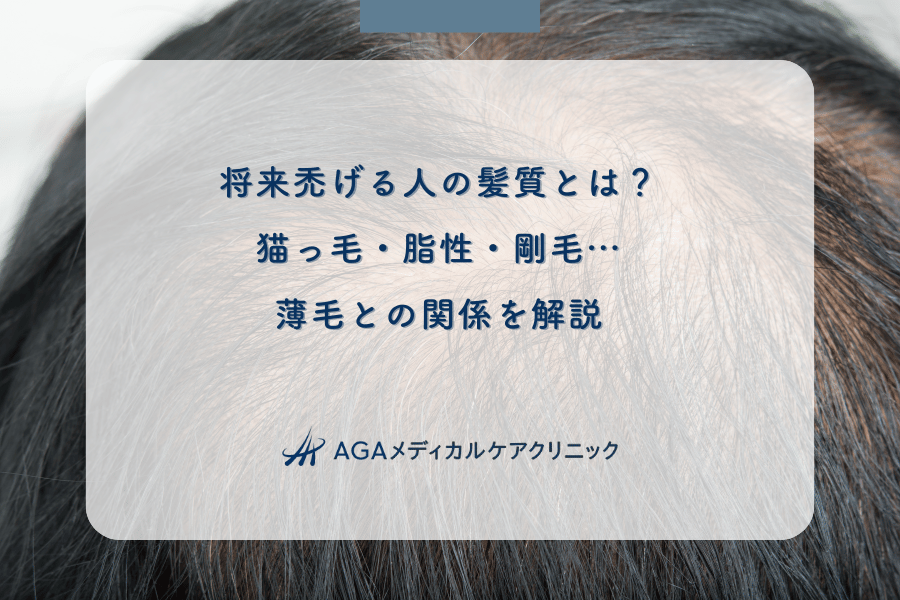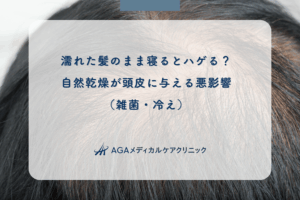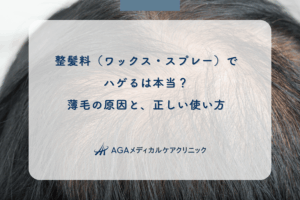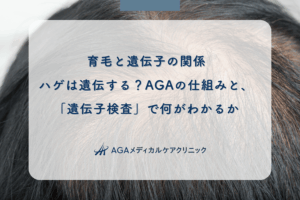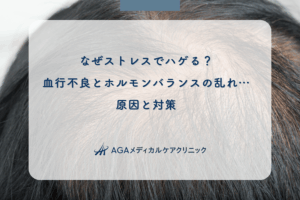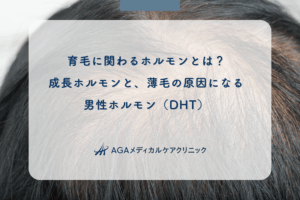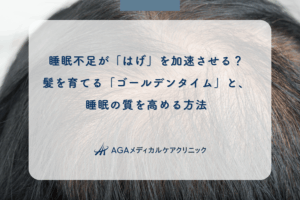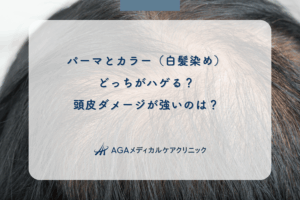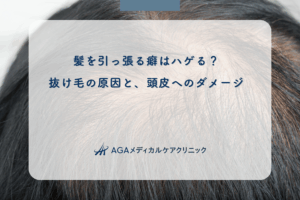「自分の髪質は将来禿げるのでは?」と不安に感じていませんか。猫っ毛や脂性、剛毛など、特定の髪質が薄毛に直結するのか気になりますよね。
この記事では、将来禿げる可能性のある人の髪質と薄毛の本当の関係性を深掘りします。髪質そのものが直接の原因でなくても、頭皮環境や生活習慣がどのように影響するかを解説。
あなたの疑問を解消し、今からできる頭皮ケアのヒントを得ることで、健やかな髪を維持するための一歩を踏み出せます。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
「将来禿げる人の髪質」は存在する?薄毛との誤解と真実
髪質(猫っ毛・剛毛)は薄毛の直接原因ではない
まず結論から言うと、「猫っ毛だから禿げる」「剛毛だから大丈夫」といったように、生まれ持った髪質が薄毛の直接的な原因になることはありません。
薄毛、特に男性型脱毛症(AGA)の主な原因は、遺伝的要因や男性ホルモンの影響によるものです。
髪の太さや硬さ、くせの有無は、毛穴の形状や髪内部のタンパク質構造によって決まるものであり、AGAの発症とは別の問題です。
ただし、髪質によっては薄毛が目立ちやすかったり、特定の頭皮トラブルを引き起こしやすかったりすることはあります。
例えば、猫っ毛で髪が細い人は、同じ本数でも地肌が透けやすく、薄毛に見えやすい傾向があります。しかし、それは「薄毛に見えやすい」だけであり、「薄毛になりやすい」とはイコールではありません。
本当に注意すべきは「頭皮環境」の変化
髪質そのものよりも、将来の薄毛リスクを考える上で遥かに重要なのは「頭皮環境」です。髪は頭皮という土壌から生えています。
この土壌の状態が悪ければ、どれほど丈夫な髪質であっても健やかに育つことはできません。
例えば、過剰な皮脂分泌、乾燥、フケ、かゆみ、炎症、血行不良などは、すべて頭皮環境の悪化を示すサインです。
これらの状態が続くと、毛根に十分な栄養が届かなくなったり、毛穴が詰まって炎症を起こしたりして、抜け毛が増加し、新しい髪が生えにくくなる可能性があります。
将来禿げるリスクを考えるなら、生まれつきの髪質を気にするよりも、現在の頭皮環境を良好に保つことが大切です。
髪質と薄毛リスクの一般的な誤解
| 髪質の特徴 | よくある誤解 | 実際のところ |
|---|---|---|
| 猫っ毛(細い・柔らかい) | 髪が弱いから禿げやすい | 薄毛に見えやすいだけで、直接の原因ではない |
| 剛毛(太い・硬い) | 髪が丈夫だから禿げない | AGAは髪質に関係なく発症する |
| 脂性(オイリー) | 毛穴が詰まって禿げる | 皮脂自体ではなく、皮脂による炎症が問題 |
遺伝(AGA)が薄毛に与える影響
男性の薄毛の大部分を占めるのがAGA(男性型脱毛症)です。
これは、男性ホルモンの一種であるテストステロンが、5αリダクターゼという酵素の働きによってジヒドロテストステロン(DHT)に変換され、このDHTが毛乳頭細胞にある受容体と結合することで発症します。
この5αリダクターゼの活性度や、受容体の感受性の強さは、遺伝によって大きく左右されます。特に母方の祖父が薄毛の場合、その遺伝的素因を受け継いでいる可能性が高いと言われています。
髪質がどうであれ、この遺伝的素因を持っている場合、将来的に薄毛が進行するリスクは高まります。
AGAは進行性の脱毛症であり、髪質に関係なく毛髪のサイクル(ヘアサイクル)が乱れ、髪が細く短くなっていく(軟毛化)のが特徴です。
髪質よりも生活習慣が重要
遺伝的素因が大きな要因である一方、薄毛の進行速度や頭皮環境の状態は、日々の生活習慣によっても大きく変わります。髪質を今から変えることは困難ですが、生活習慣は今日からでも改善できます。
睡眠不足、栄養バランスの偏った食事、過度なストレス、喫煙、運動不足などは、すべて頭皮の血行不良やホルモンバランスの乱れを引き起こし、頭皮環境を悪化させる要因となります。
例えば、脂っこい食事ばかりしていると皮脂の分泌が過剰になり、脂性の頭皮環境を助長します。将来の髪を守るためには、自分の髪質を嘆くよりも、まずは日々の生活を見直すことが重要です。
猫っ毛(軟毛)と薄毛の関係性
猫っ毛の特徴とボリュームが出にくい理由
猫っ毛(軟毛)とは、髪の毛一本一本が細く、柔らかい髪質を指します。キューティクルの層が薄かったり、内部のコルテックスの密度が低かったりすることが特徴です。
髪にハリやコシが出にくいため、全体的にボリュームダウンして見えがちです。
髪が細いと、重力や湿気の影響を受けやすく、ペタッとなりやすいのです。朝にスタイリングしても、時間が経つと髪が寝てしまい、地肌が目立ちやすくなることに悩む人も少なくありません。
髪が細いと地肌が透けやすい
猫っ毛の人が「将来禿げるのでは?」と不安に感じやすい最大の理由は、地肌が透けて見えやすい点にあります。髪の毛の本数が同じでも、一本一本が細いために頭皮を覆う面積が小さくなり、光が地肌まで届きやすくなります。
特に、髪が濡れた時や汗をかいた時は、細い髪同士が束になりやすく、さらに地肌の露出が目立ってしまいます。
これは薄毛が進行しているわけではなく、あくまで髪質による「見え方」の問題であることが多いのです。
しかし、この「薄く見える」状態がコンプレックスとなり、過度なヘアケアやストレスにつながる場合もあります。
猫っ毛の人が注意すべき頭皮ケア
猫っ毛の人は、髪が細くデリケートであるため、外部からのダメージを受けやすい傾向があります。
また、ボリュームを出そうとしてスタイリング剤を多用したり、洗浄力の強すぎるシャンプーを使いすぎたりすると、かえって頭皮環境を悪化させる可能性があります。
大切なのは、頭皮を優しく洗い上げることです。アミノ酸系などのマイルドな洗浄成分のシャンプーを選び、指の腹で頭皮をマッサージするように洗いましょう。
また、髪のダメージを補修し、ハリやコシを与えるタイプのトリートメントやコンディショナーを毛先中心に使用し、頭皮には残らないようにしっかりすすぐことが重要です。
頭皮の血行を促進する頭皮マッサージも、健やかな髪を育むために有効です。
軟毛化はAGAのサインかもしれない
生まれつきの猫っ毛(軟毛)と、AGAの進行によって髪が細くなる「軟毛化」は異なります。
もし、以前はしっかりとした太さの髪だったのに、最近になって生え際や頭頂部の髪が細く、柔らかく、色も薄くなってきたと感じる場合、それはAGAが進行しているサインかもしれません。
AGAによる軟毛化は、ヘアサイクルが短縮し、髪が十分に成長しきる前に抜け落ちてしまうために起こります。「もともと猫っ毛だから」と思い込まず、以前の髪質との違いや、抜け毛の質(細く短い毛が増えていないか)を注意深く観察することが大切です。
脂性(オイリー)な頭皮・髪質と薄毛リスク
なぜ頭皮は脂っぽくなるのか
頭皮が脂っぽくなる(脂性)のは、皮脂腺から分泌される皮脂が過剰になるためです。皮脂は本来、頭皮を乾燥や外部刺激から守るために必要なバリア機能の役割を担っています。
しかし、様々な要因によってそのバランスが崩れると、過剰に分泌されてしまいます。
主な原因としては、ホルモンバランスの影響(特に男性ホルモン)、脂質や糖質の多い食事、ビタミンB群の不足、ストレス、間違ったヘアケア(洗いすぎによる乾燥の反動など)、遺伝的体質などが挙げられます。
過剰な皮脂が引き起こす頭皮トラブル
過剰に分泌された皮脂は、頭皮の常在菌であるマラセチア菌の餌となります。マラセチア菌は皮脂を分解する過程で遊離脂肪酸を排出し、これが頭皮を刺激して炎症やかゆみを引き起こします。
この状態が悪化したものが「脂漏性皮膚炎」です。
脂漏性皮膚炎になると、頭皮が赤くなり、ベタベタとした大きめのフケが出るようになります。また、過剰な皮脂や古い角質が毛穴に詰まる(角栓)と、髪の健やかな成長を妨げたり、炎症を悪化させたりします。
こうした頭皮環境の悪化が長期間続くと、毛根がダメージを受け、抜け毛が増加する「脂漏性脱毛症」につながるリスクがあります。
脂性頭皮の原因とセルフケア
| 主な原因 | セルフケアのポイント | 補足 |
|---|---|---|
| 食生活の乱れ | 脂質・糖質を控え、ビタミンB群を摂取する | レバー、うなぎ、納豆、卵などがおすすめ |
| 間違ったシャンプー | 1日1回、夜に正しく洗う。すすぎを丁寧に | 洗いすぎは逆効果になることも |
| ストレス・睡眠不足 | リラックスできる時間を作り、質の良い睡眠を確保する | 自律神経やホルモンバランスを整える |
脂性肌の人が実践すべきシャンプー方法
脂性の頭皮を持つ人は、皮脂をしっかり落とそうとして、1日に何度もシャンプーしたり、爪を立ててゴシゴシ洗ったりしがちです。しかし、これは必要な皮脂まで奪い去り、頭皮の乾燥を招きます。
頭皮が乾燥すると、かえって皮脂の分泌を促してしまう「過乾燥」の状態に陥るため逆効果です。
シャンプーは1日1回、夜に行うのが基本です。洗う前にお湯でしっかり予洗い(湯シャン)し、汚れの大部分を落とします。
シャンプーは手のひらでよく泡立ててから、指の腹を使って頭皮をマッサージするように優しく洗いましょう。最も重要なのは「すすぎ」です。
シャンプー剤や汚れが残らないよう、時間をかけて丁寧に洗い流してください。
食生活と皮脂分泌の関連性
皮脂の分泌量は、日々の食事内容に大きく影響されます。特に、動物性脂肪(肉の脂身、バターなど)や糖質(甘いもの、炭水化物)の過剰摂取は、皮脂腺の働きを活発にし、皮脂の分泌を増加させます。
一方で、皮脂の分泌をコントロールする働きを持つビタミンB2やB6が不足すると、脂性肌に傾きやすくなります。
これらの栄養素は、レバー、うなぎ、マグロ、カツオ、納豆、卵、バナナなどに多く含まれています。
将来の頭皮環境を考えるなら、揚げ物やラーメン、スイーツなどを控え、バランスの取れた食事を心がけることが重要です。
剛毛(硬毛)と薄毛の関係性
剛毛の人が薄毛になりにくいという誤解
「髪が太くて硬い(剛毛)から、自分は薄毛とは無縁だ」と考える人は少なくありません。
確かに、一本一本がしっかりしているため、猫っ毛の人に比べて地肌が目立ちにくく、薄毛を自覚しにくい傾向はあります。
しかし、これは大きな誤解です。前述の通り、AGA(男性型脱毛症)は髪質に関係なく、遺伝的素因と男性ホルモンの影響によって発症します。
剛毛の人であっても、AGAの素因を持っていれば、ヘアサイクルが乱れ、髪は徐々に細く(軟毛化)、短くなっていきます。剛毛であることは、AGAに対する「保険」にはなりません。
髪が太くても油断できない頭皮の健康
剛毛の人は、髪が丈夫な反面、頭皮への意識が向きにくいことがあります。髪が硬いために、シャンプーの際に頭皮まで指が届きにくく、皮脂や汚れが十分に落としきれていないケースも見受けられます。
また、髪が太いために頭皮が蒸れやすく、雑菌が繁殖しやすい環境になることもあります。剛毛であっても、頭皮が脂っぽかったり、フケやかゆみがあったりする場合は、頭皮環境が悪化しているサインです。
髪の太さにあぐらをかかず、頭皮の状態を清潔に保つ努力が必要です。
剛毛の人が避けたいヘアケア
- 洗浄力が強すぎるシャンプーの連用
- 頭皮を傷つけるようなゴシゴシ洗い
- すすぎ残し
- ドライヤーの熱の当てすぎ
剛毛の人が気をつけたいヘアケアの間違い
剛毛の人は、髪が硬く広がりやすいため、スタイリング剤を多用したり、洗浄力の強いシャンプーでごっそり皮脂を落としたりする傾向があります。
しかし、強い洗浄成分は頭皮に必要な潤いまで奪い、乾燥やフケの原因となります。
また、髪が乾きにくいからといってドライヤーの熱を長時間当てすぎると、頭皮が乾燥し、髪もダメージを受けます。
シャンプーは頭皮を優しく洗い、スタイリング剤を使った日は特に丁寧にすすぐことが大切です。ドライヤーは頭皮から20cm以上離し、一箇所に集中しないように動かしながら乾かしましょう。
急に髪質が硬くなった場合の注意点
通常、加齢やAGAの進行に伴い、髪は細く柔らかくなる(軟毛化)傾向があります。もし、急に髪がゴワゴワしたり、硬くなったりした場合は、薄毛とは別の要因が考えられます。
最も一般的なのは、髪のダメージです。カラーリングやパーマ、紫外線の影響で髪のキューティクルが剥がれ、内部の水分が失われると、髪は硬くゴワついた手触りになります。
また、頭皮の血行不良や栄養不足によって、健康な髪が作られなくなっている可能性もあります。髪質の「悪い変化」は、頭皮や体からのSOSサインと捉え、ヘアケアや生活習慣を見直すきっかけにしましょう。
くせ毛(天然パーマ)は薄毛と関係があるか
くせ毛の構造と薄毛の関連は薄い
くせ毛(天然パーマ)は、毛根の形状が曲がっていたり、髪内部のタンパク質繊維のバランスが不均一だったりすることによって、髪が波打ったり縮れたりする状態を指します。
これも生まれつきの髪質の一つであり、直毛の人と比べて薄毛になりやすい、またはなりにくいといった直接的な科学的根拠はありません。
くせ毛の人も、直毛の人と同様にAGAを発症するリスクはあります。薄毛との関連性は、髪の形状そのものにはないと考えてよいでしょう。
くせ毛によるスタイリングの悩みと頭皮への負担
くせ毛の人は、髪がまとまりにくく、スタイルが決まりにくいため、スタイリング剤(ワックス、ジェル、スプレーなど)を多用する傾向があります。
これらのスタイリング剤が頭皮に付着し、シャンプーで十分に落としきれないと、毛穴の詰まりや炎症の原因となり、頭皮環境を悪化させる可能性があります。
また、くせを伸ばすためにヘアアイロンを高温で長時間使用することも、髪と頭皮に大きな負担をかけます。熱による頭皮の乾燥や、髪のタンパク質変性は、健やかな髪の成長を妨げる要因となります。
くせ毛の人が受けるダメージ要因
| 要因 | 髪・頭皮への影響 | 対策 |
|---|---|---|
| スタイリング剤の多用 | 毛穴詰まり、頭皮の炎症 | 頭皮につけないように使い、丁寧に洗う |
| ヘアアイロンの高温使用 | 髪のタンパク質変性、頭皮の乾燥 | 温度を下げ、短時間で使用する |
| 縮毛矯正 | 薬剤による化学的ダメージ、頭皮への刺激 | 頻度を減らす、頭皮に優しい施術を選ぶ |
縮毛矯正やパーマが与えるダメージ
くせ毛をコンプレックスに感じ、定期的に縮毛矯正やストレートパーマをかける人も多いです。
これらの施術は、薬剤(アルカリ剤や還元剤)を使って髪の内部構造を一度切断し、熱やロッドで形状を変えた後に再結合させるものです。
この過程は、髪に大きな化学的ダメージを与えます。薬剤が頭皮に付着すれば、強い刺激となり、炎症やアレルギー反応を引き起こすこともあります。
施術の頻度が高すぎたり、頭皮の状態が悪い時に無理に行ったりすると、頭皮環境が悪化し、抜け毛の一因となる可能性は否定できません。
くせ毛の人が意識したい頭皮の保湿
くせ毛の髪は、一般的に直毛の髪に比べて水分が蒸発しやすく、乾燥しやすい傾向があります。髪が乾燥すると、パサつきや広がりがひどくなるため、トリートメントなどで油分を補いがちです。
しかし、髪だけでなく頭皮の保湿も重要です。頭皮が乾燥すると、フケやかゆみが出やすくなるだけでなく、バリア機能が低下して外部からの刺激に弱くなります。
シャンプー後は、保湿成分(セラミド、ヒアルロン酸など)が配合された頭皮用のローションやエッセンスを使用して、頭皮の潤いを保つことを意識しましょう。
将来の薄毛リスクを高める頭皮環境とは
乾燥した頭皮(フケ・かゆみ)
将来の薄毛リスクを考える上で、頭皮の乾燥は大きな危険信号です。頭皮が乾燥すると、角質層のバリア機能が低下し、外部からのわずかな刺激にも敏感に反応してしまいます。
その結果、かゆみが生じ、無意識にかきむしることで頭皮が傷つき、炎症が悪化します。
また、乾燥によって頭皮のターンオーバー(生まれ変わり)が乱れると、剥がれ落ちた角質が「乾燥性のフケ(カサカサした細かいフケ)」として目立つようになります。
乾燥した硬い頭皮は、健康な髪が育つための土壌として不適切です。
頭皮の赤みや炎症
健康な頭皮は青白い色をしていますが、何らかのトラブルを抱えていると赤みを帯びてきます。頭皮の赤みは「炎症」が起きているサインです。
原因は様々で、前述の脂漏性皮膚炎や乾燥によるかゆみのほか、アレルギー、紫外線ダメージ、合わないヘアケア製品の使用などが考えられます。
炎症が起きている状態は、いわば頭皮が「火事」になっているようなものです。毛根が炎症によるダメージを受け続けると、髪の成長が妨げられ、抜け毛(脱毛)につながります。
頭皮環境悪化のサイン
| サイン | 主な状態 | 考えられる原因 |
|---|---|---|
| 色 | 赤い、ピンク色、茶色っぽい | 炎症、血行不良、紫外線ダメージ |
| フケ | ベタベタした大きなフケ、カサカサした細かいフケ | 脂漏性皮膚炎、乾燥、ターンオーバーの乱れ |
| 感覚 | かゆみ、ヒリヒリ感、つっぱり感 | 乾燥、炎症、アレルギー、洗いすぎ |
| 硬さ | 頭皮が硬く、指で動かない | 血行不良、ストレス、眼精疲労 |
頭皮が硬い状態(血行不良)
頭皮の健康状態は、その「硬さ」にも現れます。理想的な頭皮は、適度な弾力があり、指で動かすと柔らかく動きます。
しかし、頭皮がパンパンに張っていたり、指で押してもほとんど動かなかったりする場合は、血行不良に陥っている可能性が高いです。
髪の毛は、毛乳頭にある毛細血管から栄養を受け取って成長します。頭皮の血行が悪くなると、毛根に十分な酸素や栄養素が届かなくなり、髪が細くなったり、成長が止まって抜け落ちたりします。
長時間のデスクワークによる肩こり、眼精疲労、ストレスなどは、頭部の筋肉を緊張させ、血行不良を招く主な原因です。
頭皮環境を悪化させるNG習慣
髪質に関わらず、日々の何気ない習慣が頭皮環境を悪化させ、将来の薄毛リスクを高めていることがあります。
例えば、熱すぎるお湯でのシャンプーは、頭皮に必要な皮脂まで奪い去り、乾燥を招きます。
逆に、髪を洗った後に乾かさず、濡れたまま寝てしまうと、頭皮で雑菌が繁殖しやすくなり、かゆみやニオイの原因となります。
また、紫外線を無防備に浴びることも、頭皮に炎症や乾燥ダメージを与え、毛母細胞の働きを低下させます。心当たりのある習慣は、今日からでも見直すことが重要です。
髪質に関わらず行いたい将来のための頭皮ケア
正しいシャンプーの選び方と洗い方
将来の髪を守るためのヘアケアの基本は、毎日のシャンプーです。自分の頭皮タイプに合ったシャンプーを選びましょう。
脂性肌の人は、皮脂を適度に取り除きつつも、刺激の少ないもの(アミノ酸系洗浄成分に、一部高級アルコール系を組み合わせたものなど)を。
乾燥肌・敏感肌の人は、保湿成分が配合されたアミノ酸系やベタイン系のマイルドなシャンプーが適しています。
洗い方は、まずお湯で十分に予洗いをし、シャンプーを泡立ててから指の腹で頭皮をマッサージするように洗います。爪を立てるのは厳禁です。
そして、すすぎ残しがないように、洗った時間の倍以上の時間をかけて丁寧に洗い流しましょう。
髪に良いとされる栄養素
- タンパク質(髪の主成分)
- 亜鉛(タンパク質の合成を助ける)
- ビタミンB群(頭皮環境・代謝を整える)
- ビタミンC・E(血行促進・抗酸化)
頭皮マッサージによる血行促進
頭皮環境を良好に保つためには、頭皮の血行を促進することが非常に大切です。血流が良くなれば、毛根に必要な栄養素が行き渡りやすくなります。
最も手軽な方法は、シャンプーの際や、お風呂上がりなどのリラックスした時間に行う頭皮マッサージです。
両手の指の腹を頭皮に密着させ、頭皮全体を動かすイメージで、下から上へ、円を描くように優しく揉みほぐします。気持ち良いと感じる程度の強さで行い、爪を立てて頭皮を傷つけないように注意しましょう。
髪質・頭皮タイプ別シャンプー選びのポイント
| タイプ | 特徴 | おすすめの洗浄成分 |
|---|---|---|
| 脂性肌・剛毛 | 皮脂が多い、髪が硬い | アミノ酸系+高級アルコール系(適度な洗浄力) |
| 乾燥肌・猫っ毛 | 頭皮がカサつく、髪が細い | アミノ酸系、ベタイン系(マイルド・保湿) |
| 敏感肌・くせ毛 | 刺激に弱い、髪が広がりやすい | アミノ酸系(低刺激)、保湿成分配合 |
バランスの取れた食事と髪に必要な栄養素
髪の毛は、私たちが食べたものから作られています。健やかな髪を育てるためには、特定の食品だけを食べるのではなく、バランスの取れた食事が重要です。
髪の主成分である「タンパク質」(肉、魚、卵、大豆製品)、タンパク質の合成を助ける「亜鉛」(牡蠣、レバー、牛肉)、頭皮の代謝を整える「ビタミンB群」(豚肉、マグロ、納豆)は特に重要です。
また、血行を良くする「ビタミンE」(ナッツ類、アボカド)や、コラーゲンの生成を助ける「ビタミンC」(野菜、果物)も積極的に摂取しましょう。
質の高い睡眠とストレス管理
髪の成長には「成長ホルモン」が深く関わっています。成長ホルモンは、主に私たちが眠っている間、特に夜10時から深夜2時のゴールデンタイムと呼ばれる時間帯に多く分泌されます。
睡眠不足が続くと、成長ホルモンの分泌が減少し、髪の成長や頭皮の修復が十分に行われません。毎日6〜7時間程度の質の高い睡眠を確保するよう努めましょう。
また、過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させて頭皮の血行不良を引き起こします。
自分なりのリフレッシュ方法を見つけ、ストレスを溜め込まないことも、将来の髪を守るために大切なことです。
薄毛と遺伝子に戻る
FAQ
- 父親や祖父が薄毛だと自分も必ず禿げますか?
-
遺伝的素因が薄毛(特にAGA)の大きな要因であることは事実です。特に母方の家系に薄毛の人がいる場合、その素因を受け継いでいる可能性は高まります。
しかし、遺伝的素因があるからといって「必ず」薄毛になるわけではありませんし、発症する年齢や進行度には個人差があります。
生活習慣やヘアケア次第で、進行を遅らせたり、頭皮環境を良好に保ったりすることは可能です。
- 毎日シャンプーすると禿げやすくなりますか?
-
「シャンプーで髪が抜ける」のではなく、「寿命が来た髪がシャンプーの際に抜け落ちている」だけです。健康な人でも1日に50本から100本程度の髪は自然に抜けます。
むしろ、皮脂や汚れを放置する方が頭皮環境に悪影響です。
ただし、洗浄力が強すぎるシャンプーを使ったり、1日に何度も洗ったりすると、頭皮が乾燥してトラブルの原因になるため、1日1回、自分に合ったシャンプーで優しく洗うのが適切です。
- 育毛剤はいつから使い始めるべきですか?
-
育毛剤(医薬部外品)は、主に「今ある髪を健康に育てる」「抜け毛を防ぐ」ことを目的としており、頭皮環境を整える成分が含まれています。
将来の薄毛予防として、抜け毛が増えてきた、髪にハリがなくなってきた、頭皮が硬いなど、何らかのサインを感じ始めた段階で使用するのは良い選択です。
明確な「何歳から」という基準はなく、ご自身の頭皮の状態や不安に応じて検討するのがよいでしょう。
- 髪質は年齢と共に変わりますか?
-
はい、変わります。年齢を重ねると、髪の毛を作る毛母細胞の働きが低下したり、頭皮の血行が悪くなったりします。
そのため、若い頃は剛毛だった人でも、徐々に髪が細く、柔らかく(軟毛化)なるのが一般的です。
また、髪の水分量や油分も減少し、パサつきやすくなったり、うねりが出やすくなったりすることもあります。
Reference
FAGHIHKHORASANI, Amirhosein, et al. The Relationship between Seborrheic Dermatitis and Androgenetic Alopecia in Patients Referred to a Skin Clinic in Tehran, Iran: A Retrospective Study. Journal of Health Reports and Technology, 2024, 10.1.
OIWOH, Sebastine Oseghae, et al. Androgenetic alopecia: A review. Nigerian Postgraduate Medical Journal, 2024, 31.2: 85-92.
SUZUKI, Kazuhiro, et al. Scalp microbiome and sebum composition in Japanese male individuals with and without androgenetic alopecia. Microorganisms, 2021, 9.10: 2132.
TAMBUNAN, Regina Maharani; JUSUF, Nelva Karmila; PUTRA, Imam Budi. Correlation between sebum level and severity of male androgenetic alopecia. Bali Medical Journal, 2023, 12.2: 1578-1584.
KURE, Katsuhiro; ISAGO, Tsukasa; HIRAYAMA, Takeshi. Changes in the sebaceous gland in patients with male pattern hair loss (androgenic alopecia). Journal of Cosmetic Dermatology, 2015, 14.3: 178-184.
TRÜEB, Ralph M., et al. Scalp condition impacts hair growth and retention via oxidative stress. International journal of trichology, 2018, 10.6: 262-270.
MENTEŞOĞLU, Dilek; KURMUŞ, Gökçe Işıl; KARTAL, Selda Pelin. The Possible Bidirectional Relationship between Disease Severity in Androgenetic Alopecia and Seborrheic Dermatitis: A Cross-Sectional Study in a Tertiary Care Hospital. Indian Dermatology Online Journal, 2025, 16.4: 571-575.
CRANWELL, William; SINCLAIR, Rodney. Male androgenetic alopecia. 2015.
TRÜEB, Ralph M., et al. Th
e Hair and Scalp in Systemic Infectious Disease. In: Hair in Infectious Disease: Recognition, Treatment, and Prevention. Cham: Springer International Publishing, 2023. p. 303-365.
SINCLAIR, Rodney D.; DAWBER, Rodney PR. Androgenetic alopecia in men and women. Clinics in dermatology, 2001, 19.2: 167-178.