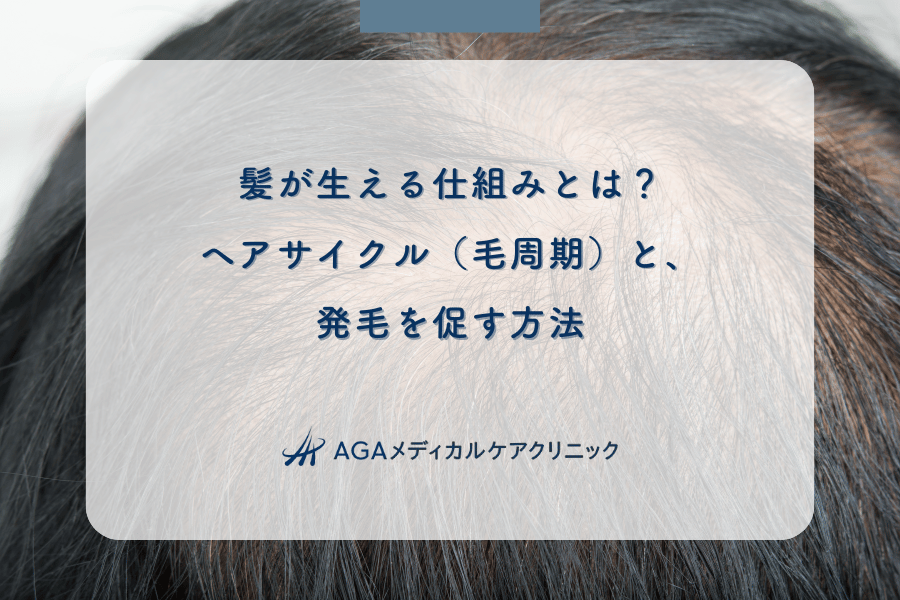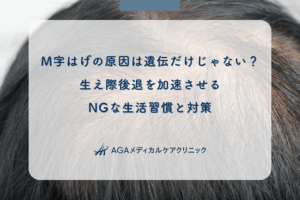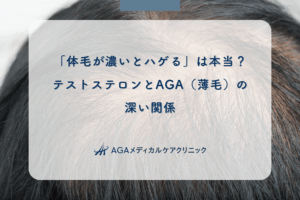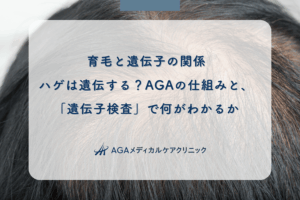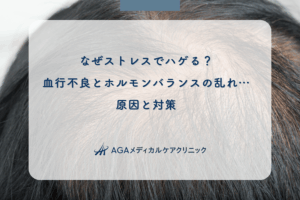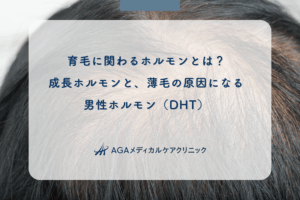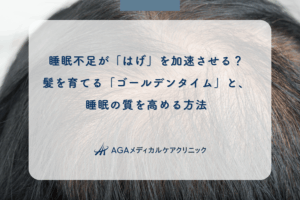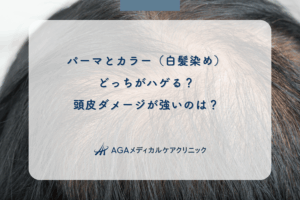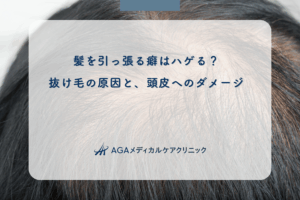「最近、髪のボリュームが減ってきた気がする」「どうすれば髪は生えてくるのだろう」と悩んでいる男性は多いかもしれません。
髪がどのようにして生え、成長し、そして抜け落ちていくのか。その基本的な仕組みである「ヘアサイクル(毛周期)」を理解することは、薄毛や抜け毛の悩みに向き合うための第一歩です。
この記事では、髪が生える仕組みを分かりやすく解説し、ヘアサイクルが乱れる原因、そして発毛を促すために日常生活でできる具体的な方法や育毛剤の役割について、詳しく掘り下げていきます。
ご自身の髪の状態を知り、前向きなヘアケアを始めるための情報としてお役立てください。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
そもそも「髪が生える」とはどういうことか
私たちが日常的に「髪が生える」と呼んでいる現象は、頭皮の下で起こる非常に精巧な生命活動の結果です。髪の毛は、単に皮膚から突き出ているだけのものではありません。
その根元には、髪を「製造する工場」とも言える重要な組織が存在します。この根本的な仕組みを知ることが、育毛を考える上で大切です。
まずは、髪の毛がどのような構造で、何からできており、どうやって生み出されるのかを見ていきましょう。
髪の毛の構造と成分
私たちが普段目にしている髪の毛は「毛幹(もうかん)」と呼ばれる部分です。これは、すでに細胞としては活動を終えた部分にあたります。毛幹の主な成分は「ケラチン」というタンパク質です。
このケラチンは、18種類のアミノ酸が結合してできており、髪の硬さや弾力を生み出しています。
毛幹の内部は、中心から「メデュラ(毛髄質)」「コルテックス(毛皮質)」「キューティクル(毛表皮)」という3層構造になっています。
コルテックスが髪の太さや色、柔軟性を決める大部分を占め、キューティクルがうろこ状に重なって内部を保護しています。
髪のツヤや手触りは、このキューティクルの状態に大きく左右されます。
髪を作り出す「毛母細胞」の役割
髪が生える上で最も重要な役割を担うのが、頭皮の内部にある「毛母細胞(もうぼさいぼう)」です。
毛根の最も深い部分にある「毛球(もうきゅう)」の中に、毛母細胞は存在します。この毛母細胞が、髪の毛の「製造工場」です。
毛母細胞は、毛細血管から運ばれてくる酸素や栄養素を受け取り、活発に細胞分裂を繰り返します。
分裂して増えた細胞が徐々に上へと押し上げられ、角化(かくか)して硬いケラチンタンパク質に変化し、やがて毛幹となって頭皮の上へと伸びていきます。
つまり、髪が生える、髪が伸びるという現象は、毛母細胞が分裂を続けることによって起こります。この毛母細胞の働きが弱まると、髪が細くなったり、成長が止まったりしてしまいます。
毛根を包む「毛包」の重要性
毛根全体は、「毛包(もうほう)」または「毛嚢(もうのう)」と呼ばれる組織に包まれています。毛包は、髪の毛を皮膚に固定し、成長を導く「さや」のような役割を果たします。
毛包の底部には、毛母細胞に栄養を届ける「毛乳頭(もうにゅうとう)」があります。
毛乳頭は、毛細血管とつながっており、毛母細胞に対して「髪を作れ」という指令を出す司令塔の役割も担います。
毛乳頭が毛細血管から栄養を受け取り、それを毛母細胞に供給し、成長シグナルを送ることで、髪の毛は健やかに成長します。毛包全体の健康状態、特に毛乳頭への血流が、発毛において非常に重要です。
毛包が何らかの原因でダメージを受けたり、血流が悪くなったりすると、毛母細胞の活動が鈍り、ヘアサイクルに異常が生じやすくなります。
髪の寿命を決める「ヘアサイクル(毛周期)」の全貌
髪の毛は、一度生えたらずっと伸び続けるわけではありません。一本一本の髪には寿命があり、「生える(成長期)」「成長が止まる(退行期)」「抜け落ちる(休止期)」というサイクルを繰り返しています。
これを「ヘアサイクル(毛周期)」と呼びます。健康な頭皮では、このサイクルが規則正しく繰り返されることで、一定の毛髪量が維持されます。
薄毛や抜け毛の悩みは、このヘアサイクルが乱れることと深く関係しています。ここでは、ヘアサイクルの各段階について詳しく解説します。
成長期 髪が太く長く伸びる期間
成長期は、毛母細胞が最も活発に分裂し、髪の毛が太く長く成長する期間です。ヘアサイクル全体の約85%~90%を占め、通常2年~6年ほど続きます。
この期間の長さが、髪がどれだけ長く伸びるかを決定します。成長期の髪は、毛根が深く、毛乳頭としっかり結びついており、毛細血管から豊富な栄養を受け取っています。
健康な髪を育むためには、この成長期をいかに長く維持するかが鍵となります。男性型脱毛症(AGA)などでは、この成長期が著しく短縮してしまうことが、薄毛の直接的な原因となります。
退行期 髪の成長が止まる期間
成長期が終わると、髪は退行期に入ります。これはヘアサイクル全体の約1%程度で、期間としては2~3週間ほどです。この段階に入ると、毛母細胞の分裂が急激に減少し、髪の毛の成長が停止します。
毛球部が縮小し始め、毛乳頭から離れていきます。髪の毛はまだ抜け落ちませんが、次の「休止期」への準備段階に入った状態です。
この期間は非常に短いため、頭部全体の毛髪に占める割合はごくわずかです。
休止期 髪が抜け落ちる準備期間
退行期を経て、髪は休止期に入ります。ヘアサイクル全体の約10%~15%を占め、期間は約3~4ヶ月です。この期間、毛母細胞の活動は完全に停止し、毛根は浅い位置まで上昇します。
毛包も縮小し、髪の毛は毛乳頭との結合を完全に失います。髪はただ頭皮にとどまっているだけの状態であり、シャンプーやブラッシングなどの軽い刺激で自然に抜け落ちていきます(これを自然脱毛と呼びます)。
そして、この休止期の毛穴の奥では、毛乳頭が再び活動の準備を始め、新しい毛母細胞が次の成長期に向けて待機しています。
休止期の髪が抜け落ちると、そこからまた新しい髪が生まれ、次の成長期がスタートします。
ヘアサイクルの各段階まとめ
| 段階 | 期間(目安) | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 成長期 | 2年~6年 | 毛母細胞が活発に分裂し、髪が太く長く成長する。 |
| 退行期 | 2~3週間 | 毛母細胞の分裂が停止し、髪の成長が止まる。 |
| 休止期 | 3~4ヶ月 | 髪が毛乳頭から離れ、自然に抜け落ちる準備状態になる。 |
ヘアサイクルと薄毛の関係
薄毛や抜け毛が進行する主な原因は、このヘアサイクルの「成長期」が短くなることです。
通常2年以上あるはずの成長期が、数ヶ月から1年程度に短縮すると、髪の毛は十分に太く、長く成長する前に退行期・休止期へと移行してしまいます。
その結果、細く短い髪の毛(うぶ毛のような髪)が増え、頭皮が透けて見えるようになります。
また、成長期が短くなる一方で休止期にとどまる髪の割合が増えるため、全体の毛髪数が減少し、抜け毛が増えたと感じるようになります。
ヘアサイクルを正常に保つことが、薄毛の予防と改善には非常に重要です。
なぜヘアサイクルは乱れるのか?薄毛・抜け毛の主な原因
健康な髪を維持するためには、ヘアサイクルが正常に機能している必要があります。しかし、さまざまな要因によってこのサイクルが乱れると、成長期が短縮し、薄毛や抜け毛が進行してしまいます。
特に男性の場合、特定のホルモンの影響が強く関わることが知られていますが、それ以外にも日常生活に潜む多くの原因が複雑に絡み合っています。
ご自身の生活習慣や体調と照らし合わせながら、主な原因を探っていきましょう。
男性ホルモンの影響 (AGA)
男性の薄毛の最も一般的な原因が、AGA(Androgenetic Alopecia)、すなわち「男性型脱毛症」です。
これは、男性ホルモンの一種である「テストステロン」が、毛根部に存在する「5αリダクターゼ」という酵素と結びつくことで、「ジヒドロテストステロン(DHT)」という強力な脱毛ホルモンに変換されることが引き金となります。
このDHTが、毛乳頭にある受容体(アンドロゲンレセプター)と結合すると、毛母細胞に対して「成長を止めろ」という誤ったシグナルを送ってしまいます。
その結果、まだ成長段階にある髪の毛の成長期が強制的に短縮され、髪が細く短いうちに抜け落ちてしまうのです。この感受性は遺伝的な要素が強いと考えられています。
生活習慣の乱れ 食事・睡眠・運動
髪の毛は、毛母細胞が血液から栄養を受け取って作られます。そのため、日々の生活習慣が髪の健康に直結します。
まず食事です。髪の主成分であるタンパク質(ケラチン)の摂取が不足すると、髪は細く弱くなります。
また、タンパク質を髪に変えるために必要な亜鉛や、頭皮の健康を保つビタミン類(特にビタミンB群、C、E)も大切です。
脂っこい食事やインスタント食品に偏ると、皮脂が過剰に分泌され、頭皮環境の悪化を招くこともあります。
次に睡眠です。髪の成長を促す「成長ホルモン」は、主に睡眠中に分泌されます。
特に午後10時から午前2時の「ゴールデンタイム」と呼ばれる時間帯(最近では入眠後最初の深い睡眠時が重要とも言われます)に質の高い睡眠をとることが、毛母細胞の修復と活性化に役立ちます。
睡眠不足は自律神経の乱れも引き起こし、血行不良の原因にもなります。
運動不足も血行不良を招く大きな要因です。デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続けていると、全身、特に頭部への血流が滞りがちになります。
適度な運動は、全身の血行を促進し、毛根に必要な栄養素を届ける助けとなります。
ストレスによる血行不良
精神的なストレスもまた、髪に大きな影響を与えます。強いストレスを感じると、交感神経が優位になり、血管が収縮します。
特に頭皮の毛細血管は非常に細いため、この影響を受けやすく、血流が著しく低下します。血行不良に陥った毛乳頭は、毛母細胞に十分な栄養と酸素を供給できなくなり、毛母細胞の活動が低下します。
これがヘアサイクルの乱れや抜け毛につながります。また、ストレスは自律神経のバランスを崩し、ホルモンバランスにも悪影響を及ぼす可能性があります。
薄毛・抜け毛を引き起こす主な要因
| 主な要因 | 髪への影響 | 対策の方向性 |
|---|---|---|
| 男性ホルモン(AGA) | 成長期が短縮され、髪が細く短くなる。 | 専門家への相談、適切なケアの検討。 |
| 生活習慣の乱れ | 栄養不足、血行不良、成長ホルモンの分泌低下。 | 食事・睡眠・運動習慣の全体的な見直し。 |
| ストレス | 血管収縮による頭皮の血行不良。 | リラックス法の発見、ストレス源の管理。 |
頭皮環境の悪化
髪が育つ土壌である頭皮の環境が悪化することも、ヘアサイクルを乱す原因です。
シャンプーの洗い残し、整髪料の詰まり、過剰な皮脂分泌などは、毛穴を塞ぎ、炎症を引き起こすことがあります(脂漏性皮膚炎など)。
また、洗浄力の強すぎるシャンプーで必要な皮脂まで取り除いてしまうと、頭皮が乾燥し、フケやかゆみの原因となります。
逆に、皮脂が酸化すると(過酸化脂質)、頭皮にダメージを与え、健康な髪の育成を妨げます。清潔で潤いのある、柔らかい頭皮環境を保つことが大切です。
髪を生やすために重要な「毛母細胞」を元気にする方法
髪を生やし、健やかに育てる鍵は、「毛母細胞」が握っています。この毛母細胞が活発に細胞分裂を繰り返すことで、髪は太く、長く成長します。
しかし、毛母細胞は自ら栄養を作り出すことはできません。外部からのサポート、特に血液を通じた栄養補給がその活動の源です。
ここでは、毛母細胞を元気にし、その働きを最大限に引き出すための具体的な方法について解説します。
発毛に必要な栄養素を届ける
毛母細胞が活動するためには、バランスの取れた栄養素が血液によって運ばれる必要があります。
どれか一つだけを摂取すれば良いというわけではなく、チームとして働く栄養素をまんべんなく摂ることが重要です。
髪の約90%以上は「ケラチン」というタンパク質でできています。そのため、まずは良質なタンパク質(肉、魚、卵、大豆製品など)をしっかり摂ることが基本です。
そして、摂取したタンパク質(アミノ酸)をケラチンに再合成する際に、補酵素として働くのが「亜鉛」です。亜鉛(牡蠣、レバー、牛肉など)が不足すると、効率よく髪を作ることができません。
さらに、「ビタミン類」も毛母細胞の活動を支える重要な役割を持ちます。ビタミンB群(特にB2、B6)は、タンパク質の代謝を助け、頭皮の皮脂バランスを整えます。
ビタミンEは血行を促進し、ビタミンCは頭皮のコラーゲン生成を助け、毛細血管を丈夫にします。
髪の成長を支える主な栄養素
| 栄養素 | 主な役割 | 多く含む食品例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料となる。 | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |
| 亜鉛 | タンパク質をケラチンに合成するのを助ける。 | 牡蠣、レバー、牛肉(赤身)、ナッツ類 |
| ビタミンB群 | タンパク質の代謝を促進し、頭皮環境を整える。 | 豚肉、レバー、うなぎ、マグロ、納豆 |
頭皮の血行を良くする
どれだけバランスの良い食事を摂っても、その栄養素が毛母細胞まで届かなければ意味がありません。栄養素を運ぶのは血液であり、頭皮の毛細血管の血流が命綱です。
しかし、頭頂部は心臓から遠く、重力にも逆らうため、もともと血行不良になりやすい部位です。
血行を良くするためには、前述した適度な運動や、ストレスを溜めない生活が基本となります。それに加えて、直接的に頭皮の血流を促す方法として「頭皮マッサージ」も有効です。
指の腹を使い、頭皮全体を優しく動かすようにマッサージすることで、硬くなった頭皮をほぐし、血流を改善する助けになります。
ただし、爪を立てたり、強くこすりすぎたりすると、逆に頭皮を傷つけてしまうため注意が必要です。
毛母細胞の働きをサポートする成分
毛母細胞の働きは、毛乳頭から送られる「成長シグナル」によってコントロールされています。
薄毛が進行している状態では、このシグナルが弱まったり、逆に脱毛シグナル(DHTによるものなど)が強まったりしています。
近年の研究では、毛母細胞の活性化や、毛乳頭からの成長シグナルを強める働きを持つ成分が注目されています。
例えば、アデノシンやt-フラバノンといった成分は、毛乳頭に直接働きかけて発毛促進因子(FGF-7など)の産生を促し、毛母細胞の増殖をサポートするとされています。
また、血行を促進する成分(ビタミンE誘導体やセンブリエキスなど)も、間接的に毛母細胞の活動を支えます。
これらの成分は、育毛剤などに配合されていることが多く、外側からのケアとして毛母細胞の働きを助ける選択肢となります。
発毛を促すために今日からできる生活習慣の見直し
髪の健康は、一朝一夕に手に入るものではありません。
日々の生活の積み重ねが、頭皮環境やヘアサイクルに大きく影響します。高価な育毛剤を試す前に、まずはご自身の生活習慣を見直すことが、発毛を促すための最も基本的かつ重要な土台作りとなります。
食事、睡眠、運動、ストレス管理という4つの側面から、今日からできる具体的な改善策を見ていきましょう。
栄養バランスの取れた食事
「髪は食事から作られる」と言っても過言ではありません。毛母細胞が活発に働くためには、多様な栄養素が必要です。特に「タンパク質」「亜鉛」「ビタミン類」は髪の三大栄養素とも言えます。
脂っこい揚げ物やジャンクフード、糖分の多い菓子類ばかり食べていると、血液がドロドロになったり、皮脂が過剰になったりして、頭皮環境にも血流にも良くありません。
和食中心の、一汁三菜を意識した食事が理想的です。特に、海藻類(ミネラル)、緑黄色野菜(ビタミン)、大豆製品(タンパク質、イソフラボン)などを積極的に取り入れることをお勧めします。
毎日完璧な食事を目指すのは大変ですが、まずは「バランス」を意識することから始めましょう。
質の高い睡眠を確保する
睡眠は、単に体を休ませるだけでなく、細胞の修復と再生を行うための重要な時間です。髪の成長を司る「成長ホルモン」は、私たちが深い眠りに入っているときに最も多く分泌されます。
この成長ホルモンが毛母細胞に作用し、日中に受けたダメージの修復や細胞分裂を促します。
重要なのは「睡眠時間」だけでなく「睡眠の質」です。寝る直前までスマートフォンやPCを見ていると、ブルーライトの影響で脳が興奮し、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。
就寝1時間前からはリラックスできる環境を整え、毎日決まった時間に寝起きする習慣をつけることが、質の高い睡眠につながります。
適度な運動で血流を改善する
頭皮への血流は、発毛の生命線です。運動不足は、全身の血行を滞らせる最大の原因の一つです。特にデスクワーク中心の方は、筋肉が硬直しやすく、血流が悪化しがちです。
激しい運動は必要ありません。むしろ、毎日続けられる「適度な運動」が効果的です。
例えば、通勤時に一駅分歩く、階段を使う、軽いジョギングやウォーキングを30分程度行うなど、日常生活の中で体を動かす機会を増やしましょう。
有酸素運動は全身の血流を改善し、毛根の隅々にまで酸素と栄養を届ける手助けをします。
生活習慣の改善ポイント
| 項目 | 望ましい習慣(例) | 避けたい習慣(例) |
|---|---|---|
| 食事 | タンパク質、ビタミン、ミネラルをバランス良く摂取する。 | 脂質や糖質の過剰摂取、偏った食事。 |
| 睡眠 | 毎日6〜7時間以上の質の高い睡眠をとる。 | 寝る直前のスマホ操作、不規則な睡眠時間。 |
| 運動 | ウォーキングなどの有酸素運動を習慣化する。 | 運動不足、長時間の同じ姿勢。 |
上手なストレス解消法を見つける
現代社会でストレスをゼロにすることは困難です。しかし、ストレスは自律神経を乱し、血管を収縮させて頭皮の血流を悪化させる大きな要因です。
大切なのは、ストレスを溜め込まず、上手に発散する方法をご自身で見つけることです。
何がストレス解消になるかは人それぞれです。自分に合った方法を見つけることが重要です。
ストレス解消法の一例
- 没頭できる趣味(音楽鑑賞、読書、模型作りなど)
- 軽いスポーツや散歩
- 友人や家族との会話
- 入浴(ぬるめのお湯にゆっくり浸かる)
- 瞑想や深呼吸
これらの生活習慣の見直しは、時間がかかるかもしれませんが、髪だけでなく体全体の健康にもつながります。育毛の土台として、根気よく取り組むことが大切です。
育毛剤は髪が生えるのをどう助けるのか
薄毛や抜け毛が気になり始めたとき、多くの方がまず検討するのが「育毛剤」の使用でしょう。
育毛剤は「医薬品」である「発毛剤」とは異なり、主に「今ある髪を健康に育て、抜け毛を防ぐ」ことを目的とした「医薬部外品」に分類されます。
つまり、直接的に髪を生やすというよりは、髪が育ちやすい環境を整え、ヘアサイクルを正常化するサポートをする役割を担います。
ここでは、育毛剤がどのように髪の成長を助けるのか、その主な働きと選び方について解説します。
育毛剤の基本的な役割とは
育毛剤の基本的な役割は、大きく分けて「頭皮環境の改善」と「血行促進」の二つです。薄毛の原因が多岐にわたるように、育毛剤もさまざまな角度から頭皮と毛根にアプローチします。
毛母細胞が働きやすいクリーンな土壌を整え、そこに必要な栄養素をしっかり届けるための「道」を整備するのが、育毛剤の仕事と言えます。
これにより、ヘアサイクルの成長期が維持されやすくなり、結果として抜け毛の予防や、ハリ・コシのある髪の育成につながります。
頭皮環境を整える成分
頭皮が乾燥していたり、逆に皮脂が過剰だったり、炎症を起こしていたりすると、健康な髪は育ちません。多くの育毛剤には、こうした頭皮トラブルを防ぐための成分が含まれています。
例えば、「グリチルリチン酸ジカリウム」や「アラントイン」などは、フケやかゆみ、炎症を抑える抗炎症作用を持ちます。
「ピロクトンオラミン」などは、皮脂の過剰分泌や常在菌のバランスを整える殺菌・抗菌作用が期待されます。
また、「セラミド」や「ヒアルロン酸」などの保湿成分は、乾燥しがちな頭皮に潤いを与え、バリア機能をサポートします。
ご自身の頭皮の状態(乾燥肌か、脂性肌か)に合わせて、これらの成分に着目するのも良いでしょう。
血行を促進する成分
毛母細胞に栄養を届ける毛細血管の血流を促すことは、育毛ケアにおいて非常に重要です。
育毛剤に含まれる血行促進成分は、頭皮に直接塗布することで、毛根周辺の血管を拡張させたり、血流をスムーズにしたりする働きをします。
代表的な成分としては、「センブリエキス」「ニンジンエキス」などの植物由来のエキスや、「ビタミンE誘導体(酢酸トコフェロールなど)」があります。
これらの成分が毛乳頭への栄養供給をサポートし、毛母細胞の活性化を間接的に助けます。
育毛剤の主な有効成分カテゴリー
| 成分の系統 | 期待される主な役割 | 代表的な成分例 |
|---|---|---|
| 血行促進成分 | 頭皮の血流を改善し、栄養供給を促す。 | センブリエキス、ビタミンE誘導体 |
| 抗炎症成分 | 頭皮の炎症やフケ・かゆみを抑える。 | グリチルリチン酸ジカリウム |
| 保湿成分 | 頭皮の乾燥を防ぎ、バリア機能を保つ。 | セラミド、ヒアルロン酸 |
ご自身の目的に合った育毛剤の選び方
育毛剤は多種多様であり、どれを選べば良いか迷うことも多いでしょう。選ぶ際のポイントは、「ご自身の頭皮の状態や悩みに合っているか」です。
例えば、フケやかゆみが気になるなら抗炎症成分が配合されたもの、頭皮の乾燥が気になるなら保湿成分が豊富なもの、頭皮が硬く血行が悪いと感じるなら血行促進成分が主体のもの、といった選び方があります。
また、AGAによる成長期短縮の懸念がある場合は、毛母細胞の活性化や脱毛シグナルの抑制をうたう独自の成分(アデノシンなど)に着目するのも一つの方法です。
大切なのは、一度使ってすぐに効果を期待するのではなく、少なくともヘアサイクルが一巡する目安とされる6ヶ月程度は継続して使用することです。
生活習慣の改善と並行して、ご自身に合った育毛剤を根気よく使い続けることが、健やかな髪を育てる道となります。
正しいヘアケアで頭皮環境を守る
発毛を促すための土台作りとして、毎日のヘアケア、特にシャンプーの方法を見直すことは非常に重要です。間違ったケアは、良かれと思っていても頭皮にダメージを与え、ヘアサイクルを乱す原因になりかねません。
髪が育ちやすい清潔で健康な頭皮環境を維持するために、シャンプー選びから洗い方、その後のケアまで、正しい知識を身につけましょう。
ご自身の肌質に合ったシャンプー選び
シャンプーの最も重要な役割は、頭皮の汚れや余分な皮脂を落とすことです。しかし、洗浄力が強すぎると、頭皮を守るために必要な皮脂まで奪ってしまい、乾燥やバリア機能の低下を招きます。
逆に洗浄力が弱すぎると、皮脂や汚れが残り、毛穴の詰まりや炎症の原因となります。
ご自身の頭皮タイプに合わせて選ぶことが大切です。乾燥肌や敏感肌の方は、洗浄力がマイルドな「アミノ酸系」の洗浄成分を主体としたシャンプーが適しています。
皮脂が多くベタつきがちな脂性肌(オイリー肌)の方は、適度な洗浄力を持つ「高級アルコール系」や「石けん系」が合う場合もありますが、洗いすぎには注意が必要です。
フケやかゆみが気になる場合は、有効成分(抗炎症成分や抗菌成分)が配合された薬用シャンプーを選ぶのも良いでしょう。
間違いやすいシャンプーの方法と正しい手順
髪を洗う際、つい髪の毛自体をゴシゴシとこすってしまいがちですが、本当に洗うべきは「頭皮」です。また、熱すぎるお湯は頭皮を乾燥させ、必要な皮脂を取りすぎてしまいます。
正しい手順で、頭皮を優しく洗い上げることが重要です。
正しいシャンプーの洗い方
| 手順 | ポイント | その理由 |
|---|---|---|
| 1. 予洗い | シャンプー前にぬるま湯(38℃程度)で頭皮と髪をしっかり濡らす。 | お湯だけで髪の汚れの7割程度は落ちる。シャンプーの泡立ちを良くする。 |
| 2. 泡立て | シャンプーを手のひらでよく泡立ててから、頭皮につける。 | 原液を直接つけると刺激になったり、洗いムラの原因になったりする。 |
| 3. 洗う | 指の腹を使って、頭皮をマッサージするように優しく洗う。 | 爪を立てると頭皮が傷つく。髪ではなく頭皮の毛穴の汚れを意識する。 |
| 4. すすぎ | 泡が完全になくなるまで、時間をかけて丁寧にすすぐ。 | すすぎ残しは、フケやかゆみ、炎症の原因になるため最も重要。 |
頭皮マッサージの具体的なやり方と注意点
シャンプー中や、育毛剤を塗布した後などに頭皮マッサージを取り入れると、血行促進に役立ちます。ただし、やり方を間違えると逆効果になるため、優しく行うことが鉄則です。
まず、両手の指の腹を頭皮にしっかりと密着させます。側頭部、前頭部、頭頂部、後頭部と、場所を移動させながら行います。
爪を立てず、指の腹で頭皮全体をつかむようにし、「こする」のではなく「頭皮自体を動かす」イメージで、ゆっくりと円を描いたり、押したり離したりします。特に血行が滞りやすい頭頂部は丁寧に行いましょう。
「気持ちいい」と感じる程度の強さが適しています。強く押しすぎたり、長時間やりすぎたりすると、かえって頭皮に負担がかかり、炎症を起こす可能性もあります。
1回あたり3分~5分程度を目安に、リラックスしながら行いましょう。
薄毛の基礎知識に戻る
髪が生える仕組みに関するよくある質問
- 髪の毛は1日にどのくらい伸びますか?
-
個人差はありますが、健康な髪の毛は1日に約0.3mm~0.4mm伸びると言われています。これを1ヶ月に換算すると、約1cm~1.2cm程度伸びる計算になります。
この成長スピードは、主にヘアサイクルの「成長期」にある毛母細胞の分裂速度によって決まります。年齢や健康状態、栄養状態、季節によっても多少変動することがあります。
- 髪を早く伸ばす方法はありますか?
-
残念ながら、髪が伸びる基本的なスピード(1日に0.4mm程度)を、魔法のように2倍や3倍にする方法はありません。髪の成長速度は、遺伝的な要素や体質によってある程度決まっています。
しかし、ヘアサイクルを正常に保ち、髪が持つ本来の成長ポテンシャルを最大限に引き出すことは可能です。
そのためには、この記事で解説したように、タンパク質を中心としたバランスの良い食事、質の高い睡眠、頭皮の血行を促す適度な運動やマッサージ、ストレス管理が重要になります。
これらを継続することで、健康な髪が育つ土壌を整え、成長期を長く維持する助けとなります。
- 抜け毛が多いと感じたら何をすべきですか?
-
まず、1日の抜け毛の本数を確認してみましょう。
健康な人でもヘアサイクルにより1日に50本~100本程度の髪は自然に抜けています。シャンプー時や朝起きた時の枕元の抜け毛が、この範囲を明らかに超えて急激に増えた場合は注意が必要です。
抜けた毛が細く短い「うぶ毛」のような毛が多い場合は、ヘアサイクルが乱れ、成長期が短縮している可能性があります。
まずは、睡眠不足や過度なストレス、偏った食事など、最近の生活習慣に乱れがなかったかを見直すことが第一歩です。
生活習慣を改善しても抜け毛が減らない場合や、特定の部位(生え際や頭頂部など)だけが薄くなる場合は、AGAの可能性も考えられるため、専門のクリニックなどに相談することを推奨します。
- 育毛剤はいつから使い始めると良いですか?
-
育毛剤を使い始めるタイミングに、早すぎるということはありません。育毛剤の主な目的は「抜け毛の予防」と「健康な髪の育成(育毛)」です。
そのため、髪が薄くなってから慌てて使い始めるよりも、「最近ハリやコシがなくなってきた」「抜け毛が少し気になり始めた」といった、髪質の変化を感じた段階で、予防的に使い始めるのが理想的です。
生活習慣の改善という「内側からのケア」と並行して、育毛剤による「外側からのケア」を早期から取り入れることで、良好な頭皮環境を長く維持し、ヘアサイクルをサポートすることにつながります。
Reference
NATARELLI, Nicole; GAHOONIA, Nimrit; SIVAMANI, Raja K. Integrative and mechanistic approach to the hair growth cycle and hair loss. Journal of clinical medicine, 2023, 12.3: 893.
PAUS, Ralf. Principles of hair cycle control. The Journal of dermatology, 1998, 25.12: 793-802.
MESSENGER, Andrew G. The control of hair growth: an overview. Journal of Investigative Dermatology, 1993, 101.1: S4-S9.
PAUS, Ralf, et al. Neural mechanisms of hair growth control. In: Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings. Elsevier, 1997. p. 61-68.
WON, Chong H., et al. The basic mechanism of hair growth stimulation by adipose-derived stem cells and their secretory factors. Current stem cell research & therapy, 2017, 12.7: 535-543.
OLSEN, Elise A. Current and novel methods for assessing efficacy of hair growth promoters in pattern hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2003, 48.2: 253-262.
PAUS, Ralf. Therapeutic strategies for treating hair loss. Drug Discovery Today: Therapeutic Strategies, 2006, 3.1: 101-110.
RUSHTON, D. H., et al. Causes of hair loss and the developments in hair rejuvenation. International journal of cosmetic science, 2002, 24.1: 17-23.
PEUS, Dominik; PITTELKOW, Mark R. Growth factors in hair organ development and the hair growth cycle. Dermatologic clinics, 1996, 14.4: 559-572.