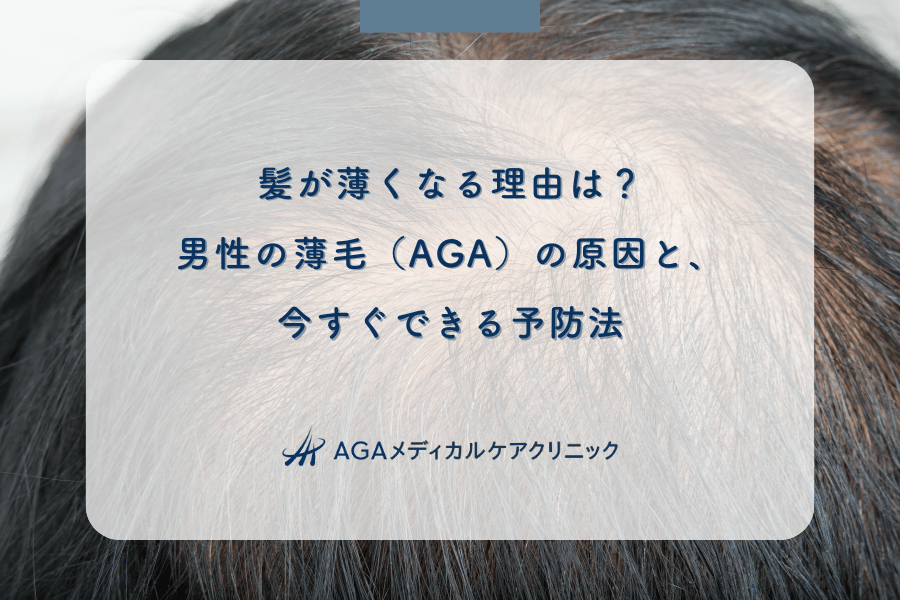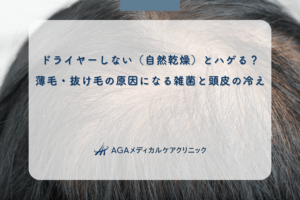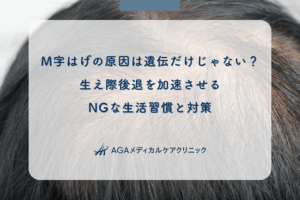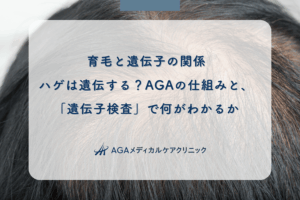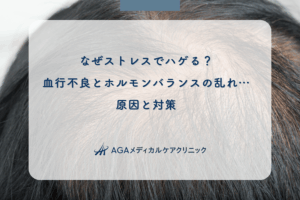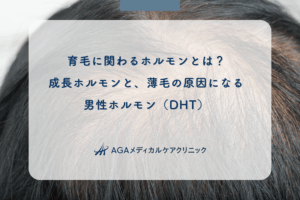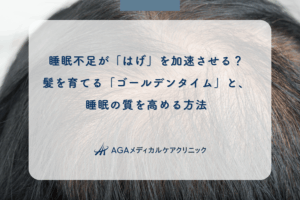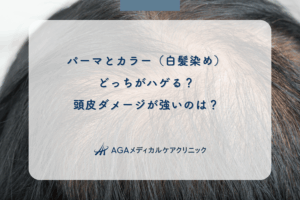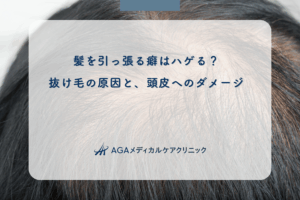「最近、抜け毛が増えた気がする」「鏡を見ると地肌が目立つようになった」。そう感じている男性は少なくないでしょう。
髪が薄くなる原因は一つではありませんが、特に男性の場合はAGA(男性型脱毛症)が大きく関わっています。
この記事では、なぜ男性の髪が薄くなるのか、その主な理由とAGAの詳しい知識、そして今日からすぐに実践できる具体的な予防法について、わかりやすく解説します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
髪が薄くなる主な原因とは?
髪が薄くなると感じる背景には、さまざまな要因が隠れています。多くの男性が悩むこの問題は、単に「年齢のせい」と片付けられるものではなく、複数の原因が複雑に絡み合っていることがほとんどです。
遺伝的な側面、日々の生活習慣、さらには精神的なストレスまで、髪の健康は私たちの身体全体のバロメーターとも言えます。
ここでは、髪が薄くなる主な原因として考えられる4つの大きな要因について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
男性型脱毛症(AGA)の影響
男性の薄毛(うすげ)において、最も一般的で大きな原因とされるのが「AGA(エージーエー)」、すなわち男性型脱毛症です。
これは成人男性によく見られる進行性の脱毛症で、遺伝や男性ホルモンの影響が強いとされています。主な特徴は、生え際(前頭部)が後退していくパターンや、頭頂部(つむじ周り)が薄くなるパターンです。
AGAは特定の男性ホルモンが毛根に作用し、髪の毛の成長サイクル(ヘアサイクル)を短縮させることが原因で発生します。
髪が十分に太く長く成長する前に抜け落ちてしまうため、徐々に細く短い毛が目立つようになり、地肌が見えやすくなるのです。
生活習慣の乱れと頭皮環境
髪の健康は、私たちが毎日送る生活習慣と密接に結びついています。特に食生活の乱れは頭皮環境に直接的な影響を与えます。
脂っこい食事やインスタント食品に偏ると、皮脂が過剰に分泌され、頭皮の毛穴を詰まらせる原因になります。毛穴の詰まりは炎症を引き起こし、健康な髪の成長を妨げます。
また、睡眠不足も大きな問題です。髪の毛は、私たちが眠っている間に分泌される成長ホルモンによって成長が促されます。
睡眠時間が不足したり、睡眠の質が低下したりすると、この成長ホルモンの分泌が減少し、髪の成長が滞ってしまうのです。
ストレスが引き起こす髪へのサイン
現代社会において、ストレスを完全に避けて生活することは困難です。しかし、過度な精神的ストレスは、髪の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
強いストレスを感じると、自律神経のバランスが崩れやすくなります。自律神経は血管の収縮や拡張をコントロールしており、バランスが崩れると頭皮の血行が悪化します。
頭皮の血流が悪くなると、髪の毛の成長に必要な栄養素や酸素が毛根まで十分に行き渡らなくなります。その結果、髪が細くなったり、抜け毛が増えたりするのです。
また、ストレスはホルモンバランスの乱れにもつながり、間接的に薄毛を進行させる要因ともなり得ます。
遺伝的要因はどの程度関わるのか
「薄毛は遺伝する」という話をよく耳にしますが、これはある程度事実です。特にAGA(男性型脱毛症)の発症には、遺伝的な要因が強く関わっていることが研究でわかっています。
具体的には、「男性ホルモン(テストステロン)を、より強力な脱毛作用を持つDHT(ジヒドロテストステロン)に変換する酵素(5αリダクターゼ)の活性度の高さ」や、「男性ホルモンの影響を受けやすい毛根の感受性」が遺伝しやすいとされています。
特に母方の家系に薄毛の人がいる場合、その遺伝的素因を受け継いでいる可能性が指摘されています。
ただし、遺伝的要因があるからといって必ず薄毛になるわけではなく、あくまで「なりやすさ」を受け継ぐということです。
最も多い原因「AGA(男性型脱毛症)」を深く知る
男性の薄毛の悩みの多くは、AGA(男性型脱毛症)に関連しています。このAGAの性質を正しく理解することは、適切な対策を講じるための第一歩です。
AGAは進行性であるため、放置すると薄毛は徐々に進んでいきます。しかし、その原因が科学的に解明されつつあるため、早期に対処することで進行を遅らせたり、改善を図ったりすることが可能です。
ここでは、AGAとは具体的にどのようなものなのか、なぜ発症するのか、そしてどのような特徴があるのかを詳しく掘り下げて解説します。
AGAとは何か?基本的な知識
AGA(Androgenetic Alopecia)は、日本語で「男性型脱毛症」と呼ばれます。成人男性に見られる進行性の脱毛症で、思春期以降に発症し、年齢とともにその割合は高くなります。
日本人男性の場合、20代で約10%、30代で20%、40代で30%、50代以降で40%以上の人がAGAを発症しているというデータもあります。
主な症状は、前頭部の生え際が後退する「M字型」や、頭頂部が薄くなる「O字型」、あるいはその両方が混合したパターンです。
AGAは、髪の毛が成長する期間(成長期)が短くなることで、髪の毛が太く長く育つ前に抜け落ちてしまう「ヘアサイクルの乱れ」が根本的な原因です。
男性ホルモンと薄毛の関係
AGAの発症に深く関わっているのが男性ホルモンです。
男性ホルモンの一種である「テストステロン」が、頭皮に存在する「5αリダクターゼ」という酵素と結びつくことで、「DHT(ジヒドロテストステロン)」という、より強力な男性ホルモンに変換されます。
DHT(ジヒドロテストステロン)の役割
このDHTが、毛根にある「アンドロゲンレセプター(男性ホルモン受容体)」と結合すると、髪の成長を抑制する信号が出されます。
この信号により、通常は数年(2年〜6年)あるはずの髪の成長期が、数ヶ月から1年程度に短縮されてしまいます。
成長期が短くなると、髪は十分に成長できず、細く短い「軟毛(なんもう)」の状態で抜け落ちるようになります。
この軟毛化が進むことで、頭皮の地肌が透けて見えるようになり、薄毛が目立つのです。
5αリダクターゼの活性度やアンドロゲンレセプターの感受性は遺伝によって個人差があり、これがAGAの「なりやすさ」を決定する大きな要因となっています。
AGAの進行パターンとセルフチェック
AGAの進行パターンには個人差がありますが、一般的には特定の分類法(ハミルトン・ノーウッド分類など)が用いられます。
生え際から進行するタイプ、頭頂部から進行するタイプなど、いくつかの典型的なパターンが存在します。
自分がAGAかどうか、またどの程度進行しているかを簡易的にチェックすることは、早期対策のために重要です。
AGAの簡易セルフチェック
以下の項目に当てはまる数が多いほど、AGAである可能性や、将来的に進行する可能性が考えられます。あくまで目安ですが、参考にしてください。
| チェック項目 | 詳細 | 該当(はい/いいえ) |
|---|---|---|
| 家族(特に母方)に薄毛の人がいる | 遺伝的要因はAGAの大きな原因の一つです。 | |
| 以前より髪のハリ・コシがなくなった | 髪が細くなる「軟毛化」はAGAのサインです。 | |
| 抜け毛が細く短い毛が多い | 成長期が短縮され、成長途中で抜けている可能性があります。 | |
| 生え際が後退してきた(M字になってきた) | AGAの典型的な進行パターンの一つです。 | |
| 頭頂部(つむじ)の地肌が目立つ | これも典型的なAGAのパターンです。 | |
| 思春期以降に薄毛が気になり始めた | AGAは思春期以降に発症することが多いです。 |
なぜ早期の対策が重要なのか
AGAは進行性の脱毛症です。つまり、何も対策をしなければ、薄毛はゆっくりと、しかし確実に進行していきます。
ヘアサイクルが乱れ、髪を生み出す毛根(毛包)が小さくなっていくと、やがてその毛根は髪の毛を作り出す活力を失ってしまいます。
毛根の活力が完全になくなってしまうと、そこから再び髪を生やすことは非常に困難になります。
そのため、AGAの対策は、毛根がまだ元気なうち、つまり「抜け毛が増えた」「髪が細くなった」と感じる初期段階で始めることが何よりも重要です。
早めに対策を開始することで、薄毛の進行を遅らせ、現状の髪の状態を維持し、さらには改善できる可能性も高まります。
AGA以外の薄毛の原因
男性の薄毛の多くはAGAによるものですが、中にはAGAとは異なる原因で髪が薄くなるケースも存在します。
これらの脱毛症は、AGAとは原因も対処法も異なるため、自分の症状がどれに当てはまるのかを見極めることが大切です。AGAだと思っていたら、実は別の要因が隠れていたということもあります。
ここでは、AGA以外に考えられる代表的な脱毛症について、その特徴と原因を解説します。
円形脱毛症とその特徴
円形脱毛症は、ある日突然、コインのような円形や楕円形に髪が抜け落ちる脱毛症です。1ヶ所だけの場合もあれば、多発する場合、あるいは頭部全体の髪が抜ける場合もあります。
年齢や性別に関わらず発症しますが、一般的には自己免疫疾患の一種と考えられています。
何らかの理由で免疫機能に異常が生じ、自分自身の毛根を異物とみなして攻撃してしまうことで、髪が抜けてしまうのです。
強い精神的ストレスが引き金になることもありますが、ストレスだけが原因とは限りません。
多くの場合、毛根自体は残っているため、自然に治癒することもありますが、症状が広範囲に及ぶ場合や繰り返す場合は、専門的な治療が必要です。
脂漏性脱毛症と皮脂の過剰分泌
脂漏性(しろうせい)脱毛症は、頭皮の皮脂が過剰に分泌されることで引き起こされる脱毛症です。皮脂が過剰になると、頭皮に常在する「マラセチア菌」というカビ(真菌)の一種が異常増殖しやすくなります。
マラセチア菌は皮脂をエサにして増殖し、その際に出す分解物が頭皮を刺激して炎症(脂漏性皮膚炎)を引き起こします。
頭皮が炎症を起こすと、赤み、かゆみ、ベタついたフケなどが現れ、毛穴が詰まったり頭皮環境が悪化したりすることで、毛根がダメージを受けて抜け毛が増加します。
脂っこい食事の多い人、洗髪が不十分な人、または体質的に皮脂分泌が多い人に見られます。
牽引性脱毛症(髪型による負担)
牽引性(けんいんせい)脱毛症は、特定の髪型を長期間続けることで、髪の毛が常に強く引っ張られ、毛根に物理的な負担がかかり続けることが原因で起こる脱毛症です。
例えば、毎日きつく髪を結ぶポニーテール、オールバック、編み込み(コーンロウ)など、特定の方向に髪を強く引っ張るヘアスタイルをしていると、その部分の生え際や分け目の毛が細くなったり、抜け落ちたりします。
これは男性よりも女性に多いとされていましたが、最近では男性でも長髪できつく結ぶスタイルや、エクステンションの利用などで見られることがあります。
原因が物理的な引っ張りであるため、その髪型をやめれば改善することが多いのが特徴です。
薬剤の副作用による脱毛
特定の薬剤の副作用として、脱毛が起こることがあります。
これはAGAや他の脱毛症とは異なり、薬の作用によってヘアサイクルが急激に停止したり、毛根の細胞分裂が阻害されたりすることで生じます。
最もよく知られているのは、抗がん剤による脱毛です。抗がん剤は、分裂が活発な細胞(がん細胞)を攻撃しますが、同じく分裂が活発な毛根の細胞(毛母細胞)も攻撃してしまうため、髪が抜けてしまいます。
その他にも、一部の抗うつ薬、高血圧の治療薬、血液をサラサラにする薬(抗凝固薬)などでも、副作用として脱毛が報告されることがあります。
薬剤による脱毛が疑われる場合は、自己判断で服薬を中止せず、必ず処方した医師に相談することが重要です。
危険信号?髪が薄くなる初期サインを見逃さない
薄毛の対策は、早期発見・早期対処が鍵となります。AGAをはじめとする多くの脱毛症は、ゆっくりと進行するため、初期段階ではなかなか自覚しにくいものです。
しかし、体は髪や頭皮を通じて何らかのサインを送っていることがよくあります。「気のせいだろう」と見過ごしてしまうと、気づいた時には症状がかなり進行していたということにもなりかねません。
ここでは、髪が薄くなる初期段階で見られる可能性のある「危険信号」について解説します。これらのサインに早めに気づき、適切なケアを始めることが大切です。
抜け毛の量が増えたと感じる
シャンプーの時や朝起きた時の枕、あるいは部屋の床に落ちている抜け毛の量が、以前よりも明らかに増えたと感じる場合、それは注意が必要なサインです。
髪にはヘアサイクルがあり、健康な人でも1日に50本から100本程度の髪は自然に抜け落ちています。これは新しい髪に生え変わるための正常な現象(生理的脱毛)です。
しかし、この本数が連日150本や200本を超えるようだと、何らかの原因でヘアサイクルが乱れ、異常な脱毛が起きている可能性があります。
1日の抜け毛本数の目安
抜け毛の本数を正確に数えるのは難しいですが、例えばシャンプー時の排水溝にたまる髪の量や、ブラッシング時にブラシにつく髪の量などで、以前との違いを比較してみるとよいでしょう。
| 状態 | 1日の抜け毛本数(目安) | 注意度 |
|---|---|---|
| 正常範囲 | 50本〜100本程度 | 低い |
| やや注意 | 100本〜150本程度 | 中 |
| 要注意 | 150本以上(連日続く場合) | 高い |
髪の毛が細く柔らかくなった(軟毛化)
抜け毛の量だけでなく、髪の「質」の変化も重要なサインです。
以前と比べて、髪の毛一本一本が細くなった、コシやハリがなくなり柔らかくなったと感じる場合、それは「軟毛化(なんもうか)」の始まりかもしれません。
軟毛化は、AGAの典型的な初期症状です。前述の通り、AGAは髪の成長期を短縮させます。そのため、髪が太く丈夫に成長する前に抜け落ちるサイクルが繰り返され、徐々に細く頼りない毛が増えていくのです。
特に頭頂部や生え際の髪が、側頭部や後頭部の髪と比べて明らかに細くなっている場合は、AGAが進行し始めている可能性を疑う必要があります。
頭皮のかゆみやフケが気になる
頭皮のかゆみやフケは、頭皮環境が悪化しているサインです。健康な頭皮は青白い色をしていますが、不健康な状態になると赤みを帯びたり、乾燥したり、逆にベタついたりします。
頭皮が乾燥すると、カサカサした細かいフケ(乾性フケ)が出やすくなり、かゆみを伴います。
逆に皮脂が過剰になると、ベタベタした大きなフケ(脂性フケ)が出やすくなり、毛穴が詰まって炎症(脂漏性皮膚炎)を引き起こす原因となります。
頭皮環境の悪化は、健康な髪の成長を妨げるため、放置すると抜け毛や薄毛につながる可能性があります。
シャンプーが合っていない、洗いすぎ、あるいは洗わなすぎなど、ヘアケアの見直しも必要かもしれません。
生え際や頭頂部の地肌が目立つ
鏡を見た時や、他人から指摘されて、生え際や頭頂部(つむじ)の地肌が以前より目立つようになったと感じる場合、それは薄毛が視覚的に進行している証拠です。
髪全体のボリュームが減った、スタイリングが決まりにくくなった、濡れた時に地肌が透けやすい、といった感覚も同様です。生え際の後退(M字)や頭頂部の薄毛(O字)は、AGAの典型的なパターンです。
この段階になると、すでにAGAはある程度進行していると考えられます。しかし、ここで「もう遅い」と諦める必要はありません。このサインに気づいた時点が、本格的な対策を始める絶好のタイミングです。
今すぐ始めたい 生活習慣による薄毛予防法
髪が薄くなる原因には遺伝的な要因もありますが、日々の生活習慣が頭皮環境や髪の成長に与える影響も非常に大きいものです。
遺伝的な素因があったとしても、生活習慣を見直すことで、薄毛の進行を遅らせたり、健康な髪を育む土台を整えたりすることが期待できます。
高額な治療や特別な道具がなくても、今日から意識を変えるだけで実践できることはたくさんあります。ここでは、髪の健康を守るために、今すぐ始めたい生活習慣の改善ポイントを具体的に解説します。
栄養バランスの取れた食事
髪の毛は、私たちが食べたものから作られています。髪の主成分は「ケラチン」というタンパク質です。そのため、良質なタンパク質(肉、魚、卵、大豆製品など)を摂取することは、丈夫な髪を作る基本です。
しかし、タンパク質だけ摂っていても髪は作られません。タンパク質を髪の毛に合成する際には、亜鉛などのミネラルや、ビタミン類(特にビタミンB群やビタミンC、E)が補酵素として働きます。
これらの栄養素が不足すると、いくらタンパク質を摂っても効率よく髪の材料として使われません。
髪の成長に必要な主な栄養素
偏った食事ではなく、多様な食材をバランス良く食べることが、健康な髪を育てることにつながります。特に外食やコンビニ食が多い人は、意識して野菜や海藻類、ナッツ類などを取り入れるようにしましょう。
| 栄養素 | 主な役割 | 多く含む食材例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料になる。 | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助け、毛母細胞の分裂を促す。 | 牡蠣、レバー、牛肉(赤身)、ナッツ類 |
| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を促し、皮脂の分泌を調整する。 | 豚肉、レバー、マグロ、カツオ、納豆 |
| ビタミンC, E | 抗酸化作用で頭皮の老化を防ぎ、血行を促進する。 | C: 果物、野菜 E: ナッツ類、植物油 |
質の高い睡眠を確保する
髪の毛は、毛根にある毛母細胞が分裂を繰り返すことによって成長します。この細胞分裂を最も活発に促すのが「成長ホルモン」です。
成長ホルモンは、私たちが深く眠っている間、特に就寝後から数時間の間に最も多く分泌されます。そのため、単に長く寝るだけでなく、「質の高い睡眠」を確保することが髪の成長には重要です。
睡眠不足が続いたり、眠りが浅かったりすると、成長ホルモンの分泌が妨げられ、毛母細胞の働きが鈍くなり、髪の成長が滞ってしまいます。
毎日決まった時間に寝る、寝る直前のスマートフォン操作やカフェイン摂取を避けるなど、睡眠の質を高める工夫をしましょう。
効果的なストレス発散方法を見つける
過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、頭皮の血行不良を引き起こすため、薄毛の大きな敵となります。
ストレスをゼロにすることは難しいですが、溜め込まないように上手に発散する方法を見つけることが大切です。自分に合ったリラックス方法を日常生活に取り入れましょう。
- 適度な運動(ウォーキング、ジョギング、ヨガなど)
- 趣味に没頭する時間を作る
- ゆっくりと入浴する(ぬるめのお湯に浸かる)
- 友人や家族と話す
- 瞑想や深呼吸を行う
上記はほんの一例です。自分が「心地よい」「リフレッシュできる」と感じることであれば、どんなことでも構いません。短時間でも良いので、意識的にリラックスする時間を持つように心がけましょう。
禁煙と適度な飲酒
喫煙は、髪の健康にとって百害あって一利なしと言えます。タバコに含まれるニコチンには、血管を強力に収縮させる作用があります。これにより、頭皮の毛細血管が収縮し、毛根への血流が著しく悪化します。
栄養や酸素が届きにくくなるだけでなく、タバコを吸うことで体内で大量に発生する活性酸素が、毛根の細胞自体を傷つける可能性もあります。
薄毛を予防・改善したいと考えるならば、禁煙は非常に重要な取り組みです。
また、過度な飲酒も控えましょう。アルコールが体内で分解される際には、髪の材料となるはずのアミノ酸や、髪の成長を助けるビタミンB群が大量に消費されてしまいます。
適度な飲酒はリラックス効果も期待できますが、飲み過ぎは髪の栄養不足を招く原因となることを覚えておきましょう。
日常でできる頭皮ケアと予防法
生活習慣の改善と並行して、日々行う「頭皮ケア」を見直すことも、薄毛予防において非常に重要です。
間違ったケアを続けていると、良かれと思ってやっていることが逆に頭皮環境を悪化させ、抜け毛を増やしてしまう可能性もあります。
健康な髪は、健康な頭皮という「土壌」から育ちます。ここでは、その土壌を整えるために日常でできる、正しい頭皮ケアと具体的な予防法について詳しく解説します。毎日の習慣を見直してみましょう。
正しいシャンプーの方法
シャンプーの目的は、髪の汚れを落とすこと以上に、「頭皮の余分な皮脂や汚れを落とし、清潔に保つこと」にあります。
しかし、洗いすぎたり、洗い方が雑だったりすると、頭皮を傷つけたり、必要な皮脂まで奪って乾燥を招いたりします。
シャンプー選びのポイント
まず、自分の頭皮タイプに合ったシャンプーを選ぶことが大切です。乾燥肌の人が洗浄力の強すぎるシャンプーを使うと、乾燥がさらに進みます。
逆に脂性肌の人がマイルドすぎるシャンプーを使うと、皮脂を落としきれない場合があります。アミノ酸系洗浄成分など、頭皮に優しい洗浄成分を主とした製品を選ぶのも一つの方法です。
| 手順 | ポイント | 目的・理由 |
|---|---|---|
| 1. ブラッシング | シャンプー前に乾いた髪をとかす。 | 髪の絡まりをほどき、大きなホコリや汚れを落とす。 |
| 2. 予洗い(湯洗い) | ぬるま湯(38度程度)で頭皮と髪をしっかり濡らす。 | これだけで汚れの7割程度は落ち、シャンプーの泡立ちが良くなる。 |
| 3. 泡立て | シャンプーを手のひらで軽く泡立ててから髪につける。 | 原液を直接頭皮につけると、すすぎ残しや刺激の原因になる。 |
| 4. 洗う | 指の腹を使って、頭皮をマッサージするように優しく洗う。爪は立てない。 | 髪の毛同士をこすり合わせるのではなく、頭皮の毛穴を洗う意識で。 |
| 5. すすぎ | シャンプーの倍以上の時間をかけ、ぬめり感がなくなるまでしっかりすすぐ。 | すすぎ残しは、かゆみやフケ、毛穴詰まりの最大原因の一つ。 |
シャンプーは基本的に1日1回で十分です。洗いすぎは頭皮のバリア機能を低下させるため注意しましょう。
頭皮マッサージのやり方と注意点
頭皮マッサージは、頭皮の血行を促進し、毛根に栄養を届けやすくするために有効な手段です。また、頭皮の緊張をほぐし、リラックス効果も期待できます。
シャンプーのついでや、お風呂上がりで体が温まっている時に行うのがおすすめです。
頭皮マッサージのポイントと注意点
マッサージを行う際は、清潔な手指で行い、力を入れすぎないことが重要です。爪を立てて頭皮を傷つけないよう、指の腹を使いましょう。
| 動作 | やり方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 押す | 指の腹で、気持ち良いと感じる強さで頭皮全体をゆっくり押す。 | 強く押しすぎない。一点を長く押し続けない。 |
| もむ | 両手の指の腹で頭皮全体をつかむようにし、円を描くように優しくもみほぐす。 | 頭皮をこするのではなく、頭皮自体を動かすイメージで。 |
| たたく | 指先でリズミカルに軽くたたく。(非推奨の場合もあり) | 強くたたくのは逆効果。行う場合もごく軽く。 |
※頭皮をブラシなどで強く叩くマッサージは、頭皮や毛細血管を傷つける恐れがあるため、推奨されません。優しく「もむ」「押す」を中心に行いましょう。
育毛剤の選び方と使い方
薄毛の予防や対策として、育毛剤の使用を検討する人も多いでしょう。
育毛剤は、頭皮環境を整え、今ある髪を健康に育てること(育毛・養毛)や、抜け毛を防ぐこと(脱毛予防)を目的とした医薬部外品です。
選ぶ際は、自分の頭皮の状態(乾燥、脂性、敏感など)や、悩みの原因(血行不良、皮脂過多など)に合った成分が配合されているかを確認しましょう。
育毛剤と発毛剤の違い
ここで混同しやすい「育毛剤」と「発毛剤」の違いを理解しておくことが重要です。目的が異なるため、自分の状態に合わせて選ぶ必要があります。
| 項目 | 育毛剤(医薬部外品) | 発毛剤(第1類医薬品) |
|---|---|---|
| 主な目的 | 頭皮環境を整え、抜け毛を予防し、今ある髪を健康に育てる。 | 新しい髪を生やし(発毛)、髪を成長させる。 |
| 分類 | 医薬部外品 | 医薬品(第1類) |
| 主な対象者 | 薄毛や抜け毛を予防したい人。髪のハリ・コシが欲しい人。 | すでに薄毛(AGA)が進行している人。 |
育毛剤は、頭皮が清潔な状態(通常は洗髪後、髪を乾かした後)で使用します。ノズルを直接頭皮につけ、気になる部分を中心に塗布し、指の腹で優しくなじませます。
塗布後に軽くマッサージを行うとより効果的です。
紫外線対策と頭皮の保護
顔や腕の紫外線対策はしていても、頭皮の紫外線対策は見落としがちです。頭皮は体の中で最も太陽に近い位置にあり、髪で守られているとはいえ、紫外線のダメージを直接受けやすい場所です。
紫外線は頭皮を乾燥させ、炎症を引き起こすだけでなく、髪の毛そのものや、髪を作り出す毛母細胞にもダメージを与えます。
日差しが強い日(特に春〜夏)に屋外で長時間過ごす場合は、頭皮の紫外線対策を怠らないようにしましょう。
- 帽子をかぶる
- 日傘を利用する
- 頭皮用の日焼け止めスプレーを使用する
ただし、帽子を長時間かぶり続けると、頭皮が蒸れて雑菌が繁殖しやすくなるため、時々脱いで通気性を良くするなど、蒸れ対策も同時に行うことが大切です。
帰宅後はしっかりシャンプーで汗や汚れを洗い流しましょう。
薄毛対策でよくある誤解
薄毛に関する情報はインターネットや口コミで溢れていますが、中には科学的根拠の乏しい「迷信」や「誤解」も少なくありません。
間違った情報を信じて自己流のケアを続けることは、時に薄毛の改善を妨げるだけでなく、かえって頭皮環境を悪化させてしまう危険性もあります。
ここでは、薄毛対策に関して多くの人が抱きがちな、よくある誤解について取り上げ、正しい知識を解説します。情報に振り回されず、適切な対策を選ぶための参考にしてください。
海藻類を食べれば髪は生える?
「ワカメやコンブなどの海藻類は髪に良い」という話は、昔からよく言われています。確かに海藻類には、髪の健康維持に役立つミネラル(特にヨウ素)や食物繊維が豊富に含まれています。
ミネラルは髪の成長を助ける働きがあり、食物繊維は腸内環境を整え、栄養素の吸収を助けます。しかし、海藻類は髪の主成分であるタンパク質を含んでいるわけではありません。
「海藻類だけを大量に食べたからといって、髪がフサフサと生えてくる」というのは誤解です。
髪の成長にはタンパク質、ビタミン、ミネラルなど多様な栄養素がバランス良く必要であり、海藻類はあくまでその一部を補う「サポート役」と考えるのが正しいでしょう。
帽子をかぶると薄毛になる?
「帽子やヘルメットを日常的にかぶっていると、頭皮が蒸れて薄毛になる」というのも、よく聞く話です。
確かに、長時間帽子をかぶり続けることで頭皮が蒸れると、汗や皮脂が混ざり合い、雑菌が繁殖しやすい環境になります。
これは頭皮の炎症やかゆみを引き起こし、頭皮環境の悪化につながる可能性があります。しかし、帽子をかぶること自体が、AGAのような薄毛の直接的な原因になるわけではありません。
むしろ、前述の通り、帽子には頭皮を紫外線から守るという大きなメリットがあります。
問題は「蒸れ」ですので、通気性の良い素材を選んだり、こまめに汗を拭いたり、帰宅後にしっかりシャンプーをして頭皮を清潔に保ったりすれば、薄毛を心配する必要は低いでしょう。
頭皮を叩くマッサージは効果的?
一昔前、「頭皮の血行を良くするために、ブラシなどで頭をトントンと叩くと良い」という健康法が流行したことがあります。適度な刺激が血行を促進するという理屈ですが、これは非常にリスクの高い行為です。
頭皮はデリケートであり、硬いブラシなどで強く叩くと、頭皮の表面だけでなく、その下にある毛細血管まで傷つけてしまう恐れがあります。
炎症や内出血を引き起こし、かえって毛根にダメージを与え、抜け毛を助長する可能性すらあります。頭皮マッサージは、あくまで指の腹を使って「優しくもみほぐす」のが基本です。
強い刺激を与えることは避けましょう。
シャンプーのしすぎは逆効果?
頭皮の皮脂や汚れを気にするあまり、1日に何度もシャンプーをしたり、洗浄力の強すぎるシャンプーでゴシゴシと洗いすぎたりする人がいます。
しかし、シャンプーのしすぎは逆効果です。頭皮には、外部の刺激や乾燥から守るために必要な「皮脂膜」という天然のバリア機能があります。過度な洗髪は、この必要な皮脂まで根こそぎ奪い去ってしまいます。
バリア機能を失った頭皮は無防備な状態になり、乾燥しやすくなります。
すると、体は「皮脂が足りない」と判断し、かえって皮脂を過剰に分泌しようとしてしまい、ベタつきや毛穴詰まりを悪化させる悪循環に陥ることがあります。
シャンプーは基本的に1日1回、自分の頭皮に合った洗浄力の製品で優しく洗うのが適切です。
薄毛の基礎知識に戻る
Q&A
ここでは、髪が薄くなる理由や男性の薄毛(AGA)、予防法に関して、多くの方から寄せられる代表的な質問とその回答をまとめました。
- 髪が薄くなるのは何歳からが多いですか?
-
男性の薄毛(AGA)が始まる年齢には個人差が非常に大きいです。早い人では10代後半から20代前半で症状が出始めることもありますし、40代や50代になってから気になり始める人もいます。
一般的には、年齢が上がるにつれてAGAを発症する人の割合は高くなる傾向にあります。
日本人男性の場合、30代で約20%、40代で約30%の人がAGAを発症しているという統計データもあり、30代から40代にかけて薄毛を自覚し始める人が多いと言えるでしょう。
しかし、始まる年齢よりも、気づいた時点で早めに対策を始めることが重要です。
- 専門のクリニックに行くべきタイミングはいつですか?
-
セルフケアで予防に努めても、「抜け毛が減らない」「髪の細さが改善しない」「生え際や頭頂部の地肌が明らかに目立ってきた」など、薄毛の進行が止まらないと感じた時が、専門のクリニックに相談する一つのタイミングです。
特にAGAは進行性のため、自己判断でのケアには限界があります。
クリニックでは、医師が頭皮の状態を専門的な機器で診断し、薄毛の原因が本当にAGAなのか、他の要因はないかを特定してくれます。
その上で、医学的根拠に基づいた治療(内服薬や外用薬の処方など)を提案してもらえます。少しでも不安を感じたら、早めに専門家の意見を聞くことをおすすめします。
- 育毛剤はどれくらいで効果が出始めますか?
-
育毛剤の効果の感じ方には個人差がありますが、一般的に即効性を期待できるものではありません。育毛剤の主な目的は、頭皮環境を整え、今ある髪の毛を健康に育て、抜け毛を予防することです。
髪の毛には「ヘアサイクル(毛周期)」があり、新しい髪が成長し、その変化を実感できるようになるまでには時間がかかります。
通常、最低でも3ヶ月から6ヶ月程度は、毎日継続して使用することが推奨されます。数週間使っただけでは効果がわからないからと諦めず、根気強くケアを続けることが大切です。
- 予防法を続ければ、薄毛は改善しますか?
-
生活習慣の見直しや正しい頭皮ケアなどの予防法は、あくまで「これ以上薄毛を進行させないための土台作り」や「健康な髪が育ちやすい環境を整える」ためのものです。
これらの予防法を実践することで、頭皮環境の悪化や血行不良が原因であった軽度の抜け毛や髪質の低下については、改善が期待できる場合があります。
しかし、すでにAGAが進行している場合、これらの予防法だけで失われた髪を取り戻したり、AGAの進行を完全に止めたりすることは難しいのが現実です。
AGAの進行を抑制するには、予防法と並行して、クリニックでの治療など、より積極的な対策を検討することが必要になる場合が多いです。
Reference
YORK, Katherine, et al. A review of the treatment of male pattern hair loss. Expert opinion on pharmacotherapy, 2020, 21.5: 603-612.
YORK, Katherine, et al. Treatment review for male pattern hair-loss. Expert Opin Pharmacother, 2020, 21.5: 603-612.
OIWOH, Sebastine Oseghae, et al. Androgenetic alopecia: A review. Nigerian Postgraduate Medical Journal, 2024, 31.2: 85-92.
HO, Chih-Yi, et al. Female pattern hair loss: an overview with focus on the genetics. Genes, 2023, 14.7: 1326.
OLSEN, Elise A., et al. Evaluation and treatment of male and female pattern hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2005, 52.2: 301-311.
BANKA, Nusrat; BUNAGAN, MJ Kristine; SHAPIRO, Jerry. Pattern hair loss in men: diagnosis and medical treatment. Dermatologic clinics, 2013, 31.1: 129-140.
REDMOND, Leah C., et al. Male pattern hair loss: Can developmental origins explain the pattern?. Experimental Dermatology, 2023, 32.7: 1174-1181.
ANASTASSAKIS, Konstantinos. Hormonal and genetic etiology of male androgenetic alopecia. In: Androgenetic Alopecia From A to Z: Vol. 1 Basic Science, Diagnosis, Etiology, and Related Disorders. Cham: Springer International Publishing, 2022. p. 135-180.
TRÜEB, Ralph M. Understanding pattern hair loss—hair biology impacted by genes, androgens, prostaglandins and epigenetic factors. Indian Journal of Plastic Surgery, 2021, 54.04: 385-392.
CRANWELL, William; SINCLAIR, Rodney. Male androgenetic alopecia. 2015.