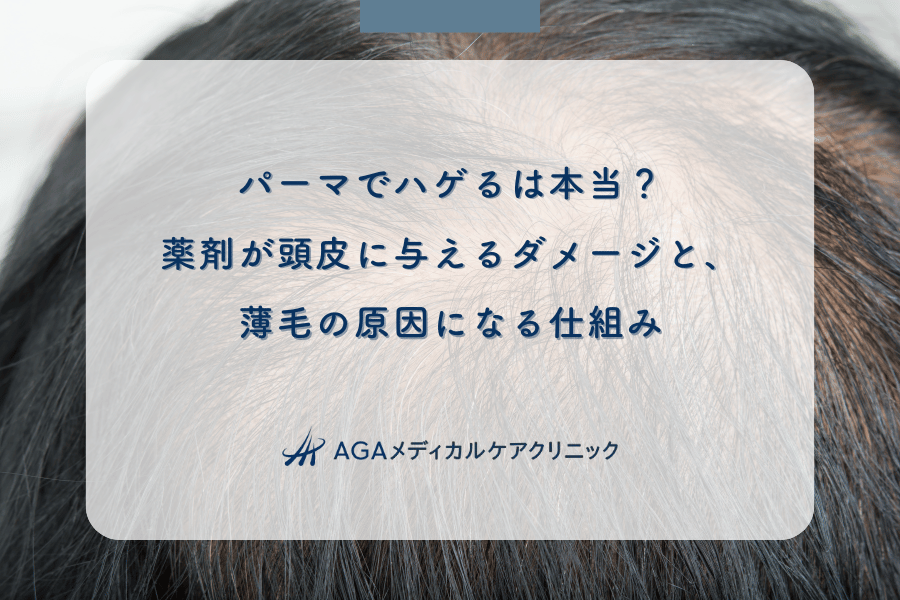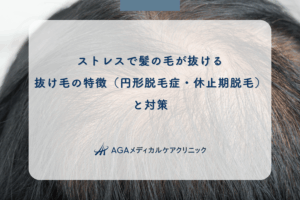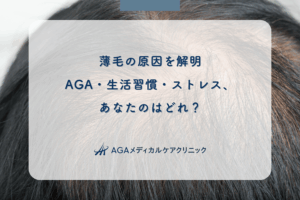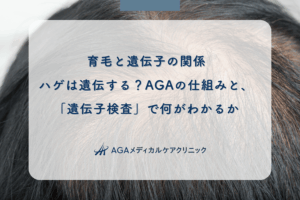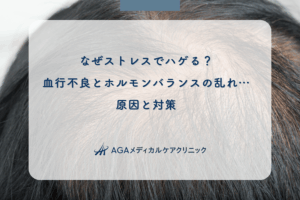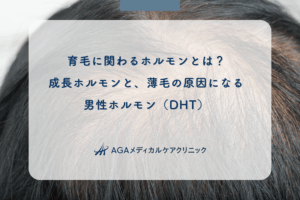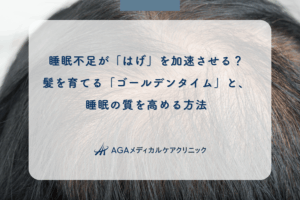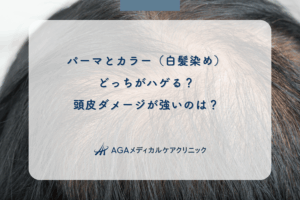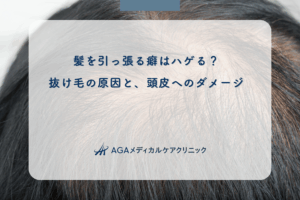「パーマをかけたいけれど、薄毛の原因になるのでは?」と不安に思う男性は少なくありません。「パーマをしたらハゲる」という噂は本当なのでしょうか。
この記事では、パーマが薄毛の直接的な原因になるのか、薬剤が頭皮や髪にどのようなダメージを与えるのかを詳しく解説します。
パーマ液の仕組みや、薄毛につながる可能性のある状況、頭皮への負担を減らす方法やパーマ後の正しいケアまでを網羅。薄毛を心配する方が、パーマとおしゃれを両立させるための知識を提供します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
パーマで「ハゲる」は本当か?薄毛との関係を解明
多くの男性が気にする「パーマをするとハゲる」という説。この疑問について、まずは薄毛の本当の原因とパーマの関係性から明らかにしていきます。
結論から言えば、パーマの施術自体が、AGA(男性型脱毛症)のような薄毛を直接引き起こす主な原因ではありません。しかし、無関係とも言い切れない側面があります。
「パーマ=ハゲる」の誤解
「パーマ=ハゲる」というイメージは、いくつかの誤解から生まれています。一つは、過去に使用されていた薬剤が非常に刺激が強かった時代の名残です。
現代の薬剤は改良が進んでいますが、強い化学薬品であることに変わりはなく、髪が傷むことは事実です。この「髪が傷む」ことと「毛根が死んでハゲる」ことが混同されやすいのです。
また、パーマによって髪がチリチリになったり、切れ毛が増えたりすることで、全体的に髪のボリュームが減ったように見え、薄毛が進行したと感じるケースもあります。
薄毛の主な原因はパーマではない
男性の薄毛の大部分は、男性ホルモンと遺伝が関与する「AGA(男性型脱毛症)」が原因です。AGAは、ヘアサイクル(毛周期)が乱れ、髪の毛が太く長く成長する前に抜け落ちてしまう状態を指します。
パーマ液が毛根の奥深くまで浸透し、このAGAの発症を促すことはありません。薄毛の進行は、主に体内の要因によって決まります。
薄毛を引き起こす主な要因
- 男性型脱毛症(AGA)
- 生活習慣の乱れ(食生活、睡眠不足)
- 過度なストレス
これらの要因が複雑に絡み合い、薄毛は進行します。パーマはこれら体内の要因に直接作用するものではありません。
パーマが薄毛の「引き金」になる可能性
では、パーマは薄毛と全く無関係かというと、そうではありません。パーマは「引き金」や「悪化要因」になる可能性があります。これは、パーマ液が頭皮に付着し、頭皮環境を悪化させる場合です。
頭皮に炎症が起きたり、乾燥がひどくなったりすると、今生えている髪の成長が妨げられ、抜け毛(休止期脱毛)が増えることがあります。
これはAGAとは異なるメカニズムの抜け毛ですが、薄毛を気にしている人にとっては深刻な問題です。
すでにAGAが進行している人が不適切なパーマで頭皮環境を悪化させると、薄毛の進行を早めてしまう懸念もあります。
髪の悩みとパーマ施術の判断基準
パーマをかけるかどうかは、現在の自分の頭皮の状態を客観的に見極めて判断することが重要です。すでにフケやかゆみ、赤みなどのトラブルがある場合、パーマは見送るべきです。
また、抜け毛が急激に増えている時期も、頭皮が何らかのSOSサインを出している可能性があるため、施術は控えるのが賢明です。
髪のおしゃれも大切ですが、長期的に健康な髪を維持するためには、頭皮の健康を最優先に考える必要があります。
なぜパーマが頭皮に良くないと言われるのか?薬剤の仕組み
パーマが頭皮に良くないと言われる最大の理由は、使用する薬剤の化学的な作用にあります。パーマは、髪の内部構造を一度分解し、望む形に再構築する化学反応を利用します。
この強力な反応が、髪だけでなく頭皮にも影響を与えるのです。
パーマ液(1剤)の役割と髪への作用
パーマの1剤には「還元剤」と「アルカリ剤」が含まれます。髪の毛は主にケラチンというタンパク質でできており、そのタンパク質同士は「シスチン結合」という強いつながりで固定されています。
1剤の主な役割は、このシスチン結合を切断することです。アルカリ剤が髪の表面を覆うキューティクルを開き、還元剤が内部に浸透して結合を切ります。
これにより、髪は柔らかくなり、ロッドなどで形を変えられる状態になります。
パーマ液(2剤)の役割と髪への作用
2剤には「酸化剤」が含まれます。ロッドで形作った状態で2剤を塗布すると、酸化剤が作用し、1剤で切断したシスチン結合を新しい位置で再結合させます。
これにより、髪のウェーブやカールが固定されます。この一連の化学反応が、パーマの基本的な仕組みです。
薬剤が頭皮に触れることのリスク
問題は、これらの薬剤が髪だけでなく「頭皮」に付着することです。特に1剤に含まれるアルカリ剤は、タンパク質を溶かす性質(タンパク変性作用)があり、非常に刺激が強い成分です。
頭皮も髪と同じくタンパク質でできているため、アルカリ剤が付着すると、頭皮の表面がダメージを受けます。
パーマ液の主な化学成分
- 還元剤(チオグリコール酸、システアミンなど)
- アルカリ剤(アンモニア、モノエタノールアミンなど)
- 酸化剤(臭素酸ナトリウム、過酸化水素など)
アルカリ剤と還元剤の刺激性
アルカリ剤は、健康な頭皮の弱酸性(pH4.5〜6.0)の状態を、アルカリ性に傾けます。これにより、頭皮のバリア機能が低下し、外部からの刺激を受けやすくなります。
また、還元剤自体も皮膚への刺激物となり得ます。これらの成分が頭皮に付着し、適切に洗い流されない場合、炎症やかぶれ(接触皮膚炎)を引き起こす原因となります。
この頭皮環境の悪化こそが、パーマが薄毛につながると懸念される最大の理由です。
パーマによる頭皮への具体的なダメージ
パーマ液が頭皮に付着すると、具体的にどのようなダメージが発生するのでしょうか。ここでは、頭皮環境を悪化させ、抜け毛や薄毛につながる可能性のある主なトラブルを解説します。
頭皮の乾燥とバリア機能の低下
パーマ液に含まれるアルカリ剤は、頭皮の表面を保護している「皮脂膜」を強力に除去してしまいます。皮脂膜は、頭皮の水分蒸発を防ぎ、外部の刺激から守る「バリア機能」の重要な役割を担っています。
この皮脂膜が失われると、頭皮は急速に乾燥します。乾燥した頭皮は非常にデリケートな状態になり、わずかな刺激にも過敏に反応し、かゆみやフケを引き起こしやすくなります。
薬剤による炎症(かぶれ)
パーマ液の成分(特に還元剤やアルカリ剤)は、頭皮にとって強い刺激物です。これらの薬剤が頭皮に直接触れることで、「刺激性接触皮膚炎」を引き起こすことがあります。
症状としては、頭皮の赤み、ヒリヒリとした痛み、かゆみなどが現れます。また、特定の成分に対してアレルギー反応を起こす「アレルギー性接触皮膚炎」の可能性もあります。
一度アレルギーを発症すると、以降、同じ成分で必ず症状が出るようになります。炎症が起きると、毛根周辺の組織もダメージを受け、正常な発毛が妨げられます。
頭皮への主なダメージ要因
| ダメージ要因 | 主な原因 | 起こり得る症状 |
|---|---|---|
| 化学的刺激 | アルカリ剤・還元剤 | 炎症、かぶれ、赤み、痛み |
| 乾燥 | アルカリ剤による皮脂除去 | フケ、かゆみ、バリア機能低下 |
| 毛穴トラブル | 薬剤の残留・皮脂バランスの乱れ | 毛穴の詰まり、ニキビ、炎症 |
毛穴の詰まりと皮脂バランスの乱れ
パーマ液のすすぎ残しがあると、薬剤の成分が毛穴に詰まることがあります。また、薬剤の刺激によって頭皮がダメージを受けると、防御反応として皮脂が過剰に分泌されることがあります。
この過剰な皮脂と、古い角質や薬剤の残りが混ざり合うことで「角栓」を形成し、毛穴を塞ぎます。毛穴が詰まると、内部で雑菌が繁殖しやすくなり、毛嚢炎(もうのうえん)などの炎症を引き起こします。
これは健康な髪の成長を直接的に阻害する要因です。
髪(毛幹)へのダメージと切れ毛
頭皮だけでなく、髪そのもの(毛幹)もパーマによって大きなダメージを受けます。1剤によってキューティクルが強制的に開かれ、髪内部のタンパク質や脂質が流出します。
2剤で再結合させても、髪の体力は施術前よりも低下しています。ダメージが蓄積すると、髪は乾燥してパサつき、強度が失われます。
結果として、ブラッシングやシャンプーなどのわずかな力で髪が途中で切れてしまう「切れ毛」が増加します。
抜け毛ではないものの、切れ毛が増えると髪の密度が低く見え、薄毛が進行したかのような印象を与えます。
パーマが薄毛の原因になる状況とは
パーマの施術が、必ずしも薄毛に直結するわけではありません。しかし、特定の状況や施術方法、施術後のケアを怠ることで、薄毛のリスクは格段に高まります。
ここでは、特に注意すべき状況について解説します。
薬剤が頭皮に長時間付着した場合
パーマの施術中、薬剤を頭皮に極力つけないように工夫する美容室が増えていますが、それでも技術的な限界や髪の根元からかけるデザインの場合、薬剤が頭皮に付着することは避けられません。
問題は、その付着時間と残留です。薬剤が必要以上に長時間頭皮にとどまったり、施術後のシャンプー(中間水洗や後シャンプー)が不十分で薬剤が頭皮や毛穴に残ってしまったりすると、化学的なダメージが継続的に頭皮を攻撃し続けます。
これが炎症や乾燥の直接的な原因となります。
間違ったセルフパーマのリスク
最もリスクが高い状況の一つが、知識や技術のない状態でのセルフパーマです。市販のパーマ液は、誰でも扱えるように調整されているとはいえ、強力な化学薬品です。
自分の頭皮の状態を見極めず、説明書通りに時間を置いただけでは、頭皮に深刻なダメージを与える可能性があります。
特に、薬剤の塗布ムラや、すすぎ残しは発生しやすく、一部の頭皮だけがひどい炎症を起こすケースもあります。薄毛を気にするのであれば、セルフパーマは避けるのが賢明です。
短い間隔での頻繁な施術
パーマによってダメージを受けた頭皮や髪が、完全に回復するには時間がかかります。髪の毛は自己修復能力がないため、ダメージは蓄積していきます。
頭皮も、バリア機能が正常に戻るまでには一定の期間が必要です。
この回復期間を待たずに、短い間隔(例えば1ヶ月以内など)で次のパーマをかけると、ダメージが上乗せされ、頭皮環境は悪化の一途をたどります。
髪は細くなり、頭皮は炎症を起こしやすい状態が慢性化し、抜け毛が増える悪循環に陥ります。
すでに頭皮トラブルを抱えている場合
パーマをかける前の頭皮コンディションは非常に重要です。すでにフケ、かゆみ、赤み、湿疹、ニキビなどがある状態でパーマをかけるのは、傷口に塩を塗るような行為です。
バリア機能が低下しているところに強力な薬剤が触れると、症状は急激に悪化します。
脂漏性皮膚炎や乾燥性皮膚炎などを抱えている場合、パーマの刺激が引き金となり、抜け毛が大幅に増加する可能性があります。
パーマを避けるべき頭皮の状態
| 頭皮の状態 | パーマを避けるべき理由 |
|---|---|
| 炎症・湿疹・傷がある | 症状が急激に悪化し、強い痛みや化学熱傷のリスクがあるため |
| フケ・かゆみがひどい | バリア機能が著しく低下しており、薬剤の刺激を強く受けすぎるため |
| 日焼け直後 | 頭皮が軽いやけど状態にあり、非常に敏感になっているため |
パーマの種類と頭皮への負担の違い
「パーマ」と一口に言っても、その施術方法や使用する薬剤によって、髪や頭皮への負担は異なります。薄毛を気にする人がパーマを選ぶ際は、これらの違いを理解しておくことも大切です。
一般的に、パーマは「コールドパーマ」と「ホットパーマ」に大別されます。
コールドパーマ(一般的なパーマ)
コールドパーマは、熱を使わずに常温で薬剤(1剤・2剤)の化学反応のみでカールをつける、最も一般的なパーマです。多くの美容室で採用されており、「水パーマ」や「クリープパーマ」などもこの一種です。
薬剤を髪全体に塗布し、頭皮にも薬剤が付着しやすい傾向があります。そのため、薬剤の刺激性がそのまま頭皮へのダメージにつながりやすいと言えます。
ただし、使用する薬剤の種類によって、刺激の強弱は異なります。
ホットパーマ(デジタルパーマなど)
ホットパーマは、デジタルパーマやエアウェーブに代表される、薬剤と「熱」の力を利用してカールを形成するパーマです。
コールドパーマに比べて、薬剤を塗布する範囲が根元から少し離れた中間〜毛先のみであることが多く、薬剤が頭皮に直接付着するリスクは比較的低いとされます。
ただし、薬剤自体のパワーが強めであったり、熱によるタンパク変性を利用するため、髪へのダメージ(特に熱による硬化や乾燥)は大きくなる傾向があります。
頭皮への刺激が少ないパーマの選び方
近年では、頭皮や髪へのダメージを軽減するために開発された薬剤も増えています。代表的なのが「コスメパーマ(化粧品カーリング剤)」です。
これは、医薬部外品である従来のパーマ液とは異なり、化粧品として登録されている薬剤を使用します。
還元剤としてシステアミンやチオグリセリンなど、比較的マイルドな成分が使われることが多く、アルカリ度も低めに設定されています。
そのため、頭皮への刺激や髪へのダメージは軽減されますが、その分カールのかかりが弱かったり、持ちが悪かったりする場合もあります。
パーマの種類別 頭皮への影響比較
| パーマの種類 | 特徴 | 頭皮への負担度(目安) |
|---|---|---|
| コールドパーマ(医薬部外品) | 常温で薬剤反応させる。薬剤が頭皮に触れやすい。 | 中〜高 |
| ホットパーマ(デジタルパーマ等) | 熱処理を加える。薬剤塗布は中間〜毛先が多い。 | 中(頭皮リスクは低めだが熱ダメージ) |
| コスメパーマ(化粧品) | 比較的マイルドな薬剤(化粧品登録)を使用する。 | 低〜中 |
薄毛が気になる人がパーマと上手に付き合う方法
薄毛が気になり始めても、おしゃれとしてパーマを楽しみたいという方は多いでしょう。
リスクをゼロにはできませんが、いくつかの点に注意することで、頭皮への負担を最小限に抑え、パーマと上手に付き合っていくことは可能です。
美容師への事前相談の重要性
最も重要なのは、美容師に自分の懸念を正直に伝えることです。「抜け毛が気になっている」「頭皮が乾燥しやすい」「以前パーマでしみたことがある」といった情報を事前に共有しましょう。
経験豊富で信頼できる美容師であれば、あなたの頭皮の状態をチェックした上で、負担の少ない薬剤を選んだり、頭皮に薬剤をつけないように塗布技術を工夫したり(ゼロテクなど)、最適な施術方法を提案してくれます。
頭皮の状態を見極める
美容師任せにするだけでなく、自分自身でも施術当日の頭皮コンディションをチェックしましょう。
寝不足や体調不良、季節の変わり目などで頭皮が敏感になっていると感じる日は、無理に施術を受けず、延期する勇気も必要です。
特に、かゆみや赤みがある場合は絶対に見送るべきです。
頭皮を保護する施術(保護オイルなど)
多くの美容室では、パーマ液を塗布する前に、頭皮全体に保護オイルやクリームを塗布するサービス(有料または無料)を提供しています。
これは、薬剤が頭皮に直接触れるのを防ぐための非常に有効な手段です。油分の膜が頭皮をコーティングし、薬剤の刺激を緩和します。
薄毛や頭皮の敏感さを伝えた上で、このような保護措置をリクエストしましょう。
美容師に伝えるべき内容
| 伝えるべき項目 | 具体的な伝え方(例) |
|---|---|
| 頭皮の悩み | 「最近フケが出やすい」「頭皮が乾燥気味でかゆい時がある」 |
| 薄毛の懸念 | 「抜け毛が気になっているので、できるだけ頭皮に優しい方法でお願いしたい」 |
| 過去のトラブル | 「以前パーマでかぶれたことがある」「薬剤がしみやすい体質です」 |
パーマをかける適切な頻度
パーマによるダメージを最小限にするには、施術の頻度を空けることが鉄則です。一度パーマをかけると、頭皮や髪が回復するのに時間が必要です。
スタイルを維持したい気持ちはわかりますが、最低でも2〜3ヶ月、できればそれ以上の間隔を空けることを推奨します。
特に薄毛が気になる方は、頻度を減らし、頭皮を休ませる期間を十分に確保することが重要です。
パーマ後の必須セルフケアで頭皮環境を守る
パーマを無事に終えても安心はできません。施術後の頭皮は非常にデリケートで、乾燥しやすく、バリア機能が低下した状態です。
この「アフターケア」をいかに丁寧に行うかが、頭皮環境を正常に保ち、薄毛や抜け毛を防ぐための鍵となります。
施術当日のシャンプーは避けるべきか
美容室では「今夜はシャンプーを控えてください」と言われることが多いです。これには二つの理由があります。一つは、パーマのカールをしっかり定着させるため。
もう一つは、頭皮への負担を減らすためです。施術直後の頭皮はアルカリ性に傾き、非常に敏感になっています。
そこに洗浄力の強いシャンプーを使うと、さらに皮脂を取りすぎてしまい、乾燥や炎症を助長する可能性があります。
当日はお湯で優しくすすぐ「湯シャン」程度にとどめ、シャンプーは翌日以降にするのが賢明です。
低刺激シャンプーでの正しい洗い方
パーマ後の1〜2週間は、特にシャンプー選びと洗い方に注意が必要です。
洗浄力の強い市販のシャンプー(高級アルコール系)は避け、頭皮への刺激がマイルドな「アミノ酸系」や「ベタイン系」の洗浄成分を使用したシャンプーを選びましょう。
洗う際は、爪を立てず、指の腹を使って頭皮をマッサージするように優しく洗います。最も重要なのは「すすぎ」です。
シャンプー剤や汚れが頭皮に残らないよう、普段よりもしっかり時間をかけて、ぬるま湯で洗い流してください。
保湿重視の頭皮ケア(育毛剤の活用)
パーマ後の頭皮は、バリア機能が低下し乾燥しやすい状態です。化粧水で肌を保湿するのと同じように、頭皮にも保湿ケアが必要です。
頭皮専用のローションやエッセンス(保湿成分:セラミド、ヒアルロン酸、コラーゲンなどが配合されたもの)を使用し、うるおいを与えましょう。
また、抗炎症成分(グリチルリチン酸2Kなど)や血行促進成分が含まれた「育毛剤」を使用するのも非常に有効です。
育毛剤は、頭皮環境を整え、抜け毛を予防し、健康な髪の成長をサポートする目的で使用します。
パーマ後の頭皮ケア用品の選び方
| アイテム | 選び方のポイント | 期待できること |
|---|---|---|
| シャンプー | アミノ酸系・ベタイン系(低刺激) | 必要な皮脂を残し、優しく洗浄する |
| 頭皮ローション | セラミド・ヒアルロン酸など保湿成分配合 | 頭皮の乾燥を防ぎ、バリア機能をサポートする |
| 育毛剤 | 抗炎症成分・保湿成分・血行促進成分配合 | 頭皮環境を整え、炎症を抑え、抜け毛を予防する |
髪と頭皮の乾燥対策
シャンプー後は、髪と頭皮を濡れたまま放置してはいけません。濡れた状態は雑菌が繁殖しやすく、キューティクルも開いたままでダメージを受けやすくなります。
まずは清潔なタオルで優しく水分を拭き取り(ゴシゴシ擦らない)、ドライヤーで速やかに乾かします。
この際、頭皮に熱風を当てすぎると乾燥を招くため、ドライヤーを頭から20cm以上離し、全体を動かしながら乾かしましょう。
8割ほど乾いたら、冷風に切り替えて頭皮をクールダウンさせると、毛穴が引き締まりやすくなります。髪には洗い流さないトリートメントをつけ、ダメージ補修と乾燥予防を心がけましょう。
薄毛を加速させる習慣に戻る
Q&A
パーマと薄毛に関してよく寄せられる質問にお答えします。
- パーマ液が頭皮にしみるのですが、続けても大丈夫ですか?
-
いいえ、危険なサインです。薬剤が頭皮に合っていないか、頭皮が弱っている証拠です。しみた場合はすぐに美容師に伝え、洗い流してもらう必要があります。
我慢して続けると、ひどい炎症や化学熱傷(やけど)につながり、毛根にダメージが及び、抜け毛の原因となる可能性があります。
少しでも違和感があれば、施術を中断する勇気を持ってください。
- パーマをかけたら髪が細くなった気がします。
-
パーマの薬剤によって髪内部のタンパク質が流出し、髪の強度が低下して細く感じることがあります。また、頭皮ダメージによって一時的に生えてくる髪が弱々しくなる可能性も否定できません。
ただし、これがAGAの進行を意味するとは限りません。適切なヘアケアと頭皮ケアで髪の状態は改善する可能性があります。
ダメージケア用のトリートメントや、頭皮環境を整える育毛剤の使用を検討しましょう。
- パーマとヘアカラーは同時に行っても問題ないですか?
-
頭皮と髪への負担を考えると、同時施術は推奨しません。どちらもアルカリ剤や化学薬品を使用するため、頭皮へのダメージが倍増します。
同じ日に施術すると、頭皮は深刻なダメージを受け、回復に時間がかかります。最低でも1〜2週間は間隔を空け、頭皮の状態が落ち着いてから次の施術を行うことが望ましいです。
- 薄毛治療中ですがパーマは可能ですか?
-
まずは担当の医師に相談することが重要です。治療内容(特に外用薬の使用など)によっては、パーマ液の成分が予期せぬ反応を起こしたり、治療の妨げになったりする可能性があります。
医師の許可が出た場合でも、美容師に治療中であることを伝え、薬剤が頭皮に絶対につかないよう細心の注意を払って施術してもらう必要があります。
自己判断での施術は危険です。
Reference
HE, Yongyu, et al. Mechanisms of impairment in hair and scalp induced by hair dyeing and perming and potential interventions. Frontiers in Medicine, 2023, 10: 1139607.
GRAY, John. Hair care and hair care products. Clinics in dermatology, 2001, 19.2: 227-236.
ROBBINS, Clarence R. Chemical and physical behavior of human hair. New York, NY: Springer New York, 2002.
ASIWAJU, T. E. EXPERIENCES OF HEALTH PROBLEMS ASSOCIATED WITH CHEMICAL HAIR RELAXATION AMONG FEMALE MASTERS OF PUBLIC HEALTH STUDENTS COLLEGE OF MEDICINE, UNIVERSITY OF IBADAN. 2015. PhD Thesis.
SOMASUNDARAM, Arun; MURUGAN, Kalaiarasi. Current trends in hair care in men. Cosmoderma, 2024, 4.
PAULA, Joane Nathache Hatsbach de; BASÍLIO, Flávia Machado Alves; MULINARI-BRENNER, Fabiane Andrade. Effects of chemical straighteners on the hair shaft and scalp. Anais Brasileiros de Dermatologia, 2022, 97.02: 193-203.
LANJEWAR, Ameya, et al. Review on Hair Problem and its Solution. Journal of Drug Delivery and Therapeutics, 2020, 10.3: 322-329.
T. CHIU, Chin-Hsien; HUANG, Shu-Hung; D. WANG, Hui-Min. A review: hair health, concerns of shampoo ingredients and scalp nourishing treatments. Current pharmaceutical biotechnology, 2015, 16.12: 1045-1052.
OLASODE, Olayinka A. Chemical hair relaxation and adverse outcomes among Negroid women in South West Nigeria. Journal of Pakistan Association of Dermatologists, 2009, 19.4: 203-207.
MCMICHAEL, Amy J. Hair and scalp disorders in ethnic populations. Dermatologic clinics, 2003, 21.4: 629-644.