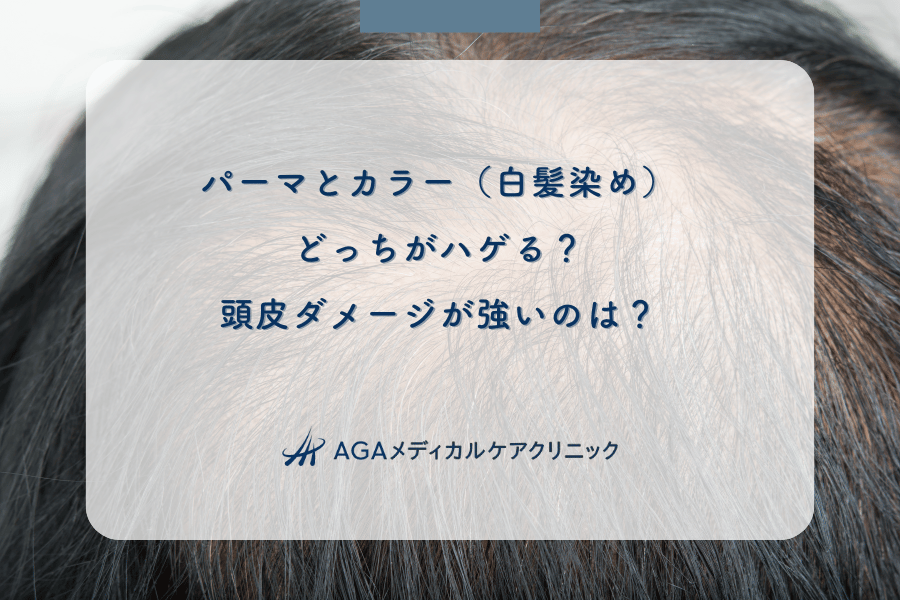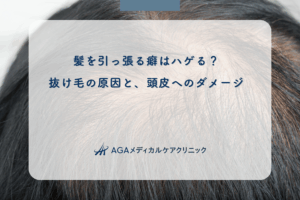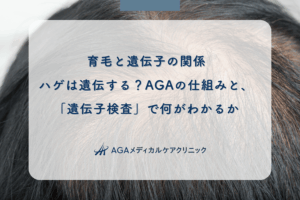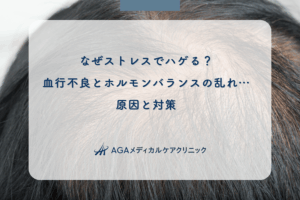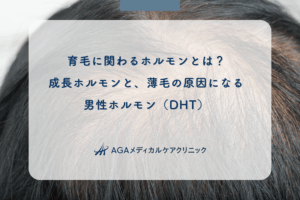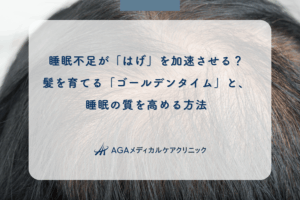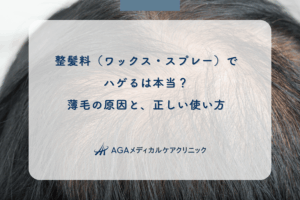「おしゃれのためにパーマやカラーを続けたいけど、薄毛が心配…」「パーマとカラー、どっちが頭皮に悪いんだろう?」そんなお悩みはありませんか。髪型が決まらないと気分も上がりませんよね。
この記事では、パーマとカラーが頭皮や髪に与える影響を徹底的に比較し、どちらが薄毛のリスクを高めるのかを詳しく解説します。
ダメージを最小限に抑える方法や、施術後の正しいヘアケアについてもご紹介します。この記事を読めば、あなたのお悩みが解消され、安心してヘアスタイルを楽しむヒントが見つかるはずです。
結論から言うと、どちらも頭皮に負担はかかりますが、ダメージの種類と対策が異なります。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
パーマとカラー(白髪染め)はどっちがハゲやすい?
パーマとカラー(白髪染め)のどちらかが直接的に「ハゲる(AGAなど)」原因になるわけではありませんが、頭皮へのダメージという点では、どちらも薄毛のリスクを高める可能性があります。
特に頭皮への刺激が強いのはカラー剤(特にアルカリカラーや白髪染め)に含まれる成分ですが、パーマ液も使い方や体質によっては強いダメージを与えます。
結論「ハゲやすさ」に大きな違いはないが
「パーマとカラーどっちがはげる?」という疑問に対しては、どちらも施術方法や使用する薬剤、個人の体質によって頭皮への負担が変わるため、一概にどちらが「ハゲやすい」とは断言できません。
どちらの施術も、薬剤が頭皮に付着することで炎症やかぶれを引き起こす可能性があり、それが頭皮環境の悪化につながり、結果として抜け毛や薄毛の一因となることがあります。
どちらも直接的なAGAの原因ではない
パーマやカラーが、男性型脱毛症(AGA)の直接的な引き金になることは医学的には考えにくいです。
AGAは主に男性ホルモンや遺伝的要因によって引き起こされるため、外部からの化学的な刺激がAGAを発症させるわけではありません。
しかし、すでにAGAが進行している場合や、頭皮環境が良くない状態での施術は、症状を悪化させる可能性が否定できません。
頭皮ダメージが抜け毛につながる仕組み
パーマ液やカラー剤に含まれる化学物質が頭皮に付着すると、頭皮のバリア機能が低下したり、アレルギー反応(接触性皮膚炎)を引き起こしたりすることがあります。
炎症が起こると、毛穴周辺の血流が悪化し、毛根に十分な栄養が届かなくなります。
その結果、髪の毛の成長期が短くなったり、弱い毛しか生えてこなくなったりして、抜け毛が増える(休止期脱毛)ことにつながります。
頭皮トラブルと抜け毛の関係
| 頭皮トラブル | 主な原因 | 抜け毛への影響 |
|---|---|---|
| 乾燥・フケ | 薬剤による皮脂の除去 | 毛穴詰まりやバリア機能低下による毛根への栄養不足 |
| かゆみ・赤み | 薬剤による化学的刺激 | 炎症による血行不良、掻きむしりによる物理的ダメージ |
| 接触性皮膚炎(かぶれ) | 薬剤へのアレルギー反応 | 重度の炎症による毛周期の乱れ、毛根のダメージ |
パーマが頭皮と髪に与えるダメージ
パーマが頭皮や髪にダメージを与える主な原因は、使用する薬剤(1剤と2剤)の化学反応によるものです。
髪の毛の内部構造(シスチン結合)を一度切断し、ロッドなどで形をつけた状態でもう一度再結合させるため、髪への負担は避けられません。
パーマ液(1剤・2剤)の役割と成分
パーマの1剤には、主に「チオグリコール酸」や「システアミン」といった還元剤が含まれています。これが髪の毛のタンパク質の結合を切断する役割を果たします。
2剤には「臭素酸ナトリウム(ブロム酸)」や「過酸化水素水」といった酸化剤が含まれ、切断された結合を新しい形のまま再結合させます。
この化学反応が髪の表面(キューティクル)を開かせたり、内部のタンパク質を流出させたりします。
パーマ薬剤の主な成分と役割
| 薬剤 | 主な成分 | 髪への主な作用 |
|---|---|---|
| 1剤(還元剤) | チオグリコール酸、システアミン | 髪のシスチン結合を切断する |
| 2剤(酸化剤) | 臭素酸ナトリウム、過酸化水素水 | 切断された結合を再結合させる |
頭皮への刺激と炎症リスク
パーマ液、特に1剤はアルカリ性が強いものが多く、頭皮に付着すると刺激(ピリピリ感など)を感じることがあります。
頭皮が敏感な人や、乾燥している人は、かぶれや炎症を引き起こすリスクが高まります。炎症が慢性化すると、健康な髪が育ちにくい頭皮環境になってしまいます。
髪へのダメージ(キューティクル・タンパク質)
パーマの化学反応は、髪の毛の表面を保護しているキューティクルを開かせるため、施術後はキューティクルが剥がれやすくなります。
また、髪内部のタンパク質や水分が流出しやすくなるため、髪が乾燥し、パサつきや枝毛、切れ毛の原因となります。特に繰り返しパーマをかけると、ダメージは蓄積していきます。
パーマの種類によるダメージの違い
一般的なコールドパーマ、デジタルパーマ、エアウェーブなど、パーマには種類があります。
熱処理を加えるデジタルパーマなどは、髪が乾燥しやすい傾向がある一方、リッジの効いたカールが長持ちするといった特徴もあります。
どのパーマが一番ダメージが少ないかは、髪質や希望するスタイルによっても異なります。
カラー(白髪染め)が頭皮と髪に与えるダメージ
カラー(白髪染め)が頭皮や髪に深刻なダメージを与える最大の要因は、薬剤に含まれる「アルカリ剤」と「酸化染料(ジアミン系)」、そして「過酸化水素水」です。
特に白髪染めは、しっかりと色を入れるために薬剤のパワーが強い傾向があります。
カラー剤(1剤・2剤)の仕組み
ヘアカラーの1剤には、アルカリ剤(アンモニアなど)と酸化染料(パラフェニレンジアミンなど)が含まれています。2剤は主に過酸化水素水(オキシ)です。
1剤のアルカリ剤がキューティクルを開き、2剤の過酸化水素水が髪のメラニン色素を脱色(ブリーチ)しつつ、1剤の酸化染料を発色させて髪の内部に定着させます。
カラー薬剤の主な成分と役割
| 薬剤 | 主な成分 | 髪への主な作用 |
|---|---|---|
| 1剤 | アルカリ剤、酸化染料(ジアミン等) | キューティクルを開き、染料を発色させる |
| 2剤 | 過酸化水素水 | メラニン色素を脱色し、染料を酸化させる |
頭皮への刺激とアレルギーリスク(ジアミン)
カラー剤はパーマ液以上に頭皮への刺激が強いとされています。特にアルカリ剤は頭皮の皮脂を奪い、乾燥や刺激を引き起こします。
さらに深刻なのが「ジアミン(パラフェニレンジアミンなど)」によるアレルギー反応です。
これは「かぶれ(接触性皮膚炎)」を引き起こし、一度発症すると、その後ジアミン系のカラー剤が一切使えなくなることもあります。重篤な場合は顔全体が腫れ上がることもあり、非常に注意が必要です。
髪へのダメージ(脱色とキューティクル)
カラー剤の2剤に含まれる過酸化水素水は、髪の色素を抜く(脱色する)作用があります。これは髪の内部構造に直接作用するため、髪への負担は大きいです。
アルカリ剤によってキューティクルが強制的に開かれるため、パーマと同様にタンパク質や水分が流出し、パサつきや切れ毛の原因となります。
白髪染めとおしゃれ染めの違い
白髪染めは、白髪をしっかりと黒や茶色に染めるため、染料の濃度が高く、脱色力も調整されています。おしゃれ染めは、黒髪を明るくしながら色を入れるため、脱色力が強い傾向があります。
どちらも基本的な仕組みは同じであり、頭皮や髪へのダメージは避けられません。
比較「パーマ」VS「カラー」ダメージが強いのは?
パーマとカラー、どちらも頭皮と髪にダメージを与えますが、その「質」が異なります。一概にどちらが悪いとは言えませんが、リスクの種類を理解することが重要です。
頭皮へのダメージ比較
頭皮への直接的な刺激やアレルギーリスクという観点では、カラー(特にジアミンを含むアルカリカラーや白髪染め)の方がリスクが高いと言えます。
パーマ液も刺激はありますが、ジアミンアレルギーのような深刻な即時型・遅延型アレルギーを引き起こすリスクはカラー剤に比べて低いです。
頭皮ダメージのリスク比較表
| 項目 | パーマ | カラー(白髪染め) |
|---|---|---|
| 主な刺激成分 | アルカリ剤、還元剤 | アルカリ剤、過酸化水素水 |
| アレルギーリスク | 低〜中(還元剤など) | 高(ジアミン染料) |
| 主な症状 | 刺激感、かゆみ、乾燥 | 刺激感、かゆみ、重いかぶれ |
髪へのダメージ比較
髪(毛幹)へのダメージは、どちらも深刻です。パーマは髪の内部構造(結合)を変化させ、カラーは内部の色素を破壊(脱色)しつつ染料を入れます。
どちらもキューティクルを開くため、髪のタンパク質や水分は失われます。ブリーチ(脱色)を伴うハイトーンカラーは、特に髪へのダメージが最も大きい施術の一つです。
結論どっちが「ハゲる」リスクが高い?
「ハゲる(薄毛・抜け毛)」につながるリスクは、頭皮環境の悪化が大きく関わります。
そのため、アレルギー反応やかぶれを引き起こす可能性がより高いカラー(白髪染め)の方が、パーマよりも頭皮トラブルを招きやすく、結果として抜け毛につながるリスクは高いと考えられます。
ただし、これはあくまでリスクの比較であり、パーマなら絶対に安全というわけではありません。
パーマとカラーを同日に施術するのは危険?
美容室では「パーマとカラーの同日施術は避けた方が良い」と言われることが多いです。これは、頭皮と髪への負担が非常に大きくなるためです。
同日施術の頭皮への負担
パーマとカラー、どちらもアルカリ剤や過酸化水素水など、頭皮への刺激となる成分を使用します。
これらを短時間のうちに連続して使用すると、頭皮のバリア機能が著しく低下し、強い炎症やただれを引き起こす可能性があります。
一度に受ける化学的ダメージが2倍以上になるため、非常に危険です。
同日施術の髪への負担
髪にとっても、同日施術は深刻なダメージとなります。パーマで髪の結合を切り、再結合させた直後に、カラーでキューティクルをこじ開けて脱色・染色を行うことは、髪の体力を完全に奪う行為です。
施術直後は良くても、数日後から深刻なパサつき、うねり、最悪の場合は「ビビリ毛」と呼ばれるチリチリの状態になるリスクがあります。
どうしても同日に行いたい場合の注意点
基本的には推奨されませんが、もし同日に行う場合は、必ず美容師に相談してください。頭皮の状態が万全であること、髪のダメージが少ないことが前提です。
また、薬剤のパワーを弱めたり、頭皮保護のトリートメントを徹底したりする必要があります。しかし、それでもリスクはゼロにはなりません。
施術の適切な間隔
パーマとカラーを行う場合、最低でも1週間、できれば2週間は間隔を空けることが推奨されます。
そうすることで、頭皮と髪が一度目の施術のダメージからある程度回復する時間(キューティクルが閉じる時間)を確保できます。
どちらを先に行うかは、スタイルや美容師の判断によりますが、一般的には色落ちなどを考慮してパーマを先に行うことが多いです。
パーマとカラーの施術間隔
| 施術間隔 | 頭皮・髪の状態 | 推奨度 |
|---|---|---|
| 同日 | ダメージが最大。炎症リスクが非常に高い。 | ×(非推奨) |
| 1週間 | 最低限の回復期間。まだ不安定な状態。 | △(要相談) |
| 2週間以上 | 頭皮と髪が落ち着き、ダメージが比較的少ない。 | ◎(推奨) |
頭皮ダメージを最小限に抑える施術の受け方
パーマもカラーも、薄毛のリスクを理解した上で、ダメージを最小限に抑える工夫をすることが、おしゃれを長く楽しむための鍵となります。
美容室での事前カウンセリング
施術前には、必ず美容師に現在の頭皮の状態(かゆみ、フケ、赤みなど)や、過去にかぶれた経験がないかを伝えてください。
薄毛が気になっていることも正直に話すことで、美容師も薬剤の選定や塗り方に配慮してくれます。
カウンセリングで伝えるべきこと
- 現在の頭皮の状態(乾燥、かゆみ、赤み、できもの等)
- 過去のアレルギー歴、かぶれた経験
- 薄毛や抜け毛に関する悩み
- 現在使用中の育毛剤や治療薬
頭皮に薬剤をつけない「ゼロテク」
カラー剤を塗布する際に、頭皮に薬剤がベッタリとつかないよう、数ミリ(ゼロコンマ数ミリ)浮かせて塗るテクニック(ゼロテク、または頭皮保護)を依頼することも有効です。
特に白髪染めは根本から塗布する必要がありますが、技術のある美容師であれば、頭皮への付着を最小限に抑えることが可能です。
ダメージ軽減メニューの活用
美容室によっては、薬剤のダメージを軽減するためのトリートメント処理や、アルカリを除去する処理剤(後処理)をメニューに用意している場合があります。
これらを活用することで、施術後の髪や頭皮のコンディションを良好に保つ助けになります。
頭皮保護オイルやスプレー
施術前に頭皮を保護するための専用オイルやスプレーを使用してもらうのも良い方法です。これにより、薬剤が頭皮に直接触れるのを防ぎ、刺激を和らげることができます。
施術後のセルフヘアケア完全ガイド
パーマやカラーをした後の髪は、非常にデリケートな状態です。施術当日から、その後のケア方法が、将来の頭皮と髪の健康を左右します。
施術当日のシャンプーは避ける
施術当日は、シャンプーをしないのが基本です。
パーマやカラーの薬剤が髪や頭皮に定着・安定するには時間がかかります(特にパーマは約24時間〜48時間)。
当日にシャンプーをすると、パーマが取れやすくなったり、色が早く落ちたりするだけでなく、バリア機能が低下した頭皮に追い打ちをかけることになります。
低刺激なシャンプーの選び方
施術後は、洗浄力がマイルドなアミノ酸系シャンプーや、頭皮ケア(スカルプケア)用のシャンプーを選びましょう。
高級アルコール系(ラウリル硫酸〜など)の洗浄力が強いシャンプーは、頭皮の皮脂を奪いすぎ、乾燥や刺激の原因となります。
シャンプーの種類と特徴
| シャンプーの種類 | 特徴 | 施術後の適性 |
|---|---|---|
| アミノ酸系 | 洗浄力がマイルドで低刺激。保湿力が高い。 | ◎(推奨) |
| 高級アルコール系 | 洗浄力が強い。安価だが刺激も強い。 | ×(非推奨) |
| 石けん系 | 洗浄力が強い。アルカリ性で髪がきしみやすい。 | △(要ケア) |
トリートメントによる保湿と補修
パーマやカラーで失われたタンパク質や水分を補うため、トリートメントは必須です。シャンプー後は、毛先を中心にトリートメントをなじませ、数分置いてからしっかりとすすぎます。
頭皮にはトリートメント剤が残らないように注意しましょう。
ドライヤーでの正しい乾かし方
濡れた髪はキューティクルが開いており、最もダメージを受けやすい状態です。自然乾燥は絶対に避け、すぐにドライヤーで乾かしてください。
乾かし方の手順
- タオルドライ: 髪をこすらず、タオルで優しく挟み込むように水分を吸い取ります。
- ドライヤー(根本): まずは頭皮と髪の根本を乾かします。
- ドライヤー(毛先): 根本が乾いたら、毛先に向かって風を当てて乾かします。オーバードライ(乾かしすぎ)に注意しましょう。
育毛剤の使用タイミング
薄毛対策として育毛剤を使用している場合、施術当日は頭皮が敏感になっているため使用を避けた方が無難です。
翌日以降、頭皮の状態が落ち着いてから(ヒリヒリ感やかゆみがないことを確認してから)再開しましょう。育毛剤は、髪を乾かした後の清潔な頭皮に使用するのが最も効果的です。
薄毛を加速させる習慣に戻る
よくある質問
- パーマやカラーをすると将来ハゲますか?
-
パーマやカラーがAGA(男性型脱毛症)の直接的な原因になることはありません。
しかし、施術によって頭皮が炎症を起こしたり、アレルギー反応(かぶれ)が出たりすると、頭皮環境が悪化し、抜け毛が増える可能性があります。
適切なケアを怠ると、薄毛のリスクを高めることにつながります。
- 頭皮が弱い(敏感肌)でもパーマやカラーはできますか?
-
頭皮が敏感な方は、施術前に必ず美容師に相談してください。パッチテスト(薬剤を皮膚につけてアレルギー反応を見ること)が必須です。
頭皮の状態によっては、施術を断念するか、低刺激な薬剤(ヘアマニキュアやノンジアミンカラー、化粧品登録のパーマ液など)に変更する必要があります。
- 市販の白髪染めと美容室のカラーはどちらが痛みますか?
-
一般的には、市販の白髪染めの方がダメージは大きい傾向にあります。市販品は、どんな髪質の人でも染まるように薬剤のパワーが強く設定されていることが多いからです。
美容室では、髪質やダメージレベルに合わせて薬剤を調合し、頭皮への付着も最小限に抑える技術があるため、ダメージをコントロールしやすいです。
- パーマとカラー、薄毛の人はどちらを優先すべきですか?
-
どちらも頭皮に負担はかかりますが、薄毛が気になる場合は、頭皮へのアレルギーリスクがより高いカラー(特に白髪染め)の方を慎重に考えるべきです。
もし白髪が気になる場合は、ジアミンを含まないヘアマニキュアやカラートリートメントなどで代用することも一つの手です。
ボリュームアップのためにパーマをかける場合は、頭皮に薬剤をつけないよう細心の注意を払って施術してもらうことが重要です。
Reference
HE, Yongyu, et al. Mechanisms of impairment in hair and scalp induced by hair dyeing and perming and potential interventions. Frontiers in Medicine, 2023, 10: 1139607.
MOREL, Olivier JX; CHRISTIE, Robert M. Current trends in the chemistry of permanent hair dyeing. Chemical reviews, 2011, 111.4: 2537-2561.
JEONG, Nam Young; LIM, Sun Nye; CHOI, Chang Nam. Hair Damage and Wave Effi ciency according to the Degree of Alkalinity in Permanent Wave. Applied Microscopy, 2012, 42.3: 136-141.
ZHANG, Guojin; MCMULLEN, Roger L.; KULCSAR, Lidia. Investigation of hair dye deposition, hair color loss, and hair damage during multiple oxidative dyeing and shampooing cycles. J. Cosmet. Sci, 2016, 67: 1-11.
MITU, Alina Mihaela. Damage assessment of human hair by electrophoretical analysis of hair proteins. 2004. PhD Thesis. Bibliothek der RWTH Aachen.
ROBBINS, Clarence R. Chemical and physical behavior of human hair. New York, NY: Springer New York, 2002.
DE SOUZA, João Carlos, et al. Comprehensive Review of Hair Dyes: Physicochemical Aspects, Classification, Toxicity, Detection, and Treatment Methods. ACS omega, 2025, 10.27: 28567-28586.
ROBBINS, Clarence R. Dyeing human hair. In: Chemical and Physical Behavior of Human Hair. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011. p. 445-488.
LEE, Eun-Jin; LEE, June-Hee; LEE, Jae-Nam. Effect of Permanent Wave on Hair Damage and Morphological Changes after Natural Henna Treatment. Journal of the Korean Applied Science and Technology, 2019, 36.3: 915-929.
LEE, Soon-Hee; KIM, Sung-Nam. Physical and morphological characteristics change of hair according to water content when heat permanent wave is treated. The Korean Fashion and Textile Research Journal, 2008, 10.3: 389-393.