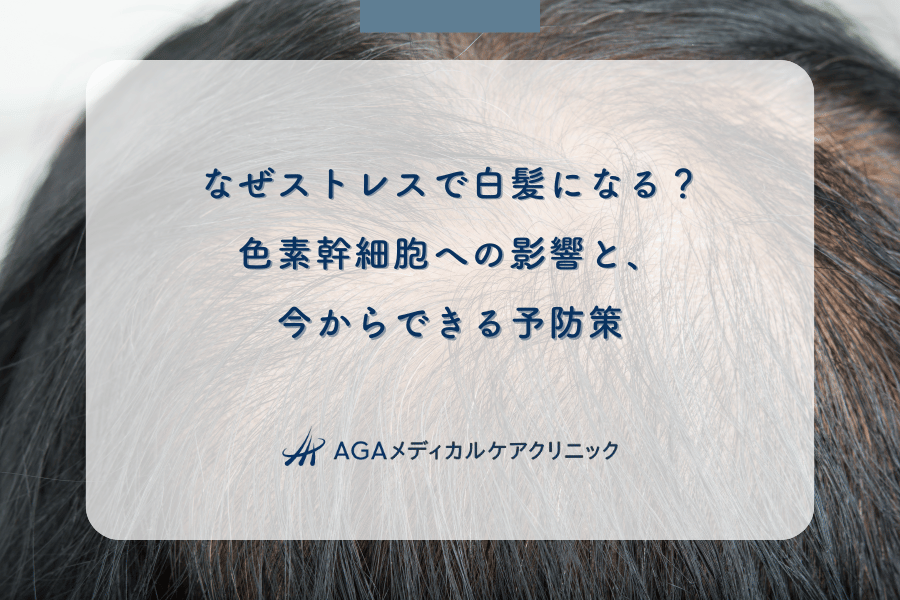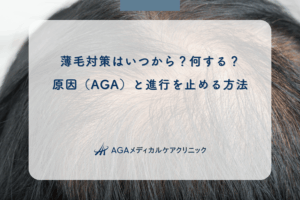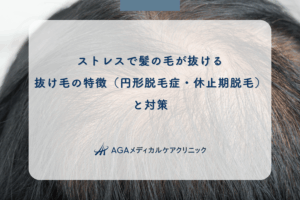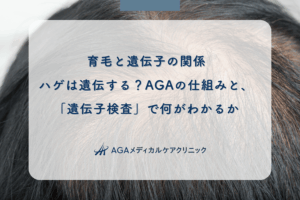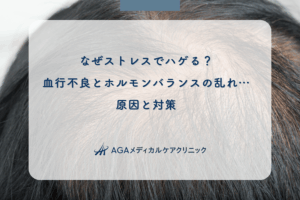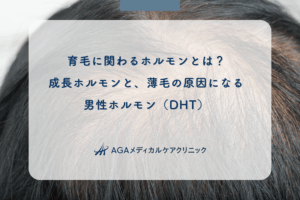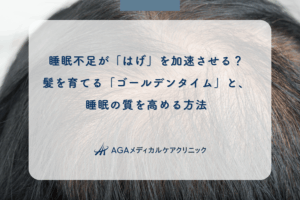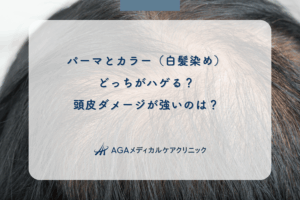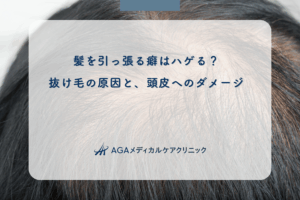鏡を見るたびに増えているように感じる白髪。「最近ストレスが多いからかもしれない」と漠然とした不安を抱えていませんか。
かつては科学的根拠が乏しいとされていましたが、近年の研究により、ストレスが白髪の直接的な原因となり得ることが明らかになってきました。
この記事では、ストレスがどのようにして髪を黒く保つ「色素幹細胞」に影響を与え、白髪を引き起こすのか、その関係性を深く掘り下げます。
さらに、日常生活で取り入れられる具体的な予防策まで、わかりやすく解説します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
ストレスが白髪を引き起こす衝撃の事実
多くの人が経験的に感じていた「ストレスで白髪が増える」という現象。これは単なる気のせいではなく、科学的な根拠があることが近年わかってきました。
特に男性は、仕事や社会生活でのプレッシャーを感じる機会も多く、ストレスと白髪の関係は切っても切れない問題と言えるでしょう。
このセクションでは、まず白髪がどのように生えるのかという基本的な点から、ストレスが髪の色にどのような影響を与えるのか、最新の研究結果を交えて解説します。
白髪はどのようにして生えるのか
私たちの髪の毛は、毛根にある「毛包(もうほう)」と呼ばれる場所で作られます。毛包の中には、髪の毛そのものを作る「毛母細胞」と、髪に色をつける「色素細胞(メラノサイト)」が存在します。
髪が成長する際、毛母細胞が分裂して髪が伸び、同時にメラノサイトが「メラニン色素」を作り出して髪に供給します。
このメラニン色素のおかげで、私たちの髪は黒や褐色など、固有の色を持つのです。
白髪が生えるのは、この仕組みのどこかに問題が生じた結果です。
具体的には、毛包内にメラノサイトが存在しなくなったり、メラノサイトはあってもメラニン色素を作る機能が停止したりすると、髪に色がつかなくなります。
色がついていない、いわば「透明」な状態の髪の毛が、光の反射によって白く見えているのが白髪の正体です。
ストレスと白髪の直接的なつながりとは
長年、ストレスと白髪の関係は明確ではありませんでした。しかし、近年の研究で、強いストレスが白髪の発生に直接関与していることが示されました。
ストレスを感じると、私たちの体は「闘争・逃走反応」と呼ばれる状態に入ります。これは、危険から身を守るための本能的な防御反応です。
この反応が起こると、交感神経が活発になり、「ノルアドレナリン」という神経伝達物質が大量に放出されます。このノルアドレナリンこそが、白髪を引き起こす引き金となるのです。
詳しい影響については後のセクションで解説しますが、ストレスが自律神経を通じて毛包に物理的な変化をもたらす、という点が重要です。
主な白髪の種類
| 白髪の種類 | 主な特徴 | 関連する要因 |
|---|---|---|
| 加齢による白髪 | 年齢と共に徐々に増える。側頭部や前頭部から始まることが多い。 | 色素幹細胞の老化・枯渇 |
| 若白髪 | 10代や20代など、比較的若い時期から生える白髪。 | 遺伝的要因、生活習慣 |
| ストレス性白髪 | 強いストレスを経験した後、急速に増えることがある。 | 交感神経、ノルアドレナリン |
研究が解き明かしたストレスの影響
アメリカの研究チームが行った動物実験では、マウスに強いストレスを与えると、短期間で体毛が白くなる現象が確認されました。
この研究は、ストレスがどのようにして毛の色素に影響を与えるのかを具体的に示しました。
研究によると、ストレスによって放出されたノルアドレナリンが、毛包にある「色素幹細胞(しきそかんさいぼう)」に作用します。
色素幹細胞は、髪に色をつけるメラノサイトの「もと」となる重要な細胞です。
ノルアドレナリンの刺激を受けると、この色素幹細胞が一斉にメラノサイトへと変化(分化)し、その結果、幹細胞が枯渇してしまうことが判明したのです。
白髪は元に戻る可能性もある?
一般的に、加齢によって一度枯渇した色素幹細胞が再生することは難しく、白髪が黒髪に戻ることはないと考えられています。しかし、ストレスが原因の場合、話は少し異なるかもしれません。
別の研究では、ストレスが軽減されると、白髪が一時的に黒髪に戻るケースが報告されています。
これは、色素幹細胞が完全に枯渇する前段階、つまりメラノサイトの機能が一時的に低下しているだけであれば、ストレス源が取り除かれることで機能が回復する可能性を示唆しています。
ただし、これは非常に限定的なケースであり、ストレスによって幹細胞そのものが失われてしまった場合は、元の黒髪に戻すのは困難です。
髪の色を決める「色素幹細胞」とは
前セクションで触れた「色素幹細胞」は、白髪を理解する上で最も重要なキーワードです。なぜストレスが白髪につながるのか、その答えはこの細胞が握っています。
ここでは、髪の色がどのように決まるのか、そして色素幹細胞がどのような役割を果たしているのかを詳しく見ていきましょう。
メラノサイトの役割と髪色の関係
髪の色は、メラノサイト(色素細胞)が作り出すメラニン色素によって決まります。メラニン色素には、主に黒~褐色の「ユーメラニン」と、赤~黄色の「フェオメラニン」の2種類があります。
日本人の黒髪は、ユーメラニンが非常に多いために黒く見えます。一方、欧米人の金髪や赤毛は、フェオメラニンの割合が多かったり、メラニン色素の総量が少なかったりすることで決まります。
これらの色素の量やバランスは、遺伝的要因によって人それぞれ異なります。メラノサイトは、毛髪が成長するサイクル(毛周期)に合わせて活動し、新しく生えてくる髪に色素を供給し続けます。
色素幹細胞の働き
メラノサイトは永久に活動し続けるわけではなく、一定の寿命があります。髪の毛が抜け落ち、新しい髪が生えるサイクル(毛周期)ごとに、新しいメラノサイトが必要になることがあります。
この新しいメラノサイトを供給する「大もと」となるのが、色素幹細胞です。色素幹細胞は、毛包の「バルジ領域」と呼ばれる特定の場所に待機しています。
普段は休眠状態に近いですが、毛周期の成長期が始まると目を覚まし、分裂して一部がメラノサイトに変化(分化)します。
そして、新しく作られる髪の毛に色をつけるために、毛球部へと移動していきます。この幹細胞による補充システムがあるおかげで、私たちは長期間にわたり黒髪を維持できるのです。
色素幹細胞が枯渇するとはどういうことか
白髪になる最大の原因は、この色素幹細胞が「枯渇」することです。枯渇とは、バルジ領域に蓄えられていた色素幹細胞のストックが尽きてしまうことを意味します。
ストックがなくなると、毛周期が新しく始まってもメラノサイトが供給されなくなります。その結果、その毛包から生えてくる髪は、色をつける細胞が存在しないため、白髪となってしまうのです。
一度枯渇した幹細胞のプールを元に戻すことは、現在の医学では非常に困難とされています。
髪が色を失う流れ
| 段階 | 毛包の状態 | 生えてくる髪 |
|---|---|---|
| 健康な状態 | 色素幹細胞が十分に存在。メラノサイトが色素を供給。 | 黒髪(または地毛の色) |
| 機能低下期 | 何らかの要因でメラノサイトの活動が低下。 | 色が薄くなる、または一時的な白髪。 |
| 幹細胞枯渇期 | 色素幹細胞が失われ、メラノサイトが作られなくなる。 | 完全な白髪。元には戻りにくい。 |
加齢による色素幹細胞の減少
色素幹細胞は、加齢によっても自然に減少していきます。これは生物として避けられない老化現象の一つです。年齢を重ねると、幹細胞自身がDNAの損傷を蓄積したり、細胞分裂の能力が低下したりします。
また、幹細胞が正常にメラノサイトへ分化せず、別の細胞になってしまったり、毛包内にとどまれなくなったりする現象も報告されています。
このようにして色素幹細胞が徐々に失われていくことが、加齢による白髪の主な原因です。ストレスは、この老化による減少を急速に早める要因となると考えられます。
ストレスが色素幹細胞を攻撃する
ここがこの記事の核心部分です。ストレスが、どのようにして大切な色素幹細胞を枯渇させてしまうのでしょうか。
それは、私たちの体を守るための「交感神経」が、皮肉にも色素幹細胞に対して攻撃的に作用してしまうためです。
交感神経の暴走
自律神経には、体を活動的にする「交感神経」と、リラックスさせる「副交感神経」があります。強いストレスを感じると、交感神経が優位になり、体は臨戦態勢に入ります。
心拍数が上がり、血圧が上昇し、全身の筋肉が緊張します。
この交感神経は、全身の臓器だけでなく、皮膚や毛包にも張り巡らされています。毛包にある色素幹細胞のすぐ近くにまで、交感神経の末端が伸びていることがわかっています。
通常、この神経系は毛包の活動を適切に調節する役割の一部を担っています。しかし、強いストレス下では、この交感神経が「暴走」とも言える状態に陥ります。
ノルアドレナリンの過剰放出
交感神経が過剰に興奮すると、神経の末端から大量の「ノルアドレナリン」が放出されます。ノルアドレナリンは、血管を収縮させたり、心臓の働きを強めたりする強力な神経伝達物質です。
毛包のバルジ領域でこのノルアドレナリンが過剰に放出されると、近くに待機している色素幹細胞が、この強力なシグナルにさらされることになります。
色素幹細胞には、ノルアドレナリンを受け取る「受容体」が備わっており、この物質に非常に敏感に反応してしまうのです。
色素幹細胞の急速な枯渇
ノルアドレナリンの過剰な刺激を受けた色素幹細胞は、「今すぐ働け!」という緊急命令を受け取ったと勘違いします。
その結果、本来であれば次の毛周期まで休眠しているはずの幹細胞が、一斉に活性化し、メラノサイトへの分化を始めてしまいます。
この「早すぎる」「一斉の」分化が問題です。色素幹細胞は、メラノサイトに変化してしまうと、もう幹細胞に戻ることはできません。
また、それらのメラノサイトは毛包の適切な場所(毛球部)に移動できないため、髪の色素生成に貢献することなく、やがて消滅してしまいます。
結果として、バルジ領域に蓄えられていた色素幹細胞のストックが、わずか数日のうちに急速に失われてしまいます。これが、ストレスによる色素幹細胞の「枯渇」です。
一度失われると再生は困難
このようにしてストレスによって失われた色素幹細胞は、現在のところ再生させる有効な手立てはありません。
毛周期が新しくなっても、色素を供給する細胞がいないため、その毛包からは白髪が生え続けることになります。
これが、「ストレスで白髪になると元に戻らない」と言われる主な理由です。
加齢による減少がゆっくりとした坂道を下るようなものだとすれば、ストレスによる減少は崖から突き落とされるような、急激で不可逆的な変化と言えるでしょう。
だからこそ、幹細胞が枯渇してしまう前の「予防」が何よりも重要なのです。
ストレス以外にもある白髪の原因
ストレスは白髪の強力な引き金の一つですが、すべての白髪がストレスだけで説明できるわけではありません。白髪の原因は非常に多様であり、複数の要因が複雑に絡み合っていることがほとんどです。
ここでは、ストレス以外の主な白髪の原因について解説します。
遺伝的要因の影響
白髪の生え始める時期や進行の速さには、個人差が非常に大きいことが知られています。この個人差に最も強く関わっているのが遺伝的要因です。
ご両親や祖父母が若白髪だった場合、その子供も若白髪になりやすい傾向があります。
これは、色素幹細胞の寿命や、メラニンを生成する能力、ストレスへの感受性などに関連する遺伝子を受け継いでいるためと考えられています。
遺伝的要因が強い場合、他の人よりも早い段階から色素幹細胞が減少しやすいため、若いうちから白髪が目立つことがあります。
白髪の主な原因
| 要因 | 概要 | 対策の方向性 |
|---|---|---|
| 遺伝 | 白髪になりやすい体質。最も影響が大きいとされる。 | 根本的な対策は難しい。進行を遅らせるケアが中心。 |
| 加齢 | 色素幹細胞の老化による自然な減少。 | エイジングケア。抗酸化作用のある食事や頭皮ケア。 |
| ストレス | 交感神経の働きにより、色素幹細胞を急速に枯渇させる。 | ストレス管理、リラクゼーション。 |
| 生活習慣 | 栄養不足、睡眠不足、喫煙などが頭皮環境を悪化させる。 | 生活全般の見直し。 |
栄養不足が招く髪の変化
髪の毛も体の一部であり、健康な髪を維持するためにはバランスの取れた栄養が必要です。
特に、メラニン色素の原料となるアミノ酸(チロシン)や、メラノサイトの働きを助けるミネラル(銅)、ビタミン(ビタミンB群など)が不足すると、髪の色素生成に支障をきたすことがあります。
過度なダイエットや偏った食生活は、これらの栄養素の不足を招きます。
栄養が足りなければ、たとえ色素幹細胞やメラノサイトが存在していても、メラニン色素を十分に作ることができず、白髪の原因となることがあります。
睡眠不足と生活習慣の乱れ
睡眠不足は、自律神経のバランスを崩す大きな要因です。交感神経が優位な状態が続くと、血流が悪化し、毛包に十分な栄養や酸素が届きにくくなります。
これは、ストレス時と似たような状態を体に強いることになります。
また、私たちの体は睡眠中に成長ホルモンを分泌し、細胞の修復や再生を行います。色素幹細胞や毛母細胞も例外ではありません。
睡眠が不足すると、これらの細胞の修復が追いつかず、機能低下や老化が早まる可能性があります。喫煙も血管を収縮させ、頭皮の血流を著しく悪化させるため、白髪の大きなリスク要因です。
病気や薬の副作用
特定の病気やその治療薬が白髪の原因となることもあります。例えば、甲状腺機能の異常(亢進症や低下症)は、体の代謝に影響を与え、白髪を増やすことがあります。
また、自己免疫疾患の一種である円形脱毛症では、毛包が攻撃されると同時にメラノサイトも影響を受け、回復後に白髪が生えてくることがあります。
一部の抗がん剤や特定の薬剤の副作用として、一時的に白髪が増えるケースも報告されています。
急激に白髪が増えた場合は、ストレスや加齢だけでなく、何らかの体調不良が隠れていないか注意することも大切です。
今すぐ始めたいストレス白髪の予防策
ストレスによって色素幹細胞が一度枯渇すると、元に戻すのは困難です。だからこそ、幹細胞が失われる前に「予防」することが何よりも重要になります。
ここでは、日常生活で意識的に取り組めるストレス管理の方法や、生活習慣の改善点について解説します。
日常でできるストレス管理術
ストレスを完全になくすことは現実的ではありませんが、ストレスと上手に付き合い、溜め込まないように工夫することは可能です。
重要なのは、交感神経が過剰に興奮し続けないよう、意識的に副交感神経を優位にする時間(リラックスする時間)を作ることです。
例えば、深呼吸は手軽で効果的な方法です。ゆっくりと息を吐くことで、副交感神経が刺激されます。仕事の合間に数分間、目を閉じて深呼吸するだけでも、心身の緊張を和らげることができます。
簡単なリラックス法
- 腹式深呼吸(ゆっくり吐くことを意識する)
- 軽いストレッチやウォーキング
- 趣味や好きな音楽に没頭する時間を作る
- 湯船にゆっくり浸かる
質の高い睡眠を確保する方法
睡眠は、心身のストレスをリセットし、自律神経のバランスを整えるために最も重要な時間です。単に長く寝るだけでなく、「質」の高い睡眠を確保することが大切です。
質の高い睡眠のためには、就寝前の習慣を見直しましょう。寝る直前までスマートフォンやパソコンの画面を見ていると、ブルーライトの刺激で交感神経が高ぶり、寝つきが悪くなります。
就寝1時間前からはデジタル機器を避け、部屋の照明を暗くし、リラックスできる環境を整えましょう。
毎日決まった時間に寝て、決まった時間に起きるという規則正しい生活リズムも、自律神経を安定させる上で効果的です。
バランスの取れた食事の重要性
食事は、ストレスへの抵抗力を高める上でも重要です。特定の食品だけを食べるのではなく、多様な食材からバランスよく栄養を摂ることが基本です。
特に、ビタミンCやビタミンEなどの抗酸化ビタミンは、ストレスによって発生する活性酸素から細胞を守る働きがあります。活性酸素は、色素幹細胞を含む全身の細胞を傷つけ、老化を早める原因となります。
野菜や果物を積極的に食事に取り入れましょう。
また、イライラを抑える効果が期待できるカルシウム(乳製品や小魚)や、セロトニンの原料となるトリプトファン(大豆製品やバナナ)なども、ストレス管理に役立つ栄養素です。
白髪予防に役立つ栄養素と食生活
ストレス管理と並行して、髪の健康を内側から支える食生活も白髪予防には欠かせません。髪の色素を作るメラノサイトが活発に働くためには、適切な栄養素が必要です。
ここでは、特に意識して摂取したい栄養素と、具体的な食材について解説します。
髪の健康を支える重要栄養素
髪の毛の約90%は「ケラチン」というタンパク質でできています。まずは、良質なタンパク質(肉、魚、卵、大豆製品など)をしっかり摂ることが、丈夫な髪の土台作りになります。
その上で、メラニン色素の生成や頭皮の健康維持に関わるビタミンやミネラルを補給することが重要です。特に、ビタミンB群は細胞の代謝を助け、頭皮環境を整える働きがあります。
また、亜鉛はタンパク質の合成に必要であり、不足すると髪の成長に影響が出ることがあります。
メラニン生成と頭皮環境をサポートする栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品例 |
|---|---|---|
| チロシン(アミノ酸) | メラニン色素の原料となる。 | チーズ、大豆製品、ナッツ類、魚介類 |
| 銅(ミネラル) | メラニンを合成する酵素(チロシナーゼ)の働きを助ける。 | レバー、ナッツ類、甲殻類、大豆製品 |
| ビタミンB群 | 頭皮の代謝を促進し、健康な毛包を維持する。 | 豚肉、レバー、うなぎ、玄米、納豆 |
| 亜鉛(ミネラル) | タンパク質の合成を助け、髪の成長をサポート。 | 牡蠣、レバー、牛肉、チーズ、ナッツ類 |
メラニン生成を助ける食べ物
メラニン色素の直接の原料となるのは、「チロシン」というアミノ酸です。チロシンは体内で合成することもできますが、食事からも積極的に摂取したい栄養素です。
チーズなどの乳製品や、納豆・豆腐などの大豆製品、アーモンドなどのナッツ類に多く含まれています。
ただし、チロシンだけがあってもメラニンは作れません。チロシンからメラニンを合成する過程で、「チロシナーゼ」という酵素が働きます。
この酵素の活性に必要となるのが、ミネラルの「銅」です。銅はレバーや甲殻類、ナッツ類などに含まれます。チロシンと銅をセットで摂ることを意識すると良いでしょう。
避けるべき食習慣
髪に良いものを摂ると同時に、髪に悪い影響を与える食習慣を避けることも大切です。過剰な脂質の摂取は、皮脂の分泌を増やし、頭皮環境を悪化させる原因となります。
揚げ物やスナック菓子、脂身の多い肉などは適量にしましょう。
また、糖分の摂り過ぎも注意が必要です。糖分は体内でタンパク質と結びつき、「糖化」という現象を引き起こします。
糖化が進むと、AGEs(終末糖化産物)という老化物質が生成され、頭皮を含む全身の細胞の老化を早めてしまいます。甘い飲み物やデザートの摂り過ぎは控えましょう。
頭皮環境を整えるヘアケア
白髪予防は、ストレス対策や栄養改善といった体の内側からのアプローチが基本ですが、髪が育つ土壌である「頭皮」の環境を整える、外側からのケアも同様に重要です。
健康な頭皮環境が、色素幹細胞やメラノサイトが正常に働くための基盤となります。
正しいシャンプーの選び方と洗い方
毎日のシャンプーは、頭皮の汚れや余分な皮脂を落とし、清潔に保つために行います。しかし、洗浄力が強すぎるシャンプーは、頭皮に必要な皮脂まで奪い去り、乾燥やかゆみの原因となることがあります。
自分の頭皮タイプに合ったシャンプーを選ぶことが大切です。乾燥しがちな人はアミノ酸系などのマイルドな洗浄成分のものを、皮脂が多いと感じる人は適度な洗浄力があるものを選びましょう。
洗い方も重要です。シャンプーを直接頭皮につけるのではなく、手のひらでよく泡立ててから、指の腹を使って頭皮をマッサージするように優しく洗いましょう。
爪を立ててゴシゴシ洗うのは、頭皮を傷つける原因になるため厳禁です。すすぎ残しは毛穴の詰まりや炎症につながるため、シャンプー剤が残らないよう、時間をかけて丁寧に洗い流してください。
頭皮タイプ別のおすすめ洗浄成分
| 頭皮タイプ | 特徴 | おすすめの洗浄成分 |
|---|---|---|
| 乾燥肌・敏感肌 | カサつき、かゆみが出やすい。 | アミノ酸系(ココイル~、ラウロイル~など) |
| 普通肌 | 特にトラブルがない。 | アミノ酸系、またはバランスの取れた石鹸系 |
| 脂性肌(オイリー肌) | ベタつき、ニオイが気になる。 | 石鹸系、高級アルコール系(ラウリル硫酸~など ※ただし洗浄力強め) |
頭皮マッサージの効果
頭皮マッサージは、頭皮の血行を促進するのに非常に効果的です。ストレスを感じると、交感神経の働きで血管が収縮し、頭皮の血流が悪化しがちです。
血流が悪くなると、毛包に必要な栄養や酸素が届きにくくなり、メラノサイトの働きも低下してしまいます。
シャンプーのついでや、お風呂上がりで体が温まっている時などに、指の腹を使って頭皮全体を優しく動かすようにマッサージしましょう。
頭頂部に向かって引き上げるように行うと、リラクゼーション効果も高まります。
簡単な頭皮マッサージの手順
- 両手の指の腹を使い、耳の上あたりから頭頂部に向かって円を描くように揉みほぐす。
- 生え際から頭頂部に向かっても同様に行う。
- 最後に、後頭部の首の付け根あたりを親指で優しく押す。
育毛剤や頭皮ケア用品の活用
白髪と抜け毛は、根本的な原因は異なりますが、「毛包の機能低下」という点で共通の悩みと言えます。特に男性の場合、白髪と同時に薄毛の悩みも抱えているケースが少なくありません。
白髪に直接働きかける製品(黒髪に戻す)はまだ研究段階のものが多いですが、頭皮環境を整え、毛包の血流を促進する「育毛剤」や「頭皮用美容液」を活用することは、白髪予防の観点からも有益です。
血行を促進する成分や、頭皮の保湿成分、抗炎症成分などが配合された製品を選び、マッサージと併用して頭皮に栄養を補給しましょう。
健康な頭皮を維持することが、色素幹細胞が正常に働ける環境を守ることにつながります。
ストレス・睡眠・運動不足に戻る
よくある質問
最後に、ストレスと白髪に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。
- ストレスを感じたらすぐに白髪になりますか?
-
いいえ、必ずしもそうとは限りません。ストレスが色素幹細胞に影響を与えるのは事実ですが、その影響の出方には個人差が非常に大きいです。
遺伝的に色素幹細胞が強い人や、ストレス耐性が高い人は、強いストレスを受けても白髪がすぐには増えないこともあります。
研究で示されたのは「強いストレスが“引き金”となり得る」ということであり、ストレスを感じた人全員が急速に白髪になるわけではありません。
ただし、慢性的なストレスは確実に色素幹細胞の減少リスクを高めるため、日頃のケアが重要です。
- 白髪を抜くと増えますか?
-
「白髪を抜くと増える」というのは科学的根拠のない迷信です。白髪が1本生えてきた毛穴から、抜いたことで2本、3本と生えてくることはありません。
ただし、白髪を無理に抜くことは推奨できません。毛根を無理やり引き抜くことで、毛包やその周辺の頭皮が傷つき、炎症を起こす可能性があります。
最悪の場合、毛包がダメージを受けて、そこから二度と髪が生えてこなくなる(脱毛)リスクもあります。気になる白髪は、抜かずに根元でカットするか、白髪染めなどで対応しましょう。
- 白髪染めは頭皮に悪いですか?
-
白髪染め(ヘアカラー)の薬剤は、化学物質を含んでおり、人によっては頭皮への刺激となったり、アレルギー反応(かぶれ)を引き起こしたりすることがあります。
特に、ジアミン系の染料はアレルギーを引き起こしやすいため、使用前には必ずパッチテストを行うことが推奨されます。
頭皮が敏感な人は、ジアミンフリーの製品や、髪の表面をコーティングするタイプのヘアマニキュア、カラートリートメントなどを選ぶと負担を軽減できます。
適切に使用すれば過度に恐れる必要はありませんが、頭皮に異常を感じたら使用を中止し、専門医に相談してください。
- 食事で白髪は黒くなりますか?
-
残念ながら、すでに白髪になってしまった髪が、特定の食品を食べたからといって黒髪に戻ることはありません。前述の通り、色素幹細胞が枯渇して生えてきた白髪は、元に戻すのが困難です。
ただし、栄養不足が原因で一時的にメラノサイトの機能が低下していた場合は、食事改善によって機能が回復し、次に生えてくる髪が黒くなる可能性はゼロではありません。
食事(栄養)の主な役割は、すでに生えた白髪を治すことではなく、「これから生えてくる髪を白髪にしない」ための予防であると理解することが大切です。
Reference
DE TOLLENAERE, Morgane, et al. Global repigmentation strategy of grey hair follicles by targeting oxidative stress and stem cells protection. Applied Sciences, 2021, 11.4: 1533.
RACHMIN, Inbal, et al. Stress‐associated ectopic differentiation of melanocyte stem cells and ORS amelanotic melanocytes in an ex vivo human hair follicle model. Experimental dermatology, 2021, 30.4: 578-587.
INOMATA, Ken, et al. Genotoxic stress abrogates renewal of melanocyte stem cells by triggering their differentiation. Cell, 2009, 137.6: 1088-1099.
SEIBERG, M. Age‐induced hair greying–the multiple effects of oxidative stress. International journal of cosmetic science, 2013, 35.6: 532-538.
NISHIMURA, Emi K.; GRANTER, Scott R.; FISHER, David E. Mechanisms of hair graying: incomplete melanocyte stem cell maintenance in the niche. Science, 2005, 307.5710: 720-724.
ARCK, Petra Clara, et al. Towards a “free radical theory of graying”: melanocyte apoptosis in the aging human hair follicle is an indicator of oxidative stress induced tissue damage. The FASEB Journal, 2006, 20.9: 1567-1569.
MOHRI, Yasuaki, et al. Antagonistic stem cell fates under stress govern decisions between hair greying and melanoma. Nature Cell Biology, 2025, 1-13.
ZHANG, Xiaojiao, et al. Melanocyte stem cells and hair graying. Journal of Cosmetic Dermatology, 2023, 22.6: 1720-1723.
SALHAB, Ola; KHAYAT, Luna; ALAAEDDINE, Nada. Stem cell secretome as a mechanism for restoring hair loss due to stress, particularly alopecia areata: narrative review. Journal of Biomedical Science, 2022, 29.1: 77.
JO, Seong Kyeong, et al. Three streams for the mechanism of hair graying. Annals of dermatology, 2018, 30.4: 397.