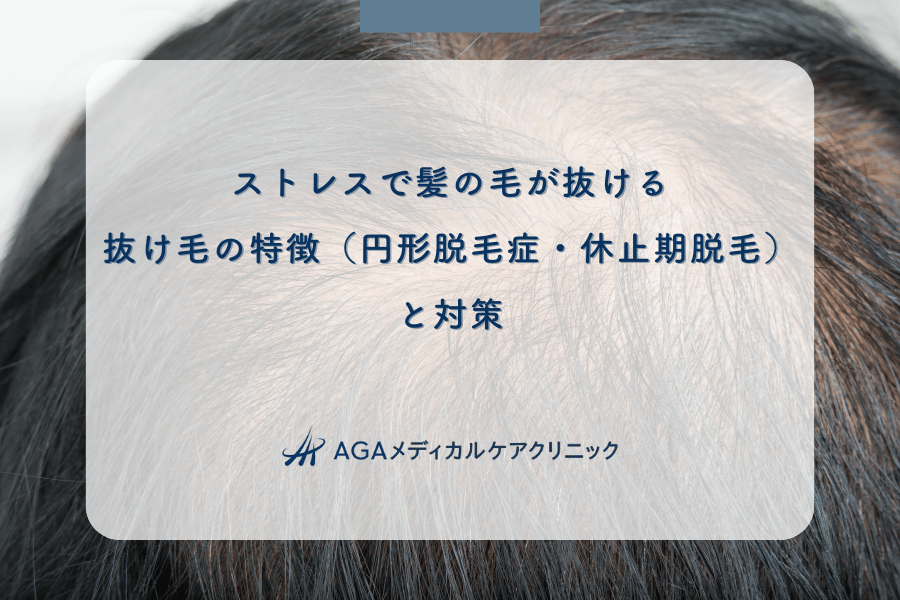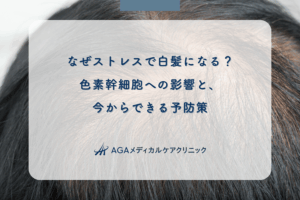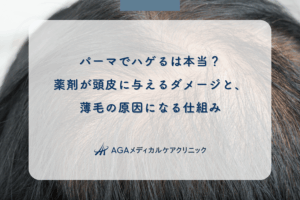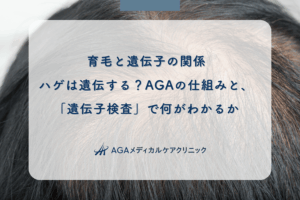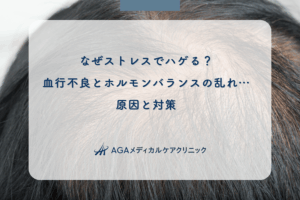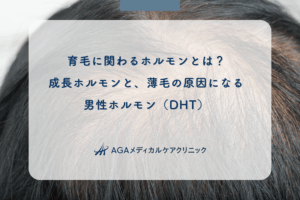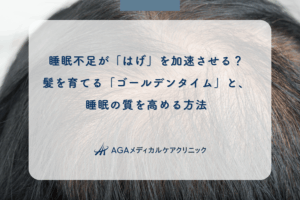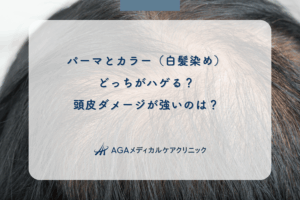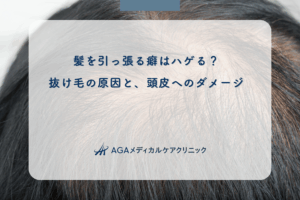「最近、急に抜け毛が増えた気がする」「仕事のプレッシャーが強くなってから髪が薄くなったかも」と感じていませんか。
現代社会で多くの人が抱えるストレスは、心身だけでなく髪の毛にも深刻な影響を与えることがあります。
この記事では、なぜストレスで髪の毛が抜けるのか、その背後にある「円形脱毛症」や「休止期脱毛」といった抜け毛の特徴を詳しく解説します。
さらに、今日から始められる具体的な対策まで、あなたの不安に寄り添いながら、丁寧にご紹介します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
ストレスが髪の毛に与える影響
過度なストレスは、私たちの体が持つデリケートなバランスを崩し、髪の毛の健康に直接的な打撃を与えます。ストレスを感じると、体は「闘争・逃走反応」と呼ばれる緊急事態モードに入ります。
この状態が慢性的に続くと、髪の毛の成長に必要なリソースが後回しにされ、抜け毛という形でサインが現れるのです。
特に男性の場合、仕事上の責任や人間関係の悩みが長期的なストレスとなりやすく、髪の問題につながるケースが少なくありません。
なぜストレスで髪が抜けるのか
ストレスが抜け毛を引き起こす主な理由は、体がストレスに対応するために分泌する物質や、それに伴う身体的な変化にあります。緊張状態が続くと、体は生命維持に重要な機能(心臓や筋肉など)を優先します。
その結果、髪の毛を作り出す毛母細胞のような末端の組織へのエネルギー供給が滞りがちになります。
髪の毛は生命維持に直接関わらないため、栄養不足や酸素不足の影響を真っ先に受けやすく、成長が妨げられたり、抜け落ちたりするのです。
自律神経の乱れと血行不良
私たちの体は、活動的な時に働く「交感神経」と、リラックスしている時に働く「副交感神経」という二つの自律神経によって調整されています。
強いストレスを受け続けると、交感神経が優位な状態が続きます。交感神経は血管を収縮させる働きがあるため、頭皮の毛細血管も細くなります。
これにより、頭皮への血流が悪化し、髪の毛の成長に必要な酸素や栄養素が毛根まで十分に届かなくなります。この血行不良が、抜け毛や薄毛の大きな原因となります。
ストレスによる主な身体的反応
| 影響を受ける系統 | 主な反応 | 髪への影響 |
|---|---|---|
| 自律神経系 | 交感神経が優位になる | 血管収縮による頭皮の血行不良 |
| 内分泌系(ホルモン) | コルチゾール(ストレスホルモン)の増加 | ヘアサイクルの乱れ、皮脂の過剰分泌 |
| 免疫系 | 免疫機能の異常 | 円形脱毛症のリスク増加 |
ホルモンバランスの崩れ
ストレスはホルモンバランスにも影響します。特に「コルチゾール」と呼ばれるストレスホルモンの分泌が増加します。
コルチゾールが過剰になると、男性ホルモンのバランスにも影響を与え、皮脂の分泌を過剰にすることがあります。
過剰な皮脂は毛穴を詰まらせ、頭皮環境を悪化させ、炎症(脂漏性皮膚炎など)を引き起こす原因ともなり得ます。
また、コルチゾールは髪の毛の成長期を短縮させ、休止期へと移行させるシグナルを送ることが研究で示唆されており、これが「休止期脱毛」につながります。
ストレスによる頭皮環境の悪化
ストレスは頭皮の健康状態にも直結します。前述の血行不良やホルモンバランスの乱れに加え、皮脂の過剰分泌は頭皮の常在菌のバランスを崩し、フケやかゆみを引き起こします。
ストレスによって免疫力が低下すると、こうした頭皮トラブルがさらに悪化しやすくなります。頭皮が健康でなければ、健康な髪は育ちません。
ストレスが頭皮環境を悪化させ、その結果として抜け毛が増えるという悪循環に陥るのです。
ストレスによる抜け毛の主な特徴
ストレスが原因で起こる抜け毛には、いくつかの特徴的なパターンがあります。代表的なものが「円形脱毛症」と「休止期脱毛」です。
これらは、AGA(男性型脱毛症)のようにゆっくりと進行するものとは異なり、比較的短期間で顕著な変化が現れることが多いのが特徴です。
自分の抜け毛がどのタイプに当てはまるかを知ることは、適切な対策を講じるための第一歩となります。
突然始まる「円形脱毛症」
円形脱毛症は、ストレスが引き金の一つと考えられている自己免疫疾患の一種です。何らかの原因で免疫機能に異常が生じ、自分の毛根を異物と誤認して攻撃してしまうことで発症します。
特徴的なのは、ある日突然、コイン大(10円玉から500円玉程度)の円形または楕円形の脱毛斑が現れることです。かゆみや痛みといった自覚症状はほとんどありません。
1か所だけの場合もあれば、多発する場合、あるいは頭部全体や全身の毛が抜ける重篤なケースもあります。
全体的に薄くなる「休止期脱毛」
休止期脱毛は、文字通り、成長を終えて「休止期」に入る髪の毛が一時的に増えることで起こる脱毛症です。
通常、髪の毛の約10%が休止期にありますが、強いストレス(精神的なものだけでなく、手術、高熱、過度なダイエットなども含む)が引き金となり、多くの髪が一斉に休止期に入ってしまうことがあります。
ストレスを受けてから実際に抜け毛が増えるまでには2〜3ヶ月程度のタイムラグがあるのが特徴です。
シャンプー時やブラッシング時に「ごっそり抜ける」と感じるほど抜け毛が増え、頭部全体のボリュームが減ったように感じます。
円形脱毛症と休止期脱毛の主な違い
| 特徴 | 円形脱毛症 | 休止期脱毛 |
|---|---|---|
| 抜け方 | 部分的(円形・楕円形)に突然抜ける | 頭部全体からまんべんなく抜ける |
| 主な原因 | 自己免疫機能の異常(ストレスが誘因の一つ) | ヘアサイクルの乱れ(ストレスが誘因の一つ) |
| 発症時期 | ストレスから数週間〜数ヶ月後(個人差大) | ストレスから約2〜3ヶ月後に抜け毛が増加 |
他の脱毛症との見分け方
男性の薄毛で最も多いのはAGA(男性型脱毛症)です。AGAは、男性ホルモンの影響で生え際や頭頂部の髪がゆっくりと時間をかけて細く、短くなっていくのが特徴です。
一方、ストレス性の円形脱毛症や休止期脱毛は、進行が比較的急激である点が異なります。円形脱毛症は「斑状に抜ける」こと、休止期脱毛は「全体的に抜ける」ことが、AGAとの大きな違いです。
ただし、AGAとストレス性の脱毛が併発することもあり、自己判断は難しい場合もあります。
抜け毛の量や質の変化に注意
日々の抜け毛のチェックも重要です。健康な人でも1日に50本から100本程度の髪は自然に抜けています。
しかし、シャンプー時や朝起きた時の枕元の抜け毛が明らかに「以前より増えた」と感じる場合は注意が必要です。また、抜けた毛の毛根部分を観察してみてください。
ストレスによる休止期脱毛の場合、毛根に「毛根鞘(もうこんしょう)」と呼ばれる白い塊がしっかり付着していることが多いです。
一方で、細く弱々しい毛や毛根が膨らんでいない毛が増えている場合は、ヘアサイクル自体が乱れているサインかもしれません。
特徴別解説「円形脱毛症」
円形脱毛症は、ストレスが関連する脱毛症の中でも特に見た目の変化が大きく、発症すると大きな精神的ショックを受ける方が多い症状です。
しかし、その正体は「毛根が攻撃されている状態」であり、毛根自体が消滅したわけではありません。適切な対処を行えば、再び髪が生えてくる可能性は十分にあります。
円形脱毛症とは
円形脱毛症は、前述の通り、免疫系の異常によってリンパ球が毛根を攻撃することで毛が抜けてしまう疾患です。年齢や性別に関わらず発症します。
一般的に「ストレスが原因」と広く知られていますが、ストレスはあくまで発症の「誘因」の一つであり、明確な原因はまだ完全には解明されていません。
アトピー性皮膚炎や甲状腺疾患など、他の自己免疫疾患を持つ人や、家族歴がある場合に発症しやすい傾向も報告されています。
ストレスと自己免疫疾患の関係
なぜストレスが自己免疫機能の異常を引き起こすのか、その詳細な理由は複雑です。しかし、強いストレスが自律神経やホルモンバランスを介して、免疫システム全体に影響を与えることは知られています。
ストレスによって免疫の司令塔が混乱し、本来守るべきはずの自分の毛根を「敵」とみなして攻撃を始めてしまう、というのが円形脱毛症の一つの側面です。
ストレスが全ての原因ではありませんが、症状の悪化や再発のきっかけとなることは多いと考えられています。
症状の進行パターン
最も多いのは、頭部に円形の脱毛斑が1か所だけできる「単発型」です。これは自然に治ることも多いタイプです。
しかし、脱毛斑が複数できる「多発型」、脱毛斑が融合して広がる「多発融合型」、さらには頭部全体の髪が抜ける「全頭型」、眉毛や体毛まで抜ける「汎発型」へと進行する場合もあり、重症度は様々です。
脱毛斑の境界がはっきりしているのが特徴です。
専門医への相談を推奨するタイミング
- 初めて円形の脱毛斑を見つけた時
- 脱毛斑が複数に増えてきた時
- 脱毛斑が拡大している時
- 一度治ったが再発した時
専門医への相談の目安
円形脱毛症を疑う症状(コイン大の脱毛)を見つけたら、まずは皮膚科を受診することを強く推奨します。
特に、脱毛斑が複数ある場合や、範囲が広がっているように感じる場合は、早めの相談が重要です。専門医は、症状の範囲や重症度を診断し、適切な治療方針を決定します。
治療にはステロイド外用薬や局所注射、紫外線療法など、症状に応じた様々な選択肢があります。自己判断で育毛剤だけに頼るのではなく、まずは正確な診断を受けることが回復への近道です。
特徴別解説「休止期脱毛」
休止期脱毛は、円形脱毛症とは異なり、「全体的に」髪が抜けるのが特徴です。
ある時期から急に抜け毛が増え、髪全体のボリュームダウンを感じるため、AGA(男性型脱毛症)の進行かと不安になる方も多いですが、原因と対処法が異なります。
休止期脱毛とは
急性の休止期脱毛は、高熱、大きな外科手術、過度なダイエット、出産、そして強い精神的ストレスなど、体に大きな負担がかかった出来事の後、約2〜3ヶ月経過してから発症することが多い脱毛症です。
体の受けたダメージやストレスに対応するため、多くの髪の毛が「成長期」から「休止期」へと一斉に移行し、その結果として大量の抜け毛が発生します。
髪の毛のヘアサイクル(成長期・退行期・休止期)
私たちの髪の毛は、1本1本が独立した「ヘアサイクル(毛周期)」を持っています。このサイクルを理解することが、休止期脱毛を理解する鍵となります。
ヘアサイクルの各段階
| 段階 | 期間の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 成長期 | 2年〜6年 | 毛母細胞が活発に分裂し、髪が太く長く成長する時期。全体の約85-90% |
| 退行期 | 約2週間 | 毛母細胞の活動が停止し、毛根が縮小していく時期。全体の約1% |
| 休止期 | 約3ヶ月 | 毛根は完全に活動を停止。毛は抜け落ちる準備状態。全体の約10-15% |
通常はこのバランスが保たれていますが、休止期脱毛では、ストレスなどの影響で「成長期」の髪が一気に「休止期」へと移行し、このバランスが崩れてしまいます。
ストレスがヘアサイクルを乱す流れ
強いストレスがかかると、交感神経が優位になり、前述の通り頭皮の血行が悪化します。
毛母細胞は髪を成長させるために大量の栄養と酸素を必要としますが、血行不良によりその供給が絶たれると、細胞は「これ以上成長できない」と判断し、成長期を中断してしまいます。
さらに、ストレスホルモンであるコルチゾールが、毛根に対して直接的に「休止期に入れ」というシグナルを送ることも、ヘアサイクルを乱す原因となります。
回復までにかかる期間
休止期脱毛の多くは一時的なものです。原因となったストレスや身体的負担が取り除かれれば、ヘアサイクルは再び正常化に向かいます。
髪が休止期に入ってから抜け落ち、新しい髪が成長を始めるまでには数ヶ月かかります。
そのため、原因が解決してもすぐに抜け毛が止まるわけではありませんが、一般的には6ヶ月から1年程度で元の状態に回復することが多いと言われています。
ただし、ストレスが慢性的に続く場合は、脱毛も慢性化する恐れがあるため注意が必要です。
ストレス以外の抜け毛の原因
「抜け毛=ストレス」と短絡的に考えるのは早計です。特に男性の場合、ストレス性の脱毛と、より一般的なAGA(男性型脱毛症)が同時進行している可能性も十分にあります。
また、生活習慣の乱れが抜け毛を加速させることも少なくありません。原因を正しく見極めることが重要です。
AGA(男性型脱毛症)の影響
AGAは、男性ホルモンの一種である「DHT(ジヒドロテストステロン)」が毛根に作用することで、ヘアサイクルの「成長期」が極端に短くなる疾患です。遺伝的な要因が大きく関わっています。
生え際が後退したり、頭頂部が薄くなったりと、特定のパターンで進行するのが特徴です。ストレス性の脱毛と異なり、ゆっくりと進行し、抜け毛は細く短い「軟毛」が多くなります。
ストレスはAGAの進行を早める一因にはなりますが、AGAの根本原因ではありません。
ストレス性脱毛とAGA(男性型脱毛症)の比較
| 比較項目 | ストレス性脱毛(休止期脱毛など) | AGA(男性型脱毛症) |
|---|---|---|
| 進行速度 | 比較的急激(数ヶ月単位) | ゆっくりと進行(数年単位) |
| 抜け方の特徴 | 頭部全体がまんべんなく薄くなる | 生え際の後退、頭頂部の薄毛 |
| 抜ける毛質 | 太さや長さは正常な毛が多い | 細く短い毛(軟毛化)が多い |
栄養不足や食生活の乱れ
髪の毛は主に「ケラチン」というタンパク質でできています。
ストレスで食欲が落ちたり、偏った食事(ファストフードやインスタント食品ばかり)が続いたりすると、髪の毛の主成分であるタンパク質や、その合成を助ける亜鉛、ビタミンB群などが不足します。
体が栄養不足の状態になれば、生命維持に直接関係のない髪の毛への栄養供給は真っ先に削られます。これが抜け毛の原因となります。
睡眠不足とその影響
髪の毛の成長は、成長ホルモンが活発に分泌される睡眠中に行われます。特に、入眠後の深いノンレム睡眠(いわゆる「ゴールデンタイム」)は、毛母細胞の分裂や頭皮のダメージ修復に重要です。
ストレスで悩み事があり寝付けない、あるいは仕事が忙しく睡眠時間が慢性的に不足していると、成長ホルモンの分泌が妨げられます。
これにより、髪の成長が阻害され、健康な髪が育ちにくくなります。
不適切なヘアケア
頭皮環境の悪化も抜け毛の大きな要因です。
洗浄力の強すぎるシャンプーで必要な皮脂まで洗い流してしまい頭皮が乾燥する、あるいは逆に、皮脂や汚れを十分に落としきれずに毛穴が詰まる、といった不適切なヘアケアは頭皮にダメージを与えます。
ストレスで皮脂分泌が過剰になっている時に、ゴシゴシと強く洗いすぎることも、頭皮を傷つけ炎症を引き起こすため逆効果です。
今すぐ始めたいストレス抜け毛対策(セルフケア編)
ストレスによる抜け毛に気づいた時、専門的な治療と並行して、あるいはその前に、自分でできる生活習慣の見直しは非常に重要です。
髪の毛が育ちやすい「土壌」である体と頭皮の環境を整えることから始めましょう。
良質な睡眠の確保
髪の成長を促す成長ホルモンは、夜10時から深夜2時と言われることもありますが、実際には「時間帯」よりも「眠りの深さ」が重要です。
毎日決まった時間に寝て、決まった時間に起きる規則正しい生活を心がけ、睡眠の質を高めましょう。寝る直前のスマートフォンやPCの使用は、ブルーライトが脳を覚醒させ、深い眠りを妨げます。
就寝1時間前からはリラックスできる音楽を聴いたり、温かい飲み物(ノンカフェイン)を飲んだりして、心身をリラックスモードに切り替える工夫が必要です。
バランスの取れた食事
健康な髪を育てるためには、特定の栄養素だけを摂取するのではなく、バランスの良い食事が大切です。特に髪の毛の材料となる栄養素を意識して摂取しましょう。
髪の成長をサポートする主な栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食材例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、赤身肉、ナッツ類 |
| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝、皮脂分泌の調整 | 豚肉、レバー、マグロ、納豆 |
忙しいからといって食事を抜いたり、簡単なもので済ませたりせず、これらの食材を意識的に取り入れた食事を1日3食きちんと摂ることが、髪の健康の基盤となります。
効果的なストレス発散方法
ストレスをゼロにすることは現実的ではありません。大切なのは、ストレスを感じた時に「上手に発散する」方法を自分なりに持っておくことです。
ストレスが溜まると交感神経が優位になり続けるため、意識的に副交感神経を働かせる時間を作ることが鍵となります。
ストレス発散とリラックスの方法例
| 分類 | 具体例 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 体を動かす | ウォーキング、ジョギング、ヨガ | 血行促進、セロトニン(幸福ホルモン)分泌 |
| 趣味に没頭する | 音楽鑑賞、読書、料理、プラモデル作り | 悩み事から意識をそらし、集中・リフレッシュ |
| リラックス | ぬるめのお湯での入浴、深呼吸、瞑想 | 副交感神経を優位にし、心身の緊張をほぐす |
自分に合った方法を見つけ、日常的に取り入れることで、ストレスを溜め込まない体質を作ることが重要です。
頭皮マッサージと正しいヘアケア
ストレスで硬くなりがちな頭皮をほぐし、血行を促進するために、頭皮マッサージは有効なセルフケアです。シャンプー時や入浴後など、頭皮が温まっている時に行うとより効果的です。
指の腹を使い、頭皮全体を優しく動かすように揉みほぐします。爪を立てて頭皮を傷つけないよう注意しましょう。
正しいシャンプーの手順
- 洗う前にブラッシングで埃を落とす
- ぬるま湯で髪と頭皮を予洗いする
- シャンプーは手のひらで泡立ててから髪につける
- 指の腹で頭皮をマッサージするように優しく洗う
- すすぎ残しがないよう、時間をかけてしっかり洗い流す
また、シャンプーは自分の頭皮タイプ(乾燥肌、脂性肌など)に合った、刺激の少ないアミノ酸系洗浄成分のものを選ぶと良いでしょう。
ストレス抜け毛対策(専門的なアプローチ)
セルフケアを続けても抜け毛が改善しない、あるいは円形脱毛症のように明らかに専門的な対処が必要だと感じる場合は、ためらわずに専門家の力を借りるべきです。
ストレス性の抜け毛は、原因がはっきりしている分、適切な対処が早ければ早いほど回復も期待できます。
皮膚科や専門クリニックでの相談
抜け毛の増加や脱毛斑に気づいたら、まずは皮膚科を受診しましょう。
医師が頭皮の状態を視診やマイクロスコープで確認し、抜け毛の原因がストレスによるものか、AGAなのか、あるいは他の皮膚疾患なのかを診断します。
円形脱毛症の場合は、症状に応じた外用薬や内服薬、注射などの治療が行われます。休止期脱毛の場合も、原因の特定と生活指導、必要に応じた治療薬の処方が行われます。
自己判断で悩む時間を減らし、専門的な診断を受けることが解決への第一歩です。
育毛剤や発毛剤の活用
ストレスによる抜け毛対策として、育毛剤の活用も有効な選択肢の一つです。
特に休止期脱毛のように頭皮全体の血行不良や栄養不足が懸念される場合、育毛剤の多くに含まれる血行促進成分や、毛母細胞に栄養を与える成分が、頭皮環境を整え、髪の成長をサポートする働きをします。
育毛剤は「今ある髪を健康に育てる」ことを目的とし、頭皮環境を改善します。ストレスで弱った頭皮に潤いを与え、フケやかゆみを抑える成分が含まれている製品も多くあります。
セルフケアの一環として頭皮マッサージと組み合わせて使用することで、より高い相乗効果が期待できます。
一方、発毛剤(ミノキシジル配合のものなど)は「新しい髪を生やす」ことを目的とした医薬品です。AGAが併発している場合などには強力な選択肢となりますが、
まずは医師の診断のもと、自分の症状に合ったものを選ぶことが重要です。
メンタルヘルスケアの重要性
抜け毛の原因が明確に「ストレス」である場合、髪の毛のケアと同時に、ストレスの根本原因に対処することも非常に重要です。
抜け毛が始まると、そのこと自体が新たなストレスとなり、「抜け毛が増えたらどうしよう」という不安がさらに症状を悪化させる悪循環に陥ることがあります。
仕事のプレッシャーや人間関係など、ストレスの原因が自分一人で解決困難な場合は、専門のカウンセラーや心療内科に相談することも検討しましょう。
ストレスマネジメントの方法を学んだり、客観的なアドバイスを受けたりすることで、心が軽くなり、結果として髪の毛の状態にも良い影響が及ぶことは少なくありません。
ストレス・睡眠・運動不足に戻る
Q&A
ストレスによる抜け毛に関して、多くの方が抱える疑問にお答えします。
- ストレスがなくなれば髪は元に戻りますか?
-
原因がストレスによる一時的な休止期脱毛であれば、ストレス要因が取り除かれ、ヘアサイクルが正常に戻れば、髪は再び生えてくる可能性が高いです。
通常、回復には6ヶ月から1年程度かかると言われています。円形脱毛症の場合も、多くは回復しますが、重症度や体質によって個人差があります。
ただし、ストレスが原因でAGA(男性型脱毛症)の進行が早まった場合、ストレスがなくなってもAGA自体の進行が止まるわけではないため、別途AGAへの対策が必要となることがあります。
- 抜け毛がひどい場合、まず何をすべきですか?
-
まずはご自身の抜け毛の特徴を観察してください。円形に抜けているのか、全体的に抜けているのか、抜けた毛が細くなっていないかなどです。
円形脱毛症が疑われる場合や、抜け毛の量が異常に多く不安な場合は、自己判断せず、速やかに皮膚科や薄毛専門のクリニックを受診してください。
医師による正確な診断を受けることが最も重要です。同時に、睡眠、食事、ストレスケアといった生活習慣の見直しを始めることも大切です。
- 育毛剤はストレスによる抜け毛にも効果がありますか?
-
育毛剤は、ストレスによって引き起こされた頭皮環境の悪化(血行不良、乾燥、皮脂過剰など)を改善し、健康な髪が育つ土壌を整えるサポートをします。
血行を促進したり、毛根に栄養を与えたりする成分が含まれているため、ストレスによる休止期脱毛の回復を助ける効果は期待できます。
ただし、育毛剤はあくまで「育毛環境を整える」ものであり、ストレスそのものを解消するものではありません。ストレス対策と並行して使用することが重要です。
Reference
RUSSO, P. M., et al. HrQoL in hair loss‐affected patients with alopecia areata, androgenetic alopecia and telogen effluvium: the role of personality traits and psychosocial anxiety. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2019, 33.3: 608-611.
HADSHIEW, Ina M., et al. Burden of hair loss: stress and the underestimated psychosocial impact of telogen effluvium and androgenetic alopecia. Journal of investigative dermatology, 2004, 123.3: 455-457.
PHILLIPS, T. Grant; SLOMIANY, W. Paul; ALLISON, Robert. Hair loss: common causes and treatment. American family physician, 2017, 96.6: 371-378.
TOADER, Mihaela Paula, et al. Unraveling the psychological impact of telogen effluvium: Understanding hair loss beyond the scalp. Bulletin of Integrative Psychiatry, 2024, 1.
MALOH, Jessica, et al. Systematic review of psychological interventions for quality of life, mental health, and hair growth in alopecia areata and scarring alopecia. Journal of clinical medicine, 2023, 12.3: 964.
IZCI, Neslihan Fişek; AKSOY, Berna; AKTAŞ, Ezgi. Significant impact of telogen effluvium on quality of life, depression, anxiety and stress: a prospective case-control study. European Journal of Dermatology, 2025, 35.4: 300-306.
REID, Erika Elise, et al. Clinical severity does not reliably predict quality of life in women with alopecia areata, telogen effluvium, or androgenic alopecia. Journal of the American Academy of Dermatology, 2012, 66.3: e97-e102.
MALTA JR, Mauri; CORSO, German. Understanding the Association Between Mental Health and Hair Loss. Cureus, 2025, 17.5.
CHENG, Yi, et al. Psychological stress impact neurotrophic factor levels in patients with androgenetic alopecia and correlated with disease progression. World journal of psychiatry, 2024, 14.10: 1437.