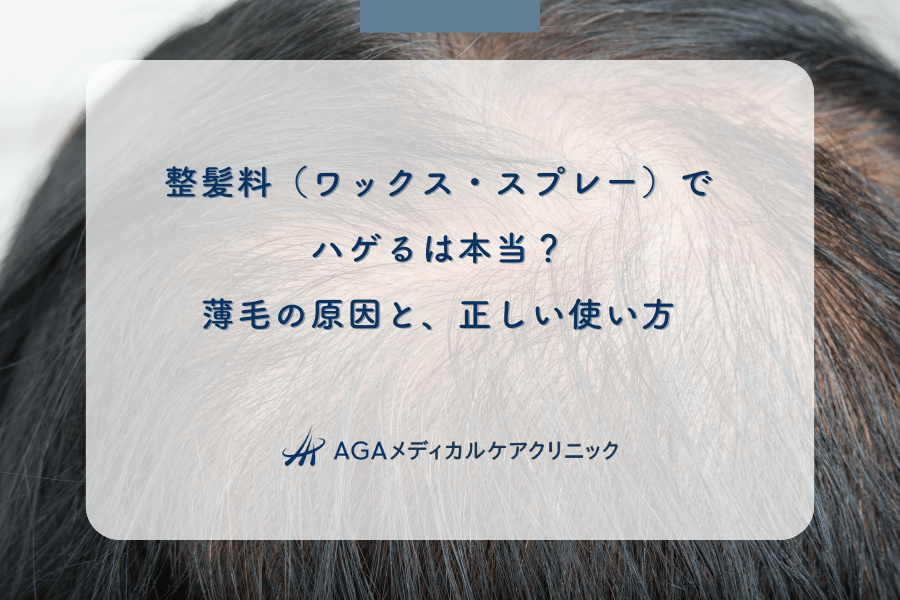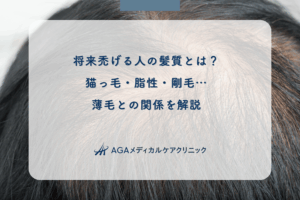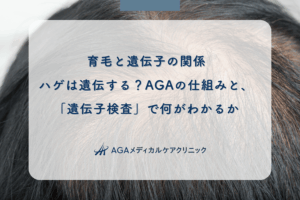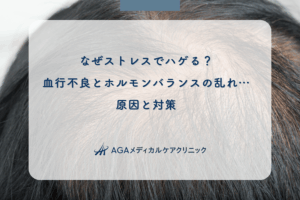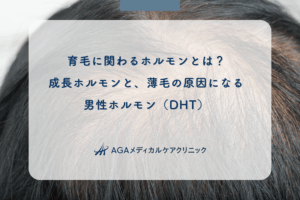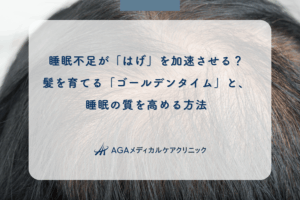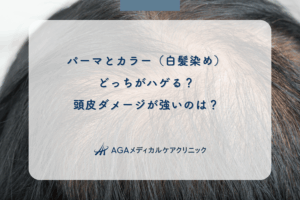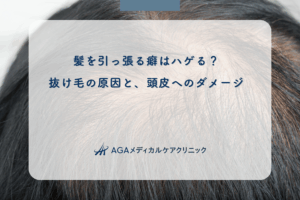毎日のスタイリングに欠かせないワックスやスプレー。「整髪料を使うとハゲる」という噂を耳にして、愛用している製品が頭皮に悪影響を与えていないか不安になっていませんか。
薄毛を気にする方にとって、これは深刻な問題です。
この記事では、整髪料が直接的な薄毛の原因になるのか、もし関連があるとしたらどのような要因が考えられるのかを詳しく解説します。
さらに、頭皮の健康を守りながらおしゃれを楽しむための正しい整髪料の使い方や選び方を紹介します。この記事を読めば、整髪料と上手に付き合っていく方法がわかります。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
「整髪料(ワックス・スプレー)でハゲる」は本当か?
整髪料が直接的な脱毛原因になる可能性は低い
結論から言うと、市販されている一般的な整髪料(ワックスやスプレー)が、それ自体で直接的に健康な髪を抜けさせたり、薄毛(AGAなど)を引き起こしたりする可能性は極めて低いです。
日本の化粧品は厳しい安全基準のもとで製造されています。整髪料の成分が毛根に浸透し、髪の成長サイクルを乱すほどの強力な作用を持つとは考えにくいです。
しかし、使い方や頭皮の状態によっては、薄毛につながる「環境」を作ってしまう間接的な要因になる可能性は否定できません。
間接的に薄毛のリスクを高める要因とは
整髪料が「ハゲる」と言われる背景には、直接的な脱毛作用ではなく、間接的な要因が隠れています。主な要因は「頭皮への残留」と「毛穴の詰まり」です。
整髪料をつけたまま寝てしまったり、シャンプーで十分に洗い流せなかったりすると、整髪料の成分や皮脂、汗、ホコリなどが混ざり合って頭皮に残ります。
これが毛穴を塞ぎ、頭皮環境を悪化させるのです。
頭皮環境の悪化が髪の成長に与える影響
毛穴が詰まると、頭皮はどのような状態になるのでしょうか。まず、皮脂や汚れをエサにする雑菌が繁殖しやすくなります。
これにより、かゆみ、フケ、赤みといった頭皮トラブル(脂漏性皮膚炎など)が発生することがあります。炎症が起きた頭皮は、健康な髪を育てるための土壌として機能しにくくなります。
血行不良にもつながり、髪の成長に必要な栄養素が毛根に届きにくくなることで、髪が細くなったり、抜けやすくなったりする可能性があります。
薄毛の本当の主な原因
男性の薄毛の多くは、男性ホルモンや遺伝的要因によるAGA(男性型脱毛症)が原因です。整髪料の使用とは無関係に、AGAは進行する可能性があります。
整髪料の使用をやめたからといって、AGAの進行が止まるわけではありません。薄毛の根本的な原因と、整髪料による頭皮環境の悪化は、分けて考える必要があります。
ただし、すでに薄毛が気になっている人が不適切な整髪料の使い方を続けると、頭皮環境の悪化が薄毛の進行を助長する可能性はあります。
整髪料が頭皮に与える具体的な懸念点
毛穴の詰まりと皮脂の酸化
ワックスやヘアクリームのような油分の多い整髪料は、特に毛穴を詰まらせやすい性質があります。
整髪料が頭皮に付着し、そこに皮脂や古い角質が混ざると、硬い角栓のようなもの(コメド)を形成することがあります。
さらに、これらの油分が空気中の酸素に触れて酸化すると、過酸化脂質という有害な物質に変化します。
過酸化脂質は頭皮を刺激し、炎症を引き起こす原因となり、頭皮の老化を早める可能性も指摘されています。
配合成分による頭皮への刺激
整髪料には、スタイリング力を維持したり、香りをつけたり、品質を保ったりするために様々な化学成分が含まれています。
例えば、ヘアスプレーに含まれるエタノール(アルコール)は、揮発性が高い一方で、頭皮の水分を奪い乾燥させる可能性があります。
また、香料、防腐剤(パラベンなど)、界面活性剤などが、体質によってはアレルギー反応やかぶれ(接触性皮膚炎)を引き起こすこともあります。
頭皮トラブルを引き起こす可能性のある主な成分
| 成分の種類 | 主な役割 | 懸念される影響 |
|---|---|---|
| アルコール類(エタノール等) | 速乾性、清涼感 | 頭皮の乾燥、刺激 |
| 合成界面活性剤 | 乳化、洗浄(洗い流すタイプ) | 皮脂の過剰な除去、バリア機能低下 |
| 防腐剤(パラベン等) | 品質保持 | アレルギー反応、刺激 |
間違った洗い方による残留リスク
整髪料を使った日のシャンプーは非常に重要です。しかし、スタイリング力の強いワックスやスプレーは、一度のシャンプーでは簡単に落ちないことがあります。
特に、洗浄力の弱いシャンプーを使っていたり、すすぎが不十分だったりすると、整髪料の成分が頭皮や髪に残留してしまいます。
この残留物が日々蓄積していくことで、毛穴の詰まりや頭皮トラブルのリスクが徐々に高まっていきます。
ハゲると誤解されやすい整髪料の使い方
整髪料が頭皮にベッタリ付着している
スタイリングの際、髪の根元を立ち上げようとして、ワックスやジェルを頭皮に直接擦り込むように使っていませんか。整髪料は、あくまでも「髪」につけるものです。
頭皮に直接つけると、毛穴を塞ぐリスクが格段に高まります。特に油分の多いワックスは、シャンプーでも落としにくくなるため注意が必要です。
頭皮に付着させる使い方は、薄毛を懸念する上では最も避けるべき行為の一つです。
スタイリング時の物理的なダメージ
整髪料そのものの影響だけでなく、スタイリングの「行為」が髪や頭皮にダメージを与えているケースもあります。
例えば、ワックスをつけた髪を無理にコーム(櫛)でとかしたり、スプレーで固めた髪を力任せにブラッシングしたりすると、髪が引っ張られて抜けたり(牽引性脱毛)、キューティクルが傷ついて切れ毛になったりします。
また、指の爪を立てて頭皮をガシガシと擦るようなスタイリングも、頭皮を傷つけ炎症の原因となります。
整髪料をつけたまま就寝する
仕事や飲み会で疲れて帰宅し、整髪料を洗い流さずにそのまま寝てしまうことはありませんか。これは頭皮環境にとって最悪の行為です。就寝中は皮脂の分泌が活発になり、体温で頭皮も蒸れやすくなります。
その環境で整髪料が頭皮に残っていると、雑菌が爆発的に繁殖する絶好の条件が揃ってしまいます。
たった一晩でも、頭皮のかゆみやニオイの原因となり、これを繰り返すことは、自ら薄毛になりやすい頭皮環境を作り出しているのと同じです。
薄毛を防ぐための正しい整髪料の選び方
自分の髪質や頭皮の状態に合わせる
整髪料を選ぶ際は、スタイリング力だけでなく、自分の頭皮の状態を考慮することが重要です。
例えば、乾燥肌や敏感肌の人は、アルコール(エタノール)の含有量が多いスプレーや、刺激の強い成分(メントールなど)が入った製品を避ける方が賢明です。
逆に、皮脂が多い(オイリー肌)の人は、油分の多いワックスやクリームの使用量を控えるなど、バランスを考える必要があります。
頭皮に優しい成分か確認する
すべての成分を理解するのは難しいですが、パッケージに「敏感肌用」「低刺激」「オーガニック認証」などの記載がある製品は、比較的頭皮への刺激が少ないように配慮されています。
また、香料、着色料、防腐剤などが無添加(フリー)の製品を選ぶのも一つの方法です。
自分の頭皮に合うかどうかは、実際に使ってみないとわからない部分もあるため、新しい製品を使う際は、まず少量から試してみることをお勧めします。
整髪料選びのポイント
| 頭皮タイプ | 避けたい成分・特徴 | 選びたい特徴 |
|---|---|---|
| 乾燥肌・敏感肌 | 高濃度のアルコール、強い香料、メントール | 低刺激、無香料、保湿成分配合 |
| オイリー肌 | 油分の多いワックスやクリームの過度な使用 | 水溶性ジェル、軽めのスプレー、洗い流しやすい製品 |
| フケ・かゆみがある | 刺激の強い成分全般 | 薬用(抗炎症・殺菌成分配合)、無添加処方 |
洗い流しやすい製品(お湯で落ちるタイプ)を選ぶ
整髪料が「ハゲる」と心配する最大の要因は「残留」です。この問題を解決する最も簡単な方法は、「洗い流しやすい製品」を選ぶことです。
最近では、お湯だけで簡単に洗い流せるワックスやスプレー(フィルムタイプなど)も増えています。シャンプー時の頭皮への負担(ゴシゴシ洗い)も減らせるため、薄毛を気にする方には特にお勧めです。
製品パッケージに「お湯でオフ」「シャンプーで簡単オフ」といった記載があるか確認してみましょう。
頭皮と髪を守る整髪料の正しい使い方
使用量を守り、手のひらでよく伸ばす
スタイリング力を高めようと、一度に多くの整髪料を手に取るのは逆効果です。量が多すぎるとムラになりやすく、結果的に頭皮にも付着しやすくなります。
まずは少量(製品推奨量、例えばワックスならパール粒大)を手に取ります。そして、指の間まで含めて、手のひら全体に透明になるまでしっかりと伸ばすことが重要です。
このひと手間で、髪全体に均一につけやすくなります。
頭皮を避け、髪の中間から毛先につける
整髪料を伸ばした手で、いきなり髪の根元や頭頂部からつけるのは避けてください。頭皮に最も付着しやすいからです。
まずは、髪の中間から毛先にかけて、髪の内側から揉み込むようにつけていきます。
ボリュームを出したい場合も、頭皮に擦り込むのではなく、指先で髪の根元近くの「毛」をつまみ上げるようにしてスタイリングします。
スプレーは頭皮から離して使用する
ヘアスプレーを使用する際は、缶を髪から最低でも15~20cmは離して噴射するようにしましょう。距離が近すぎると、一箇所に集中してかかってしまい、頭皮に直接噴射されてしまいます。
また、噴射されたガスが頭皮の毛穴を直撃し、刺激となる可能性もあります。髪全体にふんわりとかけるイメージで使用するのがコツです。
整髪料タイプ別の注意点
| タイプ | 主な使い方 | 特に注意すべき点 |
|---|---|---|
| ワックス・クリーム | 手のひらで伸ばし、中間~毛先からつける | 頭皮に擦り込まない。使用量を守る。 |
| ジェル・グリース | 髪を濡らしてからつけることが多い | 油分が多く落ちにくい製品は特に念入りに洗う。 |
| スプレー・ミスト | 仕上げに、髪から離して噴射する | 頭皮に直接かからないよう距離を保つ。吸い込まない。 |
最も重要!整髪料を使った日のシャンプー方法
シャンプー前の「予洗い」を徹底する
整髪料を落とすために、いきなりシャンプー剤をつけるのは非効率です。まずは、38度前後のぬるま湯で、頭皮と髪をしっかりと「予洗い」することが非常に重要です。
1分から2分ほどかけて、お湯だけで頭皮の皮脂やホコリ、そして髪についた整髪料の多くを洗い流します。これを行うだけで、シャンプーの泡立ちが格段に良くなり、洗浄効果が高まります。
(落ちにくい場合)コンディショナーで先に溶かす
特に油性のワックスやハードスプレーを使った日は、お湯だけでは落としきれないことがあります。
その場合は、シャンプーの前にコンディショナーやトリートメントを整髪料がついている部分に馴染ませる方法があります。
油分は油分で溶けやすい性質を利用し、整髪料を乳化させて浮き上がらせます。数分置いてからよくすすぎ、その後で通常のシャンプーを行います。
シャンプーは「頭皮」を洗う意識で
シャンプー剤は手のひらでよく泡立ててから、髪ではなく「頭皮」につけます。洗う際は、爪を立てず、指の腹を使って頭皮全体をマッサージするように優しく揉み洗いします。
整髪料が残留しやすい生え際、耳の後ろ、襟足などは特に丁寧に洗いましょう。髪の毛自体は、頭皮を洗った泡が流れるだけで十分汚れが落ちます。
ゴシゴシと髪同士を擦り合わせる必要はありません。
正しいシャンプーの手順
| 手順 | ポイント | 目的 |
|---|---|---|
| 1. ブラッシング | 乾いた状態で髪のもつれを解く | ホコリを落とす、シャンプー時の抜け毛予防 |
| 2. 予洗い | ぬるま湯で1~2分、頭皮まで濡らす | 整髪料や皮脂の多くをお湯で流す |
| 3. シャンプー | 指の腹で頭皮をマッサージ洗い | 毛穴の汚れと残留した整髪料を落とす |
| 4. すすぎ | シャンプー剤が残らないよう念入りに | 頭皮トラブルの予防 |
「すすぎ」は洗う時間の倍かける
シャンプーで最も重要なのは「すすぎ」と言っても過言ではありません。シャンプー剤やリンス、コンディショナーの成分が頭皮に残ることは、整髪料の残留と同じく、毛穴の詰まりやかゆみの原因となります。
泡が消えたと感じてから、さらに1分以上は時間をかけて、シャワーヘッドを頭皮に近づけながら、ぬめり感が完全になくなるまで念入りにすすぎましょう。
「洗う時間の倍はすすぐ」と覚えておくと良いでしょう。
シャンプー剤の選び方も重要です。スタイリング力の強い整髪料を使っているのに、洗浄力がマイルドなアミノ酸系シャンプーだけでは、落としきれない場合があります。
かといって、洗浄力の強すぎる高級アルコール系シャンプーを毎日使うと、頭皮に必要な皮脂まで奪い去り、乾燥を招くこともあります。
普段はアミノ酸系やベタイン系のシャンプーを使い、整髪料をしっかり使った日だけ、洗浄力のやや高いシャンプー(オレフィン系など)を使う、といった使い分けも一つの手です。
自分の整髪料と頭皮の状態に合ったシャンプー選びが、残留を防ぐ鍵となります。
シャンプーの種類と洗浄力(目安)
| シャンプーの種類 | 主な洗浄成分 | 特徴 |
|---|---|---|
| 高級アルコール系 | ラウレス硫酸Na、ラウリル硫酸Na | 洗浄力・泡立ちが強い。刺激も強め。 |
| アミノ酸系 | ココイルグルタミン酸Na、ラウロイルメチルアラニンNa | マイルドな洗浄力。低刺激。 |
| ベタイン系 | コカミドプロピルベタイン | ベビーシャンプーにも使われる。非常にマイルド。 |
また、シャワーの温度も意識してください。熱すぎるお湯(40度以上)は、頭皮に必要な皮脂を取りすぎて乾燥を招き、かえって皮脂の過剰分泌を引き起こす可能性があります。
かといって冷たすぎると、油性のワックスや皮脂汚れが固まって落ちにくくなります。整髪料を落とすためのシャンプーには、37度から39度程度の「ぬるま湯」が最も適しています。
薄毛が気になる人が取り入れたい頭皮ケア
シャンプー後の頭皮の保湿
整髪料の使用や毎日のシャンプーで、頭皮は乾燥しがちです。
特にアルコールを含むスプレーを使った日や、洗浄力の強いシャンプーを使った後は、頭皮の皮脂が奪われ、バリア機能が低下していることがあります。
顔を洗った後に化粧水をつけるのと同じように、お風呂上がりには頭皮専用のローションや育毛トニック(医薬部外品)を使って保湿を心がけましょう。
乾燥を防ぐことは、過剰な皮脂分泌を抑え、フケやかゆみを予防するために重要です。
頭皮マッサージで血行を促進する
健康な髪は、毛細血管から運ばれる栄養素によって作られます。
頭皮の血行が悪くなると、毛根に十分な栄養が届かず、髪が細くなる原因となります。シャンプー中や、育毛剤をつけた後などに、指の腹を使って頭皮全体を優しく動かすマッサージを取り入れましょう。
頭皮自体を動かすイメージで、前後左右に揉みほぐします。リラックス効果もあり、頭皮環境を整えるのに役立ちます。
頭皮マッサージの簡単な方法
| 部位 | マッサージ方法 |
|---|---|
| 側頭部 | 両手の指の腹で耳の上あたりを掴み、円を描くように揉む |
| 前頭部・頭頂部 | 両手の指で生え際から頭頂部に向かって引き上げるように動かす |
| 後頭部 | 襟足に両手の指を組み、親指の付け根でツボを押すように圧をかける |
生活習慣の見直しも重要
整髪料の使い方を見直すだけでなく、体の中からのケアも薄毛予防には必要です。髪の毛はタンパク質(ケラチン)でできているため、良質なタンパク質(肉、魚、大豆製品など)をしっかり摂取しましょう。
また、髪の成長を助けるビタミンやミネラル(特に亜鉛)も重要です。
バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動、ストレス管理など、基本的な生活習慣を整えることが、健康な頭皮と髪を育てる土台となります。
髪の成長に必要な主な栄養素
- タンパク質(肉、魚、卵、大豆製品)
- 亜鉛(牡蠣、レバー、牛肉)
- ビタミンB群(豚肉、マグロ、レバー)
薄毛の進行が止まらない場合は専門家へ相談
整髪料の使い方を改め、頭皮ケアをしても抜け毛が減らない、あるいは薄毛が進行していると感じる場合、その原因はAGA(男性型脱毛症)である可能性が高いです。
AGAは進行性の脱毛症であり、セルフケアだけで改善するのは困難です。整髪料のせいだと自己判断せず、早めに皮膚科やAGA専門のクリニックを受診し、医師の診断を仰ぐことを強くお勧めします。
適切な治療を開始することで、薄毛の進行を食い止め、改善できる可能性があります。
薄毛を加速させる習慣に戻る
よくある質問
- 整髪料は毎日使わない方がいいですか?
-
整髪料を毎日使用すること自体が問題ではありません。大切なのは、使用したその日のうちに、頭皮に残らないよう正しく洗い流すことです。
毎日使っても、シャンプーとすすぎが完璧であれば、頭皮への悪影響は最小限に抑えられます。
ただし、すでに頭皮に炎症やかゆみがある場合は、症状が治まるまで使用を控える方が賢明です。
- ワックスとスプレー、どちらがハゲやすいですか?
-
どちらが「ハゲやすい」ということはありませんが、頭皮への影響の出方が異なります。ワックスは油分が多く、毛穴に詰まりやすいリスクがあります。
一方、スプレーはアルコールを含むものが多く、頭皮を乾燥させたり、吸い込むことで刺激になったりする可能性があります。
どちらも頭皮に直接つけず、正しく洗い流すことが重要です。
- 水溶性のジェルなら頭皮に安全ですか?
-
水溶性のジェルは、油性のワックスに比べて洗い流しやすいというメリットがあります。そのため、頭皮への残留リスクは低いと言えます。
しかし、ジェルであっても頭皮に直接ベッタリとつければ毛穴を塞ぐ可能性はありますし、配合されているポリマーやアルコールが肌に合わない場合もあります。
「安全」と過信せず、他の整髪料と同様に、頭皮を避けて使用し、しっかり洗い流す基本を守ってください。
- 整髪料で髪が細くなることはありますか?
-
整髪料の成分が直接髪を細くすることはありません。しかし、整髪料の洗い残しで頭皮環境が悪化し、毛穴が詰まったり炎症が起きたりすると、髪の成長が妨げられる可能性があります。
その結果、新しく生えてくる髪が十分に成長できず、細く弱々しい髪(軟毛化)になることは考えられます。
- 育毛剤と整髪料を併用しても大丈夫ですか?
-
併用は可能ですが、順番が重要です。育毛剤は清潔な頭皮に直接浸透させる必要があります。
したがって、シャンプー・ドライ後、まず育毛剤を頭皮につけてマッサージし、成分が浸透するまで数分待ちます。
その後に、整髪料(ワックスやスプレー)を「頭皮を避けて髪だけ」につけてスタイリングしてください。整髪料をつけた上から育毛剤を使っても効果はありません。
育毛剤と整髪料の正しい順番
- シャンプーで頭皮を清潔にする
- タオルドライ後、髪をしっかり乾かす
- 育毛剤を頭皮に塗布・マッサージする
- 育毛剤が乾いてから、整髪料を髪につける
Reference
SOMASUNDARAM, Arun; MURUGAN, Kalaiarasi. Current trends in hair care in men. Cosmoderma, 2024, 4.
ASHIQUE, Sumel, et al. A systemic review on topical marketed formulations, natural products, and oral supplements to prevent androgenic alopecia: a review. Natural products and bioprospecting, 2020, 10.6: 345-365.
YORK, Katherine, et al. A review of the treatment of male pattern hair loss. Expert opinion on pharmacotherapy, 2020, 21.5: 603-612.
FUNG, Ernest S.; PARKER, Jillian A.; MONNOT, Andrew D. Evaluating the impact of hair care product exposure on hair follicle and scalp health. Alternatives to Laboratory Animals, 2023, 51.5: 323-334.
KO, Hee-La, et al. Effects of Adult Men’s Lifestyle on Scalp Health. Asian Journal of Beauty and Cosmetology, 2024, 22.2: 357-369.
PAN, Xuexue, et al. Technological Advances in Anti-hair Loss and Hair Regrowth Cosmeceuticals: Mechanistic Breakthroughs and Industrial Prospects Driven by Multidisciplinary Collaborative Innovation. Aesthetic Plastic Surgery, 2025, 1-50.
ASFOUR, Leila; CRANWELL, William; SINCLAIR, Rodney. Male androgenetic alopecia. Endotext [Internet], 2023.
WELZEL, Julia; WOLFF, Helmut H.; GEHRING, Wolfgang. Reduction of telogen rate and increase of hair density in androgenetic alopecia by a cosmetic product: results of a randomized, prospective, vehicle‐controlled double‐blind study in men. Journal of Cosmetic Dermatology, 2022, 21.3: 1057-1064.
GERLACH, Nicole, et al. Effect of the multifunctional cosmetic ingredient sphinganine on hair loss in males and females with diffuse hair reduction. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2016, 191-203.
T. CHIU, Chin-Hsien; HUANG, Shu-Hung; D. WANG, Hui-Min. A review: hair health, concerns of shampoo ingredients and scalp nourishing treatments. Current pharmaceutical biotechnology, 2015, 16.12: 1045-1052.